解説記事2013年03月11日 【事例で学ぶ資産税】 特定口座と株式の取得価額(取得費等)―概算取得費適用の可否などについて―(2013年3月11日号・№490)
事例で学ぶ資産税
第2回
特定口座と株式の取得価額(取得費等)
―概算取得費適用の可否などについて―
税理士 塩野入文雄
はじめに
次のQをご覧になって(特に、Q1については)、何にも問題がないのではないかと受け止められる読者も少なくないと思われます。しかしながら、ご質問者と同様に、筆者もこれらのケースに関する税務処理が必ずしも明確になっていないものと思われましたので、本稿のテーマとしました。
なお、いずれの事例も、具体的案件としては一般的な(多発する)ものではありませんが、これらの事例の検討を通じて、特定口座の税務上の位置づけや関連事項などについて整理を行うことも狙いとしています(また、条文等の解釈・適用が明らかでないケースに対応する際における筆者なりの検討方法の一例でもあります)。
Q1 甲は、X証券において、銘柄A(上場株式)を平成15年8月に@100円により特定口座で購入した(脚注1)。その後、銘柄Aは、会社の業績が著しく伸びて株価もかなり値上がりしたことから、平成25年1月に@3,000円で特定口座において売却した。
甲は、銘柄Aの売却に関して所得税の確定申告を行うことにより概算取得費(5%計算)を適用して、その取得価額(取得費)を@150円とすることができますか。
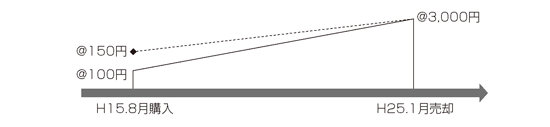
Q2 乙は、銘柄B(上場株式)を平成6年3月に@500円で購入して自宅に保管していたところ、平成15年4月にタンス株の取扱い(脚注2)によって(旧)上場株式等の取得費特例(脚注3)を適用した取得価額@1,000円(みなし取得価額)によりY証券の特定口座に入庫した。その後、Z社からの資金借入の必要が生じ、平成22年1月にその担保とするために銘柄Bを特定口座から払い出して質権を設定した(脚注4)。
平成25年1月のZ社への借入金の全額返済に伴い質権が解除され、再び、銘柄BをY証券の特定口座に再入庫してから、平成25年2月に5,000円で売却した。
乙(Y証券)は、銘柄Bの売却に関する特定口座内における所得金額の計算に当たって、その取得価額を@1,000円とした処理を行うことができますか。
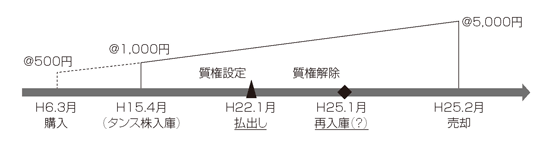
A1 甲は、所得税の確定申告を行って、概算取得費(措法31の4)を適用することができると考えられます。
なお、仄聞したところによると、ご質問の点を問題点として税務署による実地調査が行われ、国税部内での検討後に「是認」されたケースがあるようです。
A2 〔銘柄Bを特定口座に再入庫したという事実関係に不明確な点がありますが、〕税務上、ご質問のような特定口座への「再入庫」は認められていないことから、再入庫後の銘柄Bの売却に関する特定口座内における所得計算は無効(部分無効)なものと考えられます(脚注5)。
したがって、乙は、銘柄Bが平成22年1月に@1,000円の取得価額によって特定口座から払い出されたものとして、今回の売却に関する所得税の確定申告が必要になると考えられます。
(注)Q1及びQ2において、他の取引口座等に同一銘柄を保有しているケースなどに関する処理については、以下の記述の中で検討を行っています。
解説 Q1について
1.問題の所在等 現下の株式市場の情勢等からは、ご質問の点が関連してくるケースは極めてまれであると思われますが、今後の株式市場の情勢や特定口座制度の導入(創設)後10年を経過することをなど考慮した場合、将来、その売却金額が取得価額の20倍超となる銘柄も少なからず生じてくることが予想されます(また、生じてくることを願いたいものです)。したがって、一般的には、ご質問の点は喫緊の問題ではないものの、将来的には、このような問題への対応が必要となる場面が少なからず想定されるところです。
証券会社等(金融商品取引業者)によって行われる特定口座内における上場株式等(以下、「株式等」とします)の譲渡についての所得金額の計算方法は、措置法施行令25条の10の2第1項~4項に規定されています。同条(同項)には、概算取得費を適用する計算方法が規定されていないことから(脚注7)、証券会社等が概算取得費を適用した計算を行うことはできません。したがって、納税者の『選択』〔意思決定〕により開設された「特定口座」における株式等譲渡の所得金額が正当に計算されて「年間取引報告書」に記載された金額について、確定申告を行うことにより概算取得費を適用した減額(是正)ができるのかという疑問、ひいては、「特定口座」制度(同口座内で計算された所得金額)というものを税務上どのように捉えるのかという問題意識を持つことが必要になってきます。
この場合において、周知のとおり、税法には数多くの各種特例等が設けられ、それぞれの税務上の効果が付されています。また、その具体的適用に当たっては、納税者の「選択」に委ねられているものが多数あり、更に、その適用手続の多くが納税者による申告や申請などに委ねられています。
特定口座についても、その口座開設、口座内取引という納税者の「選択」により生じてくる税務上の効果としては、その特定口座における取引を他の特定口座や一般口座などにおける取引と『区分』して税務処理が行えるという点(隔離効果)などがあります(脚注8)(措法37の11の3①)。このため、筆者が仄聞した上記の税務調査が行われたとのことからも窺えるように、課税庁側においても、納税者による「選択」によって開設された特定口座内で生じた所得金額は正当に確定(固定)されており、確定申告によって、その所得金額を是正(減額)できないのではないかとの疑問が生じたものと推測されます。
2.検 討 次のとおり検討し、確定申告を行うことによって、銘柄Aの売却に関して概算取得費を適用することが可能であると考えます。
(1)制度創設の趣旨等からの検討(脚注9) 特定口座の創設趣旨については、もっぱら納税者における税務計算の事務負担(取得価額の管理)の軽減を図るものであり(脚注10)、他の多くの諸特例等とは異なり、所得金額の軽減等を図ることを目的としたものではない点に着目して、その「選択」(口座開設・口座内取引)の性格を捉えるべきものと考えます(脚注11)。このことから、証券会社等によって行われる特定口座内の所得計算は、「絶対的な確定」を生じるものではなく、是正(修正)し得るものとして捉えることが可能であると考えます(ただし、後記脚注21の点について注意が必要です)。
一方、特定口座の開設等によって、納税者サイドの事務負担の軽減が図られるだけでなく、上述した税務上の隔離効果も生じてきます。しかしながら、このような効果は、納税者の事務負担の軽減を確保するための「反射的・間接的効果」にすぎないものとして捉えるべきものであって、その特定口座の取引を他の取引と区分(隔離)することによって生じてくる所得金額の計算への影響(金額の増減)(脚注12)を云々すべきものとは考えられません(特定口座の開設等によって、結果的に生じてくる隔離効果を重要視する必要性、あるいは絶対的な所得金額の確定を生じるとする必要性は乏しいものと考えられます)。
(2)条文規定からの検討 上記(1)の点については、条文の規定としても読み取ることが可能であると考えます。
まず、措置法37条の11の3第1項には、次のとおり規定されています。
この規定を読んで、
① 特定口座内における株式等の譲渡に係る所得金額の計算に関する限りにおいて、その処理を定めたもの(確定申告による是正が可能なもの)として捉えるのか、
あるいは、
② その納税者の株式等譲渡の最終的な処理について定めた規定、すなわち、その特定口座内の所得金額を所与のもの(絶対的に確定しているもの)として捉えるのか
という点については、文理上、必ずしも判然としない面があると考えられます。
この点について、その規定対象がタンス株の取得価額などの誤りに限定されたものとはなっていますが、証券会社等によって、一端確定された所得金額を是正し得る条項が平成14年改正措置法施行令附則14条の3第5項(脚注13)として設けられていることからも、上記(1)のような捉え方、あるいは上記①のような解釈等を行う余地が生じていると考えます。
すなわち、同附則第4項は、特例上場株式等(タンス株)の入庫時において付されたその株式等の取得価額、取得の日についての誤りが、「当該営業所長の責めに帰すべき理由(脚注14)があると認める場合を除き」年間取引報告書の是正を要しないものとしています〔その反対解釈として、そのような理由によりタンス株の取得価額等に誤りが生じている場合には、その営業所長が、再計算、年間取引報告書の訂正等を行うことが必要であり、その結果、例えば、納税者が簡易特定口座について既に行っている確定申告に関して、修正申告や更正の請求等による是正を要するケースも生じてきます〕。
また、同附則第5項によって、当該営業所長の責めに帰すべき理由がある場合以外の理由により所得税の負担が少なくなったケースについては、申告不要の規定(脚注15)を適用しないこととされています。その結果、そのような誤り(タンス株の取得価額等の誤りによる所得税額の減少)がある場合には、「証券業者が譲渡所得や源泉徴収税額の再計算、年間取引報告書の修正を行う必要がなくても、個人が正しい取得価額により計算した譲渡所得を計算する必要がある。」(※)(脚注16)ことになります。
この場合において、第5項の規定が源泉あり特定口座についての申告を求める規定(申告不要規定の適用除外)に留まってはいるものの、過少な所得金額等になっているケースについて是正し得る以上は、簡易特定口座についても、また、過大な所得金額等となっているケースについても是正し得ることは当然のことと考えます。したがって、第5項については、特定口座における所得金額に関しても確定申告による是正が可能なものであり、過少となっているケースの是正に対応するために申告不要規定(脚注17)の適用を除外しているにすぎないものとして捉えることになります(第5項の規定を設けることで、その対応が足りるものとなっています)。
一方、これらの規定は、タンス株の取得価額等の誤りを是正するケースに限ったものであって、正当(適法)に計算された所得金額を是正することまでも予定したものではないと解することもできると思われます。しかしながら、然りであるとするならば、制度創設の趣旨等に沿わないものとなり、また、国税職員による措置法37条の11の3第12項~16項に基づく証券会社等に対する調査権限規定は不要のものとなることからも、そのように限定した捉え方は相当でないと考えられます。更に、証券会社等によって行われる特定口座の所得金額の計算に誤りが生じる可能性は極めて低いことから、上記附則を設けることによって、特例的なタンス株の入庫に限って、確認的な是正条項として、証券会社等に対して無用な負担を生じさせないように整備されたとも考えられます。
なお、この附則に基づく是正は、上記引用資料(※)の解説の文面によると、その特定口座外における同一銘柄との関係に言及していないことから(「正しい取得価額」とは、証券会社等によるその特定口座の計算に限定されているように読めることから)、是正を要するのは、その特定口座における誤りの部分に限られている(隔離効果が維持されている)ものと思われます〔この点については、後述する検討事項3(1)及び(2)にも関連してきます〕。
(3)「選択」に関する検討 別の視点として、特定口座の開設等は納税者の「選択」によるものであることから、概算取得費を適用した計算が特定口座内で行われないことを承知した上で、納税者が口座開設を行ったものであると捉えることによって、確定申告による再計算を行うことはできないとも考え得ると思われます。
しかしながら、もとより、概算取得費の適用については申告要件等が付されておらず、納税者の選択適用を求める制度とはなっていません。また、その銘柄の売却価額が、概算取得費による計算を行う前提となる取得価額の20倍超の金額となるか否かについては、特定口座の開設、株式等の取得時においては誰もが知り得ないところです。したがって、概算取得費の適用は結果的なものでしかなく、納税者による特定口座の開設等が概算取得費の適用を排したものと評価することは不適当であると考えます。更に加えるならば、特定口座の開設等については、例えば、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(所法10)における「非課税貯蓄申告書」(同条③)などのように、税務署長に対する申告書等を提出する制度とはなっていない点も看過してはならないと考えます(脚注18 脚注19)。
一方、上場株式等の取得費特例(みなし取得価額)(脚注20)を適用した取得価額によりタンス株を特定口座に入庫して売却したところ、後日、購入時の売買報告書が見つかり、その取得価額の方が高い場合であっても、確定申告を行うことで年間取引報告書の金額を是正することはできないものと解されています(脚注21)。しかしながら、これは、入庫時において、タンス株に関する特別の取扱い(平成14年改正措令附則14の3)に基づいた取得価額を選択適用した結果(脚注22)が確定していることによるものであって、特定口座の開設、同口座内での株式等の取引という「選択」とは、その性格が異なるものであると考えます。
以上の検討のとおり、特定口座は、納税者の便宜(事務負担の軽減)のために設けられた制度であり、また、所得金額(税負担)の直接的な軽減等を生じさせる「選択」ではないとの基本的な考え方や概算取得費の適用には申告要件が付されていないことなどから、甲が所得税の確定申告を行うことにより、銘柄Aについて概算取得費を適用した「再計算」を行うことが認められるものと考えます。
なお、本稿において筆者が意図しているところは、特定口座の所得計算(年間取引報告書の記載金額)に対して、納税者がフリー・ハンドで是正し得るものとしているものではありません。例えば、ある銘柄の特定口座内において付されている取得価額が@100円で、特定口座外で保有等している同一銘柄の取得価額が@500円であるような場合において、特定口座内での売却により生じた譲渡益について、@500円の取得価額を織り込んだ再計算に基づいて確定申告を行うことによる譲渡益の圧縮が可能となるとは考えていません。なぜなら、そのような申告は、特定口座制度創設の趣旨等から全く離れたものであり、また、納税者は、株式等を特定口座から払出して一般口座で売却しても、そのような税務上の効果を実現できるからです〔Q1についても、甲が、X証券の特定口座外に銘柄Aを保有等していないのであれば、その払出しを行って売却するとの対応があることは言うまでもありません(脚注23)〕。
3.その他 特定口座内における株式等の売却について概算取得費を適用する場合は、次のような点についても検討する必要があります(脚注24)。
(1)別に同一銘柄を保有している場合などに関する検討 概算取得費を適用して銘柄Aの売却を確定申告の対象とした場合、甲が、その特定口座外においても銘柄Aを保有等していると、両者を併せて取得価額の再計算を行う必要があるのかとの疑問が生じます。換言すると、〔甲案〕特定口座から銘柄Aが払い出された際と同様に取得費等の再計算(脚注25)が必要となるのか、あるいは、〔乙案〕特定口座内における銘柄Aの売却のみを取り出した概算取得費の適用(再計算)に留めることができるのかとの論点となります(脚注26)。
この点について、筆者は、特定口座制度創設の趣旨や概算取得費の趣旨等に鑑み、特定口座を利用して取得、譲渡した取引行為を無為にする必要性は低く、銘柄Aの取得価額の再計算を求めるまでもないと考えます(また、この点に関連して、上記引用資料(※)の記述が、〔甲案〕のような再計算を想定したものとなっていない(隔離効果を維持している)ものとも思われます)。
しかしながら、文理解釈上、措置法37条の11の3第1項には、「…これらの金額を計算するものとする。」と規定されており、銘柄Aの売却についてのみとはいえ、特定口座による所得計算から離脱する以上は、概算取得費を適用する銘柄Aの取引以外に甲がその特定口座外において保有等している銘柄Aの取得価額との関連性(影響)なしとするには、措通37の11の3-4(脚注27)の定めに相当するような緩和措置(通達)が講じられていないことから、形式的文理解釈からの疑問を払拭すことができません。このことから、他に同一銘柄を保有しているケースについては、税務署に対して事前の個別相談や文書照会等を行うことが得策であると考えられます〔また、例えば、銘柄Aを特定口座から払出してから売却すると、その影響が及ぶ範囲は、措通37の11の3-4による取扱いに留まることになります〕。
(2)その特定口座全体への影響 銘柄Aの売却が行われた特定口座における他の銘柄についての所得金額(取得価額)の算定にも影響させるのか(再計算が必要となるのか)との疑問も生じてきます。すなわち、銘柄Aに関するその特定口座内の所得計算からの離脱が、その特定口座全体に影響を及ぼすのかとの疑問です。
この点についても、筆者は、上記(1)と同様に、全体的な影響を生じさせる必要性はないと考えますが、形式的文理解釈としての疑問を払拭できない点などについては、上記(1)と同様です。
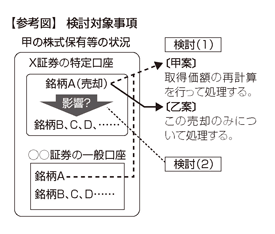
Q2について
1.問題の所在等 担保の対象としようとする株式等が乙(担保権設定者・債務者)の特定口座に保管されている場合、その株式等が特定口座から払出されて質権等の設定が行われることになります(脚注28)。その後、担保権が解除されたとしても、特定口座への受入れ可能な株式等は、措置法37条の11の3第二号及び措置法施行令25条の10の2第15項において限定列挙されており、担保の用に供されていた銘柄Bを乙の特定口座に「再入庫」することができません(脚注29)。
それにもかかわらず、ご質問のケースでは再入庫したとのことですから、税法の規定に沿っていない再入庫した株式等についての税務処理について検討する必要が生じます(また、そのような事務処理を行った事実関係などの点についての再度の確認が必要です)。
2.検 討 銘柄Bの特定口座への再入庫は、税務上(脚注30)、認められないものとなっています(以下、本稿においては、便宜上、「無効」と表現します)。この場合、特定口座による税務処理が無効となるのであって、B銘柄の売却自体を無効とする必要性は全くないと考えます(脚注31)。
しかしながら、特定口座としての税務処理に当たって、その無効が銘柄Bの売却に留まるものと見るか、あるいは、その特定口座内における全体の取引にも及ぶのかとの問題も生じてきます。すなわち、その特定口座以外に同一銘柄を保有している場合の「区分」処理を認容し得るかなどの問題として捉えることになります。
このような問題点についても、Q1と同様の理由により、その再計算は部分的(銘柄B)に留めるべきものと考えられます。
もっとも、Q1のケースとは異なり、Q2におけるB銘柄の再入庫が無効なものと認識されることから、具体的な申告方法としては、平成22年1月に銘柄Bが@1,000円の取得価額によって払い出されたものとして対応することになると考えます。
また、その特定口座内における他の銘柄についての再計算等の必要はないものと考えます。なぜなら、他の部分については、税法の規定に適った計算等が行われているのであり、銘柄Bの再入庫について生じた無効が、その特定口座の全部に及ぶとする規定はなく、また、その必要性もないと考えられることによるものです〔なお、証券会社等が、どのように年間取引報告書を作成するのか、予め確定申告前に確認しておく必要もあります〕。
脚注
1 証券取引における特定口座の位置づけ等については、参考1の日本証券業協会のQ&A(23頁)を参照。
2 タンス株については、参考2(25頁)を参照。
3 旧措置法37条の11の2、厳密には、平成14年改正措令附則14の3による特例です(参考3(26頁)を参照)。
4 株式担保の概要については、参考4(27頁)を参照。
5 証券会社等によっては、証券会社等からの借入に伴う担保として特定口座に株式等を入庫したままで担保の用に供することができる貸付契約などを用意しているところもあります。
なお、顧客が証券会社等に対して貸株を行い、その貸付契約に基づき株式が返還された際の特定口座への再入庫については措置法施行令25条の10の2⑮十六によって可能となっていますが、ご質問のケースはこの貸株の返還とは異なるものです。
6 念のために申し添えると、この論点は、特定口座内で生じた譲渡損失について、確定申告を行うことにより損益通算などを適用することができることとは(措法37の12の2)別のものです。以下の記述においても同様です。
7 概算取得費を適用した計算が可能となるように証券会社等の計算システムを修正することは技術的には可能とは思われますが、このようなレア・ケースにコストをかける必要性は乏しいところです。また、条文の規定としても、措置法31条の4の概算取得費の適用対象となるのは、昭和27年12月31日以前から所有していた土地等・建物等の譲渡に限られているところ、通達によってその適用対象が緩和されているものにすぎないものであることから(所基通38-16(措通31の4)参照)、措置法施行令25条の10の2に、その適用を可能とする規定を設けることも難しいものと思われます(株式等譲渡への適用は、通達の定めに基づく緩和措置となっています)。
なお、特定口座内の所得計算においては、株式等の譲渡に係る事業所得又は雑所得の売上原価と譲渡所得の取得費等については、その区分にかかわらず総平均法に準じた計算によって行われます(措令25の10の2①一)。
8 特に、源泉あり特定口座(源泉徴収選択口座)については、申告不要とすることができるという効果が生じてきます(措法37の11の5)。
9 税理士としての立場からは、本来、まず、条文の解釈等からアプローチすべきところですが、特定口座に関する基本条項である措置法37条の11の3①における「…これらの金額を計算するものとする。」の解釈等が必ずしも判然としない点があると思われることから、特定口座創設の趣旨等についての検討を条文規定の検討に先行して行っています。
10 また、課税庁側においても、申告書の審査等の事務負担の大幅な軽減が図られることにもなります。
11 参考1の「1」(23頁)を参照。
12 例えば、甲が銘柄Aをその特定口座外でも保有しており、その取得価額が、特定口座内の取得価額よりも低いケースなど。
13 平成17年改正措令附則11条第5項においても同様です。
14 営業所長の責めに帰すべき具体的な理由については、平成15年4月の日本証券業協会から会員への通知に例示されており、国税庁「株式譲渡益課税のあらまし」(平成15年6月)の問48として引用されています(TAINS・相談事例・所事例7048を参照)。
15 措置法37の11の5①
16 前記脚注14のTAINSの相談事例(国税庁資料)より引用。
17 申告を不要(除外)とすることができるとする規定(措法37の11の5①)。
18 このように確定申告書以外の申告書等の提出によって、税務上の効果が生じるものには、次のようなものがあります。ⅰ)みなし配当特例(措法9の7)…発行会社を通じた「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」の税務署長への提出(措令5の2①・②) ⅱ)特定障害者非課税信託(扶養信託)(相法21の4)…受託者である信託銀行等を通じた「特定障害者非課税信託申告書」の税務署長への提出(相令4の9①、4の18) ⅲ)少額上場株式等投資の非課税口座・日本版ISA(措法37の14:平成26年施行)…証券会社等を通じた税務署長からの「非課税口座開設確認書」の交付(措法37の14⑩)、証券会社等を通じた「非課税口座開設届出書」情報の税務署長への提供(同条⑬) ⅳ)教育資金の一括贈与の非課税(平成25年度税制改正大綱49頁・平成25.4.1~27.12.31施行見込み)…金融機関を通じた「教育資金非課税申告書」の税務署長への提出 etc.
19 消費税の簡易課税制度(消法37)も納税者の事務負担の軽減を考慮した制度となっていますが、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署長に直接提出するものであること、自らが行う所得金額の計算に関するものである点などにおいて、特定口座とは、その性格を異にしているものと考えます。
20 旧措置法37の11の2、厳密には、平成14年改正措令附則14の3による特例です(参考3(26頁)参照)。
21 鈴木修編「平成23年版 税務相談事例集」107頁(大蔵財務協会)の質疑応答を参照。
22 確定申告による上場株式等の取得費特例(旧措法37の11の2)の適用には特段の申告要件が求められていませんが(単なる「できる規定」となっていました)、タンス株の入庫に関する特例の適用とは異なっていることによるものです。
23 実務的にも(申告書作成の方法等としても)、年間取引報告書の金額と相違している点などの説明資料を添付する煩雑さを避けることができます。
24 他に同一銘柄を保有していない場合には検討を要しない事項です。また、他の特定口座において、銘柄Aを保有していても、隔離効果が生じていることから、このような検討は不要です。
25 措通31の11の3-4((特定口座内保管上場株式等を払出した場合))を参照してください。
26 概算取得費と実額等による取得価額の比較にも関連する事項です。
27 表題:特定口座内保管上場株式等を払い出した場合
28 株券の電子化後の株式担保の概略については、参考4(27頁)を参照。また、前記脚注5を参照。
29 全国銀行協会の「平成21年度税制改正に関する要望」(平成20年9月)として、「株券等の電子化に伴い、顧客が担保として銀行に差し入れる特定口座内の上場株式等について、特定口座への再受入を可能とすること。」との要望が提出されたことがありました。
30 顧客と証券会社等の間における取引契約(上場株式等保管約款など)においても、措置法の規定を引用しているのが通例です。
31 私法上も、一般的には、その売買自体が無効になるとは考えられません。
32 措令25の10の2⑫二の金額
33 特定口座に受入れ可能な上場株式等については、特定口座の利便性を高める等の観点から、順次、各年度の税制改正によって、その拡大(拡充)が図られてきています。
34 旧措法37の11の2((平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例))
35 見出し:平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置
36 その銘柄の基準日における終値等をいいます。
第2回
特定口座と株式の取得価額(取得費等)
―概算取得費適用の可否などについて―
税理士 塩野入文雄
はじめに
次のQをご覧になって(特に、Q1については)、何にも問題がないのではないかと受け止められる読者も少なくないと思われます。しかしながら、ご質問者と同様に、筆者もこれらのケースに関する税務処理が必ずしも明確になっていないものと思われましたので、本稿のテーマとしました。
なお、いずれの事例も、具体的案件としては一般的な(多発する)ものではありませんが、これらの事例の検討を通じて、特定口座の税務上の位置づけや関連事項などについて整理を行うことも狙いとしています(また、条文等の解釈・適用が明らかでないケースに対応する際における筆者なりの検討方法の一例でもあります)。
Q1 甲は、X証券において、銘柄A(上場株式)を平成15年8月に@100円により特定口座で購入した(脚注1)。その後、銘柄Aは、会社の業績が著しく伸びて株価もかなり値上がりしたことから、平成25年1月に@3,000円で特定口座において売却した。
甲は、銘柄Aの売却に関して所得税の確定申告を行うことにより概算取得費(5%計算)を適用して、その取得価額(取得費)を@150円とすることができますか。
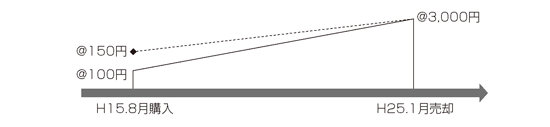
Q2 乙は、銘柄B(上場株式)を平成6年3月に@500円で購入して自宅に保管していたところ、平成15年4月にタンス株の取扱い(脚注2)によって(旧)上場株式等の取得費特例(脚注3)を適用した取得価額@1,000円(みなし取得価額)によりY証券の特定口座に入庫した。その後、Z社からの資金借入の必要が生じ、平成22年1月にその担保とするために銘柄Bを特定口座から払い出して質権を設定した(脚注4)。
平成25年1月のZ社への借入金の全額返済に伴い質権が解除され、再び、銘柄BをY証券の特定口座に再入庫してから、平成25年2月に5,000円で売却した。
乙(Y証券)は、銘柄Bの売却に関する特定口座内における所得金額の計算に当たって、その取得価額を@1,000円とした処理を行うことができますか。
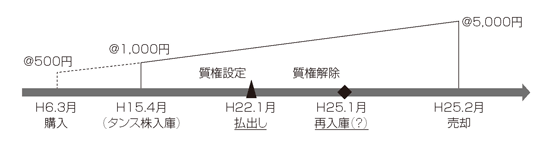
A1 甲は、所得税の確定申告を行って、概算取得費(措法31の4)を適用することができると考えられます。
なお、仄聞したところによると、ご質問の点を問題点として税務署による実地調査が行われ、国税部内での検討後に「是認」されたケースがあるようです。
A2 〔銘柄Bを特定口座に再入庫したという事実関係に不明確な点がありますが、〕税務上、ご質問のような特定口座への「再入庫」は認められていないことから、再入庫後の銘柄Bの売却に関する特定口座内における所得計算は無効(部分無効)なものと考えられます(脚注5)。
したがって、乙は、銘柄Bが平成22年1月に@1,000円の取得価額によって特定口座から払い出されたものとして、今回の売却に関する所得税の確定申告が必要になると考えられます。
(注)Q1及びQ2において、他の取引口座等に同一銘柄を保有しているケースなどに関する処理については、以下の記述の中で検討を行っています。
解説 Q1について
| 《検討事項の要約》
イ 概算取得費の適用に可否について、措置法37条の11の3第1項の「…これらの金額を計算するものとする。」との規定をどのように解釈・適用するのか。 ⇒正当(適法)に計算された特定口座の所得金額を確定申告を行うことによって是正(減額)できるのか(脚注6)。 ⅰ)制度創設の趣旨からのアプローチ ⅱ)条文規定からのアプローチ ⅲ)納税者による特定口座の開設、取引行為(『選択』)をどのように捉えるのかとの視点からのアプローチ→特例適用等(選択)の位置づけに関する検討 ロ 他口座等に銘柄A(同一銘柄)を保有しているケースなどに関する検討 ⇒概算取得費を適用した確定申告を行うことによる影響が及ぶ範囲はどこまでか。 →その特定口座における銘柄Aの売却のみの所得計算に留まるのか。 |
1.問題の所在等 現下の株式市場の情勢等からは、ご質問の点が関連してくるケースは極めてまれであると思われますが、今後の株式市場の情勢や特定口座制度の導入(創設)後10年を経過することをなど考慮した場合、将来、その売却金額が取得価額の20倍超となる銘柄も少なからず生じてくることが予想されます(また、生じてくることを願いたいものです)。したがって、一般的には、ご質問の点は喫緊の問題ではないものの、将来的には、このような問題への対応が必要となる場面が少なからず想定されるところです。
証券会社等(金融商品取引業者)によって行われる特定口座内における上場株式等(以下、「株式等」とします)の譲渡についての所得金額の計算方法は、措置法施行令25条の10の2第1項~4項に規定されています。同条(同項)には、概算取得費を適用する計算方法が規定されていないことから(脚注7)、証券会社等が概算取得費を適用した計算を行うことはできません。したがって、納税者の『選択』〔意思決定〕により開設された「特定口座」における株式等譲渡の所得金額が正当に計算されて「年間取引報告書」に記載された金額について、確定申告を行うことにより概算取得費を適用した減額(是正)ができるのかという疑問、ひいては、「特定口座」制度(同口座内で計算された所得金額)というものを税務上どのように捉えるのかという問題意識を持つことが必要になってきます。
この場合において、周知のとおり、税法には数多くの各種特例等が設けられ、それぞれの税務上の効果が付されています。また、その具体的適用に当たっては、納税者の「選択」に委ねられているものが多数あり、更に、その適用手続の多くが納税者による申告や申請などに委ねられています。
特定口座についても、その口座開設、口座内取引という納税者の「選択」により生じてくる税務上の効果としては、その特定口座における取引を他の特定口座や一般口座などにおける取引と『区分』して税務処理が行えるという点(隔離効果)などがあります(脚注8)(措法37の11の3①)。このため、筆者が仄聞した上記の税務調査が行われたとのことからも窺えるように、課税庁側においても、納税者による「選択」によって開設された特定口座内で生じた所得金額は正当に確定(固定)されており、確定申告によって、その所得金額を是正(減額)できないのではないかとの疑問が生じたものと推測されます。
2.検 討 次のとおり検討し、確定申告を行うことによって、銘柄Aの売却に関して概算取得費を適用することが可能であると考えます。
(1)制度創設の趣旨等からの検討(脚注9) 特定口座の創設趣旨については、もっぱら納税者における税務計算の事務負担(取得価額の管理)の軽減を図るものであり(脚注10)、他の多くの諸特例等とは異なり、所得金額の軽減等を図ることを目的としたものではない点に着目して、その「選択」(口座開設・口座内取引)の性格を捉えるべきものと考えます(脚注11)。このことから、証券会社等によって行われる特定口座内の所得計算は、「絶対的な確定」を生じるものではなく、是正(修正)し得るものとして捉えることが可能であると考えます(ただし、後記脚注21の点について注意が必要です)。
一方、特定口座の開設等によって、納税者サイドの事務負担の軽減が図られるだけでなく、上述した税務上の隔離効果も生じてきます。しかしながら、このような効果は、納税者の事務負担の軽減を確保するための「反射的・間接的効果」にすぎないものとして捉えるべきものであって、その特定口座の取引を他の取引と区分(隔離)することによって生じてくる所得金額の計算への影響(金額の増減)(脚注12)を云々すべきものとは考えられません(特定口座の開設等によって、結果的に生じてくる隔離効果を重要視する必要性、あるいは絶対的な所得金額の確定を生じるとする必要性は乏しいものと考えられます)。
(2)条文規定からの検討 上記(1)の点については、条文の規定としても読み取ることが可能であると考えます。
まず、措置法37条の11の3第1項には、次のとおり規定されています。
| 居住者…が、…特定口座(…)に係る…上場株式等(…)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分してこれらの金額を計算するものとする。 |
この規定を読んで、
① 特定口座内における株式等の譲渡に係る所得金額の計算に関する限りにおいて、その処理を定めたもの(確定申告による是正が可能なもの)として捉えるのか、
あるいは、
② その納税者の株式等譲渡の最終的な処理について定めた規定、すなわち、その特定口座内の所得金額を所与のもの(絶対的に確定しているもの)として捉えるのか
という点については、文理上、必ずしも判然としない面があると考えられます。
この点について、その規定対象がタンス株の取得価額などの誤りに限定されたものとはなっていますが、証券会社等によって、一端確定された所得金額を是正し得る条項が平成14年改正措置法施行令附則14条の3第5項(脚注13)として設けられていることからも、上記(1)のような捉え方、あるいは上記①のような解釈等を行う余地が生じていると考えます。
すなわち、同附則第4項は、特例上場株式等(タンス株)の入庫時において付されたその株式等の取得価額、取得の日についての誤りが、「当該営業所長の責めに帰すべき理由(脚注14)があると認める場合を除き」年間取引報告書の是正を要しないものとしています〔その反対解釈として、そのような理由によりタンス株の取得価額等に誤りが生じている場合には、その営業所長が、再計算、年間取引報告書の訂正等を行うことが必要であり、その結果、例えば、納税者が簡易特定口座について既に行っている確定申告に関して、修正申告や更正の請求等による是正を要するケースも生じてきます〕。
また、同附則第5項によって、当該営業所長の責めに帰すべき理由がある場合以外の理由により所得税の負担が少なくなったケースについては、申告不要の規定(脚注15)を適用しないこととされています。その結果、そのような誤り(タンス株の取得価額等の誤りによる所得税額の減少)がある場合には、「証券業者が譲渡所得や源泉徴収税額の再計算、年間取引報告書の修正を行う必要がなくても、個人が正しい取得価額により計算した譲渡所得を計算する必要がある。」(※)(脚注16)ことになります。
この場合において、第5項の規定が源泉あり特定口座についての申告を求める規定(申告不要規定の適用除外)に留まってはいるものの、過少な所得金額等になっているケースについて是正し得る以上は、簡易特定口座についても、また、過大な所得金額等となっているケースについても是正し得ることは当然のことと考えます。したがって、第5項については、特定口座における所得金額に関しても確定申告による是正が可能なものであり、過少となっているケースの是正に対応するために申告不要規定(脚注17)の適用を除外しているにすぎないものとして捉えることになります(第5項の規定を設けることで、その対応が足りるものとなっています)。
一方、これらの規定は、タンス株の取得価額等の誤りを是正するケースに限ったものであって、正当(適法)に計算された所得金額を是正することまでも予定したものではないと解することもできると思われます。しかしながら、然りであるとするならば、制度創設の趣旨等に沿わないものとなり、また、国税職員による措置法37条の11の3第12項~16項に基づく証券会社等に対する調査権限規定は不要のものとなることからも、そのように限定した捉え方は相当でないと考えられます。更に、証券会社等によって行われる特定口座の所得金額の計算に誤りが生じる可能性は極めて低いことから、上記附則を設けることによって、特例的なタンス株の入庫に限って、確認的な是正条項として、証券会社等に対して無用な負担を生じさせないように整備されたとも考えられます。
なお、この附則に基づく是正は、上記引用資料(※)の解説の文面によると、その特定口座外における同一銘柄との関係に言及していないことから(「正しい取得価額」とは、証券会社等によるその特定口座の計算に限定されているように読めることから)、是正を要するのは、その特定口座における誤りの部分に限られている(隔離効果が維持されている)ものと思われます〔この点については、後述する検討事項3(1)及び(2)にも関連してきます〕。
(3)「選択」に関する検討 別の視点として、特定口座の開設等は納税者の「選択」によるものであることから、概算取得費を適用した計算が特定口座内で行われないことを承知した上で、納税者が口座開設を行ったものであると捉えることによって、確定申告による再計算を行うことはできないとも考え得ると思われます。
しかしながら、もとより、概算取得費の適用については申告要件等が付されておらず、納税者の選択適用を求める制度とはなっていません。また、その銘柄の売却価額が、概算取得費による計算を行う前提となる取得価額の20倍超の金額となるか否かについては、特定口座の開設、株式等の取得時においては誰もが知り得ないところです。したがって、概算取得費の適用は結果的なものでしかなく、納税者による特定口座の開設等が概算取得費の適用を排したものと評価することは不適当であると考えます。更に加えるならば、特定口座の開設等については、例えば、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(所法10)における「非課税貯蓄申告書」(同条③)などのように、税務署長に対する申告書等を提出する制度とはなっていない点も看過してはならないと考えます(脚注18 脚注19)。
一方、上場株式等の取得費特例(みなし取得価額)(脚注20)を適用した取得価額によりタンス株を特定口座に入庫して売却したところ、後日、購入時の売買報告書が見つかり、その取得価額の方が高い場合であっても、確定申告を行うことで年間取引報告書の金額を是正することはできないものと解されています(脚注21)。しかしながら、これは、入庫時において、タンス株に関する特別の取扱い(平成14年改正措令附則14の3)に基づいた取得価額を選択適用した結果(脚注22)が確定していることによるものであって、特定口座の開設、同口座内での株式等の取引という「選択」とは、その性格が異なるものであると考えます。
以上の検討のとおり、特定口座は、納税者の便宜(事務負担の軽減)のために設けられた制度であり、また、所得金額(税負担)の直接的な軽減等を生じさせる「選択」ではないとの基本的な考え方や概算取得費の適用には申告要件が付されていないことなどから、甲が所得税の確定申告を行うことにより、銘柄Aについて概算取得費を適用した「再計算」を行うことが認められるものと考えます。
なお、本稿において筆者が意図しているところは、特定口座の所得計算(年間取引報告書の記載金額)に対して、納税者がフリー・ハンドで是正し得るものとしているものではありません。例えば、ある銘柄の特定口座内において付されている取得価額が@100円で、特定口座外で保有等している同一銘柄の取得価額が@500円であるような場合において、特定口座内での売却により生じた譲渡益について、@500円の取得価額を織り込んだ再計算に基づいて確定申告を行うことによる譲渡益の圧縮が可能となるとは考えていません。なぜなら、そのような申告は、特定口座制度創設の趣旨等から全く離れたものであり、また、納税者は、株式等を特定口座から払出して一般口座で売却しても、そのような税務上の効果を実現できるからです〔Q1についても、甲が、X証券の特定口座外に銘柄Aを保有等していないのであれば、その払出しを行って売却するとの対応があることは言うまでもありません(脚注23)〕。
3.その他 特定口座内における株式等の売却について概算取得費を適用する場合は、次のような点についても検討する必要があります(脚注24)。
(1)別に同一銘柄を保有している場合などに関する検討 概算取得費を適用して銘柄Aの売却を確定申告の対象とした場合、甲が、その特定口座外においても銘柄Aを保有等していると、両者を併せて取得価額の再計算を行う必要があるのかとの疑問が生じます。換言すると、〔甲案〕特定口座から銘柄Aが払い出された際と同様に取得費等の再計算(脚注25)が必要となるのか、あるいは、〔乙案〕特定口座内における銘柄Aの売却のみを取り出した概算取得費の適用(再計算)に留めることができるのかとの論点となります(脚注26)。
この点について、筆者は、特定口座制度創設の趣旨や概算取得費の趣旨等に鑑み、特定口座を利用して取得、譲渡した取引行為を無為にする必要性は低く、銘柄Aの取得価額の再計算を求めるまでもないと考えます(また、この点に関連して、上記引用資料(※)の記述が、〔甲案〕のような再計算を想定したものとなっていない(隔離効果を維持している)ものとも思われます)。
しかしながら、文理解釈上、措置法37条の11の3第1項には、「…これらの金額を計算するものとする。」と規定されており、銘柄Aの売却についてのみとはいえ、特定口座による所得計算から離脱する以上は、概算取得費を適用する銘柄Aの取引以外に甲がその特定口座外において保有等している銘柄Aの取得価額との関連性(影響)なしとするには、措通37の11の3-4(脚注27)の定めに相当するような緩和措置(通達)が講じられていないことから、形式的文理解釈からの疑問を払拭すことができません。このことから、他に同一銘柄を保有しているケースについては、税務署に対して事前の個別相談や文書照会等を行うことが得策であると考えられます〔また、例えば、銘柄Aを特定口座から払出してから売却すると、その影響が及ぶ範囲は、措通37の11の3-4による取扱いに留まることになります〕。
(2)その特定口座全体への影響 銘柄Aの売却が行われた特定口座における他の銘柄についての所得金額(取得価額)の算定にも影響させるのか(再計算が必要となるのか)との疑問も生じてきます。すなわち、銘柄Aに関するその特定口座内の所得計算からの離脱が、その特定口座全体に影響を及ぼすのかとの疑問です。
この点についても、筆者は、上記(1)と同様に、全体的な影響を生じさせる必要性はないと考えますが、形式的文理解釈としての疑問を払拭できない点などについては、上記(1)と同様です。
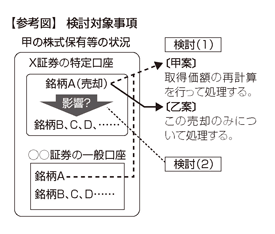
Q2について
1.問題の所在等 担保の対象としようとする株式等が乙(担保権設定者・債務者)の特定口座に保管されている場合、その株式等が特定口座から払出されて質権等の設定が行われることになります(脚注28)。その後、担保権が解除されたとしても、特定口座への受入れ可能な株式等は、措置法37条の11の3第二号及び措置法施行令25条の10の2第15項において限定列挙されており、担保の用に供されていた銘柄Bを乙の特定口座に「再入庫」することができません(脚注29)。
それにもかかわらず、ご質問のケースでは再入庫したとのことですから、税法の規定に沿っていない再入庫した株式等についての税務処理について検討する必要が生じます(また、そのような事務処理を行った事実関係などの点についての再度の確認が必要です)。
2.検 討 銘柄Bの特定口座への再入庫は、税務上(脚注30)、認められないものとなっています(以下、本稿においては、便宜上、「無効」と表現します)。この場合、特定口座による税務処理が無効となるのであって、B銘柄の売却自体を無効とする必要性は全くないと考えます(脚注31)。
しかしながら、特定口座としての税務処理に当たって、その無効が銘柄Bの売却に留まるものと見るか、あるいは、その特定口座内における全体の取引にも及ぶのかとの問題も生じてきます。すなわち、その特定口座以外に同一銘柄を保有している場合の「区分」処理を認容し得るかなどの問題として捉えることになります。
このような問題点についても、Q1と同様の理由により、その再計算は部分的(銘柄B)に留めるべきものと考えられます。
もっとも、Q1のケースとは異なり、Q2におけるB銘柄の再入庫が無効なものと認識されることから、具体的な申告方法としては、平成22年1月に銘柄Bが@1,000円の取得価額によって払い出されたものとして対応することになると考えます。
また、その特定口座内における他の銘柄についての再計算等の必要はないものと考えます。なぜなら、他の部分については、税法の規定に適った計算等が行われているのであり、銘柄Bの再入庫について生じた無効が、その特定口座の全部に及ぶとする規定はなく、また、その必要性もないと考えられることによるものです〔なお、証券会社等が、どのように年間取引報告書を作成するのか、予め確定申告前に確認しておく必要もあります〕。
脚注
1 証券取引における特定口座の位置づけ等については、参考1の日本証券業協会のQ&A(23頁)を参照。
2 タンス株については、参考2(25頁)を参照。
3 旧措置法37条の11の2、厳密には、平成14年改正措令附則14の3による特例です(参考3(26頁)を参照)。
4 株式担保の概要については、参考4(27頁)を参照。
5 証券会社等によっては、証券会社等からの借入に伴う担保として特定口座に株式等を入庫したままで担保の用に供することができる貸付契約などを用意しているところもあります。
なお、顧客が証券会社等に対して貸株を行い、その貸付契約に基づき株式が返還された際の特定口座への再入庫については措置法施行令25条の10の2⑮十六によって可能となっていますが、ご質問のケースはこの貸株の返還とは異なるものです。
6 念のために申し添えると、この論点は、特定口座内で生じた譲渡損失について、確定申告を行うことにより損益通算などを適用することができることとは(措法37の12の2)別のものです。以下の記述においても同様です。
7 概算取得費を適用した計算が可能となるように証券会社等の計算システムを修正することは技術的には可能とは思われますが、このようなレア・ケースにコストをかける必要性は乏しいところです。また、条文の規定としても、措置法31条の4の概算取得費の適用対象となるのは、昭和27年12月31日以前から所有していた土地等・建物等の譲渡に限られているところ、通達によってその適用対象が緩和されているものにすぎないものであることから(所基通38-16(措通31の4)参照)、措置法施行令25条の10の2に、その適用を可能とする規定を設けることも難しいものと思われます(株式等譲渡への適用は、通達の定めに基づく緩和措置となっています)。
なお、特定口座内の所得計算においては、株式等の譲渡に係る事業所得又は雑所得の売上原価と譲渡所得の取得費等については、その区分にかかわらず総平均法に準じた計算によって行われます(措令25の10の2①一)。
8 特に、源泉あり特定口座(源泉徴収選択口座)については、申告不要とすることができるという効果が生じてきます(措法37の11の5)。
9 税理士としての立場からは、本来、まず、条文の解釈等からアプローチすべきところですが、特定口座に関する基本条項である措置法37条の11の3①における「…これらの金額を計算するものとする。」の解釈等が必ずしも判然としない点があると思われることから、特定口座創設の趣旨等についての検討を条文規定の検討に先行して行っています。
10 また、課税庁側においても、申告書の審査等の事務負担の大幅な軽減が図られることにもなります。
11 参考1の「1」(23頁)を参照。
12 例えば、甲が銘柄Aをその特定口座外でも保有しており、その取得価額が、特定口座内の取得価額よりも低いケースなど。
13 平成17年改正措令附則11条第5項においても同様です。
14 営業所長の責めに帰すべき具体的な理由については、平成15年4月の日本証券業協会から会員への通知に例示されており、国税庁「株式譲渡益課税のあらまし」(平成15年6月)の問48として引用されています(TAINS・相談事例・所事例7048を参照)。
15 措置法37の11の5①
16 前記脚注14のTAINSの相談事例(国税庁資料)より引用。
17 申告を不要(除外)とすることができるとする規定(措法37の11の5①)。
18 このように確定申告書以外の申告書等の提出によって、税務上の効果が生じるものには、次のようなものがあります。ⅰ)みなし配当特例(措法9の7)…発行会社を通じた「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」の税務署長への提出(措令5の2①・②) ⅱ)特定障害者非課税信託(扶養信託)(相法21の4)…受託者である信託銀行等を通じた「特定障害者非課税信託申告書」の税務署長への提出(相令4の9①、4の18) ⅲ)少額上場株式等投資の非課税口座・日本版ISA(措法37の14:平成26年施行)…証券会社等を通じた税務署長からの「非課税口座開設確認書」の交付(措法37の14⑩)、証券会社等を通じた「非課税口座開設届出書」情報の税務署長への提供(同条⑬) ⅳ)教育資金の一括贈与の非課税(平成25年度税制改正大綱49頁・平成25.4.1~27.12.31施行見込み)…金融機関を通じた「教育資金非課税申告書」の税務署長への提出 etc.
19 消費税の簡易課税制度(消法37)も納税者の事務負担の軽減を考慮した制度となっていますが、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署長に直接提出するものであること、自らが行う所得金額の計算に関するものである点などにおいて、特定口座とは、その性格を異にしているものと考えます。
20 旧措置法37の11の2、厳密には、平成14年改正措令附則14の3による特例です(参考3(26頁)参照)。
21 鈴木修編「平成23年版 税務相談事例集」107頁(大蔵財務協会)の質疑応答を参照。
22 確定申告による上場株式等の取得費特例(旧措法37の11の2)の適用には特段の申告要件が求められていませんが(単なる「できる規定」となっていました)、タンス株の入庫に関する特例の適用とは異なっていることによるものです。
23 実務的にも(申告書作成の方法等としても)、年間取引報告書の金額と相違している点などの説明資料を添付する煩雑さを避けることができます。
24 他に同一銘柄を保有していない場合には検討を要しない事項です。また、他の特定口座において、銘柄Aを保有していても、隔離効果が生じていることから、このような検討は不要です。
25 措通31の11の3-4((特定口座内保管上場株式等を払出した場合))を参照してください。
26 概算取得費と実額等による取得価額の比較にも関連する事項です。
27 表題:特定口座内保管上場株式等を払い出した場合
28 株券の電子化後の株式担保の概略については、参考4(27頁)を参照。また、前記脚注5を参照。
29 全国銀行協会の「平成21年度税制改正に関する要望」(平成20年9月)として、「株券等の電子化に伴い、顧客が担保として銀行に差し入れる特定口座内の上場株式等について、特定口座への再受入を可能とすること。」との要望が提出されたことがありました。
30 顧客と証券会社等の間における取引契約(上場株式等保管約款など)においても、措置法の規定を引用しているのが通例です。
31 私法上も、一般的には、その売買自体が無効になるとは考えられません。
32 措令25の10の2⑫二の金額
33 特定口座に受入れ可能な上場株式等については、特定口座の利便性を高める等の観点から、順次、各年度の税制改正によって、その拡大(拡充)が図られてきています。
34 旧措法37の11の2((平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例))
35 見出し:平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置
36 その銘柄の基準日における終値等をいいます。
| 【参考1】「特定口座」関係規定等の整理 |
1 趣旨等
○ 「平成14年度税制改正のすべて」(99頁)・抜粋 個人投資家が、これまで源泉分離課税を選択していれば必要のなかった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算の負担を軽減する等の観点から、証券会社に開設された特定口座(1証券会社につき1口座に限ります)内に保管されていた上場株式等を譲渡した場合などの所得の金額については、その特定口座においてした上場株式等の譲渡に係るものだけを基礎として計算することができることとするとともに、その計算結果をその特定口座の開設者に報告する等の特例が設けられました。 (参考1)日本証券業協会「特定口座に関するQ&A(改定4版)」(平成21年11月)・抜粋
(注1)省略 (注2)証券会社によっては、新たに別の口座を開設するところもあります。詳しくは、お取引先の証券会社にお尋ねください。 (参考2)「源泉分離選択課税制度」について 昭和63年度税制改正により、従来「原則非課税」であった株式等の譲渡が、平成元年4月1日以降の譲渡について「原則課税」となりました。これに伴い措置されたのが『源泉分離選択課税制度』であり、平成元年4月1日から平成14年12月31日までの間、証券会社等への売委託等による上場株式等の譲渡に適用され、この制度の適用を受ける場合には、納税者による申告等は不要となっていました。
2 規定構成
 3 その他
なお、証券会社等は、その払出しに際し、顧客に対して「特定口座払出し通知書」などによって、払出した株式等に係る取得の日や取得価額(所定の計算をした金額(脚注32))などに関する一定の事項を(措令25の10の2⑩)を書面等(電磁的方法も可能)により交付することとされています。 (注)別の証券会社等における特定口座への移管に当たっても、その移管方法が定められています(措令25の10の2⑪・⑫)。 |
| 【参考2】「タンス株」に関する整理事項等 |
1 概要
しかしながら、平成15年からの株式等譲渡の申告分離課税への原則的一本化への移行に際して、その円滑な移行を期するために、自宅で保管していた株式(株券)を特定口座に受け入れることを可能とする措置が講じられていました。また、その際に付される株式の取得価額についても、実額等(注)によるほか、旧措置法37条の11の2の取得費の特例に準じた取得価額(みなし取得価額)〔参考3(26頁)参照〕によることができました(ただし、第2次タンス株については、みなし取得価額適用による入庫はできませんでした)。 (注)購入した際の取引報告書などの直接的な確認資料に記載された金額にとどまらず、名義変更の日における終値や納税者がつけていた日記帳等の記載金額によることもできました。 2 経緯(推移)
① 第1次タンス株…平成15年4月1日~平成16年12月31日 実額又はみなし取得価額による入庫が可能でした。 なお、タンス株以外にも、みなし取得価額による入庫が可能でした(次図参照)。 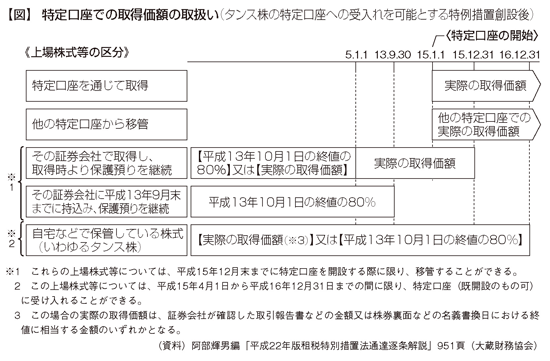 ② 第2次タンス株…平成17年4月1日~平成21年5月31日 株券の電子化への円滑な移行等に配慮して、タンス株の措置が延長されたものです。ただし、入庫する株式等の取得価額は実額等のみによることとされ、みなし取得価額による入庫はできなくなりました。 ③ タンス株廃止後…平成21年6月1日~現在 タンス株の入庫はできず、特定口座を開設している証券会社等への買委託などによる上場株式等の入庫に限られ、実額等に基づく取得価額が付されています。 なお、金融所得課税の一体化に伴い、平成28年1月1日以降に証券会社等への買委託により取得した特定公社債等の特定口座への受入れが始まりますが、その際にも、同日前に取得した特定公社債等の受入れ措置が講じられます(平成25年度税制改正大綱12頁)。 |
| 【参考3】旧「上場株式等の取得費特例」について |
1 概 要
具体的には、タンス株の特例規定である平成14年改正措置法施行令附則14の3(脚注35)のうち、同条3項三号に基づき、平成13年9月30日をその株式等の取得の日とするとともに、平成13年10月1日におけるその株式等の終値の80%相当額を取得価額(みなし取得価額)とすることもできました。 現在においても、特定口座内にある株式等については、同特例を適用したみなし取得価額が付されているものがあり(入庫され保管されているものがあり)、その売却に当たっては、その取得価額を基礎とした所定の計算を行って、特定口座における所得金額が計算されています。 一方、「旧・上場株式等の取得費特例」の具体的内容(要件等)としては、 ⅰ)基準日前(平成13年9月30日以前)から引き続き所有していた上場株式等で、 ⅱ)基準日(平成13年10月1日時点)において上場株式等であったものについては、 ⅲ)いわゆる相対取引の譲渡も含めて、 ⅳ)譲渡所得金額の計算における取得費等を ⅴ)それぞれの銘柄の「基準日の価額(脚注36)×80%」相当の金額 を基礎とした所定の計算に基づいて確定申告を行うことができました。 なお、繰り返しになりますが、特定口座内における所得金額の計算において、この特例を適用した計算が行われていた訳ではなく、あくまでも、タンス株などの入庫時における取得価額を決定する特例として同様の処理が行われていたものです。 2 特例の趣旨等
その創設趣旨としては、申告分離課税への円滑な移行に資する一環として位置づけられていたもので(「平成14年度 改正税法のすべて」(76頁))、具体的には、従来、個人納税者が上場株式等の取得価額の管理を十分に行っていなかった実情や申告分離課税に習熟するまでの間の配慮が行われたもので、その適用期限の到来を以て廃止されました。 なお、平成13年10月以降の取得については、証券会社の顧客勘定元帳によって確認できることから(10年間の帳簿保存義務)、平成22年末までの時限立法によったとされていました。 |
| 【参考4】上場株式の担保(株券電子化後) |
| 一般的に、上場株式等を担保の用に供することは、不動産担保に比して、価額変動の可能性が大きいものの、その換価(処分)容易性に優れており、少なからずその利用が行われています。 上場株式(株券)の電子化への移行後(平成21年1月5日より)における株式担保の態様は、次図のとおりです。 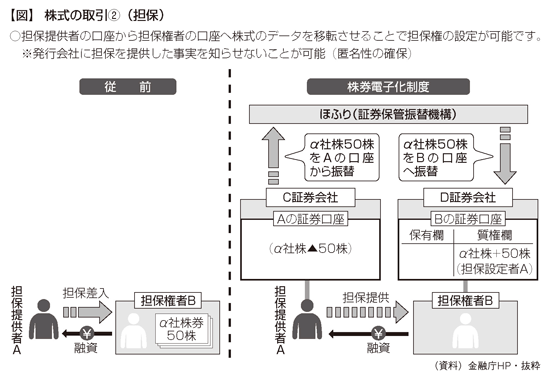 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















