解説記事2013年12月09日 【ニュース特集】 少人数私募債利子の節税メリットはあと2年に(2013年12月9日号・№526)
26年度税制改正速報・長期償還期間設定の社債発行の動きを封じ込め
少人数私募債利子の節税メリットはあと2年に
昨年度の税制改正では、少人数私募債の利子を利用した役員給与の節税策を封じ込める改正が実施されたものの、この節税封じ込め策が適用されるのは「平成28年1月1日以後に発行された社債から」ということが分かり、大きな話題を呼んだ。
これを受け、平成27年12月31日までに、償還期間が長期に渡る少人数私募債を“駆け込み”で発行しようとする動きが一部に見られたが、平成26年度税制改正では、「平成27年12月31日以前」に発行された少人数私募債に係る利子も「総合課税」の対象に取り込む旨の法令改正が実施されることが確実となった。この結果、少人数私募債の利子を使った節税策を使えるのはあと2年ということになる。
本特集では、この改正案の詳細を緊急レポートする。
現状、27年末までに発行なら、28年以後も20%の税率が適用
少人数私募債とは、50人未満の縁故者(社長、社長の親族、社員、得意先など)を対象に発行される社債であり、公募債を発行する際に求められる有価証券届出書の提出や社債管理者(銀行、信託銀行等が就任)の設置が不要なうえ、取締役会の承認のみによって発行できるなど発行手続きが簡易なのが特徴となっている。実務上は税理士の関与だけで発行されるケースが多い。
そして、少人数私募債を利用した節税とは、簡潔に言えば総合課税と分離課税の税率の差を利用するもので、役員給与に対して適用される所得税率が分離課税の税率(15%)より高い場合に効果を発揮する。すなわち、会社が少人数私募債を発行してこれを役員が購入し、役員給与の代わりに少人数私募債の利子を受け取ることで、累進税率と15%の差分の節税が実現することになる(本誌491号4頁~参照)。
この節税策を封じ込めるため、平成25年度税制改正では、「同族会社が発行し、当該同族会社の役員等が支払いを受ける社債」の利子で、「平成28年1月1日以後に支払いを受けるべきもの」には分離課税を適用せず、総合課税の対象とする旨の改正が実施された(措法3条①四、3条①一および8条の4①四)。
ところが、条文の解釈上(本誌497号9頁参照)、この節税封じ込め策が適用されるのは「平成28年1月1日以後に発行された社債から」ということが判明し、大きな話題を呼んだ。つまり、「平成27年12月31日まで」に少人数私募債を発行すれば、平成28年1月1日以後に支払われる利子についても20%(所得税15%+住民税5%)の税率(平成27年までに支払いを受ける利子には源泉分離課税(措法3条①四)、28年以後支払いを受ける利子には申告分離課税(措法3条①一、8条の4①四))が適用されるということである(図表1参照)。
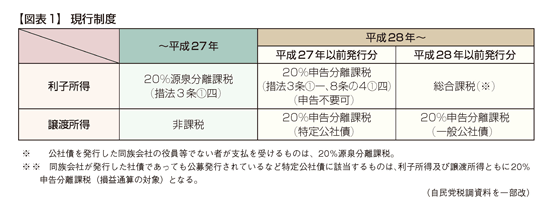
26年度改正案はこうなる
ここでポイントとなるのは、27年12月31日までに少人数私募債を発行してしまえば、節税効果を(28年以後に支払われる利子についても)ずっと享受できるという点。こうした中、平成27年末までに償還期間を長期間に設定した少人数私募債を“駆け込み”で発行しようという動きが既に出ている。
税務当局はこうした動きを問題視、平成26年度税制改正により、28年1月1日以後に支払われる利子については「総合課税」の対象とする旨の改正を実現したい意向だ。すなわち、平成27年末までに発行された少人数私募債に係る「平成28年分以後」の利子所得を申告分離課税の対象外とし、総合課税の対象とする(図表2参照)。この改正は、自民党税制調査会の資料「納税環境整備」にも盛り込まれており、実現は確実と言っていいだろう。
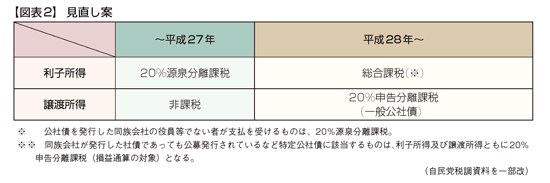
本誌497号(9頁)で既報のとおり、平成25年度税制改正の問題点は、「特定公社債“以外”の公社債で、同族会社が発行し、当該同族会社の役員等が支払いを受けるもの」を分離課税の対象外としつつ(措法3条①四、3条①一および8条の4①四)、ここでいう「特定公社債」を「平成27年12月31日以前に発行された公社債(措法37条の11②十四)」としていることにある。つまり、平成27年12月31日以前に発行された公社債はたとえ「同族会社が発行したもの」であっても特定公社債に該当し、分離課税(平成27年までに支払いを受ける利子には源泉分離課税(措法3条①四)、28年以降支払いを受ける利子には申告分離課税(措法3条①一、8条の4①四)の対象となってしまうということだ(図表3参照)。
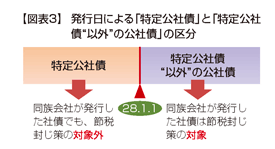
そこで、平成26年度税制改正では、現在のところ「特定公社債」に該当することになる「平成27年12月31日以前に発行された公社債」から、「同族会社が発行した社債」を除外する旨の改正が行われることになる。具体的には、上記改正法案例のような改正になるだろう。
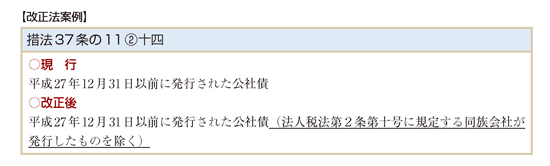
既に顧客に提案してしまった場合は?
なかには、平成25年度税制改正の内容を踏まえ、顧客に対し「28年以降の社債利子にも20%の税率が適用される」旨を説明し、既に少人数私募債を発行させてしまったケースもある。平成26年度税制改正で28年以降の社債利子が「総合課税」されるとなれば、顧客からは「話が違う」とのクレームを受ける可能性もある。
そこで、平成26年度税制改正は「不利益規定の不遡及の原則」に反するのではないかとの疑問がわく。しかし、公社債に係る平成25年度税制改正の内容は、金融所得の一体課税に関する改正同様、改正法令の適用開始日は「平成28年1月1日」とされている。すなわち、それまでは「未施行」の状態にあるため、これを26年度改正で見直したとしても、不利益規定の遡及適用にはあたらない。
もっとも、平成26年度税制改正の適用開始も同様に「平成28年1月1日」からとなる。したがって、平成27年分までの利子所得については現行通り源泉分離課税による20%の税率が適用される。つまり、少人数私募債の利子を活用した節税スキームは、あと2年間は使えることになる。
少人数私募債利子の節税メリットはあと2年に
昨年度の税制改正では、少人数私募債の利子を利用した役員給与の節税策を封じ込める改正が実施されたものの、この節税封じ込め策が適用されるのは「平成28年1月1日以後に発行された社債から」ということが分かり、大きな話題を呼んだ。
これを受け、平成27年12月31日までに、償還期間が長期に渡る少人数私募債を“駆け込み”で発行しようとする動きが一部に見られたが、平成26年度税制改正では、「平成27年12月31日以前」に発行された少人数私募債に係る利子も「総合課税」の対象に取り込む旨の法令改正が実施されることが確実となった。この結果、少人数私募債の利子を使った節税策を使えるのはあと2年ということになる。
本特集では、この改正案の詳細を緊急レポートする。
現状、27年末までに発行なら、28年以後も20%の税率が適用
少人数私募債とは、50人未満の縁故者(社長、社長の親族、社員、得意先など)を対象に発行される社債であり、公募債を発行する際に求められる有価証券届出書の提出や社債管理者(銀行、信託銀行等が就任)の設置が不要なうえ、取締役会の承認のみによって発行できるなど発行手続きが簡易なのが特徴となっている。実務上は税理士の関与だけで発行されるケースが多い。
そして、少人数私募債を利用した節税とは、簡潔に言えば総合課税と分離課税の税率の差を利用するもので、役員給与に対して適用される所得税率が分離課税の税率(15%)より高い場合に効果を発揮する。すなわち、会社が少人数私募債を発行してこれを役員が購入し、役員給与の代わりに少人数私募債の利子を受け取ることで、累進税率と15%の差分の節税が実現することになる(本誌491号4頁~参照)。
この節税策を封じ込めるため、平成25年度税制改正では、「同族会社が発行し、当該同族会社の役員等が支払いを受ける社債」の利子で、「平成28年1月1日以後に支払いを受けるべきもの」には分離課税を適用せず、総合課税の対象とする旨の改正が実施された(措法3条①四、3条①一および8条の4①四)。
ところが、条文の解釈上(本誌497号9頁参照)、この節税封じ込め策が適用されるのは「平成28年1月1日以後に発行された社債から」ということが判明し、大きな話題を呼んだ。つまり、「平成27年12月31日まで」に少人数私募債を発行すれば、平成28年1月1日以後に支払われる利子についても20%(所得税15%+住民税5%)の税率(平成27年までに支払いを受ける利子には源泉分離課税(措法3条①四)、28年以後支払いを受ける利子には申告分離課税(措法3条①一、8条の4①四))が適用されるということである(図表1参照)。
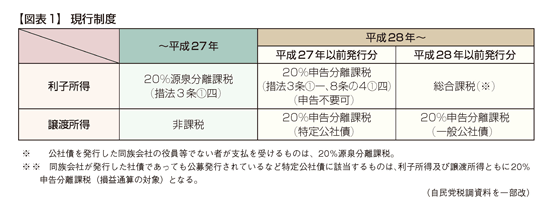
26年度改正案はこうなる
ここでポイントとなるのは、27年12月31日までに少人数私募債を発行してしまえば、節税効果を(28年以後に支払われる利子についても)ずっと享受できるという点。こうした中、平成27年末までに償還期間を長期間に設定した少人数私募債を“駆け込み”で発行しようという動きが既に出ている。
税務当局はこうした動きを問題視、平成26年度税制改正により、28年1月1日以後に支払われる利子については「総合課税」の対象とする旨の改正を実現したい意向だ。すなわち、平成27年末までに発行された少人数私募債に係る「平成28年分以後」の利子所得を申告分離課税の対象外とし、総合課税の対象とする(図表2参照)。この改正は、自民党税制調査会の資料「納税環境整備」にも盛り込まれており、実現は確実と言っていいだろう。
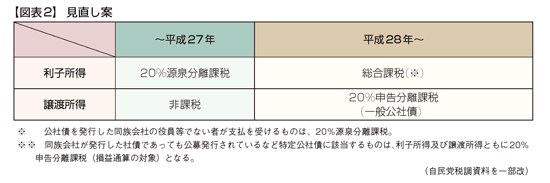
本誌497号(9頁)で既報のとおり、平成25年度税制改正の問題点は、「特定公社債“以外”の公社債で、同族会社が発行し、当該同族会社の役員等が支払いを受けるもの」を分離課税の対象外としつつ(措法3条①四、3条①一および8条の4①四)、ここでいう「特定公社債」を「平成27年12月31日以前に発行された公社債(措法37条の11②十四)」としていることにある。つまり、平成27年12月31日以前に発行された公社債はたとえ「同族会社が発行したもの」であっても特定公社債に該当し、分離課税(平成27年までに支払いを受ける利子には源泉分離課税(措法3条①四)、28年以降支払いを受ける利子には申告分離課税(措法3条①一、8条の4①四)の対象となってしまうということだ(図表3参照)。
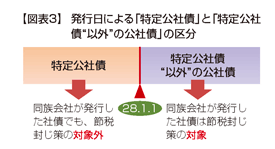
そこで、平成26年度税制改正では、現在のところ「特定公社債」に該当することになる「平成27年12月31日以前に発行された公社債」から、「同族会社が発行した社債」を除外する旨の改正が行われることになる。具体的には、上記改正法案例のような改正になるだろう。
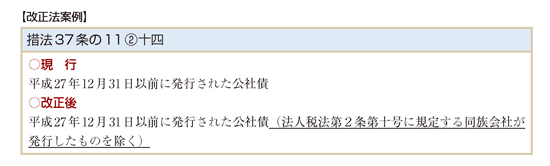
既に顧客に提案してしまった場合は?
なかには、平成25年度税制改正の内容を踏まえ、顧客に対し「28年以降の社債利子にも20%の税率が適用される」旨を説明し、既に少人数私募債を発行させてしまったケースもある。平成26年度税制改正で28年以降の社債利子が「総合課税」されるとなれば、顧客からは「話が違う」とのクレームを受ける可能性もある。
そこで、平成26年度税制改正は「不利益規定の不遡及の原則」に反するのではないかとの疑問がわく。しかし、公社債に係る平成25年度税制改正の内容は、金融所得の一体課税に関する改正同様、改正法令の適用開始日は「平成28年1月1日」とされている。すなわち、それまでは「未施行」の状態にあるため、これを26年度改正で見直したとしても、不利益規定の遡及適用にはあたらない。
もっとも、平成26年度税制改正の適用開始も同様に「平成28年1月1日」からとなる。したがって、平成27年分までの利子所得については現行通り源泉分離課税による20%の税率が適用される。つまり、少人数私募債の利子を活用した節税スキームは、あと2年間は使えることになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















