解説記事2014年03月10日 【ニュース特集】 内部統制監査の免除など、金融商品取引法改正案を読み解く(2014年3月10日号・№538)
上場企業の資金調達がやりやすく!
内部統制監査の免除など、金融商品取引法改正案を読み解く
自民党の財務金融部会・金融調査会合同会議が3月4日に開催され、政府が通常国会に提出する「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を了承した。改正金商法案には、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」が取りまとめた報告書の内容が主な改正項目として盛り込まれている。
新規上場の促進のため、新規上場後一定期間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査を免除する。また、資金調達の円滑化等を図るため、自己株式の取得等する場合には大量保有報告書の提出を不要とするほか、流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損害賠償責任については、現行の「無過失責任」から「過失責任」に改正する。そのほか、米国と同様、少額のクラウドファンディングの利用促進から金商業者の参入要件を緩和する。これらの改正は、原則として公布の日から1年以内に政令で定める日から施行される。本特集では、金融商品取引法改正案の概要をお伝えする。
新規上場企業の内部統制監査は3年間免除
今回の金融商品取引法改正案は、市場の活性化策として、新規上場の促進や資金調達の円滑化、新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等を掲げている。
新規上場の促進策としては、内部統制報告書の提出義務自体は現行どおりとするが、新規上場後、「3年間」に限り内部統制報告書に係る公認会計士等による監査を免除することとしている(図表1参照)。2012年4月に施行された米国のJOBS法(Jumpstart Our Business Startups Act=新興成長企業起業促進法)をモデルとするものだ。
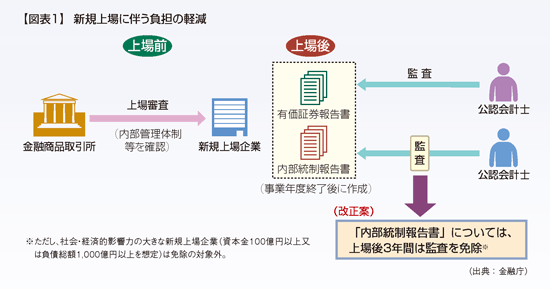
理由としては、①新規上場企業については、金融商品取引所から内部管理体制も含めた厳格な上場審査を受けていること、②年間監査報酬額の20%程度を占めるといわれる内部統制に係る監査報酬が新規上場企業にとっては負担であることなどが挙げられている。
また、公認会計士等による監査を免除する期間が「3年間」となった背景には、新規上場後3年間は、売上高、従業員数、役員数のいずれの指標も上場時からの変化率が50%を下回っているとして企業状態に大きな変化はないと考えられるからとしている。
一定規模以上の企業は監査あり ただし、新規上場企業であっても、一定規模の企業については市場への影響等を勘案し対象外とする方針だ。
具体的には、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上の企業が該当することになる。この点は政令で規定される見通しである。なお、最近の新規上場企業のうち、この基準に抵触する企業は日本航空や大塚ホールディングスなど7社が該当している。
企業規模拡大しても監査義務は復活せず 一方、米国の場合は新規上場企業の内部統制監査を「5年間」免除しているが、その一方で免除対象企業が成長し、免除基準(売上高10億ドル未満等)を満たさなくなった場合は、監査義務を復活させる仕組みとなっている。
日本の場合は、一定規模の会社(資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上)に該当したとしても、①3年間に限定した措置であること、②基準値到達が視野に入った場合、監査負担を避けるために資本金・負債を抑制するおそれがあることなどの理由から米国のように監査義務を復活させる措置は講じられていない。
投資型クラウドファンディングの参入要件を緩和へ
米国のJOBS法と同様、投資型クラウドファンディングの利用促進のため、金融商品取引業者の参入要件を緩和するとともに、投資者保護のためのルールを整備する(図表2参照)。
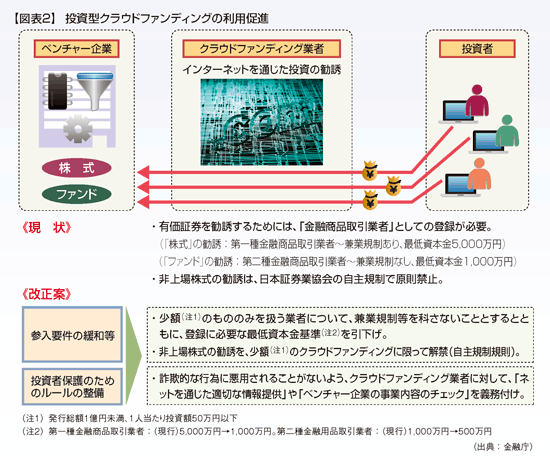
1人当たりの投資額は50万円以下 具体的には、少額の株式やファンドのみを扱う金融商品取引業者については、兼業規制を課さないこととするとともに、登録に必要な最低資本金基準を引き下げる。少額とは、発行総額1億円未満、1人当たりの投資額が50万円以下のものだ。非上場株式の勧誘についても少額のクラウドファンディングに限って解禁する。
また、投資者保護として「ネットを通じた適切な情報提供」や「ベンチャー企業の事業内容のチェック」を義務付けるほか、クーリングオフの対象にする。
新たな非上場株式の取引制度が創設
新たな非上場株式の取引制度が創設する運びだ。現行、一般の非上場株式の場合、証券会社は投資勧誘が原則として禁止されている。グリーンシート銘柄については投資勧誘が可能だが、インサイダー取引規制や開示義務の適用対象となっているため、非上場企業にとっては大きな負担となっているのが現状だ。
投資グループに限った投資勧誘が可能に 今回、新たに創設される非上場株式の取引制度は、証券会社が組成する「投資グループ」のメンバーに限って投資勧誘を可能とするもの。現行制度と同様、日本証券業協会の自主規制に基づくものである。投資グループのメンバーとしては、①当該企業の役員・従業員、②当該企業の株主・取引先、③当該企業から財・サービスの提供を受けている者等が想定される。
投資グループのメンバーに限ったものであるため、一般の非上場株式に準じた規制内容とする。具体的には、インサイダー取引規制の対象外とするとともに、開示の負担も軽減する。これにより、非上場株式の取引・換金ニーズに応えられる制度となることが期待される。
証券会社の事業年度規制を撤廃
金融商品取引業者の事業年度規制の見直しが行われる(図表3参照)。現行、証券会社については統一的な監督を行う必要から、事業年度は3月期決算であることが法定化されている。
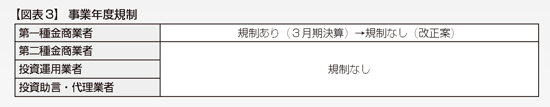
このため、たとえば、12月決算を行っている外国証券会社が日本に現地法人・支店を設立して業務を行う場合、本国と日本それぞれに時期が異なる決算書類等を作成する必要があり、過大な事務負担が生じている。今回の金融商品取引法の改正では、この事業年度規制を撤廃することとしている(公布の日から6月以内に政令で定める日から施行)。
大量保有報告制度は適用対象から自己株式を除外へ
大量保有報告制度については、上場企業の資金調達の円滑化の観点から大幅な見直しが行われる。
大量保有報告制度は、株券等の保有割合が5%超となった場合に、その日から5営業日以内に「大量保有報告書」を提出することとされている。また、その後の保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合には、変更があった日から5営業日以内に「変更報告書」を提出することが求められている。
自己株式の取得等は有報等でも開示 現在、同制度の対象となる株券等には自己株式も含まれるが、①企業は議決権を有しないため、経営に対する影響力は通常の株式に比べて限定的、②市場における需給環境に影響を与えるような自己株式の取得や処分が行われる場合には、自己株券買付状況報告書や有価証券報告書等により別途情報が開示されているなどの理由から、自己株式を対象から除外することになったものである。
例年、大量保有報告書提出件数の約1割(平成24年の場合は120件(9.1%))が自己株式の保有に係るものとなっている。自己株式が対象外となることで、多くの上場企業で円滑な資本政策の実施が可能になる。
大量保有報告書提出者の事務負担を大幅軽減に
上記以外にも大量保有報告制度については、報告書提出者の負担軽減を図るため、①変更報告書の同時提出者義務を廃止、②短期大量譲渡報告における記載事項から、僅少な株券等の譲渡先に関する事項を除外する、③訂正報告書の公衆縦覧期間の末日を、訂正の基礎である大量保有報告書等の公衆縦覧期間の末日と同一にする、④大量保有報告書等の写しを発行企業に対して送付する義務を免除する(公衆の縦覧に供されるEDINETを通じて提出されたことが条件)の措置が講じられる。
変更報告書の同時提出義務を廃止 まずは、変更報告書の同時提出義務の廃止だ。大量保有報告制度では、「変更報告書」の提出日の前日までに、「新たな提出事由」が生じた場合には、当初の提出事由に係る大量保有報告書や変更報告書と同時に「新たな提出事由に係る変更報告書」を提出するという同時提出義務が課されている。また、この同時提出義務を踏まえ、株券等の大量保有者は、提出日の前日に、共同保有者の分を含め、株券等の保有状況を確認したうえで変更報告書の提出を行う必要がある。
しかし、最近では子会社等を多く抱える投資者の場合には、保有状況の確認に時間を要するため、実務上の対応ができないといった弊害が指摘されている。実際に遵守できない事例もあり、今回、同時提出義務を廃止することになったものである。
希少な株券等の譲渡の相手先の記載は不要 ②短期大量譲渡報告に関しては、記載事項から僅少な株券等の譲渡先に関する事項が除外される。
大量保有報告制度においては、大量保有報告書を提出後、保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に「変更報告書」を提出しなければならないとされている。このうち、保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者については、短期大量譲渡に該当する場合には、最近60日間の「すべての譲渡」について、「相手方及び対価に関する事項」を当該変更報告書に記載することが義務付けられている。
しかし、僅少な株券等を譲渡したに過ぎない場合であっても、その「相手方及び対価に関する事項」を開示させることは過大な負担となっているとの指摘があったものである。このため、譲渡の相手方についての記載事項は除かれることになっている。
訂正報告書の公衆縦覧期間を変更 ③の訂正報告書の公衆縦覧期間については、訂正の基礎である大量保有報告書や変更報告書の公衆縦覧期間の末日と同日にするというもの。現行制度では、大量保有報告書等の公衆縦覧期間の終了後も、一定期間、訂正報告書のみが公衆縦覧に供されている状況となっており、開示しておく意義は乏しいとの指摘があるものである。
また、④大量保有報告書等については、その提出者は遅滞なく、これらの書類の写しを発行体企業に対して送付しなければならないとされている。
しかし、大量保有報告書等に記載される情報はEDINETによる開示を通じてタイムリーに行われているため、当該通知事務を免除することとしている。
継続開示書類の訂正発行登録書は免除に そのほか、発行登録書を提出している企業が有価証券報告書等の継続開示書類を提出し場合の訂正発行登録書の提出義務を免除する。
発行登録制度は、将来、有価証券の募集・売出しを予定している企業が「有価証券届出書」を提出する代わりに、予め募集・売出しに係る一定の事項を発行登録しておくことにより、発行条件を決めた後、当該条件等を記載した簡易な「発行登録追補書類」を提出すれば、すぐに有価証券の発行ができる制度のこと。ただし、現行制度では、有価証券報告書や四半期報告書といった定期的に提出されることが明らかな「継続開示書類」についても、その提出の度に「訂正発行登録書」の提出が義務付けられている。このため、発行登録制度の利用を阻害する一因となっている。
そもそも有価証券報告書等が提出される度に「訂正発行登録書」の提出が求められているのは、「発行登録書」で参照している企業情報が更新されたことを投資家に周知し、古い企業情報による投資判断を防止するためだ。
しかし、インターネットが普及しEDINETが整備されたことにより投資家は最新の有価証券報告書等にアクセスすることが容易になっているほか、有価証券報告書や四半期報告書、半期報告書については提出期限が法令で定められているため、これらの提出が予測可能になっている。したがって、「継続開示書類」については、提出のたびに「訂正登録報告書」を提出させる必要はないと判断したものだ。提出義務を免除するに当たっては、「発行登録書」に「継続開示書類」の法定提出期限を記載させることとし、仮に当該期間を過ぎた場合には、「訂正発行登録書」を提出することになる。
なお、臨時報告書については、有価証券報告書等とは異なり、定期的に提出されるものではないため、現行どおり、臨時報告書が提出された場合には、「訂正発行登録報告書」の提出が求められることになる。
株券の処分者も損害賠償請求が可能に 流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損害賠償責任については、現行の「無過失責任」から「過失責任」に改正する(図表4参照)。そもそも損害賠償請求責任は、「過失責任」が原則だからだ。
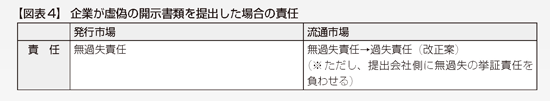
ただし、提出会社の故意・過失の有無に係る立証責任については、投資者の訴訟負担が過大にならないよう、現行の役員等の損害賠償責任に係る立証責任と同様、提出会社側に無過失の挙証責任を負わせることとする。
加えて損害賠償請求者の範囲も拡大する。取得者のみでなく、すでに株券を処分した者も対象とする。米国や英国と同様となる。
株券電子化により問題が深刻化
そのほか、電子化された株券等の没収手続の整備が行われる(本誌537号15頁参照)。
金融商品取引法上、犯人が犯罪行為により得た財産等は没収の対象になっている。対象となる財産は有体物、無体財産(金銭債権等)であるが、「有体物」については刑事訴訟法により没収が可能であるものの、「無体財産」については没収に係る手続規定がないため、没収不可という状況となっている。また、株券も電子化により無体財産となり没収ができなくなっている。
このため、今回の改正では、電子化された株券等、「無体財産」の没収に係る手続規定が整備されることになる(公布の日から6月以内に政令で定める日から施行)。
内部統制監査の免除など、金融商品取引法改正案を読み解く
自民党の財務金融部会・金融調査会合同会議が3月4日に開催され、政府が通常国会に提出する「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を了承した。改正金商法案には、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」が取りまとめた報告書の内容が主な改正項目として盛り込まれている。
新規上場の促進のため、新規上場後一定期間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査を免除する。また、資金調達の円滑化等を図るため、自己株式の取得等する場合には大量保有報告書の提出を不要とするほか、流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損害賠償責任については、現行の「無過失責任」から「過失責任」に改正する。そのほか、米国と同様、少額のクラウドファンディングの利用促進から金商業者の参入要件を緩和する。これらの改正は、原則として公布の日から1年以内に政令で定める日から施行される。本特集では、金融商品取引法改正案の概要をお伝えする。
新規上場企業の内部統制監査は3年間免除
今回の金融商品取引法改正案は、市場の活性化策として、新規上場の促進や資金調達の円滑化、新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等を掲げている。
新規上場の促進策としては、内部統制報告書の提出義務自体は現行どおりとするが、新規上場後、「3年間」に限り内部統制報告書に係る公認会計士等による監査を免除することとしている(図表1参照)。2012年4月に施行された米国のJOBS法(Jumpstart Our Business Startups Act=新興成長企業起業促進法)をモデルとするものだ。
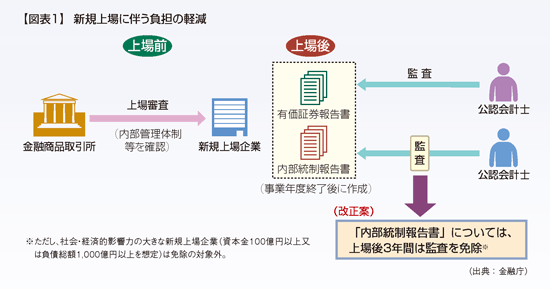
理由としては、①新規上場企業については、金融商品取引所から内部管理体制も含めた厳格な上場審査を受けていること、②年間監査報酬額の20%程度を占めるといわれる内部統制に係る監査報酬が新規上場企業にとっては負担であることなどが挙げられている。
また、公認会計士等による監査を免除する期間が「3年間」となった背景には、新規上場後3年間は、売上高、従業員数、役員数のいずれの指標も上場時からの変化率が50%を下回っているとして企業状態に大きな変化はないと考えられるからとしている。
一定規模以上の企業は監査あり ただし、新規上場企業であっても、一定規模の企業については市場への影響等を勘案し対象外とする方針だ。
具体的には、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上の企業が該当することになる。この点は政令で規定される見通しである。なお、最近の新規上場企業のうち、この基準に抵触する企業は日本航空や大塚ホールディングスなど7社が該当している。
企業規模拡大しても監査義務は復活せず 一方、米国の場合は新規上場企業の内部統制監査を「5年間」免除しているが、その一方で免除対象企業が成長し、免除基準(売上高10億ドル未満等)を満たさなくなった場合は、監査義務を復活させる仕組みとなっている。
日本の場合は、一定規模の会社(資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上)に該当したとしても、①3年間に限定した措置であること、②基準値到達が視野に入った場合、監査負担を避けるために資本金・負債を抑制するおそれがあることなどの理由から米国のように監査義務を復活させる措置は講じられていない。
投資型クラウドファンディングの参入要件を緩和へ
米国のJOBS法と同様、投資型クラウドファンディングの利用促進のため、金融商品取引業者の参入要件を緩和するとともに、投資者保護のためのルールを整備する(図表2参照)。
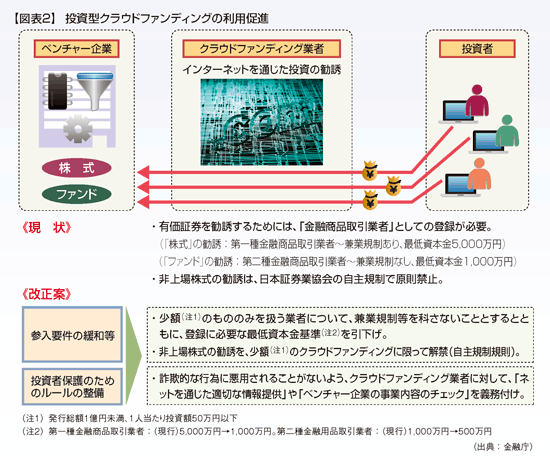
1人当たりの投資額は50万円以下 具体的には、少額の株式やファンドのみを扱う金融商品取引業者については、兼業規制を課さないこととするとともに、登録に必要な最低資本金基準を引き下げる。少額とは、発行総額1億円未満、1人当たりの投資額が50万円以下のものだ。非上場株式の勧誘についても少額のクラウドファンディングに限って解禁する。
また、投資者保護として「ネットを通じた適切な情報提供」や「ベンチャー企業の事業内容のチェック」を義務付けるほか、クーリングオフの対象にする。
新たな非上場株式の取引制度が創設
新たな非上場株式の取引制度が創設する運びだ。現行、一般の非上場株式の場合、証券会社は投資勧誘が原則として禁止されている。グリーンシート銘柄については投資勧誘が可能だが、インサイダー取引規制や開示義務の適用対象となっているため、非上場企業にとっては大きな負担となっているのが現状だ。
投資グループに限った投資勧誘が可能に 今回、新たに創設される非上場株式の取引制度は、証券会社が組成する「投資グループ」のメンバーに限って投資勧誘を可能とするもの。現行制度と同様、日本証券業協会の自主規制に基づくものである。投資グループのメンバーとしては、①当該企業の役員・従業員、②当該企業の株主・取引先、③当該企業から財・サービスの提供を受けている者等が想定される。
投資グループのメンバーに限ったものであるため、一般の非上場株式に準じた規制内容とする。具体的には、インサイダー取引規制の対象外とするとともに、開示の負担も軽減する。これにより、非上場株式の取引・換金ニーズに応えられる制度となることが期待される。
証券会社の事業年度規制を撤廃
金融商品取引業者の事業年度規制の見直しが行われる(図表3参照)。現行、証券会社については統一的な監督を行う必要から、事業年度は3月期決算であることが法定化されている。
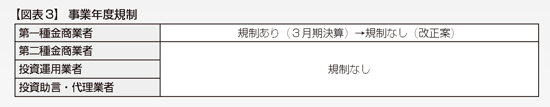
このため、たとえば、12月決算を行っている外国証券会社が日本に現地法人・支店を設立して業務を行う場合、本国と日本それぞれに時期が異なる決算書類等を作成する必要があり、過大な事務負担が生じている。今回の金融商品取引法の改正では、この事業年度規制を撤廃することとしている(公布の日から6月以内に政令で定める日から施行)。
大量保有報告制度は適用対象から自己株式を除外へ
大量保有報告制度については、上場企業の資金調達の円滑化の観点から大幅な見直しが行われる。
大量保有報告制度は、株券等の保有割合が5%超となった場合に、その日から5営業日以内に「大量保有報告書」を提出することとされている。また、その後の保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合には、変更があった日から5営業日以内に「変更報告書」を提出することが求められている。
自己株式の取得等は有報等でも開示 現在、同制度の対象となる株券等には自己株式も含まれるが、①企業は議決権を有しないため、経営に対する影響力は通常の株式に比べて限定的、②市場における需給環境に影響を与えるような自己株式の取得や処分が行われる場合には、自己株券買付状況報告書や有価証券報告書等により別途情報が開示されているなどの理由から、自己株式を対象から除外することになったものである。
例年、大量保有報告書提出件数の約1割(平成24年の場合は120件(9.1%))が自己株式の保有に係るものとなっている。自己株式が対象外となることで、多くの上場企業で円滑な資本政策の実施が可能になる。
大量保有報告書提出者の事務負担を大幅軽減に
上記以外にも大量保有報告制度については、報告書提出者の負担軽減を図るため、①変更報告書の同時提出者義務を廃止、②短期大量譲渡報告における記載事項から、僅少な株券等の譲渡先に関する事項を除外する、③訂正報告書の公衆縦覧期間の末日を、訂正の基礎である大量保有報告書等の公衆縦覧期間の末日と同一にする、④大量保有報告書等の写しを発行企業に対して送付する義務を免除する(公衆の縦覧に供されるEDINETを通じて提出されたことが条件)の措置が講じられる。
変更報告書の同時提出義務を廃止 まずは、変更報告書の同時提出義務の廃止だ。大量保有報告制度では、「変更報告書」の提出日の前日までに、「新たな提出事由」が生じた場合には、当初の提出事由に係る大量保有報告書や変更報告書と同時に「新たな提出事由に係る変更報告書」を提出するという同時提出義務が課されている。また、この同時提出義務を踏まえ、株券等の大量保有者は、提出日の前日に、共同保有者の分を含め、株券等の保有状況を確認したうえで変更報告書の提出を行う必要がある。
しかし、最近では子会社等を多く抱える投資者の場合には、保有状況の確認に時間を要するため、実務上の対応ができないといった弊害が指摘されている。実際に遵守できない事例もあり、今回、同時提出義務を廃止することになったものである。
希少な株券等の譲渡の相手先の記載は不要 ②短期大量譲渡報告に関しては、記載事項から僅少な株券等の譲渡先に関する事項が除外される。
大量保有報告制度においては、大量保有報告書を提出後、保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に「変更報告書」を提出しなければならないとされている。このうち、保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者については、短期大量譲渡に該当する場合には、最近60日間の「すべての譲渡」について、「相手方及び対価に関する事項」を当該変更報告書に記載することが義務付けられている。
しかし、僅少な株券等を譲渡したに過ぎない場合であっても、その「相手方及び対価に関する事項」を開示させることは過大な負担となっているとの指摘があったものである。このため、譲渡の相手方についての記載事項は除かれることになっている。
訂正報告書の公衆縦覧期間を変更 ③の訂正報告書の公衆縦覧期間については、訂正の基礎である大量保有報告書や変更報告書の公衆縦覧期間の末日と同日にするというもの。現行制度では、大量保有報告書等の公衆縦覧期間の終了後も、一定期間、訂正報告書のみが公衆縦覧に供されている状況となっており、開示しておく意義は乏しいとの指摘があるものである。
また、④大量保有報告書等については、その提出者は遅滞なく、これらの書類の写しを発行体企業に対して送付しなければならないとされている。
しかし、大量保有報告書等に記載される情報はEDINETによる開示を通じてタイムリーに行われているため、当該通知事務を免除することとしている。
継続開示書類の訂正発行登録書は免除に そのほか、発行登録書を提出している企業が有価証券報告書等の継続開示書類を提出し場合の訂正発行登録書の提出義務を免除する。
発行登録制度は、将来、有価証券の募集・売出しを予定している企業が「有価証券届出書」を提出する代わりに、予め募集・売出しに係る一定の事項を発行登録しておくことにより、発行条件を決めた後、当該条件等を記載した簡易な「発行登録追補書類」を提出すれば、すぐに有価証券の発行ができる制度のこと。ただし、現行制度では、有価証券報告書や四半期報告書といった定期的に提出されることが明らかな「継続開示書類」についても、その提出の度に「訂正発行登録書」の提出が義務付けられている。このため、発行登録制度の利用を阻害する一因となっている。
そもそも有価証券報告書等が提出される度に「訂正発行登録書」の提出が求められているのは、「発行登録書」で参照している企業情報が更新されたことを投資家に周知し、古い企業情報による投資判断を防止するためだ。
しかし、インターネットが普及しEDINETが整備されたことにより投資家は最新の有価証券報告書等にアクセスすることが容易になっているほか、有価証券報告書や四半期報告書、半期報告書については提出期限が法令で定められているため、これらの提出が予測可能になっている。したがって、「継続開示書類」については、提出のたびに「訂正登録報告書」を提出させる必要はないと判断したものだ。提出義務を免除するに当たっては、「発行登録書」に「継続開示書類」の法定提出期限を記載させることとし、仮に当該期間を過ぎた場合には、「訂正発行登録書」を提出することになる。
なお、臨時報告書については、有価証券報告書等とは異なり、定期的に提出されるものではないため、現行どおり、臨時報告書が提出された場合には、「訂正発行登録報告書」の提出が求められることになる。
株券の処分者も損害賠償請求が可能に 流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損害賠償責任については、現行の「無過失責任」から「過失責任」に改正する(図表4参照)。そもそも損害賠償請求責任は、「過失責任」が原則だからだ。
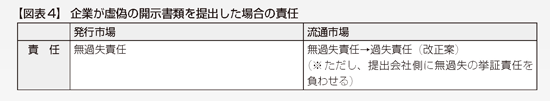
ただし、提出会社の故意・過失の有無に係る立証責任については、投資者の訴訟負担が過大にならないよう、現行の役員等の損害賠償責任に係る立証責任と同様、提出会社側に無過失の挙証責任を負わせることとする。
加えて損害賠償請求者の範囲も拡大する。取得者のみでなく、すでに株券を処分した者も対象とする。米国や英国と同様となる。
株券電子化により問題が深刻化
そのほか、電子化された株券等の没収手続の整備が行われる(本誌537号15頁参照)。
金融商品取引法上、犯人が犯罪行為により得た財産等は没収の対象になっている。対象となる財産は有体物、無体財産(金銭債権等)であるが、「有体物」については刑事訴訟法により没収が可能であるものの、「無体財産」については没収に係る手続規定がないため、没収不可という状況となっている。また、株券も電子化により無体財産となり没収ができなくなっている。
このため、今回の改正では、電子化された株券等、「無体財産」の没収に係る手続規定が整備されることになる(公布の日から6月以内に政令で定める日から施行)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























