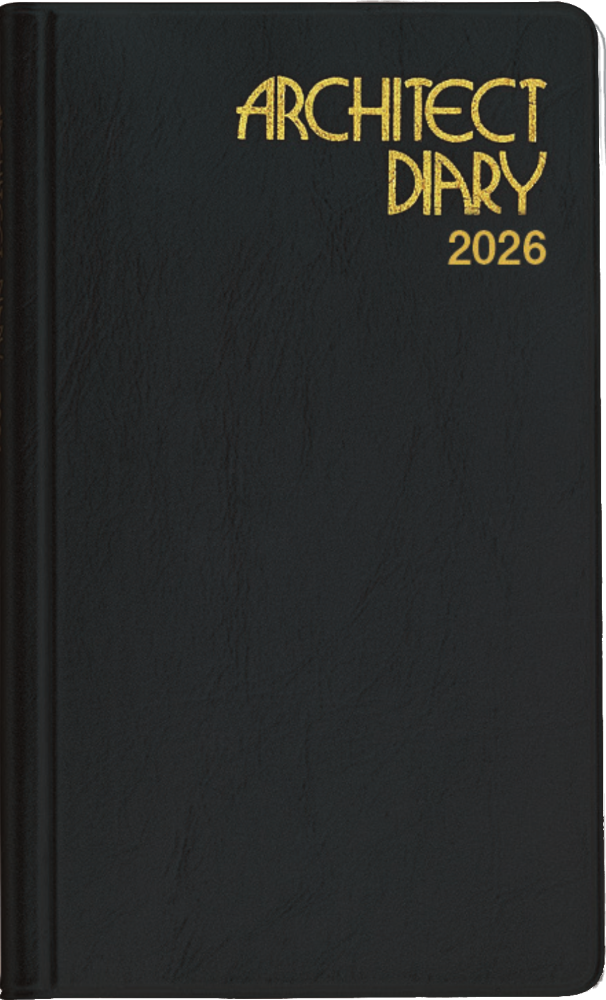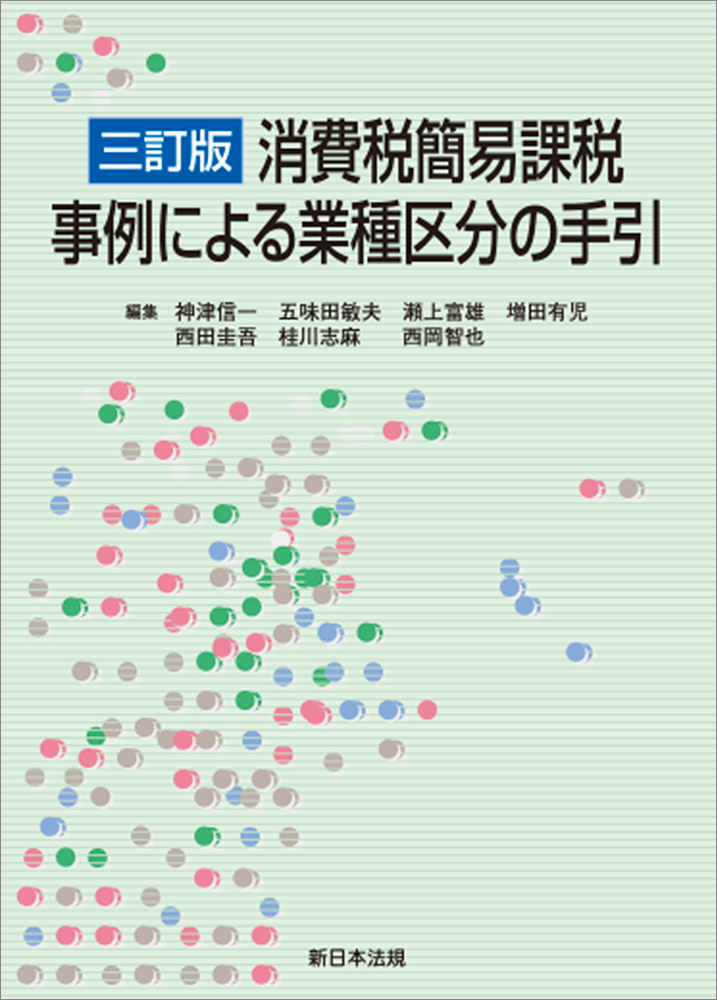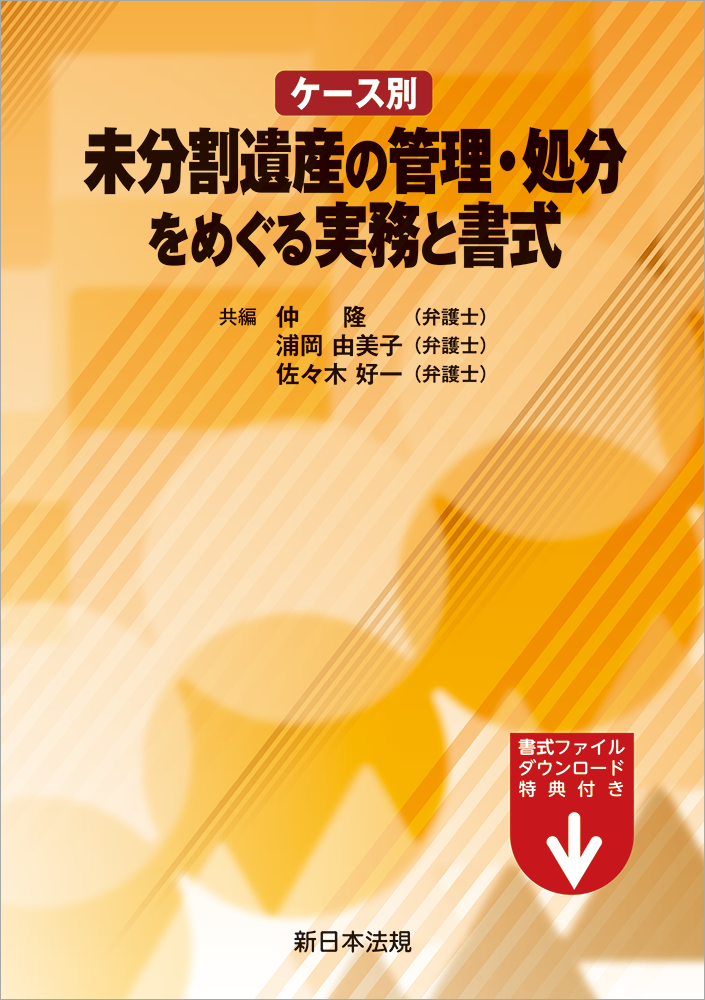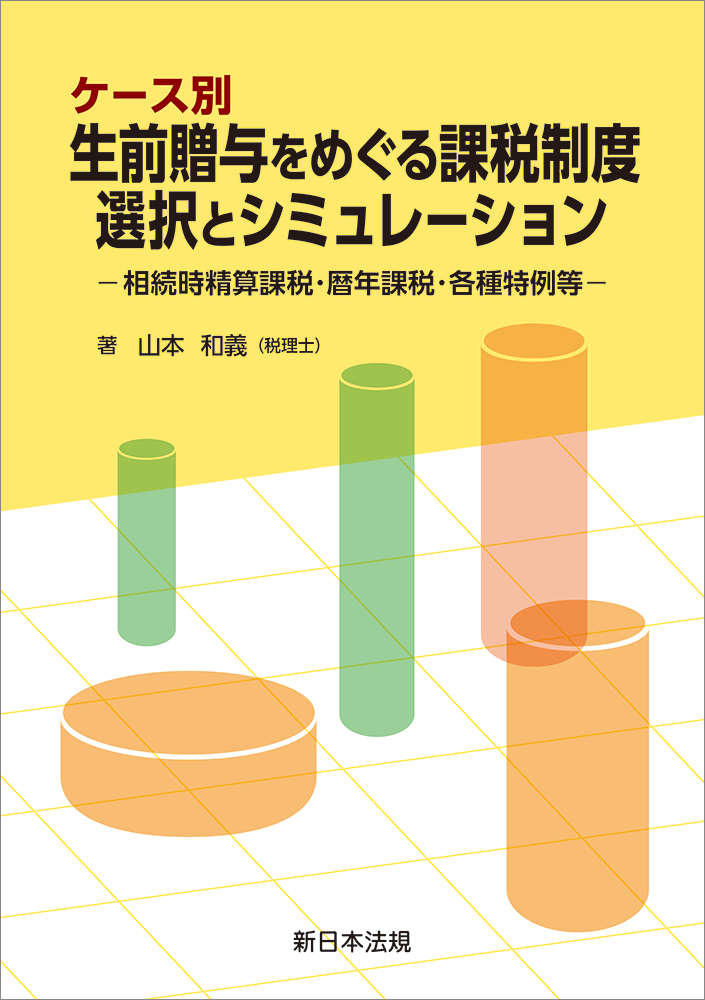解説記事2014年03月31日 【最新判決研究】 従業員等の海外慰安旅行の費用負担と経済的利益の供与(給与)(2014年3月31日号・№540)
最新判決研究
従業員等の海外慰安旅行の費用負担と経済的利益の供与(給与)
東京地裁平成24年12月25日判決(平成23年(行ウ)第385号)
東京高裁平成25年5月30日判決(平成25年(行コ)第31号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X会社(原告、控訴人)は、鉄道線路工事の請負事業を営む株式会社であるが、平成21年1月10日から同月12日まで、同社の代表者、同社の従業員10人(以下「本件従業員」という。)及び外注先の従業員等21人の合計32人を参加者として、中国澳門特別行政区(以下「マカオ」という。)への2泊3日の慰安旅行(以下「本件旅行」という。)を実施し、その費用(以下「本件旅行費用」という。)の全額合計800万円を負担した。X会社は、本件旅行費用のうち、本件従業員に係る1人当たり24万1,300円(以下「本件従業員分費用」という。)の合計241万3,000円を福利厚生費として処理した(経済的利益の供与として所得税の源泉徴収をしなかった。)。
(2)これに対し、所轄税務署長は、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するとして、国税通則法36条1項に基づき、平成21年11月25日付けで、平成21年1月分の源泉所得税の額34万7,472円とする納税の告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の額3万4,000円とする賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をした。X会社は、本件納税告知及び本件賦課決定を不服として、前審手続を経て、国(被告、被控訴人)に対し、当該各処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
なお、本件に係る裁決(平成22年12月17日付け)では、従業員の海外慰安旅行における一般的な会社負担額は、当該旅行費用の平均額8万1,154円の70.1%に相当する5万6,889円であり、本件従業員分費用がそれを大幅に上回るものであるから、所得税法上の「給与等」に該当する旨判断されている。
二、争点と当事者の主張
1 争 点 本件の争点は、本件納税告知等の適否、具体的には、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与が所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
2 国の主張 (1)本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し、X会社は、同法183条1項の規定により、上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ、この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから、X会社がこれについて本件従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7,472円である。
(2)所得税法は、給与所得とは、雇用契約又はこれに準ずる関係に基づいて提供される非独立的な人的役務の提供の対価としての性質を有する所得であると解される。そして、同法36条1項が、経済的利益による収入も課税対象となることを明らかにしていることからすると、使用者が従業員に慰安旅行に係る経済的利益を供与した場合も「給与等」に該当するということとなる。
(3)本件旅行は本件従業員の慰安及び親睦を目的として行われたものであるところ、本件従業員は、X会社の費用負担において本件旅行に係る経済的利益の供与を受けたものであるから、その経済的利益が、本件従業員との雇用契約に基づいて提供された非独立的な人的役務の提供の対価としての性質を有するものであることは明らかであり、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するというべきである。
3 X会社の主張 (1)X会社は、基礎杭打工事の中でもとりわけ危険な鉄道線路の基礎杭打工事の施行において高い技術を有しているところ、過誤が許されない危険な工事を安全に施行するためには、強固な指揮命令系統を確立し、維持することが必要不可欠である。本件旅行の目的は、退職する取引先の従業員を盛大に送り出すことを現場の全従業員に示すことにより強固な指揮命令系統を更に強化することにある。本件旅行は、X会社の社内において絶対の存在であるX会社代表者の企画立案の下に行われたものであり、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択、旅程の選択、自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって、反射的に利益を受けることはあっても、この利益を自由に処分することはできなかった。
(2)所得税法36条1項が経済的利益を「収入すべき金額」の一態様として規定しているところ、その経済的利益が所得性を有し所得税の課税対象となるためには、① 人の行為により物権の変動又は債権発生に伴い管理、使用収益及び処分権を取得すること(流入性)、② 流入によって取得した物権又は債権が直接又は間接に生活目的に何らかの役に立つ性質すなわち効用を有すること(価値の保有性)、③ 貨幣数値による評価の可能なものであること(金銭的評価の可能性)という三つの要件をいずれも満たす必要があると解すべきである(幸田久「所得税法上の経済的利益について」税務大学校編・税大研究資料第34号(昭和45年6月)研究科論文集(所得税編)。以下「幸田論文」という。)。
(3)幸田論文は、レクリエーション施設の利用、無料の研修その他の教育費等の利益は、業務の一環とみることができるのであって、流入性を有しないとしているところ、前記のとおり、本件従業員は、本件旅行について参加するか否かの選択、旅程の選択、自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであることからすれば、本件従業員分費用相当の経済的利益は、前記の流入性の要件を満たすものではない。
(4)幸田論文は、上記の私経済における反射的利益は価値の保有性についても疑問があり、職務上の必要性から自己の欲求を犠牲にしているとみられる場合には、経済的利益があるように見えても、保有性を有しないというべきであるところ、本件旅行は、職務上の必要性から自己の欲求を犠牲にして参加しなければならない社内行事であり、自由時間である休日に行われたにもかかわらず、本件従業員の生活目的に何ら役立っていないのであるから、本件従業員分費用相当の経済的利益は、価値の保有性の要件を満たすものではない。
(5)幸田論文は、所得税の課税客体である所得は全て貨幣数値で表現され、租税の納付は金銭納付を原則とするから、貨幣数値による評価の可能なもののみが課税対象の範疇に含まれるとしているところ、本件旅行は、私的な自由旅行とは区別されるべきものであり、本件従業員分費用相当の経済的利益は、金銭的評価の可能性の要件を満たすものではない。
(6)最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決・裁判集民事197号75頁は、労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとしているところ、本件旅行に参加不参加の自由はなく、行き先などについて従業員が意見を述べる機会はなく、X会社代表者の一方的指示で、旅行に連れて行かれ、旅行中であっても代表者が集合時間について厳しく注意していたことからすれば、X会社代表者が旅行中も従業員を指揮監督する状況にあったものであり、本件旅行は、業務に不可欠な指揮命令系統を強固にするためのものであった。
三、一審判決要旨
請求棄却。 (1)所得税法28条1項にいう「給与等」とは、俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(同法28条1項)、すなわち、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者等の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいうものであると解される(最高裁昭和52年(行ツ)第12号同56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁等参照)ところ、同法が、人の担税力を増加させる利得はその源泉のいかんにかかわらず全て所得を構成するものとするいわゆる包括的所得概念を採用しており、利得の形式についても、36条1項において、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額の中には金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も含まれるものとしていることによれば、上記「給与等」の給付の形式は金銭の支払には限られず、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の移転又は供与であっても、それが上記のような労務の対価としてされたものであれば、上記「給与等」の支払に当たるものというべきである。
(2)本件従業員に対する本件旅行に係る経済的な利益の供与が「給与等」の支払に該当するか否かについて検討するに、前提事実に加えて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
① X会社の業務内容 X会社は、土木建築工事の中でも鉄道線路の基礎杭打工事を専門に請け負っているものであるところ、鉄道線路の基礎杭打工事は、時間的及び空間的制約が厳しいことから、一般的な基礎杭打工事と比べても危険性が高いとされ、その現場作業においては、分秒単位で厳格に管理された作業工程を確実に実施することが必要とされる。
② 本件旅行の目的 X会社は、従業員及び恒常的に取引関係のある外注先の従業員等を対象として、その慰安と親睦のため、数年に1度、2泊3日程度の旅程で海外への社員旅行を実施しており、本件旅行の前には、平成16年に上海への社員旅行を実施した。
③ 本件旅行の企画立案 本件旅行の企画立案は、X会社代表者が旅行代理店である東西トラベル・ビューローの担当者と相談の上で行った。X会社代表者は、宿泊先について、一流ホテルに1人1部屋で宿泊することとするという指示をするとともに、食事関係について、全6食を最高の食事とすることとするという指示等をし、上記担当者は、この指示に従い、マカオで最高級のホテルである「ホテルリスボア」を宿泊先として選定するなどした。
④ 本件旅行の実施 本件旅行は、X会社が主催して実施されたものである。X会社の従業員のうち、現場作業を担当するもの(本件従業員)は全員が本件旅行に参加したが、総務職を担当する女性従業員2人は本件旅行に参加しなかった。
⑤ 本件旅行費用の負担及びその経理処理 X会社は、本件旅行の代金として合計800万円を支払った。X会社は、そのうち、外注先の従業員等21人分の代金に相当する506万7,300円を交際費として、本件従業員10人分241万3,000円を福利厚生費として、X会社代表者分51万9,700円を役員賞与として、それぞれ経理処理した。また、本件旅行に参加しなかった上記女性従業員2人に対し、参加に代えて金銭の支給等がされることはなかった。
(3)上記認定したことによれば、本件従業員は、本件旅行に参加することにより、その使用者であるX会社から、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当である。そして、上記で認定した事実によれば、本件旅行は、X会社代表者が、鉄道線路の基礎杭打工事の現場作業に日々従事している本件従業員や外注先の従業員等を慰労し、併せて、相互の親睦を深め、今後の業務の遂行をより円滑なものとする目的をもって、企画立案したものであり、実際にも、2泊3日の旅程中は、マカオ及びその周辺地域の観光に終始し、指揮命令系統を強化するための研修などは一切行われなかったと認めることができるのであって、専ら本件従業員ほかのレクリエーションのための観光を目的とする慰安旅行であったものであると認めるのが相当である。そうすると、本件従業員は、その使用者であるX会社から、雇用契約に基づきX会社の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであるということができる。
(4)X会社は、経済的利益が所得性を有し所得税の課税対象となるためには、流入性、価値の保有性、金銭的評価の可能性という三つの要件をいずれも満たす必要があると解すべきである旨主張する。しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりであり、上記主張は前提を欠くものである。
(5)X会社は、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択等いずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって、本件旅行に係る経済的利益が本件従業員のコントロールの下に入ったことはないというべきであるから、権利確定主義はもとより、管理支配基準によっても、所得の帰属時期を確定することはできない旨主張する。
しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりである。そして、所得税法は、各種所得の収入金額の収入すべき時期について、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定的に発生したときは、その発生の時に所得の実現があったものとして、当該確定的な権利発生の時の属する年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべきものとするいわゆる権利確定主義を採用していると解されるところ、これを本件についてみると、本件従業員は、本件旅行に参加することにより、その使用者であるX会社から、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当である。
(6)X会社は、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択等いずれの観点からも自由を与えられていなかったことによれば、本件旅行は私的な自由旅行とは区別されるべきものであり、少なくとも本件従業員分費用の額がそのまま本件従業員が供与を受けた経済的利益の額となるということはできないと主張する。
しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりである。そして、使用者が役員又は使用人に提供した用役については、当該用役につき通常支払われるべき対価の額により評価するのが相当であると解される(所得税基本通達36-50参照)ところ、弁論の全趣旨によれば、X会社が本件従業員に供与した本件旅行に係る経済的な利益につき通常支払われるべき対価の額は本件従業員分費用の額である24万1,300円であると認めることができるのであって、本件従業員が供与を受けた経済的な利益の額は本件従業員分費用の額となるとするのが相当である。
(7)本件旅行は所得税基本通達36-30にいう「役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的な利益については、課税しなくて差し支えないものとするのは、上記のような行事は簡易なものであることが多く、それに参加することにより享受する経済的な利益の額は少額であることに鑑み、少額不追求の観点から強いて課税しないこととするのが相当であるためであると解されるところ、X会社代表者は、宿泊先について、一流ホテルに1人1部屋で宿泊することとするという指示をするとともに、食事関係について、全6食を最高の食事とすることとするという指示をし、東西トラベル・ビューローの担当者は、この指示に従い、マカオで最高級のホテルである「ホテルリスボア」を宿泊先として選定するなどしたこと、X会社代表者は、予算については、特に指示をしなかったため、本件旅行の費用は、マカオを渡航先とする一般的な旅行と比べて、割高なものとなったことは、上記で認定したとおりであり、本件各従業員が供与を受けた経済的な利益の額は本件従業員分費用の額すなわち24万1,300円となるとするのが相当である。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。 (1)当裁判所も、本件従業員分旅行費用の負担は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものと判断する。その理由は、下記に当審におけるX会社の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
(2)X会社は、「本件旅行は、従業員に対して、指揮命令系統を強固にし、工事の安全を図ることを目的として、X会社代表者の業務命令によりされたものであり、参加不参加の自由はなく、X会社代表者は、旅行中でも従業員を指揮監督していたものであるから、業務のためのものである。X会社代表者が異議調査で指揮命令系統を強固にするためという目的を述べていないのは、そのような主張をする場でなかったことなどからであって、異議調査において上記の目的に一切触れていないとするのは不当である。」旨主張する。
しかし、X会社代表者自身、本件旅行の目的が、定年制を前提に、熟練技能者等の長年の労に対して盛大に報い、きちんと勤め上げると全社を挙げて盛大に送り出してもらえると社員に感じさせるために本件旅行を企画したとしているのであり、そのことによって会社に対する忠誠心がかん養され、ひいては指揮命令系統が強まることがあり得るとしても、付随的派生的効果にすぎず、従業員等の慰安や親睦を目的とする一般の慰安旅行と異なるところはないと考えられる。
また、異議調査においてX会社代表者が述べた内容についても、本件旅行の趣旨目的について説明しなかったというのではなく、慰安と親睦のための旅行であり、行き先は一般的な観光場所である旨積極的に回答しているのであるから、主張をする場でなかったとのX会社の主張は理由がない。
(3)X会社は、「本件旅行に参加することは従業員の職務であり、職務遂行に必要な旅費交通費を会社が負担したというにすぎないから、従業員が支払を免れたということはできず、その代金を従業員が経済的利益として自由に処分できたという状況ではない。経済的利益については、給与を受ける側から考えて、流入性、価値の保有性及び金銭的評価の可能性という3要件が必要であるが、原審はこの点についての検討をしておらず、審理不尽である。」旨主張する。
しかし、本件旅行の目的は、上記のとおり、X会社従業員などの慰安と親睦にあったものであり、X会社の業務上の必要に基づいて本件従業員に参加を強制して行われたものと認めることはできず、X会社の業務上の必要に基づいて経済的な利益の供与を受けたものということができないことは原判決説示のとおりである。
(4)X会社は、所得税基本通達36-30に関し、「本件旅行は、X会社に定年まで勤め上げた従業員を丁重に送り出すことにより、従業員の忠誠心を引き出すという目的があるが、従業員がそろって旅行に行く社員旅行という行事そのものが今となっては不人気となっているため、社員旅行はある程度贅沢にしないと社員に評価してもらえないという最近の実情があることや、飲料代を引いたものがツアー料金と考えるべきであること、X会社の業務に差し障りのない日程(連休)で旅行を計画するとなると、料金が高くならざるを得ないこと、土産物屋に寄らないためにマージン分が安くならないことなどの観点からすると、社会通念上一般的に行われているものと評価すべきである。」旨主張する。
しかし、従業員の参加意欲を喚起するためにある程度贅沢にしなければならないとの主張は、本件旅行が業務命令であるとするX会社の前記主張に必ずしも沿わないものである。また、本件従業員が享受した経済的利益の観点からは、旅行代金から飲料代や土産物屋のマージン分を控除する理由はなく、本件旅行に参加することにより享受する経済的な利益の額が少額であるものと認められないことは、原判決説示のとおりである。
五、解説
はじめに 本件は、会社の従業員及び外注先の従業員等が参加して実施された海外慰安旅行に要した費用のうち、従業員に係る費用(本件従業員分費用)が当該従業員に対する「給与等」として所得税の源泉徴収義務の対象になるか否かが争われたものである。
本件のようないわゆる社員慰安旅行については、娯楽やレジャーが多様化する中で下火になっているともいわれるが、それが故に、当該慰安旅行に通常の旅行では経験できないような工夫が凝らされていることもある。しかし、そのことが、「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われている」と認められないとして、当該従業員に対する所得税課税(源泉徴収)の要否が問題となる。
本件は、そのような慰安旅行の典型的なケースであるといえるが、所得税法上の経済的利益課税のあり方に問題を提起するものである。すなわち、本件のような場合には、経済的利益に対する給与所得課税の範囲、所定の経済的利益を非課税とすることの法的根拠と当該非課税の範囲、本件旅行によって享受される経済的利益に対する課税の要否等が問題となる。そこで、それらの問題を検討した上で、本件各判決の当否を検討することとする。
1 給与所得の意義と収入金額 (1)所得税法上、給与所得とは、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」(所法28①)と定められている。この給与所得の金額は、「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額」(所法28②)である。
そして、この給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌日10日までに、これを国に納付しなければならない(所法183①)。納付しなければ、徴収のための納税の告知が行われる(通法36①二)。本件においては、本件旅行費用のうち、本件従業員分費用が給与等に該当するとして、本件納税告知が行われたものである。
また、所得税法28条2項にいう「収入金額」については、「収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」(所法36①)と定められている。そして、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」は、「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額」(所法36②)である。
(2)上記の所得税法上の各規定のうち、「給与所得」の意義についての判例上の解釈は、次のように整理することができる。まず、判例では、「勤労者が勤労者たる地位に基づいて使用者から受ける給付は、すべて給与所得を構成する」(注1)と解されているところ、本件旅行費用のうち本件従業員分費用が、本件従業員が勤労者たる地位に基づいて使用者たるX会社から給付されたことは否定できない。ただし、当該給付が所得税の課税対象となるものか否かについては、非課税とする規定もあるので追って検討を要することになる。
また、本件各判決が引用している最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)は、弁護士の顧問料が事業所得に当たるか給与所得に当たるかが争われた事案において、「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」と判示している。
本件においても、本件従業員らは、X会社との間で雇傭契約に服していることは明らかであるから、本件旅行に参加することによって何らかの「労務の対価」を受けたというのであれば、当該対価は、原則として、給与所得を構成することになる。
2 経済的利益とそれに対する非課税規定 (1)前記1で述べたように、各種所得の金額の計算上、収入すべき金額には、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を含むこととされている。このような経済的利益については、所得税基本通達36-15は、次のような利益が含まれるとしている。
① 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
② 土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
③ 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益
④ ②及び③以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
⑤ 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益
(2)もっとも、このような経済的利益については、それらの全てが「収入すべき金額」として所得税が課税されるわけではなく、所定の経済的利益は非課税とされている。その中で、雇用契約等に係るもの(給与所得)については、次のものについて非課税としている(所法9①四~六、所令20の2、21)。
① 転勤等の旅行に必要な支出に充てるため支給される金品
② 通常必要と認められる通勤手当
③ 使用者から受ける経済的利益でその職務の性質上欠くことのできないもの(船員に支給される所定の食料、制服その他の身回品の支給又は貸与、職務遂行上必要な所定の家の貸与等)
以上の給与所得に係る経済的利益の供与は、所得税法上の非課税規定によるものであるが、所得税基本通達では、給与等に係る経済的利益のうち、所定のものを課税しない(又は一部課税しない)こととしている(所基通36-21~36-36-35の2)。その主要なものは、次のとおりである。
① 永年勤続者の記念品等
② 創業記念品等
③ 商品、製品等の値引販売
④ 残業又は宿日直した者に支給する食事
⑤ 寄宿者の電気料等
⑥ 金銭の無利息貸付け等
⑦ 用役の提供等
⑧ 使用者が負担するレクリエーション費用
⑨ 使用者が負担する少額な保険料等
これらの経済的利益の供与については、前述の所得税法36条1項及び同法9条1項の規定に照らして、法律上、非課税所得であるとは解されないので、その意味では租税法律主義に反するとも解される。しかし、前述の経済的利益については、雇用関係において一般的に行われていることであり、かつ、少額なものであるから、所得税基本通達の取扱いにも合理性があるものである。そうであれば、当該通達の取扱いの法的根拠を所得税法9条又は同36条の規定の中で明確にすべきであると考えられる(注2)。
3 海外慰安旅行に対する課税の取扱いとその変遷 (1)前記2(2)で述べたように、所得税基本通達は、雇傭契約等において使用者がその使用人又は役員に対して所定の経済的利益を供与している場合には、これを非課税として取り扱うこととしている。その中に、本件に関わる取扱いは、同通達36-30の取扱いである。同通達は、次のように定めている。
「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金額については、給与等として課税することに留意する。」
この取扱いについては、従前、従業員等の慰安旅行に要する費用につき、国内旅行であれば、非課税であるが、海外旅行であれば課税するものと取り扱われていた(注3)。そのため、その取扱いに沿う裁判例(注4)もみられた。
(2)ところが、京都地裁昭和61年8月8日判決(判例時報1208号77頁)は、従業員約450人のうち171人が参加した2泊3日の香港旅行に要した費用(1人当たり7万7,500円のうち会社負担約2万9,000円)が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、「外国旅行は、昭和56年当時すでに特殊な人だけのものではなく大衆化して来ており、その費用も国内旅行よりも低廉な場合もあるし、国内旅行以上にレクリエーションとしての効果が大きく、従業員の勤労意欲を高める面も強いことを考えると、使用者が負担した費用が外国旅行費であるというだけで、国内旅行費と全く異なった取扱いをするのは相当ではない。」と判示し、当該費用を参加した従業員らに対する給与等に当たるとした当該納税の告知を取り消した。そして、控訴審の大阪高裁昭和63年3月31日判決(税資163号1,082頁)も、原判決と同様の理由により、会社側の請求を認容した(注5)。
(3)このような京都地裁判決に対し、国税庁は、次のような個別通達(昭和61年12月24日付直法6-13)を発遣し、当該京都地裁判決の事案ではその案件(参加者の割合等)を満たしていないとして、控訴した。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う慰安旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、次のすべての要件を満たしている場合に限り、課税しなくて差し支えない。
(1)当該旅行に要する期間が2泊3日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に要する費用の50%以上を使用者が負担していること。
(3)当該旅行に参加する従業員等の数は全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」
しかし、国税庁は、前掲の大阪高裁判決においても敗訴したため、前記個別通達を更に次のように改めることとし、その取扱いの弾力化を図った(昭和63年5月25日付直法6-9)。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために従う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のすべての要件を満たしている場合には、原則として、課税しなくて差し支えないものとする。
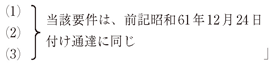
その後、平成元年の通達改正(直所3-3)では、前記「2泊3日」の要件が「3泊4日」に改められた。そして、平成5年の税制改正では、総合的な経済対策(内需拡大等の景気対策)の一環として、非課税の対象となる従業員レクリエーション旅行の一層の拡充が求められ(注6)、同年の通達改正(課所4-5)において、前記の取扱いが次のように定められた。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」
(4)以上のように、海外慰安旅行に対する国税庁の取扱い通達は、何度かの改正をみたのであるが、海外慰安旅行を「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われている」と認めた以降は次のような事例が見受けられる。
例えば、平成3年7月18日裁決(裁決事例集42号128頁)では、グループ3社でタイへの3泊4日の社員旅行の費用の負担金(審査請求人では全社員の3人参加、1人当たり18万3,771円)が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、本裁決は、当該タイ旅行について、従業員の福利厚生を目的とするレクリエーションとして社会通念上一般的に行われている程度のものであるとして、当該負担金を福利厚生費に該当すると判断している。
また、平成8年1月26日裁決(裁決事例集51号346頁)では、平成3年にシンガポールへ3泊4日(滞在日数、1人当たり費用34万1,000円)、平成4年にアメリカ西海岸へ3泊4日(同、同45万4,411円)、平成5年にカナダへ3泊4日(同、同52万円)の海外慰安旅行に要した費用が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、本裁決は、各慰安旅行とも社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められないと判断し、当該費用を参加した従業員に対する給与等と認定した各納税の告知を適法とした。
4 本件旅行費用(本件従業員分費用)の給与等該当性 (1)本件においては、前述したように、全従業員等12人のうち10人が参加したマカオへの2泊3日の慰安旅行(本件旅行)に要した本件旅行費用のうち本件従業員分費用(1人当たり24万1,300円)が福利厚生費に当たるか給与等に当たるかが争われたものである。X会社は、本件従業員分費用が給与等に該当するためには、主として、幸田論文を引用し、①管理、使用収益及び処分権を取得するという流入性、②その流入によって効用を有するという価値の保有性、及び③当該効用についての金銭的評価の可能性という三つの要件を満たす必要があるところ、本件旅行が業務上の要請によって半強制的に行われたものであるから、本件従業員分費用には上記3要件を満たしていない(福利厚生費に該当する)旨主張した。
これに対し、本件各判決は、前述のように、本件旅行は観光旅行に終始し、指揮命令系統強化のための研修等は行われなかったのであるから、本件従業員は雇用契約に基づき経済的利益の供与を受けたものであり、かつ、本件旅行が、所得税基本通達36-30にいう「役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に該当すると認めることはできないとして、本件納税告知及び本件賦課決定を適法と判示した。
(2)本訴の結果については、それぞれの立場によって評価が異なるものと考えられる。しかし、その結果の原因の一つは、X会社の主張の方法にあったものと考えられる。X会社は、本訴において、主として、幸田論文を引用して、前述のような主張を行い、本件従業員分費用が所得税法36条1項にいう「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(すなわち「経済的利益」)に当たらないことを強調した。
しかしながら、幸田論文それ自体は国税庁税務大学校研究科生の研修のための論文であるから、その内容がそれほど高度で権威のある理論に基づいているものとも考えられない。むしろ、雇用関係における各種レクリエーション行事に従業員等が参加することによって種々の経済的利益を享受していて、それが所得税法上の「収入金額」を原則として構成することは公知の事実である。そして、本件のようなレクリエーション行事であっても、それに参加することが会社の行事であるということで少なくとも心理的な強制力が作用することもあろうが、参加する従業員等に対して何らかの経済的利益がもたらされることも事実である。したがって、そのような経済的利益の享受について、所得税法36条1項にいう「経済的利益」の収入それ自体を否定することに合理性があるとも考えられない。
しかし、それらの経済的利益の全てを所得税の課税対象にすべきかについては、特に、雇用契約等に基づく経済的利益の享受の特殊性からいって首肯し難いところがある。それであるが故に、前記1で述べたように、所得税法9条1項では、雇傭関係からもたらされる特定の経済的利益について所得税を課さないこととしているのである(この非課税規定は、経済的利益の享受それ自体を否定しているわけではない。)。
更に、前記2で述べたように、租税法律主義上の問題はともかくとして、所得税基本通達36-21以下において、雇用契約等に基づいて享受する特定の経済的利益について課税しないことを定めているところである。その中で、本件旅行に関する所得税基本通達36-30は、「社会通念上一般的に行われていると認められる」レクリエーション行事によって享受する経済的利益について課税しないこととしているわけである。そして、この取扱いについては、前記3で述べたように、種々の変遷を経て非課税の範囲が拡大してきているところである。
そうであれば、当該取扱い(改正)の趣旨に基づいて本件旅行が「社会通念上一般的に行われていると認められる」ものか否かが一層慎重に検討されるべきであったものと考えられる。特に、平成5年の個別通達の改正によって海外での滞在期間を4泊5日まで延長して非課税の対象を拡大したのは、需要拡大のための景気対策の一環として行われたわけであるから、その趣旨に則った対応も必要であるはずである。特に、本件のような慰安旅行については、ある程度豪華なものでなければ参加社員の満足は得られないはずである。換言すると、安価な海外ツアーで得られるような海外旅行であれば、慰安の効果も得られないことになる。それらのことを総合的に考えると、本件旅行については、「社会通念上一般的に行われていると認められる」範ちゅうに入らないとも限らないものと考えられる。いずれにしても、本訴においては、このような政策的な要請又は海外旅行の実態という観点からの検討(当事者の主張)がなかったことが惜しまれるところである。
5 本件各判決の意義と問題点
以上のように、本件は、マカオに2泊3日で行った社員等の海外慰安旅行(本件旅行)に要した費用(本件旅行費用)のうち、X会社が負担した従業員分の費用(本件従業員分費用)が福利厚生費に当たるか給与等に当たるかが争われたものである。本件各判決は、本件従業員分費用が1人当たり24万1,300円という高額なものであること等を理由に、当該費用が給与等に当たると判断した。
本件のような海外慰安旅行については、特に、中小企業の厚生福利対策としてまま行われているところであるが、取扱い通達が4泊5日の旅行まで課税しないとしているものの、1人当たりの費用負担が幾許まで認められるかについて関心の強いところである。その点に関しては、本件各判決が、1人当たり24万1,300円の本件旅行費用を給与等に当たると判示したことは、実務の指針としては参考になるところである。
しかしながら、本件各判決がそのように判断した経緯においては、前記4で述べたような種々の問題を抱えているところであるので、必ずしも説得力があるものともいい難い。よって、今後、同種の海外慰安旅行を企画している各社においては、それらの問題点も検討した上で対応して行く必要がある。
(注1)最高裁昭和37年8月10日第二小法廷判決(民集16巻8号1,749頁)。
(注2)品川芳宣編著「現物給付の税務」(新日本法規 平成12年)12頁等参照。
(注3)伊藤一行・柴田幸一共著「所得税基本通達逐条解説」(大蔵財務協会 昭和50年)192頁等参照。
(注4)例えば、岡山地裁昭和54年7月18日判決(行裁例集30巻7号1,315頁)では、ハワイへの慰安旅行につき、海外慰安旅行は未だ社会通念上一般的に行われているとは認められていないとして、当該費用(1人当たり約18万6,000円)を給与等に当たると判断している。
(注5)これらの判決の内容と解説については、品川芳宣「重要租税判決の実務研究」(大蔵財務協会 平成26年)161頁参照。
(注6)国税庁「平成5年 改正税法のすべて」16頁等参照。
従業員等の海外慰安旅行の費用負担と経済的利益の供与(給与)
東京地裁平成24年12月25日判決(平成23年(行ウ)第385号)
東京高裁平成25年5月30日判決(平成25年(行コ)第31号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X会社(原告、控訴人)は、鉄道線路工事の請負事業を営む株式会社であるが、平成21年1月10日から同月12日まで、同社の代表者、同社の従業員10人(以下「本件従業員」という。)及び外注先の従業員等21人の合計32人を参加者として、中国澳門特別行政区(以下「マカオ」という。)への2泊3日の慰安旅行(以下「本件旅行」という。)を実施し、その費用(以下「本件旅行費用」という。)の全額合計800万円を負担した。X会社は、本件旅行費用のうち、本件従業員に係る1人当たり24万1,300円(以下「本件従業員分費用」という。)の合計241万3,000円を福利厚生費として処理した(経済的利益の供与として所得税の源泉徴収をしなかった。)。
(2)これに対し、所轄税務署長は、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するとして、国税通則法36条1項に基づき、平成21年11月25日付けで、平成21年1月分の源泉所得税の額34万7,472円とする納税の告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の額3万4,000円とする賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をした。X会社は、本件納税告知及び本件賦課決定を不服として、前審手続を経て、国(被告、被控訴人)に対し、当該各処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
なお、本件に係る裁決(平成22年12月17日付け)では、従業員の海外慰安旅行における一般的な会社負担額は、当該旅行費用の平均額8万1,154円の70.1%に相当する5万6,889円であり、本件従業員分費用がそれを大幅に上回るものであるから、所得税法上の「給与等」に該当する旨判断されている。
二、争点と当事者の主張
1 争 点 本件の争点は、本件納税告知等の適否、具体的には、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与が所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
2 国の主張 (1)本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し、X会社は、同法183条1項の規定により、上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ、この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから、X会社がこれについて本件従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7,472円である。
(2)所得税法は、給与所得とは、雇用契約又はこれに準ずる関係に基づいて提供される非独立的な人的役務の提供の対価としての性質を有する所得であると解される。そして、同法36条1項が、経済的利益による収入も課税対象となることを明らかにしていることからすると、使用者が従業員に慰安旅行に係る経済的利益を供与した場合も「給与等」に該当するということとなる。
(3)本件旅行は本件従業員の慰安及び親睦を目的として行われたものであるところ、本件従業員は、X会社の費用負担において本件旅行に係る経済的利益の供与を受けたものであるから、その経済的利益が、本件従業員との雇用契約に基づいて提供された非独立的な人的役務の提供の対価としての性質を有するものであることは明らかであり、本件従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するというべきである。
3 X会社の主張 (1)X会社は、基礎杭打工事の中でもとりわけ危険な鉄道線路の基礎杭打工事の施行において高い技術を有しているところ、過誤が許されない危険な工事を安全に施行するためには、強固な指揮命令系統を確立し、維持することが必要不可欠である。本件旅行の目的は、退職する取引先の従業員を盛大に送り出すことを現場の全従業員に示すことにより強固な指揮命令系統を更に強化することにある。本件旅行は、X会社の社内において絶対の存在であるX会社代表者の企画立案の下に行われたものであり、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択、旅程の選択、自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって、反射的に利益を受けることはあっても、この利益を自由に処分することはできなかった。
(2)所得税法36条1項が経済的利益を「収入すべき金額」の一態様として規定しているところ、その経済的利益が所得性を有し所得税の課税対象となるためには、① 人の行為により物権の変動又は債権発生に伴い管理、使用収益及び処分権を取得すること(流入性)、② 流入によって取得した物権又は債権が直接又は間接に生活目的に何らかの役に立つ性質すなわち効用を有すること(価値の保有性)、③ 貨幣数値による評価の可能なものであること(金銭的評価の可能性)という三つの要件をいずれも満たす必要があると解すべきである(幸田久「所得税法上の経済的利益について」税務大学校編・税大研究資料第34号(昭和45年6月)研究科論文集(所得税編)。以下「幸田論文」という。)。
(3)幸田論文は、レクリエーション施設の利用、無料の研修その他の教育費等の利益は、業務の一環とみることができるのであって、流入性を有しないとしているところ、前記のとおり、本件従業員は、本件旅行について参加するか否かの選択、旅程の選択、自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであることからすれば、本件従業員分費用相当の経済的利益は、前記の流入性の要件を満たすものではない。
(4)幸田論文は、上記の私経済における反射的利益は価値の保有性についても疑問があり、職務上の必要性から自己の欲求を犠牲にしているとみられる場合には、経済的利益があるように見えても、保有性を有しないというべきであるところ、本件旅行は、職務上の必要性から自己の欲求を犠牲にして参加しなければならない社内行事であり、自由時間である休日に行われたにもかかわらず、本件従業員の生活目的に何ら役立っていないのであるから、本件従業員分費用相当の経済的利益は、価値の保有性の要件を満たすものではない。
(5)幸田論文は、所得税の課税客体である所得は全て貨幣数値で表現され、租税の納付は金銭納付を原則とするから、貨幣数値による評価の可能なもののみが課税対象の範疇に含まれるとしているところ、本件旅行は、私的な自由旅行とは区別されるべきものであり、本件従業員分費用相当の経済的利益は、金銭的評価の可能性の要件を満たすものではない。
(6)最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決・裁判集民事197号75頁は、労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとしているところ、本件旅行に参加不参加の自由はなく、行き先などについて従業員が意見を述べる機会はなく、X会社代表者の一方的指示で、旅行に連れて行かれ、旅行中であっても代表者が集合時間について厳しく注意していたことからすれば、X会社代表者が旅行中も従業員を指揮監督する状況にあったものであり、本件旅行は、業務に不可欠な指揮命令系統を強固にするためのものであった。
三、一審判決要旨
請求棄却。 (1)所得税法28条1項にいう「給与等」とは、俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(同法28条1項)、すなわち、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者等の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいうものであると解される(最高裁昭和52年(行ツ)第12号同56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁等参照)ところ、同法が、人の担税力を増加させる利得はその源泉のいかんにかかわらず全て所得を構成するものとするいわゆる包括的所得概念を採用しており、利得の形式についても、36条1項において、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額の中には金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も含まれるものとしていることによれば、上記「給与等」の給付の形式は金銭の支払には限られず、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の移転又は供与であっても、それが上記のような労務の対価としてされたものであれば、上記「給与等」の支払に当たるものというべきである。
(2)本件従業員に対する本件旅行に係る経済的な利益の供与が「給与等」の支払に該当するか否かについて検討するに、前提事実に加えて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
① X会社の業務内容 X会社は、土木建築工事の中でも鉄道線路の基礎杭打工事を専門に請け負っているものであるところ、鉄道線路の基礎杭打工事は、時間的及び空間的制約が厳しいことから、一般的な基礎杭打工事と比べても危険性が高いとされ、その現場作業においては、分秒単位で厳格に管理された作業工程を確実に実施することが必要とされる。
② 本件旅行の目的 X会社は、従業員及び恒常的に取引関係のある外注先の従業員等を対象として、その慰安と親睦のため、数年に1度、2泊3日程度の旅程で海外への社員旅行を実施しており、本件旅行の前には、平成16年に上海への社員旅行を実施した。
③ 本件旅行の企画立案 本件旅行の企画立案は、X会社代表者が旅行代理店である東西トラベル・ビューローの担当者と相談の上で行った。X会社代表者は、宿泊先について、一流ホテルに1人1部屋で宿泊することとするという指示をするとともに、食事関係について、全6食を最高の食事とすることとするという指示等をし、上記担当者は、この指示に従い、マカオで最高級のホテルである「ホテルリスボア」を宿泊先として選定するなどした。
④ 本件旅行の実施 本件旅行は、X会社が主催して実施されたものである。X会社の従業員のうち、現場作業を担当するもの(本件従業員)は全員が本件旅行に参加したが、総務職を担当する女性従業員2人は本件旅行に参加しなかった。
⑤ 本件旅行費用の負担及びその経理処理 X会社は、本件旅行の代金として合計800万円を支払った。X会社は、そのうち、外注先の従業員等21人分の代金に相当する506万7,300円を交際費として、本件従業員10人分241万3,000円を福利厚生費として、X会社代表者分51万9,700円を役員賞与として、それぞれ経理処理した。また、本件旅行に参加しなかった上記女性従業員2人に対し、参加に代えて金銭の支給等がされることはなかった。
(3)上記認定したことによれば、本件従業員は、本件旅行に参加することにより、その使用者であるX会社から、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当である。そして、上記で認定した事実によれば、本件旅行は、X会社代表者が、鉄道線路の基礎杭打工事の現場作業に日々従事している本件従業員や外注先の従業員等を慰労し、併せて、相互の親睦を深め、今後の業務の遂行をより円滑なものとする目的をもって、企画立案したものであり、実際にも、2泊3日の旅程中は、マカオ及びその周辺地域の観光に終始し、指揮命令系統を強化するための研修などは一切行われなかったと認めることができるのであって、専ら本件従業員ほかのレクリエーションのための観光を目的とする慰安旅行であったものであると認めるのが相当である。そうすると、本件従業員は、その使用者であるX会社から、雇用契約に基づきX会社の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであるということができる。
(4)X会社は、経済的利益が所得性を有し所得税の課税対象となるためには、流入性、価値の保有性、金銭的評価の可能性という三つの要件をいずれも満たす必要があると解すべきである旨主張する。しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりであり、上記主張は前提を欠くものである。
(5)X会社は、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択等いずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって、本件旅行に係る経済的利益が本件従業員のコントロールの下に入ったことはないというべきであるから、権利確定主義はもとより、管理支配基準によっても、所得の帰属時期を確定することはできない旨主張する。
しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりである。そして、所得税法は、各種所得の収入金額の収入すべき時期について、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定的に発生したときは、その発生の時に所得の実現があったものとして、当該確定的な権利発生の時の属する年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべきものとするいわゆる権利確定主義を採用していると解されるところ、これを本件についてみると、本件従業員は、本件旅行に参加することにより、その使用者であるX会社から、本件旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当である。
(6)X会社は、本件従業員は、本件旅行について、参加するか否かの選択等いずれの観点からも自由を与えられていなかったことによれば、本件旅行は私的な自由旅行とは区別されるべきものであり、少なくとも本件従業員分費用の額がそのまま本件従業員が供与を受けた経済的利益の額となるということはできないと主張する。
しかし、本件旅行が、現場作業員の指揮命令系統を強化し、操業の安全と能率の増進を図るというX会社の業務上の必要に基づいて、本件従業員に参加を強制して行われたものであると認めることはできないことは、上記のとおりである。そして、使用者が役員又は使用人に提供した用役については、当該用役につき通常支払われるべき対価の額により評価するのが相当であると解される(所得税基本通達36-50参照)ところ、弁論の全趣旨によれば、X会社が本件従業員に供与した本件旅行に係る経済的な利益につき通常支払われるべき対価の額は本件従業員分費用の額である24万1,300円であると認めることができるのであって、本件従業員が供与を受けた経済的な利益の額は本件従業員分費用の額となるとするのが相当である。
(7)本件旅行は所得税基本通達36-30にいう「役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的な利益については、課税しなくて差し支えないものとするのは、上記のような行事は簡易なものであることが多く、それに参加することにより享受する経済的な利益の額は少額であることに鑑み、少額不追求の観点から強いて課税しないこととするのが相当であるためであると解されるところ、X会社代表者は、宿泊先について、一流ホテルに1人1部屋で宿泊することとするという指示をするとともに、食事関係について、全6食を最高の食事とすることとするという指示をし、東西トラベル・ビューローの担当者は、この指示に従い、マカオで最高級のホテルである「ホテルリスボア」を宿泊先として選定するなどしたこと、X会社代表者は、予算については、特に指示をしなかったため、本件旅行の費用は、マカオを渡航先とする一般的な旅行と比べて、割高なものとなったことは、上記で認定したとおりであり、本件各従業員が供与を受けた経済的な利益の額は本件従業員分費用の額すなわち24万1,300円となるとするのが相当である。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。 (1)当裁判所も、本件従業員分旅行費用の負担は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものと判断する。その理由は、下記に当審におけるX会社の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
(2)X会社は、「本件旅行は、従業員に対して、指揮命令系統を強固にし、工事の安全を図ることを目的として、X会社代表者の業務命令によりされたものであり、参加不参加の自由はなく、X会社代表者は、旅行中でも従業員を指揮監督していたものであるから、業務のためのものである。X会社代表者が異議調査で指揮命令系統を強固にするためという目的を述べていないのは、そのような主張をする場でなかったことなどからであって、異議調査において上記の目的に一切触れていないとするのは不当である。」旨主張する。
しかし、X会社代表者自身、本件旅行の目的が、定年制を前提に、熟練技能者等の長年の労に対して盛大に報い、きちんと勤め上げると全社を挙げて盛大に送り出してもらえると社員に感じさせるために本件旅行を企画したとしているのであり、そのことによって会社に対する忠誠心がかん養され、ひいては指揮命令系統が強まることがあり得るとしても、付随的派生的効果にすぎず、従業員等の慰安や親睦を目的とする一般の慰安旅行と異なるところはないと考えられる。
また、異議調査においてX会社代表者が述べた内容についても、本件旅行の趣旨目的について説明しなかったというのではなく、慰安と親睦のための旅行であり、行き先は一般的な観光場所である旨積極的に回答しているのであるから、主張をする場でなかったとのX会社の主張は理由がない。
(3)X会社は、「本件旅行に参加することは従業員の職務であり、職務遂行に必要な旅費交通費を会社が負担したというにすぎないから、従業員が支払を免れたということはできず、その代金を従業員が経済的利益として自由に処分できたという状況ではない。経済的利益については、給与を受ける側から考えて、流入性、価値の保有性及び金銭的評価の可能性という3要件が必要であるが、原審はこの点についての検討をしておらず、審理不尽である。」旨主張する。
しかし、本件旅行の目的は、上記のとおり、X会社従業員などの慰安と親睦にあったものであり、X会社の業務上の必要に基づいて本件従業員に参加を強制して行われたものと認めることはできず、X会社の業務上の必要に基づいて経済的な利益の供与を受けたものということができないことは原判決説示のとおりである。
(4)X会社は、所得税基本通達36-30に関し、「本件旅行は、X会社に定年まで勤め上げた従業員を丁重に送り出すことにより、従業員の忠誠心を引き出すという目的があるが、従業員がそろって旅行に行く社員旅行という行事そのものが今となっては不人気となっているため、社員旅行はある程度贅沢にしないと社員に評価してもらえないという最近の実情があることや、飲料代を引いたものがツアー料金と考えるべきであること、X会社の業務に差し障りのない日程(連休)で旅行を計画するとなると、料金が高くならざるを得ないこと、土産物屋に寄らないためにマージン分が安くならないことなどの観点からすると、社会通念上一般的に行われているものと評価すべきである。」旨主張する。
しかし、従業員の参加意欲を喚起するためにある程度贅沢にしなければならないとの主張は、本件旅行が業務命令であるとするX会社の前記主張に必ずしも沿わないものである。また、本件従業員が享受した経済的利益の観点からは、旅行代金から飲料代や土産物屋のマージン分を控除する理由はなく、本件旅行に参加することにより享受する経済的な利益の額が少額であるものと認められないことは、原判決説示のとおりである。
五、解説
はじめに 本件は、会社の従業員及び外注先の従業員等が参加して実施された海外慰安旅行に要した費用のうち、従業員に係る費用(本件従業員分費用)が当該従業員に対する「給与等」として所得税の源泉徴収義務の対象になるか否かが争われたものである。
本件のようないわゆる社員慰安旅行については、娯楽やレジャーが多様化する中で下火になっているともいわれるが、それが故に、当該慰安旅行に通常の旅行では経験できないような工夫が凝らされていることもある。しかし、そのことが、「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われている」と認められないとして、当該従業員に対する所得税課税(源泉徴収)の要否が問題となる。
本件は、そのような慰安旅行の典型的なケースであるといえるが、所得税法上の経済的利益課税のあり方に問題を提起するものである。すなわち、本件のような場合には、経済的利益に対する給与所得課税の範囲、所定の経済的利益を非課税とすることの法的根拠と当該非課税の範囲、本件旅行によって享受される経済的利益に対する課税の要否等が問題となる。そこで、それらの問題を検討した上で、本件各判決の当否を検討することとする。
1 給与所得の意義と収入金額 (1)所得税法上、給与所得とは、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」(所法28①)と定められている。この給与所得の金額は、「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額」(所法28②)である。
そして、この給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌日10日までに、これを国に納付しなければならない(所法183①)。納付しなければ、徴収のための納税の告知が行われる(通法36①二)。本件においては、本件旅行費用のうち、本件従業員分費用が給与等に該当するとして、本件納税告知が行われたものである。
また、所得税法28条2項にいう「収入金額」については、「収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」(所法36①)と定められている。そして、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」は、「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額」(所法36②)である。
(2)上記の所得税法上の各規定のうち、「給与所得」の意義についての判例上の解釈は、次のように整理することができる。まず、判例では、「勤労者が勤労者たる地位に基づいて使用者から受ける給付は、すべて給与所得を構成する」(注1)と解されているところ、本件旅行費用のうち本件従業員分費用が、本件従業員が勤労者たる地位に基づいて使用者たるX会社から給付されたことは否定できない。ただし、当該給付が所得税の課税対象となるものか否かについては、非課税とする規定もあるので追って検討を要することになる。
また、本件各判決が引用している最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)は、弁護士の顧問料が事業所得に当たるか給与所得に当たるかが争われた事案において、「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」と判示している。
本件においても、本件従業員らは、X会社との間で雇傭契約に服していることは明らかであるから、本件旅行に参加することによって何らかの「労務の対価」を受けたというのであれば、当該対価は、原則として、給与所得を構成することになる。
2 経済的利益とそれに対する非課税規定 (1)前記1で述べたように、各種所得の金額の計算上、収入すべき金額には、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を含むこととされている。このような経済的利益については、所得税基本通達36-15は、次のような利益が含まれるとしている。
① 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
② 土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
③ 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益
④ ②及び③以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
⑤ 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益
(2)もっとも、このような経済的利益については、それらの全てが「収入すべき金額」として所得税が課税されるわけではなく、所定の経済的利益は非課税とされている。その中で、雇用契約等に係るもの(給与所得)については、次のものについて非課税としている(所法9①四~六、所令20の2、21)。
① 転勤等の旅行に必要な支出に充てるため支給される金品
② 通常必要と認められる通勤手当
③ 使用者から受ける経済的利益でその職務の性質上欠くことのできないもの(船員に支給される所定の食料、制服その他の身回品の支給又は貸与、職務遂行上必要な所定の家の貸与等)
以上の給与所得に係る経済的利益の供与は、所得税法上の非課税規定によるものであるが、所得税基本通達では、給与等に係る経済的利益のうち、所定のものを課税しない(又は一部課税しない)こととしている(所基通36-21~36-36-35の2)。その主要なものは、次のとおりである。
① 永年勤続者の記念品等
② 創業記念品等
③ 商品、製品等の値引販売
④ 残業又は宿日直した者に支給する食事
⑤ 寄宿者の電気料等
⑥ 金銭の無利息貸付け等
⑦ 用役の提供等
⑧ 使用者が負担するレクリエーション費用
⑨ 使用者が負担する少額な保険料等
これらの経済的利益の供与については、前述の所得税法36条1項及び同法9条1項の規定に照らして、法律上、非課税所得であるとは解されないので、その意味では租税法律主義に反するとも解される。しかし、前述の経済的利益については、雇用関係において一般的に行われていることであり、かつ、少額なものであるから、所得税基本通達の取扱いにも合理性があるものである。そうであれば、当該通達の取扱いの法的根拠を所得税法9条又は同36条の規定の中で明確にすべきであると考えられる(注2)。
3 海外慰安旅行に対する課税の取扱いとその変遷 (1)前記2(2)で述べたように、所得税基本通達は、雇傭契約等において使用者がその使用人又は役員に対して所定の経済的利益を供与している場合には、これを非課税として取り扱うこととしている。その中に、本件に関わる取扱いは、同通達36-30の取扱いである。同通達は、次のように定めている。
「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金額については、給与等として課税することに留意する。」
この取扱いについては、従前、従業員等の慰安旅行に要する費用につき、国内旅行であれば、非課税であるが、海外旅行であれば課税するものと取り扱われていた(注3)。そのため、その取扱いに沿う裁判例(注4)もみられた。
(2)ところが、京都地裁昭和61年8月8日判決(判例時報1208号77頁)は、従業員約450人のうち171人が参加した2泊3日の香港旅行に要した費用(1人当たり7万7,500円のうち会社負担約2万9,000円)が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、「外国旅行は、昭和56年当時すでに特殊な人だけのものではなく大衆化して来ており、その費用も国内旅行よりも低廉な場合もあるし、国内旅行以上にレクリエーションとしての効果が大きく、従業員の勤労意欲を高める面も強いことを考えると、使用者が負担した費用が外国旅行費であるというだけで、国内旅行費と全く異なった取扱いをするのは相当ではない。」と判示し、当該費用を参加した従業員らに対する給与等に当たるとした当該納税の告知を取り消した。そして、控訴審の大阪高裁昭和63年3月31日判決(税資163号1,082頁)も、原判決と同様の理由により、会社側の請求を認容した(注5)。
(3)このような京都地裁判決に対し、国税庁は、次のような個別通達(昭和61年12月24日付直法6-13)を発遣し、当該京都地裁判決の事案ではその案件(参加者の割合等)を満たしていないとして、控訴した。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う慰安旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、次のすべての要件を満たしている場合に限り、課税しなくて差し支えない。
(1)当該旅行に要する期間が2泊3日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に要する費用の50%以上を使用者が負担していること。
(3)当該旅行に参加する従業員等の数は全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」
しかし、国税庁は、前掲の大阪高裁判決においても敗訴したため、前記個別通達を更に次のように改めることとし、その取扱いの弾力化を図った(昭和63年5月25日付直法6-9)。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために従う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のすべての要件を満たしている場合には、原則として、課税しなくて差し支えないものとする。
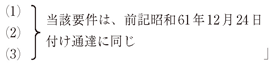
その後、平成元年の通達改正(直所3-3)では、前記「2泊3日」の要件が「3泊4日」に改められた。そして、平成5年の税制改正では、総合的な経済対策(内需拡大等の景気対策)の一環として、非課税の対象となる従業員レクリエーション旅行の一層の拡充が求められ(注6)、同年の通達改正(課所4-5)において、前記の取扱いが次のように定められた。
「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」
(4)以上のように、海外慰安旅行に対する国税庁の取扱い通達は、何度かの改正をみたのであるが、海外慰安旅行を「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われている」と認めた以降は次のような事例が見受けられる。
例えば、平成3年7月18日裁決(裁決事例集42号128頁)では、グループ3社でタイへの3泊4日の社員旅行の費用の負担金(審査請求人では全社員の3人参加、1人当たり18万3,771円)が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、本裁決は、当該タイ旅行について、従業員の福利厚生を目的とするレクリエーションとして社会通念上一般的に行われている程度のものであるとして、当該負担金を福利厚生費に該当すると判断している。
また、平成8年1月26日裁決(裁決事例集51号346頁)では、平成3年にシンガポールへ3泊4日(滞在日数、1人当たり費用34万1,000円)、平成4年にアメリカ西海岸へ3泊4日(同、同45万4,411円)、平成5年にカナダへ3泊4日(同、同52万円)の海外慰安旅行に要した費用が福利厚生費に当たるか否かが争われた事案につき、本裁決は、各慰安旅行とも社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められないと判断し、当該費用を参加した従業員に対する給与等と認定した各納税の告知を適法とした。
4 本件旅行費用(本件従業員分費用)の給与等該当性 (1)本件においては、前述したように、全従業員等12人のうち10人が参加したマカオへの2泊3日の慰安旅行(本件旅行)に要した本件旅行費用のうち本件従業員分費用(1人当たり24万1,300円)が福利厚生費に当たるか給与等に当たるかが争われたものである。X会社は、本件従業員分費用が給与等に該当するためには、主として、幸田論文を引用し、①管理、使用収益及び処分権を取得するという流入性、②その流入によって効用を有するという価値の保有性、及び③当該効用についての金銭的評価の可能性という三つの要件を満たす必要があるところ、本件旅行が業務上の要請によって半強制的に行われたものであるから、本件従業員分費用には上記3要件を満たしていない(福利厚生費に該当する)旨主張した。
これに対し、本件各判決は、前述のように、本件旅行は観光旅行に終始し、指揮命令系統強化のための研修等は行われなかったのであるから、本件従業員は雇用契約に基づき経済的利益の供与を受けたものであり、かつ、本件旅行が、所得税基本通達36-30にいう「役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に該当すると認めることはできないとして、本件納税告知及び本件賦課決定を適法と判示した。
(2)本訴の結果については、それぞれの立場によって評価が異なるものと考えられる。しかし、その結果の原因の一つは、X会社の主張の方法にあったものと考えられる。X会社は、本訴において、主として、幸田論文を引用して、前述のような主張を行い、本件従業員分費用が所得税法36条1項にいう「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(すなわち「経済的利益」)に当たらないことを強調した。
しかしながら、幸田論文それ自体は国税庁税務大学校研究科生の研修のための論文であるから、その内容がそれほど高度で権威のある理論に基づいているものとも考えられない。むしろ、雇用関係における各種レクリエーション行事に従業員等が参加することによって種々の経済的利益を享受していて、それが所得税法上の「収入金額」を原則として構成することは公知の事実である。そして、本件のようなレクリエーション行事であっても、それに参加することが会社の行事であるということで少なくとも心理的な強制力が作用することもあろうが、参加する従業員等に対して何らかの経済的利益がもたらされることも事実である。したがって、そのような経済的利益の享受について、所得税法36条1項にいう「経済的利益」の収入それ自体を否定することに合理性があるとも考えられない。
しかし、それらの経済的利益の全てを所得税の課税対象にすべきかについては、特に、雇用契約等に基づく経済的利益の享受の特殊性からいって首肯し難いところがある。それであるが故に、前記1で述べたように、所得税法9条1項では、雇傭関係からもたらされる特定の経済的利益について所得税を課さないこととしているのである(この非課税規定は、経済的利益の享受それ自体を否定しているわけではない。)。
更に、前記2で述べたように、租税法律主義上の問題はともかくとして、所得税基本通達36-21以下において、雇用契約等に基づいて享受する特定の経済的利益について課税しないことを定めているところである。その中で、本件旅行に関する所得税基本通達36-30は、「社会通念上一般的に行われていると認められる」レクリエーション行事によって享受する経済的利益について課税しないこととしているわけである。そして、この取扱いについては、前記3で述べたように、種々の変遷を経て非課税の範囲が拡大してきているところである。
そうであれば、当該取扱い(改正)の趣旨に基づいて本件旅行が「社会通念上一般的に行われていると認められる」ものか否かが一層慎重に検討されるべきであったものと考えられる。特に、平成5年の個別通達の改正によって海外での滞在期間を4泊5日まで延長して非課税の対象を拡大したのは、需要拡大のための景気対策の一環として行われたわけであるから、その趣旨に則った対応も必要であるはずである。特に、本件のような慰安旅行については、ある程度豪華なものでなければ参加社員の満足は得られないはずである。換言すると、安価な海外ツアーで得られるような海外旅行であれば、慰安の効果も得られないことになる。それらのことを総合的に考えると、本件旅行については、「社会通念上一般的に行われていると認められる」範ちゅうに入らないとも限らないものと考えられる。いずれにしても、本訴においては、このような政策的な要請又は海外旅行の実態という観点からの検討(当事者の主張)がなかったことが惜しまれるところである。
5 本件各判決の意義と問題点
以上のように、本件は、マカオに2泊3日で行った社員等の海外慰安旅行(本件旅行)に要した費用(本件旅行費用)のうち、X会社が負担した従業員分の費用(本件従業員分費用)が福利厚生費に当たるか給与等に当たるかが争われたものである。本件各判決は、本件従業員分費用が1人当たり24万1,300円という高額なものであること等を理由に、当該費用が給与等に当たると判断した。
本件のような海外慰安旅行については、特に、中小企業の厚生福利対策としてまま行われているところであるが、取扱い通達が4泊5日の旅行まで課税しないとしているものの、1人当たりの費用負担が幾許まで認められるかについて関心の強いところである。その点に関しては、本件各判決が、1人当たり24万1,300円の本件旅行費用を給与等に当たると判示したことは、実務の指針としては参考になるところである。
しかしながら、本件各判決がそのように判断した経緯においては、前記4で述べたような種々の問題を抱えているところであるので、必ずしも説得力があるものともいい難い。よって、今後、同種の海外慰安旅行を企画している各社においては、それらの問題点も検討した上で対応して行く必要がある。
(注1)最高裁昭和37年8月10日第二小法廷判決(民集16巻8号1,749頁)。
(注2)品川芳宣編著「現物給付の税務」(新日本法規 平成12年)12頁等参照。
(注3)伊藤一行・柴田幸一共著「所得税基本通達逐条解説」(大蔵財務協会 昭和50年)192頁等参照。
(注4)例えば、岡山地裁昭和54年7月18日判決(行裁例集30巻7号1,315頁)では、ハワイへの慰安旅行につき、海外慰安旅行は未だ社会通念上一般的に行われているとは認められていないとして、当該費用(1人当たり約18万6,000円)を給与等に当たると判断している。
(注5)これらの判決の内容と解説については、品川芳宣「重要租税判決の実務研究」(大蔵財務協会 平成26年)161頁参照。
(注6)国税庁「平成5年 改正税法のすべて」16頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -