解説記事2014年07月28日 【巻頭特集】 検証・IBM裁判〔第2回〕(2014年7月28日号・№556)
特集
日本で得た4,000億円の利益に課税できず?
検証・IBM裁判〔第2回〕
前回の朝長税理士へのインタビューでは、「国際的租税回避」事件という地裁判決では見られなかった新たな視点が提示され、読者から大きな反響を呼んだ。
今回はこの「国際的租税回避」について掘り下げ、なぜIBM事件を「国際的租税回避」事件と捉えるべきなのか、具体的なスキームに基づき、お話しいただいた。
その中で、本件は、日本IBMが日本で得た1兆円を超える巨額な利益をアメリカの親会社に送る過程に存在する課税問題であり、そのうちの4,000億円の利益に対して日本で課税ができなくなる可能性があることが分かってきた。
IBM事件を「国際的租税回避」事件と捉えるべき根拠とは?
――前回お話が出た「国際的租税回避」(554号7頁参照)について詳しくお聞きしたいと思います。具体的にはどのようなものなのでしょうか。
朝長 「国際的租税回避」にはいくつかのパターンがあります。スターバックスのイギリス法人のように、14年間で累計約4,200億円の売上がありながら合計約12億円の法人税しか払わなかったということでイギリスで大きな問題になり、約24億円を「法の求めを超えて」支払ったと報道されているようなものもあれば、低税率国に法人を作って現地では大いに歓迎される一方で、本国では問題視されている、というようなものもあります。
――IBM事件はどのパターンに該当するのでしょうか?
朝長 現地国で歓迎されないパターンの「国際的租税回避」と捉えてよいと思います。
――何故そのように捉えるべきなのでしょうか?
朝長 仮に、同族関係にない法人間、これは「グループ法人でない法人間」と言い換えてもよいと思いますが、そのような法人間では、株主である法人が株式の発行法人に自己株式を買い取らせたことにより、その株主である法人にみなし配当と株式の譲渡損が計上されたとしても、特におかしなことではありません。他人から株式を買い取って、その株式を発行法人に買い取らせること自体は、通常、特に問題視されるようなことではありません。グループ法人関係にない法人間での株式の売買では、株式を売却した法人にとって、その株式を購入した法人の課税関係は何ら関係のない話ですし、株式を購入した法人にとっても、その株式を売却した法人の課税関係は何ら関係のない話です。売買の当事者となったこれらの法人がグループ法人の関係になければ、本件のような処理は、通常問題にならない、と考えられます。
一方、IBM事件のように、米国IBMと日本IBM・原告(中間純粋持株会社=IBM・APホールディングス)がグループ法人である場合には、本件のような処理を行うことは、まずあり得ません。
それは何故かというと、株式を売却する法人に莫大な譲渡益が生じて、巨額の納税が必要となるからです。
それにもかかわらず、本件においてそのような行為が行われているのは、アメリカの税法では原告を米国IBMの「支店」として扱うことが可能とされており、日本IBMの株式の譲渡益に課税が行われない仕組みになっているからです。
仮に米国IBMが日本の内国法人であったとしたら、あるいは、アメリカで原告を「支店」として扱うという特別な取扱いがなかったとしたら、本件のような行為は行われなかったはずです。
本件は、アメリカの税制において日本IBM株式のキャピタルゲインに対する課税が行われないことを奇貨として、グループ法人関係にあれば通常はやるはずのない行為を行って日本の税金を減少させたという性格のものであって、国際間の税制の違いを利用し、あえて日本にトンネル会社的性格の中間純粋持株会社を置いて「国際的租税回避」を行ったのではないか、という視点から捉えるべきものだと思っています。
要するに、本件は、日本の税制とアメリカの税制の隙間を突いた「国際的租税回避」なのではないか、ということです。

スターバックスほど注目されなかった理由
――ただ、その割には、日本でもあまり話題になりませんでした。問題となっている税額も、スターバックスよりはるかに多いと思いますが。
朝長 二つの事件で問題とされている金額は桁違いです。租税特別措置法による法人税の政策措置の昨年の減収額が我が国全体で約4,900億円ですから、その4分の1に相当する金額の減税を1社で享受する状態と考えてもよい規模のものです。
それにもかかわらず日本であまり話題にならなかったのは、IBM事件は「国際課税」に関する事件ではなく、「同族会社」に関する事件として問題にされてきたことが一番の理由だと思っています。
――本来は、スターバックスよりもはるかに大きな注目を集めてもおかしくない事件だということですね。
朝長 金額の点でも、また、内容の点でも、そう思いますね。
ヤフー・IDCF事件では、どのようなことが行われたのかということを既に多くの人が知っていますが、IBM事件については、これを詳しく解説する記事も少なく、内容が見えにくいということも、注目度が低い原因になっていると思います。
132条は現在の「社会通念」「常識」を考慮して解釈されるべき
――本件では「同族会社等の行為又は計算の否認」規定の適用が争われていますが、半世紀前に創られた同族会社に関する規定と「国際的租税回避」事件というのは、どうもイメージが合わないように思います。
朝長 法人税法132条に関して、いつまでも半世紀前の古色蒼然とした解釈を持ち出して旧態依然とした議論が繰り返されているからだと思います。132条についても、本来は、税を取り巻く環境の変化というものをしっかりと認識して解釈と適用のあり方を考える必要があります。
「節税」と「租税回避」は、その境界が必ずしも判然としているわけではなく、そのどちらに当たるのかは、最終的には「社会通念」や「常識」に従って判断するしかないと言ってもよい事柄ですから、租税回避防止規定の解釈と適用に当たっては、他の規定以上に、特に環境の変化というものを重視しなければならないはずです。
――半世紀前ということは、132条が創設された昭和40年ですか。近年の事象を当時の前提で見るのは無理がありますね。
朝長 現在の条文の形に整備されたのは確かに現行法人税法ができた昭和40年ですが、原型となるものができたのは大正12年です。
繰り返しになりますが、IBM事件に関しては、事実関係をしっかり見て、「同族会社の租税回避」の事件と見るべきか「国際的租税回避」の事件と見るべきかをよく考える必要があると思います。
ヤフー・IDCF事件で問題になった132条の2は新しい規定ですから、そのようなことを考える必要はないわけですが、これよりはるか昔に創られた132条に関しては、その現代的な意義を考慮せずに解釈をするといったことはあり得ない、と考えています。
――現在の「社会通念」や「常識」で判断しなければならないということですね。
朝長 そうです。当然ながら、「社会通念」や「常識」に反する結論には妥当性がないということになりますので、個別の案件において「租税回避」に該当するのか否かを判断する場合には、その時々の「社会通念」や「常識」に照らしてどうなのか、という判断を行う必要があるということです。
――ただ、一口に「社会通念」や「常識」と言っても、誰にとっての「社会通念」や「常識」かという問題があるように思いますが。
朝長 税とは全く無縁な人達の「社会通念」や「常識」ということではなく、税に関係する人達の「社会通念」や「常識」ということですね。
――そうすると、納税者や税理士、弁護士、税法学者といった方々の「社会通念」や「常識」と考えればよいのでしょうか。
朝長 そうですね。税法の世界には、多くの実務家等に認知され、「社会通念」や「常識」となっているものがあります。例えば、前回紹介した「国際的租税回避」について定義した書籍(554号8頁参照)は、大学の租税法の教科書としても使われているようですので、その内容は「社会通念」や「常識」と考えるべきものだと思います。この書籍では、「濫用」や「潜脱」が「租税回避」に当たるという前提で「国際的租税回避」を説明しています。
現在の法人の行為や計算について132条の適用の適否を検討するという場合には、現在の「社会通念」や「常識」を考慮することが不可欠です。
事実認定が根本的に変わる可能性は?
――朝長先生は、平成13年にみなし配当の規定を抜本改正されたわけですが、IBM事件はこれを“活用”したものとなっています。この点についてはどうお考えですか?
朝長 先日も、ある税理士の方から、「立法した際には、あのようなみなし配当と譲渡損を両建てして欠損金を計上するものを認めるつもりだったんですか?」と聞かれました。
平成13年に自己株式の取得に関するみなし配当の規定が創設されて話題に上っているまさにその時に、その規定を適用するスキームを作り、自己株式の取得を行って実際にその規定を適用しながら、自己株式の取得で欠損金が生ずることが「何らの関心の対象ではなかった」といっても(554号10頁参照)、常識的に考えて、そのような主張は通り難いのではないかと思います。
税制改正の直後にその税制を適用して巨額な欠損金を計上しながら、「何らの関心の対象ではなかった」というようなことは、実務を行ってきた経験からすると、あり得ないことのように思います。
――地裁における原告の主張では、「平成14年譲渡がされた前後の頃、米国PwCのアドバイザーから、日本IBMによる自己株式取得の結果原告に多額の税務上の損失が生じることになるという電話を受けたことから、本件各譲渡に伴って日本の税務上発生する損失の扱いに初めて考えを巡らせ、」と述べられています。
朝長 アメリカのアドバイザーから電話で言われる前に、日本では税制改正後に改正条文が公布されて解説も行われているわけですから、当然、その頃には内容を分かっているはずだと思いますね。
普通、日本の大きな会社は、税制改正の頃になると、少なくとも自分の会社に適用される改正については、税理士法人や税理士に説明を頼んだり自ら情報収集をしたりしています。
特に平成13年度税制改正は、組織再編成税制の創設という非常に重要な改正がありましたから、大手の税理士事務所などは、企業を対象に、相当に力を入れて説明会等を行っていました。金庫株の解禁に伴って措置した自己株式の取得に関する法人税法24条1項4号の改正も当然話題になっていました。
――日本IBMは、従来から巨額の自己株式取得を行ってきていたわけですが、判決の中の主張を見ると、改正にはあまり関心がなかったということのようです。
朝長 先ほど話に出た原告の主張の「平成14年譲渡がされた前後の頃」というと、平成14年12月20日前後の頃ということになりますので、改正後、約1年9か月経ってから、自らが行うことによって生ずる巨額の欠損金について「初めて考えを巡らせ(た)」ということになります。
本件の場合は証拠資料がないわけですから、税理士法人や税理士に説明を頼んだり自ら情報収集したりして検討するというようなことは本当に行われていなかったのかもしれませんが、実務をやっている人達から見れば、この辺りは疑問を感じるところだと思いますね。
――原告は、米国IBMが日本再編プロジェクトの計画及び目的を承認した時期は、「遅くとも2001年(平成13年)11月」と述べていますが、このタイミングに関してはどのようにお考えですか?
朝長 一般に、企業は前年の12月の税制改正大綱が出る頃から、改正の詳細に関心を持つようになります。次の年の4月1日から始まる事業年度の計画に大きく影響するからです。特に平成13年度税制改正は非常に大きな改正でしたから、前年の政府の税制調査会における議論の時から高い関心を集めていましたが、みなし配当に関しては、既に平成12年6月に、税制調査会法人課税小委員会で組織再編成税制の基本的考え方の案を出して議論をして頂く時点から、帳簿価額基準を用いないことを明確にしていました。
IBM側が実際にどのよう認識していたのかは全く分かりませんが、「2001年(平成13年)11月」の約1年半以上前には、原告のような中間純粋持株会社を作って自己株式取得を行えばそこに巨額の欠損金が計上されるということは、考えれば直ぐに分かる状態にあったことは間違いありません。
平成13年4月1日に合併等を行った会社もいくつかありましたが、そのようなケースでは、前年中にスキームを決めておかないと手続きも間に合わなかったはずですし、マスコミでも取り上げられて話題となったパチンコ企業40社が組織再編成と資本等取引を多用して租税回避を行ったとされる事例でも、その最初の組織再編成や資本等取引は、平成13年には既に実行されていたように記憶しています。つまり、そのスキームは、平成12年から13年の初め頃には既に作られていたものと思われます。
――原告は、「そのような損失について米国IBMのグループ全体の連結財務諸表に何らかの記載をする必要もない(甲92、93)という判断をした(甲27、48)。」と主張し、米国IBMの繰延税金資産に税効果を計上していないことを「米国IBMが日本再編プロジェクトの当初から自己株式取得により原告に生ずる譲渡損失には何の関心も持っていなかった」ことの根拠としていますね。
朝長 欠損金は、それが利用できるという確実性がある程度ないと資産計上できませんので、繰延税金資産に計上していなかったということは、確実に利用できるという判断がされていなかったということの証拠にはなっても、「何の関心も持っていなかったこと」の証拠になるものではありません。
税務上、欠損金が損金となる可能性が低いという場合にも、会計上、繰延税金資産を計上しないことになります。
――事実認定が根本から変わることもあり得る、ということでしょうか。
朝長 そうですね。米国IBMや日本IBMが、日本再編プロジェクトが承認された時期とされている「遅くとも2001年(平成13年)11月」の前に、13年3月のみなし配当に関する税制改正によって原告に巨額の欠損金が生ずることになるということを知っていたのか否かということが、事実関係に関する判断の最も重要なポイントになるはずです。
――原告は、平成14年3月20日に提出されたPwC意見書に関して、「PwC意見書(乙19)は、日本IBMが自己株式取得を行う際の同社における税務上の取扱いについて記載されているものであり、当該自己株式を譲渡する株主(原告)の課税関係については何の記載もない。」と述べています。
朝長 本件においては、中間純粋持株会社を置けば莫大な欠損金が計上されることは始めから分かっていたわけですから、意見書にはその話がたくさん書かれていても決しておかしくないと思いますし、仮にそのような話を踏まえて、「巨額の欠損金は使わない」という結論がどこかに記述されているのであれば、IBM側の主張のとおりと判断してもよいと思いますが、これほど巨額の欠損金が発生するにもかかわらず、「何の記載もない」ことを以って「何の関心も持っていなかった」と主張しても、この点に疑問を抱く人に対してはあまり説得力がなく、疑問が晴れることはないように思われます。
――事実関係をどのように捉えるかということは難しく、裁判では非常に重要なポイントになりますね。
朝長 そうですね。ヤフー・IDCF事件のように、国側に立って、事実関係にはタッチせず、法令解釈だけを述べればよいということであれば楽なのですが、私自身、納税者側に立ってやらせて頂いている訴訟では、どの案件も事実関係の把握と整理には苦労しています。
政府税調でも「国際的租税回避」の防止を最優先課題に
――日本でも国を挙げて国際的租税回避に取り組もうとしているようですね。
朝長 税務執行の現場においては、以前から国際取引に関してはかなり厳しい目で見てきましたが、最近は識者の見方にも変化が見られます。
首相官邸のホームページに掲載されていますが、昨年6月24日の第1回税制調査会で、安倍総理が中里実会長以下の委員に、「先週出席したG8首脳サミットでは、多国籍企業による国際的な租税回避への対応策が主要議題のひとつとして取り上げられました。こうした議題についても、委員の皆様でご検討の上、議論を整理していただきたいと思います」と述べています。
――現在、税調でもかなり強い問題意識をもって議論が行われているようですね。
朝長 そうですね。内閣府のホームページから、昨年10月8日の第3回税制調査会において、国際課税関係について熱心な議論が行われたことが分かります。議事録によれば、説明者の浅川雅嗣OECD租税委員会議長から次のような発言がなされています。
――これまでの流れを見ると、国際的租税回避への対応は、日本主導というよりも、まずG8やOECDで「国際的租税回避」への対応という方向性が出てきて、日本もこれに足並みをそろえた、というようにも見えますね。
朝長 確かに浅川氏の発言には「ふと気が付くと、国際的租税回避への対応がなおざりにされていた」とありますが、先ほど述べたとおり、税務執行の現場では、「国際的租税回避」はかなり以前から問題視されていました。
「国際的租税回避」に対応するために、主要な国税局に「国際化対応プロジェクトチーム」が創設されたのは平成14年です。その頃は既に、プロジェクトチームを作らなければならないほど問題があると認識されていたわけです。
ですから、G8やOECDで問題になったから急に日本でも問題視するようになった、ということではありません。
――税務の現場ではかなり以前から問題視されてきており、その流れが更に大きくなった、ということですか。
朝長 そうですね。
日本の税源を浸食したり利益を海外に移転したりするものに対しては、当然のことながら強い態度で臨まなければならないわけですから、政府税調でも、「国際的租税回避」を防止することに強い関心を持っているわけです。
IBM事件についても、法人税法132条の創設時からのこのような環境変化を念頭に置いた上で、「社会通念上、是認され得るものであるのか否か?」ということを考えてみる必要があると思います。
ヤフー事件の132条の解釈は「132条の2の解釈」の明確化のため
――ヤフー・IDCF事件の判決では132条の解釈も示しています。この判決によれば、従来の解釈のとおり、同条は「同族会社は不合理・不自然な行為や計算を行い得るから、それを防止する趣旨・目的で設けられているものである」とされていますが、そうであるとすれば、従来の解釈を変えて「国際的租税回避」に対応するということはできないのではないでしょうか?
朝長 ご指摘のとおり、ヤフー・IDCF事件の判決では132条の解釈にも言及していますが、これはあくまで同事件の適用条文である132条の2の解釈を明確にするためのものに過ぎません。ヤフー・IDCF事件の判決においては、132条が「国際的租税回避」に適用されるのか否かということを考える必要は全くないわけで、132条の2の解釈が明確になれば、それで必要かつ十分なわけです。
――132条の解釈は、それが適用される事件によって判断すればよいということでしょうか?
朝長 132条が適用される事件では、当該事件において同条をどのように解釈し、どのように適用するのかということを明らかにしなければなりません。つまり、他の事件で132条の解釈が示されていたとしても、当該事件において132条をどのように解釈するのかを明らかにする必要があるということです。
次回以降に詳しくお話をさせて頂くことになりますが、132条の条文は、十分、「国際的租税回避」にも対応できる規定振りになっていますので、正しく解釈すれば、本件への適用に全く問題はない、と考えています。
本件は日本で得た巨額の利益を親会社に送金する過程の問題
――IBM事件の事実関係に関してもう少しお話をお聞きしたいと思います。
最も重要な部分はどこだとお考えですか?
朝長 IBM事件は、日本IBMが日本で得た巨額の利益をアメリカの親会社に送る過程における課税問題であるという点が一番重要です。
次の表は、「日本IBMによる配当・自己株式取得の状況」と題して判決文に添付されているものです。
この表には合計欄がありませんが、「配当の金額」と「自己株式取得代金の額」の欄の金額を合計してみると、約1兆2千億円になります。つまり、この表は、平成9年3月から20年12月までの約10年間で、日本IBMが日本で得た約1兆2千億円もの巨額な利益をアメリカの親会社に送った、ということを示しています。
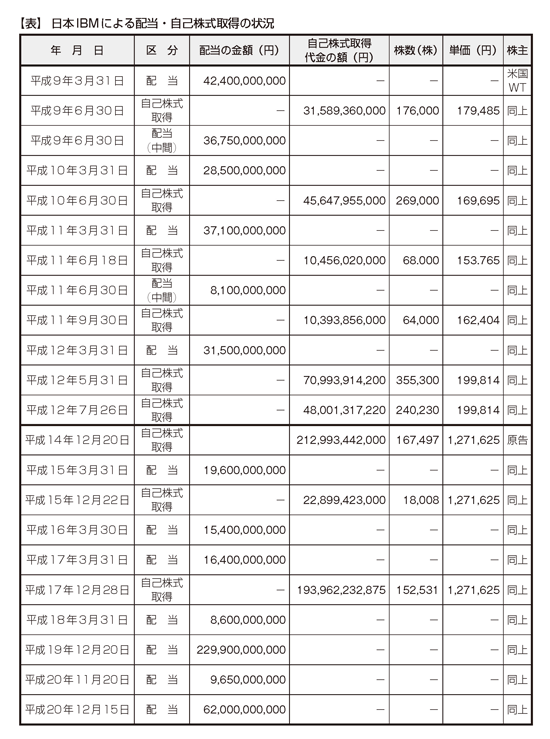
IBM事件の判決文をご覧になったある税理士さんは、「判決の内容よりも、この表に目が釘付けになった」と言っておられました。
――確かに1兆2千億円はすごいですね。
朝長 この日本で得た巨額な利益をアメリカに送る手段の一つとして日本IBMによる「自己株式取得」が行われたということです。
――日本IBM株式の譲渡損計上が租税回避とされたのは平成14年から17年までの3件の「自己株式取得」ですが、この表を見ると、「自己株式取得」は平成9年から行っています。この3件だけが租税回避と言われたのは何故でしょうか?
朝長 この表は一見するとずっと同じことを続けてきただけではないかと錯覚しがちですが、税の観点からこの表を見てみると、平成14年前の「自己株式取得」と同年以後の「自己株式取得」には、大きな違いがあることが分かります。
平成14年前の「自己株式取得」は随時配当の手段
――具体的に教えてください。
朝長 当時の旧商法においては、配当は定期配当と中間配当のみとなっており、親会社に対して任意の時期に配当を行うことができなかったため、日本IBMは、限定的に認められていた自己株式の消却を行うことにより、アメリカの親会社に対して日本で得た利益の実質的な配当を行っていたものと思われます。この表の平成9年から12年までの「自己株式取得」とされているものは、自己の株式の消却を行うことを目的とした取得だと考えられます。
この平成14年前の法人税法においては、「株式の消却」を行った場合には、みなし配当が生ずるものとされていましたが、みなし配当とされる金額は株主における株式の帳簿価額を超える部分に限定されていたため、日本IBMに大きな利益が留保されていたとしても、それに対応する金額がみなし配当とされてそれと同額の株式の譲渡損が両建てで計上されるということはありませんでした。
要するに、税のメリット・デメリットには関係なく、日本IBMが日本で稼いだ利益を米国IBMに任意の時期に配当するための単なる手段として「自己株式取得」が行われていたものと思われます。
この表の平成9年から12年までの「自己株式取得」は、当時の法人税法における用語を用いると、「株式の消却」ということになります。
――平成14年前は、単に随時配当の手段として使われていただけということですね。
朝長 そのように捉えてよいと思います。
「直接配当」を「間接配当」とすることで利益が「欠損金」に
――平成14年以後の「自己株式取得」はどのようなものだと考えるべきでしょうか?
朝長 平成13年度税制改正により、有価証券の帳簿価額を超える部分のみをみなし配当とする従来の取扱いを廃止しましたので、みなし配当と株式の譲渡損の双方が多額に計上されるという現象が起こり得る状態となりました。
――IBMはそれを利用して多額の欠損金を計上したということですね。
朝長 いえ、そうではありません。
従来のように、日本IBMがアメリカの親会社に「自己の株式の取得」によって利益を送金したとしても、日本IBMとアメリカの親会社のいずれにも欠損金が生ずることはありません。平成13年度の税制改正によって欠損金が生ずるようになった、というわけではないのです。
――具体的にご説明をお願いします。
朝長 多額の欠損金が生ずることになったのは、平成14年に、日本IBMとアメリカの親会社の間に、日本法人として中間純粋持株会社(原告)を置いたからです。これによって、その中間純粋持株会社に多額の欠損金が生ずることとなったわけです。
逆に言うと、日本IBMとアメリカの親会社の間に日本法人を設けず、従来どおり日本IBMがアメリカの親会社に利益を送金していれば、そもそも本件のような課税問題は生じませんでした。
――中間純粋持株会社を設け、従来の「直接配当」を「間接配当」とすることによって、その中間純粋持株会社に欠損金が計上される構造となったわけですね。
朝長 そうです。日本IBMが日本で得た利益は、原告を介してアメリカの親会社に送金されるわけですが、原告に生ずる欠損金は、このアメリカの親会社に送金される利益、すなわち、原告においてみなし配当とされる額に相当する金額となります。
要するに、日本IBMが日本で大きな利益を上げれば上げるほど、みなし配当の額が大きくなり、みなし配当の額が大きくなればなるほど、原告において日本IBM株式の譲渡損の額が大きくなる、という普通ではなかなか理解できない不思議な構造ができ上がったわけです。
利益が日本で課税されずにアメリカの親会社に移転
――通常は、損をすればするほど欠損金が大きくなるはずですが、中間に日本法人を設けて「直接配当」を「間接配当」にすれば、逆に利益を上げれば上げるほど欠損金が大きくなるという状況を創出できるわけですね。
朝長 そうですね。この日本IBMから原告に送金される利益は更にアメリカの親会社に送金されるわけですから、実質的には、日本で損金を計上してアメリカに利益を送金するのと同じ状態になります。
――そうすると、最終的には、日本IBMが日本で稼いだ利益に対して日本で課税を行えない、ということになりませんか?
朝長 そういうことになります。通期でみれば、日本からアメリカへの利益移転に課税を行い得ず、日本IBMが日本で得た利益が日本で課税を行われないままアメリカに移転する、ということになります。
「ゼロから損失を創り出した」という言い方をされる方もいらっしゃいますが、私はむしろ、「配当を損金にする状態を創り出した」と見てもよいと思っています。
こういう点からも、IBM事件は、日本から見た「国際的租税回避」と言うべきものではないかという観点から検討を行うべき事件だと思います。
会社の対応と当局の対応が錯綜
――平成18年以後、自己株式の取得が行われていないのは何故でしょうか?
18年以後も自己株式取得を行えば、同じ状態が創り出せたはずです。
朝長 そうですね。平成18年以後に自己株式取得が行われなくなったのは、同年以後、会社法によって随時配当が可能とされたことから、自己株式取得によって実質的な利益の随時配当を行う必要がなくなったこともあると思いますが、同年頃に、税務当局から自己株式取得によって欠損金を計上することを問題視されたことも影響している可能性があると考えています。
――原告への課税は、まず原告が平成20年の最初の連結納税において14年から17年までの欠損金を損金とせずに確定申告を行い、これに対し原告が行った「更正の請求」でその欠損金の損金算入が認められ、その後、税務調査でその損金算入が否認される、という異例の展開の中で行われているのですが、これも18年頃の税務調査が影響しているのでしょうか?
朝長 原告が確定申告で欠損金を損金とせずに申告と納税を行った上で、後から欠損金を損金とするように求める更正の請求を行うという異例の対応を採ったのは、原告が欠損金の損金算入を否認される可能性があると考えていたためだと思われます。
過去の税務調査で問題視されたことから、欠損金の損金算入が否認される可能性があると判断したのかもしれませんし、元々そのように判断していて、税務調査やその後の当局の感触から欠損金の損金算入が可能と判断したのかもしれません。そのあたりはよく分かりませんが、申告・納税を行った上で更正の請求をするというように、損金算入が認められなかったとしてもダメージが少なく、チャレンジし易い方法を採っていることからすると、欠損金の損金算入が絶対に大丈夫という判断をしていなかったのは間違いないと言ってよいでしょう。
――本件においては、会社の対応と当局の対応がかなり複雑に錯綜しているようですね。
朝長 そうですね。詳しいことはよく分かりませんが、他の案件とは違って、本件の場合には、お互いに数年間にわたって相手の動きを気にして見ていた、ということではないでしょうか。
更正の請求で本件の欠損金の損金算入を求めるという異例の対応が採られているということは、IBMにおいて相当な熟議が行われ、また、かなり上の役職者による判断がなされていることを示していると思います。
ヤフー・IDCF事件の影響額は本件の7分の1ですが、それでも原告の株主の会社のトップ自らがスキームを実行するのか否かの判断を下しており、その判断を仰ぐに当たっては入念な検討が行われていたと推測されます。金額が7倍にもなるIBMでも同様だったであろうと考えるのが自然でしょう。

――これだけの巨額な金額ですから、現場レベルの役職の人が意思決定できるとは思えないですよね。
朝長 本件のような意思決定を行う場合には、当局がどのような考えを持っており、どのように動くのかということが、最も重要な判断材料になります。
このため、更正の請求を行うか否かの判断に当たっては、過去の税務調査(平成15年、平成18年及び平成19年の税務調査)において、どのような資料の提出を求められ、どのような内容の指摘を受けたのかというようなことを確認するために、過去の税務調査の記録を取り寄せて確認をしたり、その後の当局の動きが分かる記事等を集めたりすることになったのではないかと思われます。
また、本件では、一旦、更正の請求を受けて当局が減額更正を行っているわけですから、その減額更正の際の当局との間のやり取り等の記録も、本件の課税を行うこととなった税務調査の際には存在していたはずです。
――どの会社でも税務調査の記録は作るものでしょうか?
朝長 上層部に報告したり、後の税務調査に備えたり、後任者に引き継いだりしないといけませんから、大きな会社はほぼ全て作っていると思います。特に、日本IBMのような子会社の場合、親会社に報告をしなければなりませんから、作らないということはまずないはずです。
――原告が「本件過去調査が行われた際、本件株式購入、本件各譲渡及び欠損金の計上について詳細に調査がなされたが、何の指摘もなかった」と主張していることからすると、何の記録もないという可能性はないのでしょうか。
朝長 その「本件過去調査」というのは、平成15年の税務調査と平成18年から始まった税務調査のことだと思いますが、「何の指摘もなかった」ということではなかったはずです。むしろ調査官は、「譲渡損の計上には問題がある」という指摘を行ったはずです。ただ、まだその欠損金を使用していなかったことから様子を見ることにしただけだったのではないかと思います。
しかし、問題は、その過去の税務調査の「内容」の如何よりも、その「記録」が把握されている気配がない、ということにあると思っています。特に、平成18年に始まった税務調査は長期にわたるものとなっていますので、各調査日毎に、調査官と会社側がどのようなやり取りをしたのかという記録等があるはずであり、それが本件においては極めて重要な証拠資料になるはずです。
前回、原告を中間純粋持株会社として置くことを決めた際の欠損金の取扱いに関する資料が見当たらないという話をさせて頂きましたが、それだけでなく、本件においては、過去の税務調査等に関する資料も見当たらないように思われます。
IBM事件においては、ヤフー・IDCF事件とは違って、「本件過去調査が行われた際、本件株式購入、本件各譲渡及び欠損金の計上について詳細に調査がなされた」ということになっていますので、各調査日毎に、調査に対応した者が調査官の言ったことと会社側の者が言ったことなどを記録した応接録、その調査の状況を上層部・親会社に報告し指示を受けたメール、そして、調査結果の報告書などが、極めて重要となります。
――しかし、お話のとおり、そのようなものは裁判資料の中には無いようですね。
そのようなものが無いということは、国側としては苦しいということでしょうか。
朝長 そうかもしれませんね。
ただ、裁判は勝ち負けも大事ですが、「真実は何か」ということも忘れてはならないことだと思っています。証拠資料が乏しい中で、真実をどのように見極めるのかということが問われる、ということではないでしょうか。
「中間純粋持株会社を置いた目的」が問われる
――国側は、原告に関して「原告の主な収入源や支出先は、日本IBM及び米国WTであって、原告はその2社の間にあっていわば資金を通過させるだけのトンネル会社的存在にすぎ(ない)」と主張しています。この点についてはどのようにお考えですか?
朝長 原告には専任の役員及び使用人はおらず、原告の役員には、米国IBMの100%子会社の日本における代表者、日本IBMの役職者の2、3名が本業と兼務して就任しています。また、原告は固有の事務所を所有しておらず、本店所在地は米国IBMの100%子会社の日本支店・日本IBMの本店の所在地と同一となっています。さらに、日本IBMとの間で経理、財務、税務等の業務の委託契約を締結し、同契約に基づく業務委託料として月額50万円を支払う一方、役員に対しては報酬を支払っておらず、人件費等の固有の経費も発生していない、とのことです。
普通、そのようなものは「トンネル」と言われても仕方がないのではないでしょうか。
――業務は全て日本IBMに委託しているようですね。
朝長 そのようですね。判決文によれば、次のように述べられていますので、原告のような法人を作ったのは日本だけのようです。
「多くの国」と同じように、日本においても、原告を日本IBMが吸収合併していれば、本件のような問題も発生することはなかったわけです。
――仮にこの中間純粋持株会社が日本の税制のみなし配当と株式の譲渡損益の規定を利用して巨額の欠損金を計上することを目的としていたのであれば、そもそも業務はあまり発生しないでしょうね。
朝長 日本IBMと米国IBMのような会社の間に持株会社を置けば、必ず何らかの業務があり、何も業務がないというようなことはあり得ないはずですが、租税回避に当たるのか否かという観点からすると、中間に純粋持株会社を置いた主たる目的は何だったのか、ということが問われることになると思います。
――お話をまとめると、アメリカの税制に日本IBMの株式の譲渡益に課税しない特例がある一方、日本の税制に巨額のみなし配当を計上して益金不算入とするとともに巨額の株式の譲渡損を計上して損金算入とすることができる取扱いができたことから、日本に中間純粋持株会社を置いて間接的に「自己株式取得」によって配当を行うことで、その中間純粋持株会社に配当と同じ金額の欠損金を発生させ、その欠損金を連結納税に利用して日本における納税額を少なくした、ということでよろしいでしょうか。
朝長 経緯に着目すれば、そういうことでしょうね。
132条の解釈や平成13年のみなし配当の立法等に関しては、次回以降にお話しますが、先ほども申し上げたとおり、本件については、日本の税制とアメリカの税制の隙間を突いた「国際的租税回避」ではないかという観点から検討を行うべき事件だと考えています。
――有り難うございました。次回は、関係法令の解釈を交えてお話をうかがいたいと思います。
(第3回へ続く)
日本で得た4,000億円の利益に課税できず?
検証・IBM裁判〔第2回〕
前回の朝長税理士へのインタビューでは、「国際的租税回避」事件という地裁判決では見られなかった新たな視点が提示され、読者から大きな反響を呼んだ。
今回はこの「国際的租税回避」について掘り下げ、なぜIBM事件を「国際的租税回避」事件と捉えるべきなのか、具体的なスキームに基づき、お話しいただいた。
その中で、本件は、日本IBMが日本で得た1兆円を超える巨額な利益をアメリカの親会社に送る過程に存在する課税問題であり、そのうちの4,000億円の利益に対して日本で課税ができなくなる可能性があることが分かってきた。
IBM事件を「国際的租税回避」事件と捉えるべき根拠とは?
――前回お話が出た「国際的租税回避」(554号7頁参照)について詳しくお聞きしたいと思います。具体的にはどのようなものなのでしょうか。
朝長 「国際的租税回避」にはいくつかのパターンがあります。スターバックスのイギリス法人のように、14年間で累計約4,200億円の売上がありながら合計約12億円の法人税しか払わなかったということでイギリスで大きな問題になり、約24億円を「法の求めを超えて」支払ったと報道されているようなものもあれば、低税率国に法人を作って現地では大いに歓迎される一方で、本国では問題視されている、というようなものもあります。
――IBM事件はどのパターンに該当するのでしょうか?
朝長 現地国で歓迎されないパターンの「国際的租税回避」と捉えてよいと思います。
――何故そのように捉えるべきなのでしょうか?
朝長 仮に、同族関係にない法人間、これは「グループ法人でない法人間」と言い換えてもよいと思いますが、そのような法人間では、株主である法人が株式の発行法人に自己株式を買い取らせたことにより、その株主である法人にみなし配当と株式の譲渡損が計上されたとしても、特におかしなことではありません。他人から株式を買い取って、その株式を発行法人に買い取らせること自体は、通常、特に問題視されるようなことではありません。グループ法人関係にない法人間での株式の売買では、株式を売却した法人にとって、その株式を購入した法人の課税関係は何ら関係のない話ですし、株式を購入した法人にとっても、その株式を売却した法人の課税関係は何ら関係のない話です。売買の当事者となったこれらの法人がグループ法人の関係になければ、本件のような処理は、通常問題にならない、と考えられます。
一方、IBM事件のように、米国IBMと日本IBM・原告(中間純粋持株会社=IBM・APホールディングス)がグループ法人である場合には、本件のような処理を行うことは、まずあり得ません。
それは何故かというと、株式を売却する法人に莫大な譲渡益が生じて、巨額の納税が必要となるからです。
それにもかかわらず、本件においてそのような行為が行われているのは、アメリカの税法では原告を米国IBMの「支店」として扱うことが可能とされており、日本IBMの株式の譲渡益に課税が行われない仕組みになっているからです。
仮に米国IBMが日本の内国法人であったとしたら、あるいは、アメリカで原告を「支店」として扱うという特別な取扱いがなかったとしたら、本件のような行為は行われなかったはずです。
本件は、アメリカの税制において日本IBM株式のキャピタルゲインに対する課税が行われないことを奇貨として、グループ法人関係にあれば通常はやるはずのない行為を行って日本の税金を減少させたという性格のものであって、国際間の税制の違いを利用し、あえて日本にトンネル会社的性格の中間純粋持株会社を置いて「国際的租税回避」を行ったのではないか、という視点から捉えるべきものだと思っています。
要するに、本件は、日本の税制とアメリカの税制の隙間を突いた「国際的租税回避」なのではないか、ということです。

スターバックスほど注目されなかった理由
――ただ、その割には、日本でもあまり話題になりませんでした。問題となっている税額も、スターバックスよりはるかに多いと思いますが。
朝長 二つの事件で問題とされている金額は桁違いです。租税特別措置法による法人税の政策措置の昨年の減収額が我が国全体で約4,900億円ですから、その4分の1に相当する金額の減税を1社で享受する状態と考えてもよい規模のものです。
それにもかかわらず日本であまり話題にならなかったのは、IBM事件は「国際課税」に関する事件ではなく、「同族会社」に関する事件として問題にされてきたことが一番の理由だと思っています。
――本来は、スターバックスよりもはるかに大きな注目を集めてもおかしくない事件だということですね。
朝長 金額の点でも、また、内容の点でも、そう思いますね。
ヤフー・IDCF事件では、どのようなことが行われたのかということを既に多くの人が知っていますが、IBM事件については、これを詳しく解説する記事も少なく、内容が見えにくいということも、注目度が低い原因になっていると思います。
132条は現在の「社会通念」「常識」を考慮して解釈されるべき
――本件では「同族会社等の行為又は計算の否認」規定の適用が争われていますが、半世紀前に創られた同族会社に関する規定と「国際的租税回避」事件というのは、どうもイメージが合わないように思います。
朝長 法人税法132条に関して、いつまでも半世紀前の古色蒼然とした解釈を持ち出して旧態依然とした議論が繰り返されているからだと思います。132条についても、本来は、税を取り巻く環境の変化というものをしっかりと認識して解釈と適用のあり方を考える必要があります。
「節税」と「租税回避」は、その境界が必ずしも判然としているわけではなく、そのどちらに当たるのかは、最終的には「社会通念」や「常識」に従って判断するしかないと言ってもよい事柄ですから、租税回避防止規定の解釈と適用に当たっては、他の規定以上に、特に環境の変化というものを重視しなければならないはずです。
――半世紀前ということは、132条が創設された昭和40年ですか。近年の事象を当時の前提で見るのは無理がありますね。
朝長 現在の条文の形に整備されたのは確かに現行法人税法ができた昭和40年ですが、原型となるものができたのは大正12年です。
繰り返しになりますが、IBM事件に関しては、事実関係をしっかり見て、「同族会社の租税回避」の事件と見るべきか「国際的租税回避」の事件と見るべきかをよく考える必要があると思います。
ヤフー・IDCF事件で問題になった132条の2は新しい規定ですから、そのようなことを考える必要はないわけですが、これよりはるか昔に創られた132条に関しては、その現代的な意義を考慮せずに解釈をするといったことはあり得ない、と考えています。
――現在の「社会通念」や「常識」で判断しなければならないということですね。
朝長 そうです。当然ながら、「社会通念」や「常識」に反する結論には妥当性がないということになりますので、個別の案件において「租税回避」に該当するのか否かを判断する場合には、その時々の「社会通念」や「常識」に照らしてどうなのか、という判断を行う必要があるということです。
――ただ、一口に「社会通念」や「常識」と言っても、誰にとっての「社会通念」や「常識」かという問題があるように思いますが。
朝長 税とは全く無縁な人達の「社会通念」や「常識」ということではなく、税に関係する人達の「社会通念」や「常識」ということですね。
――そうすると、納税者や税理士、弁護士、税法学者といった方々の「社会通念」や「常識」と考えればよいのでしょうか。
朝長 そうですね。税法の世界には、多くの実務家等に認知され、「社会通念」や「常識」となっているものがあります。例えば、前回紹介した「国際的租税回避」について定義した書籍(554号8頁参照)は、大学の租税法の教科書としても使われているようですので、その内容は「社会通念」や「常識」と考えるべきものだと思います。この書籍では、「濫用」や「潜脱」が「租税回避」に当たるという前提で「国際的租税回避」を説明しています。
現在の法人の行為や計算について132条の適用の適否を検討するという場合には、現在の「社会通念」や「常識」を考慮することが不可欠です。
事実認定が根本的に変わる可能性は?
――朝長先生は、平成13年にみなし配当の規定を抜本改正されたわけですが、IBM事件はこれを“活用”したものとなっています。この点についてはどうお考えですか?
朝長 先日も、ある税理士の方から、「立法した際には、あのようなみなし配当と譲渡損を両建てして欠損金を計上するものを認めるつもりだったんですか?」と聞かれました。
平成13年に自己株式の取得に関するみなし配当の規定が創設されて話題に上っているまさにその時に、その規定を適用するスキームを作り、自己株式の取得を行って実際にその規定を適用しながら、自己株式の取得で欠損金が生ずることが「何らの関心の対象ではなかった」といっても(554号10頁参照)、常識的に考えて、そのような主張は通り難いのではないかと思います。
税制改正の直後にその税制を適用して巨額な欠損金を計上しながら、「何らの関心の対象ではなかった」というようなことは、実務を行ってきた経験からすると、あり得ないことのように思います。
――地裁における原告の主張では、「平成14年譲渡がされた前後の頃、米国PwCのアドバイザーから、日本IBMによる自己株式取得の結果原告に多額の税務上の損失が生じることになるという電話を受けたことから、本件各譲渡に伴って日本の税務上発生する損失の扱いに初めて考えを巡らせ、」と述べられています。
朝長 アメリカのアドバイザーから電話で言われる前に、日本では税制改正後に改正条文が公布されて解説も行われているわけですから、当然、その頃には内容を分かっているはずだと思いますね。
普通、日本の大きな会社は、税制改正の頃になると、少なくとも自分の会社に適用される改正については、税理士法人や税理士に説明を頼んだり自ら情報収集をしたりしています。
特に平成13年度税制改正は、組織再編成税制の創設という非常に重要な改正がありましたから、大手の税理士事務所などは、企業を対象に、相当に力を入れて説明会等を行っていました。金庫株の解禁に伴って措置した自己株式の取得に関する法人税法24条1項4号の改正も当然話題になっていました。
――日本IBMは、従来から巨額の自己株式取得を行ってきていたわけですが、判決の中の主張を見ると、改正にはあまり関心がなかったということのようです。
朝長 先ほど話に出た原告の主張の「平成14年譲渡がされた前後の頃」というと、平成14年12月20日前後の頃ということになりますので、改正後、約1年9か月経ってから、自らが行うことによって生ずる巨額の欠損金について「初めて考えを巡らせ(た)」ということになります。
本件の場合は証拠資料がないわけですから、税理士法人や税理士に説明を頼んだり自ら情報収集したりして検討するというようなことは本当に行われていなかったのかもしれませんが、実務をやっている人達から見れば、この辺りは疑問を感じるところだと思いますね。
――原告は、米国IBMが日本再編プロジェクトの計画及び目的を承認した時期は、「遅くとも2001年(平成13年)11月」と述べていますが、このタイミングに関してはどのようにお考えですか?
朝長 一般に、企業は前年の12月の税制改正大綱が出る頃から、改正の詳細に関心を持つようになります。次の年の4月1日から始まる事業年度の計画に大きく影響するからです。特に平成13年度税制改正は非常に大きな改正でしたから、前年の政府の税制調査会における議論の時から高い関心を集めていましたが、みなし配当に関しては、既に平成12年6月に、税制調査会法人課税小委員会で組織再編成税制の基本的考え方の案を出して議論をして頂く時点から、帳簿価額基準を用いないことを明確にしていました。
IBM側が実際にどのよう認識していたのかは全く分かりませんが、「2001年(平成13年)11月」の約1年半以上前には、原告のような中間純粋持株会社を作って自己株式取得を行えばそこに巨額の欠損金が計上されるということは、考えれば直ぐに分かる状態にあったことは間違いありません。
平成13年4月1日に合併等を行った会社もいくつかありましたが、そのようなケースでは、前年中にスキームを決めておかないと手続きも間に合わなかったはずですし、マスコミでも取り上げられて話題となったパチンコ企業40社が組織再編成と資本等取引を多用して租税回避を行ったとされる事例でも、その最初の組織再編成や資本等取引は、平成13年には既に実行されていたように記憶しています。つまり、そのスキームは、平成12年から13年の初め頃には既に作られていたものと思われます。
――原告は、「そのような損失について米国IBMのグループ全体の連結財務諸表に何らかの記載をする必要もない(甲92、93)という判断をした(甲27、48)。」と主張し、米国IBMの繰延税金資産に税効果を計上していないことを「米国IBMが日本再編プロジェクトの当初から自己株式取得により原告に生ずる譲渡損失には何の関心も持っていなかった」ことの根拠としていますね。
朝長 欠損金は、それが利用できるという確実性がある程度ないと資産計上できませんので、繰延税金資産に計上していなかったということは、確実に利用できるという判断がされていなかったということの証拠にはなっても、「何の関心も持っていなかったこと」の証拠になるものではありません。
税務上、欠損金が損金となる可能性が低いという場合にも、会計上、繰延税金資産を計上しないことになります。
――事実認定が根本から変わることもあり得る、ということでしょうか。
朝長 そうですね。米国IBMや日本IBMが、日本再編プロジェクトが承認された時期とされている「遅くとも2001年(平成13年)11月」の前に、13年3月のみなし配当に関する税制改正によって原告に巨額の欠損金が生ずることになるということを知っていたのか否かということが、事実関係に関する判断の最も重要なポイントになるはずです。
――原告は、平成14年3月20日に提出されたPwC意見書に関して、「PwC意見書(乙19)は、日本IBMが自己株式取得を行う際の同社における税務上の取扱いについて記載されているものであり、当該自己株式を譲渡する株主(原告)の課税関係については何の記載もない。」と述べています。
朝長 本件においては、中間純粋持株会社を置けば莫大な欠損金が計上されることは始めから分かっていたわけですから、意見書にはその話がたくさん書かれていても決しておかしくないと思いますし、仮にそのような話を踏まえて、「巨額の欠損金は使わない」という結論がどこかに記述されているのであれば、IBM側の主張のとおりと判断してもよいと思いますが、これほど巨額の欠損金が発生するにもかかわらず、「何の記載もない」ことを以って「何の関心も持っていなかった」と主張しても、この点に疑問を抱く人に対してはあまり説得力がなく、疑問が晴れることはないように思われます。
――事実関係をどのように捉えるかということは難しく、裁判では非常に重要なポイントになりますね。
朝長 そうですね。ヤフー・IDCF事件のように、国側に立って、事実関係にはタッチせず、法令解釈だけを述べればよいということであれば楽なのですが、私自身、納税者側に立ってやらせて頂いている訴訟では、どの案件も事実関係の把握と整理には苦労しています。
政府税調でも「国際的租税回避」の防止を最優先課題に
――日本でも国を挙げて国際的租税回避に取り組もうとしているようですね。
朝長 税務執行の現場においては、以前から国際取引に関してはかなり厳しい目で見てきましたが、最近は識者の見方にも変化が見られます。
首相官邸のホームページに掲載されていますが、昨年6月24日の第1回税制調査会で、安倍総理が中里実会長以下の委員に、「先週出席したG8首脳サミットでは、多国籍企業による国際的な租税回避への対応策が主要議題のひとつとして取り上げられました。こうした議題についても、委員の皆様でご検討の上、議論を整理していただきたいと思います」と述べています。
――現在、税調でもかなり強い問題意識をもって議論が行われているようですね。
朝長 そうですね。内閣府のホームページから、昨年10月8日の第3回税制調査会において、国際課税関係について熱心な議論が行われたことが分かります。議事録によれば、説明者の浅川雅嗣OECD租税委員会議長から次のような発言がなされています。
| 今日、ふと気が付くと、後者の租税回避への対応の方がかえってなおざりにされていて、我々が苦労してこれまで構築してきた種々の国際課税ルールが、必ずしも国際的な租税回避行動に対応しきれていないのではないかという問題意識が芽生えてきたわけです。今日は、むしろそちらの流れで、今、盛んに議論が行われていますBEPS(税源浸食と利益移転。引用者注)という話と、情報交換という二つの話をしたいと思いますが、それはいずれにしても、最初にお話をしました二つの論点のうちの後者の話です。いずれも、国際的な租税回避への対応をどうしていこうかという基本的な問題意識から出たものとご理解いただきたいと思います。 |
朝長 確かに浅川氏の発言には「ふと気が付くと、国際的租税回避への対応がなおざりにされていた」とありますが、先ほど述べたとおり、税務執行の現場では、「国際的租税回避」はかなり以前から問題視されていました。
「国際的租税回避」に対応するために、主要な国税局に「国際化対応プロジェクトチーム」が創設されたのは平成14年です。その頃は既に、プロジェクトチームを作らなければならないほど問題があると認識されていたわけです。
ですから、G8やOECDで問題になったから急に日本でも問題視するようになった、ということではありません。
――税務の現場ではかなり以前から問題視されてきており、その流れが更に大きくなった、ということですか。
朝長 そうですね。
日本の税源を浸食したり利益を海外に移転したりするものに対しては、当然のことながら強い態度で臨まなければならないわけですから、政府税調でも、「国際的租税回避」を防止することに強い関心を持っているわけです。
IBM事件についても、法人税法132条の創設時からのこのような環境変化を念頭に置いた上で、「社会通念上、是認され得るものであるのか否か?」ということを考えてみる必要があると思います。
ヤフー事件の132条の解釈は「132条の2の解釈」の明確化のため
――ヤフー・IDCF事件の判決では132条の解釈も示しています。この判決によれば、従来の解釈のとおり、同条は「同族会社は不合理・不自然な行為や計算を行い得るから、それを防止する趣旨・目的で設けられているものである」とされていますが、そうであるとすれば、従来の解釈を変えて「国際的租税回避」に対応するということはできないのではないでしょうか?
朝長 ご指摘のとおり、ヤフー・IDCF事件の判決では132条の解釈にも言及していますが、これはあくまで同事件の適用条文である132条の2の解釈を明確にするためのものに過ぎません。ヤフー・IDCF事件の判決においては、132条が「国際的租税回避」に適用されるのか否かということを考える必要は全くないわけで、132条の2の解釈が明確になれば、それで必要かつ十分なわけです。
――132条の解釈は、それが適用される事件によって判断すればよいということでしょうか?
朝長 132条が適用される事件では、当該事件において同条をどのように解釈し、どのように適用するのかということを明らかにしなければなりません。つまり、他の事件で132条の解釈が示されていたとしても、当該事件において132条をどのように解釈するのかを明らかにする必要があるということです。
次回以降に詳しくお話をさせて頂くことになりますが、132条の条文は、十分、「国際的租税回避」にも対応できる規定振りになっていますので、正しく解釈すれば、本件への適用に全く問題はない、と考えています。
本件は日本で得た巨額の利益を親会社に送金する過程の問題
――IBM事件の事実関係に関してもう少しお話をお聞きしたいと思います。
最も重要な部分はどこだとお考えですか?
朝長 IBM事件は、日本IBMが日本で得た巨額の利益をアメリカの親会社に送る過程における課税問題であるという点が一番重要です。
次の表は、「日本IBMによる配当・自己株式取得の状況」と題して判決文に添付されているものです。
この表には合計欄がありませんが、「配当の金額」と「自己株式取得代金の額」の欄の金額を合計してみると、約1兆2千億円になります。つまり、この表は、平成9年3月から20年12月までの約10年間で、日本IBMが日本で得た約1兆2千億円もの巨額な利益をアメリカの親会社に送った、ということを示しています。
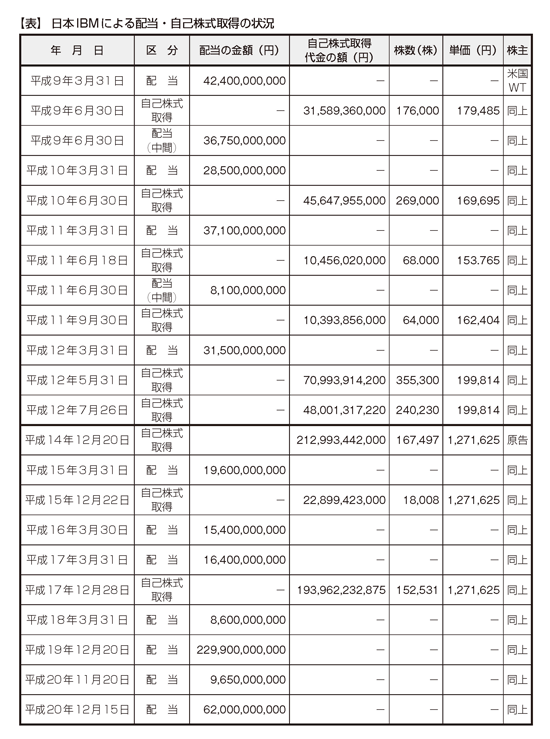
IBM事件の判決文をご覧になったある税理士さんは、「判決の内容よりも、この表に目が釘付けになった」と言っておられました。
――確かに1兆2千億円はすごいですね。
朝長 この日本で得た巨額な利益をアメリカに送る手段の一つとして日本IBMによる「自己株式取得」が行われたということです。
――日本IBM株式の譲渡損計上が租税回避とされたのは平成14年から17年までの3件の「自己株式取得」ですが、この表を見ると、「自己株式取得」は平成9年から行っています。この3件だけが租税回避と言われたのは何故でしょうか?
朝長 この表は一見するとずっと同じことを続けてきただけではないかと錯覚しがちですが、税の観点からこの表を見てみると、平成14年前の「自己株式取得」と同年以後の「自己株式取得」には、大きな違いがあることが分かります。
平成14年前の「自己株式取得」は随時配当の手段
――具体的に教えてください。
朝長 当時の旧商法においては、配当は定期配当と中間配当のみとなっており、親会社に対して任意の時期に配当を行うことができなかったため、日本IBMは、限定的に認められていた自己株式の消却を行うことにより、アメリカの親会社に対して日本で得た利益の実質的な配当を行っていたものと思われます。この表の平成9年から12年までの「自己株式取得」とされているものは、自己の株式の消却を行うことを目的とした取得だと考えられます。
この平成14年前の法人税法においては、「株式の消却」を行った場合には、みなし配当が生ずるものとされていましたが、みなし配当とされる金額は株主における株式の帳簿価額を超える部分に限定されていたため、日本IBMに大きな利益が留保されていたとしても、それに対応する金額がみなし配当とされてそれと同額の株式の譲渡損が両建てで計上されるということはありませんでした。
要するに、税のメリット・デメリットには関係なく、日本IBMが日本で稼いだ利益を米国IBMに任意の時期に配当するための単なる手段として「自己株式取得」が行われていたものと思われます。
この表の平成9年から12年までの「自己株式取得」は、当時の法人税法における用語を用いると、「株式の消却」ということになります。
――平成14年前は、単に随時配当の手段として使われていただけということですね。
朝長 そのように捉えてよいと思います。
「直接配当」を「間接配当」とすることで利益が「欠損金」に
――平成14年以後の「自己株式取得」はどのようなものだと考えるべきでしょうか?
朝長 平成13年度税制改正により、有価証券の帳簿価額を超える部分のみをみなし配当とする従来の取扱いを廃止しましたので、みなし配当と株式の譲渡損の双方が多額に計上されるという現象が起こり得る状態となりました。
――IBMはそれを利用して多額の欠損金を計上したということですね。
朝長 いえ、そうではありません。
従来のように、日本IBMがアメリカの親会社に「自己の株式の取得」によって利益を送金したとしても、日本IBMとアメリカの親会社のいずれにも欠損金が生ずることはありません。平成13年度の税制改正によって欠損金が生ずるようになった、というわけではないのです。
――具体的にご説明をお願いします。
朝長 多額の欠損金が生ずることになったのは、平成14年に、日本IBMとアメリカの親会社の間に、日本法人として中間純粋持株会社(原告)を置いたからです。これによって、その中間純粋持株会社に多額の欠損金が生ずることとなったわけです。
逆に言うと、日本IBMとアメリカの親会社の間に日本法人を設けず、従来どおり日本IBMがアメリカの親会社に利益を送金していれば、そもそも本件のような課税問題は生じませんでした。
――中間純粋持株会社を設け、従来の「直接配当」を「間接配当」とすることによって、その中間純粋持株会社に欠損金が計上される構造となったわけですね。
朝長 そうです。日本IBMが日本で得た利益は、原告を介してアメリカの親会社に送金されるわけですが、原告に生ずる欠損金は、このアメリカの親会社に送金される利益、すなわち、原告においてみなし配当とされる額に相当する金額となります。
要するに、日本IBMが日本で大きな利益を上げれば上げるほど、みなし配当の額が大きくなり、みなし配当の額が大きくなればなるほど、原告において日本IBM株式の譲渡損の額が大きくなる、という普通ではなかなか理解できない不思議な構造ができ上がったわけです。
利益が日本で課税されずにアメリカの親会社に移転
――通常は、損をすればするほど欠損金が大きくなるはずですが、中間に日本法人を設けて「直接配当」を「間接配当」にすれば、逆に利益を上げれば上げるほど欠損金が大きくなるという状況を創出できるわけですね。
朝長 そうですね。この日本IBMから原告に送金される利益は更にアメリカの親会社に送金されるわけですから、実質的には、日本で損金を計上してアメリカに利益を送金するのと同じ状態になります。
――そうすると、最終的には、日本IBMが日本で稼いだ利益に対して日本で課税を行えない、ということになりませんか?
朝長 そういうことになります。通期でみれば、日本からアメリカへの利益移転に課税を行い得ず、日本IBMが日本で得た利益が日本で課税を行われないままアメリカに移転する、ということになります。
「ゼロから損失を創り出した」という言い方をされる方もいらっしゃいますが、私はむしろ、「配当を損金にする状態を創り出した」と見てもよいと思っています。
こういう点からも、IBM事件は、日本から見た「国際的租税回避」と言うべきものではないかという観点から検討を行うべき事件だと思います。
会社の対応と当局の対応が錯綜
――平成18年以後、自己株式の取得が行われていないのは何故でしょうか?
18年以後も自己株式取得を行えば、同じ状態が創り出せたはずです。
朝長 そうですね。平成18年以後に自己株式取得が行われなくなったのは、同年以後、会社法によって随時配当が可能とされたことから、自己株式取得によって実質的な利益の随時配当を行う必要がなくなったこともあると思いますが、同年頃に、税務当局から自己株式取得によって欠損金を計上することを問題視されたことも影響している可能性があると考えています。
――原告への課税は、まず原告が平成20年の最初の連結納税において14年から17年までの欠損金を損金とせずに確定申告を行い、これに対し原告が行った「更正の請求」でその欠損金の損金算入が認められ、その後、税務調査でその損金算入が否認される、という異例の展開の中で行われているのですが、これも18年頃の税務調査が影響しているのでしょうか?
朝長 原告が確定申告で欠損金を損金とせずに申告と納税を行った上で、後から欠損金を損金とするように求める更正の請求を行うという異例の対応を採ったのは、原告が欠損金の損金算入を否認される可能性があると考えていたためだと思われます。
過去の税務調査で問題視されたことから、欠損金の損金算入が否認される可能性があると判断したのかもしれませんし、元々そのように判断していて、税務調査やその後の当局の感触から欠損金の損金算入が可能と判断したのかもしれません。そのあたりはよく分かりませんが、申告・納税を行った上で更正の請求をするというように、損金算入が認められなかったとしてもダメージが少なく、チャレンジし易い方法を採っていることからすると、欠損金の損金算入が絶対に大丈夫という判断をしていなかったのは間違いないと言ってよいでしょう。
――本件においては、会社の対応と当局の対応がかなり複雑に錯綜しているようですね。
朝長 そうですね。詳しいことはよく分かりませんが、他の案件とは違って、本件の場合には、お互いに数年間にわたって相手の動きを気にして見ていた、ということではないでしょうか。
更正の請求で本件の欠損金の損金算入を求めるという異例の対応が採られているということは、IBMにおいて相当な熟議が行われ、また、かなり上の役職者による判断がなされていることを示していると思います。
ヤフー・IDCF事件の影響額は本件の7分の1ですが、それでも原告の株主の会社のトップ自らがスキームを実行するのか否かの判断を下しており、その判断を仰ぐに当たっては入念な検討が行われていたと推測されます。金額が7倍にもなるIBMでも同様だったであろうと考えるのが自然でしょう。

――これだけの巨額な金額ですから、現場レベルの役職の人が意思決定できるとは思えないですよね。
朝長 本件のような意思決定を行う場合には、当局がどのような考えを持っており、どのように動くのかということが、最も重要な判断材料になります。
このため、更正の請求を行うか否かの判断に当たっては、過去の税務調査(平成15年、平成18年及び平成19年の税務調査)において、どのような資料の提出を求められ、どのような内容の指摘を受けたのかというようなことを確認するために、過去の税務調査の記録を取り寄せて確認をしたり、その後の当局の動きが分かる記事等を集めたりすることになったのではないかと思われます。
また、本件では、一旦、更正の請求を受けて当局が減額更正を行っているわけですから、その減額更正の際の当局との間のやり取り等の記録も、本件の課税を行うこととなった税務調査の際には存在していたはずです。
――どの会社でも税務調査の記録は作るものでしょうか?
朝長 上層部に報告したり、後の税務調査に備えたり、後任者に引き継いだりしないといけませんから、大きな会社はほぼ全て作っていると思います。特に、日本IBMのような子会社の場合、親会社に報告をしなければなりませんから、作らないということはまずないはずです。
――原告が「本件過去調査が行われた際、本件株式購入、本件各譲渡及び欠損金の計上について詳細に調査がなされたが、何の指摘もなかった」と主張していることからすると、何の記録もないという可能性はないのでしょうか。
朝長 その「本件過去調査」というのは、平成15年の税務調査と平成18年から始まった税務調査のことだと思いますが、「何の指摘もなかった」ということではなかったはずです。むしろ調査官は、「譲渡損の計上には問題がある」という指摘を行ったはずです。ただ、まだその欠損金を使用していなかったことから様子を見ることにしただけだったのではないかと思います。
しかし、問題は、その過去の税務調査の「内容」の如何よりも、その「記録」が把握されている気配がない、ということにあると思っています。特に、平成18年に始まった税務調査は長期にわたるものとなっていますので、各調査日毎に、調査官と会社側がどのようなやり取りをしたのかという記録等があるはずであり、それが本件においては極めて重要な証拠資料になるはずです。
前回、原告を中間純粋持株会社として置くことを決めた際の欠損金の取扱いに関する資料が見当たらないという話をさせて頂きましたが、それだけでなく、本件においては、過去の税務調査等に関する資料も見当たらないように思われます。
IBM事件においては、ヤフー・IDCF事件とは違って、「本件過去調査が行われた際、本件株式購入、本件各譲渡及び欠損金の計上について詳細に調査がなされた」ということになっていますので、各調査日毎に、調査に対応した者が調査官の言ったことと会社側の者が言ったことなどを記録した応接録、その調査の状況を上層部・親会社に報告し指示を受けたメール、そして、調査結果の報告書などが、極めて重要となります。
――しかし、お話のとおり、そのようなものは裁判資料の中には無いようですね。
そのようなものが無いということは、国側としては苦しいということでしょうか。
朝長 そうかもしれませんね。
ただ、裁判は勝ち負けも大事ですが、「真実は何か」ということも忘れてはならないことだと思っています。証拠資料が乏しい中で、真実をどのように見極めるのかということが問われる、ということではないでしょうか。
「中間純粋持株会社を置いた目的」が問われる
――国側は、原告に関して「原告の主な収入源や支出先は、日本IBM及び米国WTであって、原告はその2社の間にあっていわば資金を通過させるだけのトンネル会社的存在にすぎ(ない)」と主張しています。この点についてはどのようにお考えですか?
朝長 原告には専任の役員及び使用人はおらず、原告の役員には、米国IBMの100%子会社の日本における代表者、日本IBMの役職者の2、3名が本業と兼務して就任しています。また、原告は固有の事務所を所有しておらず、本店所在地は米国IBMの100%子会社の日本支店・日本IBMの本店の所在地と同一となっています。さらに、日本IBMとの間で経理、財務、税務等の業務の委託契約を締結し、同契約に基づく業務委託料として月額50万円を支払う一方、役員に対しては報酬を支払っておらず、人件費等の固有の経費も発生していない、とのことです。
普通、そのようなものは「トンネル」と言われても仕方がないのではないでしょうか。
――業務は全て日本IBMに委託しているようですね。
朝長 そのようですね。判決文によれば、次のように述べられていますので、原告のような法人を作ったのは日本だけのようです。
| 米国IBMは、2002年(平成14年)7月、PwCCを全世界において買収することとし、多くの国においては、PwCCの現地法人を当該国のIBMグループに属する会社に吸収合併させる形で買収がされたが、日本においては、PwCの日本法人であったPwCC株式会社から日本におけるコンサルティング業務に係る事業(同月1日時点で従業員数1650名)の譲渡を受けたマンデーを原告の100%子会社とする形(日本IBMといわゆる兄弟会社とする形)により買収がされることとなり、原告は、同年9月5日、マンデーの発行済株式の全部を取得した。マンデーは、同月18日、IBCSに商号を変更し、平成22年4月1日、日本IBMに吸収合併された(甲64、69)。 |
――仮にこの中間純粋持株会社が日本の税制のみなし配当と株式の譲渡損益の規定を利用して巨額の欠損金を計上することを目的としていたのであれば、そもそも業務はあまり発生しないでしょうね。
朝長 日本IBMと米国IBMのような会社の間に持株会社を置けば、必ず何らかの業務があり、何も業務がないというようなことはあり得ないはずですが、租税回避に当たるのか否かという観点からすると、中間に純粋持株会社を置いた主たる目的は何だったのか、ということが問われることになると思います。
――お話をまとめると、アメリカの税制に日本IBMの株式の譲渡益に課税しない特例がある一方、日本の税制に巨額のみなし配当を計上して益金不算入とするとともに巨額の株式の譲渡損を計上して損金算入とすることができる取扱いができたことから、日本に中間純粋持株会社を置いて間接的に「自己株式取得」によって配当を行うことで、その中間純粋持株会社に配当と同じ金額の欠損金を発生させ、その欠損金を連結納税に利用して日本における納税額を少なくした、ということでよろしいでしょうか。
朝長 経緯に着目すれば、そういうことでしょうね。
132条の解釈や平成13年のみなし配当の立法等に関しては、次回以降にお話しますが、先ほども申し上げたとおり、本件については、日本の税制とアメリカの税制の隙間を突いた「国際的租税回避」ではないかという観点から検討を行うべき事件だと考えています。
――有り難うございました。次回は、関係法令の解釈を交えてお話をうかがいたいと思います。
(第3回へ続く)
| 朝長英樹 ともなが ひでき 財務省主税局において、金融取引に係る法人税制の抜本改正(平成12年)・組織再編成税制の創設(平成13年)・連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。 税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。 現在、日本税制研究所 代表理事、朝長英樹税理士事務所 所長 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















