解説記事2014年08月25日 【第2特集】 検証・IBM裁判〔第4回(最終回)〕(2014年8月25日号・№559)
第2特集
立法趣旨から見て容認されるのか?
検証・IBM裁判〔第4回(最終回)〕
法人税法132条の適用が争われたIBM事件だが、地裁判決は、132条の解釈そのものが検討されたというよりも、税務当局による事実認定がことごとく否定された結果、「132条の適用も認められない」との結論に至ったものと言える。その背景にあるのが「証拠資料の不足」だが、この点について、財務省時代に本事件に関係の深い法令の創設を主導した朝長英樹税理士は、「不足していているのは租税回避の「目的」を確認することができる資料に過ぎない」と指摘する。
欠損金の発生と連結納税におけるその利用は制度設計の際に「当然に予想されていた」と主張するIBM側に対し、朝長税理士は、その主張を否定し、「予想外の問題」には132条で対処するしかないとした上で、同条の適用の有無は、行為の「目的」ではなく「結果」によって判断されるべきだと語る。
最終回となる今回は、金銭等の交付がない場合のみなし配当を廃止した法人税法24条2項の改正理由や、IBMの事例が容認された場合における租税理論への影響など、地裁判決で触れられていなかった重要な論点に迫りたい。
平成13年改正はIBMのようなケースを認めない趣旨だった
――前回は「法律鑑定意見書」(本誌558号6頁)の中の「法令の解釈」に関する部分についてお話をうかがいましたので、今回は「法令の立法」に関する部分について詳しくお話をうかがいたいと思います。この部分は地裁判決に大きな影響を与えているのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか?
朝長 この「法律鑑定意見書」を書かれた先生は、平成12年の有価証券の譲渡損益の規定の抜本改正、13年の組織再編成税制の創設とみなし配当を含む資本等取引税制の抜本改正、そして14年の連結納税制度の創設などを行った頃も政府税制調査会の委員をやっておられましたので、この部分は、極めて重要であり、当然、地裁の裁判官の判断に大きな影響を与えたものと思われます。
――原告が巨額の子会社株式譲渡損を計上する根拠とした法人税法61条の2、みなし配当を計上する根拠とした24条1項4号、そして連結納税の規定と、いずれも朝長先生が主導して創られたということですので、今回は、これらの立法に関する部分でIBM事件に関係するところを詳しくお聞きしたいと思います。
これらの改正の中で、IBM事件に一番大きく影響しているのは、やはり、平成13年の24条1項の帳簿価額基準を廃止した改正でしょうか?
朝長 そうですね。ただ、平成13年には、その他にも、みなし配当に関し、金銭等の交付がない場合のみなし配当の規定である24条2項を廃止したり、自己株式を取得した場合のみなし配当の規定である同条1項4号を創るなどの改正を行っています。これらの改正は、みなし配当に関する従来の課題を解決したり、組織再編成税制を創るために見直したりしたものですが、全てお話すると長くなってしまいますので、今回は直接IBM事件に関係する部分だけをお話ししたいと思います。
――「法律鑑定意見書」の立法に関する部分の冒頭には、次のように述べられています。
IBM事件におけるような欠損金の発生と連結納税におけるその利用は制度設計の際に「当然に予想されていた」という主張だと思いますが、これについてはどのようにお考えでしょうか?
朝長 この部分がそのような主張だとすれば、それは全く事実に反するものです。
ここで列挙されている制度はいずれも私が設計して条文案を作成させて頂いたわけですが、IBM事件のような行為を認めることを予定して税制度を創るはずがありません。
そのような主張をされるのであれば、明確な証拠を示す必要があります。
――「認めることを予定していなかった」という明確な証拠を示すことも難しいのではないでしょうか?
朝長 基本的には、証明を求められるのは「ある」と主張する側になりますので、明確な証拠の提示が必要になりますが、IBM事件のように、みなし配当と株式の譲渡損を両建てで計上することによって欠損金を発生させて税を減少させることを容認することは全く予定していないどころか、逆に、そのような行為を容認するべきでないと考えて改正を行ったことを明確に示す資料が存在します。
みなし配当における帳簿価額基準の廃止によりIBM事件が生ずることとなったわけですが、先ほども触れたとおり、その改正を行った平成13年度税制改正では、金銭等の交付がない場合のみなし配当の規定を廃止する改正も行っています。これらのみなし配当に関する改正に関しては、「法律鑑定意見書」を書かれた先生も出席された法人課税小委員会の平成12年6月2日の第7回会議で、「みなし配当に係る現行税制の論点(例)」として、主税局から説明資料を提出させて頂きました。
その説明資料には、24条2項の金銭等の交付がない場合のみなし配当を廃止するべき理由として、次のように書かせて頂いています。
――これはまさしく「帳簿価額のかさ上げによる課税逃れ」に触れたものですね。
朝長 そうです。この説明資料からも、平成13年度税制改正は、IBM事件のようなケースを容認するどころか、その反対に、そのようなケースを容認しないという改正であったことをはっきりと確認して頂けるはずです。
――この第7回会議においては、みなし配当における帳簿価額基準に関する意見は出なかったのでしょうか?
朝長 主税局からの資料の説明だけで、委員の方々からの意見は全く出ませんでした。
平成13年のみなし配当の改正については、帳簿価額基準を廃止したことでみなし配当と株式の譲渡損が両建てとなって欠損金が発生するという現象だけを見て、この改正がそのような欠損金の発生を容認する改正であったかのごとく語る方がおられますが、改正全体を眺めて頂くと直ぐに分かるとおり、この改正は、そのような現象を生じさせないようにするための改正であったと言ってもよいわけです。
24条2項の規定について「株式の帳簿価額が増額されること」による問題が存在するために廃止するとしながら、同時に、同条1項の規定について「株式の帳簿価額が増額されること」による問題を発生させようとする改正を行うというようなことがあるはずがありません。
24条1項の帳簿価額基準に関しては、そもそも利益の還元額は株主における株式の帳簿価額とは関係がないこと、そして、組織再編成税制を理論的に正しい制度として創り上げるためにはみなし配当の規定を理論的に正しい仕組みとする必要があることから、廃止したものです。
IBM事件のようなケースは、このみなし配当の帳簿価額基準の廃止の改正を奇貨として行った「租税回避」であり、税制度の「濫用」と言うべきものと考えています。
――しかし、帳簿価額基準を廃止すれば、「帳簿価額のかさ上げによる課税逃れ」が行われることになるということは、予想できたのではないでしょうか。
朝長 税制改正の際には、いろいろなケースを想定して検討を行います。帳簿価額が時価よりも低い株式を持っている者がその株式をペーパーカンパニーに移転して帳簿価額を引き上げ、みなし配当と株式の譲渡損を両建てで計上するというケースも想定の中にあったわけですが、そのようなケースでは、確かにペーパーカンパニーに欠損金が生ずるものの、株式を移転する際に、譲渡益に対する課税が行われることになりますので、そのデメリットとペーパーカンパニーに欠損金を創り出すメリットを比較衡量すると、結果的には、メリットがないわけです。
つまり、平成13年の改正当時は、IBM事件のようなケースが生ずることはないはずだ、と考えていました。
――非課税法人から株式を取得するケースやアメリカにおける「帳簿価額のかさ上げによる課税逃れ」のケースを想定されたことはなかったのでしょうか?
朝長 法人が非課税法人と取引するという特殊な場面まで想定して税制度を企画立案することまでは、現実には行っていません。通常の税制改正では、譲渡益が発生すれば課税されるという前提で企画立案を行います。アメリカにおいても、非課税法人との間の取引に関して問題が出た後に措置を講じたとのことですが、いずれの国においても、問題事案が出る前に、非課税法人や非課税措置の適用を受けることができる法人との間の取引を想定して規定を設けるということまではできていないものと思われます。まして、事前に、国境をまたがって取引が行われることまで想定し、その国における当該取引の取扱いまで調べ、その上で税制改正を行うというようなことは、まず無いはずです。
――「繰越欠損金の連結納税による利用」を「予想」していた、という指摘に関してはいかがでしょうか?
朝長 平成13年のみなし配当の規定の改正の際には、連結納税制度をどのような仕組みとするのかということは決まっていませんでしたので、IBM事件のような欠損金を連結納税で利用させることを予想するはずもありません。
また、平成14年の連結納税制度の創設の際には、そもそもIBM事件におけるような欠損金の計上を予定していませんので、そのような欠損金を連結納税で控除することを予想するはずがありません。
「帳簿価額のかさ上げ」による譲渡損を認めることは理論的に誤り
――平成13・14年の改正の際に、IBM事件におけるような欠損金の計上を認めることを予定していなかったということはよく分かりましたが、「予定していなかった」ということを理由に否認することは可能なのでしょうか?
朝長 立法時に予定していなかった事項はたくさんありますので、「予定していなかった」ということが直ちに否認理由になるわけではありません。
立法時に「予定していなかった」ということを理由にして課税が行われるものは、通常、課税上弊害があるケースです。
IBM事件に関しては、国側の主張の中に「欠損金を創出することになっている」等の話がたくさん出てきますので、ここで改めて課税上の弊害について説明する必要はないと思いますが、「帳簿価額のかさ上げ」によって計上した譲渡損を認めることは理論的に誤っているという点は、はっきりと指摘しておく必要があると思っています。
――どういうことでしょうか?
朝長 法人税は「所得」に課税を行う税ですので、「所得」があれば当然それに課税を行わなければならないわけです。「所得」があるにもかかわらず「課税を行わない」というのは理論的に誤りということになります。
――先ほど「譲渡益が発生すれば課税されるという前提で企画立案を行う」というお話がありましたが、「所得があれば課税を行う」ということが理論的に正しいという前提があるということですね。
朝長 そうですね。さらに言えば、「益金」があれば「所得」を増やし、「損金」があれば「所得」を減らすのが正しい処理ということになります。
しかし、IBM事件のケースを見てみると、原告が「帳簿価額のかさ上げ」を行った取引によって生ずる譲渡益は「所得」とはされず、「帳簿価額のかさ上げ」を行って生じた譲渡損は「所得」を減らすものとされています。
このような状態は、「所得」に課税をする税の理論からすると、明らかにおかしいわけです。
――原告は、「米国でキャピタルゲイン課税がされなかったのは、あくまで米国の税制を適用した結果にすぎず、132条の適用(日本の法人税の税負担の不当な減少)の判断とは何の関係もない」と主張していますよね。
朝長 そのような主張は、「所得」課税の理論を無視した「国際的租税回避」容認論と言わざるを得ないように思います。
そのような国際間の税制の違いを奇貨として税理論に穴をあけて税負担を減少させるような行為は「国際的租税回避」の典型であると思っています。
私は、IBM事件は株式の譲渡損の損金算入よりもみなし配当の益金不算入に問題があると考えているわけですが、今申し上げたとおり、IBM事件には、株式の譲渡損益の取扱いだけを見ても理論的に重大な問題がある、と考えています。
「予想外の問題」には132条で対処
――立法の際にそのような問題に対処するのはやはり難しいものですか?
朝長 法制度改正も森羅万象を知悉して行うということはできませんので、現実には、いろいろなところに予想もしなかったような問題が起こってきます。そのような問題を解決する手段となるのが132条のような規定です。
中里教授も、『タックスシェルター』において次のように述べておられます。
(239頁)
――IBM事件のようなケースでも、課税を「放棄」するのではなく、課税を行って「司法判断」を仰ぎ、「裁判所の活動により、一定の範囲内において正義が回復(確保)される」ことを期待する、ということですか。
朝長 そうせざるを得ないでしょうね。
ただ、中里教授も指摘されているように、近年は「日本の課税の世界は、その形式尊重主義の強さゆえ、タックスシェルターのアレンジャーにより壟断されているのが実情である」という現実を真剣に受け止めることが必要になってきていると感じます。
特に「租税回避」の判断に関しては、時代の変化に対応した判断を行うということが非常に重要になってきます。132条の適用前に適用されている個別規定は、みなし配当の規定のように、かなりの程度、時代の変化に合わせて変わってきていますが、そのような中にあって、132条の解釈だけは変えないということであれば、「租税回避」の防止において穴ができたり隙間ができたりするのは当然のことです。
132条は、同条の適用前に個別規定を適用した状態が法人税の負担を不当に減少させる結果となっているのか否かということを判断して適用するものですから、同条の解釈は、同条の適用前に適用されている個別規定の改正が行われた場合には、見直しが必要となります。結果的には、132条の解釈を変える必要はないという場合が多いものと思われますが、解釈を変えなければならない場合も当然出てくることになります。
グレゴリー判決由来の「経済合理性基準」は132条の解釈に代置できない
――「法律鑑定意見書」では、「これらの税制改正においては、個別の制限規定を設けて対処したもの以外は、税制として容認すると割り切っていた。」とも述べられていますが、この点に関しては如何でしょうか。
朝長 想定していないものについて「容認する」という割切りを行うといったことは、当然、あり得ません。
「容認すると割り切っていた」という記述は「見解」等でなく「事実関係」に関するものですから、そのような主張をするのであれば、その明確な根拠を示す必要があります。
――IBM事件のようなケースについては、事件発生当時、平成22年改正で創設された個別の防止規定が設けられていたわけではないので、容認せざるを得ないということにはならないのでしょうか。
朝長 先ほども述べましたが、そのようなことにはなりません。
租税回避について語る際に、「事業目的の原理」(Business Purpose Doctrine)を確立したと言われているアメリカのグレゴリー判決の話がよく出てきますが、このグレゴリー判決は、日本の132条のような租税回避防止規定の解釈として出されたものではなく、132条のような規定がない中で出されたものです。IBM事件に例えて言えば、みなし配当と有価証券の譲渡損益の規定はあるが租税回避防止規定はない、という状態で出された判決ということです。
このグレゴリー判決に関して、中里教授は、『タックスシェルター』の中で次のように述べておられます。
(229頁)
――みなし配当と有価証券の譲渡損益の規定の「特有の趣旨・目的」が重要で、「当該規定が本来予定していないような(すなわち、当該規定の射程範囲の外にあると思われる)行為についてまで、課税の減免を認める必要はない」ということであり、「それは、法律解釈の方法としていわば当然のこと」であると。
朝長 そうです。
先ほど申し上げたとおり、原告が適用したみなし配当の規定の改正の趣旨・目的は、みなし配当と株式の譲渡損の両建て計上による欠損金の発生を認めるということではなく、逆にそのようなものを認めない、というものですから、当該規定の解釈も当然「そのようなものを認める必要はない」ということになるはずです。
13年の改正当時に、「IBM事件のようなケースを認めるつもりか?」と聞かれたとしたら、間違いなく、「そのようなものは租税回避として否認するべきである」と答えたはずです。
――日本の場合には、グレゴリー判決が出された時のアメリカとは異なり、132条が存在しますよね。
朝長 そうです。132条が存在しますから、まず、同条を文理に従い趣旨・目的を踏まえて正しく解釈することが必要となります。
私もグレゴリー判決の解釈方法は日本でも適用できると思っていますが、それを日本で適用するという場合には、グレゴリー判決の解釈方法を正しく適用することに留意しなければなりません。つまり、グレゴリー判決が出された時、アメリカには132条に相当する規定は存在していなかったわけですから、グレゴリー判決の解釈方法を日本で適用するという場合には、132条とは関係ないところで適用する必要があります。グレゴリー判決の解釈方法を日本で適用するということは、グレゴリー判決の「事業目的の原理」を132条の解釈に代置するということではありません。「解釈方法」と「解釈の内容」とを混同してはいけません。
グレゴリー判決の「事業目的の原理」の射程と法人税法132条の射程は、右の図のような関係となるはずです。
――「経済合理性基準」はグレゴリー判決に由来するものとして語られることが多いように思いますが、「経済合理性基準」を132条の解釈に代置してはいけない、ということですね。
朝長 そうです。そういうことをすると、132条を正しく解釈することができなくなってしまいます。
日本とは前提が異なるアメリカにおける判決を日本に持ち込んで日本の条文を解釈しようとすれば、日本の条文の解釈が歪んでしまうことになりかねません。
IBM事件に関しては、132条の条文を文理に即して正しく解釈し、趣旨・目的を正しく踏まえて解釈すればよいわけで、「結果」が近年の「社会通念」や「常識」に照らして「不当」ということになるのか否かという点のみが判断を要するところだと考えています。
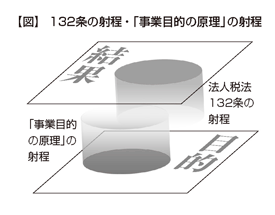
昭和25年の132条の改正担当者も「否認する」と判断したはず
――132条を現在のような規定とした昭和25年改正の立法担当者に、当時IBM事件のようなケースが生じたと仮定して「どうするべきか」と尋ねたとしたら、どのような答えが返ってくるのでしょうか?
朝長 「認める」という答えが返ってくることは、あり得ないと考えられます。「132条は当然そのようなものにも適用してよい規定になっている」という答えが返ってくるはずです。
それは何故かというと、132条の条文は、同条の適用前に適用されている個別規定の「濫用」や「潜脱」によって法人税の負担を減少させる結果となっているものを否認する規定を創設しようとした場合に、立法者によって立案されるであろう文言そのものと言ってもよいからです。
――どういうことでしょうか?
朝長 仮に、「経済合理性基準」によって法人税の負担を減少させるものを否認する規定を創設しようとした場合にどうなるかということを考えてみると、理解し易いと思います。そもそも法人税法は「経済合理性」のないものに課税を行い、「経済合理性」のあるものには課税を行わないという考え方を採っているわけではないため、132条の適用前に適用されている個別規定にも「経済合理性」という観点が存在しないこと、そして、「目的」の有無を判断基準とする経済合理性基準に基づいて否認規定を創設するとしたら、「結果」という用語を用いることができないことから、現在の132条のような文言になることはあり得ません。現在の132条のような文言で「経済合理性基準」によって否認することを前提にした否認規定の条文案を創って内閣法制局に持って行ったとしても、通してもらうことができないのは、明らかです。
――前回、「昭和25年改正後の規定は、税制度の「濫用」「潜脱」などにも適用されていた」という話をお聞きしましたが、そうであれば、昭和25年改正時と実質的に変わっていない現在の132条を税制度の「濫用」「潜脱」に適用することに障害はないと思うのですが、この点はいかがでしょうか?
朝長 132条については、昭和25年の改正後も何度か細かな字句修正や条文番号変更が行われて現在に至っているわけですが、実質的な内容の変更はないと言ってよい状態です。
昭和25年当時の規定に関しては、通達(昭和25直法1-100「355」)でどのようなものに適用されるのかということが例示されていました。その通達では、過大出資、高価買入、低価譲渡、寄附金、無収益資産、過大給与、用益贈与、過大料率賃貸借、不良債権の肩代り、債務の無償引受が挙げられていました。もちろん、これら以外にも適用を受けるものはあったわけで、当時の規定はかなり広くさまざまなケースに適用されていたことが分かります。抜かないことに意味がある“伝家の宝刀”として創られたものではないということです。
「租税回避」に当たるのか否かという問題には、その性質上、さまざまなものがあり、企業の経済活動の範囲や内容、私法や企業会計、税法、そして「社会通念」や「常識」などが変わってくると、当然、その問題が生ずる場面や内容なども変わってきますので、「租税回避」となるのか否かを単純な基準だけで判断するということには、そもそも無理があります。
もっとも、仮に、132条の規定を正しく解釈した場合に同条の適用対象の判断基準が「経済合理性」基準と「濫用」「潜脱」基準のどちらとなるかというように「二者択一」で質問されたとすれば、明らかに後者と答えることになる、と考えています。
――当時の通達はその後どうなったのですか?
朝長 昭和44年改正で、「法令に規定されており、または法令の解釈上疑義がなく、もしくは条理上明らかであるため、特に通達として定める必要がないと認められた」という理由で廃止されています。
このため、現在は個別に判断せざるを得ないということになります。
地裁判決では、132条の判断基準が明確に意識されず
朝長 第1回のインタビューの際にも触れさせて頂きましたが、IBM事件では、証拠資料の把握に大きな困難が伴ったものと推測されます。
原告を中間純粋持株会社として置くことを決めた際の欠損金の取扱いに関する資料、過去の税務調査の際の日々の応接録―原告においては「応答録」と呼んでいるようですが―、それらの応接録を添付して上層部・親会社等に送るメール、税務調査について上層部・親会社に報告したメールや報告書、税務調査への対応について上層部・親会社から指示を受けたメール、弁護士・会計士・税理士に質問をしたり助言を求めたりするメールとそれらの返信メール、各税務調査の結果の報告書など、ヤフー・IDCF事件において事実関係の把握に重要な役割を果たした資料がかなり不足しているように見受けられます。
これには、アメリカでスキームの企画立案が行われたことも影響していると推測されます
――証拠の不足に関しては、新聞報道(日本経済新聞(2014.5.29))でも、アメリカで資料収集ができなかったと伝えられていましたね。
朝長 中里教授も、『タックスシェルター』において、次のような指摘をしておられます。
(277頁)
――「日本で企画立案が行われた租税回避」に対する税務調査と「外国で企画立案が行われた租税回避」に対する税務調査について、国側に同じように立証責任が課されるとすると、「租税回避の企画立案は外国でやればよい」ということにはならないでしょうか?
この点は、実務に大きな影響を与える可能性があるように思います。
朝長 そうですね。日本企業は「租税回避」と言われ易いが、外資系企業は言われにくい、ということになるおそれもあります。
このように、IBM事件ではスキームの企画立案が外国で行われていることから「証拠資料の不足」という難問が残り、これをどのように考えるのかということが大きな争点とならざるを得ないわけですが、これは事実関係に関するものであることから、多くの方は、如何ともしがたいと感じるかも知れません。
しかし、私は、この争点には出口があると考えています。
――具体的に教えて下さい。
朝長 不足していると言われている証拠資料が何かというと、それは、「租税回避」の「目的」を確認することができる資料であると思われます。
しかし、既に繰り返し述べてきたとおり、132条は、「目的」ではなく「結果」で「不当」か否かを判断するということになっているわけです。
「目的」が「租税回避」であったことを確認することができる資料があればそれに越したことはないのですが、既に述べたとおり、132条は、「目的」の事実確認によって適用の有無を判断する規定ではありません。
一審の判決は、この132条の判断基準に関する重要な部分を看過して、「目的」の事実確認によって、「……とまでは言えない」というような判断をしたもののように見受けられます。
――なるほど。そもそも一審では、132条が「目的」ではなく「結果」で判断する規定となっているということが明確に意識されていなかったため、目を向ける所がずれてしまっている感じはしますね。
朝長 昭和25年の改正を知り、「結果」という文言が用いられている条文を読み直してみると、誰もがそういう印象を受けると思います。
IBM事件は、法令の規定を正しく解釈することがいかに大事かということを示している典型的な案件だと感じています。
法律鑑定意見書の筆者も「否認するべき」と主張?
――「法律鑑定意見書」には、次のように「IBM事件に132条を適用することに違和感がある」という旨の記述もありますが、この主張についてはどのようにお考えですか?
朝長 「法律鑑定意見書」を書かれた先生も、平成13年当時はIBM事件のようなケースを容認するべきであると考えておられたわけではなく、反対に、そのようなケースは132条によって否認するべきである、と考えておられたはずです。
――そう考える具体的な根拠を教えて頂けないでしょうか。
朝長 平成13年度税制改正が終わった後の平成13年6月26日の第14回法人課税小委員会において、連結納税制度の創設の適否に関する議論の際に、ある委員の方から租税回避を懸念する次のような発言がありました。
このような発言があったことによるものと思われますが、「法律鑑定意見書」を書かれた先生から、平成13年7月24日の第15回法人課税小委員会の際に、次のような内容のペーパーが出されています。ただし、このペーパーに記載されていることは、連結納税制度の創設の適否に関するものではなく、租税回避防止の一般論の話であったことから、これに関する議論は行われませんでした。
――これはかなり具体的な記述ですね。IBM事件に近いことを指摘しているように見えます。
朝長 「帳簿価額が引き上げられる場合においても、濫用がおこりえ(る)」という観点に立って、「非課税の法人から資産の移転を受けても帳簿価額は引き上げられないこと」を「確認しておく」ことが必要であり、「同族会社の行為計算否認規定を拡大して、外国法人である同族会社の行為計算により所得税、法人税、相続税などが不当に減少させられた場合」にも否認を可能にするべきである、と主張されています。
このペーパーは、IBM事件のようなケースが日本でも発生することを予言し、そのようなケースは132条で否認するべきであると主張したものと捉えてもよい内容になっていると思います。
IBM事件は22年改正が想定するケースよりも租税回避の性格が強い
――「法律鑑定意見書」の最後には次のような見解が述べられていますが、これについてはどのように考えておられますか?
朝長 前回、中里教授の『タックスシェルター』において「課税逃れの否認規定の立法を行わないと否認できないということではない」という主張が明確に述べられている部分を引用して話をさせて頂いたとおりです(本誌558号13頁)。
平成22年度税制改正では、本来は、株式の譲渡損益を計上させないとするのではなく、配当の益金不算入を認めないこととするべきであったと考えていますが、いずれにせよ、改正の趣旨は、IBM事件のようなケースを「租税回避」と捉えた上で、欠損金を生じさせないようにしたものです。
この改正は、改正前のIBM事件のようなケースを容認するべきであるということではなく、逆に、そのようなケースは「租税回避」として否認するべきであるという前提に立って行われたものであることが明らかです。仮に、容認するべきであるという前提に立ってこの改正が行われたということであれば、国は原告に対する更正処分を取り消さなければなりません。
――IBM事件のようなケースを否認するために、完全支配関係にある法人間の自己株式の買取り等の場合に株式の譲渡損益を計上させないという個別の租税回避防止規定を創ったということですよね。
朝長 先ほど申し上げたとおり、私は、みなし配当に関する22年の改正の内容には賛成しませんが、IBM事件のようなケースを「租税回避」として否認することは、当然、必要であると考えています。
IBM事件は、株式の譲渡損益を計上させない改正に繋がったことから、この改正との関係ばかりが話題になりますが、22年におけるもう一つの改正である「自己株式の買取り予定取得の場合のみなし配当の益金算入」という租税回避の防止の措置(法法23③)との関係にも注目しておく必要があります。
この措置は、株式を譲渡する者がどのような課税を受けるかということとは関係なく適用されます。このため、株式を譲渡した者が巨額の譲渡益を計上し多額の納税を行っているとしても、この措置が適用され、みなし配当が益金算入されます。このように、この措置は、たとえ株式を譲渡した者が譲渡益について納税を行っていても、その株式を取得して発行会社に買い取らせる者におけるみなし配当と譲渡損の両建て計上を「租税回避」と捉え、みなし配当の益金不算入を認めないとしたものです。しかし、IBM事件では、株式を譲渡する者は株式の譲渡益の計上さえも行っていません。
このような点からすれば、IBM事件は、この措置が想定する「租税回避」の状態よりも更に「租税回避」の性格が強いと言えます。
実務家と研究者の双方に非常に大きな影響
――4回にわたる本インタビューは、「租税回避」というものをどのように捉えるべきか、また、OECDや政府税調でも検討されている「国際的租税回避」への対処、税務調査への対応などについて、非常に示唆に富んだものとなりました。「IBM事件=現行制度には関係がない事件」という認識が変わった読者も多いと思います。
朝長 これまで述べてきたように、この事件について正しい判断が下されるかどうかは、みなし配当の規定である24条1項の平成13年の改正の趣旨・目的を正しく理解すること、「租税回避」の包括的な防止規定である132条の昭和25年の改正の趣旨・目的を正しく理解すること、同条の規定を正しく文理解釈すること、そして、「結果」を近年の「社会通念」や「常識」に照らして適切に判断することにかかっていると思います。
ヤフー事件では、被合併法人において実際に発生した欠損金を控除してよいのか否かが争われていますが、IBM事件においては、IBMが日本の事業で損をしたわけではないにもかかわらず、「欠損金」を計上して法人税額を減少させています。また、アメリカの親会社に対する利益の配当が損金となる状態にもなっています。IBM事件のこのような「結果」を「社会通念」や「常識」で判断すると、IBM事件は、ヤフー事件よりも明らかな「租税回避」ということになると感じています。
――今回のインタビューは、実務家と研究者の双方に非常に大きな影響を与えることになるものと思います。
非常に貴重な話をお聞かせ頂き、大変有り難うございました。高裁判決が出ましたら、また話をお聞かせ下さい。 (了)
立法趣旨から見て容認されるのか?
検証・IBM裁判〔第4回(最終回)〕
法人税法132条の適用が争われたIBM事件だが、地裁判決は、132条の解釈そのものが検討されたというよりも、税務当局による事実認定がことごとく否定された結果、「132条の適用も認められない」との結論に至ったものと言える。その背景にあるのが「証拠資料の不足」だが、この点について、財務省時代に本事件に関係の深い法令の創設を主導した朝長英樹税理士は、「不足していているのは租税回避の「目的」を確認することができる資料に過ぎない」と指摘する。
欠損金の発生と連結納税におけるその利用は制度設計の際に「当然に予想されていた」と主張するIBM側に対し、朝長税理士は、その主張を否定し、「予想外の問題」には132条で対処するしかないとした上で、同条の適用の有無は、行為の「目的」ではなく「結果」によって判断されるべきだと語る。
最終回となる今回は、金銭等の交付がない場合のみなし配当を廃止した法人税法24条2項の改正理由や、IBMの事例が容認された場合における租税理論への影響など、地裁判決で触れられていなかった重要な論点に迫りたい。
平成13年改正はIBMのようなケースを認めない趣旨だった
――前回は「法律鑑定意見書」(本誌558号6頁)の中の「法令の解釈」に関する部分についてお話をうかがいましたので、今回は「法令の立法」に関する部分について詳しくお話をうかがいたいと思います。この部分は地裁判決に大きな影響を与えているのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか?
朝長 この「法律鑑定意見書」を書かれた先生は、平成12年の有価証券の譲渡損益の規定の抜本改正、13年の組織再編成税制の創設とみなし配当を含む資本等取引税制の抜本改正、そして14年の連結納税制度の創設などを行った頃も政府税制調査会の委員をやっておられましたので、この部分は、極めて重要であり、当然、地裁の裁判官の判断に大きな影響を与えたものと思われます。
――原告が巨額の子会社株式譲渡損を計上する根拠とした法人税法61条の2、みなし配当を計上する根拠とした24条1項4号、そして連結納税の規定と、いずれも朝長先生が主導して創られたということですので、今回は、これらの立法に関する部分でIBM事件に関係するところを詳しくお聞きしたいと思います。
これらの改正の中で、IBM事件に一番大きく影響しているのは、やはり、平成13年の24条1項の帳簿価額基準を廃止した改正でしょうか?
朝長 そうですね。ただ、平成13年には、その他にも、みなし配当に関し、金銭等の交付がない場合のみなし配当の規定である24条2項を廃止したり、自己株式を取得した場合のみなし配当の規定である同条1項4号を創るなどの改正を行っています。これらの改正は、みなし配当に関する従来の課題を解決したり、組織再編成税制を創るために見直したりしたものですが、全てお話すると長くなってしまいますので、今回は直接IBM事件に関係する部分だけをお話ししたいと思います。
――「法律鑑定意見書」の立法に関する部分の冒頭には、次のように述べられています。
| このような事象(みなし配当の計算方式の改正に伴う有価証券譲渡損失の発生、グループ内取引による繰越欠損金の連結納税による利用)は、組織再編税制、連結納税制度といった新たな税制の制度設計をする際に、そのような効果が生じることが当然に予想されていたものである。 |
朝長 この部分がそのような主張だとすれば、それは全く事実に反するものです。
ここで列挙されている制度はいずれも私が設計して条文案を作成させて頂いたわけですが、IBM事件のような行為を認めることを予定して税制度を創るはずがありません。
そのような主張をされるのであれば、明確な証拠を示す必要があります。
――「認めることを予定していなかった」という明確な証拠を示すことも難しいのではないでしょうか?
朝長 基本的には、証明を求められるのは「ある」と主張する側になりますので、明確な証拠の提示が必要になりますが、IBM事件のように、みなし配当と株式の譲渡損を両建てで計上することによって欠損金を発生させて税を減少させることを容認することは全く予定していないどころか、逆に、そのような行為を容認するべきでないと考えて改正を行ったことを明確に示す資料が存在します。
みなし配当における帳簿価額基準の廃止によりIBM事件が生ずることとなったわけですが、先ほども触れたとおり、その改正を行った平成13年度税制改正では、金銭等の交付がない場合のみなし配当の規定を廃止する改正も行っています。これらのみなし配当に関する改正に関しては、「法律鑑定意見書」を書かれた先生も出席された法人課税小委員会の平成12年6月2日の第7回会議で、「みなし配当に係る現行税制の論点(例)」として、主税局から説明資料を提出させて頂きました。
その説明資料には、24条2項の金銭等の交付がない場合のみなし配当を廃止するべき理由として、次のように書かせて頂いています。
| ○ 資産の交付がない場合のみなし配当は、受取配当等の益金不算入の対象となり課税対象とならない一方で、そのみなし配当相当額だけ株式の帳簿価額が増額されることから、その株式の時価法による評価益の過少計上や評価損の計上あるいは譲渡をした場合の譲渡益の過少計上や譲渡損の計上を通じて課税所得を減少させる結果となる。 |
朝長 そうです。この説明資料からも、平成13年度税制改正は、IBM事件のようなケースを容認するどころか、その反対に、そのようなケースを容認しないという改正であったことをはっきりと確認して頂けるはずです。
――この第7回会議においては、みなし配当における帳簿価額基準に関する意見は出なかったのでしょうか?
朝長 主税局からの資料の説明だけで、委員の方々からの意見は全く出ませんでした。
平成13年のみなし配当の改正については、帳簿価額基準を廃止したことでみなし配当と株式の譲渡損が両建てとなって欠損金が発生するという現象だけを見て、この改正がそのような欠損金の発生を容認する改正であったかのごとく語る方がおられますが、改正全体を眺めて頂くと直ぐに分かるとおり、この改正は、そのような現象を生じさせないようにするための改正であったと言ってもよいわけです。
24条2項の規定について「株式の帳簿価額が増額されること」による問題が存在するために廃止するとしながら、同時に、同条1項の規定について「株式の帳簿価額が増額されること」による問題を発生させようとする改正を行うというようなことがあるはずがありません。
24条1項の帳簿価額基準に関しては、そもそも利益の還元額は株主における株式の帳簿価額とは関係がないこと、そして、組織再編成税制を理論的に正しい制度として創り上げるためにはみなし配当の規定を理論的に正しい仕組みとする必要があることから、廃止したものです。
IBM事件のようなケースは、このみなし配当の帳簿価額基準の廃止の改正を奇貨として行った「租税回避」であり、税制度の「濫用」と言うべきものと考えています。
――しかし、帳簿価額基準を廃止すれば、「帳簿価額のかさ上げによる課税逃れ」が行われることになるということは、予想できたのではないでしょうか。
朝長 税制改正の際には、いろいろなケースを想定して検討を行います。帳簿価額が時価よりも低い株式を持っている者がその株式をペーパーカンパニーに移転して帳簿価額を引き上げ、みなし配当と株式の譲渡損を両建てで計上するというケースも想定の中にあったわけですが、そのようなケースでは、確かにペーパーカンパニーに欠損金が生ずるものの、株式を移転する際に、譲渡益に対する課税が行われることになりますので、そのデメリットとペーパーカンパニーに欠損金を創り出すメリットを比較衡量すると、結果的には、メリットがないわけです。
つまり、平成13年の改正当時は、IBM事件のようなケースが生ずることはないはずだ、と考えていました。
――非課税法人から株式を取得するケースやアメリカにおける「帳簿価額のかさ上げによる課税逃れ」のケースを想定されたことはなかったのでしょうか?
朝長 法人が非課税法人と取引するという特殊な場面まで想定して税制度を企画立案することまでは、現実には行っていません。通常の税制改正では、譲渡益が発生すれば課税されるという前提で企画立案を行います。アメリカにおいても、非課税法人との間の取引に関して問題が出た後に措置を講じたとのことですが、いずれの国においても、問題事案が出る前に、非課税法人や非課税措置の適用を受けることができる法人との間の取引を想定して規定を設けるということまではできていないものと思われます。まして、事前に、国境をまたがって取引が行われることまで想定し、その国における当該取引の取扱いまで調べ、その上で税制改正を行うというようなことは、まず無いはずです。
――「繰越欠損金の連結納税による利用」を「予想」していた、という指摘に関してはいかがでしょうか?
朝長 平成13年のみなし配当の規定の改正の際には、連結納税制度をどのような仕組みとするのかということは決まっていませんでしたので、IBM事件のような欠損金を連結納税で利用させることを予想するはずもありません。
また、平成14年の連結納税制度の創設の際には、そもそもIBM事件におけるような欠損金の計上を予定していませんので、そのような欠損金を連結納税で控除することを予想するはずがありません。
「帳簿価額のかさ上げ」による譲渡損を認めることは理論的に誤り
――平成13・14年の改正の際に、IBM事件におけるような欠損金の計上を認めることを予定していなかったということはよく分かりましたが、「予定していなかった」ということを理由に否認することは可能なのでしょうか?
朝長 立法時に予定していなかった事項はたくさんありますので、「予定していなかった」ということが直ちに否認理由になるわけではありません。
立法時に「予定していなかった」ということを理由にして課税が行われるものは、通常、課税上弊害があるケースです。
IBM事件に関しては、国側の主張の中に「欠損金を創出することになっている」等の話がたくさん出てきますので、ここで改めて課税上の弊害について説明する必要はないと思いますが、「帳簿価額のかさ上げ」によって計上した譲渡損を認めることは理論的に誤っているという点は、はっきりと指摘しておく必要があると思っています。
――どういうことでしょうか?
朝長 法人税は「所得」に課税を行う税ですので、「所得」があれば当然それに課税を行わなければならないわけです。「所得」があるにもかかわらず「課税を行わない」というのは理論的に誤りということになります。
――先ほど「譲渡益が発生すれば課税されるという前提で企画立案を行う」というお話がありましたが、「所得があれば課税を行う」ということが理論的に正しいという前提があるということですね。
朝長 そうですね。さらに言えば、「益金」があれば「所得」を増やし、「損金」があれば「所得」を減らすのが正しい処理ということになります。
しかし、IBM事件のケースを見てみると、原告が「帳簿価額のかさ上げ」を行った取引によって生ずる譲渡益は「所得」とはされず、「帳簿価額のかさ上げ」を行って生じた譲渡損は「所得」を減らすものとされています。
このような状態は、「所得」に課税をする税の理論からすると、明らかにおかしいわけです。
――原告は、「米国でキャピタルゲイン課税がされなかったのは、あくまで米国の税制を適用した結果にすぎず、132条の適用(日本の法人税の税負担の不当な減少)の判断とは何の関係もない」と主張していますよね。
朝長 そのような主張は、「所得」課税の理論を無視した「国際的租税回避」容認論と言わざるを得ないように思います。
そのような国際間の税制の違いを奇貨として税理論に穴をあけて税負担を減少させるような行為は「国際的租税回避」の典型であると思っています。
私は、IBM事件は株式の譲渡損の損金算入よりもみなし配当の益金不算入に問題があると考えているわけですが、今申し上げたとおり、IBM事件には、株式の譲渡損益の取扱いだけを見ても理論的に重大な問題がある、と考えています。
「予想外の問題」には132条で対処
――立法の際にそのような問題に対処するのはやはり難しいものですか?
朝長 法制度改正も森羅万象を知悉して行うということはできませんので、現実には、いろいろなところに予想もしなかったような問題が起こってきます。そのような問題を解決する手段となるのが132条のような規定です。
中里教授も、『タックスシェルター』において次のように述べておられます。
| まず、第一に認識しておかなければならないことは、租税法規をどのように精密なかたちで制定しようが、実態と形式の乖離を利用した課税逃れは可能であるという点である。その意味で、「欠陥」のない租税法規は存在しないのである。 では、そのような欠陥を利用した課税逃れが行われた場合には、課税庁は、具体的妥当性を断念して、必ず課税を放棄しなければならないのであろうか。答は否であろう。具体的妥当性を確保するために司法権が存在するのであり、裁判所の活動により、一定の範囲内において正義が回復(確保)されるのである。具体的な妥当性の確保を行わないということは、司法の役割の自己放棄に他ならない。 日本の課税の世界は、その形式尊重主義の強さゆえ、タックスシェルターのアレンジャーにより壟断されているのが実情である。 |
――IBM事件のようなケースでも、課税を「放棄」するのではなく、課税を行って「司法判断」を仰ぎ、「裁判所の活動により、一定の範囲内において正義が回復(確保)される」ことを期待する、ということですか。
朝長 そうせざるを得ないでしょうね。
ただ、中里教授も指摘されているように、近年は「日本の課税の世界は、その形式尊重主義の強さゆえ、タックスシェルターのアレンジャーにより壟断されているのが実情である」という現実を真剣に受け止めることが必要になってきていると感じます。
特に「租税回避」の判断に関しては、時代の変化に対応した判断を行うということが非常に重要になってきます。132条の適用前に適用されている個別規定は、みなし配当の規定のように、かなりの程度、時代の変化に合わせて変わってきていますが、そのような中にあって、132条の解釈だけは変えないということであれば、「租税回避」の防止において穴ができたり隙間ができたりするのは当然のことです。
132条は、同条の適用前に個別規定を適用した状態が法人税の負担を不当に減少させる結果となっているのか否かということを判断して適用するものですから、同条の解釈は、同条の適用前に適用されている個別規定の改正が行われた場合には、見直しが必要となります。結果的には、132条の解釈を変える必要はないという場合が多いものと思われますが、解釈を変えなければならない場合も当然出てくることになります。
グレゴリー判決由来の「経済合理性基準」は132条の解釈に代置できない
――「法律鑑定意見書」では、「これらの税制改正においては、個別の制限規定を設けて対処したもの以外は、税制として容認すると割り切っていた。」とも述べられていますが、この点に関しては如何でしょうか。
朝長 想定していないものについて「容認する」という割切りを行うといったことは、当然、あり得ません。
「容認すると割り切っていた」という記述は「見解」等でなく「事実関係」に関するものですから、そのような主張をするのであれば、その明確な根拠を示す必要があります。
――IBM事件のようなケースについては、事件発生当時、平成22年改正で創設された個別の防止規定が設けられていたわけではないので、容認せざるを得ないということにはならないのでしょうか。
朝長 先ほども述べましたが、そのようなことにはなりません。
租税回避について語る際に、「事業目的の原理」(Business Purpose Doctrine)を確立したと言われているアメリカのグレゴリー判決の話がよく出てきますが、このグレゴリー判決は、日本の132条のような租税回避防止規定の解釈として出されたものではなく、132条のような規定がない中で出されたものです。IBM事件に例えて言えば、みなし配当と有価証券の譲渡損益の規定はあるが租税回避防止規定はない、という状態で出された判決ということです。
このグレゴリー判決に関して、中里教授は、『タックスシェルター』の中で次のように述べておられます。
| 私も、金子名誉教授にしたがって、グレゴリー判決に示された解釈方法は、日本においても適用可能であると考える。当然のことではあるが、各種の課税減免規定にはそれぞれ特有の趣旨・目的がある。その場合に、当該規定を、その立法趣旨にしたがって解釈するのは、自然なことである。したがって、当該規定が本来予定していないような(すなわち、当該規定の射程範囲の外にあると思われる)行為についてまで、課税の減免を認める必要はないということになろう。それは、法律解釈の方法としていわば当然のことであり、このような解釈を個別的な法律規定が存在しない場合に行うことは租税法律主義に反するといった考え方は、成立しえないものと思われる。 |
――みなし配当と有価証券の譲渡損益の規定の「特有の趣旨・目的」が重要で、「当該規定が本来予定していないような(すなわち、当該規定の射程範囲の外にあると思われる)行為についてまで、課税の減免を認める必要はない」ということであり、「それは、法律解釈の方法としていわば当然のこと」であると。
朝長 そうです。
先ほど申し上げたとおり、原告が適用したみなし配当の規定の改正の趣旨・目的は、みなし配当と株式の譲渡損の両建て計上による欠損金の発生を認めるということではなく、逆にそのようなものを認めない、というものですから、当該規定の解釈も当然「そのようなものを認める必要はない」ということになるはずです。
13年の改正当時に、「IBM事件のようなケースを認めるつもりか?」と聞かれたとしたら、間違いなく、「そのようなものは租税回避として否認するべきである」と答えたはずです。
――日本の場合には、グレゴリー判決が出された時のアメリカとは異なり、132条が存在しますよね。
朝長 そうです。132条が存在しますから、まず、同条を文理に従い趣旨・目的を踏まえて正しく解釈することが必要となります。
私もグレゴリー判決の解釈方法は日本でも適用できると思っていますが、それを日本で適用するという場合には、グレゴリー判決の解釈方法を正しく適用することに留意しなければなりません。つまり、グレゴリー判決が出された時、アメリカには132条に相当する規定は存在していなかったわけですから、グレゴリー判決の解釈方法を日本で適用するという場合には、132条とは関係ないところで適用する必要があります。グレゴリー判決の解釈方法を日本で適用するということは、グレゴリー判決の「事業目的の原理」を132条の解釈に代置するということではありません。「解釈方法」と「解釈の内容」とを混同してはいけません。
グレゴリー判決の「事業目的の原理」の射程と法人税法132条の射程は、右の図のような関係となるはずです。
――「経済合理性基準」はグレゴリー判決に由来するものとして語られることが多いように思いますが、「経済合理性基準」を132条の解釈に代置してはいけない、ということですね。
朝長 そうです。そういうことをすると、132条を正しく解釈することができなくなってしまいます。
日本とは前提が異なるアメリカにおける判決を日本に持ち込んで日本の条文を解釈しようとすれば、日本の条文の解釈が歪んでしまうことになりかねません。
IBM事件に関しては、132条の条文を文理に即して正しく解釈し、趣旨・目的を正しく踏まえて解釈すればよいわけで、「結果」が近年の「社会通念」や「常識」に照らして「不当」ということになるのか否かという点のみが判断を要するところだと考えています。
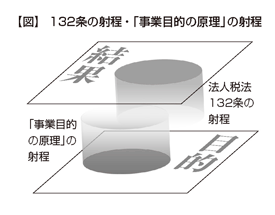
昭和25年の132条の改正担当者も「否認する」と判断したはず
――132条を現在のような規定とした昭和25年改正の立法担当者に、当時IBM事件のようなケースが生じたと仮定して「どうするべきか」と尋ねたとしたら、どのような答えが返ってくるのでしょうか?
朝長 「認める」という答えが返ってくることは、あり得ないと考えられます。「132条は当然そのようなものにも適用してよい規定になっている」という答えが返ってくるはずです。
それは何故かというと、132条の条文は、同条の適用前に適用されている個別規定の「濫用」や「潜脱」によって法人税の負担を減少させる結果となっているものを否認する規定を創設しようとした場合に、立法者によって立案されるであろう文言そのものと言ってもよいからです。
――どういうことでしょうか?
朝長 仮に、「経済合理性基準」によって法人税の負担を減少させるものを否認する規定を創設しようとした場合にどうなるかということを考えてみると、理解し易いと思います。そもそも法人税法は「経済合理性」のないものに課税を行い、「経済合理性」のあるものには課税を行わないという考え方を採っているわけではないため、132条の適用前に適用されている個別規定にも「経済合理性」という観点が存在しないこと、そして、「目的」の有無を判断基準とする経済合理性基準に基づいて否認規定を創設するとしたら、「結果」という用語を用いることができないことから、現在の132条のような文言になることはあり得ません。現在の132条のような文言で「経済合理性基準」によって否認することを前提にした否認規定の条文案を創って内閣法制局に持って行ったとしても、通してもらうことができないのは、明らかです。
――前回、「昭和25年改正後の規定は、税制度の「濫用」「潜脱」などにも適用されていた」という話をお聞きしましたが、そうであれば、昭和25年改正時と実質的に変わっていない現在の132条を税制度の「濫用」「潜脱」に適用することに障害はないと思うのですが、この点はいかがでしょうか?
朝長 132条については、昭和25年の改正後も何度か細かな字句修正や条文番号変更が行われて現在に至っているわけですが、実質的な内容の変更はないと言ってよい状態です。
昭和25年当時の規定に関しては、通達(昭和25直法1-100「355」)でどのようなものに適用されるのかということが例示されていました。その通達では、過大出資、高価買入、低価譲渡、寄附金、無収益資産、過大給与、用益贈与、過大料率賃貸借、不良債権の肩代り、債務の無償引受が挙げられていました。もちろん、これら以外にも適用を受けるものはあったわけで、当時の規定はかなり広くさまざまなケースに適用されていたことが分かります。抜かないことに意味がある“伝家の宝刀”として創られたものではないということです。
「租税回避」に当たるのか否かという問題には、その性質上、さまざまなものがあり、企業の経済活動の範囲や内容、私法や企業会計、税法、そして「社会通念」や「常識」などが変わってくると、当然、その問題が生ずる場面や内容なども変わってきますので、「租税回避」となるのか否かを単純な基準だけで判断するということには、そもそも無理があります。
もっとも、仮に、132条の規定を正しく解釈した場合に同条の適用対象の判断基準が「経済合理性」基準と「濫用」「潜脱」基準のどちらとなるかというように「二者択一」で質問されたとすれば、明らかに後者と答えることになる、と考えています。
――当時の通達はその後どうなったのですか?
朝長 昭和44年改正で、「法令に規定されており、または法令の解釈上疑義がなく、もしくは条理上明らかであるため、特に通達として定める必要がないと認められた」という理由で廃止されています。
このため、現在は個別に判断せざるを得ないということになります。
地裁判決では、132条の判断基準が明確に意識されず
朝長 第1回のインタビューの際にも触れさせて頂きましたが、IBM事件では、証拠資料の把握に大きな困難が伴ったものと推測されます。
原告を中間純粋持株会社として置くことを決めた際の欠損金の取扱いに関する資料、過去の税務調査の際の日々の応接録―原告においては「応答録」と呼んでいるようですが―、それらの応接録を添付して上層部・親会社等に送るメール、税務調査について上層部・親会社に報告したメールや報告書、税務調査への対応について上層部・親会社から指示を受けたメール、弁護士・会計士・税理士に質問をしたり助言を求めたりするメールとそれらの返信メール、各税務調査の結果の報告書など、ヤフー・IDCF事件において事実関係の把握に重要な役割を果たした資料がかなり不足しているように見受けられます。
これには、アメリカでスキームの企画立案が行われたことも影響していると推測されます
――証拠の不足に関しては、新聞報道(日本経済新聞(2014.5.29))でも、アメリカで資料収集ができなかったと伝えられていましたね。
朝長 中里教授も、『タックスシェルター』において、次のような指摘をしておられます。
| 課税庁に調査権限がなく、調べようのない外国のことについてまで、課税庁が立証責任を負うのは正義衡平の理念に反するという考え方が成立しうるからである。もちろん、客観的立証責任をそのような事情で動かすこと自体は、理論上問題もあろうが、課税庁の調査不能な事項に関して納税者が知っていれば、その行政庁による立証について何らかの軽減措置を考えるのが適切なのではないかと考えるが、ここではこれ以上立ち入らない。 |
――「日本で企画立案が行われた租税回避」に対する税務調査と「外国で企画立案が行われた租税回避」に対する税務調査について、国側に同じように立証責任が課されるとすると、「租税回避の企画立案は外国でやればよい」ということにはならないでしょうか?
この点は、実務に大きな影響を与える可能性があるように思います。
朝長 そうですね。日本企業は「租税回避」と言われ易いが、外資系企業は言われにくい、ということになるおそれもあります。
このように、IBM事件ではスキームの企画立案が外国で行われていることから「証拠資料の不足」という難問が残り、これをどのように考えるのかということが大きな争点とならざるを得ないわけですが、これは事実関係に関するものであることから、多くの方は、如何ともしがたいと感じるかも知れません。
しかし、私は、この争点には出口があると考えています。
――具体的に教えて下さい。
朝長 不足していると言われている証拠資料が何かというと、それは、「租税回避」の「目的」を確認することができる資料であると思われます。
しかし、既に繰り返し述べてきたとおり、132条は、「目的」ではなく「結果」で「不当」か否かを判断するということになっているわけです。
「目的」が「租税回避」であったことを確認することができる資料があればそれに越したことはないのですが、既に述べたとおり、132条は、「目的」の事実確認によって適用の有無を判断する規定ではありません。
一審の判決は、この132条の判断基準に関する重要な部分を看過して、「目的」の事実確認によって、「……とまでは言えない」というような判断をしたもののように見受けられます。
――なるほど。そもそも一審では、132条が「目的」ではなく「結果」で判断する規定となっているということが明確に意識されていなかったため、目を向ける所がずれてしまっている感じはしますね。
朝長 昭和25年の改正を知り、「結果」という文言が用いられている条文を読み直してみると、誰もがそういう印象を受けると思います。
IBM事件は、法令の規定を正しく解釈することがいかに大事かということを示している典型的な案件だと感じています。
法律鑑定意見書の筆者も「否認するべき」と主張?
――「法律鑑定意見書」には、次のように「IBM事件に132条を適用することに違和感がある」という旨の記述もありますが、この主張についてはどのようにお考えですか?
| もちろん、課税の公平を著しく損ねるような予想外の事象が生じた場合に備えて、それぞれ独自の否認規定が設けられていたが(132条の2及び132条の3)、それは制度制定時に想像もつかないような事態に備えるものであって、制度制定時に予想されていた事象(本件で問題となっていると聞いているところの、みなし配当の計算方式の改正に伴う有価証券譲渡損失の発生や、グループ内取引による繰越欠損金の連結納税による利用)について適用するためのものではない。のみならず、本件は、いわば、これらの税制改正において想定されていた事象を「租税回避」として、(132条の2や132条の3ではなく)既存の否認規定である132条を適用して否認するというのであり、これらの税制改正の経緯に照らすと非常に違和感がある。 |
――そう考える具体的な根拠を教えて頂けないでしょうか。
朝長 平成13年度税制改正が終わった後の平成13年6月26日の第14回法人課税小委員会において、連結納税制度の創設の適否に関する議論の際に、ある委員の方から租税回避を懸念する次のような発言がありました。
| 租税回避防止行為のための制度、これはある程度、恣意的に繰越欠損を行うもの、例えば親を買うような場合が出てくるわけですよね。親が巨額な繰越欠損を持っていると。その親を買って自分のところの子にくっつけるということによって租税潜脱行為ということもアメリカで実例あるようですので、こういうものについては当然租税回避行為として除外、回避しなければいけない行為かなと思いますけれども、基本的な考えはこれでいいのかなと私は考えております。 |
| 1 租税回避否認規定の整備について 昨年から今年にかけてアメリカにおいて否認された様々なタックスシェルターを見てみますと、組織再編税制や連結納税制度における帳簿価額の付け替えの仕組みを用いたものがみられます。租税回避否認に関する日本おける従来の感覚からしますと、帳簿価額の引継ぎによる課税繰延が濫用された場合に備えることに主眼が置かれがちですが、帳簿価額が引き上げられる場合においても、濫用がおこりえます。例えば、アメリカにおいては、非課税法人(たとえば、アメリカに恒久的施設を有しない外国法人で、キャピタルゲインについてアメリカで非課税とされるもの)から資産の移転を受けた法人において、当該資産について帳簿価額の引き上げが行われますと、当該資産の移転を受けた法人が当該資産を譲渡した場合にロスを実現することが可能となります(1999年改正において新設された内国歳入法典357条(d)参照)。日本において同様のことが生ずるかどうかわかりませんが、様々な場合に備える意味で、従来において法人課税小委員会において議論してきた連結納税制度に固有の否認規定に加えて、たとえば、次のような措置が必要と思われます。 第一に、非課税の法人から資産の移転を受けても帳簿価額は引き上げられないことを確認しておく。 第二に、同族会社の行為計算否認規定を拡大して、外国法人である同族会社の行為計算により所得税、法人税、相続税などが不当に減少させられた場合にも否認が可能にする。 |
朝長 「帳簿価額が引き上げられる場合においても、濫用がおこりえ(る)」という観点に立って、「非課税の法人から資産の移転を受けても帳簿価額は引き上げられないこと」を「確認しておく」ことが必要であり、「同族会社の行為計算否認規定を拡大して、外国法人である同族会社の行為計算により所得税、法人税、相続税などが不当に減少させられた場合」にも否認を可能にするべきである、と主張されています。
このペーパーは、IBM事件のようなケースが日本でも発生することを予言し、そのようなケースは132条で否認するべきであると主張したものと捉えてもよい内容になっていると思います。
IBM事件は22年改正が想定するケースよりも租税回避の性格が強い
――「法律鑑定意見書」の最後には次のような見解が述べられていますが、これについてはどのように考えておられますか?
| これらの税制改正において想定されていた事象が租税回避的に利用された場合への対応については、既に、平成22年度税制改正において、グループ法人税制を導入し、あるいは制度の租税回避的な利用の制限を行うなど、立法措置による対応が行われていることを見ても、本来、執行ではなく立法で対応すべき問題であることは明らかであろう。 |
平成22年度税制改正では、本来は、株式の譲渡損益を計上させないとするのではなく、配当の益金不算入を認めないこととするべきであったと考えていますが、いずれにせよ、改正の趣旨は、IBM事件のようなケースを「租税回避」と捉えた上で、欠損金を生じさせないようにしたものです。
この改正は、改正前のIBM事件のようなケースを容認するべきであるということではなく、逆に、そのようなケースは「租税回避」として否認するべきであるという前提に立って行われたものであることが明らかです。仮に、容認するべきであるという前提に立ってこの改正が行われたということであれば、国は原告に対する更正処分を取り消さなければなりません。
――IBM事件のようなケースを否認するために、完全支配関係にある法人間の自己株式の買取り等の場合に株式の譲渡損益を計上させないという個別の租税回避防止規定を創ったということですよね。
朝長 先ほど申し上げたとおり、私は、みなし配当に関する22年の改正の内容には賛成しませんが、IBM事件のようなケースを「租税回避」として否認することは、当然、必要であると考えています。
IBM事件は、株式の譲渡損益を計上させない改正に繋がったことから、この改正との関係ばかりが話題になりますが、22年におけるもう一つの改正である「自己株式の買取り予定取得の場合のみなし配当の益金算入」という租税回避の防止の措置(法法23③)との関係にも注目しておく必要があります。
この措置は、株式を譲渡する者がどのような課税を受けるかということとは関係なく適用されます。このため、株式を譲渡した者が巨額の譲渡益を計上し多額の納税を行っているとしても、この措置が適用され、みなし配当が益金算入されます。このように、この措置は、たとえ株式を譲渡した者が譲渡益について納税を行っていても、その株式を取得して発行会社に買い取らせる者におけるみなし配当と譲渡損の両建て計上を「租税回避」と捉え、みなし配当の益金不算入を認めないとしたものです。しかし、IBM事件では、株式を譲渡する者は株式の譲渡益の計上さえも行っていません。
このような点からすれば、IBM事件は、この措置が想定する「租税回避」の状態よりも更に「租税回避」の性格が強いと言えます。
実務家と研究者の双方に非常に大きな影響
――4回にわたる本インタビューは、「租税回避」というものをどのように捉えるべきか、また、OECDや政府税調でも検討されている「国際的租税回避」への対処、税務調査への対応などについて、非常に示唆に富んだものとなりました。「IBM事件=現行制度には関係がない事件」という認識が変わった読者も多いと思います。
朝長 これまで述べてきたように、この事件について正しい判断が下されるかどうかは、みなし配当の規定である24条1項の平成13年の改正の趣旨・目的を正しく理解すること、「租税回避」の包括的な防止規定である132条の昭和25年の改正の趣旨・目的を正しく理解すること、同条の規定を正しく文理解釈すること、そして、「結果」を近年の「社会通念」や「常識」に照らして適切に判断することにかかっていると思います。
ヤフー事件では、被合併法人において実際に発生した欠損金を控除してよいのか否かが争われていますが、IBM事件においては、IBMが日本の事業で損をしたわけではないにもかかわらず、「欠損金」を計上して法人税額を減少させています。また、アメリカの親会社に対する利益の配当が損金となる状態にもなっています。IBM事件のこのような「結果」を「社会通念」や「常識」で判断すると、IBM事件は、ヤフー事件よりも明らかな「租税回避」ということになると感じています。
――今回のインタビューは、実務家と研究者の双方に非常に大きな影響を与えることになるものと思います。
非常に貴重な話をお聞かせ頂き、大変有り難うございました。高裁判決が出ましたら、また話をお聞かせ下さい。 (了)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















