資料2014年09月01日 【重要資料】 輸出物品販売場制度に関するQ&A(2014年9月1日号・№560)
重要資料
輸出物品販売場制度に関するQ&A
平成26年8月
国税庁消費税室
Ⅰ 輸出物品販売場制度の概要等
1 輸出物品販売場制度の概要
(輸出物品販売場制度の概要)
【答】
「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、通常生活の用に供する物品を一定の方法(問2参照)で販売する場合に、消費税が免除される制度です(消法8①)。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります(消法8⑥)。
(免税販売の方法)
【答】
輸出物品販売場における非居住者に対する免税販売の方法は、次のとおりです。
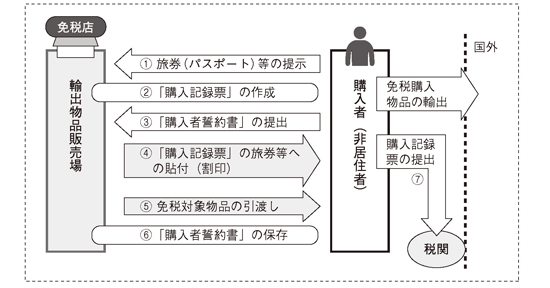
① 旅券(パスポート)等の提示
非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し、その所持する旅券等を提示します(旧消令18②一、新消令18②一イ)。
次に掲げる旅券等のいずれの提示もないときには、免税となりません。
イ 旅券(上陸許可の証印を受けたもの)
ロ 乗員上陸許可書
ハ 緊急上陸許可書
ニ 遭難による上陸許可書
(注)平成26年10月1日以降、一定の場合には、非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に旅券等の写しを提出する必要があります(新消令18②一ハ)(問33、34参照)。
② 購入記録票の作成
輸出物品販売場を経営する事業者は、「購入記録票」(免税対象物品の購入事実を記載した書類をいいます。以下同じ。)を作成します(旧消令18②一、新消令18②一イ)。
③ 購入者誓約書の提出
非居住者は、購入者誓約書(免税対象物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類をいいます。以下同じ。)を作成し、輸出物品販売場を経営する事業者に提出します(旧消令18②一、新消令18②一ロ)。
(注)平成26年10月1日から新たに免税対象となる消耗品については、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約する書類を輸出物品販売場を経営する事業者に提出する必要があります(新消令18②ニイ)(問22参照)。
④ 購入記録票の旅券等への貼付け
輸出物品販売場を経営する事業者は、②により作成した購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付け、旅券等と購入記録票との間に次の形式の印で割印します(旧消令18②一、新消令18②一イ、消基通8-1-7)。
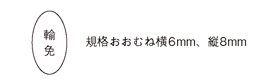
⑤ 免税対象物品の引渡し
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品を引き渡す際には、購入者との事後のトラブルを防止するためにも、購入記録票に記載されている次の事項を説明します。
・ 免税で購入した物品を帰国の際に携帯していなかったときは、その購入物品に対する消費税が徴収されること。
(注)平成26年10月1日から新たに免税対象となる消耗品については、購入後30日以内に、指定された包装を開封せずに国外に持ち出す必要があることを非居住者に説明してください(問22、27~30参照)。
⑥ 購入者誓約書の保存
輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者から提出された購入者誓約書を、免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません(旧消規則7①、新消規則7①)。
購入者誓約書の保存がない場合や、その記載内容に不備がある場合には、非居住者に対する販売であっても免税となりません(消法8②)。
ただし、災害等やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者が証明した場合には、この限りではありません(消法8②)。
(注)平成26年10月1日以降、一定の場合には、非居住者から提出された旅券等の写しを保存する必要があります(新消規則7①)(問33、34参照)。
⑦ 購入記録票の提出
非居住者は、出国する際、免税購入物品を携帯等の方法により輸出するとともに、旅券等に貼付けられた購入記録票を、出港地を所轄する税関長に提出しなければなりません(旧消令18③、新消令18⑤)。
非居住者が出国する際に免税購入物品を携帯していない(輸出しない)場合には、出国時に、当該非居住者から、免除された消費税額に相当する消費税が徴収されることとなります(消法8③)。
なお、非居住者が免税購入物品を別送の方法により輸出した場合は、出国する際に免税購入物品を携帯していませんので、別送による輸出手続をとる際に購入記録票を提示し、税関において輸出済である旨の証印を受けることにより確認を受けることとなります。
ただし、郵便により輸出するものについては、郵便局が発行する受領証(内容品の品名、数量、価格が記載されているものに限ります。)又は受理明細証により確認できるものは、これにより確認を受けることとなります。
(非居住者の意義)
【答】
輸出物品販売場において免税販売できるのは、外国人旅行者などの「非居住者」に対する販売に限られます(消法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者をいい、具体的には、次のとおりです。
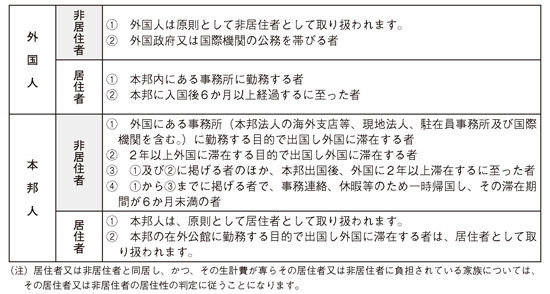
(非居住者であることの確認)
【答】
輸出物品販売場で免税販売を行う場合には、旅券等により購入者が非居住者であることを確認しなければなりません(問2参照)。
したがって、旅券に上陸許可の証印が押印されておらず、非居住者であることが確認できない場合には、免税販売できません。
(参考) 日本人及び日本在留資格を有する外国人(再入国許可を有する者に限ります。)については、所定の登録手続(指紋情報の提供等)をすれば、入国審査官から証印を受けることなく自動化ゲートを通過して出入国ができることとされており、出入国手続の簡素化・迅速化が図られています。
自動化ゲートを利用して入国する場合、旅券に上陸許可の証印が押印されませんが、旅券等に上陸許可の証印が必要な旨を自動化ゲート利用時に申し出ることによって、証印を受けることができることとなっています。
自動化ゲートの運用の詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html
(免税対象物品)
【答】
免税販売の対象となる物品は、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品を除く。)で、その物品の購入額の合計額が1万円超の物品とされています(旧消令18①⑤)。
したがって、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は含まれません。 (注)平成26年10月1日以降は、一定の要件の下、通常生活の用に供する物品の全てが免税販売の対象となります(新消令18①⑦)(問22参照)。
(事業用のための購入)
【答】
輸出物品販売場における免税の対象となる物品は、その購入者が通常生活の用に供する物品に限られますので(旧消令18①、新消令18①)、事業用又は販売用として購入されるものは、免税の対象となりません。
(注)輸出物品販売場を経営する事業者自らが、外国人事業者の指定する国へ輸出する場合には、消費税法第7条の輸出免税の規定の適用を受けることができます。この場合には以下の証明書類等の保存が必要となります(消7②、消基通7-2-23)。
① 輸出許可を受ける貨物の場合
輸出許可書(税関長が証明した書類)
② 価格20万円超の資産を郵便物として輸出する場合
輸出許可書(税関長が証明した書類)
③ 価格20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合
その事実を記載した帳簿又は書類
(出張販売)
【答】
輸出物品販売場とは、一定の要件(問10参照)を満たす課税事業者が経営する販売場で、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます(消法8⑥)。
出張販売は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場での販売ではありませんので、免税の対象にはなりません。
(免税販売物品の返品についての取扱い)
【答】
旅券等に貼り付けた購入記録票は、そのままにしておき、その余白に免税販売した物品が返品された旨を記載するとともに、返品処理した者が分かる印(社印や担当者の印など)を押印してください。
2 輸出物品販売場の許可申請
(輸出物品販売場を開設する場合の手続)
【答】
事業者が経営する販売場で、その販売場を輸出物品販売場としようとする事業者は、その販売場ごとに、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります(消法8⑥)。
具体的には、「輸出物品販売場許可申請書」により申請することとなります(旧消規則10①、新消規則10①)。
輸出物品販売場の許可に当たっては、税務署において販売場を確認するなどして許可要件(問10参照)を満たしているかどうか審査を行いますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。
なお、次のような参考書類を添付していただくことにより、許可要件の確認が円滑に行えますので、参考書類の添付にご協力をお願いします。
① 許可を受けようとする販売場の見取り図(販売場全体のレイアウト及び免税手続を行う場所が分かるもの)
② 社内の免税販売マニュアル(免税販売の方法を販売員に周知するためのものとして、例えば、問2の「免税販売の方法」を記載しているもの)
③ 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内及びホームページ掲載情報があれば、ホームページアドレス)
④ 許可を受けようとする販売場の取扱商品が分かるもの(主な取扱商品の一覧表など)
(輸出物品販売場としての許可要件)
【答】
事業者が経営する販売場について、輸出物品販売場としての許可を受けるためには、次の要件の全てを満たすことが必要です(消基通8-2-1)。
① 販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること(問11参照)。
② 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること(問12参照)。
③ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
④ 申請者の資力及び信用が十分であること。
⑤ ①から④までのほか、許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
(非居住者の利用度が高いと認められる場所)
【答】
「非居住者の利用度が高いと認められる場所」については、許可申請の時点で利用度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含みます。
(販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するもの)
【答】
「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。
なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者が手続を理解していただければ十分です。
また、「非居住者に対する販売に必要な物的施設を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。
(複数の販売場に係る許可申請)
【答】
輸出物品販売場としての許可は、その販売場ごとに受けなければなりませんが、許可を受けようとする販売場が複数ある場合で、複数の販売場の許可を同時に受けようとするときは、「輸出物品販売場許可申請書」の「販売場の所在地、名称」、「販売場所在地の所轄税務署名」欄については適宜の様式に記載し、申請書に添付した上、納税地の所轄税務署長に提出することで、各販売場についての許可申請を行うことができます。
(輸出物品販売場を移転した場合)
【答】
事業者が経営する販売場についての輸出物品販売場としての許可は、その販売場ごとに受けなければなりませんので、その販売場を移転した場合には、移転後の販売場について、「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
また、移転前の販売場については、「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(本店所在地を移転した場合)
【答】
輸出物品販売場の移転がない場合には、輸出物品販売場についての手続は必要ありません。
(輸出物品販売場の住所表示の変更があった場合)
【答】
「消費税異動届出書」に変更内容を記載して、輸出物品販売場を経営する事業者の納税地を所轄する税務署長に提出してください。
(吸収合併があった場合)
【答】
輸出物品販売場とは、一定の要件(問10参照)を満たす課税事業者が経営する販売場で、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます(消法8⑥)。
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、被合併法人から引き継ぐ販売場について、合併法人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
また、合併法人は、被合併法人が許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(営業譲渡があった場合)
【答】
輸出物品販売場とは、一定の要件(問10参照)を満たす課税事業者が経営する販売場で、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます(消法8⑥)。
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、営業譲渡先の法人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
なお、貴社においては、許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(相続があった場合)
【答】
輸出物品販売場とは、一定の要件(問10参照)を満たす課税事業者が経営する販売場で、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます(消法8⑥)。
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、被相続人から引き継ぐ販売場について、相続人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
また、相続人は、被相続人が許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(消費税の免税事業者の場合)
【答】
消費税の免税事業者の場合、消費税の納税義務がありませんので、輸出物品販売場制度は適用されません。
したがって、輸出物品販売場の許可を受けることはできません。
Ⅱ 輸出物品販売場制度の改正について
1 改正の概要
(改正の概要)
【答】
輸出物品販売場制度については、主に次の①から③の改正が行われました。
これらの改正は、平成26年10月1日以後に行う免税対象物品の販売から適用されます。
① 免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されました(問22参照)。
(注)非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、従前同様、免税販売の対象となりません。
② 一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となりました(問33参照)。
③ 購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られました(問35参照)。
2 免税対象物品の範囲の拡大
(免税対象物品の範囲の拡大)
【答】
改正前の免税対象物品は、「通常生活の用に供する物品のうち、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)以外のもの」とされていましたが、今般の改正により、平成26年10月1日から、食品や飲料、化粧品などの消耗品も免税対象物品とされました。
ただし、新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までの範囲内のものであって、次の方法で販売する場合に限り、免税対象となります(新消令18)。
① 非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
② 非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③ 指定された方法により包装されていること(問27参照)。
なお、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、従前同様、免税販売の対象となりません。
(消耗品の範囲)
【答】
消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます(新消令18①)。
なお、消耗品に該当するか一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のものをいいます。以下同じ。)に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。
(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
【答】
「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、下記のように一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合をいい、この場合は消耗品として免税手続を行います(新消令18④、消基通8-1-2の2)。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当し、この場合は一般物品として免税手続を行います。
【一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合の例】 (消耗品として免税手続を行います。)
・おもちゃ付き菓子
・ポーチ付き化粧品
・グラス付き飲料類
【一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合の例】 (一般物品として免税手続を行います。)
・必要最小限の乾電池が付属された電化製品
・インクカートリッジが装着された状態のプリンタ
(免税対象物品の範囲の拡大に伴う輸出物品販売場の許可申請①)
【答】
輸出物品販売場の許可要件を満たす場合には、平成26年10月1日より前であっても輸出物品販売場の許可を受けることができます。
ただし、消耗品が免税販売の対象となるのは平成26年10月1日からですので、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場であっても、平成26年10月1日より前に消耗品を免税販売することはできません。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります(消法8⑥)。
(注)輸出物品販売場の許可に当たっては、税務署において販売場を確認するなどして許可要件(問10参照)を満たしているかどうか審査を行いますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。
(免税対象物品の範囲の拡大に伴う輸出物品販売場の許可申請②)
【答】
既に輸出物品販売場としての許可を受けた販売場において消耗品の免税販売を行う場合には、改めて許可申請する必要はありません。
ただし、消耗品が免税販売の対象となるのは平成26年10月1日からですので、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場であっても、平成26年10月1日より前に消耗品を免税販売することはできません。
なお、消耗品の免税販売については、一般物品と異なる金額基準が設けられているほか、指定された方法により包装を行うなど、一般物品とは異なる免税販売方法となっていますのでご注意ください(問22参照)。
(包装の方法)
【答】
消耗品を免税で販売する際に必要となる包装の方法は、次の①から④の要件の全てを満たす「袋」又は「箱」に入れ、かつ、開封された場合に開封されたものであることを示す文字が表示されるシールの貼付けにより封印をする方法によることが定められています(平成26年3月31日 経済産業省 国土交通省 告示第6号)。
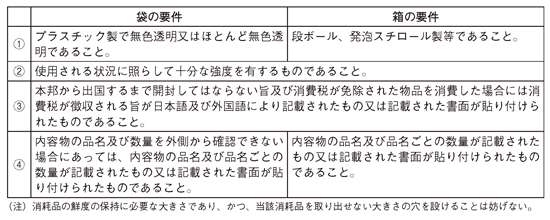 <包装のイメージ>
<包装のイメージ>
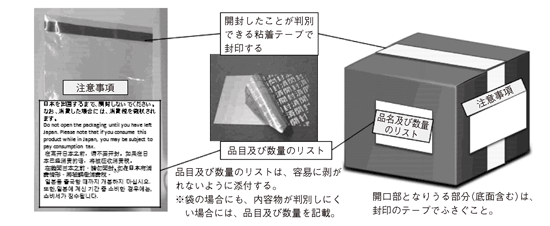
一度の販売で包装が複数個に分かれる場合、「注意事項」と「品目及び数量のリスト」は
それぞれの包装に貼付ける必要があります。
※ 包装方法の詳細については、観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
(包装材の購入先)
【答】
消耗品を免税販売する際に必要となる包装に使用する「袋」、「箱」及び「シール」については、国土交通大臣及び経済産業大臣が告示により規格を定めています(平成26年3月31日 経済産業省 国土交通省 告示第6号)。
お手数ですが、各事業者において包装材の製造業者等にご確認ください。
(包装材の仕様が要件を満たしているかどうかの確認)
【答】
包装材の要件は、国土交通大臣及び経済産業大臣が告示により定めています(平成26年3月31日 経済産業省 国土交通省 告示第6号)。
詳しくは、観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
(免税で購入した消耗品を国内において消費した場合)
【答】
免税で購入した消耗品について、非居住者が国内において一部でも消費した場合には、購入者が、出国する際に免税購入物品を携帯していない(輸出しない)こととなりますので、出国時に、その出港地を所轄する税関長が、当該非居住者から、免除された消費税額に相当する消費税を徴収することとなります(消法8③、消基通8-1-3の2)。
(免税対象金額の判定)
【答】
一般物品については、同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した一般物品の販売額の合計が1万円を超えるかどうか、また、消耗品については、同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した消耗品の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定することとなります(新消令18⑦)。
なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合(組み合わせ商品の場合。問24参照)には、消耗品の販売として免税対象金額の判定を行うこととなります。
(注) 税抜価額で判定します。
〈具体例〉 同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した物品の内訳が一般物品 6,000円、消耗品 6,000円、合計12,000円である場合
一般物品については、一般物品の販売額の合計が1万円を超えていないことから、免税対象となりません。
一方、消耗品については、消耗品の販売額の合計が5千円を超えていることから、免税対象となります。
(消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合)
【答】
消耗品については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものに限り免税販売の対象となりますが(新消令18①)、販売額の合計が50万円を超える場合の取扱いは、次の例のとおりとなります。
(注)税抜価額で判定します。
① 1個60万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額が50万円を超えるため、1個60万円の消耗品については、免税対象となりません。
② 1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額の合計が50万円を超えるため、1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品のいずれか一方のみ、免税対象となります。
③ 1個60万円の消耗品と1個4千円の消耗品を販売する場合
この場合、1個60万円の消耗品は、その販売額が50万円を超えているため、免税対象となりません。
また、1個4千円の消耗品は、その販売額が5千円を超えていないため、免税対象となりません。
④ 1個5万円の消耗品を12個販売する場合
この場合、1個5万円の消耗品10個までは免税対象となりますが、残りの2個については免税対象となりません。
3 輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加
(輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加)
【答】
今般の改正により、平成26年10月1日以降は、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100万円を超える場合には、非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に旅券等の写し(パスポートの場合、パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)を提出しなければならず、輸出物品販売場を経営する事業者は、当該旅券等の写しを納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならないこととされました(新消令18②一ハ、新消令18⑧、新消規則7①)。
なお、保存期間は、免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間となります。
(旅券等の写しの電磁的記録による保存)
【答】
同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者の旅券等の写し(パスポートの場合は、パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)を、その事業者の納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません(新消令18②一ハ、新消令18⑧、新消規則7①)(問33参照)。
この場合において、旅券等の写しに代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)による提供を受けて、これを電磁的に保存することも可能とされています(新消令18③⑧)。
例えば、IC旅券をパスポートリーダーで読み取り、又はパスポートをスキャナ等により読み取ることにより、パスポート番号、非居住者の氏名等といった所定の情報をデータで保存することも可能となります。
ただし、データで保存する場合は、このデータを保存している場所において、そのデータの内容をディスプレイに表示して確認できることや、きちんと目視できる状態のものとして紙にプリントできることが必要となります。また、そのような操作をどのように行えばよいかが分かるよう操作説明書も備え付けておくことが必要となります(新消規則7②)。
4 購入記録票等の様式の弾力化・記載事項の簡素化
(購入記録票等の様式の弾力化・記載事項の簡素化)
【答】
免税販売に当たっては、輸出物品販売場を経営する事業者は「購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)」を作成して非居住者の旅券等に貼付けて割印することとされており、非居住者は「購入者誓約書(免税物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類)」を当該事業者に提出することとされています(問2参照)。
この購入記録票及び購入者誓約書については、改正前は法令(消費税法施行規則)において様式が定められていましたが、今般の改正により、平成26年10月1日以降は、特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととされました(新消規則6①~④)。
また、購入記録票等に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等(購入者に対し交付する領収書の写しなど)を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等との間に事業者が割印をした場合には、当該明細書等に記載された事項については、購入記録票等への記載を省略できることとされました(新消規則6⑦)。
なお、購入記録票への記載の省略のために貼付ける領収書の写しは、購入記録票等に品名や数量、価額等の明細を記載する代わりに貼付けられるものであり、かつ、当該購入記録票との間に割印がされることから、当該購入記録票の一部と認められ、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者から金銭を受領した事実を証するために作成されたものではありませんから、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当せず、印紙税は課税されません。
(購入記録票等に記載すべき事項)
【答】
購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項は次のとおりです(新消規則6①~④)。
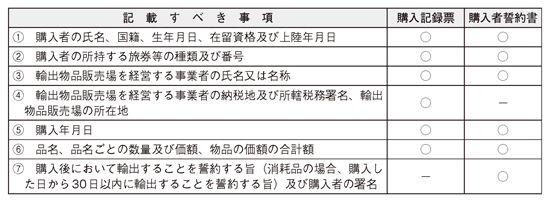
また、購入記録票には、次の事項を日本語及び外国語で記載する必要があります(新消規則6⑧)。
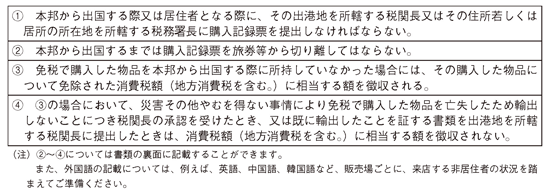
(既存の購入記録票等の継続使用)
【答】
これまで使用していた様式(改正前の消費税法施行規則に定められていた定型の様式)は、購入記録票及び購入者誓約書については「物品の価額の合計額」、購入者誓約書については消耗品の場合の記載事項である「購入後30日以内に輸出することを誓約する旨」を記載する欄がありませんので、これらの事項を追記していただければ、引き続き使用していただいて差し支えありません。
なお、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載する場合には、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」について、それぞれ区分して記載する必要があります(問39参照)。
(購入記録票の大きさ)
【答】
購入記録票は、非居住者の所持する旅券等に貼付けることとされていますので、旅券への貼付けに支障のない大きさとする必要があります(新消規則6①)。
また、法令に定められた記載事項は、整然と、かつ、明瞭に記載する必要があります。
(一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法)
【答】
同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品を販売する場合に作成することとなる購入記録票は、
① 一般物品に係る購入記録票と消耗品に係る購入記録票をそれぞれ作成する方法
② 一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載して作成する方法
のいずれかによることができます。
一の書類にまとめて記載して作成する場合、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、国籍、生年月日など、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項の記載内容が同一となる事項については、重複して記載する必要はありません。
ただし、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と消耗品のいずれも販売する場合にあっては、それぞれの対価の額の合計額が、一般物品については1万円を超えるかどうか、消耗品については5千円を超え50万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定する必要がありますので、一の書類として作成する場合であっても、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があります。(消基通8-1-7の3)
なお、同一の輸出物品販売場において、一般物品と消耗品を譲渡する場合に作成することとなる一般物品及び消耗品に係る購入者誓約書についても同様です。
(購入記録票等と明細書等との間の割印の形式)
【答】
次の形式の印により割印します。
なお、この印の形式は、購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付け、割印する場合の印の形式と同様です(消基通8-1-7の2)。
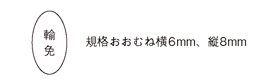
輸出物品販売場制度に関するQ&A
平成26年8月
国税庁消費税室
| 凡例
文中、文末引用の条文等の略称は、次のとおりである。 消法・・・・・・・・ 消費税法(昭和63年法律第108号) 新消令・・・・・・・ 消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第141号)による改正後の消費税法施行令 旧消令・・・・・・・ 消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第141号)による改正前の消費税法施行令 新消規則・・・・・・ 消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第26号)による改正後の消費税法施行規則 旧消規則・・・・・・ 消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第26号)による改正前の消費税法施行規則 消基通・・・・・・・ 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊) |
Ⅰ 輸出物品販売場制度の概要等
1 輸出物品販売場制度の概要
(輸出物品販売場制度の概要)
| 問1 輸出物品販売場制度の概要を教えてください。 |
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります(消法8⑥)。
(免税販売の方法)
| 問2 輸出物品販売場における免税販売の方法について教えてください。 |
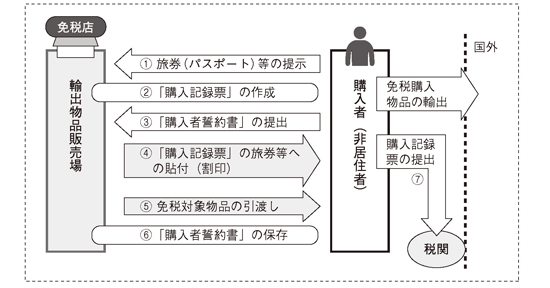
① 旅券(パスポート)等の提示
非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し、その所持する旅券等を提示します(旧消令18②一、新消令18②一イ)。
次に掲げる旅券等のいずれの提示もないときには、免税となりません。
イ 旅券(上陸許可の証印を受けたもの)
ロ 乗員上陸許可書
ハ 緊急上陸許可書
ニ 遭難による上陸許可書
(注)平成26年10月1日以降、一定の場合には、非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に旅券等の写しを提出する必要があります(新消令18②一ハ)(問33、34参照)。
② 購入記録票の作成
輸出物品販売場を経営する事業者は、「購入記録票」(免税対象物品の購入事実を記載した書類をいいます。以下同じ。)を作成します(旧消令18②一、新消令18②一イ)。
③ 購入者誓約書の提出
非居住者は、購入者誓約書(免税対象物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類をいいます。以下同じ。)を作成し、輸出物品販売場を経営する事業者に提出します(旧消令18②一、新消令18②一ロ)。
(注)平成26年10月1日から新たに免税対象となる消耗品については、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約する書類を輸出物品販売場を経営する事業者に提出する必要があります(新消令18②ニイ)(問22参照)。
④ 購入記録票の旅券等への貼付け
輸出物品販売場を経営する事業者は、②により作成した購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付け、旅券等と購入記録票との間に次の形式の印で割印します(旧消令18②一、新消令18②一イ、消基通8-1-7)。
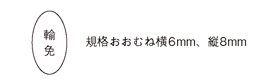
⑤ 免税対象物品の引渡し
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品を引き渡す際には、購入者との事後のトラブルを防止するためにも、購入記録票に記載されている次の事項を説明します。
・ 免税で購入した物品を帰国の際に携帯していなかったときは、その購入物品に対する消費税が徴収されること。
(注)平成26年10月1日から新たに免税対象となる消耗品については、購入後30日以内に、指定された包装を開封せずに国外に持ち出す必要があることを非居住者に説明してください(問22、27~30参照)。
⑥ 購入者誓約書の保存
輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者から提出された購入者誓約書を、免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません(旧消規則7①、新消規則7①)。
購入者誓約書の保存がない場合や、その記載内容に不備がある場合には、非居住者に対する販売であっても免税となりません(消法8②)。
ただし、災害等やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者が証明した場合には、この限りではありません(消法8②)。
(注)平成26年10月1日以降、一定の場合には、非居住者から提出された旅券等の写しを保存する必要があります(新消規則7①)(問33、34参照)。
⑦ 購入記録票の提出
非居住者は、出国する際、免税購入物品を携帯等の方法により輸出するとともに、旅券等に貼付けられた購入記録票を、出港地を所轄する税関長に提出しなければなりません(旧消令18③、新消令18⑤)。
非居住者が出国する際に免税購入物品を携帯していない(輸出しない)場合には、出国時に、当該非居住者から、免除された消費税額に相当する消費税が徴収されることとなります(消法8③)。
なお、非居住者が免税購入物品を別送の方法により輸出した場合は、出国する際に免税購入物品を携帯していませんので、別送による輸出手続をとる際に購入記録票を提示し、税関において輸出済である旨の証印を受けることにより確認を受けることとなります。
ただし、郵便により輸出するものについては、郵便局が発行する受領証(内容品の品名、数量、価格が記載されているものに限ります。)又は受理明細証により確認できるものは、これにより確認を受けることとなります。
(非居住者の意義)
| 問3 「非居住者」とはどのような者をいうのですか。 |
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者をいい、具体的には、次のとおりです。
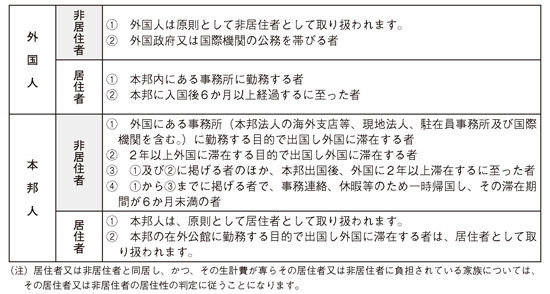
(非居住者であることの確認)
| 問4 旅券に上陸許可の証印が押印されておらず、非居住者であるかどうかを確認できない場合、免税販売することはできますか。 |
したがって、旅券に上陸許可の証印が押印されておらず、非居住者であることが確認できない場合には、免税販売できません。
(参考) 日本人及び日本在留資格を有する外国人(再入国許可を有する者に限ります。)については、所定の登録手続(指紋情報の提供等)をすれば、入国審査官から証印を受けることなく自動化ゲートを通過して出入国ができることとされており、出入国手続の簡素化・迅速化が図られています。
自動化ゲートを利用して入国する場合、旅券に上陸許可の証印が押印されませんが、旅券等に上陸許可の証印が必要な旨を自動化ゲート利用時に申し出ることによって、証印を受けることができることとなっています。
自動化ゲートの運用の詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html
(免税対象物品)
| 問5 免税販売の対象となる物品について教えてください。 |
したがって、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は含まれません。 (注)平成26年10月1日以降は、一定の要件の下、通常生活の用に供する物品の全てが免税販売の対象となります(新消令18①⑦)(問22参照)。
(事業用のための購入)
| 問6 輸出物品販売場としての許可を受けた販売場において、外国人事業者に対して免税販売することはできますか。 |
① 輸出許可を受ける貨物の場合
輸出許可書(税関長が証明した書類)
② 価格20万円超の資産を郵便物として輸出する場合
輸出許可書(税関長が証明した書類)
③ 価格20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合
その事実を記載した帳簿又は書類
(出張販売)
| 問7 当社は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場を経営していますが、外国の船舶が入港した際に、その船舶に出張して船舶の乗組員等に免税販売することはできますか。 |
出張販売は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場での販売ではありませんので、免税の対象にはなりません。
(免税販売物品の返品についての取扱い)
| 問8 当社は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場を経営していますが、非居住者に免税販売した物品の返品を受けた場合には、旅券等に貼り付けた購入記録票はどのように処理すればよいですか。 |
2 輸出物品販売場の許可申請
(輸出物品販売場を開設する場合の手続)
| 問9 輸出物品販売場を開設する場合の手続について教えてください。 |
具体的には、「輸出物品販売場許可申請書」により申請することとなります(旧消規則10①、新消規則10①)。
輸出物品販売場の許可に当たっては、税務署において販売場を確認するなどして許可要件(問10参照)を満たしているかどうか審査を行いますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。
なお、次のような参考書類を添付していただくことにより、許可要件の確認が円滑に行えますので、参考書類の添付にご協力をお願いします。
① 許可を受けようとする販売場の見取り図(販売場全体のレイアウト及び免税手続を行う場所が分かるもの)
② 社内の免税販売マニュアル(免税販売の方法を販売員に周知するためのものとして、例えば、問2の「免税販売の方法」を記載しているもの)
③ 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内及びホームページ掲載情報があれば、ホームページアドレス)
④ 許可を受けようとする販売場の取扱商品が分かるもの(主な取扱商品の一覧表など)
(輸出物品販売場としての許可要件)
| 問10 輸出物品販売場としての許可要件について教えてください。 |
① 販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること(問11参照)。
② 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること(問12参照)。
③ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
④ 申請者の資力及び信用が十分であること。
⑤ ①から④までのほか、許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
(非居住者の利用度が高いと認められる場所)
| 問11 許可要件の「非居住者の利用度が高いと認められる場所」について教えてください。 |
(販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するもの)
| 問12 許可要件の「販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること」について教えてください。 |
なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者が手続を理解していただければ十分です。
また、「非居住者に対する販売に必要な物的施設を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。
(複数の販売場に係る許可申請)
| 問13 当社は、衣料品店を経営しており、販売場が5店舗あります。この5店舗について、輸出物品販売場としての許可を受けたいのですが、申請方法を教えてください。 |
(輸出物品販売場を移転した場合)
| 問14 輸出物品販売場としての許可を受けた販売場を移転しましたが、どのような手続が必要ですか。 |
また、移転前の販売場については、「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(本店所在地を移転した場合)
| 問15 当社は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場を経営していますが、この度、本社ビルの移転に伴い本店所在地が変更となりました。この場合にはどのような手続が必要ですか。なお、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場の移転はありません。 |
(輸出物品販売場の住所表示の変更があった場合)
| 問16 輸出物品販売場としての許可を受けた販売場の住所表示が変更になりますが、どのような手続が必要ですか。 |
(吸収合併があった場合)
| 問17 当社は、輸出物品販売場を経営する法人を吸収合併し、その法人が経営していた輸出物品販売場を引き継ぐ予定です。この場合には、どのような手続が必要ですか。 |
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、被合併法人から引き継ぐ販売場について、合併法人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
また、合併法人は、被合併法人が許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(営業譲渡があった場合)
| 問18 当社は、輸出物品販売場としての許可を受けている販売場を経営しています。この度、その販売場の営業に係る事業を他社に譲渡することとなりましたが、どのような手続が必要ですか。 |
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、営業譲渡先の法人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
なお、貴社においては、許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(相続があった場合)
| 問19 私は、輸出物品販売場としての許可を受けている販売場を相続によって父から承継しましたが、どのような手続が必要ですか。 |
このため、輸出物品販売場を経営する事業者が異なることとなる場合には、改めて納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
したがって、照会の場合、被相続人から引き継ぐ販売場について、相続人が納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、改めて輸出物品販売場としての許可を受ける必要があります。
また、相続人は、被相続人が許可を受けていた販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出する必要があります(旧消規則10④、新消規則10④)。
(消費税の免税事業者の場合)
| 問20 私は、個人でアクセサリーショップを経営していますが、消費税の免税事業者です。当店には外国人旅行者の来客が多いのですが、当店は輸出物品販売場としての許可を受けることはできますか。 |
したがって、輸出物品販売場の許可を受けることはできません。
Ⅱ 輸出物品販売場制度の改正について
1 改正の概要
(改正の概要)
| 問21 輸出物品販売場制度の改正の概要について教えてください。 |
これらの改正は、平成26年10月1日以後に行う免税対象物品の販売から適用されます。
① 免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されました(問22参照)。
(注)非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、従前同様、免税販売の対象となりません。
② 一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となりました(問33参照)。
③ 購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られました(問35参照)。
2 免税対象物品の範囲の拡大
(免税対象物品の範囲の拡大)
| 問22 輸出物品販売場制度の改正により、免税対象物品の範囲が消耗品を含む全ての物品に拡大されたとのことですが、その概要について教えてください。 |
ただし、新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までの範囲内のものであって、次の方法で販売する場合に限り、免税対象となります(新消令18)。
① 非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
② 非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③ 指定された方法により包装されていること(問27参照)。
なお、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、従前同様、免税販売の対象となりません。
(消耗品の範囲)
| 問23 「消耗品」とはどのようなものをいうのですか。 |
なお、消耗品に該当するか一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のものをいいます。以下同じ。)に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。
(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
| 問24 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、当該資産を消耗品として、免税手続を行うこととなるとのことですが、この「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、どのような場合をいうのですか。 |
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当し、この場合は一般物品として免税手続を行います。
【一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合の例】 (消耗品として免税手続を行います。)
・おもちゃ付き菓子
・ポーチ付き化粧品
・グラス付き飲料類
【一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合の例】 (一般物品として免税手続を行います。)
・必要最小限の乾電池が付属された電化製品
・インクカートリッジが装着された状態のプリンタ
(免税対象物品の範囲の拡大に伴う輸出物品販売場の許可申請①)
| 問25 当社は、消耗品のみを扱う販売場を経営しています。この度、輸出物品販売場制度が改正され、平成26年10月1日から消耗品も免税対象物品とされるとのことですが、平成26年10月1日より前に輸出物品販売場の許可を受けることができますか。 |
ただし、消耗品が免税販売の対象となるのは平成26年10月1日からですので、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場であっても、平成26年10月1日より前に消耗品を免税販売することはできません。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります(消法8⑥)。
(注)輸出物品販売場の許可に当たっては、税務署において販売場を確認するなどして許可要件(問10参照)を満たしているかどうか審査を行いますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。
(免税対象物品の範囲の拡大に伴う輸出物品販売場の許可申請②)
| 問26 当社が経営する販売場は輸出物品販売場としての許可を受けています。この度、輸出物品販売場制度が改正され、平成26年10月1日から消耗品も免税対象物品とされるとのことですが、既に許可を受けた販売場において消耗品の免税販売を行う場合、改めて許可申請する必要がありますか。 |
ただし、消耗品が免税販売の対象となるのは平成26年10月1日からですので、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場であっても、平成26年10月1日より前に消耗品を免税販売することはできません。
なお、消耗品の免税販売については、一般物品と異なる金額基準が設けられているほか、指定された方法により包装を行うなど、一般物品とは異なる免税販売方法となっていますのでご注意ください(問22参照)。
(包装の方法)
| 問27 消耗品を免税で販売するには、指定された方法により包装する必要があるとのことですが、具体的にどのように行うのですか。 |
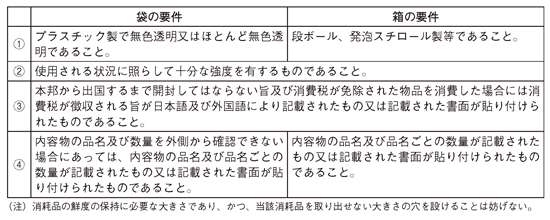 <包装のイメージ>
<包装のイメージ>
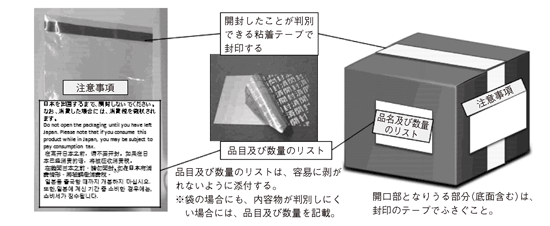
一度の販売で包装が複数個に分かれる場合、「注意事項」と「品目及び数量のリスト」は
それぞれの包装に貼付ける必要があります。
※ 包装方法の詳細については、観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
(包装材の購入先)
| 問28 消耗品の免税販売の際に行う包装に使用する袋や箱はどこで購入できますか。 |
お手数ですが、各事業者において包装材の製造業者等にご確認ください。
(包装材の仕様が要件を満たしているかどうかの確認)
| 問29 消耗品の免税販売の際に必要な包装材の仕様が要件を満たすものであるかどうかは、どのように確認すればよいですか。 |
詳しくは、観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
(免税で購入した消耗品を国内において消費した場合)
| 問30 非居住者が免税で購入した消耗品を国内において消費してしまった場合、どうなりますか。 |
(免税対象金額の判定)
| 問31 当社が経営する輸出物品販売場では、一般物品と消耗品の両方を取り扱っていますが、免税対象金額の判定はどのように行うのですか。 |
なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合(組み合わせ商品の場合。問24参照)には、消耗品の販売として免税対象金額の判定を行うこととなります。
(注) 税抜価額で判定します。
〈具体例〉 同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した物品の内訳が一般物品 6,000円、消耗品 6,000円、合計12,000円である場合
一般物品については、一般物品の販売額の合計が1万円を超えていないことから、免税対象となりません。
一方、消耗品については、消耗品の販売額の合計が5千円を超えていることから、免税対象となります。
(消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合)
| 問32 消耗品については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものが免税販売の対象となるとのことですが、販売額の合計が50万円を超える場合の取扱いを教えてください。 |
(注)税抜価額で判定します。
① 1個60万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額が50万円を超えるため、1個60万円の消耗品については、免税対象となりません。
② 1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額の合計が50万円を超えるため、1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品のいずれか一方のみ、免税対象となります。
③ 1個60万円の消耗品と1個4千円の消耗品を販売する場合
この場合、1個60万円の消耗品は、その販売額が50万円を超えているため、免税対象となりません。
また、1個4千円の消耗品は、その販売額が5千円を超えていないため、免税対象となりません。
④ 1個5万円の消耗品を12個販売する場合
この場合、1個5万円の消耗品10個までは免税対象となりますが、残りの2個については免税対象となりません。
3 輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加
(輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加)
| 問33 輸出物品販売場制度の改正により、一定の場合には輸出物品販売場において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となるとのことですが、その概要について教えてください。 |
なお、保存期間は、免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間となります。
(旅券等の写しの電磁的記録による保存)
| 問34 非居住者が、同一の輸出物品販売場において、同一の日に購入する一般物品の購入額の合計が100万円を超える場合には、非居住者は旅券等の写しを当該輸出物品販売場を経営する事業者に提出することとされています。この場合、旅券等の写しの提出は、電磁的記録の提供により代えることができるとされていますが、その詳細について教えてください。 |
この場合において、旅券等の写しに代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)による提供を受けて、これを電磁的に保存することも可能とされています(新消令18③⑧)。
例えば、IC旅券をパスポートリーダーで読み取り、又はパスポートをスキャナ等により読み取ることにより、パスポート番号、非居住者の氏名等といった所定の情報をデータで保存することも可能となります。
ただし、データで保存する場合は、このデータを保存している場所において、そのデータの内容をディスプレイに表示して確認できることや、きちんと目視できる状態のものとして紙にプリントできることが必要となります。また、そのような操作をどのように行えばよいかが分かるよう操作説明書も備え付けておくことが必要となります(新消規則7②)。
4 購入記録票等の様式の弾力化・記載事項の簡素化
(購入記録票等の様式の弾力化・記載事項の簡素化)
| 問35 輸出物品販売場制度の改正により、購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られたとのことですが、その概要について教えてください。 |
この購入記録票及び購入者誓約書については、改正前は法令(消費税法施行規則)において様式が定められていましたが、今般の改正により、平成26年10月1日以降は、特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととされました(新消規則6①~④)。
また、購入記録票等に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等(購入者に対し交付する領収書の写しなど)を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等との間に事業者が割印をした場合には、当該明細書等に記載された事項については、購入記録票等への記載を省略できることとされました(新消規則6⑦)。
なお、購入記録票への記載の省略のために貼付ける領収書の写しは、購入記録票等に品名や数量、価額等の明細を記載する代わりに貼付けられるものであり、かつ、当該購入記録票との間に割印がされることから、当該購入記録票の一部と認められ、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者から金銭を受領した事実を証するために作成されたものではありませんから、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当せず、印紙税は課税されません。
(購入記録票等に記載すべき事項)
| 問36 購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項は具体的にはどのようなものですか。 |
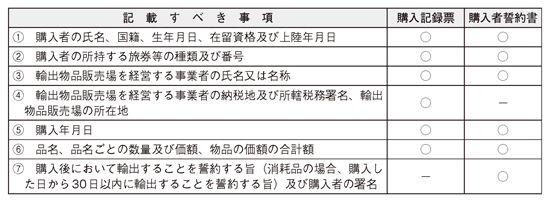
また、購入記録票には、次の事項を日本語及び外国語で記載する必要があります(新消規則6⑧)。
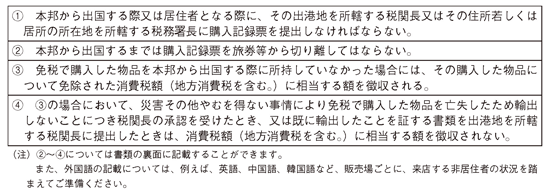
(既存の購入記録票等の継続使用)
| 問37 購入記録票及び購入者誓約書について、これまで使用していた様式を引き続き使用することはできますか。 |
なお、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載する場合には、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」について、それぞれ区分して記載する必要があります(問39参照)。
(購入記録票の大きさ)
| 問38 購入記録票については、法令に定められた事項が記載された書類であればよいとのことですが、どのような大きさでもよいのですか。 |
また、法令に定められた記載事項は、整然と、かつ、明瞭に記載する必要があります。
(一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法)
| 問39 同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票の作成方法について教えてください。 |
① 一般物品に係る購入記録票と消耗品に係る購入記録票をそれぞれ作成する方法
② 一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載して作成する方法
のいずれかによることができます。
一の書類にまとめて記載して作成する場合、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、国籍、生年月日など、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項の記載内容が同一となる事項については、重複して記載する必要はありません。
ただし、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と消耗品のいずれも販売する場合にあっては、それぞれの対価の額の合計額が、一般物品については1万円を超えるかどうか、消耗品については5千円を超え50万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定する必要がありますので、一の書類として作成する場合であっても、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があります。(消基通8-1-7の3)
なお、同一の輸出物品販売場において、一般物品と消耗品を譲渡する場合に作成することとなる一般物品及び消耗品に係る購入者誓約書についても同様です。
(購入記録票等と明細書等との間の割印の形式)
| 問40 購入記録票等に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等とを割印した場合には、当該明細書等に記載された事項の購入記録票等への記載を省略できるとのことですが、購入記録票等と明細書等との間の割印は、どのような形式の印で行うのですか。 |
なお、この印の形式は、購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付け、割印する場合の印の形式と同様です(消基通8-1-7の2)。
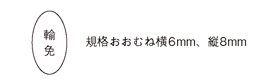
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















