解説記事2014年11月03日 【事例で学ぶ資産税】 「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(下)(2014年11月3日号・№569)
事例で学ぶ資産税
第9回
「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(下)
税理士 塩野入文雄
(注)本稿(上)は、本誌No.568(2014.10.27)21頁に掲載されています。
Ⅱ「事業供用」等の判定(建物の所有者・事業者)
第2点目に、①(表九号下欄適用の前提整理として、)買換え取得する土地等の上に建築する建物等の所有者と事業者との関係〔同一の所有者であることが必要か?〔検討項目1〕〕、及び、②その土地等に係る「事業供用」(「事業用資産」としての該当性)の判定〔生計一親族であるZによる事業供用を通じて、どの範囲までの資産が、Xにとっての「事業用資産」に該当すると判定できるのか?〔検討項目2〕〕の2点について検討します。
1.検討項目
〔検討項目1〕建物等と土地等(敷地)の所有者について 表九号の適用に当たって「買換資産」を土地等とする場合、特定施設の敷地に該当することが必要です(脚注24)。具体的には、表九号下欄に、「土地等(事務所……(特定施設)……)の敷地の用に供されるもの……」と規定されており(脚注25)、その土地等が、特定施設に該当する建物等の「敷地」であることが求められています(脚注26)。
一方、同様に、表一号・表四号上欄においても、「譲渡資産」である土地等について、「事務所……又はその敷地の用に供されている土地等……」(表一号)、「事務所……として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等……」(表四号かっこ書)と規定されています(脚注27)。更に、この2つの号の規定を受け、措置法通達37-11の8に、「その敷地の用に供されている土地等」とは、「……建物の敷地の用に供されている当該建物を所有する者が有する土地等をいい、……」と定められています(脚注28)。
このため、「敷地」という同一文言による要件が付されている表九号下欄における買換資産についても、表一号上欄などと同じように、「建物(特定施設)の所有者=土地等の所有者」であることが必要なのかとの疑問も生じてくると思われます。
〔検討項目2〕「事業供用」の判定について 措置法通達37-22(33-43)の定めによる、生計一親族による事業供用の判定に関する拡張措置が及ぶ資産の範囲は、どこまでなのかという疑問も生じてくると思われます。
上記Qの事例(本稿(上)21頁)において、買換え取得する新土地の上に建築され、生計一親族のZによって事業の用に供される新建物(特定施設)の所有者が、a)譲渡者本人(X)である場合のほか、b)生計一親族の事業者(Z)である場合もあり得ます(脚注29)。
そこで、a)のケースについて、事例のA(答)のように、Xが買換え取得する新土地を「買換資産」(特例適用の対象資産)とし、その上に建築する新建物を買換資産としない点に関して、通達文言を形式的に解釈した場合、事業供用に関する拡張措置の対象とならないのではないかとの疑問となります。
また、b)のケースについては、Xの所有資産でない(Zの所有資産である)新建物を、Zが、その事業の用に供することを通じて、Xが取得した土地について事業の用に供したもの(事業用資産)として取り扱われるのかという疑問となります。
2.規定の解釈等〔筆者意見〕
〔検討項目1〕建物等と土地等(敷地)の所有者の関係について
○結論 表九号下欄の買換資産は、「建物(特定施設)の所有者≠土地等の所有者」であったとしても、その土地等を「買換資産」とすることが出来ます(脚注30)〔ただし、別途、事業供用及び敷地属性に関する検討が必要です〕。 その理由は、次のとおりです。
① 表一号・表四号上欄と表九号下欄における条文の規定が異なっています。
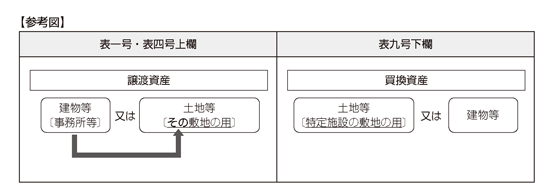
表一号上欄は、譲渡資産について、建物(事務所等)「又はその敷地の用に供されている土地等」と規定されています(脚注31)。ここで、「その」との文言は、買換え特例を適用する個人の譲渡資産が建物等(事務所等)及び土地等である場合(脚注32)、土地等がその建物等(譲渡した建物)の敷地であること、すなわち、譲渡資産である建物等及び土地等が同一の個人(譲渡者)の所有に属することを求めた規定となっています〔この制限は、平成3年度改正により講じられた措置であり、その趣旨等については、【資料4】③(29頁)を参照〕。
【資料4】建物等の所有者関係
一方、表九号下欄は、買換資産の土地等が、特定施設の敷地であることを求めているに留まり、買換え取得する土地等について買換え特例を適用する個人と、その土地等上の特定施設の所有者との関係を問う規定になっていないと解されます。何故なら、取得した土地等に関する「敷地属性」(特定施設の敷地の用)は求められていますが、その特定施設の所有者との関係については、表一号・表四号上欄における、「その」に対応する限定(文言)が何ら規定されていないからです。
(注)表一号(表四号)上欄について措置法通達37-11の8の定めがわざわざ設けられている理由は、表一号における譲渡資産の範囲の限定が、平成3年度改正によって導入されたことに伴い、「その(譲渡資産である建物等の)敷地である」ことが要件となっている点に注意喚起を図ったと考えられ、また、そのような条文読解が必ずしも容易に行えるとは思われなかったため、同通達の定めを設けることで、その意味を確認(補充)する必要もあったと思われます。
② 次の〔検討項目2〕④に記述する改正趣旨等の視点からも、上記の解釈が可能と考えられます。
〔検討項目2〕「事業供用」の判定について
○結論 「買換資産」となる(買換え特例の対象とする)土地等に係る事業供用の判定は、その土地等の上にある買換資産に該当しない建物等に係る事業供用の状況によっても判定することができ、また、
「買換資産」となる(買換え特例の対象とする)土地等に係る事業供用の判定は、その土地等の上にある買換資産に該当しない建物等に係る事業供用の状況によっても判定することができ、また、 譲渡者(X)の所有(取得)資産に該当しない建物等であっても、生計一親族(Z)による事業供用があれば、その判定は影響されない、と筆者は考えます。
その理由は、次のとおりです。
譲渡者(X)の所有(取得)資産に該当しない建物等であっても、生計一親族(Z)による事業供用があれば、その判定は影響されない、と筆者は考えます。
その理由は、次のとおりです。
① 土地等に係る利用属性に関する判定の基本は、その上にある建物等の利用状況によっています。
例えば、土地等が事業の用に供されているかどうかの判定は、その上にある建物等の事業供用の状況によって判定されています(措通37-21(1)(脚注33))〔また、平成16年度改正前の税務処理において、別荘地にある土地のみを損失譲渡しても損益通算が可能で、その土地の上に別荘(建物)があれば、損益通算が不可となっていた点からも、その「別荘」(所令178①(脚注34))としての属性が、その土地の上にある建物の利用に応じて判定されていたことが分かります(脚注35)〕。
更に、「居住の用」に関する取扱いではあるものの、建物とその敷地の所有者が異なる場合であっても、それぞれの所有者が生計一親族であることなどを条件として、建物の利用状況を中心に構築されている居住用財産関係の特例(措法35など)の適用について、その土地の所有者にとっての居住用財産として取り扱われています(措通35-4(脚注36)など)。このような判定方法(緩和措置)は、「事業の用」に関しても通じると考えられ、また、「事業の用」、あるいは、事業用資産に関する特例であったとしても、特段、排除すべき理由はない、と筆者は考えます。
② 措置法通達37-22の準用に関する定めが、単純な準用の定めとなっています。
仮に、措置法通達33-43について、譲渡者に係る代替資産、すなわち、譲渡者の所有に属する代替資産(買換資産)が生計一親族の事業の用に供された場合のみに限って緩和対象にした定めであるとします。然りであるならば、上記〔検討項目1〕のとおり、もとより、表九号下欄が「土地所有者≠建物所有者」との法文構造になっているところ、建物等所有者(特定施設の所有者)の敷地の利用関係が、借地権によらずに使用貸借による場合もあることなどから、生計一親族による事業供用の判定に係る準用の定めが、現行通達のような単純な定めにはならないはずであると考えられます(脚注37)。
③ 後述Ⅲ(25頁)の「敷地属性」(特定施設の敷地の用)に関する「逐条解説」の記述からも、生計一親族による事業供用判定についても同様に取り扱われると考えられます。
④ 本特例の趣旨等からも、上記のように解されると考えられます。
買換え特例の趣旨や平成24年度改正による特定施設の敷地要件を追加した趣旨である「経済の活性化を図るとの政策目的」からも(脚注38)、例えば、上記Qの事例のように、X(譲渡者)が土地を買換え取得して、Z(生計一親族)が、その土地の上に特定施設を建築(所有権を取得)して事業を営むようなケースは、本特例の政策目的にも適った買換えであると考えられます(更に付言するならば、今日の高齢化社会における高齢者が保有する資産の活用にも資する買換え特例のあり方としても適切と思われます)。
なお、それぞれの特例における政策目的は異なるのでしょうが、このように解することを通じて、買換え特例と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)における「事業用」に関する取扱いとの一定の整合性が確保されることにもなります(次の<小規模宅地等の特例との接点 >参照)。
>参照)。
ところで、措置法通達37-22により準用されている同33-43の定めにおいて、事業者である生計一親族への貸付の態様(無償貸付・有償貸付)が明らかにされていないことから、無償貸付(使用貸借)を前提とした定めではないのか、という疑問も生じてきます。
しかしながら、同33-43の定めは、上述したとおり(Ⅰ・2(本稿(上)24頁))、所得税法56条の規定によって、XがZから受領する対価がXの収入金額にならない点(Zの必要経費にならない点)を考慮した措置であること、及び、小規模宅地等の特例適用に関する措置法通達69の4-4の定めのように、貸付の態様(無償貸付・有償貸付)が問われることなく、もっぱら生計一親族による事業供用であるか否かを、その適用条件としています。よって、生計一親族に対する有償貸付であっても、買換え特例の適用が可能であると考えられます。
<小規模宅地等の特例との接点 >
小規模宅地等の特例の適用に当たって、「一定の条件」が付されてはいますが、対象宅地等を敷地とする建物等の所有者は、必ずしも、被相続人(X)である必要はありません。
>
小規模宅地等の特例の適用に当たって、「一定の条件」が付されてはいますが、対象宅地等を敷地とする建物等の所有者は、必ずしも、被相続人(X)である必要はありません。
その「一定の条件」とは、特定事業用宅地等を適用する場合、①その宅地等の上にある建物等の所有者は、被相続人又はその親族(生計一親族又は生計別親族)に限られ、また、②その建物等の利用関係(建物等の所有者と事業者(被相続人又は生計一親族)との関係)も無償使用に限られており、かつ、③その建物等と宅地等の利用関係(宅地等の所有者である被相続人と建物等の所有者との関係)も無償使用によることが、その適用条件になっています(措通69の4-4・【資料5】(30頁)参照)。
【資料5】建物等の所有者・利用者と小規模宅地等の特例(脚注60)
Ⅲ 建物及び敷地の利用関係(「敷地属性」)
上記Ⅱの検討の結果、両特例(脚注39)の適用を前提とした場合においても、買換資産である土地等の上に建築する建物等(特定施設)の所有者が、a)譲渡者本人(X)である場合とb)生計一親族の事業者(Z)である場合とが想定されます(脚注40)。
そこで、第3点目に、建物等及びその敷地に係る利用関係(無償・有償使用)と買換え特例の要件の一つである「敷地属性」(特定施設の敷地の用)との関係について検討します。
1.建物が譲渡者(X)所有の場合 表九号の適用に当たって、買換え取得する土地等の上に建築する建物等(特定施設)が譲渡者(X)によって所有されているものであれば、その「敷地属性」を充足していることに何ら疑問は生じてきません。
この場合、その建物等を無償貸付する場合と有償貸付する場合とが考えられます。
(1)XがZに対して建物を「無償貸付」 措置法通達37-22(33-43)の定めにより、その特定施設が生計一親族の事業の用に供されることになり、①事業(事業者・事業供用)要件を充足するとともに、②特定施設としての敷地属性(事業所の敷地としての利用属性)の要件も充足することになります。
(2)XがZに対して建物を「有償貸付」 もとより、準事業も含めた貸付も「事業」の範疇にあることから、事業要件とともに敷地属性の要件も充足しているところであり、加えて、生計一親族による事業供用に関する措置法通達37-22の定めの適用もあります。
<小規模宅地等の特例との接点 >
上記と同様に、Xが取得した新建物(脚注41)を相続開始の直前において、Zに対して無償貸付している場合と、有償貸付している場合とが考えられます。無償貸付であれば、特段の問題はありませんが、有償貸付であった場合、小規模宅地等の特例の適用について、次の点に注意が必要です。
>
上記と同様に、Xが取得した新建物(脚注41)を相続開始の直前において、Zに対して無償貸付している場合と、有償貸付している場合とが考えられます。無償貸付であれば、特段の問題はありませんが、有償貸付であった場合、小規模宅地等の特例の適用について、次の点に注意が必要です。
所得税法56条の規定は、もっぱら、所得税法における不動産所得などの事業における所得金額の計算における必要経費(収入金額)の処理に関する特則であって、他の課税場面に適用される規定とはなっていません(脚注42)。
Xが、その所有する新建物(病院)をZに対して賃貸した場合、Zが生計一親族であるXに家賃を払っても、所得税の税務処理においては、Xの不動産所得の収入金額にはなりません。しかしながら、小規模宅地等の特例の適用上、すなわち、相続税の税務処理に当たって、Xが所有する建物が「貸家」であるという課税事実までもが所得税法56条に基づいて否定される訳ではなく、その貸家としての利用事実がXに係る不動産貸付に該当する結果、その敷地は「貸家建付地」に該当すると認められ、特定事業用宅地等に該当せずに、「貸付事業用宅地等」に該当すると考えます(脚注43)(<小規模宅地等の特例との接点 >(本稿(上)23頁)参照)。
>(本稿(上)23頁)参照)。
なお、このように、所得税法56条と他の税法規定との適用関係に関する具体的な証左の一つに、消費税法基本通達5-1-10の定めがあることからも(【資料3】③(本稿(上)28頁)参照)、上記の点は首肯されると考えます。
2.建物が事業者(Z)所有の場合 買換え特例の適用に当たって、Xによって買換え取得される(「買換資産」とする)新土地の上に建築する新建物がZによって取得され、X所有(取得)の土地を敷地として利用する場合、その土地に関する「敷地属性」(特定施設の敷地の用)について検討します。
なお、当該ケースが、買換え特例における「事業供用」を充足すると考えられる点については、上記Ⅱ〔検討項目2〕((23頁)参照)において、筆者の意見を述べたとおりです。
(1)前提整理 個人間における土地の貸付、借地権などの設定については、権利金等の支払いを行わない(権利金等の認定課税を受けない)ことを前提にすると、a)使用貸借による場合(脚注44)が通例であり、また、実例が多いと思われませんが、b)相当地代による貸付の場合(脚注45)もあり得ます〔個人間に関しては、法人が関連してくる場合における「土地の無償返還に関する届出書」を税務署長に提出して借地権を設定する取扱い(脚注46)などの点は措置されていません〕。
この点を踏まえ、その利用態様に応じた、買換え特例(表九号)における「敷地属性」の要件について検討します。
(2)解釈等 「敷地属性」の具体的な態様(意義)に関して、措置法通達37-11の8に関する「逐条解説」599頁(脚注47)において、表一号・表四号上欄の譲渡資産について、土地(底地)の所有者甲が、①建物とその敷地(借地権)の所有者(権利者)である乙と生計一親族の関係にある場合は、その土地が表一号などの「譲渡資産に該当するものとして取り扱われることになる。」と(脚注48)、また、②両者が生計一親族の関係にない場合は、原則どおり、その建物の敷地は借地権であって、「甲が所有する土地(底地)は、これに〔筆注:譲渡資産(「その敷地」)〕に該当しない。」との解説が記述されています。すなわち、両者(甲及び乙)が、生計一親族の関係にない場合、借地権が設定されている底地は、建物の敷地足り得ないとことが明記されています(脚注49)。
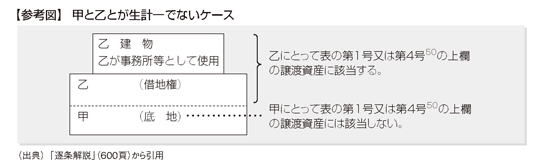
一方、表一号・表四号上欄と表九号下欄の規定における「敷地」の意義は同一に解されることから、表九号下欄における「敷地属性」についても、同様に取り扱われると考えられます。
① 土地をXが生計一親族であるZに対して「無償貸付」(使用借権の設定) 両者が生計一親族の関係にあれば、借地権が設定されている場合ですら敷地に該当するとされているので、使用貸借による場合も、敷地属性を充足することになります。
② 土地をXが生計一親族であるZに対して「有償貸付」(借地権の設定) 上記「逐条解説」の記述のとおり取り扱われているので、敷地属性を充足することになります(脚注51)。
<小規模宅地等の特例との接点 >
上記<小規模宅地等の特例との接点
>
上記<小規模宅地等の特例との接点 ~
~ >(本稿(上)25頁ほか)に記述したとおりです。
>(本稿(上)25頁ほか)に記述したとおりです。
Ⅳ その他の関連事項(買換え途中で相続開始があった場合)
上記Qの事例のように譲渡者(X)が高齢者である場合は、次の点にも注意が必要です。
1.買換え特例関係 Xが旧病院を譲渡し、譲渡年分(α1年分)に関する所得税の申告において、買換え特例を見積額に基づいて(買換え予定で)申告(脚注52)したが、その直後(α2年)に相続が開始した場合の処理は、次表のとおりです。
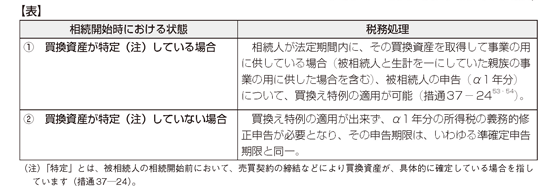
2.小規模宅地等の特例関係 新病院の建築中、Xに相続開始があった場合(Zによる新病院事業への供用前)における特定事業用宅地等の特例適用の可否について確認します。
小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等は、相続開始直前において、被相続人等(被相続人又は生計一親族)の事業(居住)の用に供されていた宅地等であることが、その適用要件の一つとなっています。しかしながら、上記Qの事例については、旧病院の敷地に新病院を建築(建替え)するのではなく、Xが新たに買換え取得する土地の上に建物を建築することから(かつ、建築中であることから)、その宅地等は、相続開始直前において、事業の用に供されていた宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例対象になりません。
なお、措置法通達69の4-5(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)の定めに基づく緩和措置は、相続開始直前に事業の用に供されていた宅地等に係る建物の建替え中などのケースに関する取扱いであって、上記のように新たに取得した宅地等が事業の用に供されていないケースまでをもカバーしている取扱いになっていません(脚注55)。
〔参考判例〕新規開業に向けて建築中であった事例 立体駐車場として事業(貸付事業)の用に供すべく建築に着手していた事例について(相続開始直後に事業に供用)、相続開始直前において現実に事業の用に供されていなかったことを理由として、特例の適用が否認された事案があります(最判平成10.2.26(脚注56)、東京高裁平成9.5.22(脚注57)、東京地裁平成8.6.21(脚注58))。
(注)上記の東京地裁判決文より引用
上記の点について、小規模宅地等の特例の創設の趣旨やその果たしている機能・効果などに鑑みれば、一律に、上記の結論に沿って処理することが適切なのかとの点に疑問が生じるところであり、例えば、買換え途中にあるケースについては、措置法通達37-24の定めに相当するような、何らかの緩和措置が講じられることが望まれます。
【資料6】建物等の建替えに関する取扱い(脚注67)
脚注
24 「特定施設の敷地」に関する要件の該当性についても、別途、後記Ⅲ(25頁)において検討します。
25 条文は、【資料1】①(本稿(上)25頁)を参照。他に、300㎡以上の面積要件(下限面積要件)などがあります。
26 「特定施設」の具体的用途は、【資料1】②(本稿(上)26頁)を参照。
27 条文は、【資料4】①(29頁)を参照。
28 通達文は、【資料4】②(29頁)を参照。
29 このほか、Z以外の親族が所有する建物となるケースも想定されます。
30 例えば、Xが取得した土地の上に、Z所有の建物(病院)を建築しても買換え特例の対象となります。
31 表四号も、表一号と同様です。
32 表一号は、譲渡資産が土地等のみである場合は、特例対象になっていません。
33 ただし、通達の文言は、「その者の建物、構築物等の建設等をする場合においても、……」と限定された定めとなっています。
34 見出し:生活に通常必要でない資産
35 平成16年度改正により、不動産の譲渡損失に係る損益通算が制限されたことから、現行法の下では、このような課税(判定)場面はありません。
36 表題:居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い
37 表九号は、〔検討項目1〕のとおり、土地等と建物等の所有者が異なり得ること、また、買換え特例における「事業」の意義に「貸付の用」も含まれており、特定施設としての利用が、譲渡者本人による利用に限られていません。このような点からも、表九号下欄において、土地等と建物等の所有者及びその利用者が異なる場合があり得ることは、国税当局においても、その想定の範囲内にあると思われます。
38 平成24年度改正前の表九号買換え特例については、「買換資産である土地等の用途に限定がなく、政策目的が曖昧であるという指摘があり、より付加価値の高い資産の買換えを促進し、経済の活性化を図るとの政策目的を明確化する観点から見直しが行われました。」(「平成24年度税制改正の解説」317頁)。
39 貸付事業用宅地等も含みます。
40 このほか、Z以外の親族が所有する建物であるケースも想定されます。
41 「買換資産」として取得するか、あるいは、自己資金等で取得するかなどの点を問いません。
42 「○○の金額の計算上」と、限定された規定となっています。したがって、その適用範囲を、根拠規定を欠いたまま相続税などに拡大適用することは違法な税務処理になります。
43 具体的には、貸家建付地として評価額を算定した上で、貸付事業用宅地等(措法69の4③四一)の対象とすることになります。
44 昭和48.11.1付個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の適用対象となります。
45 昭和60.6.5付個別通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の適用対象となります。
46 法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)の定めによる取扱いです。
47 直接的には、表一号及び表四号の譲渡資産に関する「その敷地の用に供されている土地等」に関する解説となっています。
48 措置法通達37-22(33-43)の取扱いの準用が、その根拠とされています。
49 例えば、同族会社が借地権上に特定施設を有している場合、その経営者(個人)が底地を取得しても買換え特例(表九号)の対象になりません。
50 現行条文(通達)に修正しています。
51 筆者には、上記の「逐条解説」に記述されている取扱いは、少なくとも、通達に織り込まれることが必要な取扱いではないかと思われます。何故なら、不動産所得などの事業に係る必要経費(収入金額)の算定に関する特則である所得税法56条の規定を、借地権が設定されている底地に関する「敷地属性」の判定にまで準用するには些か難があるように思われます。
52 措置法37条第4項に基づく申告を指しています。
53 表題:相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合
54 収用等の代替特例(措法33)、居住用の買換え特例(措法36の2)及び立体買換え特例(措法37の5)についても、それぞれ、措通33-45、同36の2-21及び同37の5-6に、同様の定めが設けられています。
55 【資料6】(31頁)を参照。通達文は、【資料6】②(32頁)を参照。
56 TAINS Z230-8098
57 TAINS Z223-7921
58 TAINS Z216-7742
59 平成3年度改正では、買換資産に関し、改正前は土地等の取得を伴わない建物等の取得が、その適用範囲から除かれていましたが、建物等(減価償却資産)のみによる買換えも特例対象となりました。
60 本文<小規模宅地等の特例との接点 ~
~ >(本稿(上)25頁ほか)の関連資料です。
>(本稿(上)25頁ほか)の関連資料です。
61 相続税の課税対象となる宅地等であり、被相続人が所有していることが前提となります。
62 加藤浩編「相続税・贈与税関係租税特別措置法通達逐条解説(平成23年版)」((大蔵財務協会刊)42頁)
63 宅地等の所有者(被相続人)、建物等の所有者及び建物等の利用者に関する三者関係。
64 措置法69条の4第1項における「事業」の意義については、【資料2】(本稿(上)27頁)を参照。
65 措置法通達69の4-7(2)……(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)
66 有償による貸付けであれば、不動産貸付業などに該当し、貸付事業用宅地等(措法69の4③四)となります(特定同族会社事業用宅地等に該当する場合もあります)。なお、「無償」には、相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合も含まれています(措通69の4-4かっこ書)。
67 本文Ⅳ・2(27頁)の関連資料です。
68 居住用建物については、その定めを準用する旨、措通69の4-8(居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)などに定められています。
69 被相続人等の事業の用に供されていた建物等の移転を指しています。
70 同通達の定めは、特定事業用宅地等(措法69の4③一イ・ロ)に関するものですが、同通達の注書によって、特定居住用宅地等などの特例適用の可否を判定する際にも準用することができます。
第9回
「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(下)
税理士 塩野入文雄
(注)本稿(上)は、本誌No.568(2014.10.27)21頁に掲載されています。
Ⅱ「事業供用」等の判定(建物の所有者・事業者)
第2点目に、①(表九号下欄適用の前提整理として、)買換え取得する土地等の上に建築する建物等の所有者と事業者との関係〔同一の所有者であることが必要か?〔検討項目1〕〕、及び、②その土地等に係る「事業供用」(「事業用資産」としての該当性)の判定〔生計一親族であるZによる事業供用を通じて、どの範囲までの資産が、Xにとっての「事業用資産」に該当すると判定できるのか?〔検討項目2〕〕の2点について検討します。
1.検討項目
〔検討項目1〕建物等と土地等(敷地)の所有者について 表九号の適用に当たって「買換資産」を土地等とする場合、特定施設の敷地に該当することが必要です(脚注24)。具体的には、表九号下欄に、「土地等(事務所……(特定施設)……)の敷地の用に供されるもの……」と規定されており(脚注25)、その土地等が、特定施設に該当する建物等の「敷地」であることが求められています(脚注26)。
一方、同様に、表一号・表四号上欄においても、「譲渡資産」である土地等について、「事務所……又はその敷地の用に供されている土地等……」(表一号)、「事務所……として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等……」(表四号かっこ書)と規定されています(脚注27)。更に、この2つの号の規定を受け、措置法通達37-11の8に、「その敷地の用に供されている土地等」とは、「……建物の敷地の用に供されている当該建物を所有する者が有する土地等をいい、……」と定められています(脚注28)。
このため、「敷地」という同一文言による要件が付されている表九号下欄における買換資産についても、表一号上欄などと同じように、「建物(特定施設)の所有者=土地等の所有者」であることが必要なのかとの疑問も生じてくると思われます。
〔検討項目2〕「事業供用」の判定について 措置法通達37-22(33-43)の定めによる、生計一親族による事業供用の判定に関する拡張措置が及ぶ資産の範囲は、どこまでなのかという疑問も生じてくると思われます。
上記Qの事例(本稿(上)21頁)において、買換え取得する新土地の上に建築され、生計一親族のZによって事業の用に供される新建物(特定施設)の所有者が、a)譲渡者本人(X)である場合のほか、b)生計一親族の事業者(Z)である場合もあり得ます(脚注29)。
そこで、a)のケースについて、事例のA(答)のように、Xが買換え取得する新土地を「買換資産」(特例適用の対象資産)とし、その上に建築する新建物を買換資産としない点に関して、通達文言を形式的に解釈した場合、事業供用に関する拡張措置の対象とならないのではないかとの疑問となります。
また、b)のケースについては、Xの所有資産でない(Zの所有資産である)新建物を、Zが、その事業の用に供することを通じて、Xが取得した土地について事業の用に供したもの(事業用資産)として取り扱われるのかという疑問となります。
2.規定の解釈等〔筆者意見〕
〔検討項目1〕建物等と土地等(敷地)の所有者の関係について
○結論 表九号下欄の買換資産は、「建物(特定施設)の所有者≠土地等の所有者」であったとしても、その土地等を「買換資産」とすることが出来ます(脚注30)〔ただし、別途、事業供用及び敷地属性に関する検討が必要です〕。 その理由は、次のとおりです。
① 表一号・表四号上欄と表九号下欄における条文の規定が異なっています。
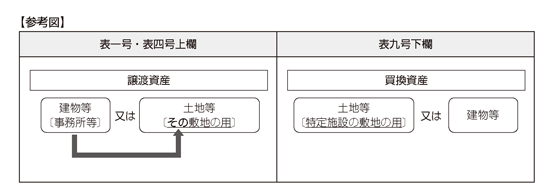
表一号上欄は、譲渡資産について、建物(事務所等)「又はその敷地の用に供されている土地等」と規定されています(脚注31)。ここで、「その」との文言は、買換え特例を適用する個人の譲渡資産が建物等(事務所等)及び土地等である場合(脚注32)、土地等がその建物等(譲渡した建物)の敷地であること、すなわち、譲渡資産である建物等及び土地等が同一の個人(譲渡者)の所有に属することを求めた規定となっています〔この制限は、平成3年度改正により講じられた措置であり、その趣旨等については、【資料4】③(29頁)を参照〕。
【資料4】建物等の所有者関係
① 条文(措法37①)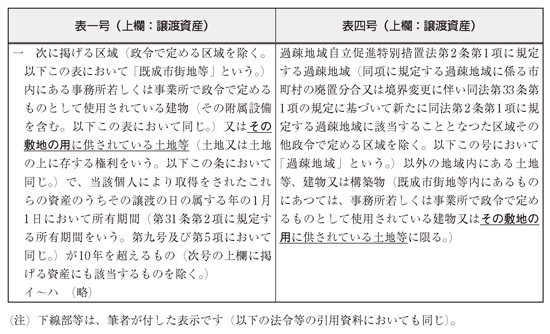 ② 措置法通達
③ 表一号の譲渡資産に係る制限について(改正の沿革関係) 表一号(既成市街地内から外への買換え)上欄における譲渡資産に関する制限(対象となる譲渡資産の範囲の限定)、すなわち、a)建物の用途及びb)その敷地であること(所有者)に関する制限は、平成3年度改正によって付加されたものです。同改正は、当時、「既成市街地等の内から外への買換えが、近年、東京都心部における地価上昇が周辺地域及び地方に波及する際の原因の一つとなったのではないか、……など、かえって土地政策上の弊害をもたらしているといった問題点の指摘があるほか、……」(「平成3年度税制改正のすべて」113頁)などの理由によるものです。 なお、同改正においては、貸付の用に供されていた事務所等(建物等)についても、対象資産から除かれていましたが(脚注59)、平成10年度改正により、その制限は廃止されています。 |
一方、表九号下欄は、買換資産の土地等が、特定施設の敷地であることを求めているに留まり、買換え取得する土地等について買換え特例を適用する個人と、その土地等上の特定施設の所有者との関係を問う規定になっていないと解されます。何故なら、取得した土地等に関する「敷地属性」(特定施設の敷地の用)は求められていますが、その特定施設の所有者との関係については、表一号・表四号上欄における、「その」に対応する限定(文言)が何ら規定されていないからです。
(注)表一号(表四号)上欄について措置法通達37-11の8の定めがわざわざ設けられている理由は、表一号における譲渡資産の範囲の限定が、平成3年度改正によって導入されたことに伴い、「その(譲渡資産である建物等の)敷地である」ことが要件となっている点に注意喚起を図ったと考えられ、また、そのような条文読解が必ずしも容易に行えるとは思われなかったため、同通達の定めを設けることで、その意味を確認(補充)する必要もあったと思われます。
② 次の〔検討項目2〕④に記述する改正趣旨等の視点からも、上記の解釈が可能と考えられます。
〔検討項目2〕「事業供用」の判定について
○結論
 「買換資産」となる(買換え特例の対象とする)土地等に係る事業供用の判定は、その土地等の上にある買換資産に該当しない建物等に係る事業供用の状況によっても判定することができ、また、
「買換資産」となる(買換え特例の対象とする)土地等に係る事業供用の判定は、その土地等の上にある買換資産に該当しない建物等に係る事業供用の状況によっても判定することができ、また、 譲渡者(X)の所有(取得)資産に該当しない建物等であっても、生計一親族(Z)による事業供用があれば、その判定は影響されない、と筆者は考えます。
その理由は、次のとおりです。
譲渡者(X)の所有(取得)資産に該当しない建物等であっても、生計一親族(Z)による事業供用があれば、その判定は影響されない、と筆者は考えます。
その理由は、次のとおりです。① 土地等に係る利用属性に関する判定の基本は、その上にある建物等の利用状況によっています。
例えば、土地等が事業の用に供されているかどうかの判定は、その上にある建物等の事業供用の状況によって判定されています(措通37-21(1)(脚注33))〔また、平成16年度改正前の税務処理において、別荘地にある土地のみを損失譲渡しても損益通算が可能で、その土地の上に別荘(建物)があれば、損益通算が不可となっていた点からも、その「別荘」(所令178①(脚注34))としての属性が、その土地の上にある建物の利用に応じて判定されていたことが分かります(脚注35)〕。
更に、「居住の用」に関する取扱いではあるものの、建物とその敷地の所有者が異なる場合であっても、それぞれの所有者が生計一親族であることなどを条件として、建物の利用状況を中心に構築されている居住用財産関係の特例(措法35など)の適用について、その土地の所有者にとっての居住用財産として取り扱われています(措通35-4(脚注36)など)。このような判定方法(緩和措置)は、「事業の用」に関しても通じると考えられ、また、「事業の用」、あるいは、事業用資産に関する特例であったとしても、特段、排除すべき理由はない、と筆者は考えます。
② 措置法通達37-22の準用に関する定めが、単純な準用の定めとなっています。
仮に、措置法通達33-43について、譲渡者に係る代替資産、すなわち、譲渡者の所有に属する代替資産(買換資産)が生計一親族の事業の用に供された場合のみに限って緩和対象にした定めであるとします。然りであるならば、上記〔検討項目1〕のとおり、もとより、表九号下欄が「土地所有者≠建物所有者」との法文構造になっているところ、建物等所有者(特定施設の所有者)の敷地の利用関係が、借地権によらずに使用貸借による場合もあることなどから、生計一親族による事業供用の判定に係る準用の定めが、現行通達のような単純な定めにはならないはずであると考えられます(脚注37)。
③ 後述Ⅲ(25頁)の「敷地属性」(特定施設の敷地の用)に関する「逐条解説」の記述からも、生計一親族による事業供用判定についても同様に取り扱われると考えられます。
④ 本特例の趣旨等からも、上記のように解されると考えられます。
買換え特例の趣旨や平成24年度改正による特定施設の敷地要件を追加した趣旨である「経済の活性化を図るとの政策目的」からも(脚注38)、例えば、上記Qの事例のように、X(譲渡者)が土地を買換え取得して、Z(生計一親族)が、その土地の上に特定施設を建築(所有権を取得)して事業を営むようなケースは、本特例の政策目的にも適った買換えであると考えられます(更に付言するならば、今日の高齢化社会における高齢者が保有する資産の活用にも資する買換え特例のあり方としても適切と思われます)。
なお、それぞれの特例における政策目的は異なるのでしょうが、このように解することを通じて、買換え特例と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)における「事業用」に関する取扱いとの一定の整合性が確保されることにもなります(次の<小規模宅地等の特例との接点
 >参照)。
>参照)。ところで、措置法通達37-22により準用されている同33-43の定めにおいて、事業者である生計一親族への貸付の態様(無償貸付・有償貸付)が明らかにされていないことから、無償貸付(使用貸借)を前提とした定めではないのか、という疑問も生じてきます。
しかしながら、同33-43の定めは、上述したとおり(Ⅰ・2(本稿(上)24頁))、所得税法56条の規定によって、XがZから受領する対価がXの収入金額にならない点(Zの必要経費にならない点)を考慮した措置であること、及び、小規模宅地等の特例適用に関する措置法通達69の4-4の定めのように、貸付の態様(無償貸付・有償貸付)が問われることなく、もっぱら生計一親族による事業供用であるか否かを、その適用条件としています。よって、生計一親族に対する有償貸付であっても、買換え特例の適用が可能であると考えられます。
<小規模宅地等の特例との接点
 >
小規模宅地等の特例の適用に当たって、「一定の条件」が付されてはいますが、対象宅地等を敷地とする建物等の所有者は、必ずしも、被相続人(X)である必要はありません。
>
小規模宅地等の特例の適用に当たって、「一定の条件」が付されてはいますが、対象宅地等を敷地とする建物等の所有者は、必ずしも、被相続人(X)である必要はありません。その「一定の条件」とは、特定事業用宅地等を適用する場合、①その宅地等の上にある建物等の所有者は、被相続人又はその親族(生計一親族又は生計別親族)に限られ、また、②その建物等の利用関係(建物等の所有者と事業者(被相続人又は生計一親族)との関係)も無償使用に限られており、かつ、③その建物等と宅地等の利用関係(宅地等の所有者である被相続人と建物等の所有者との関係)も無償使用によることが、その適用条件になっています(措通69の4-4・【資料5】(30頁)参照)。
【資料5】建物等の所有者・利用者と小規模宅地等の特例(脚注60)
| ① 概 要 小規模宅地等の特例の適用における対象宅地等の具体的な利用関係は、a)宅地等の所有者(脚注61)及びb)建物等の所有者並びにc)建物等の利用者の『三者関係』について、次図による当事者の組み合わせがあり得ます。 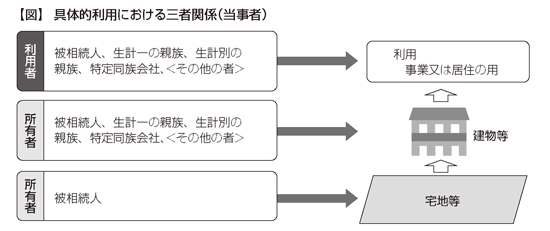 上図における三者関係の全てが被相続人であるならば、その判断は簡明ですが、実際的には、様々な態様(状況)があり、措置法通達の定めによって、その取扱いの明確化が図られています。 具体的には、措置法69条の4の規定(文言上)は、 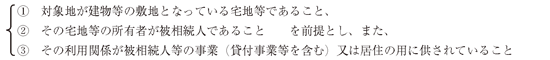 を、その特例適用要件として規定しているに留まっているところ、被相続人等の事業・居住の用に供していたものと認め得る範囲について、「本特例の趣旨及びこの特例が建物等の敷地として使用される宅地等に適用される制度であること」(脚注62)などを考慮して、その三者関係を明らかにしたとされている措置法通達69の4-4などの定めがあります。 ② 特定事業用宅地等に係る利用条件 特定事業用宅地等における、三者(脚注63)の「具体的利用関係」(自己利用、賃貸借、使用貸借)は、措置法通達69の4-4の定めによって、特例の適用の可否が明確化(補完)されています。 ただし、本項は、もっぱら措置法69の4第1項が定める「事業」の意義を明らかにしている定めとなっています(脚注64)。したがって、建物等の所有者や利用者が生計一親族である場合及び建物等の所有者が生計別親族である場合において、特定居住用宅地等に関する通達の定めのように(脚注65)、その敷地を被相続人から無償で借受けて(脚注66)いるとの条件が付されていません。しかしながら、特定事業用宅地等(措法69の4③一)に該当するためには、その借受けが無償であること、すなわち、貸付事業に該当しないことが必要になっています。 ○ 措通69の4-4(被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲)の定め 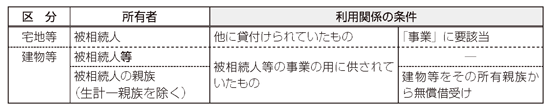 ○ 措置法通達
|
Ⅲ 建物及び敷地の利用関係(「敷地属性」)
上記Ⅱの検討の結果、両特例(脚注39)の適用を前提とした場合においても、買換資産である土地等の上に建築する建物等(特定施設)の所有者が、a)譲渡者本人(X)である場合とb)生計一親族の事業者(Z)である場合とが想定されます(脚注40)。
そこで、第3点目に、建物等及びその敷地に係る利用関係(無償・有償使用)と買換え特例の要件の一つである「敷地属性」(特定施設の敷地の用)との関係について検討します。
1.建物が譲渡者(X)所有の場合 表九号の適用に当たって、買換え取得する土地等の上に建築する建物等(特定施設)が譲渡者(X)によって所有されているものであれば、その「敷地属性」を充足していることに何ら疑問は生じてきません。
この場合、その建物等を無償貸付する場合と有償貸付する場合とが考えられます。
(1)XがZに対して建物を「無償貸付」 措置法通達37-22(33-43)の定めにより、その特定施設が生計一親族の事業の用に供されることになり、①事業(事業者・事業供用)要件を充足するとともに、②特定施設としての敷地属性(事業所の敷地としての利用属性)の要件も充足することになります。
(2)XがZに対して建物を「有償貸付」 もとより、準事業も含めた貸付も「事業」の範疇にあることから、事業要件とともに敷地属性の要件も充足しているところであり、加えて、生計一親族による事業供用に関する措置法通達37-22の定めの適用もあります。
<小規模宅地等の特例との接点
 >
上記と同様に、Xが取得した新建物(脚注41)を相続開始の直前において、Zに対して無償貸付している場合と、有償貸付している場合とが考えられます。無償貸付であれば、特段の問題はありませんが、有償貸付であった場合、小規模宅地等の特例の適用について、次の点に注意が必要です。
>
上記と同様に、Xが取得した新建物(脚注41)を相続開始の直前において、Zに対して無償貸付している場合と、有償貸付している場合とが考えられます。無償貸付であれば、特段の問題はありませんが、有償貸付であった場合、小規模宅地等の特例の適用について、次の点に注意が必要です。所得税法56条の規定は、もっぱら、所得税法における不動産所得などの事業における所得金額の計算における必要経費(収入金額)の処理に関する特則であって、他の課税場面に適用される規定とはなっていません(脚注42)。
Xが、その所有する新建物(病院)をZに対して賃貸した場合、Zが生計一親族であるXに家賃を払っても、所得税の税務処理においては、Xの不動産所得の収入金額にはなりません。しかしながら、小規模宅地等の特例の適用上、すなわち、相続税の税務処理に当たって、Xが所有する建物が「貸家」であるという課税事実までもが所得税法56条に基づいて否定される訳ではなく、その貸家としての利用事実がXに係る不動産貸付に該当する結果、その敷地は「貸家建付地」に該当すると認められ、特定事業用宅地等に該当せずに、「貸付事業用宅地等」に該当すると考えます(脚注43)(<小規模宅地等の特例との接点
 >(本稿(上)23頁)参照)。
>(本稿(上)23頁)参照)。なお、このように、所得税法56条と他の税法規定との適用関係に関する具体的な証左の一つに、消費税法基本通達5-1-10の定めがあることからも(【資料3】③(本稿(上)28頁)参照)、上記の点は首肯されると考えます。
2.建物が事業者(Z)所有の場合 買換え特例の適用に当たって、Xによって買換え取得される(「買換資産」とする)新土地の上に建築する新建物がZによって取得され、X所有(取得)の土地を敷地として利用する場合、その土地に関する「敷地属性」(特定施設の敷地の用)について検討します。
なお、当該ケースが、買換え特例における「事業供用」を充足すると考えられる点については、上記Ⅱ〔検討項目2〕((23頁)参照)において、筆者の意見を述べたとおりです。
(1)前提整理 個人間における土地の貸付、借地権などの設定については、権利金等の支払いを行わない(権利金等の認定課税を受けない)ことを前提にすると、a)使用貸借による場合(脚注44)が通例であり、また、実例が多いと思われませんが、b)相当地代による貸付の場合(脚注45)もあり得ます〔個人間に関しては、法人が関連してくる場合における「土地の無償返還に関する届出書」を税務署長に提出して借地権を設定する取扱い(脚注46)などの点は措置されていません〕。
この点を踏まえ、その利用態様に応じた、買換え特例(表九号)における「敷地属性」の要件について検討します。
(2)解釈等 「敷地属性」の具体的な態様(意義)に関して、措置法通達37-11の8に関する「逐条解説」599頁(脚注47)において、表一号・表四号上欄の譲渡資産について、土地(底地)の所有者甲が、①建物とその敷地(借地権)の所有者(権利者)である乙と生計一親族の関係にある場合は、その土地が表一号などの「譲渡資産に該当するものとして取り扱われることになる。」と(脚注48)、また、②両者が生計一親族の関係にない場合は、原則どおり、その建物の敷地は借地権であって、「甲が所有する土地(底地)は、これに〔筆注:譲渡資産(「その敷地」)〕に該当しない。」との解説が記述されています。すなわち、両者(甲及び乙)が、生計一親族の関係にない場合、借地権が設定されている底地は、建物の敷地足り得ないとことが明記されています(脚注49)。
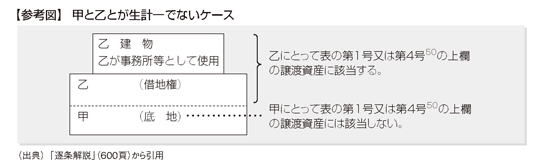
一方、表一号・表四号上欄と表九号下欄の規定における「敷地」の意義は同一に解されることから、表九号下欄における「敷地属性」についても、同様に取り扱われると考えられます。
① 土地をXが生計一親族であるZに対して「無償貸付」(使用借権の設定) 両者が生計一親族の関係にあれば、借地権が設定されている場合ですら敷地に該当するとされているので、使用貸借による場合も、敷地属性を充足することになります。
② 土地をXが生計一親族であるZに対して「有償貸付」(借地権の設定) 上記「逐条解説」の記述のとおり取り扱われているので、敷地属性を充足することになります(脚注51)。
<小規模宅地等の特例との接点
 >
上記<小規模宅地等の特例との接点
>
上記<小規模宅地等の特例との接点 ~
~ >(本稿(上)25頁ほか)に記述したとおりです。
>(本稿(上)25頁ほか)に記述したとおりです。Ⅳ その他の関連事項(買換え途中で相続開始があった場合)
上記Qの事例のように譲渡者(X)が高齢者である場合は、次の点にも注意が必要です。
1.買換え特例関係 Xが旧病院を譲渡し、譲渡年分(α1年分)に関する所得税の申告において、買換え特例を見積額に基づいて(買換え予定で)申告(脚注52)したが、その直後(α2年)に相続が開始した場合の処理は、次表のとおりです。
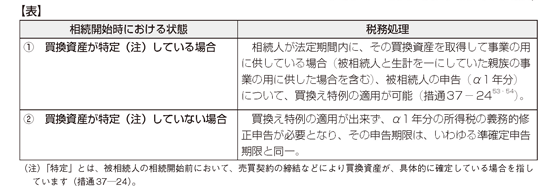
2.小規模宅地等の特例関係 新病院の建築中、Xに相続開始があった場合(Zによる新病院事業への供用前)における特定事業用宅地等の特例適用の可否について確認します。
小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等は、相続開始直前において、被相続人等(被相続人又は生計一親族)の事業(居住)の用に供されていた宅地等であることが、その適用要件の一つとなっています。しかしながら、上記Qの事例については、旧病院の敷地に新病院を建築(建替え)するのではなく、Xが新たに買換え取得する土地の上に建物を建築することから(かつ、建築中であることから)、その宅地等は、相続開始直前において、事業の用に供されていた宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例対象になりません。
なお、措置法通達69の4-5(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)の定めに基づく緩和措置は、相続開始直前に事業の用に供されていた宅地等に係る建物の建替え中などのケースに関する取扱いであって、上記のように新たに取得した宅地等が事業の用に供されていないケースまでをもカバーしている取扱いになっていません(脚注55)。
〔参考判例〕新規開業に向けて建築中であった事例 立体駐車場として事業(貸付事業)の用に供すべく建築に着手していた事例について(相続開始直後に事業に供用)、相続開始直前において現実に事業の用に供されていなかったことを理由として、特例の適用が否認された事案があります(最判平成10.2.26(脚注56)、東京高裁平成9.5.22(脚注57)、東京地裁平成8.6.21(脚注58))。
| ……本件特例は、課税の公平、迅速の観点から、一義的、明確な基準によってその適用要件を客観的、外形的に判断する必要があることからすれば、本件特例の可否の判断は、対象となる宅地の相続開始の直前における現実の利用状態をみて判断すべきであって、……一時的な中断と見られる場合を除き、現実に事業用宅地として利用していなければ本件特例を適用することはできないというべきである…… |
上記の点について、小規模宅地等の特例の創設の趣旨やその果たしている機能・効果などに鑑みれば、一律に、上記の結論に沿って処理することが適切なのかとの点に疑問が生じるところであり、例えば、買換え途中にあるケースについては、措置法通達37-24の定めに相当するような、何らかの緩和措置が講じられることが望まれます。
【資料6】建物等の建替えに関する取扱い(脚注67)
| ① 概要 事業用建物等の建替えなどについて、措置法通達69の4-5(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)及び同69の4-19(申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合)の定めが設けられています(脚注68)。 しかしながら、これらの取扱いの対象となる建替え等に関する定めは、次のとおり構成されており、例え、計画的な建替えに基づいていたとしても、上記Qの事例のように、新たに宅地等を取得し、かつ、新たな建物等を建築中で、相続開始時には、被相続人等の事業の用に供されていないケースまでをもカバーしている定めとなっていない点に注意が必要です。 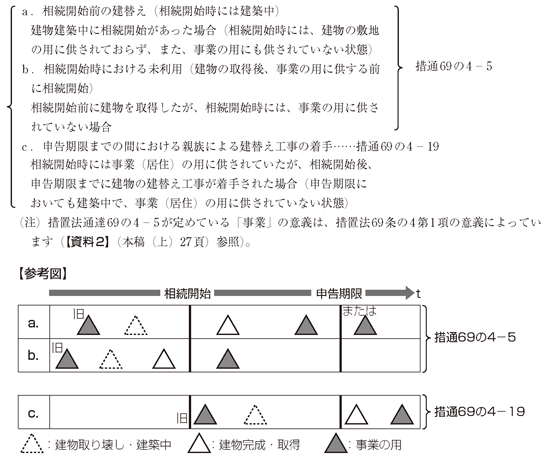 イ 上図a.及びb.のケースについて 次表の条件を充足していれば、特定事業用宅地等として判定することが可能です。 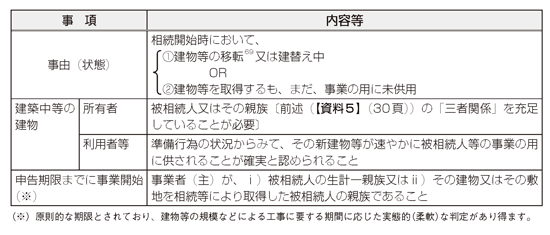 ロ 上図c.のケースについて 措置法通達69の4-19(申告期限までに事業用建物等を建替えた場合)の定めによります。この通達本文における「事業」の意義は、「狭義」(不動産貸付業などを除く)による定めとなっています(脚注70)。 ② 措置法通達
|
脚注
24 「特定施設の敷地」に関する要件の該当性についても、別途、後記Ⅲ(25頁)において検討します。
25 条文は、【資料1】①(本稿(上)25頁)を参照。他に、300㎡以上の面積要件(下限面積要件)などがあります。
26 「特定施設」の具体的用途は、【資料1】②(本稿(上)26頁)を参照。
27 条文は、【資料4】①(29頁)を参照。
28 通達文は、【資料4】②(29頁)を参照。
29 このほか、Z以外の親族が所有する建物となるケースも想定されます。
30 例えば、Xが取得した土地の上に、Z所有の建物(病院)を建築しても買換え特例の対象となります。
31 表四号も、表一号と同様です。
32 表一号は、譲渡資産が土地等のみである場合は、特例対象になっていません。
33 ただし、通達の文言は、「その者の建物、構築物等の建設等をする場合においても、……」と限定された定めとなっています。
34 見出し:生活に通常必要でない資産
35 平成16年度改正により、不動産の譲渡損失に係る損益通算が制限されたことから、現行法の下では、このような課税(判定)場面はありません。
36 表題:居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い
37 表九号は、〔検討項目1〕のとおり、土地等と建物等の所有者が異なり得ること、また、買換え特例における「事業」の意義に「貸付の用」も含まれており、特定施設としての利用が、譲渡者本人による利用に限られていません。このような点からも、表九号下欄において、土地等と建物等の所有者及びその利用者が異なる場合があり得ることは、国税当局においても、その想定の範囲内にあると思われます。
38 平成24年度改正前の表九号買換え特例については、「買換資産である土地等の用途に限定がなく、政策目的が曖昧であるという指摘があり、より付加価値の高い資産の買換えを促進し、経済の活性化を図るとの政策目的を明確化する観点から見直しが行われました。」(「平成24年度税制改正の解説」317頁)。
39 貸付事業用宅地等も含みます。
40 このほか、Z以外の親族が所有する建物であるケースも想定されます。
41 「買換資産」として取得するか、あるいは、自己資金等で取得するかなどの点を問いません。
42 「○○の金額の計算上」と、限定された規定となっています。したがって、その適用範囲を、根拠規定を欠いたまま相続税などに拡大適用することは違法な税務処理になります。
43 具体的には、貸家建付地として評価額を算定した上で、貸付事業用宅地等(措法69の4③四一)の対象とすることになります。
44 昭和48.11.1付個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の適用対象となります。
45 昭和60.6.5付個別通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の適用対象となります。
46 法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)の定めによる取扱いです。
47 直接的には、表一号及び表四号の譲渡資産に関する「その敷地の用に供されている土地等」に関する解説となっています。
48 措置法通達37-22(33-43)の取扱いの準用が、その根拠とされています。
49 例えば、同族会社が借地権上に特定施設を有している場合、その経営者(個人)が底地を取得しても買換え特例(表九号)の対象になりません。
50 現行条文(通達)に修正しています。
51 筆者には、上記の「逐条解説」に記述されている取扱いは、少なくとも、通達に織り込まれることが必要な取扱いではないかと思われます。何故なら、不動産所得などの事業に係る必要経費(収入金額)の算定に関する特則である所得税法56条の規定を、借地権が設定されている底地に関する「敷地属性」の判定にまで準用するには些か難があるように思われます。
52 措置法37条第4項に基づく申告を指しています。
53 表題:相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合
54 収用等の代替特例(措法33)、居住用の買換え特例(措法36の2)及び立体買換え特例(措法37の5)についても、それぞれ、措通33-45、同36の2-21及び同37の5-6に、同様の定めが設けられています。
55 【資料6】(31頁)を参照。通達文は、【資料6】②(32頁)を参照。
56 TAINS Z230-8098
57 TAINS Z223-7921
58 TAINS Z216-7742
59 平成3年度改正では、買換資産に関し、改正前は土地等の取得を伴わない建物等の取得が、その適用範囲から除かれていましたが、建物等(減価償却資産)のみによる買換えも特例対象となりました。
60 本文<小規模宅地等の特例との接点
 ~
~ >(本稿(上)25頁ほか)の関連資料です。
>(本稿(上)25頁ほか)の関連資料です。61 相続税の課税対象となる宅地等であり、被相続人が所有していることが前提となります。
62 加藤浩編「相続税・贈与税関係租税特別措置法通達逐条解説(平成23年版)」((大蔵財務協会刊)42頁)
63 宅地等の所有者(被相続人)、建物等の所有者及び建物等の利用者に関する三者関係。
64 措置法69条の4第1項における「事業」の意義については、【資料2】(本稿(上)27頁)を参照。
65 措置法通達69の4-7(2)……(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)
66 有償による貸付けであれば、不動産貸付業などに該当し、貸付事業用宅地等(措法69の4③四)となります(特定同族会社事業用宅地等に該当する場合もあります)。なお、「無償」には、相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合も含まれています(措通69の4-4かっこ書)。
67 本文Ⅳ・2(27頁)の関連資料です。
68 居住用建物については、その定めを準用する旨、措通69の4-8(居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)などに定められています。
69 被相続人等の事業の用に供されていた建物等の移転を指しています。
70 同通達の定めは、特定事業用宅地等(措法69の4③一イ・ロ)に関するものですが、同通達の注書によって、特定居住用宅地等などの特例適用の可否を判定する際にも準用することができます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























