解説記事2014年11月10日 【判例評釈】 外形標準課税の持株会社特例の分母と分子(2014年11月10日号・№570)
判例評釈
外形標準課税の持株会社特例の分母と分子
東京地判平成26年2月28日平成25(行ウ)99号
東京高判平成26年7月18日平成26(行コ)130号
立教大学法学部教授 浅妻章如
Ⅰ 事実の概要
平成21年3月31日以前において、訴外A社(外国法人である持株会社)が、訴外B社(内国法人)及びX社(原告。内国法人)の株式を100%保有し、Xは訴外C社(内国法人)の株式を100%保有していた。同年4月1日、Xを株式交換完全親会社とし、Bを株式交換完全子会社とする適格株式交換(法人税法2条12号の16)を行った(図1)。
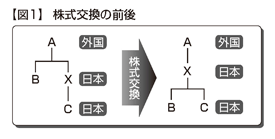
Xが同年4月1日に取得するBの株式の会計上の帳簿価額は、株式交換直前(3月31日)にBが付していた適正な帳簿価額による株主資本の額とされる(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針236-4及び236-5)。すなわち、494億3947万8742円(資本金及び資本準備金の合計)+137億4593万8217円(利益剰余金)=631億8541万6959円となる。
Xが同年4月1日に取得するBの株式の法人税法上の帳簿価額は、外国法人Aが有していたBの株式の株式交換直前(3月31日)の法人税法上の帳簿価額とされる(法人税法施行令119条1項9号イ)。すなわち、Aの出資金額である494億3947万8742円となる。適格組織再編成の前後で、AにとってのB株式の法人税法上の帳簿価額が、XにとってのB株式の法人税法上の帳簿価額へと引き継がれる。
Xは、平成22年6月30日及び平成23年6月30日に、平成22年3月期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)及び平成23年3月期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)に係る法人事業税の確定申告をした。Xは、法人事業税の資本割の持株会社特例に係る地方税法72条の21第5項2号が規定するところの内国法人(X)が保有する特定子会社(B)の株式の「帳簿価額」につき、会計上の帳簿価額と解釈していた。
「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成22年4月1日総税都第16号総務大臣通知。以下「本件取扱通知」)4の6の8柱書は、「法72条の21第5項2号に規定する帳簿価格は税務上の帳簿価格によること。」と定めている。平成24年3月27日、処分行政庁は、法人税法上の帳簿価額を前提として、Xの平成22年3月期及び平成23年3月期の法人事業税について、更正処分及び過少申告加算金の決定処分を行った(図2)。なお、分母が会計上の帳簿価額であることについて争いはない。
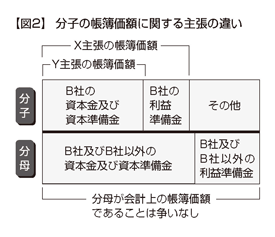
Xは次のように主張した──持株会社特例は、単純に「資本金等の額」を資本割の課税標準とした場合の、持株会社の「資本金等の額」及び子会社の「資本金等の額」の両方が課税されるという二重課税(多層構造の場合は多重課税)を防ぐために存在する。二重課税排除のためには持株会社特例の算式における分母と分子を統一的に解釈することが必要不可欠である。分母の「総資産の帳簿価額」は会計上の帳簿価額と解されるため、分子の「子会社株式の帳簿価額」も当然に会計上の帳簿価額と解される。東京湾横断道路建設事業者に対する資本割の課税標準に関する特例(地方税法附則9条7項。以下「横断道路特例」)において、資本割の課税標準である「資本金等の額」から「総資産の帳簿価額」のうちに「総務省令で定める未収金の帳簿価額」の占める割合を「資本金等の額」に乗じて計算した金額を控除することを定めているところ、横断道路特例の算式の分子の「帳簿価額」は「当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるもの」の「帳簿価額」であると規定されており、分母(「総資産」の「帳簿価額」)と同様に会計上の帳簿価額を意味する。本件取扱通知4の6の8柱書は違法である。
Y(被告。東京都)は次のように主張した──持株会社特例は、課税標準である資本金等の額について(二重課税防止ではなく)一定程度減額する措置を講じたものである。二重課税は持株会社のみならず子会社を有する法人一般に生じうる事態であり、持株会社についてのみ二重課税を排除する趣旨で持株会社特例が立法されたとは考えられない。地方税法上特段の規定がない「帳簿価額」は法人税法上の帳簿価額を意味する。「帳簿価額」が法人税法上の帳簿価額ではない場合には、地方税法72条の21第5項1号(持株会社特例の算式における分母)にある「確定した決算に基づく貸借対照表上に計上されている総資産の帳簿価額」という、会計上の概念であることを明らかにした限定規定が付記される。法人税法における負債利子控除の計算として総資産按分法(法人税法23条)が規定されていることを、持株会社特例において参照することには、合理性がある。
東京地裁は、下に引用する判旨①~⑤のように述べてXの請求を棄却した。
控訴審において、Xは次のような主張を追加した──販売用土地特例(平成21年法律第9号による改正前の地方税法附則9条9項)において、分子の帳簿価額が会計上の帳簿価額であるとは明示されていないが、会計上の帳簿価額と解するのが自然であり、持株会社特例の解釈に当たっても販売用土地特例と同様に解すべきである。下に引用する一審判旨②に関し、分子を会計上の帳簿価額とした方が、簡素で納税事務の小さい仕組みとなる。
東京高裁は、一審判決を全て引用し、追加主張についても判旨⑦~⑧のように述べて、控訴を棄却した。(X上告)
Ⅱ 判 旨
(請求棄却・控訴棄却) ① 「持株会社特例が設けられた趣旨は、資本割が外形標準課税のうちの補完的な項目であることを前提としつつ、株式等の保有を通じ子会社の事業活動を支配することを目的とする持株会社については、自らが行う事業活動に比して資本等の金額が多額のものとなっていることを考慮して、課税標準の算定上、一定の金額を控除することとしたものであるというべきであり、持株会社特例の適用により資本割に関する二重課税が一定の範囲で排除されるという効果を生じさせることにはなるものの、二重課税の排除を貫徹するという考え方に立脚するものとまではいえないと解することが相当である。」
② 「法人事業税の資本割の課税標準である資本金等の額が、法人税法上の資本金等の額を基にしていることについては……外形標準課税の導入時における基本的な考え方の一つであった簡素で納税事務負担の小さい仕組みを実現するために、新たな課税標準である付加価値額及び資本金等の額を導入するに当たり、これまでも法人税の税額計算に用いられる概念や数値等をできるだけ用いて算定することとしたものと考えられる。」
③ 「法人税法において『帳簿価額』という文言が用いられる場合、特段の規定がない限りは、法人税法上の帳簿価額であると解されている……ところ、[②]の点を踏まえれば、地方税法においても、特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』という文言については法人税法上の帳簿価額をいうものと解釈することが合理的であるということができる。」
「横断道路特例の算式の分子については、『未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額』という限定規定が付されているから、このような限定規定のない持株会社特例の算式の分子(特定子会社の株式の『帳簿価額』)を、横断道路特例の算式の分子と同様に理解すべき理由はない。」
④ 「[③]の点を踏まえれば、地方税法の委任を受けて定められた地方税法施行令においても、特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』については、法人税法上の『帳簿価額』と解釈することが合理的であるということができる。」
⑤ 法人税法23条4項、法人税法施行令22条が、負債利子控除に関し「『負債の利子の額の合計額』に『総資産の帳簿価額』のうちに『株式等の帳簿価額』の占める割合を乗じて計算する旨を規定している」ことについて、昭和40年度税制改正時に規定された法人税法施行令22条1「項1号は、負債利子控除の算式における分母について、『確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額』と規定しており、同改正前は税務計算上の総資産の帳簿価額とされていたものを、簡素化及び計算の安定性の見地から、貸借対照表上の総資産の帳簿価額すなわち会計上の総資産の帳簿価額へと改正したものである。同改正は、分母を税務計算上の総資産の帳簿価額とすると、個々の資産について税務上の更正等があった場合に納税者においてその計算を最初からやり直さなければならないなど、計算が極めて複雑になり、かつ安定性を欠く結果となっていたことから、分母を『貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額』と簡素化し,総資産について税務否認金の調整を要しないこととしたものである。……ただし、負債利子控除の算式における分子の株式等の『帳簿価額』については、資産のうち株式等の『帳簿価額』に限定されているため、その税務上の帳簿価額を計算させてもさほど複雑にはならないことから、同改正にもかかわらず、従前の税務計算上の『帳簿価額』のままとしたものと解される」。
⑥ 「持株会社特例に係る地方税法72条の21第5項及び地方税法施行令20条の2の19の規定が、負債利子控除に係る法人税法施行令22条の規定の用例を踏まえて規定されたことがうかがわれることに照らすと、持株会社特例の算式における分子の特定子会社の株式の『帳簿価額』について、負債利子控除の算式における分子の株式等の『帳簿価額』と同様に、法人税法上の帳簿価額と解することには、合理性があり、このような解釈は、既存の概念をできるだけ用いて納税事務の負担を小さくしようという外形標準課税導入時の基本的な考え方……にも沿うものということができる。」
以下、控訴審追加主張について
⑦ 「販売用土地特例は、上記3社にのみ適用される規定で、その適用期間も5年間と限定されたものである」。「特別の事情が存在することを前提とする販売用土地特例の解釈をもって、上記のような特別の事情もない他の通常の法人について、地方税法の本条に規定され同法所定の持株会社に一般的及び継続的に適用される持株会社特例の算式の分子の帳簿価額を会計上の帳簿価額と解すべきとする根拠にはならない。」
⑧ 「法人においては、特定子会社株式など有価証券は有価証券管理台帳等を作成して管理しているのが通常である上に、Xの特定子会社株式の会計上の帳簿価額と法人税法上の帳簿価額の差額は、法人税の申告に必要な別表5(1)に記載されている……。そこで、持株会社特例の算式における分子の帳簿価額を法人税法上の帳簿価額と解することにより、納税者に新たな事務負担を課することはなく、……簡素で納税事務負担の小さい仕組みという基本的な考え方に反することにはならない。」
Ⅲ 評 釈
(判旨反対)
1 本判決の意義と判旨の流れ (脚注1)本判決の意義は、持株会社特例の分母(地方税法72条の21第5項1号「貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」)と分子(同項2号「帳簿価額」)の表現の違いに着目し、分子は法人税法上の帳簿価額を意味するという判断をしたことにある。
一見するとこの判断は強烈に不合理な帰結をもたらす。子会社の資産が90であり、持株会社の総資産の会計上の帳簿価額が100であり、持株会社から見た子会社株式の会計上の帳簿価額が90であり、持株会社から見た子会社株式の法人税法上の帳簿価額が70である場合、子会社では90が課税ベースとなる一方、持株会社の方では、判旨によれば100×(1-70/100)=30が課税ベースとなる、という不整合(持株会社への救済が不足)が生じる。本件では、会計上の帳簿価額>法人税法上の帳簿価額、であるが、事案によっては、会計上の帳簿価額<法人税法上の帳簿価額、という事態も存在しうるため、会計上の帳簿価額が70、法人税法上の帳簿価額が90の場合、判旨によれば100×(1-90/100)=10が課税ベースとなる、という不整合(持株会社への救済が過剰)が生じる。
裁判官が前段落の不合理を認識しなかった筈はないため、裁判官がこの不合理を乗り越えて請求棄却に至った理由を、判旨から読み解く作業が要請される。ところで、判例評釈は、裁判官の内心の探求ではなく、書かれた判旨が法令・先例等に照らしてどう読まれるかを探求する作業である(従って書いた本人の内心の意思と一致しない可能性もある)(脚注2)、ということを念のためではあるが改めて予め確認しておく。
判旨の流れは次の通りである。
この判旨の流れの中で判旨⑥が結論である。この結論を導く上で判旨のどこが中核的な理由をなしているか。
まず、判旨①の意義は弱いと解される。判旨①判旨⑥を繋げると、持株会社特例は不完全な規定だから分母・分子がズレて不整合な救済となっても構わない、ということになる。しかし、仮に二重課税排除不徹底を前提とするとしても、分母・分子のズレの積極的な正当化理由となるものではない(脚注3)。【分母・分子がズレたら二重課税排除は徹底されないから解釈論としておかしい】という議論を斥けるという消極的な意義しか判旨①には認められない。従って判旨①の意義は無ではないが弱いと解される。
次に、判旨②は判旨⑥と結びついている(更に判旨⑧は判旨②の繰り返しである)ため、裁判官は判旨の流れの中で比較的強い意義を判旨②に持たせようとしている、と読める(判旨の内在的理解)。しかし、分子を会計上の帳簿価額と解することが「簡素で納税事務負担の小さい仕組み」を阻害するとは考えにくく(判旨の外在的批判)、更に、判旨⑧はX主張への応答になってない。
次に、判旨②③④は、判決文中では「『帳簿価額』の文言解釈」という表題の下で論じられている箇所であり、その中でも③④について裁判官は判旨の形式的根拠としての意義を持たせようとしている、と読める。そして、実質的考慮として、判旨⑤において負債利子控除が参考となると論じる一方、判旨⑦において販売用土地特例は参考とならないと論じている、というのが判旨の流れである。しかし、○○が××と関係し△△が××と関係しない、という作文は容易であり、本件では【販売用土地特例は地方税法に関するものであるから参考となり、負債利子控除は法人税法に関するものであるから参考にならない】という考え方もありえよう。また、判旨③④の反例として販売用土地特例が示されてしまったので、反例に目を瞑って判旨⑦は単に強弁しているだけ、とも読みうる。
以上より、評釈として限られた字数(脚注4)の中で焦点を当てるべきは判旨③④であると考えられる。
2 租税法令における用語の解釈 借用概念(脚注5)の問題として従来盛んに論じられてきたのは、租税法令が民法・商法など他の法分野から概念を借用している場合に、借用元における意味と同じ意味に解釈すべきか、という問題であった。これに対し、判旨③④は、【或る租税法令の用語の解釈において別の租税法令における概念と同じ意味に解釈すべきか】という問題を扱っている。しかし、或る租税法令が別の租税法令の概念を借用する場合は借用している旨を明示することが通例であるところ、限定のない「帳簿価額」が法人税法上の帳簿価額を指しているという一般論が成り立つのか、という疑問が呈せられる。
借用概念に限られない租税法上の用語の解釈に関する先例としてしばしば引用されるのが、いわゆるホステス報酬計算期間事件・最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁である。所得税法施行令322条の「5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」の解釈に際し、必要経費概算控除の観点から各ホステスの実際の出勤日数を意味するとした国側の主張を斥け、単純な日数を意味すると最高裁は判示した。これは、文言から外れた解釈をいましめるものではある。但し、立法趣旨を考慮しないということまで意味するものではない(脚注6)。ホステス報酬計算期間事件では「[国側主張の解釈が]文言上困難であるのみならず、ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採られた趣旨は、できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあった」と判示されている。
他方、借用概念ではあっても借用元における意味と異なる意味に解釈した先例としてしばしば引用されるのが、浜名湖競艇場用地事件・東京高判昭和62年9月9日行集38巻8=9号987頁である。60条1項「1号の『贈与』とは、単純贈与と贈与者に経済的利益を生じない負担付贈与をいう」と判示し、負担付贈与の事案で贈与者から受贈者への租税属性(取得価額、保有期間等)を引き継がないとした事例であり、その理由として「課税時期の繰り延べが認められるためには、資産の譲渡があっても、その時期に譲渡所得課税がされない場合でなければならない」と判示したものである。「借用概念は、原則として、本来の法分野におけると同じ意義に解釈すべき」(脚注7)とされるものの、同時に「別意に解すべきことが租税法規の明文またはその趣旨から明らかな場合は別として」(脚注8)ともいわれている。浜名湖競艇場用地事件は、譲渡人の手元で課税し譲受人の手元で租税属性を更新するか、譲渡人の手元で課税しない代わりに譲受人に租税属性を引き継がせるか、という所得税法60条の趣旨及び所得税法の構造(関連規定として所得税法33条・38条・59条)に照らした判断を示した好例と位置付けられる。
一見すると異なる解釈態度であるかのようなホステス報酬計算期間事件と浜名湖競艇場用地事件は、「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」(脚注9)で矛盾なく整理される。
本件判旨も、裁判官の内心としては、「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」によって導かれたものであろうと推測される。「文理」について判旨③④を述べ、「趣旨」に関してXの主張を否定する消極的論拠として判旨①を述べ、判旨③④の積極的補強材料として判旨②⑤を述べた、と読解されるからである。しかし、判旨の内在的理解としてはかように読解されるにしても、外在的疑問として、文理から判旨③④が導かれるのかという疑問は拭い難い。判旨①②は弱い意義しかない(評釈1参照)し、判旨⑤⑦も結論ありきならどうとでも書ける(評釈1参照)ため、繰り返しになるがやはり判旨③④が鍵である。
3 判旨③④:【限定のない「帳簿価額」という文言】という文理? ホステス報酬計算期間事件における「日数」という文言が出勤日数ではなく暦上の日数を意味するように、本件の分子の「帳簿価額」という文言は、会計との繋がりを想起させることから会計上の帳簿価額を意味する。このように考えることは、憲法84条の要請である予測可能性の確保、課税要件明確主義に資する。
これに対し、判旨③④は、【『帳簿価額』という文言】ではなく「特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』という文言」(縮めて【限定のない『帳簿価額』という文言】)に着目している。持株会社特例の分母につき「貸借対照表に計上されている」という限定が付されていることと対比して、分子の【限定のない『帳簿価額』という文言】には【限定のない】という文理上の意味がある、と判旨は考えている。分母と分子の規定振りの違いから、判旨③④は予測可能性を害しない、と考えているのであろう。
しかし、【分子が会計上の帳簿価額を意味するならば、その旨が明示される筈である】が判旨なりの文理解釈であるところ、【分子が法人税法上の帳簿価額を意味するならば、その旨が明示される筈である】という文理解釈と比べ、よくてどっこいどっこいであり、前々段落に述べたように「帳簿価額」という文言が会計との繋がりを想起させることと考え合わせると、【限定のない】ことを重視する判旨には疑問が残る。更に、判旨③④の反例もXは挙げている。
勿論、判旨は【限定のない】という文理だけを理由としているのではない。そこで次に、判旨①②⑤における既定の趣旨の理解が、裁判官の意図通りに判旨③④の補強材料になっているのかを見る。
4 【限定のない「帳簿価額」は法人税法上の帳簿価額を意味する】を補強する規定の趣旨と立案過程? 評釈1第2段落で見たように分母と分子とのズレを許容することは強烈な不合理をもたらすため、会計上の帳簿価額を用いる分母に合わせて、分子も(法人税法上のという特段の明示のない限り)会計上の帳簿価額を意味する、ということは規定の文理のみならず趣旨からも導きやすいところである。この不合理による違和感を封じようとするのが判旨①における二重課税排除不徹底という説明であるが、不徹底さが判旨⑥の結論を積極的に基礎付けるわけではないことは評釈1で既述した。
判旨②(及び⑧)についても、判旨の流れの中では強い意義があると内在的理解としては読めるものの、しかし外在的には説得力に乏しいことを、評釈1で既述した。
そうすると、判旨③④の文理解釈を支える趣旨に関する理由付けは判旨⑤から判旨⑥への流れである、ということになる。しかし、負債利子控除と同様に分母・分子を意図的にズレさせることが予定されていたならば、評釈1第2段落の不合理を呼び起こす制度となるわけであるから、そうしたズレの導入について相当量の議論が湧き起こった筈ではないか、との疑問が浮かぶ(脚注10)。この点に関し、判旨⑥が「持株会社特例……が、負債利子控除……を踏まえて規定されたことがうかがわれる」と述べてはいるものの、平成15年度税制改正大綱や平成14年10月1日税制調査会基礎問題小委員会資料等からも、ズレの導入に関するかような痕跡は見出しがたい(脚注11)。
以上をまとめると、判旨③④の文理解釈の妥当性には疑問が残る上に、判旨③④を補強しようとする判旨①・②(及び⑧)・⑤における既定の趣旨に関する理解も、評釈1第2段落の不合理を乗り越えるとはいいがたい、ということから、本評釈は結論として判旨に反対する。
余談:ところで、本件で分子を会計上の帳簿価額と判断した場合に、本件取扱通知4の6の8柱書を信じて法人税法上の帳簿価額の前提で申告していた別の納税者に不測の不利益(脚注12)が生じるかもしれない、ということを裁判官は懸念するかもしれないが、本件取扱通知が法源ではないといっても納税者を救済する道はありうる(脚注13)ので、本段落の問題はとりあえず無視して構わないであろう。
脚注
1 本評釈では、「 」『 』を引用のために用い、【 】を区切りの明確化のために用いる。人名に職名・敬称を付さない。
2 外税控除余裕枠りそな銀行事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁の「取引自体によっては外国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本件取引をあえて行う」という判示に関し、吉村政穂・判批・判例評論572号(判例時報1937号)184頁以下、186頁(2006.10)は、「要は、外国税額控除制度が、外国税を支払った後のネットの所得がマイナスになる場合をも救済する、まさにそのために設けられた制度だということである。(略)本件判決が損失の出る取引だと言及したことは、本件取引を全体としてみた結果を考慮に入れた、言い換えれば、本件ローン契約及び本件預金契約に基づく各取引を一体として考え得たという点にのみ意味がある。」と読解している。「本件取引をあえて行う」の判旨から内在的に「全体として」云々という読解を導くことは難しい(裁判官の内心に沿ったものではないかもしれない)が、判旨外在的に法令との整合性にも配慮すると「全体として」云々と読解せざるをえない、ということである。
勿論、前段落のようにいったからといって、判例評釈が評釈者の個性を表さないということを意味するのではなく、評釈者自身は客観的な読解に努めようとするものの、複数の評釈者の間で判旨の読解が異なりうることは、仕方のないことである。
3 高野幸大・判解・ジュリスト1468号8頁以下(2014.6)の解説Ⅱは、二重課税排除不徹底論が藁人形論法なのではないかという疑問を提示する。ただし、高裁判決文ではX主張が「[二重課税を]完全に排除することにある(一部の排除で足りるというのであれば、持株会社特例の算式における分子の子会社株式の帳簿価額を会計上の帳簿価額と解すべきことには必ずしもならない。)」に改められている。
4 予定字数を超過してしまったことについて編集部の配慮に感謝申し上げるが、それでも全論点について論じることは難しい。
5 金子宏『租税法』114頁(19版、弘文堂、2014)参照。
6 同旨・中里実ほか『租税法概説』43頁(有斐閣、2011、増井良啓執筆)。同頁は「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」の例として、ホステス報酬計算期間事件に続き、ガイアックス事件・最判平成18年6月19日判時1940号120頁(天然ガスから作ったガイアックスは地方税法700条の3第3項「炭化水素とその他の物との混合物」に該当せず軽油引取税が課せられないという主張を斥けた例)も挙げている。
7 金子・註5、116頁。
8 金子・註5、115-116頁。
9 註6より。増井良啓『租税法入門』311・314頁(有斐閣、2014)も参照。
10 なお、註6の「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」を基本とすることと合わせ、立案過程よりも法令の文言が解釈における最重要材料となるべきであり(それは課税要件明確主義に沿うのみならず、課税要件法定主義の見地からも、議会の意図は法令の文言に表現されている筈である)、立案過程は参照されうるにしても参照材料という位置付けにとどまり決め手となる訳ではないことからすると、仮に立案過程において分母・分子のズレの導入が議論されていたとしても、そこから直ちに【限定のない「帳簿価額」を法人税法上の帳簿価額と解す】という結論を導ける訳ではないのではないかとの疑問も湧くが、とりあえずその疑問は措く。
11 私の管見のせいであることも考えられるが、平成15年前後に分母・分子のズレの導入に関する議論が仮に存在していたならば、外形標準課税制度導入時に立案過程に実際に参加していた中里実(本件に関し意見書を執筆している)が、それを記憶していないとは考え難い。
12 Xの主張が常に納税者に有利であるとは限らないことについて評釈1第2段落参照。
13 註6、25頁(藤谷武史執筆)より抜粋――「通達は法源ではないが、だからといって法的に『無』であるわけでもない」。
外形標準課税の持株会社特例の分母と分子
東京地判平成26年2月28日平成25(行ウ)99号
東京高判平成26年7月18日平成26(行コ)130号
立教大学法学部教授 浅妻章如
Ⅰ 事実の概要
平成21年3月31日以前において、訴外A社(外国法人である持株会社)が、訴外B社(内国法人)及びX社(原告。内国法人)の株式を100%保有し、Xは訴外C社(内国法人)の株式を100%保有していた。同年4月1日、Xを株式交換完全親会社とし、Bを株式交換完全子会社とする適格株式交換(法人税法2条12号の16)を行った(図1)。
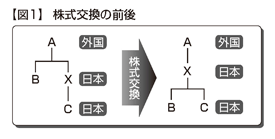
Xが同年4月1日に取得するBの株式の会計上の帳簿価額は、株式交換直前(3月31日)にBが付していた適正な帳簿価額による株主資本の額とされる(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針236-4及び236-5)。すなわち、494億3947万8742円(資本金及び資本準備金の合計)+137億4593万8217円(利益剰余金)=631億8541万6959円となる。
Xが同年4月1日に取得するBの株式の法人税法上の帳簿価額は、外国法人Aが有していたBの株式の株式交換直前(3月31日)の法人税法上の帳簿価額とされる(法人税法施行令119条1項9号イ)。すなわち、Aの出資金額である494億3947万8742円となる。適格組織再編成の前後で、AにとってのB株式の法人税法上の帳簿価額が、XにとってのB株式の法人税法上の帳簿価額へと引き継がれる。
Xは、平成22年6月30日及び平成23年6月30日に、平成22年3月期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)及び平成23年3月期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)に係る法人事業税の確定申告をした。Xは、法人事業税の資本割の持株会社特例に係る地方税法72条の21第5項2号が規定するところの内国法人(X)が保有する特定子会社(B)の株式の「帳簿価額」につき、会計上の帳簿価額と解釈していた。
「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成22年4月1日総税都第16号総務大臣通知。以下「本件取扱通知」)4の6の8柱書は、「法72条の21第5項2号に規定する帳簿価格は税務上の帳簿価格によること。」と定めている。平成24年3月27日、処分行政庁は、法人税法上の帳簿価額を前提として、Xの平成22年3月期及び平成23年3月期の法人事業税について、更正処分及び過少申告加算金の決定処分を行った(図2)。なお、分母が会計上の帳簿価額であることについて争いはない。
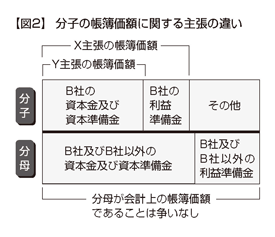
Xは次のように主張した──持株会社特例は、単純に「資本金等の額」を資本割の課税標準とした場合の、持株会社の「資本金等の額」及び子会社の「資本金等の額」の両方が課税されるという二重課税(多層構造の場合は多重課税)を防ぐために存在する。二重課税排除のためには持株会社特例の算式における分母と分子を統一的に解釈することが必要不可欠である。分母の「総資産の帳簿価額」は会計上の帳簿価額と解されるため、分子の「子会社株式の帳簿価額」も当然に会計上の帳簿価額と解される。東京湾横断道路建設事業者に対する資本割の課税標準に関する特例(地方税法附則9条7項。以下「横断道路特例」)において、資本割の課税標準である「資本金等の額」から「総資産の帳簿価額」のうちに「総務省令で定める未収金の帳簿価額」の占める割合を「資本金等の額」に乗じて計算した金額を控除することを定めているところ、横断道路特例の算式の分子の「帳簿価額」は「当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるもの」の「帳簿価額」であると規定されており、分母(「総資産」の「帳簿価額」)と同様に会計上の帳簿価額を意味する。本件取扱通知4の6の8柱書は違法である。
Y(被告。東京都)は次のように主張した──持株会社特例は、課税標準である資本金等の額について(二重課税防止ではなく)一定程度減額する措置を講じたものである。二重課税は持株会社のみならず子会社を有する法人一般に生じうる事態であり、持株会社についてのみ二重課税を排除する趣旨で持株会社特例が立法されたとは考えられない。地方税法上特段の規定がない「帳簿価額」は法人税法上の帳簿価額を意味する。「帳簿価額」が法人税法上の帳簿価額ではない場合には、地方税法72条の21第5項1号(持株会社特例の算式における分母)にある「確定した決算に基づく貸借対照表上に計上されている総資産の帳簿価額」という、会計上の概念であることを明らかにした限定規定が付記される。法人税法における負債利子控除の計算として総資産按分法(法人税法23条)が規定されていることを、持株会社特例において参照することには、合理性がある。
東京地裁は、下に引用する判旨①~⑤のように述べてXの請求を棄却した。
控訴審において、Xは次のような主張を追加した──販売用土地特例(平成21年法律第9号による改正前の地方税法附則9条9項)において、分子の帳簿価額が会計上の帳簿価額であるとは明示されていないが、会計上の帳簿価額と解するのが自然であり、持株会社特例の解釈に当たっても販売用土地特例と同様に解すべきである。下に引用する一審判旨②に関し、分子を会計上の帳簿価額とした方が、簡素で納税事務の小さい仕組みとなる。
東京高裁は、一審判決を全て引用し、追加主張についても判旨⑦~⑧のように述べて、控訴を棄却した。(X上告)
Ⅱ 判 旨
(請求棄却・控訴棄却) ① 「持株会社特例が設けられた趣旨は、資本割が外形標準課税のうちの補完的な項目であることを前提としつつ、株式等の保有を通じ子会社の事業活動を支配することを目的とする持株会社については、自らが行う事業活動に比して資本等の金額が多額のものとなっていることを考慮して、課税標準の算定上、一定の金額を控除することとしたものであるというべきであり、持株会社特例の適用により資本割に関する二重課税が一定の範囲で排除されるという効果を生じさせることにはなるものの、二重課税の排除を貫徹するという考え方に立脚するものとまではいえないと解することが相当である。」
② 「法人事業税の資本割の課税標準である資本金等の額が、法人税法上の資本金等の額を基にしていることについては……外形標準課税の導入時における基本的な考え方の一つであった簡素で納税事務負担の小さい仕組みを実現するために、新たな課税標準である付加価値額及び資本金等の額を導入するに当たり、これまでも法人税の税額計算に用いられる概念や数値等をできるだけ用いて算定することとしたものと考えられる。」
③ 「法人税法において『帳簿価額』という文言が用いられる場合、特段の規定がない限りは、法人税法上の帳簿価額であると解されている……ところ、[②]の点を踏まえれば、地方税法においても、特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』という文言については法人税法上の帳簿価額をいうものと解釈することが合理的であるということができる。」
「横断道路特例の算式の分子については、『未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額』という限定規定が付されているから、このような限定規定のない持株会社特例の算式の分子(特定子会社の株式の『帳簿価額』)を、横断道路特例の算式の分子と同様に理解すべき理由はない。」
④ 「[③]の点を踏まえれば、地方税法の委任を受けて定められた地方税法施行令においても、特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』については、法人税法上の『帳簿価額』と解釈することが合理的であるということができる。」
⑤ 法人税法23条4項、法人税法施行令22条が、負債利子控除に関し「『負債の利子の額の合計額』に『総資産の帳簿価額』のうちに『株式等の帳簿価額』の占める割合を乗じて計算する旨を規定している」ことについて、昭和40年度税制改正時に規定された法人税法施行令22条1「項1号は、負債利子控除の算式における分母について、『確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額』と規定しており、同改正前は税務計算上の総資産の帳簿価額とされていたものを、簡素化及び計算の安定性の見地から、貸借対照表上の総資産の帳簿価額すなわち会計上の総資産の帳簿価額へと改正したものである。同改正は、分母を税務計算上の総資産の帳簿価額とすると、個々の資産について税務上の更正等があった場合に納税者においてその計算を最初からやり直さなければならないなど、計算が極めて複雑になり、かつ安定性を欠く結果となっていたことから、分母を『貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額』と簡素化し,総資産について税務否認金の調整を要しないこととしたものである。……ただし、負債利子控除の算式における分子の株式等の『帳簿価額』については、資産のうち株式等の『帳簿価額』に限定されているため、その税務上の帳簿価額を計算させてもさほど複雑にはならないことから、同改正にもかかわらず、従前の税務計算上の『帳簿価額』のままとしたものと解される」。
⑥ 「持株会社特例に係る地方税法72条の21第5項及び地方税法施行令20条の2の19の規定が、負債利子控除に係る法人税法施行令22条の規定の用例を踏まえて規定されたことがうかがわれることに照らすと、持株会社特例の算式における分子の特定子会社の株式の『帳簿価額』について、負債利子控除の算式における分子の株式等の『帳簿価額』と同様に、法人税法上の帳簿価額と解することには、合理性があり、このような解釈は、既存の概念をできるだけ用いて納税事務の負担を小さくしようという外形標準課税導入時の基本的な考え方……にも沿うものということができる。」
以下、控訴審追加主張について
⑦ 「販売用土地特例は、上記3社にのみ適用される規定で、その適用期間も5年間と限定されたものである」。「特別の事情が存在することを前提とする販売用土地特例の解釈をもって、上記のような特別の事情もない他の通常の法人について、地方税法の本条に規定され同法所定の持株会社に一般的及び継続的に適用される持株会社特例の算式の分子の帳簿価額を会計上の帳簿価額と解すべきとする根拠にはならない。」
⑧ 「法人においては、特定子会社株式など有価証券は有価証券管理台帳等を作成して管理しているのが通常である上に、Xの特定子会社株式の会計上の帳簿価額と法人税法上の帳簿価額の差額は、法人税の申告に必要な別表5(1)に記載されている……。そこで、持株会社特例の算式における分子の帳簿価額を法人税法上の帳簿価額と解することにより、納税者に新たな事務負担を課することはなく、……簡素で納税事務負担の小さい仕組みという基本的な考え方に反することにはならない。」
Ⅲ 評 釈
(判旨反対)
1 本判決の意義と判旨の流れ (脚注1)本判決の意義は、持株会社特例の分母(地方税法72条の21第5項1号「貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」)と分子(同項2号「帳簿価額」)の表現の違いに着目し、分子は法人税法上の帳簿価額を意味するという判断をしたことにある。
一見するとこの判断は強烈に不合理な帰結をもたらす。子会社の資産が90であり、持株会社の総資産の会計上の帳簿価額が100であり、持株会社から見た子会社株式の会計上の帳簿価額が90であり、持株会社から見た子会社株式の法人税法上の帳簿価額が70である場合、子会社では90が課税ベースとなる一方、持株会社の方では、判旨によれば100×(1-70/100)=30が課税ベースとなる、という不整合(持株会社への救済が不足)が生じる。本件では、会計上の帳簿価額>法人税法上の帳簿価額、であるが、事案によっては、会計上の帳簿価額<法人税法上の帳簿価額、という事態も存在しうるため、会計上の帳簿価額が70、法人税法上の帳簿価額が90の場合、判旨によれば100×(1-90/100)=10が課税ベースとなる、という不整合(持株会社への救済が過剰)が生じる。
裁判官が前段落の不合理を認識しなかった筈はないため、裁判官がこの不合理を乗り越えて請求棄却に至った理由を、判旨から読み解く作業が要請される。ところで、判例評釈は、裁判官の内心の探求ではなく、書かれた判旨が法令・先例等に照らしてどう読まれるかを探求する作業である(従って書いた本人の内心の意思と一致しない可能性もある)(脚注2)、ということを念のためではあるが改めて予め確認しておく。
判旨の流れは次の通りである。
| ①:持株会社特例の趣旨は二重課税排除徹底ではなく「一定の金額を控除すること」にとどまる。 ②⑧:持株会社特例は、簡素で納税事務負担の小さい仕組みのため法人税の概念や数値をできるだけ用いようとしている。 ③④:地方税法及び地方税法施行令における無限定の「帳簿価額」は、法人税法上の「帳簿価額」を意味する。 ⑤:負債利子控除の分母と分子がズレていることは、持株会社特例の参考材料となる。 ⑥:持株会社特例の分母と分子がズレており、それは②の考慮に沿っている。 ⑦:販売用土地特例の「帳簿価額」が会計上の帳簿価額を指すことは、持株会社特例の参考材料にならない。 |
まず、判旨①の意義は弱いと解される。判旨①判旨⑥を繋げると、持株会社特例は不完全な規定だから分母・分子がズレて不整合な救済となっても構わない、ということになる。しかし、仮に二重課税排除不徹底を前提とするとしても、分母・分子のズレの積極的な正当化理由となるものではない(脚注3)。【分母・分子がズレたら二重課税排除は徹底されないから解釈論としておかしい】という議論を斥けるという消極的な意義しか判旨①には認められない。従って判旨①の意義は無ではないが弱いと解される。
次に、判旨②は判旨⑥と結びついている(更に判旨⑧は判旨②の繰り返しである)ため、裁判官は判旨の流れの中で比較的強い意義を判旨②に持たせようとしている、と読める(判旨の内在的理解)。しかし、分子を会計上の帳簿価額と解することが「簡素で納税事務負担の小さい仕組み」を阻害するとは考えにくく(判旨の外在的批判)、更に、判旨⑧はX主張への応答になってない。
次に、判旨②③④は、判決文中では「『帳簿価額』の文言解釈」という表題の下で論じられている箇所であり、その中でも③④について裁判官は判旨の形式的根拠としての意義を持たせようとしている、と読める。そして、実質的考慮として、判旨⑤において負債利子控除が参考となると論じる一方、判旨⑦において販売用土地特例は参考とならないと論じている、というのが判旨の流れである。しかし、○○が××と関係し△△が××と関係しない、という作文は容易であり、本件では【販売用土地特例は地方税法に関するものであるから参考となり、負債利子控除は法人税法に関するものであるから参考にならない】という考え方もありえよう。また、判旨③④の反例として販売用土地特例が示されてしまったので、反例に目を瞑って判旨⑦は単に強弁しているだけ、とも読みうる。
以上より、評釈として限られた字数(脚注4)の中で焦点を当てるべきは判旨③④であると考えられる。
2 租税法令における用語の解釈 借用概念(脚注5)の問題として従来盛んに論じられてきたのは、租税法令が民法・商法など他の法分野から概念を借用している場合に、借用元における意味と同じ意味に解釈すべきか、という問題であった。これに対し、判旨③④は、【或る租税法令の用語の解釈において別の租税法令における概念と同じ意味に解釈すべきか】という問題を扱っている。しかし、或る租税法令が別の租税法令の概念を借用する場合は借用している旨を明示することが通例であるところ、限定のない「帳簿価額」が法人税法上の帳簿価額を指しているという一般論が成り立つのか、という疑問が呈せられる。
借用概念に限られない租税法上の用語の解釈に関する先例としてしばしば引用されるのが、いわゆるホステス報酬計算期間事件・最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁である。所得税法施行令322条の「5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」の解釈に際し、必要経費概算控除の観点から各ホステスの実際の出勤日数を意味するとした国側の主張を斥け、単純な日数を意味すると最高裁は判示した。これは、文言から外れた解釈をいましめるものではある。但し、立法趣旨を考慮しないということまで意味するものではない(脚注6)。ホステス報酬計算期間事件では「[国側主張の解釈が]文言上困難であるのみならず、ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採られた趣旨は、できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあった」と判示されている。
他方、借用概念ではあっても借用元における意味と異なる意味に解釈した先例としてしばしば引用されるのが、浜名湖競艇場用地事件・東京高判昭和62年9月9日行集38巻8=9号987頁である。60条1項「1号の『贈与』とは、単純贈与と贈与者に経済的利益を生じない負担付贈与をいう」と判示し、負担付贈与の事案で贈与者から受贈者への租税属性(取得価額、保有期間等)を引き継がないとした事例であり、その理由として「課税時期の繰り延べが認められるためには、資産の譲渡があっても、その時期に譲渡所得課税がされない場合でなければならない」と判示したものである。「借用概念は、原則として、本来の法分野におけると同じ意義に解釈すべき」(脚注7)とされるものの、同時に「別意に解すべきことが租税法規の明文またはその趣旨から明らかな場合は別として」(脚注8)ともいわれている。浜名湖競艇場用地事件は、譲渡人の手元で課税し譲受人の手元で租税属性を更新するか、譲渡人の手元で課税しない代わりに譲受人に租税属性を引き継がせるか、という所得税法60条の趣旨及び所得税法の構造(関連規定として所得税法33条・38条・59条)に照らした判断を示した好例と位置付けられる。
一見すると異なる解釈態度であるかのようなホステス報酬計算期間事件と浜名湖競艇場用地事件は、「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」(脚注9)で矛盾なく整理される。
本件判旨も、裁判官の内心としては、「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」によって導かれたものであろうと推測される。「文理」について判旨③④を述べ、「趣旨」に関してXの主張を否定する消極的論拠として判旨①を述べ、判旨③④の積極的補強材料として判旨②⑤を述べた、と読解されるからである。しかし、判旨の内在的理解としてはかように読解されるにしても、外在的疑問として、文理から判旨③④が導かれるのかという疑問は拭い難い。判旨①②は弱い意義しかない(評釈1参照)し、判旨⑤⑦も結論ありきならどうとでも書ける(評釈1参照)ため、繰り返しになるがやはり判旨③④が鍵である。
3 判旨③④:【限定のない「帳簿価額」という文言】という文理? ホステス報酬計算期間事件における「日数」という文言が出勤日数ではなく暦上の日数を意味するように、本件の分子の「帳簿価額」という文言は、会計との繋がりを想起させることから会計上の帳簿価額を意味する。このように考えることは、憲法84条の要請である予測可能性の確保、課税要件明確主義に資する。
これに対し、判旨③④は、【『帳簿価額』という文言】ではなく「特段の限定規定を付さずに用いられている『帳簿価額』という文言」(縮めて【限定のない『帳簿価額』という文言】)に着目している。持株会社特例の分母につき「貸借対照表に計上されている」という限定が付されていることと対比して、分子の【限定のない『帳簿価額』という文言】には【限定のない】という文理上の意味がある、と判旨は考えている。分母と分子の規定振りの違いから、判旨③④は予測可能性を害しない、と考えているのであろう。
しかし、【分子が会計上の帳簿価額を意味するならば、その旨が明示される筈である】が判旨なりの文理解釈であるところ、【分子が法人税法上の帳簿価額を意味するならば、その旨が明示される筈である】という文理解釈と比べ、よくてどっこいどっこいであり、前々段落に述べたように「帳簿価額」という文言が会計との繋がりを想起させることと考え合わせると、【限定のない】ことを重視する判旨には疑問が残る。更に、判旨③④の反例もXは挙げている。
勿論、判旨は【限定のない】という文理だけを理由としているのではない。そこで次に、判旨①②⑤における既定の趣旨の理解が、裁判官の意図通りに判旨③④の補強材料になっているのかを見る。
4 【限定のない「帳簿価額」は法人税法上の帳簿価額を意味する】を補強する規定の趣旨と立案過程? 評釈1第2段落で見たように分母と分子とのズレを許容することは強烈な不合理をもたらすため、会計上の帳簿価額を用いる分母に合わせて、分子も(法人税法上のという特段の明示のない限り)会計上の帳簿価額を意味する、ということは規定の文理のみならず趣旨からも導きやすいところである。この不合理による違和感を封じようとするのが判旨①における二重課税排除不徹底という説明であるが、不徹底さが判旨⑥の結論を積極的に基礎付けるわけではないことは評釈1で既述した。
判旨②(及び⑧)についても、判旨の流れの中では強い意義があると内在的理解としては読めるものの、しかし外在的には説得力に乏しいことを、評釈1で既述した。
そうすると、判旨③④の文理解釈を支える趣旨に関する理由付けは判旨⑤から判旨⑥への流れである、ということになる。しかし、負債利子控除と同様に分母・分子を意図的にズレさせることが予定されていたならば、評釈1第2段落の不合理を呼び起こす制度となるわけであるから、そうしたズレの導入について相当量の議論が湧き起こった筈ではないか、との疑問が浮かぶ(脚注10)。この点に関し、判旨⑥が「持株会社特例……が、負債利子控除……を踏まえて規定されたことがうかがわれる」と述べてはいるものの、平成15年度税制改正大綱や平成14年10月1日税制調査会基礎問題小委員会資料等からも、ズレの導入に関するかような痕跡は見出しがたい(脚注11)。
以上をまとめると、判旨③④の文理解釈の妥当性には疑問が残る上に、判旨③④を補強しようとする判旨①・②(及び⑧)・⑤における既定の趣旨に関する理解も、評釈1第2段落の不合理を乗り越えるとはいいがたい、ということから、本評釈は結論として判旨に反対する。
余談:ところで、本件で分子を会計上の帳簿価額と判断した場合に、本件取扱通知4の6の8柱書を信じて法人税法上の帳簿価額の前提で申告していた別の納税者に不測の不利益(脚注12)が生じるかもしれない、ということを裁判官は懸念するかもしれないが、本件取扱通知が法源ではないといっても納税者を救済する道はありうる(脚注13)ので、本段落の問題はとりあえず無視して構わないであろう。
| 浅妻章如 あさつま あきゆき 横浜翠嵐高校卒、東京大学法学部卒・同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。立教大学法学部教授。修士論文「恒久的施設を始めとする課税権配分基準の考察─所謂電子商取引課税を見据えて─」国家学会雑誌115巻3・4号321頁(2002)、博士論文「所得源泉の基準、及びnetとgrossとの関係(1~3・完)」法学協会雑誌121巻8号1174頁、9号1378頁、10号1507頁(2004)。中里実ら『租税法概説』(有斐閣、2011)分担執筆。 |
脚注
1 本評釈では、「 」『 』を引用のために用い、【 】を区切りの明確化のために用いる。人名に職名・敬称を付さない。
2 外税控除余裕枠りそな銀行事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁の「取引自体によっては外国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本件取引をあえて行う」という判示に関し、吉村政穂・判批・判例評論572号(判例時報1937号)184頁以下、186頁(2006.10)は、「要は、外国税額控除制度が、外国税を支払った後のネットの所得がマイナスになる場合をも救済する、まさにそのために設けられた制度だということである。(略)本件判決が損失の出る取引だと言及したことは、本件取引を全体としてみた結果を考慮に入れた、言い換えれば、本件ローン契約及び本件預金契約に基づく各取引を一体として考え得たという点にのみ意味がある。」と読解している。「本件取引をあえて行う」の判旨から内在的に「全体として」云々という読解を導くことは難しい(裁判官の内心に沿ったものではないかもしれない)が、判旨外在的に法令との整合性にも配慮すると「全体として」云々と読解せざるをえない、ということである。
勿論、前段落のようにいったからといって、判例評釈が評釈者の個性を表さないということを意味するのではなく、評釈者自身は客観的な読解に努めようとするものの、複数の評釈者の間で判旨の読解が異なりうることは、仕方のないことである。
3 高野幸大・判解・ジュリスト1468号8頁以下(2014.6)の解説Ⅱは、二重課税排除不徹底論が藁人形論法なのではないかという疑問を提示する。ただし、高裁判決文ではX主張が「[二重課税を]完全に排除することにある(一部の排除で足りるというのであれば、持株会社特例の算式における分子の子会社株式の帳簿価額を会計上の帳簿価額と解すべきことには必ずしもならない。)」に改められている。
4 予定字数を超過してしまったことについて編集部の配慮に感謝申し上げるが、それでも全論点について論じることは難しい。
5 金子宏『租税法』114頁(19版、弘文堂、2014)参照。
6 同旨・中里実ほか『租税法概説』43頁(有斐閣、2011、増井良啓執筆)。同頁は「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」の例として、ホステス報酬計算期間事件に続き、ガイアックス事件・最判平成18年6月19日判時1940号120頁(天然ガスから作ったガイアックスは地方税法700条の3第3項「炭化水素とその他の物との混合物」に該当せず軽油引取税が課せられないという主張を斥けた例)も挙げている。
7 金子・註5、116頁。
8 金子・註5、115-116頁。
9 註6より。増井良啓『租税法入門』311・314頁(有斐閣、2014)も参照。
10 なお、註6の「規定の趣旨と文理に照らして解釈を行うという態度」を基本とすることと合わせ、立案過程よりも法令の文言が解釈における最重要材料となるべきであり(それは課税要件明確主義に沿うのみならず、課税要件法定主義の見地からも、議会の意図は法令の文言に表現されている筈である)、立案過程は参照されうるにしても参照材料という位置付けにとどまり決め手となる訳ではないことからすると、仮に立案過程において分母・分子のズレの導入が議論されていたとしても、そこから直ちに【限定のない「帳簿価額」を法人税法上の帳簿価額と解す】という結論を導ける訳ではないのではないかとの疑問も湧くが、とりあえずその疑問は措く。
11 私の管見のせいであることも考えられるが、平成15年前後に分母・分子のズレの導入に関する議論が仮に存在していたならば、外形標準課税制度導入時に立案過程に実際に参加していた中里実(本件に関し意見書を執筆している)が、それを記憶していないとは考え難い。
12 Xの主張が常に納税者に有利であるとは限らないことについて評釈1第2段落参照。
13 註6、25頁(藤谷武史執筆)より抜粋――「通達は法源ではないが、だからといって法的に『無』であるわけでもない」。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















