コラム2014年11月24日 【SCOPE】 遺留分に関する民法特例、親族外承継も対象に(2014年11月24日号・№572)
経営承継円滑化法の改正案が来年の通常国会へ
遺留分に関する民法特例、親族外承継も対象に
遺留分に関する民法の特例だが、親族外承継についても対象とする方向であることが分かった。来年の通常国会に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年法律第33号)の一部改正案が提出される運びだ。すでに事業承継税制については、平成25年度税制改正により、平成27年1月から親族外承継も同税制の対象となっており、これに合わせた見直しとなる。
現行は経営者の親族(推定相続人)のみが対象
事業承継においては、現経営者の保有する株式等の事業用資産を後継者に円滑に承継することが重要となるが、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとして生前贈与や遺言を行ったとしても、遺留分の制約があるため、株式が分散化するリスクがある。
このため、中小企業経営承継円滑化法では、「遺留分に関する民法の特例」を創設。この民法特例は、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)(図表1参照)、又は②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)(図表2参照)をすることができることとされている。
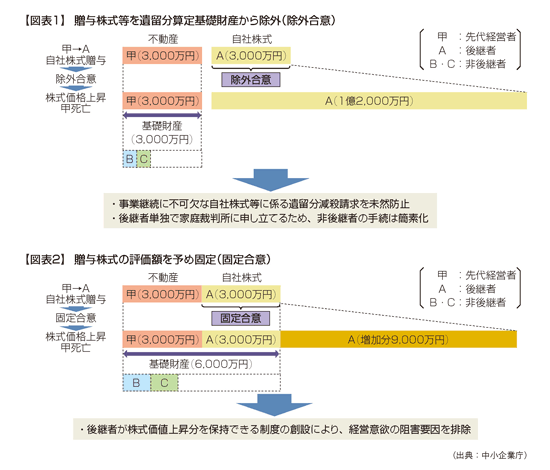 除外合意なら株式を対象外に
少し説明すると、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等は、その贈与がいつ行われたものであっても、民法の規定により、「特別受益」としてすべて遺留分算定基礎財産に算入され、原則として、遺留分減殺請求の対象となる。しかし、当該株式を除外合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないわけだ。
除外合意なら株式を対象外に
少し説明すると、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等は、その贈与がいつ行われたものであっても、民法の規定により、「特別受益」としてすべて遺留分算定基礎財産に算入され、原則として、遺留分減殺請求の対象となる。しかし、当該株式を除外合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないわけだ。
固定合意で株式の価額を固定 また、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額は、相続開始時を基準とする評価額となる。例えば、贈与時に3,000万円だった自社株式の価値が相続開始時に1億2,000万円に上昇していた場合には、価値の上昇分が後継者の努力によるものであったとしても、上昇後の1億2,000万円が遺留分算定基礎財産に算入されることになる。しかし、当該株式等を固定合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入すべき価額は3,000万円となり、価値上昇分の9,000万円については遺留分算定基礎財産に算入されないことになる。
この民法特例の適用を受けるには、3年以上継続して事業を行っている非上場企業であることなど、一定の要件を満たす必要があるが、事業承継を受ける者は合意時点において会社の代表者であることのほか、現経営者(法律上は旧代表者)の「親族」(推定相続人)に限られており、親族外承継は認められていない。
最近は親族外承継が増加傾向、事業承継税制は27年1月から対象
しかし、最近の事業承継では、以前は約9割で行われていた親族内承継も約6割に減少。その一方で親族外承継が約4割と増加傾向にある。このような背景もあり、平成25年度税制改正では平成27年1月より親族外承継も可能とする見直しが行われている。
このため、政府は、民法特例についても親族外承継を認めるよう、中小企業経営承継円滑化法の改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。
中小企業庁は、法改正により、民法特例と税制の乖離を是正するほか、親族外の者に株式を贈与で承継させた場合において、財産分与だけが目的で会社経営に無関心の親族から遺留分減殺請求をされてトラブルとなるといった事態を回避させたいとしている。
遺留分に関する民法特例、親族外承継も対象に
遺留分に関する民法の特例だが、親族外承継についても対象とする方向であることが分かった。来年の通常国会に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年法律第33号)の一部改正案が提出される運びだ。すでに事業承継税制については、平成25年度税制改正により、平成27年1月から親族外承継も同税制の対象となっており、これに合わせた見直しとなる。
現行は経営者の親族(推定相続人)のみが対象
事業承継においては、現経営者の保有する株式等の事業用資産を後継者に円滑に承継することが重要となるが、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとして生前贈与や遺言を行ったとしても、遺留分の制約があるため、株式が分散化するリスクがある。
このため、中小企業経営承継円滑化法では、「遺留分に関する民法の特例」を創設。この民法特例は、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)(図表1参照)、又は②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)(図表2参照)をすることができることとされている。
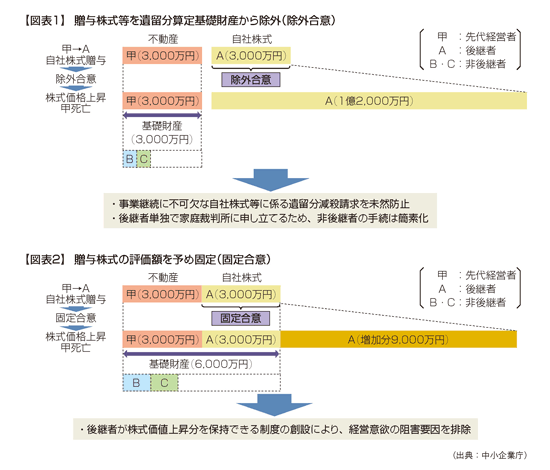 除外合意なら株式を対象外に
少し説明すると、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等は、その贈与がいつ行われたものであっても、民法の規定により、「特別受益」としてすべて遺留分算定基礎財産に算入され、原則として、遺留分減殺請求の対象となる。しかし、当該株式を除外合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないわけだ。
除外合意なら株式を対象外に
少し説明すると、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等は、その贈与がいつ行われたものであっても、民法の規定により、「特別受益」としてすべて遺留分算定基礎財産に算入され、原則として、遺留分減殺請求の対象となる。しかし、当該株式を除外合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないわけだ。固定合意で株式の価額を固定 また、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額は、相続開始時を基準とする評価額となる。例えば、贈与時に3,000万円だった自社株式の価値が相続開始時に1億2,000万円に上昇していた場合には、価値の上昇分が後継者の努力によるものであったとしても、上昇後の1億2,000万円が遺留分算定基礎財産に算入されることになる。しかし、当該株式等を固定合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産に算入すべき価額は3,000万円となり、価値上昇分の9,000万円については遺留分算定基礎財産に算入されないことになる。
この民法特例の適用を受けるには、3年以上継続して事業を行っている非上場企業であることなど、一定の要件を満たす必要があるが、事業承継を受ける者は合意時点において会社の代表者であることのほか、現経営者(法律上は旧代表者)の「親族」(推定相続人)に限られており、親族外承継は認められていない。
最近は親族外承継が増加傾向、事業承継税制は27年1月から対象
しかし、最近の事業承継では、以前は約9割で行われていた親族内承継も約6割に減少。その一方で親族外承継が約4割と増加傾向にある。このような背景もあり、平成25年度税制改正では平成27年1月より親族外承継も可能とする見直しが行われている。
このため、政府は、民法特例についても親族外承継を認めるよう、中小企業経営承継円滑化法の改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。
中小企業庁は、法改正により、民法特例と税制の乖離を是正するほか、親族外の者に株式を贈与で承継させた場合において、財産分与だけが目的で会社経営に無関心の親族から遺留分減殺請求をされてトラブルとなるといった事態を回避させたいとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















