解説記事2014年12月15日 【ニュース特集】 受取配当益金不算入規定はこう変わる!(2014年12月15日号・№575)
33.3%と5%を分岐点とする区分が新設
受取配当益金不算入規定はこう変わる!
法人税に関する平成27年度税制改正項目の中で、繰越欠損金の控除限度割合の縮小などとともに注目を集めているのが、受取配当の益金不算入規定の改正だ。会社やその顧問税理士等の間では、益金不算入割合の区分見直しに伴う税負担増加に備え、保有株式がより益金不算入割合の高い区分に入るよう株式を買い集める動きが早くも見られるが、このほど本誌取材により、改正の詳細が判明した。
現行制度では、受取配当の益金不算入割合に係る持分比率の区分は「100%」「25%以上100%未満」「25%未満」の3つとされるが、平成27年度税制改正によりこれが「100%」「33.3%以上100%未満」「5%以上33.3%未満」「5%未満」の4つに細分化され、「5%未満」の区分では益金不算入割合が20%に制限される。
改正の詳細とともに、その影響を探った。
持分比率の区分が「4つ」に細分化、一部負債利子控除なしに
受取配当益金不算入規定の改正の最大のポイントは、益金不算入割合に係る持分比率の区分の見直しだ。
現行制度上、受取配当の益金不算入割合は、持分比率に応じて、①100%の場合は、受取配当額の「全額」、②25%以上100%未満の場合は、「受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額」、③25%未満の場合は、「(受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額)×50%」――とされている。
平成27年度税制改正では、このうち「100%」以外の区分が「33.3%以上100%未満」「5%以上33.3%未満」「5%未満」の3つに細分化され、「5%以上33.3%未満」「5%未満」の区分では負債利子控除がなくなり、「5%未満」の区分では益金不算入割合が20%に制限される。「5%未満」の区分では全額益金算入となる可能性も指摘されていたが、最終的には一部益金不算入が認められることとなった(前ページの表参照)。
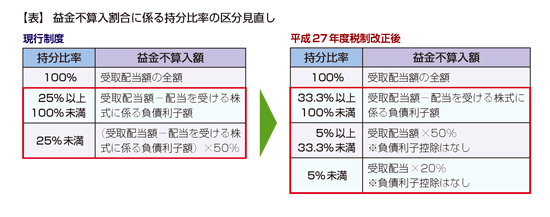
今回の改正の背景には、法人実効税率引下げに伴う税収の確保があることは言うまでもないが、同時に、「支配関係を目的とする場合」と「運用を目的とする場合」では配当に関する課税上の取扱いを明確に分けるべきとの問題意識がある。「保有割合5%未満」の株式はまさに「運用目的」に該当することになる。
株式投資信託の収益分配額は全額益金算入に、ETFは80%算入
現行制度上、株式投資信託の収益分配額については、その1/2の50%、あるいは1/4の50%の益金不算入が認められているが、平成27年度税制改正により、これが「全額益金算入」とされる。前段で述べたとおり、保有割合5%未満の株式は「運用目的」であることから益金不算入割合が20%に引き下げられるが、株式投資信託の保有は保有割合5%未満の株式以上に運用目的の性格が強いためだ。
株式投資信託は、メインバンクなどを通じ中小企業が購入するケースも少なくないだけに、本改正の影響は広範囲に及ぶことになるだろう。
株式投資信託同様、運用目的の性格を持つETF(Exchange Traded Funds)の収益分配額は現行、その全額の50%が益金不算入とされている。ETFも株式投資信託の一種ではあるが、こちらは5%未満の株式と同じく、「20%」の益金不算入が認められることになる(80%益金算入)。
改正の影響と対策
この改正を受け、会社やその顧問税理士等の間では、株式の保有割合引上げを検討する動きが広がることが予想される。
もっとも、4ページの表で示したとおり、33.3%以上の持分比率であれば、現行制度と益金不算入額は変わらないため、現状33.3%以上保有している会社の株式を買い増すインセンティブは薄い。
一時期、33.3%ではなく「50%」という数字が検討されていた際には、出資比率を「51:49」に設定するJV(合弁事業)への影響(出資比率49%の法人の税負担が増加)が懸念されていたが、33.3%となったことで、「51:49」のJVへの影響は回避される。また、「66:34」のJVも少なくないが、34%ではなく33.3%となったため、こちらも影響を受けない。
このように考えると、持分比率が33.3%未満、特に、平成27年度税制改正によって益金不算入割合が100%から50%に引き下げられることになる持分比率「25%以上33.3%未満」の会社の株式を買い増そうと考えるところは少なからず出てきそうだ。ただ、保有割合が33.3%超となれば、株主総会の特別決議を単独で阻止できることになる。このような株式保有を被保有会社が受け入れるかどうかは1つのハードルとなる可能性がある。
持分比率「25%以上33.3%未満」のケースとともに、税負担が大きく増えることになるのが、持分比率が「5%未満」のケースだ。銀行や損害保険会社はこの区分に属する上場会社株式を多数保有していることが多いが、多くの場合、持分比率は「1%未満」であり、これを「5%以上」にまでを引き上げるには、大量の資金を要することになる。また、独禁法および銀行法上、銀行は5%を超えて株式を保有することが禁止されているため、5%以上33.3%未満の区分に入るには、「5%」ちょうど保有するしかない。これは現実的ではないだろう。
一方、損害保険会社は10%までは株式を保有することができるため(独占禁止法および保険業法では、10%を超えて株式を保有することを禁止)、銀行よりも持分比率引上げはやりやすいとはいえ、やはり資金面の負担は大きい。したがって、今後、銀行や損害保険会社が保有株式を手放す動きに出ることも考えられ、株式市場への影響が懸念される。
なお、生命保険会社は、契約者配当が損金算入される代わりに、受取配当は元々益金不算入とならないため、今回の改正による影響は一切受けない。
「自己株式として取得されること」を予定した取得?
銀行や損害保険会社の例のように、株式を買い集める際にネックとなるのが資金だが、この資金を捻出するため、配当により子会社の資金を吸い上げるほか、子会社に親会社が保有する当該子会社株式(当該子会社にとっての自己株式)を買い取らせ、これによって得た資金を分散している当該子会社株式の取得に充てるという手法を検討する向きもある。
ただ、IBM事件を受け、平成22年度税制改正以降は、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式の譲渡」により生じたみなし配当については、受取配当等の益金不算入規定を適用しないこととされている(法法23条③)。そこで、今回の改正を受け子会社に自己株式を買い取らせた場合、これが税務当局に「自己株式として取得されることを予定して取得した株式の譲渡」と認定されるリスクが気になるところだ。
ただ、仮に平成27年度税制改正で受取配当課税が見直されるという話がなければ、そもそも資金捻出のために子会社に自己株式を取得させることもなかったと考えられるため、当該自己株式が「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」とは言い難い。受取配当課税の見直しの詳細をいち早く取り上げたのは本誌だが、少なくとも本誌の記事が掲載されるの前から保有している株式については、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」に当たることはあり得ないと言える。今回の改正に関連して法人税法23条3項が適用される可能性は極めて低いと考えてよさそうだ。
受取配当益金不算入規定はこう変わる!
法人税に関する平成27年度税制改正項目の中で、繰越欠損金の控除限度割合の縮小などとともに注目を集めているのが、受取配当の益金不算入規定の改正だ。会社やその顧問税理士等の間では、益金不算入割合の区分見直しに伴う税負担増加に備え、保有株式がより益金不算入割合の高い区分に入るよう株式を買い集める動きが早くも見られるが、このほど本誌取材により、改正の詳細が判明した。
現行制度では、受取配当の益金不算入割合に係る持分比率の区分は「100%」「25%以上100%未満」「25%未満」の3つとされるが、平成27年度税制改正によりこれが「100%」「33.3%以上100%未満」「5%以上33.3%未満」「5%未満」の4つに細分化され、「5%未満」の区分では益金不算入割合が20%に制限される。
改正の詳細とともに、その影響を探った。
持分比率の区分が「4つ」に細分化、一部負債利子控除なしに
受取配当益金不算入規定の改正の最大のポイントは、益金不算入割合に係る持分比率の区分の見直しだ。
現行制度上、受取配当の益金不算入割合は、持分比率に応じて、①100%の場合は、受取配当額の「全額」、②25%以上100%未満の場合は、「受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額」、③25%未満の場合は、「(受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額)×50%」――とされている。
平成27年度税制改正では、このうち「100%」以外の区分が「33.3%以上100%未満」「5%以上33.3%未満」「5%未満」の3つに細分化され、「5%以上33.3%未満」「5%未満」の区分では負債利子控除がなくなり、「5%未満」の区分では益金不算入割合が20%に制限される。「5%未満」の区分では全額益金算入となる可能性も指摘されていたが、最終的には一部益金不算入が認められることとなった(前ページの表参照)。
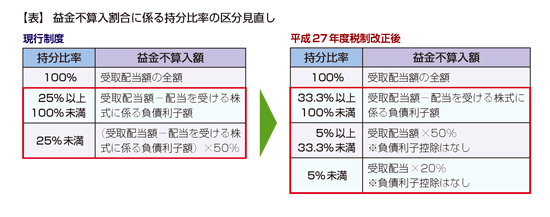
今回の改正の背景には、法人実効税率引下げに伴う税収の確保があることは言うまでもないが、同時に、「支配関係を目的とする場合」と「運用を目的とする場合」では配当に関する課税上の取扱いを明確に分けるべきとの問題意識がある。「保有割合5%未満」の株式はまさに「運用目的」に該当することになる。
株式投資信託の収益分配額は全額益金算入に、ETFは80%算入
現行制度上、株式投資信託の収益分配額については、その1/2の50%、あるいは1/4の50%の益金不算入が認められているが、平成27年度税制改正により、これが「全額益金算入」とされる。前段で述べたとおり、保有割合5%未満の株式は「運用目的」であることから益金不算入割合が20%に引き下げられるが、株式投資信託の保有は保有割合5%未満の株式以上に運用目的の性格が強いためだ。
株式投資信託は、メインバンクなどを通じ中小企業が購入するケースも少なくないだけに、本改正の影響は広範囲に及ぶことになるだろう。
株式投資信託同様、運用目的の性格を持つETF(Exchange Traded Funds)の収益分配額は現行、その全額の50%が益金不算入とされている。ETFも株式投資信託の一種ではあるが、こちらは5%未満の株式と同じく、「20%」の益金不算入が認められることになる(80%益金算入)。
改正の影響と対策
この改正を受け、会社やその顧問税理士等の間では、株式の保有割合引上げを検討する動きが広がることが予想される。
もっとも、4ページの表で示したとおり、33.3%以上の持分比率であれば、現行制度と益金不算入額は変わらないため、現状33.3%以上保有している会社の株式を買い増すインセンティブは薄い。
一時期、33.3%ではなく「50%」という数字が検討されていた際には、出資比率を「51:49」に設定するJV(合弁事業)への影響(出資比率49%の法人の税負担が増加)が懸念されていたが、33.3%となったことで、「51:49」のJVへの影響は回避される。また、「66:34」のJVも少なくないが、34%ではなく33.3%となったため、こちらも影響を受けない。
このように考えると、持分比率が33.3%未満、特に、平成27年度税制改正によって益金不算入割合が100%から50%に引き下げられることになる持分比率「25%以上33.3%未満」の会社の株式を買い増そうと考えるところは少なからず出てきそうだ。ただ、保有割合が33.3%超となれば、株主総会の特別決議を単独で阻止できることになる。このような株式保有を被保有会社が受け入れるかどうかは1つのハードルとなる可能性がある。
持分比率「25%以上33.3%未満」のケースとともに、税負担が大きく増えることになるのが、持分比率が「5%未満」のケースだ。銀行や損害保険会社はこの区分に属する上場会社株式を多数保有していることが多いが、多くの場合、持分比率は「1%未満」であり、これを「5%以上」にまでを引き上げるには、大量の資金を要することになる。また、独禁法および銀行法上、銀行は5%を超えて株式を保有することが禁止されているため、5%以上33.3%未満の区分に入るには、「5%」ちょうど保有するしかない。これは現実的ではないだろう。
一方、損害保険会社は10%までは株式を保有することができるため(独占禁止法および保険業法では、10%を超えて株式を保有することを禁止)、銀行よりも持分比率引上げはやりやすいとはいえ、やはり資金面の負担は大きい。したがって、今後、銀行や損害保険会社が保有株式を手放す動きに出ることも考えられ、株式市場への影響が懸念される。
なお、生命保険会社は、契約者配当が損金算入される代わりに、受取配当は元々益金不算入とならないため、今回の改正による影響は一切受けない。
「自己株式として取得されること」を予定した取得?
銀行や損害保険会社の例のように、株式を買い集める際にネックとなるのが資金だが、この資金を捻出するため、配当により子会社の資金を吸い上げるほか、子会社に親会社が保有する当該子会社株式(当該子会社にとっての自己株式)を買い取らせ、これによって得た資金を分散している当該子会社株式の取得に充てるという手法を検討する向きもある。
ただ、IBM事件を受け、平成22年度税制改正以降は、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式の譲渡」により生じたみなし配当については、受取配当等の益金不算入規定を適用しないこととされている(法法23条③)。そこで、今回の改正を受け子会社に自己株式を買い取らせた場合、これが税務当局に「自己株式として取得されることを予定して取得した株式の譲渡」と認定されるリスクが気になるところだ。
ただ、仮に平成27年度税制改正で受取配当課税が見直されるという話がなければ、そもそも資金捻出のために子会社に自己株式を取得させることもなかったと考えられるため、当該自己株式が「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」とは言い難い。受取配当課税の見直しの詳細をいち早く取り上げたのは本誌だが、少なくとも本誌の記事が掲載されるの前から保有している株式については、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」に当たることはあり得ないと言える。今回の改正に関連して法人税法23条3項が適用される可能性は極めて低いと考えてよさそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















