解説記事2014年12月15日 【解説】 最近の税務争訟の傾向と対策(2014年12月15日号・№575)
解説
最近の税務争訟の傾向と対策
EY 弁護士法人 弁護士 手塚崇史
弁護士 北村 豊
Ⅰ はじめに
近年、企業による国際的な活動の著しい増加に伴い、そのような企業が当事者となる取引も必然的に国際的となり多数の法域にまたがった複雑なものとなっている。課税当局は、このような国際的な取引についての適正な課税を実現するとの目的のもと、外部の弁護士や金融の専門家を登用するなどして、その総力を挙げて取引関係の把握とそれに基づいた課税問題を検討しているという状況にある。クロスボーダーの取引においては、そのような取引を我が国における課税との関係でどのように取り扱うかが明確に定まっているものは多くはなく、往々にして課税当局と納税者との間で見解の相違が生じ、それが税務争訟の場に持ち込まれることも増加している。
そこで、本稿では、以上のような状況について、近時の税務争訟の傾向という観点から検討するとともに、それに対して納税者はどのように対応すべきかについて論じることとする。
Ⅱ 近時の税務争訟の傾向
上記でみたように、クロスボーダーの取引においては、日本の課税上、どのような取引ないし状況として把握するかについて、必ずしも明確な基準はなく、しかも、その検討の前提としては、我が国の私法のみならず外国の私法も検討する必要が生ずる。また、クロスボーダーの取引においては、租税条約をはじめとして、ウィーン条約法条約(脚注1)やウィーン売買条約(脚注2)などの条約や国際法が関連することもある。これらの問題が、近時の税務争訟において問題となることが増えてきつつある。
1.国内外の私法が問題となる場合 租税法は、純粋に国内であろうが、あるいは、クロスボーダーであろうが、私法上の取引について適用されるのが基本であるので、国内外の私法の適用関係や解釈が、租税法規の適用の前提として問題となるのは当然である。
従来はともすれば、以上のような租税法規適用の前提となる国内外の私法の解釈をそれほどには重視することなく、むしろ直接的な租税法規の解釈適用の問題としてとらえてきた側面があったように思われる。しかしながら、近年では、租税法規の解釈・適用の前提として、検討対象となっている取引の私法上の性質が問題とされた裁判例が現れている。
具体的には、ある保険会社が、地震のように重大な保険事故(地震)が生じた場合には莫大な保険金支払額となるリスクを分散させるためにファイナイト保険契約を締結しようとしたが、日本にある保険会社がファイナイト契約を結ぶのではなく、アイルランドに子会社を作って、親会社と子会社が再保険契約をまず結び、そのアイルランドの子会社が、他の第三者の保険会社とさらにファイナイト再々保険契約を結んだ事例において、課税当局が更正処分をしたものがある。ファイナイト再保険においては、期間満了までの間に重大な事故が発生しなかった場合には、一定の要件を満たせば、保険料が還付される仕組みとなっていた。日本の保険会社にとっては、アイルランド子会社に対して再保険料を支払っており、支払保険料は損金としつつ、アイルランドの子会社がファイナイト再々保険料を払い、期間満了後の還付金をアイルランドで運用していたのであるが、課税当局は、アイルランドの子会社は導管に過ぎず、日本の親会社が直接ファイナイト保険契約を締結していた状況にあるとして、還付がなされる部分においてはアイルランド子会社に対する支払保険料の損金算入を否認したものである。本件は納税者の勝訴で確定(脚注3)したが、この判決では、私法上、保険であるものについては保険として課税上も扱うべき、との考え方が採られていると考えられよう。
以上のほか、デラウエア州LPSが日本の課税上、法人として扱われるか否かが争われた事例についても、デラウエア州LPS法が検討され、外国の私法が問題となっている(脚注4)。
2.条約や国際法が問題となる場合 近時の税務争訟においては、条約や国際法が問題となる事例も増加しつつあるといってよいであろう。これは、国際課税が問題となる局面においては、租税条約はもちろん一定の取引に関して適用可能性のあるその他の条約や、さらには国際法原則に配慮をする必要がある場合がある。そのような配慮を欠くと、場合によっては極めて奇異な判決となることもあり得るのであって、これらに対して慎重に検討することも必要である。
具体的には、外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン対策税制)が日本シンガポール租税条約に反するのではないかが争われた事例(脚注5)などがある。この事例は、条約が問題となった事例である。また、より一般的な国際法が問題となった事例としては、アメリカ大使館に勤務する日本の現地職員が同大使館から得ていた所得と大使館による源泉徴収義務の有無を争点としたものがある(脚注6)。当該事例では、国家(すなわち日本)が国家(すなわち米国)に対して、一方的に課税権を行使することは原則としてできないとするのが国際法上の法原理であるとの判断をしており、国際法の一般原則が問題となったということができる。
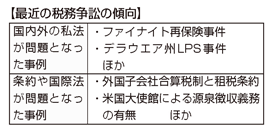
Ⅲ 近時の税務争訟の傾向を見据えた対策
以上のような近時の税務争訟の傾向を受けて、納税者としてはどのような対応が望ましいか、課税当局からのあり得べき指摘に対して、少しでもそのリスクを逓減させるためにはどのようにすべきかについて、以下論ずる。基本的には、税務と法務の双方から主張を行うということである。
1.国内外の私法からの対応 上記Ⅰにみたように、課税当局は、複雑な構成をとっている国際的な取引の課税問題に対処するため、外部の弁護士や金融の専門家を登用するなどして、その総力を挙げて取引関係の把握とそれに基づいた課税問題を検討しているという状況にある。このような課税当局の状況に適切に対応するためには、納税者の側においても、税務面での検討はもちろん、法務面からも十分な検討をすることが必要であることが容易に想像がつくであろう。
ルーティーン的な範疇にとどまる課税当局の指摘については、税務調査に精通した企業の経理部や税務部の担当者や、あるいは、調査官の思考を知り尽くした外部の税務専門家の関与で足りることがほとんどであろう。
しかしながら、シリアスな課税処分に至ることが推測されるような状況にあるときは、課税当局もまた税務面のみならず法務面からも相応の分析を経ていることが予測されるので、早期に企業の法務部や外部の法律家も関与させることで、問題となっている契約書の分析、取引に関する事実関係の認定などの検討を行って、課税当局に対して税務面と法務面を併せて適切に主張することにより、更正処分に至るリスクを減らすことが可能となる。また、このような調査段階からの法務部や法律家の関与により、その後不運にも更正処分が下され、不服申立てや訴訟に至ったとしても、納税者側の主張がぶれることなく、一貫した主張が可能となるというメリットも考えられる。さらに、訴訟の段階では、裁判所にとって租税法規に比べてはるかになじみ深い私法上の主張を、納税者側において早期から準備でき、勝訴の可能性も高まるということができる。訴訟段階においては、課税当局は、当然ではあるが、租税法の通達や会計原則など、課税当局が深く理解している土俵で主張を展開することが多い。しかしながら、そのような課税当局の主張に対してのみ反駁しても、それを裁判所に納得させることは難しいことが多いであろう。そもそも、課税当局がその得意とする土俵である税務上の主張について、裁判所によって認められないような主張を展開することもそれほどは多くない。そこで、納税者としては、課税当局の設定した土俵に乗って主張を展開して敗訴のリスクを高めるよりは、裁判所にとってよりなじみの深い私法上の主張を(税務上の主張とともに)展開していくことが望ましいといえる。そして、クロスボーダーの取引で私法が問題となる場合には、外国の私法が問題となることが多いから、そのような場合には、諸外国の法律に対する知識もまた必要になる。
2.条約や国際法からの対応 次に、条約や国際法への目配せをしたうえでの主張ができるかどうかも重要な観点である。このような観点もまた、法務の面からの主張の一つということができよう。
我が国では、条約や国際法は国内法に優位するという考え方が採られている。そのため、条約の考え方を自己の有利に援用できるのであれば、条約や国際法の側面から主張をしない手はないということができる。
3.その他~証拠法との関係 本項は、必ずしも最近の税務争訟の傾向と関連するものではなく、争訟一般に問題となるものであるが、税務問題が紛争段階となると、証拠法の問題も生ずることになる。これは、不服申立てや訴訟の場においては、どのように証拠を提出するか、ある証明すべき命題に対して適切な証拠は何か、証拠からどのような事実認定が可能か、ということが問題となるということを意味する。このような証拠法の問題は、やはり企業の法務部や外部の法律専門家が対処すべき領域であるということができる。企業の法務部や外部の法律専門家を税務問題に関与させるメリットの一つであるということができよう。
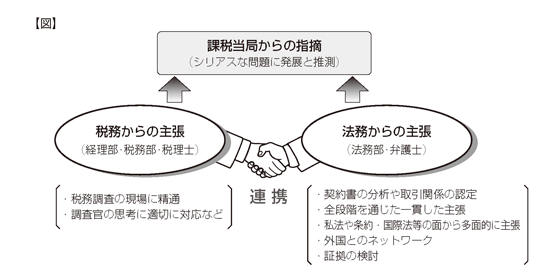
Ⅳ おわりに
繰り返しになるが、課税当局は、近年の複雑なクロスボーダーの取引についての課税に対処するために、その総力を挙げて対処をしてきている。そのような状況下においては、納税者サイドもまた、税務と法務が緊密に連携・協働して、十分に説得力のある主張を展開する必要がある。納税者がそのような主張を展開するに当たって外部の専門家を登用する場合には、税務(税理士)と法務(弁護士)が、いわば車の両輪としていかにスムーズに意思疎通ができるか、また、グローバルなネットワークが形成されており迅速かつ効率的な税務を含む外国法の分析や証拠収集が可能か、さらには必要に応じて会計上の問題も解決できるかなどが問われているといえよう。そのような対応が可能であれば、課税当局からの指摘に対しても非常に効果的な対応が可能となり、万一争訟に至ったとしても納税者サイドに不測の不利益が生ずるリスクを減らすことができる。
脚注
1 正式名称は「条約法に関するウィーン条約」である。
2 正式名称は「国際物品売買契約に関する国連条約」である。
3 東京高判平成22年5月27日判例時報2115号35頁。
4 名古屋高判平成25年1月24日LEX/DB文献番号25445906、東京高判平成25年3月13日LEX/DB文献番号25501415、大阪高判平成25年4月25日LEX/DB文献番号25445991。名古屋高判のみデラウエア州LPSは日本の課税上、法人ではないと判断し、東京高判と大阪高判は理由付けは異なるところがあるが、デラウエア州LPSについて法人該当性を肯定している。これらの事件は現在、最高裁判所に上告中である。
5 最判平成21年10月29日民集68巻8号1881頁。これは、納税者が敗訴している。なお、欧州諸国においては、我が国の外国子会社合算税制に相当する税制について、それが関連する租税条約に違反するのではないかが争われた事件があり、フランスでは、フランスのタックスヘイブン対策税制に相当する税制は、フランス・スイス租税条約に反するという判断が下されているものもあり(Schneider Electric事件)、上記最判事例における納税者側はこのフランスの事例を引用して主張を行っている。
6 判決はいくつかあるが代表的なものとして東京高判平成16年11月30日訟務月報51巻9号2512頁。結論としては、納税者が敗訴している。
最近の税務争訟の傾向と対策
EY 弁護士法人 弁護士 手塚崇史
弁護士 北村 豊
Ⅰ はじめに
近年、企業による国際的な活動の著しい増加に伴い、そのような企業が当事者となる取引も必然的に国際的となり多数の法域にまたがった複雑なものとなっている。課税当局は、このような国際的な取引についての適正な課税を実現するとの目的のもと、外部の弁護士や金融の専門家を登用するなどして、その総力を挙げて取引関係の把握とそれに基づいた課税問題を検討しているという状況にある。クロスボーダーの取引においては、そのような取引を我が国における課税との関係でどのように取り扱うかが明確に定まっているものは多くはなく、往々にして課税当局と納税者との間で見解の相違が生じ、それが税務争訟の場に持ち込まれることも増加している。
そこで、本稿では、以上のような状況について、近時の税務争訟の傾向という観点から検討するとともに、それに対して納税者はどのように対応すべきかについて論じることとする。
Ⅱ 近時の税務争訟の傾向
上記でみたように、クロスボーダーの取引においては、日本の課税上、どのような取引ないし状況として把握するかについて、必ずしも明確な基準はなく、しかも、その検討の前提としては、我が国の私法のみならず外国の私法も検討する必要が生ずる。また、クロスボーダーの取引においては、租税条約をはじめとして、ウィーン条約法条約(脚注1)やウィーン売買条約(脚注2)などの条約や国際法が関連することもある。これらの問題が、近時の税務争訟において問題となることが増えてきつつある。
1.国内外の私法が問題となる場合 租税法は、純粋に国内であろうが、あるいは、クロスボーダーであろうが、私法上の取引について適用されるのが基本であるので、国内外の私法の適用関係や解釈が、租税法規の適用の前提として問題となるのは当然である。
従来はともすれば、以上のような租税法規適用の前提となる国内外の私法の解釈をそれほどには重視することなく、むしろ直接的な租税法規の解釈適用の問題としてとらえてきた側面があったように思われる。しかしながら、近年では、租税法規の解釈・適用の前提として、検討対象となっている取引の私法上の性質が問題とされた裁判例が現れている。
具体的には、ある保険会社が、地震のように重大な保険事故(地震)が生じた場合には莫大な保険金支払額となるリスクを分散させるためにファイナイト保険契約を締結しようとしたが、日本にある保険会社がファイナイト契約を結ぶのではなく、アイルランドに子会社を作って、親会社と子会社が再保険契約をまず結び、そのアイルランドの子会社が、他の第三者の保険会社とさらにファイナイト再々保険契約を結んだ事例において、課税当局が更正処分をしたものがある。ファイナイト再保険においては、期間満了までの間に重大な事故が発生しなかった場合には、一定の要件を満たせば、保険料が還付される仕組みとなっていた。日本の保険会社にとっては、アイルランド子会社に対して再保険料を支払っており、支払保険料は損金としつつ、アイルランドの子会社がファイナイト再々保険料を払い、期間満了後の還付金をアイルランドで運用していたのであるが、課税当局は、アイルランドの子会社は導管に過ぎず、日本の親会社が直接ファイナイト保険契約を締結していた状況にあるとして、還付がなされる部分においてはアイルランド子会社に対する支払保険料の損金算入を否認したものである。本件は納税者の勝訴で確定(脚注3)したが、この判決では、私法上、保険であるものについては保険として課税上も扱うべき、との考え方が採られていると考えられよう。
以上のほか、デラウエア州LPSが日本の課税上、法人として扱われるか否かが争われた事例についても、デラウエア州LPS法が検討され、外国の私法が問題となっている(脚注4)。
2.条約や国際法が問題となる場合 近時の税務争訟においては、条約や国際法が問題となる事例も増加しつつあるといってよいであろう。これは、国際課税が問題となる局面においては、租税条約はもちろん一定の取引に関して適用可能性のあるその他の条約や、さらには国際法原則に配慮をする必要がある場合がある。そのような配慮を欠くと、場合によっては極めて奇異な判決となることもあり得るのであって、これらに対して慎重に検討することも必要である。
具体的には、外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン対策税制)が日本シンガポール租税条約に反するのではないかが争われた事例(脚注5)などがある。この事例は、条約が問題となった事例である。また、より一般的な国際法が問題となった事例としては、アメリカ大使館に勤務する日本の現地職員が同大使館から得ていた所得と大使館による源泉徴収義務の有無を争点としたものがある(脚注6)。当該事例では、国家(すなわち日本)が国家(すなわち米国)に対して、一方的に課税権を行使することは原則としてできないとするのが国際法上の法原理であるとの判断をしており、国際法の一般原則が問題となったということができる。
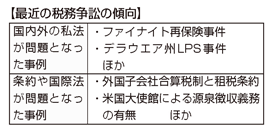
Ⅲ 近時の税務争訟の傾向を見据えた対策
以上のような近時の税務争訟の傾向を受けて、納税者としてはどのような対応が望ましいか、課税当局からのあり得べき指摘に対して、少しでもそのリスクを逓減させるためにはどのようにすべきかについて、以下論ずる。基本的には、税務と法務の双方から主張を行うということである。
1.国内外の私法からの対応 上記Ⅰにみたように、課税当局は、複雑な構成をとっている国際的な取引の課税問題に対処するため、外部の弁護士や金融の専門家を登用するなどして、その総力を挙げて取引関係の把握とそれに基づいた課税問題を検討しているという状況にある。このような課税当局の状況に適切に対応するためには、納税者の側においても、税務面での検討はもちろん、法務面からも十分な検討をすることが必要であることが容易に想像がつくであろう。
ルーティーン的な範疇にとどまる課税当局の指摘については、税務調査に精通した企業の経理部や税務部の担当者や、あるいは、調査官の思考を知り尽くした外部の税務専門家の関与で足りることがほとんどであろう。
しかしながら、シリアスな課税処分に至ることが推測されるような状況にあるときは、課税当局もまた税務面のみならず法務面からも相応の分析を経ていることが予測されるので、早期に企業の法務部や外部の法律家も関与させることで、問題となっている契約書の分析、取引に関する事実関係の認定などの検討を行って、課税当局に対して税務面と法務面を併せて適切に主張することにより、更正処分に至るリスクを減らすことが可能となる。また、このような調査段階からの法務部や法律家の関与により、その後不運にも更正処分が下され、不服申立てや訴訟に至ったとしても、納税者側の主張がぶれることなく、一貫した主張が可能となるというメリットも考えられる。さらに、訴訟の段階では、裁判所にとって租税法規に比べてはるかになじみ深い私法上の主張を、納税者側において早期から準備でき、勝訴の可能性も高まるということができる。訴訟段階においては、課税当局は、当然ではあるが、租税法の通達や会計原則など、課税当局が深く理解している土俵で主張を展開することが多い。しかしながら、そのような課税当局の主張に対してのみ反駁しても、それを裁判所に納得させることは難しいことが多いであろう。そもそも、課税当局がその得意とする土俵である税務上の主張について、裁判所によって認められないような主張を展開することもそれほどは多くない。そこで、納税者としては、課税当局の設定した土俵に乗って主張を展開して敗訴のリスクを高めるよりは、裁判所にとってよりなじみの深い私法上の主張を(税務上の主張とともに)展開していくことが望ましいといえる。そして、クロスボーダーの取引で私法が問題となる場合には、外国の私法が問題となることが多いから、そのような場合には、諸外国の法律に対する知識もまた必要になる。
2.条約や国際法からの対応 次に、条約や国際法への目配せをしたうえでの主張ができるかどうかも重要な観点である。このような観点もまた、法務の面からの主張の一つということができよう。
我が国では、条約や国際法は国内法に優位するという考え方が採られている。そのため、条約の考え方を自己の有利に援用できるのであれば、条約や国際法の側面から主張をしない手はないということができる。
3.その他~証拠法との関係 本項は、必ずしも最近の税務争訟の傾向と関連するものではなく、争訟一般に問題となるものであるが、税務問題が紛争段階となると、証拠法の問題も生ずることになる。これは、不服申立てや訴訟の場においては、どのように証拠を提出するか、ある証明すべき命題に対して適切な証拠は何か、証拠からどのような事実認定が可能か、ということが問題となるということを意味する。このような証拠法の問題は、やはり企業の法務部や外部の法律専門家が対処すべき領域であるということができる。企業の法務部や外部の法律専門家を税務問題に関与させるメリットの一つであるということができよう。
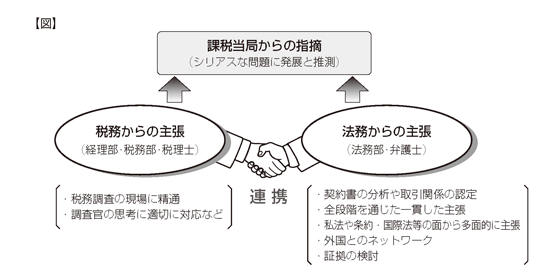
Ⅳ おわりに
繰り返しになるが、課税当局は、近年の複雑なクロスボーダーの取引についての課税に対処するために、その総力を挙げて対処をしてきている。そのような状況下においては、納税者サイドもまた、税務と法務が緊密に連携・協働して、十分に説得力のある主張を展開する必要がある。納税者がそのような主張を展開するに当たって外部の専門家を登用する場合には、税務(税理士)と法務(弁護士)が、いわば車の両輪としていかにスムーズに意思疎通ができるか、また、グローバルなネットワークが形成されており迅速かつ効率的な税務を含む外国法の分析や証拠収集が可能か、さらには必要に応じて会計上の問題も解決できるかなどが問われているといえよう。そのような対応が可能であれば、課税当局からの指摘に対しても非常に効果的な対応が可能となり、万一争訟に至ったとしても納税者サイドに不測の不利益が生ずるリスクを減らすことができる。
| 手塚崇史 てづか たかし 弁護士・ニューヨーク州弁護士。EY弁護士法人所属。九州大学法科大学院非常勤講師(租税法担当)。旧自治省・総務省勤務後、弁護士登録。法務・税務・会計の専門家が協働することにより付加価値の高いサービスを提供することができる税務争訟、税務調査対応のほか、アンチダンピング等の国際通商法、行政法、一般企業法務に関する法務・税務等に注力している。東京大学法学部・ハーバード大学ロースクール(International Tax Program)卒業。主な著書に「知的財産権取引の国際課税・国内課税」ほか、論文・講演多数。 |
| 北村 豊 きたむら ゆたか 弁護士・ニューヨーク州弁護士。EY弁護士法人マネージングパートナー(2013~)。京都大学法科大学院非常勤講師(税法事例演習)(2010~)。金融庁総務企画局政策課金融税制室課長補佐(2009~2012)を経て、2012年からEYグループに参加。法務・税務・会計の専門家が協働することにより付加価値の高いサービスを提供することができる税務訴訟、税務調査対応、金融取引に関する法務・税務等に注力している。東京大学法学部・ニューヨーク大学ロースクール(LLM in Taxation)卒業。 |
脚注
1 正式名称は「条約法に関するウィーン条約」である。
2 正式名称は「国際物品売買契約に関する国連条約」である。
3 東京高判平成22年5月27日判例時報2115号35頁。
4 名古屋高判平成25年1月24日LEX/DB文献番号25445906、東京高判平成25年3月13日LEX/DB文献番号25501415、大阪高判平成25年4月25日LEX/DB文献番号25445991。名古屋高判のみデラウエア州LPSは日本の課税上、法人ではないと判断し、東京高判と大阪高判は理由付けは異なるところがあるが、デラウエア州LPSについて法人該当性を肯定している。これらの事件は現在、最高裁判所に上告中である。
5 最判平成21年10月29日民集68巻8号1881頁。これは、納税者が敗訴している。なお、欧州諸国においては、我が国の外国子会社合算税制に相当する税制について、それが関連する租税条約に違反するのではないかが争われた事件があり、フランスでは、フランスのタックスヘイブン対策税制に相当する税制は、フランス・スイス租税条約に反するという判断が下されているものもあり(Schneider Electric事件)、上記最判事例における納税者側はこのフランスの事例を引用して主張を行っている。
6 判決はいくつかあるが代表的なものとして東京高判平成16年11月30日訟務月報51巻9号2512頁。結論としては、納税者が敗訴している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















