解説記事2015年01月12日 【ニュース特集】 法人税率引下げと課税ベース拡大、平成27年度の重要改正を読み解く(2015年1月12日号・№578)
繰越欠損金、外形標準課税が増税のターゲットに
法人税率引下げと課税ベース拡大、平成27年度の重要改正を読み解く
法人実効税率の引下げおよびそれに伴う課税ベース拡大をめぐる平成27年度税制改正議論が決着した。自由民主党および公明党が12月30日に取りまとめた税制改正大綱には、法人実効税率の段階的な引下げ(平成27年度は32.11%、平成28年度は31.33%に引下げ)が盛り込まれる一方で、欠損金繰越控除や受取配当益金不算入の縮減をはじめとする“増税項目”(課税ベース拡大)が複数盛り込まれることになった。
本特集では、企業に大きな影響を及ぼす重要改正項目のポイントを、自民党税制調査会や財務省などの資料をもとに図表を交えわかりやすく解説する。
平成27年度は32.11%(▲2.51%)に引き下げ
法人実効税率をめぐっては、昨年6月に閣議決定された「骨太の方針2014」のなかで「数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す。」と明記されていた。
だが、骨太の方針では、具体的な引下げ幅が明記されなかったため、平成27年度税制改正でどの程度の「引下げ幅」が実現するか、大きな注目が集まっていた。
28年度の法人実効税率は「31.33%」に 法人実効税率の「引下げ幅」は、平成27年度については「2.51%」で決着した(図表1参照)。
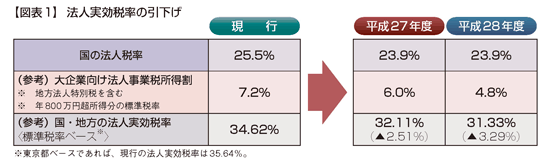
具体的にみると、国税である法人税の税率(現行25.5%)は、平成27年度は23.9%に引き下げられる。
また、地方税である法人事業税の所得割(現行7.2%、年800万円を超える所得分の標準税率)は、平成27年度は6.0%、平成28年度は4.8%に引き下げられる。この法人税および法人事業税所得割の税率引下げにより、法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度については「32.11%」(平成28年度は「31.33%」)に引き下げられる運びとなった。
28年度改正ではさらなる引下げも なお、平成28年度における法人実効税率の引下げ幅に関し大綱では、「課税ベースの拡大等により財源を確保して、平成28年度における税率引下げ幅の更なる上乗せを図る」と明記された。平成28年度税制改正では、法人実効税率のさらなる引下げが行われるかどうかに注目が集まりそうだ。
中小企業、軽減税率「15%」は2年延長 今回の法人税率の引下げは、主に大企業(資本金1億円超の法人)に対し適用される法人税率(現行25.5%)を23.9%に引き下げるというもの。資本金1億円以下の中小企業(年800万円以下の所得金額に限る)に適用される法人税率は現行どおり「19%」のままだ。
ただ、平成27年度税制改正では、中小企業に対する「19%」の法人税率をさらに「15%」まで軽減する租税特別措置(措法42の3の2)の2年延長(適用期限:平成28年度末まで)が決まっている。昨年6月の政府税制調査会の法人税改革案(本誌553号4頁参照)では、この軽減税率(措法15%部分)の廃止が盛り込まれていたが、中小企業に配慮するかたちで維持されることになった。
繰越欠損金の控除限度、27・28年度は65%、29年度は50%に
平成27年度税制改正では、法人実効税率が引き下げられる一方で、課税ベース拡大が複数項目にわたり実施される。なかでも、増税色が強い改正項目といえるのが「欠損金繰越控除の縮減」だ(図表2参照)。
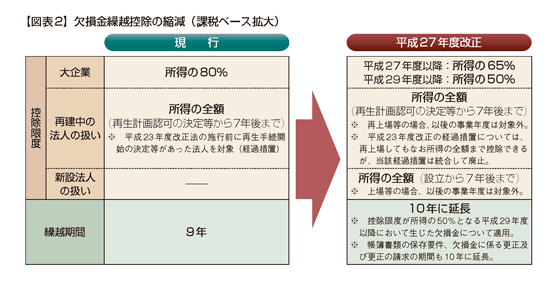
具体的には、大企業における繰越欠損金の控除限度割合(現行:所得の80%)を、平成27年度および平成28年度は「所得の65%」、平成29年度以降は「所得の50%」に引き下げる(再建中の法人や新設法人は7年後まで100%控除可)。
また、控除限度割合の引下げにあわせるかたちで、欠損金の繰越期間を現行の9年から10年に延長する。この繰越期間の延長は、平成29年度に生じた欠損金から適用される。
中小企業は全額控除可、繰越期間は10年に 繰越欠損金の縮減(控除割合引下げ)の対象は「大企業」のみで、「中小企業」は対象外である。
つまり、「中小企業」は現行どおり繰越欠損金の全額を課税所得から控除することができるわけだ。
ただ、欠損金の繰越期間の延長(10年間)は、「大企業」だけでなく「中小企業」も適用対象となる。今回の欠損金に関する税制改正は、大企業にとっては増税色が強いものの、繰越期間延長の恩恵のみを享受する中小企業にとってはメリットがある改正項目といえそうだ。
持分比率5%以下の株式等、益金不算入割合(現行50%)が20%に
平成27年度税制改正のなかで、大企業の税負担が増加する「欠損金繰越控除の縮減」に対し、中小企業にとっても税負担が増加するのが「受取配当益金不算入の縮減」だ。
現行制度上、益金不算入割合は、株式等の持分比率に応じて、①持分比率が25%未満の場合は50%を益金不算入、②持分比率が25%以上の場合は100%益金不算入とする取扱いになっている。平成27年度税制改正では、この2つの区分を3つの区分に見直したうえで、益金不算入割合が引き下げられる運びとなった。具体的な内容は、本誌既報(575号4頁参照)のとおり、①持分比率が5%以下の場合は20%のみ益金不算入、②持分比率が5%超3分の1(33.3%)以下の場合は50%のみ益金不算入、③持分比率が3分の1(33.3%)超の場合は100%の益金不算入を認めるというもの(図表3参照)。この見直しは、大企業だけでなく中小企業にも適用される。ただ、保険会社については、特例として「持分比率5%以下」の株式の配当について40%のみ益金不算入となる。
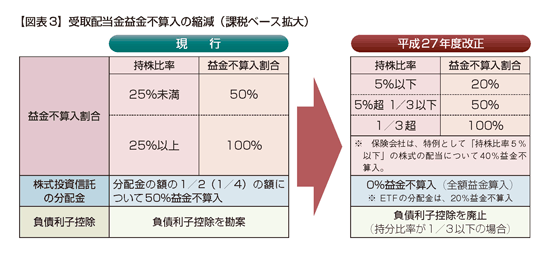
株式投資信託の分配金、100%益金算入に そのほか、受取配当益金不算入に関し平成27年度税制改正では、株式投資信託の分配金の益金不算入割合が引き下げられることになった。
具体的には、現行制度上、分配金の2分の1(または4分の1)の額について50%の益金不算入が認められているが、平成27年度税制改正により、0%益金不算入(100%益金算入)となる。ただし、株式投資信託の一種であるETF(Exchange Traded Funds)の分配金については、20%のみが益金不算入(80%益金算入)の対象とされる。
外形標準課税を拡充、賃上げ企業や中堅企業には軽減措置も用意
法人実効税率の引下げに伴う課税ベース拡大は、法人税(国税)だけでなく、地方税にも及び、法人事業税の外形標準課税が拡充される。
財務省資料によると、平成27年度分でみると外形標準課税の拡充に伴う税収増は約3,300億円(平成28年度は約6,600億円)であるのに対し、欠損金繰越控除の縮減による税収増は約1,900億円(平成28年度は約4,000億円)にとどまる。つまり、企業に与える増税のインパクトは、欠損金繰越控除の縮減よりも外形標準課税の拡充の方がはるかに大きいわけだ。
改正内容を具体的にみると、付加価値割については、現行0.48%の税率が平成27年度は0.72%、平成28年度以降は0.96%に拡充される(図表4参照)。
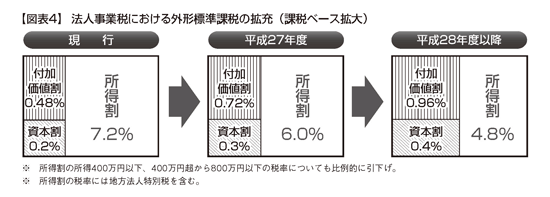
また、資本割については、現行0.2%の税率が平成27年度は0.3%、平成28年度は0.4%に拡充される。
これらの改正は、赤字法人を含むすべての大企業(資本金1億円超)が適用対象だ(中小企業は対象外)。
賃上げ分を課税標準から控除 平成27年度税制改正では、外形標準課税の拡充にあわせ、①賃上げした企業や②中堅企業を対象にした付加価値割の軽減措置(時限措置)が手当てされている。
具体的には、①賃上げした企業については、平成29年度末までの3年間に限り、その企業が法人税の所得拡大促進税制の要件(給与等支給額の総額が前事業年度以上など)を満たす場合には、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度を導入する(図表5参照)。
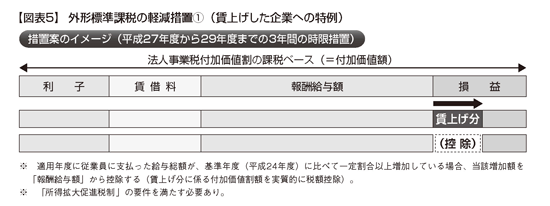
また、②中堅企業については、平成28年度末までの2年間に限り、その企業の適用年度における付加価値額が30億円以下である場合には、外形標準課税の拡充による負担増加額について50%の税額を軽減する(図表6参照)。なお、付加価値額30億円超40億円未満の法人については、付加価値額に応じて50%から0の間で負担増加額ついて税額が軽減される。
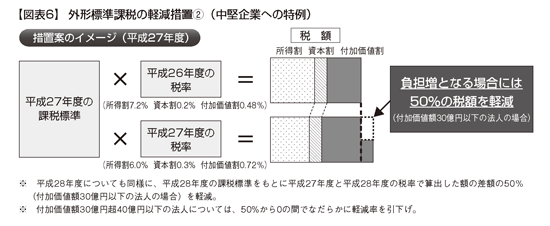
これらの付加価値割の軽減措置は、赤字法人でも適用が可能だ。
研究開発税制、特別試験研究費の控除率を大幅に引上げ
税額控除の上限は30%を維持 平成27年度税制改正では、租税特別措置の1つである研究開発税制(総額型)の見直しが実施される。
具体的にみると、総額型の税額控除限度額の上限を法人税額の30%(原則20%)に引き上げる措置が適用期限到来(平成26年度末)もって廃止される。
一方で、総額型(25%)とオープンイノベーション型(5%)を別枠化し、あわせて控除限度額の上限を法人税額の30%とする改正も実施される。要するに、控除限度額の上限30%は維持されるわけだ(図表7参照)。これにより、上乗せ措置である「増加型または高水準型」(いずれも控除上限10%)もあわせて適用することで、最大法人税額の40%まで税額控除が可能となる。
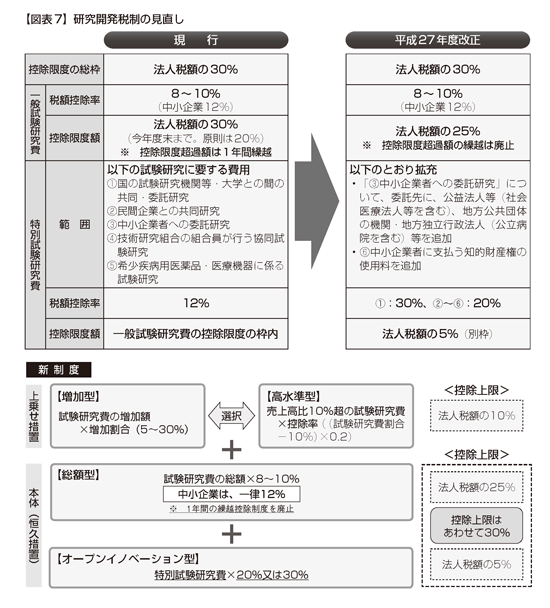
なお、研究開発費の総額型の税額控除に関する1年間の繰越控除制度は廃止される。
特別試験研究費、知的財産権使用料も対象に そのほか、研究開発税制に関し平成27年度税制改正では、オープンイノベーション型(特別試験研究費)の税額控除税率(現行12%)について、大学・特別試験研究機関等との共同・委託研究に関するものは30%、それ以外のものは20%に引き上げられる。
また、特別試験研究費の範囲が拡充される。具体的には、「中小企業者への委託研究」について、委託先に公益法人や地方公共団体の機関などが追加されるほか、中小企業者に支払う知的財産権の使用料などが追加されることになった。
所得拡大促進税制の要件緩和、中小企業にはさらなる緩和措置
そのほか、平成27年度税制改正では、法人税の所得拡大促進税制における給与等支給額の増加要件が緩和される(図表8参照)。
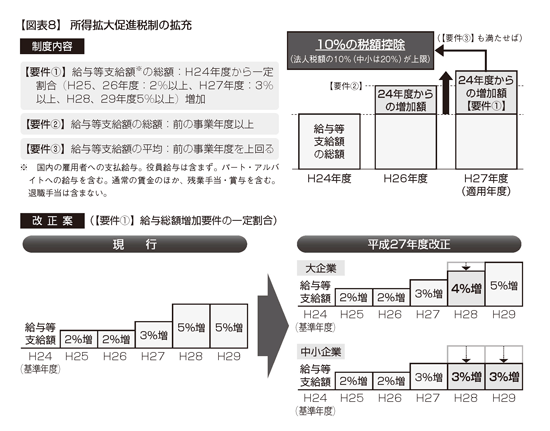
具体的には現行制度上、基準年度(平成24年度)と比較して平成28年度は5%以上、平成29年度も5%以上給与等の支給額を増加させる必要があるが、今回の改正により、大企業については平成28年度のみ「4%」以上の増加で所得拡大促進税制の適用を受けることが可能となる。
中小企業は3%以上の増加でOK! また、中小企業についてはさらに要件を緩和し、平成28年度および平成29年度の増加要件(現行5%以上)が「3%」以上に引き下げられることになった。
法人税率引下げと課税ベース拡大、平成27年度の重要改正を読み解く
法人実効税率の引下げおよびそれに伴う課税ベース拡大をめぐる平成27年度税制改正議論が決着した。自由民主党および公明党が12月30日に取りまとめた税制改正大綱には、法人実効税率の段階的な引下げ(平成27年度は32.11%、平成28年度は31.33%に引下げ)が盛り込まれる一方で、欠損金繰越控除や受取配当益金不算入の縮減をはじめとする“増税項目”(課税ベース拡大)が複数盛り込まれることになった。
本特集では、企業に大きな影響を及ぼす重要改正項目のポイントを、自民党税制調査会や財務省などの資料をもとに図表を交えわかりやすく解説する。
平成27年度は32.11%(▲2.51%)に引き下げ
法人実効税率をめぐっては、昨年6月に閣議決定された「骨太の方針2014」のなかで「数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す。」と明記されていた。
だが、骨太の方針では、具体的な引下げ幅が明記されなかったため、平成27年度税制改正でどの程度の「引下げ幅」が実現するか、大きな注目が集まっていた。
28年度の法人実効税率は「31.33%」に 法人実効税率の「引下げ幅」は、平成27年度については「2.51%」で決着した(図表1参照)。
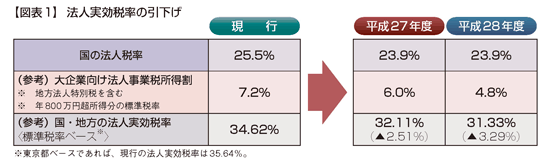
具体的にみると、国税である法人税の税率(現行25.5%)は、平成27年度は23.9%に引き下げられる。
また、地方税である法人事業税の所得割(現行7.2%、年800万円を超える所得分の標準税率)は、平成27年度は6.0%、平成28年度は4.8%に引き下げられる。この法人税および法人事業税所得割の税率引下げにより、法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度については「32.11%」(平成28年度は「31.33%」)に引き下げられる運びとなった。
28年度改正ではさらなる引下げも なお、平成28年度における法人実効税率の引下げ幅に関し大綱では、「課税ベースの拡大等により財源を確保して、平成28年度における税率引下げ幅の更なる上乗せを図る」と明記された。平成28年度税制改正では、法人実効税率のさらなる引下げが行われるかどうかに注目が集まりそうだ。
中小企業、軽減税率「15%」は2年延長 今回の法人税率の引下げは、主に大企業(資本金1億円超の法人)に対し適用される法人税率(現行25.5%)を23.9%に引き下げるというもの。資本金1億円以下の中小企業(年800万円以下の所得金額に限る)に適用される法人税率は現行どおり「19%」のままだ。
ただ、平成27年度税制改正では、中小企業に対する「19%」の法人税率をさらに「15%」まで軽減する租税特別措置(措法42の3の2)の2年延長(適用期限:平成28年度末まで)が決まっている。昨年6月の政府税制調査会の法人税改革案(本誌553号4頁参照)では、この軽減税率(措法15%部分)の廃止が盛り込まれていたが、中小企業に配慮するかたちで維持されることになった。
繰越欠損金の控除限度、27・28年度は65%、29年度は50%に
平成27年度税制改正では、法人実効税率が引き下げられる一方で、課税ベース拡大が複数項目にわたり実施される。なかでも、増税色が強い改正項目といえるのが「欠損金繰越控除の縮減」だ(図表2参照)。
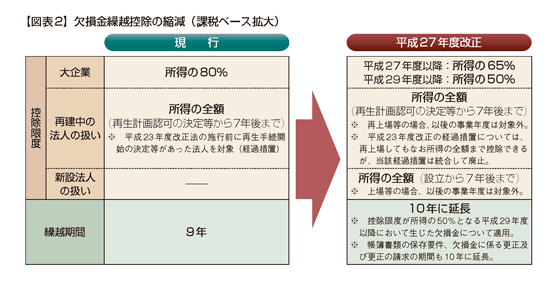
具体的には、大企業における繰越欠損金の控除限度割合(現行:所得の80%)を、平成27年度および平成28年度は「所得の65%」、平成29年度以降は「所得の50%」に引き下げる(再建中の法人や新設法人は7年後まで100%控除可)。
また、控除限度割合の引下げにあわせるかたちで、欠損金の繰越期間を現行の9年から10年に延長する。この繰越期間の延長は、平成29年度に生じた欠損金から適用される。
中小企業は全額控除可、繰越期間は10年に 繰越欠損金の縮減(控除割合引下げ)の対象は「大企業」のみで、「中小企業」は対象外である。
つまり、「中小企業」は現行どおり繰越欠損金の全額を課税所得から控除することができるわけだ。
ただ、欠損金の繰越期間の延長(10年間)は、「大企業」だけでなく「中小企業」も適用対象となる。今回の欠損金に関する税制改正は、大企業にとっては増税色が強いものの、繰越期間延長の恩恵のみを享受する中小企業にとってはメリットがある改正項目といえそうだ。
持分比率5%以下の株式等、益金不算入割合(現行50%)が20%に
平成27年度税制改正のなかで、大企業の税負担が増加する「欠損金繰越控除の縮減」に対し、中小企業にとっても税負担が増加するのが「受取配当益金不算入の縮減」だ。
現行制度上、益金不算入割合は、株式等の持分比率に応じて、①持分比率が25%未満の場合は50%を益金不算入、②持分比率が25%以上の場合は100%益金不算入とする取扱いになっている。平成27年度税制改正では、この2つの区分を3つの区分に見直したうえで、益金不算入割合が引き下げられる運びとなった。具体的な内容は、本誌既報(575号4頁参照)のとおり、①持分比率が5%以下の場合は20%のみ益金不算入、②持分比率が5%超3分の1(33.3%)以下の場合は50%のみ益金不算入、③持分比率が3分の1(33.3%)超の場合は100%の益金不算入を認めるというもの(図表3参照)。この見直しは、大企業だけでなく中小企業にも適用される。ただ、保険会社については、特例として「持分比率5%以下」の株式の配当について40%のみ益金不算入となる。
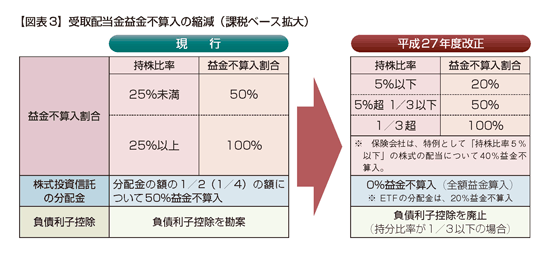
株式投資信託の分配金、100%益金算入に そのほか、受取配当益金不算入に関し平成27年度税制改正では、株式投資信託の分配金の益金不算入割合が引き下げられることになった。
具体的には、現行制度上、分配金の2分の1(または4分の1)の額について50%の益金不算入が認められているが、平成27年度税制改正により、0%益金不算入(100%益金算入)となる。ただし、株式投資信託の一種であるETF(Exchange Traded Funds)の分配金については、20%のみが益金不算入(80%益金算入)の対象とされる。
外形標準課税を拡充、賃上げ企業や中堅企業には軽減措置も用意
法人実効税率の引下げに伴う課税ベース拡大は、法人税(国税)だけでなく、地方税にも及び、法人事業税の外形標準課税が拡充される。
財務省資料によると、平成27年度分でみると外形標準課税の拡充に伴う税収増は約3,300億円(平成28年度は約6,600億円)であるのに対し、欠損金繰越控除の縮減による税収増は約1,900億円(平成28年度は約4,000億円)にとどまる。つまり、企業に与える増税のインパクトは、欠損金繰越控除の縮減よりも外形標準課税の拡充の方がはるかに大きいわけだ。
改正内容を具体的にみると、付加価値割については、現行0.48%の税率が平成27年度は0.72%、平成28年度以降は0.96%に拡充される(図表4参照)。
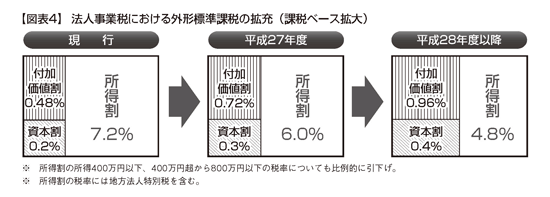
また、資本割については、現行0.2%の税率が平成27年度は0.3%、平成28年度は0.4%に拡充される。
これらの改正は、赤字法人を含むすべての大企業(資本金1億円超)が適用対象だ(中小企業は対象外)。
賃上げ分を課税標準から控除 平成27年度税制改正では、外形標準課税の拡充にあわせ、①賃上げした企業や②中堅企業を対象にした付加価値割の軽減措置(時限措置)が手当てされている。
具体的には、①賃上げした企業については、平成29年度末までの3年間に限り、その企業が法人税の所得拡大促進税制の要件(給与等支給額の総額が前事業年度以上など)を満たす場合には、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度を導入する(図表5参照)。
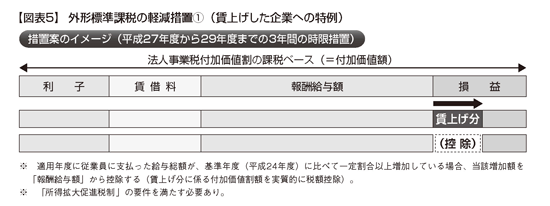
また、②中堅企業については、平成28年度末までの2年間に限り、その企業の適用年度における付加価値額が30億円以下である場合には、外形標準課税の拡充による負担増加額について50%の税額を軽減する(図表6参照)。なお、付加価値額30億円超40億円未満の法人については、付加価値額に応じて50%から0の間で負担増加額ついて税額が軽減される。
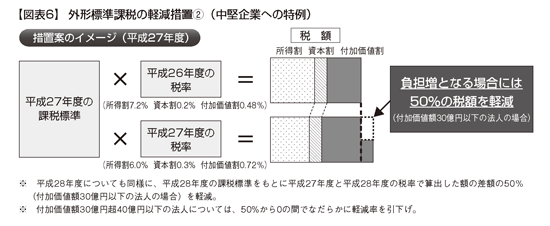
これらの付加価値割の軽減措置は、赤字法人でも適用が可能だ。
研究開発税制、特別試験研究費の控除率を大幅に引上げ
税額控除の上限は30%を維持 平成27年度税制改正では、租税特別措置の1つである研究開発税制(総額型)の見直しが実施される。
具体的にみると、総額型の税額控除限度額の上限を法人税額の30%(原則20%)に引き上げる措置が適用期限到来(平成26年度末)もって廃止される。
一方で、総額型(25%)とオープンイノベーション型(5%)を別枠化し、あわせて控除限度額の上限を法人税額の30%とする改正も実施される。要するに、控除限度額の上限30%は維持されるわけだ(図表7参照)。これにより、上乗せ措置である「増加型または高水準型」(いずれも控除上限10%)もあわせて適用することで、最大法人税額の40%まで税額控除が可能となる。
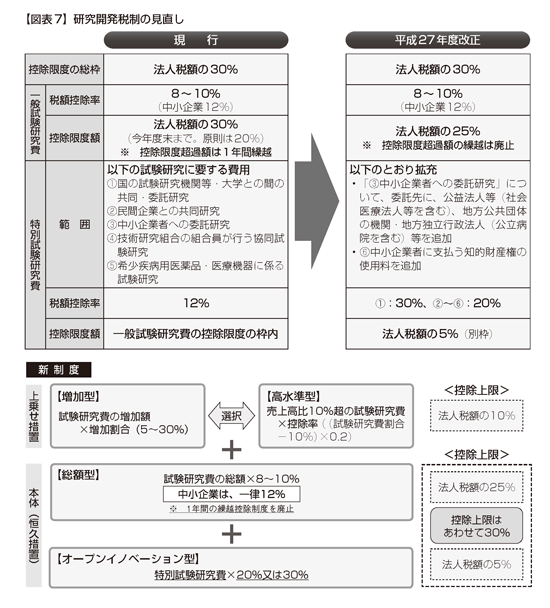
なお、研究開発費の総額型の税額控除に関する1年間の繰越控除制度は廃止される。
特別試験研究費、知的財産権使用料も対象に そのほか、研究開発税制に関し平成27年度税制改正では、オープンイノベーション型(特別試験研究費)の税額控除税率(現行12%)について、大学・特別試験研究機関等との共同・委託研究に関するものは30%、それ以外のものは20%に引き上げられる。
また、特別試験研究費の範囲が拡充される。具体的には、「中小企業者への委託研究」について、委託先に公益法人や地方公共団体の機関などが追加されるほか、中小企業者に支払う知的財産権の使用料などが追加されることになった。
所得拡大促進税制の要件緩和、中小企業にはさらなる緩和措置
そのほか、平成27年度税制改正では、法人税の所得拡大促進税制における給与等支給額の増加要件が緩和される(図表8参照)。
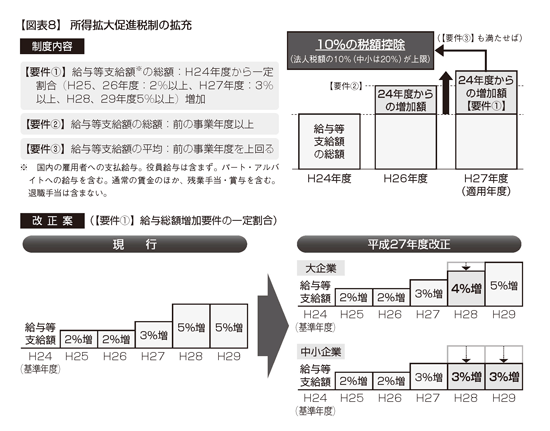
具体的には現行制度上、基準年度(平成24年度)と比較して平成28年度は5%以上、平成29年度も5%以上給与等の支給額を増加させる必要があるが、今回の改正により、大企業については平成28年度のみ「4%」以上の増加で所得拡大促進税制の適用を受けることが可能となる。
中小企業は3%以上の増加でOK! また、中小企業についてはさらに要件を緩和し、平成28年度および平成29年度の増加要件(現行5%以上)が「3%」以上に引き下げられることになった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















