解説記事2015年02月09日 【ニュース特集】 私道の相続税評価額、ゼロ評価となる分岐点(2015年2月9日号・№582)
固定資産税評価額がゼロ円のケースは?
私道の相続税評価額、ゼロ評価となる分岐点
今年1月からの相続税の課税強化(基礎控除縮小)に伴い、全体の相続財産の40%強を占める土地の評価の重要性がますます高まっている。この土地の評価に関連し、「私道」の相続税評価額を規定した評価通達24の合理性が問題となった裁判で判決が下された(東京地裁平成26年10月15日判決)。裁判所は、評価通達24の合理性を認めたうえで、不特定多数の者の通行の用に供されていない本件私道は同通達により30%相当額で評価すべきと判断。ゼロ評価すべき旨などを主張した納税者の訴えを斥ける判断を示した(敗訴した納税者は控訴)。 本特集では、通達の合理性をめぐる裁判所の判断内容に加え、本件裁判のなかで課税当局が挙げたゼロ評価できる「私道」の具体例などを紹介する。
評価通達24が規定する「30%評価」の合理性が争点に
「私道」とは、国や地方公共団体が築造・管理する道路以外の道路で、一般公衆の通行の用に供されている“私有地”である道路のことだ。
この私道の相続税評価額を規定した財産評価基本通達24(以下、「評価通達24」)では、私道は路線価などにより計算した価額の30%相当額で評価する旨を前段において規定する一方で、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときはその私道は評価しない旨を後段において規定している(下囲参照)。
今回紹介する裁判事例で問題となったのは、評価通達24の評価方法が合理的なものであると認められるか否かという点に加え、本件私道(詳しい形状および位置は右頁図を参照)の相続税評価額は幾らかという点だ。
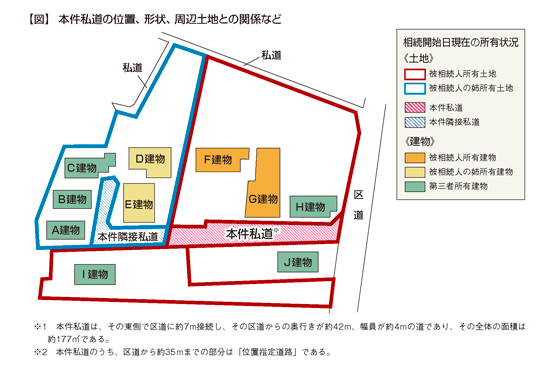
納税者、通達の30%評価は不合理と主張 この本件私道の評価に関し課税当局は、本件私道の相続税評価は評価通達24の前段の規定に基づき30%相当額で評価した約1,600万円であると主張していた。
一方の納税者は、評価通達24による評価方法が不合理であるという主張を訴訟のなかで展開した。
具体的にみると、本件私道が建築基準法などの規定によりその廃止などが厳しく制限されている「位置指定道路」(建築基準法が規定する道路の1つで地方公共団体等が道路の位置を指定したもの)である点などを踏まえれば、本件私道を評価通達24に基づき30%相当額で評価することは不合理であると主張。また、納税者は、固定資産税評価額がゼロ円である本件私道と固定資産税評価額がゼロ円でない私道とを一律に評価する点が不合理であると主張した。さらに、納税者は、位置指定道路は不特定多数の通行の用に供されることを法的に義務付けられた道路であるため、本件私道は評価通達24の後段の規定により、ゼロ評価すべき旨を主張していた。
裁判所、固定資産税が非課税でもゼロ評価と認められず
納税者の主張に対し裁判所は、まず、評価通達24の趣旨・内容(次頁表参照)を確認したうえで、評価通達24は位置指定によるものを含めた種々の規制の有無等を踏まえつつも私道の用に供されている宅地が「不特定多数の者の通行の用に供されている」といえるか否かにより評価割合を異にする評価方式を定めたものであって、合理性を有するものというべきであると判断した(通達の合理性に関する判断内容は今号7頁の参考参照)。
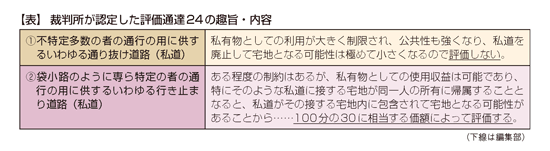
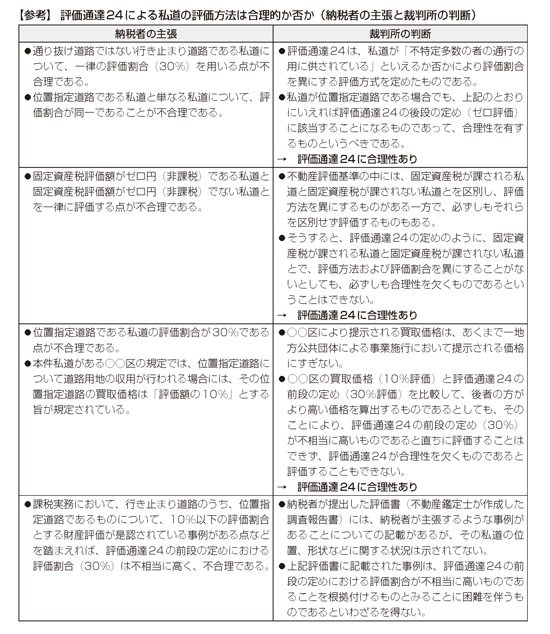
評価通達24の規定は合理的と認定 評価通達24の適用を前提としたうえで、裁判所は、行き止まり道路の一部である本件私道を利用する者は本件私道や本件隣接私道に接する宅地上にあるA建物からH建物(一戸建て住宅・共同住宅など8棟)までを出入りする者に限られ、これらの建物を出入りする者はそこの居住者やその関係者などに限られると認定した。
この認定事実を踏まえ裁判所は、本件私道は位置指定道路を含むものであるが、その現実の状況に照らすと不特定多数の者の通行の用に供されているものではなく、評価通達24の前段の定め(30%相当額)に基づいて評価されるべきであると判断。評価通達24の評価方法は不合理である旨の主張を展開した納税者の訴えを斥けた(敗訴した納税者は控訴している)。
不特定多数の者が公共施設に出入りしている私道であればゼロ評価も
今回紹介した裁判事案の「本件私道」に関し裁判所は、評価通達24の評価方法は合理的である認定したうえで、本件私道の利用者は本件私道に接する宅地上の建物を出入りする者(居住者など)に限られ、不特定多数の者の通行の用に供されていないと判断して、納税者が主張するゼロ評価は認められない(30%相当額で評価すべき)と結論付けた。
では、具体的にどのような「私道」であれば、評価通達24の後段の規定によるゼロ評価が認められる「不特定多数の者の通行の用に供されている」私道に該当するのか。
この点に関し、本件裁判のなかで課税当局は、私道の価額を評価しない具体例として、①公道と私道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け道路、②いわゆる行き止まりの道路であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道および③私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合におけるその私道などを挙げている。
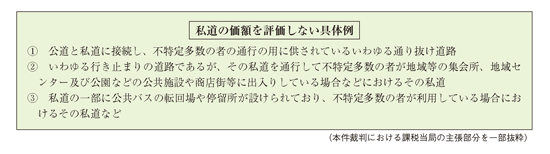
評価通達24の合理性を肯定した本件判決も踏まえれば、課税当局が挙げる具体例に当てはまるような「私道」は、ゼロ評価が認められる可能性が高いといえるだろう。
私道の相続税評価額、ゼロ評価となる分岐点
今年1月からの相続税の課税強化(基礎控除縮小)に伴い、全体の相続財産の40%強を占める土地の評価の重要性がますます高まっている。この土地の評価に関連し、「私道」の相続税評価額を規定した評価通達24の合理性が問題となった裁判で判決が下された(東京地裁平成26年10月15日判決)。裁判所は、評価通達24の合理性を認めたうえで、不特定多数の者の通行の用に供されていない本件私道は同通達により30%相当額で評価すべきと判断。ゼロ評価すべき旨などを主張した納税者の訴えを斥ける判断を示した(敗訴した納税者は控訴)。 本特集では、通達の合理性をめぐる裁判所の判断内容に加え、本件裁判のなかで課税当局が挙げたゼロ評価できる「私道」の具体例などを紹介する。
評価通達24が規定する「30%評価」の合理性が争点に
「私道」とは、国や地方公共団体が築造・管理する道路以外の道路で、一般公衆の通行の用に供されている“私有地”である道路のことだ。
この私道の相続税評価額を規定した財産評価基本通達24(以下、「評価通達24」)では、私道は路線価などにより計算した価額の30%相当額で評価する旨を前段において規定する一方で、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときはその私道は評価しない旨を後段において規定している(下囲参照)。
| 財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価) 私道の用に供されている宅地の価額は、評価通達11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。 この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。 |
今回紹介する裁判事例で問題となったのは、評価通達24の評価方法が合理的なものであると認められるか否かという点に加え、本件私道(詳しい形状および位置は右頁図を参照)の相続税評価額は幾らかという点だ。
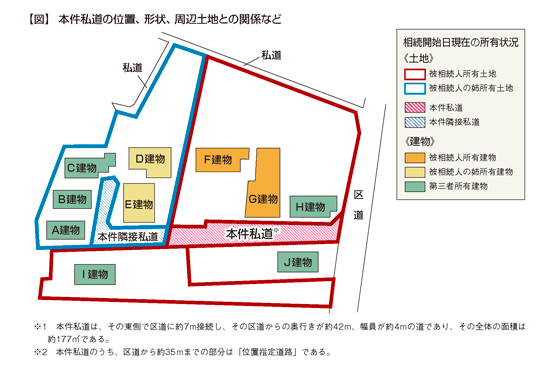
納税者、通達の30%評価は不合理と主張 この本件私道の評価に関し課税当局は、本件私道の相続税評価は評価通達24の前段の規定に基づき30%相当額で評価した約1,600万円であると主張していた。
一方の納税者は、評価通達24による評価方法が不合理であるという主張を訴訟のなかで展開した。
具体的にみると、本件私道が建築基準法などの規定によりその廃止などが厳しく制限されている「位置指定道路」(建築基準法が規定する道路の1つで地方公共団体等が道路の位置を指定したもの)である点などを踏まえれば、本件私道を評価通達24に基づき30%相当額で評価することは不合理であると主張。また、納税者は、固定資産税評価額がゼロ円である本件私道と固定資産税評価額がゼロ円でない私道とを一律に評価する点が不合理であると主張した。さらに、納税者は、位置指定道路は不特定多数の通行の用に供されることを法的に義務付けられた道路であるため、本件私道は評価通達24の後段の規定により、ゼロ評価すべき旨を主張していた。
裁判所、固定資産税が非課税でもゼロ評価と認められず
納税者の主張に対し裁判所は、まず、評価通達24の趣旨・内容(次頁表参照)を確認したうえで、評価通達24は位置指定によるものを含めた種々の規制の有無等を踏まえつつも私道の用に供されている宅地が「不特定多数の者の通行の用に供されている」といえるか否かにより評価割合を異にする評価方式を定めたものであって、合理性を有するものというべきであると判断した(通達の合理性に関する判断内容は今号7頁の参考参照)。
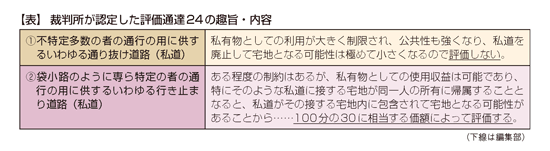
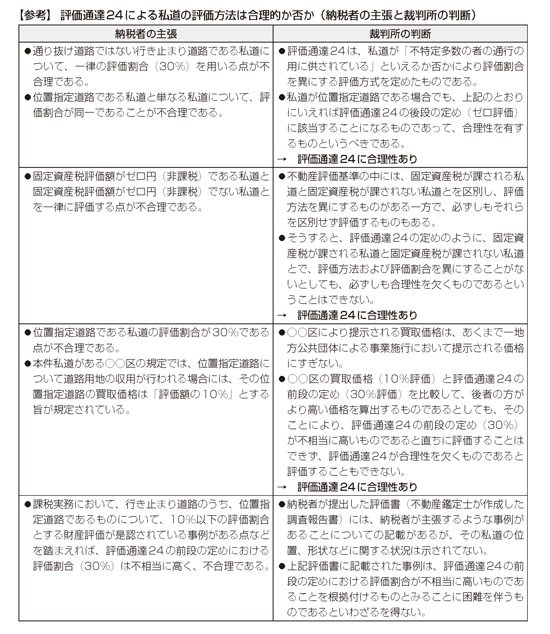
評価通達24の規定は合理的と認定 評価通達24の適用を前提としたうえで、裁判所は、行き止まり道路の一部である本件私道を利用する者は本件私道や本件隣接私道に接する宅地上にあるA建物からH建物(一戸建て住宅・共同住宅など8棟)までを出入りする者に限られ、これらの建物を出入りする者はそこの居住者やその関係者などに限られると認定した。
この認定事実を踏まえ裁判所は、本件私道は位置指定道路を含むものであるが、その現実の状況に照らすと不特定多数の者の通行の用に供されているものではなく、評価通達24の前段の定め(30%相当額)に基づいて評価されるべきであると判断。評価通達24の評価方法は不合理である旨の主張を展開した納税者の訴えを斥けた(敗訴した納税者は控訴している)。
不特定多数の者が公共施設に出入りしている私道であればゼロ評価も
今回紹介した裁判事案の「本件私道」に関し裁判所は、評価通達24の評価方法は合理的である認定したうえで、本件私道の利用者は本件私道に接する宅地上の建物を出入りする者(居住者など)に限られ、不特定多数の者の通行の用に供されていないと判断して、納税者が主張するゼロ評価は認められない(30%相当額で評価すべき)と結論付けた。
では、具体的にどのような「私道」であれば、評価通達24の後段の規定によるゼロ評価が認められる「不特定多数の者の通行の用に供されている」私道に該当するのか。
この点に関し、本件裁判のなかで課税当局は、私道の価額を評価しない具体例として、①公道と私道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け道路、②いわゆる行き止まりの道路であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道および③私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合におけるその私道などを挙げている。
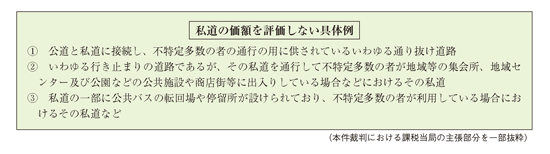
評価通達24の合理性を肯定した本件判決も踏まえれば、課税当局が挙げる具体例に当てはまるような「私道」は、ゼロ評価が認められる可能性が高いといえるだろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















