解説記事2015年03月16日 【ニュース特集】 名古屋地裁 TH税制における「主たる事業」の判定方法(2015年3月16日号・№586)
金額的規模のみ重視の判定方法を否定で国が敗訴
名古屋地裁 TH税制における「主たる事業」の判定方法
最近発生した国際課税分野における税務紛争の中で大きな話題を呼んだのが、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件における「主たる事業」の判定方法が争点となった大手自動車部品メーカーの事案だ。
税務当局は、タックスヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである事業基準について、地域統括会社の収入や所得金額に占める株式保有業に係る収入や所得金額の割合によって「主たる事業」を判定し、タックスヘイブン対策税制を適用する課税処分を行ったところ、国税不服審判所もこれを支持、海外に地域統括会社を抱える企業に衝撃が走った。
この判断はその後名古屋地裁で覆され、国が敗訴しているが、「主たる事業」の判定方法について裁判所がどのような判断を示したのかはこれまでベールに包まれていた。本特集ではこの部分に迫りたい。
経 緯
本件自動車部品メーカーを巡っては「2つ」の事案があるが、両者とも海外の地域統括会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして追徴課税が行われたものであり、基本的に同じ内容となっている。それぞれを第一次事案、第二次事案として経緯を整理すると次頁の表のとおりとなる。本特集で取り上げるのは、第一次事案の地裁判決である。
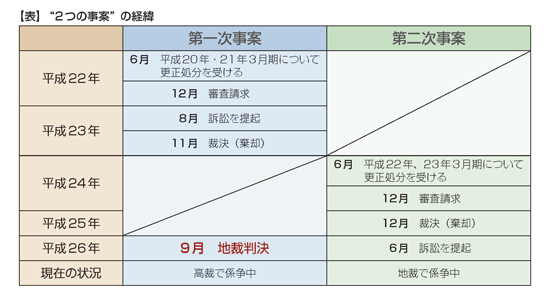
なお、第一次事案では、訴訟に至った後に裁決が出されており、審査請求前置主義との関係が気になるが、これは国税通則法上もあり得ることになる(国税通則法115条②、42頁参照)。
一過性の株式売却益発生で「株式保有業」に?
本事案では、電子部品メーカーの特定外国子会社等である地域統括会社が「2以上の事業」を営んでいたが、税務当局は、タックスヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである事業基準における「主たる事業」の判定を、地域統括会社の収入や所得金額に占める株式保有業に係る収入や所得金額の割合によって行った結果、「主たる事業=株式保有業」であると認定、当該地域統括会社を同税制の適用対象とする旨の課税処分を行った。
自動車部品メーカーはこの課税処分を不服とし審査請求を行ったが、国税不服審判所は税務当局による課税処分を支持(平成23年11月22日裁決)、海外に地域統括会社を抱える企業に衝撃が走った。この裁決を受け、企業の間では、通常であればタックスヘイブン対策税制の適用除外となるはずの特定外国子会社等において一過性の大きな株式売却益が発生した場合、主たる事業が「株式保有業」と判断されてしまうのではないかとの懸念が広がっていた。
平成23年11月22日裁決の要旨は次頁のとおり。
使用人数、事務所、店舗、固定施設の状況等も「主たる事業」の判定要素
これに対し、昨年(2014年)9月4日に下された名古屋地裁判決では、一転して納税者側が勝訴している。
注目を集めていたのが、裁判所が「主たる事業」の判定方法についてどのような判断を示したのかという点だ。
本誌取材によると、名古屋地裁は、「主たる事業」の判定方法について「特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定するほかない」とし、特定外国子会社等が複数の事業を営んでいる場合には、「それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、それぞれの事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等の具体的かつ客観的な事業活動の内容を総合的に勘案して判定するのが相当」との考えを示している。
そして、本件地域統括会社の事業を見ると、①地域統括会社の従業員(35人程度)のうち株式保有業務に従事している者は1人もいなかったこと、②事務用什器備品、車両、コンピュータ等の固定施設はすべて株式保有業務以外の業務に使用されていたこと、③地域統括会社の収入の85%を物流改善業務に関する売上が占めていたこと、④地域統括会社は地域統括業務を行うことを目的として設立されたこと、⑤材料・資材の調達交渉や廉価調達先の発掘、グループローンの実施、原材料の品質調査、インボイスの集中発行決済などの地域統括業務により集中生産・相互補完体制の構築・維持・発展が図られた結果、グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、これが被統括会社からの配当収入の中に相当程度反映されることとなったこと―――といった事実があったことから、「主たる事業」は株式保有業ではなく地域統括事業であったことは明らかであるとした。
事業活動の収益状況が厳しければ「株式保有業」に?
これに対し税務当局は、仮に事業実体に係る人的・物的な規模を「主たる事業」の判断要素にした場合、そもそも株式保有業には大した生産要素が必要ないことから、株式の保有によりいかに多額の所得を得ていたとしても、株式の保有は主たる事業になり得ないという結論になるのは不合理としたうえで、①地域統括会社の「所得金額」の大部分を子会社からの配当が占めていること、②資産規模に占める保有株式の割合が過半を占めていることを根拠に、「主たる事業」は株式保有業であると主張した。
しかし名古屋地裁は、「我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害することにならないよう、正常かつ合理的な経済活動についてはタックスヘイブン対策税制の適用対象外とする」という適用除外基準の趣旨を踏まえ、「特定外国子会社等が株式の保有に係る事業の他に実体的な事業活動をしており、これを当該国において行うことが十分に経済的合理性がある場合には、当該事業が主たる事業であるかどうかを検討しなければならないのは当然のことであり、たとえ株式の配当による所得金額が大きいとしても、株式保有以外の実体的な事業活動が現実に行われており、当該事業活動に相応の経営資源が投入されている場合には、事業基準を満たすと解することこそが、タックスヘイブン対策税制の制度趣旨にかなう」とし、この点についても税務当局の主張を退けている。
さらに、仮に税務当局の主張するように「収入金額や所得金額」という金額的な規模を示す判断要素のみを重視して主たる事業を判断した場合、株式保有以外の実体的な事業活動にいかに多大な経営資源が投入されていても、当該事業活動の収益状況が芳しくない状況の下では、当該特定外国子会社等の主たる事業が株式保有業と判定されるという不合理な結果になりかねない旨も指摘し、税務当局の主張を一蹴している。
勝訴した原告も控訴
このほか裁判では、統括会社の主たる事業が「卸売業」に該当するかどうかも争点となった。
タックスヘイブン対策税制上、事業運営会社が7業種(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業)に該当する場合には、非関連者(50%超出資会社等以外の者)との間の取引に係る販売取扱金額又は仕入取扱金額が「統括会社の販売取扱金額又は仕入取扱金額の総額×50%」以下であれば、当該統括会社はタックス・ヘイブン対策税制の適用対象となる(措令39の17⑧。以下「非関連者基準」)。税務当局は、統括会社の主たる事業は「卸売業」に該当し、また、統括会社が行った物流改善業務の売上金額等の多くは関連者との取引であることから、非関連者基準を満たさないと主張した。
これに対し裁判所は、統括会社の事業は、上述した(6ページ中段参照)各種業務が相互に関連し、「有機的一体」をなして機能していたのであり、そこから売買取引のみを取り出して主たる事業が「卸売業」に当たるとすることは、事業の実態にそぐわないものであり、相当ではないとし、この点についても税務当局の主張を退けている。
裁判所は訴訟費用を「被告(国):原告(メーカー)=399:1」としたが、メーカー側はこの「1」にも納得せず双方が控訴するという事態となっている(現在高裁で係争中)。
名古屋地裁 TH税制における「主たる事業」の判定方法
最近発生した国際課税分野における税務紛争の中で大きな話題を呼んだのが、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件における「主たる事業」の判定方法が争点となった大手自動車部品メーカーの事案だ。
税務当局は、タックスヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである事業基準について、地域統括会社の収入や所得金額に占める株式保有業に係る収入や所得金額の割合によって「主たる事業」を判定し、タックスヘイブン対策税制を適用する課税処分を行ったところ、国税不服審判所もこれを支持、海外に地域統括会社を抱える企業に衝撃が走った。
この判断はその後名古屋地裁で覆され、国が敗訴しているが、「主たる事業」の判定方法について裁判所がどのような判断を示したのかはこれまでベールに包まれていた。本特集ではこの部分に迫りたい。
経 緯
本件自動車部品メーカーを巡っては「2つ」の事案があるが、両者とも海外の地域統括会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして追徴課税が行われたものであり、基本的に同じ内容となっている。それぞれを第一次事案、第二次事案として経緯を整理すると次頁の表のとおりとなる。本特集で取り上げるのは、第一次事案の地裁判決である。
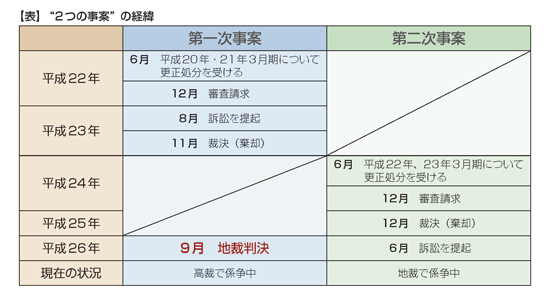
なお、第一次事案では、訴訟に至った後に裁決が出されており、審査請求前置主義との関係が気になるが、これは国税通則法上もあり得ることになる(国税通則法115条②、42頁参照)。
一過性の株式売却益発生で「株式保有業」に?
本事案では、電子部品メーカーの特定外国子会社等である地域統括会社が「2以上の事業」を営んでいたが、税務当局は、タックスヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである事業基準における「主たる事業」の判定を、地域統括会社の収入や所得金額に占める株式保有業に係る収入や所得金額の割合によって行った結果、「主たる事業=株式保有業」であると認定、当該地域統括会社を同税制の適用対象とする旨の課税処分を行った。
自動車部品メーカーはこの課税処分を不服とし審査請求を行ったが、国税不服審判所は税務当局による課税処分を支持(平成23年11月22日裁決)、海外に地域統括会社を抱える企業に衝撃が走った。この裁決を受け、企業の間では、通常であればタックスヘイブン対策税制の適用除外となるはずの特定外国子会社等において一過性の大きな株式売却益が発生した場合、主たる事業が「株式保有業」と判断されてしまうのではないかとの懸念が広がっていた。
平成23年11月22日裁決の要旨は次頁のとおり。
| 名古屋国税不服審判所 平成23年11月22日裁決 棄却
請求人は、租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの。)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)の事業は、地域統括事業であり、その内容は、地域企画機能・調達機能・経理機能など多岐にわたっており、これらの機能は、それぞれが独立して機能するわけではなく、有機的一体として、地域の各拠点に提供されており、また、所得金額の多寡のみを基準として事業の判定を行った場合には、本件特定外国子会社における現実の事業活動の実態を無視し又は実態から乖離した判断がなされるおそれがあり、本件特定外国子会社のような地域統括会社においては、必ずしも、所得金額がその事業活動の結果、経済的効果を反映するものではなく、所得金額が使用人の数や固定施設の状況に比して重要であるとはいえない旨主張する。 しかしながら、本件特定外国子会社は、その収入金額、所得金額のおおむねを株式保有業から得ており、また、保有資産の額の過半が株式保有業に係るものと認められる。一方で、使用人はすべて地域関連会社に対するサービス業に投入されているが、そもそも株式保有業は従業員がいなくても行い得る事業であり、固定施設についても、株式保有業にはさして必要ではないから、これらを重視して本件特定外国子会社の事業基準に係る主たる事業の判定を行うことは適当ではないと考えられる。 本件特定外国子会社の事業について、収入金額や所得金額の状況、使用人の数や固定施設等の状況を事業基準の趣旨に基づいて総合勘案すると、その主たる事業は株式保有業と認めるのが相当である。(平23.11.22 名裁(法)平23-49) |
使用人数、事務所、店舗、固定施設の状況等も「主たる事業」の判定要素
これに対し、昨年(2014年)9月4日に下された名古屋地裁判決では、一転して納税者側が勝訴している。
注目を集めていたのが、裁判所が「主たる事業」の判定方法についてどのような判断を示したのかという点だ。
本誌取材によると、名古屋地裁は、「主たる事業」の判定方法について「特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定するほかない」とし、特定外国子会社等が複数の事業を営んでいる場合には、「それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、それぞれの事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等の具体的かつ客観的な事業活動の内容を総合的に勘案して判定するのが相当」との考えを示している。
そして、本件地域統括会社の事業を見ると、①地域統括会社の従業員(35人程度)のうち株式保有業務に従事している者は1人もいなかったこと、②事務用什器備品、車両、コンピュータ等の固定施設はすべて株式保有業務以外の業務に使用されていたこと、③地域統括会社の収入の85%を物流改善業務に関する売上が占めていたこと、④地域統括会社は地域統括業務を行うことを目的として設立されたこと、⑤材料・資材の調達交渉や廉価調達先の発掘、グループローンの実施、原材料の品質調査、インボイスの集中発行決済などの地域統括業務により集中生産・相互補完体制の構築・維持・発展が図られた結果、グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、これが被統括会社からの配当収入の中に相当程度反映されることとなったこと―――といった事実があったことから、「主たる事業」は株式保有業ではなく地域統括事業であったことは明らかであるとした。
事業活動の収益状況が厳しければ「株式保有業」に?
これに対し税務当局は、仮に事業実体に係る人的・物的な規模を「主たる事業」の判断要素にした場合、そもそも株式保有業には大した生産要素が必要ないことから、株式の保有によりいかに多額の所得を得ていたとしても、株式の保有は主たる事業になり得ないという結論になるのは不合理としたうえで、①地域統括会社の「所得金額」の大部分を子会社からの配当が占めていること、②資産規模に占める保有株式の割合が過半を占めていることを根拠に、「主たる事業」は株式保有業であると主張した。
しかし名古屋地裁は、「我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害することにならないよう、正常かつ合理的な経済活動についてはタックスヘイブン対策税制の適用対象外とする」という適用除外基準の趣旨を踏まえ、「特定外国子会社等が株式の保有に係る事業の他に実体的な事業活動をしており、これを当該国において行うことが十分に経済的合理性がある場合には、当該事業が主たる事業であるかどうかを検討しなければならないのは当然のことであり、たとえ株式の配当による所得金額が大きいとしても、株式保有以外の実体的な事業活動が現実に行われており、当該事業活動に相応の経営資源が投入されている場合には、事業基準を満たすと解することこそが、タックスヘイブン対策税制の制度趣旨にかなう」とし、この点についても税務当局の主張を退けている。
さらに、仮に税務当局の主張するように「収入金額や所得金額」という金額的な規模を示す判断要素のみを重視して主たる事業を判断した場合、株式保有以外の実体的な事業活動にいかに多大な経営資源が投入されていても、当該事業活動の収益状況が芳しくない状況の下では、当該特定外国子会社等の主たる事業が株式保有業と判定されるという不合理な結果になりかねない旨も指摘し、税務当局の主張を一蹴している。
勝訴した原告も控訴
このほか裁判では、統括会社の主たる事業が「卸売業」に該当するかどうかも争点となった。
タックスヘイブン対策税制上、事業運営会社が7業種(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業)に該当する場合には、非関連者(50%超出資会社等以外の者)との間の取引に係る販売取扱金額又は仕入取扱金額が「統括会社の販売取扱金額又は仕入取扱金額の総額×50%」以下であれば、当該統括会社はタックス・ヘイブン対策税制の適用対象となる(措令39の17⑧。以下「非関連者基準」)。税務当局は、統括会社の主たる事業は「卸売業」に該当し、また、統括会社が行った物流改善業務の売上金額等の多くは関連者との取引であることから、非関連者基準を満たさないと主張した。
これに対し裁判所は、統括会社の事業は、上述した(6ページ中段参照)各種業務が相互に関連し、「有機的一体」をなして機能していたのであり、そこから売買取引のみを取り出して主たる事業が「卸売業」に当たるとすることは、事業の実態にそぐわないものであり、相当ではないとし、この点についても税務当局の主張を退けている。
裁判所は訴訟費用を「被告(国):原告(メーカー)=399:1」としたが、メーカー側はこの「1」にも納得せず双方が控訴するという事態となっている(現在高裁で係争中)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















