解説記事2015年06月01日 【特集】 検証・IBM事件 高裁判決〔第3回〕(2015年6月1日号・№596)
特集
IBM事件はヤフー事件よりも「租税回避」の性格が強い
検証・IBM事件 高裁判決〔第3回〕
前2回の朝長英樹税理士(日本税制研究所 代表理事)へのインタビュー(592号、595号参照)では、IBM事件の高裁判決は、法人税法132条に関して創設の趣旨・目的等とは相容れない「経済的合理性」基準によって「租税回避」に該当するか否かを判定するという解釈を採っていることが明らかになったところだ。これは、132条の解釈の従来の通説を否定するものであり、また、この高裁判決により、「事業目的」や「事業上の理由」が有りさえすれば「租税回避」には当たらないという理解に基づく現在の実務が通用しなくなるおそれがある。
これに対し朝長税理士は、「132条の創設の趣旨・目的を踏まえ、同条を文理に即して正しく解釈すれば、税制度の「濫用」や「潜脱」を同条が適用される「租税回避」とするべきである」と主張する。そして、このような解釈に基づき、IBM事件には132条が適用されるべきであるという。
最終回である今回は、132条がIBM事件に適用されるべき理由を詳細に語ってもらった。
全3回のインタビューで朝長税理士により示されたIBM事件に対する論理的で深度ある緻密な検証は、132条の「租税回避」に関する従来の学説と実務に非常に大きなインパクトを与えることになろう。
巨額の税金に全く関心を持たずに大きな再編等を行ったというのであれば、明らかに「不自然」
――今回はまず、前回のインタビューの最後にお話が出た法人税法132条の「行為又は計算」が「不自然・不合理」であることについてうかがいたいと思います。「不自然・不合理」とは具体的にどういうことでしょうか?
朝長 重要なところから二点をお話しておきたいと思います。
一点目は、1千億円以上ともなる税金に全く関心を持たずにグループ再編(中間持株会社の設置)や資本等取引(自己株式取得)を行ったということであれば、それらの行為は、明らかに「不自然」であるということです。
実際に実務に携わってみると分かりますが、大企業が大きなグループ再編や巨額の資本等取引を行う場合には、法務・税務・会計の取扱いを注意深く検討することになります。特に税務については、法務や会計よりも難解な部分が多い上、最終利益に大きな影響を与え、しかも、後に税務調査を受けることにもなりますので、慎重に検討するのが通例であり、税務について検討しないなどということは、まず有り得ないはずです。通常は、社内の税務担当者や社外の税務の専門家がスキーム、税額を示したケーススタディ、利益への影響、スケジュール、法令の規定や関係通達などを示した資料を作成して詳細な検討を繰り返し、案が出来たら、これらの資料を用いて役員等に説明を行うということになります。当然、社内や社外の税務の専門家との間においては、メールのやり取りも頻繁に行われることになります。これらの一連の作業が一回で終わるということは、ほとんどありません。
しかし、IBM事件においては、ヤフー事件と対照的に、このような検討ややり取り等を行ったことを確認できるものがほとんど出てきていません。
訴訟の場では、納税者側から、中間持株会社に巨額の株式譲渡損が生じて青色欠損金となることについて「全く関心を持っていなかった」「何の関心も持っていなかった」という主張が繰り返し行われているわけですが、本件のような大きなグループ再編や巨額の資本等取引を行う場合に税務に関心を持たないなどということは現実にはあり得ず、むしろ、反対に「最大の関心事項」であったとしても、決しておかしくないと思っています。
これは、基本的には、実際にそのようなことが在ったのか無かったのかという事実に関する問題ですが、上記の詳細な検討ややり取り等が行われないまま本件のグループ再編や資本等取引が行われたということであれば、本件のグループ再編や資本等取引は、明らかに「不自然」な行為と言わざるを得ません。
――上記の詳細な検討ややり取り等が行われていたのであれば、その内容を確認できるものが示されていないことに問題があり、他方、それらが行われていなかったというのであれば、本件のグループ再編や資本等取引は明らかに「不自然」である、ということですね。
朝長 そうです。上記の「全く関心を持っていなかった」云々というような主張は、実際にグループ再編や資本等取引を行っている実務者の間では有り得ないものであると考えています。
税金の影響額が1千億円以上となるにもかかわらず税金がどうなるのかということに全く関心を持たずに大きなグループ再編や巨額の資本等取引が行われるなどということは、ほとんど考えられません。もし、そのようなことがあったというのであれば、それらの行為は、「不自然・不合理」ということを通り越して「異常」と言っても過言ではないと思います。
中間持株会社を設けて自己株式取得を行うことも「不自然」
――もう一点はどういうことでしょうか。
朝長 中間持株会社を設けた上で自己株式取得を行うことは「不自然」である、ということです。
納税者側は、中間持株会社を設けたことと自己株式取得を行ったことは関係がなく、自己株式取得は平成9年から行ってきたことの延長線上で行われたものであり、「日本IBMが、株主への利益還元を目的として、通常配当の方法とともに自己株式取得という方法を使用していたのは、当時の商法上、日本の株式会社が配当を行うことが許されるタイミングに制約があったことから、通常配当や中間配当を行うことができないタイミングでの株主への利益還元を実現するためであって、平成18(2006)年の会社法施行により、株式会社の配当可能時期に法律上の制約がなくなった時点以降は、日本IBMは株主への利益還元を全て通常配当の方法により行っている。」と主張していますが、この主張に関しても、多分に疑義があります。
図1は、地裁の段階で国側から提出された日本IBMの株主への利益還元の状況の一覧表(本誌556号11頁参照)に基づいて作成したものです。
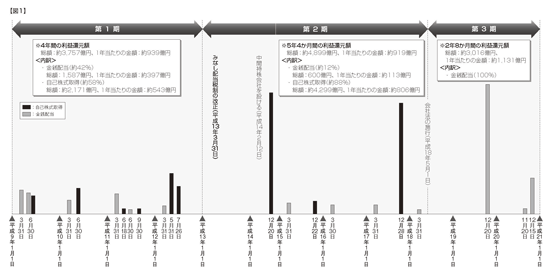
この図1を見れば、日本IBMによる株主への利益還元の方法が図1に示した第1期、第2期及び第3期で大きく異なっていることが一目瞭然です。
本件において問題となっているのは、第2期における平成14年12月20日、平成15年12月22日及び平成17年12月28日の自己株式取得です。
――日本IBMの株主への利益還元の状況の一覧表を見て、自己株式取得は昔から行われており、平成13年・14年に自己株式取得を行ったことは、何ら「不自然・不合理」ではないのではないかと思っていましたが、こうしてグラフで見ると全く印象が違いますね。
朝長 この図1からは、次のような特徴を読み取ることができます。
ⅰ 日本IBMは、平成9年から平成20年までの12年間に、日本で事業を行って得た利益から約1兆2千億円を米国IBMに還元しており、日本IBMの米国IBMへの1年当たりの利益の還元額は、約1千億円と考えてもよい。
ⅱ 第1期の4年間は、毎年、通常配当と中間配当を行うことを繰り返してきており、金銭配当と自己株式取得の割合も、概ねバランスが保たれている。
ⅲ 第2期は、第1期と大きく異なり、通常配当と中間配当を毎年繰り返すパターンが崩れて、金銭配当と自己株式取得の割合もバランスが崩れてしまっている。
ⅳ 第2期は、法人税法24条1項の規定の改正が行われた平成13年3月から通常配当が行われなくなっており、平成14年12月20日に多額の自己株式取得が行われるまで、約1年9か月間、一度も株主への利益還元が行われていない。
ⅴ 第1期の1年当たりの利益還元額は約939億円、第2期の1年当たりの利益還元額は約919億円であり大差はないが、金銭配当と自己株式取得の割合は、第1期が42%:58%、第2期が12%:88%となっており、第2期は、自己株式取得の割合が極めて大きくなっている。
ⅵ 第1期及び第2期においても、第3期の平成19年12月20日の金銭配当のような多額の金銭配当を行い得るにもかかわらず、一度もそのような多額の金銭配当は行われたことがなく、第2期の2回の多額な株主への利益還元も、自己株式取得として行われている。
ⅶ 第3期は、会社法改正により、任意の時期に株主への利益還元が行い得ないために自己株式取得を行っているという説明が困難となっているが、この時期には自己株式取得は行われていない。
第1期に関しては、通常配当(平成9年3月31日、平成10年3月31日、平成11年3月31日、平成12年3月31日の金銭配当)、中間配当(平成9年6月30日の金銭配当・自己株式取得、平成10年6月30日の自己株式取得、平成11年6月30日の金銭配当)及びその他の配当(平成11年6月18日・9月30日、平成12年5月31日・7月26日の自己株式取得)を行っており、上記の納税者側の主張に反する部分はありません。
また、第3期に関しても、会社法の施行により、自由な時期に金銭配当を行い得るようになったことからすると、不自然なところはなく、上記の納税者側の主張は、首肯できるものです。
要するに、第1期の状態がそのまま第3期の前まで続いていたとしたら、上記の納税者側の主張には何の疑義もないわけです。
しかし、実際には、同じ商法による配当規制の下にありながら、第1期と第2期とで株主への利益還元の方法が大きく異なっています。
何故、平成13年3月を境として、株主への利益還元の方法が大きく変わったのでしょうか。
この問に対する答えは、納税者側の主張の中には見当たりません。
しかし、その答えを推測することは可能です。
上記の表は、日本IBMが公表している「日本IBMトピックス」により平成9年から平成14年までの間の日本IBMの各年の「当期利益」の額を確認し、株主への利益還元額と対比したものです。

この表からも直ぐに分かるとおり、第2期の開始の時期である平成13年と平成14年の株主への利益還元の仕方は、明らかに「不自然」です。平成13年と平成14年の当期利益の合計額は2,012億円ですが、この金額は、平成14年12月20日の自己株式取得の金額2,130億円に非常に近い金額となっています。
図1とこの表を見れば、誰もが、平成13年と平成14年には例年のような株主への利益還元を行わないようにしておいて、中間持株会社を設立したところで、自己株式取得(平成14年12月20日)の方法により、貯めた利益の全てを一度に株主に還元している、と判断するでしょう。
このように、納税者側の主張とは反対に、中間持株会社を設けたことと自己株式取得を行ったことには密接不可分の関係がある、と考えられるわけです。
これは、即ち、中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったことには「不自然」さがあるということを意味していると考えています。
――このように精緻な分析に基づく説明をうかがうと、確かに、本件で問題となっている第2期の自己株式取得は「不自然」に見えてきますね。
朝長 IBM事件において「行為又は計算」が「不自然・不合理」であるということに関しては、以上の二点を指摘しておきたいと思います。
平成13年度改正は、より一層、みなし配当制度を重複課税排除に資する仕組みとする趣旨・目的で行われた改正
――次に、「結果」が「不当」であるということに関してはいかがでしょうか。
朝長 その点については、前回のインタビューで、本件は132条の創設の趣旨・目的からすれば株式譲渡損を否認すべき案件であるということを述べさせて頂きましたが、本件は平成13年のみなし配当に関する改正後の制度を適用して株式譲渡損を計上していますので、同年の改正がどのような趣旨・目的で行われたものか、本件のような株式譲渡損を認める趣旨・目的のものであったのか否かということも明らかにしておく必要があります。本件の株式譲渡損を損金の額とすることが平成13年度改正後のみなし配当制度の趣旨・目的からみて適当でないということであれば、本件の「結果」は「不当」である、ということになります。
このため、まず、この平成13年度改正の趣旨・目的についてご説明しましょう。
平成13年度の法人税法24条1項の規定の帳簿価額基準を廃止する改正は、みなし配当制度について、理論的に正しい仕組みとするとともに、法人段階における重複課税(株式発行法人の所得に対する課税と法人株主の株式譲渡益に対する課税という重複課税)を排除するという受取配当益金不算入制度の創設の趣旨・目的により一層沿う仕組みとすることを趣旨・目的として行われたものです。
この平成13年度改正の際には、この改正の趣旨・目的を次のように説明しています。
(大蔵省主税局税制第一課(法人税制企画室)課長補佐 朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』社団法人日本租税研究協会 53頁 平成13年8月10日)
株主における株式の帳簿価額とは関係なく、「法人がその活動により稼得した利益を還元したと考えられる部分の金額」を正しく捉えることは、みなし配当の制度を理論的に正しい仕組みとすることに資するとともに、法人段階における重複課税を排除することに大きく資することとなります。
この平成13年度改正の二つの趣旨・目的のうち、法人段階における重複課税の排除に大きく資するということについて、帳簿価額基準が働く最も単純なケースで具体的に解説を行うこととします。
次の図2をご覧ください。
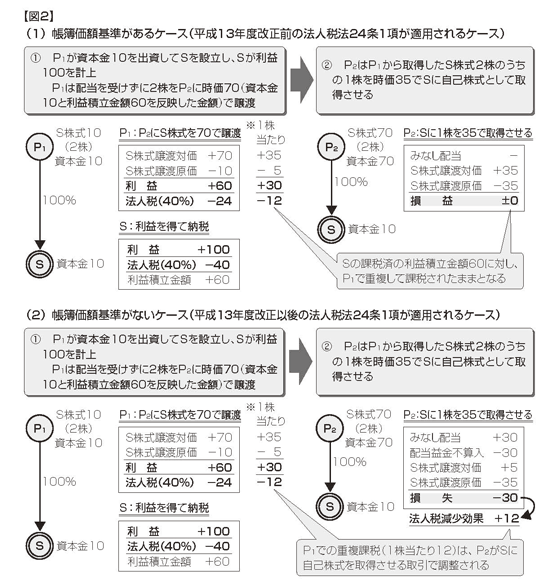
――図2で株式を譲渡するケースを想定しているのは何故ですか?。
朝長 帳簿価額基準は、株式発行法人(図2のS)の資本金等の額を超える金額で株主(図2のP1・P2)が株式の帳簿価額を付している状態でなければ働かないため、帳簿価額基準の検証は、株式発行法人の株式が旧株主から新株主に譲渡されたケースを想定して行う必要があるわけです。
――なるほど。
朝長 図2の二つの図は、法人が子会社を設立して、その子会社において事業を行うケースを示したものであり、図2(1)は帳簿価額基準があるケース、図2(2)は帳簿価額基準がないケースとなっています。
これらのいずれのケースにおいても、P1が保有していたS株式の2株をP2が時価70(資本金10と利益積立金額60を反映した金額)で買い取り、P2は、Sに自己株式1株を時価35で取得させています。
図2(1)のケースを見ると、Sが事業を行って稼得した所得100に対して、法人段階でSに40の課税が行われ、更にP1に24の課税が行われて、合計64の法人税が課される状態となっています。
しかし、全体の所得はSが事業を行って得た100のみですから、本来は、法人段階で課される法人税は、その所得100に対する40のみとなるべきです。
要するに、図2(1)のケースにおいては、P1においてS株式の譲渡利益に対して課される法人税24が過大となっているわけです。
これに対して、図2(2)のケースを見ると、P2においてS株式の1株をSに取得させることによって30の損失が生じているため、法人段階における税負担額は、この損失による12の法人税額の減少効果を加味して、52(Sにおける40+P1における24-P2における12)となっています。
――P1とP2は法人格が異なるため、P1とP2が合併したり連結納税を行ったりしない限り、直ちにP1の利益がP2の損失で相殺されるということにはならないわけですよね。
朝長 そうですね。
しかし、P2の損失をP2の将来の利益から控除することとなった場合には、全体としてみれば、その控除する時点でP1に対して行った課税を取り消した状態と同じ状態になります。
――将来、法人税額が少なくなるわけですね。
朝長 そうなります。
仮に、S株式の分割等が行われて更に自己株式取得が行われるとすれば、P2において生ずる損失は限りなく60に近づくこととなり、法人段階では、P1において計上したS株式の譲渡利益60を実質的に打ち消す損失が計上されて、Sにおいて課された40の法人税のみを負担する状態に近づくこととなります。
この図2(1)のケースと図2(2)のケースとを比べてみて、法人段階の税負担のあり方としていずれが適切かということを考えてみると、図2(2)のケースが適切であるということに異論はないはずです。
これらの二つのケースに違いが生ずるのは、図2(1)のケースにおいては、図2(2)のケースとは異なり、帳簿価額基準があるために、Sが利益積立金額を反映した金額の譲渡対価をP2に支払ったとしても、P2がS株式の帳簿価額を超える譲渡対価の交付を受けない限りみなし配当が発生しないためです。
このように、帳簿価額基準は、結果として、法人段階で重複課税を生じさせるものとなっていたわけです。
このような事情を考慮し、平成13年度改正においては、帳簿価額基準を廃止し、「法人がその活動により稼得した利益を還元したと考えられる部分の金額」を正しく捉えることとして、みなし配当の制度を、より一層、法人段階における重複課税の排除に資する仕組みとすることにしました。
ただし、この平成13年度改正に関しては、図2(1)のケースと図2(2)のケースの例で言えば、P1からP2にS株式が譲渡される際の譲渡益に課税が行われることを前提としていた、ということに留意する必要があります。
要するに、この平成13年度改正は、株主における株式の譲渡益に対する課税によって法人の利益に重複して課税が行われることが有り得ないところにまで、損失の計上を認めて課税所得を減少させることを認めるという趣旨・目的で行ったものではない、ということです。
IBM事件における「結果」はみなし配当制度の趣旨・目的に明らかに反する「不当」なものである
――なるほど。しかし、実際にそのような行為が行われてしまったら、認めざるを得ないということにはならないのでしょうか。
朝長 一般論としては、そのようなケースもあり得ると思います。
しかし、この平成13年度改正と本件のケースに関しては、同改正が本件のようなケースを容認しないという観点に立って行ったものであることは明確ですから、そのようなことにはなりません。
昨年、貴誌のインタビュー(2014.8.25、559号)を受けた際にもご紹介させて頂きましたが、平成12年6月2日の法人課税小委員会においては、みなし配当の制度のあり方に関して、当時の大蔵省主税局が作成した「3 みなし配当に係る現行税制の論点(例)」という資料に基づき、検討が行われています。この資料は、平成13年度改正前の法人税法24条2項の規定に定められていた資産の交付がない場合のみなし配当の規定の問題を指摘したものであり、その問題があったために、同改正において同項を廃止することとなったものですが、この資料に記載されているみなし配当の制度の問題とは、資産の交付がない場合には、みなし配当が益金不算入となって課税対象とならない一方でそのみなし配当相当額だけ株式の帳簿価額が増額されることから、その後、その株式の評価益の過少計上、評価損の計上、譲渡益の過少計上、譲渡損の計上を通じて、課税所得を減少させる結果となる、というものです。
要するに、課税を受けずに株式の帳簿価額を引き上げることによって、実際には生じているはずの利益を計上させないこととなったり、実際には生じていないはずの損失を計上させることとなったりすることで、課税所得を減少させる結果となるものは、課税上の弊害があると言わざるを得ず、認めるわけにはいかない、ということです。
この資料は、24条2項の規定を廃止する改正の資料であり、1項の改正に関する資料ではありませんが、課税を受けずに株式の帳簿価額を引き上げて課税所得を圧縮することを認めないこととするために2項を廃止する改正を行っておきながら、同時に、課税を受けずに帳簿価額を引き上げて課税所得を圧縮することを1項において認めることとする改正を行うなどということは、絶対に有り得ません。
――平成13年度の24条の改正は、全体としてみれば、IBM事件における「結果」を容認しない趣旨・目的で行われたものであることが明らかであり、IBM事件における「結果」は、みなし配当制度の趣旨・目的に明らかに反する「不当」なものである、ということですね。
朝長 そういうことになります。
IBM事件における「結果」は法人税法そのものの趣旨・目的にも反する明らかに「不当」なものである
――昨年の朝長先生へのインタビューの中で、IBM事件においては日本とアメリカのいずれでも課税されない所得を創り出しているというお話がありましたが、この点に関しても、もう少し具体的にお話を聞かせてください。
朝長 分かり易いように、シンプルなケースでご説明しましょう。
次の図3は、通常の自己株式取得を行ったもの(ケース1)、中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったもの(ケース2)、そして、本件と同じようにアメリカの株主と日本の法人との間に中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったもの(ケース3)について、それぞれの法人税における取扱いを示したものです。
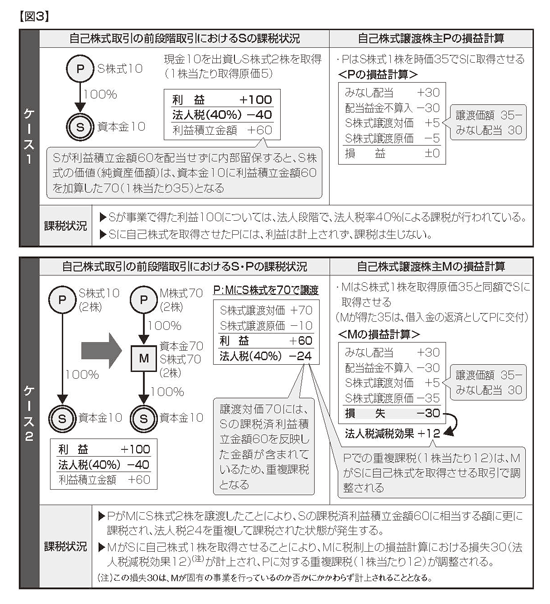
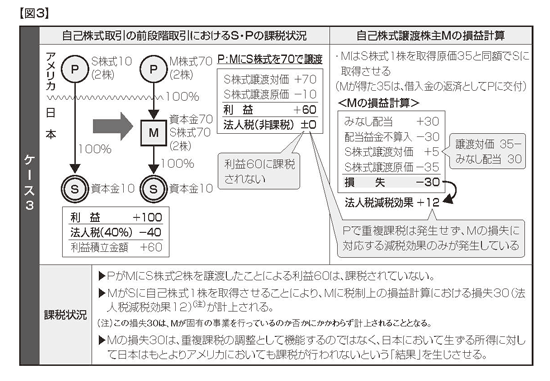
図3の三つのケースにおいては、いずれも事業はSのみが行い、その事業で得られた利益はいずれも100で、法人税率はいずれも40%と仮定しています。
ケース1:通常の自己株式取得 ケース1においては、P・Sのグループは、Sが事業を行って稼得した100の利益について、法人段階で法人税率40%に相当する法人税40を負担することとなっています。
このケースは、何ら疑義のない通常の自己株式取得の取扱いとなっています。
ケース2:親会社が中間持株会社を設けて行う自己株式取得 ケース2は、中間持株会社を設けて自己株式取得を行うこととしたケースです。
このケースにおいては、株式の譲渡益に対して課税が行われ、自己株式取得に伴ってみなし配当と株式の譲渡損失が計上されることとなります。
また、このケースでは、Sの利益100について法人税40を負担しながら、更に、Sの利益積立金額60を反映して値が増加したS株式の譲渡益60についても法人税24を負担することとなり、重複課税が先行することとなりますが、MがS株式を自己株式取得により手放す都度、先に計上した譲渡益を実質的に打ち消す損失を計上する状態となって、次第に法人段階における重複課税が是正されることとなります。
ケース3:米国の親会社が日本に中間持株会社を設けて行う自己株式取得 ケース3は、中間持株会社を設けて自己株式取得を行う点ではケース2と同様ですが、PにおいてS株式の譲渡益に課税が行われないという点で、ケース2とは大きく異なります。このケースにおいては、PにおけるS株式の譲渡益の課税によってSの利益に重複して課税が行われることが有り得ないにもかかわらず、Mで損失を計上されているわけです。
このため、このケースにおいては、Mの損失30は、法人段階における重複課税を排除するのではなく、日本における事業で得る所得30に対する日本の課税を免れるという「結果」を生じさせることになります。
そして、この日本における事業で得る所得30に対しては、日本とアメリカのいずれの国においても課税されることはないわけです。
当然のことながら、法人税法は、「所得」があればそれに過不足なく課税することを予定しており、このケースのように、現に「所得」が存在するにもかかわらず、その「所得」に対して課税を行わないという状態は、所得課税の理論では説明できず、課税上も弊害のある異常な事態と言わなければなりません。
――なるほど。IBM事件の「結果」は、そもそも「所得」に課税をするという法人税法の趣旨・目的にも反しているため、「不当」であるということですね。
朝長 そうです。
IBM事件においては、日本で稼得した「所得」がどの国でも課税されないという「結果」になっているわけですが、この「結果」は、平成13年度改正によるみなし配当の制度の趣旨・目的に反するというに止まらず、法人税法そのものの趣旨・目的にも反する明らかに「不当」なものであると考えています。
昨年のインタビューの最後にお話をさせて頂いたように、IBM事件は、日本IBMに大きな利益があればあるほど大きな損失が計上できるというスキームになっており、被合併法人で実際に発生した損失を合併法人で控除してよいのか否かが争われているヤフー事件よりも、明らかに「租税回避」の性格が強いと思っています。IBM事件のようなスキームで税負担を減少させることは、社会通念上も容認されないものと考えられます。
二つの「租税回避」事件に関する見解が求められる
――今回のインタビューで、132条の解釈やIBM事件の内容に関する理解が相当に深まりました。
朝長 IBM事件は、初めて包括的な租税回避防止規定として創られた132条の解釈と適用が争われているものであり、ヤフー事件以上に重要な事件と言ってもよいものであることは、既に述べたとおりです。
ヤフー事件においては、私だけでなく、国側で今村先生、納税者側で7名の税法学者が132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の解釈・適用に関して鑑定意見書を書かれています。この納税者側で鑑定意見書を書かれた7名のうちの一人は、IBM事件に関して「法律鑑定意見書」を書かれており、見解が分かりましたので、昨年のインタビュー(2014.8.25、559号)で触れさせて頂いたところですが、他の方々も、ヤフー事件とともにIBM事件に関する見解を披歴して頂くと、「租税回避」に関する研究や実務の水準の向上に資するものと思われます。
第1回目のインタビューでもお話をさせて頂いたところですが、時期を同じくして起こったこれらの二つの「租税回避」事件は、従来の「租税回避」に関する理論や条文解釈を抜本的に変えることになる可能性のあるかつてない極めて重要な事件ですから、出来るだけ多くの研究者や実務家が自らの見解を出されるべきであると思っています。
――これらの二つの事件は、いずれも我が国における最も重要な税務訴訟事件の一つに数えられることになるものと思われますので、そうなるように期待したいですね。
第1回から今回まで長時間にわたり、非常に貴重なお話を聞かせて頂き、誠に有り難うございました。本件の判決が確定しましたら、またお話をお聞かせ下さい。
朝長 判決が確定しましたら、裁判では触れられなかったことも含め、少し視野を広げてお話をしたいと思っています。
――宜しくお願いします。
(了)
IBM事件はヤフー事件よりも「租税回避」の性格が強い
検証・IBM事件 高裁判決〔第3回〕
前2回の朝長英樹税理士(日本税制研究所 代表理事)へのインタビュー(592号、595号参照)では、IBM事件の高裁判決は、法人税法132条に関して創設の趣旨・目的等とは相容れない「経済的合理性」基準によって「租税回避」に該当するか否かを判定するという解釈を採っていることが明らかになったところだ。これは、132条の解釈の従来の通説を否定するものであり、また、この高裁判決により、「事業目的」や「事業上の理由」が有りさえすれば「租税回避」には当たらないという理解に基づく現在の実務が通用しなくなるおそれがある。
これに対し朝長税理士は、「132条の創設の趣旨・目的を踏まえ、同条を文理に即して正しく解釈すれば、税制度の「濫用」や「潜脱」を同条が適用される「租税回避」とするべきである」と主張する。そして、このような解釈に基づき、IBM事件には132条が適用されるべきであるという。
最終回である今回は、132条がIBM事件に適用されるべき理由を詳細に語ってもらった。
全3回のインタビューで朝長税理士により示されたIBM事件に対する論理的で深度ある緻密な検証は、132条の「租税回避」に関する従来の学説と実務に非常に大きなインパクトを与えることになろう。
巨額の税金に全く関心を持たずに大きな再編等を行ったというのであれば、明らかに「不自然」
――今回はまず、前回のインタビューの最後にお話が出た法人税法132条の「行為又は計算」が「不自然・不合理」であることについてうかがいたいと思います。「不自然・不合理」とは具体的にどういうことでしょうか?
朝長 重要なところから二点をお話しておきたいと思います。
一点目は、1千億円以上ともなる税金に全く関心を持たずにグループ再編(中間持株会社の設置)や資本等取引(自己株式取得)を行ったということであれば、それらの行為は、明らかに「不自然」であるということです。
実際に実務に携わってみると分かりますが、大企業が大きなグループ再編や巨額の資本等取引を行う場合には、法務・税務・会計の取扱いを注意深く検討することになります。特に税務については、法務や会計よりも難解な部分が多い上、最終利益に大きな影響を与え、しかも、後に税務調査を受けることにもなりますので、慎重に検討するのが通例であり、税務について検討しないなどということは、まず有り得ないはずです。通常は、社内の税務担当者や社外の税務の専門家がスキーム、税額を示したケーススタディ、利益への影響、スケジュール、法令の規定や関係通達などを示した資料を作成して詳細な検討を繰り返し、案が出来たら、これらの資料を用いて役員等に説明を行うということになります。当然、社内や社外の税務の専門家との間においては、メールのやり取りも頻繁に行われることになります。これらの一連の作業が一回で終わるということは、ほとんどありません。
しかし、IBM事件においては、ヤフー事件と対照的に、このような検討ややり取り等を行ったことを確認できるものがほとんど出てきていません。
訴訟の場では、納税者側から、中間持株会社に巨額の株式譲渡損が生じて青色欠損金となることについて「全く関心を持っていなかった」「何の関心も持っていなかった」という主張が繰り返し行われているわけですが、本件のような大きなグループ再編や巨額の資本等取引を行う場合に税務に関心を持たないなどということは現実にはあり得ず、むしろ、反対に「最大の関心事項」であったとしても、決しておかしくないと思っています。
これは、基本的には、実際にそのようなことが在ったのか無かったのかという事実に関する問題ですが、上記の詳細な検討ややり取り等が行われないまま本件のグループ再編や資本等取引が行われたということであれば、本件のグループ再編や資本等取引は、明らかに「不自然」な行為と言わざるを得ません。
――上記の詳細な検討ややり取り等が行われていたのであれば、その内容を確認できるものが示されていないことに問題があり、他方、それらが行われていなかったというのであれば、本件のグループ再編や資本等取引は明らかに「不自然」である、ということですね。
朝長 そうです。上記の「全く関心を持っていなかった」云々というような主張は、実際にグループ再編や資本等取引を行っている実務者の間では有り得ないものであると考えています。
税金の影響額が1千億円以上となるにもかかわらず税金がどうなるのかということに全く関心を持たずに大きなグループ再編や巨額の資本等取引が行われるなどということは、ほとんど考えられません。もし、そのようなことがあったというのであれば、それらの行為は、「不自然・不合理」ということを通り越して「異常」と言っても過言ではないと思います。
中間持株会社を設けて自己株式取得を行うことも「不自然」
――もう一点はどういうことでしょうか。
朝長 中間持株会社を設けた上で自己株式取得を行うことは「不自然」である、ということです。
納税者側は、中間持株会社を設けたことと自己株式取得を行ったことは関係がなく、自己株式取得は平成9年から行ってきたことの延長線上で行われたものであり、「日本IBMが、株主への利益還元を目的として、通常配当の方法とともに自己株式取得という方法を使用していたのは、当時の商法上、日本の株式会社が配当を行うことが許されるタイミングに制約があったことから、通常配当や中間配当を行うことができないタイミングでの株主への利益還元を実現するためであって、平成18(2006)年の会社法施行により、株式会社の配当可能時期に法律上の制約がなくなった時点以降は、日本IBMは株主への利益還元を全て通常配当の方法により行っている。」と主張していますが、この主張に関しても、多分に疑義があります。
図1は、地裁の段階で国側から提出された日本IBMの株主への利益還元の状況の一覧表(本誌556号11頁参照)に基づいて作成したものです。
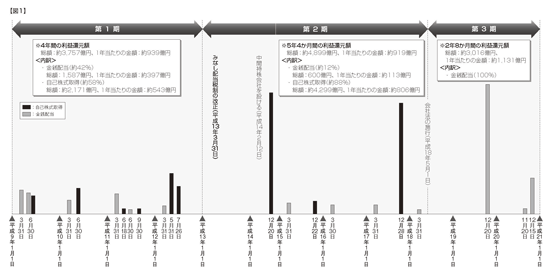
この図1を見れば、日本IBMによる株主への利益還元の方法が図1に示した第1期、第2期及び第3期で大きく異なっていることが一目瞭然です。
本件において問題となっているのは、第2期における平成14年12月20日、平成15年12月22日及び平成17年12月28日の自己株式取得です。
――日本IBMの株主への利益還元の状況の一覧表を見て、自己株式取得は昔から行われており、平成13年・14年に自己株式取得を行ったことは、何ら「不自然・不合理」ではないのではないかと思っていましたが、こうしてグラフで見ると全く印象が違いますね。
朝長 この図1からは、次のような特徴を読み取ることができます。
ⅰ 日本IBMは、平成9年から平成20年までの12年間に、日本で事業を行って得た利益から約1兆2千億円を米国IBMに還元しており、日本IBMの米国IBMへの1年当たりの利益の還元額は、約1千億円と考えてもよい。
ⅱ 第1期の4年間は、毎年、通常配当と中間配当を行うことを繰り返してきており、金銭配当と自己株式取得の割合も、概ねバランスが保たれている。
ⅲ 第2期は、第1期と大きく異なり、通常配当と中間配当を毎年繰り返すパターンが崩れて、金銭配当と自己株式取得の割合もバランスが崩れてしまっている。
ⅳ 第2期は、法人税法24条1項の規定の改正が行われた平成13年3月から通常配当が行われなくなっており、平成14年12月20日に多額の自己株式取得が行われるまで、約1年9か月間、一度も株主への利益還元が行われていない。
ⅴ 第1期の1年当たりの利益還元額は約939億円、第2期の1年当たりの利益還元額は約919億円であり大差はないが、金銭配当と自己株式取得の割合は、第1期が42%:58%、第2期が12%:88%となっており、第2期は、自己株式取得の割合が極めて大きくなっている。
ⅵ 第1期及び第2期においても、第3期の平成19年12月20日の金銭配当のような多額の金銭配当を行い得るにもかかわらず、一度もそのような多額の金銭配当は行われたことがなく、第2期の2回の多額な株主への利益還元も、自己株式取得として行われている。
ⅶ 第3期は、会社法改正により、任意の時期に株主への利益還元が行い得ないために自己株式取得を行っているという説明が困難となっているが、この時期には自己株式取得は行われていない。
第1期に関しては、通常配当(平成9年3月31日、平成10年3月31日、平成11年3月31日、平成12年3月31日の金銭配当)、中間配当(平成9年6月30日の金銭配当・自己株式取得、平成10年6月30日の自己株式取得、平成11年6月30日の金銭配当)及びその他の配当(平成11年6月18日・9月30日、平成12年5月31日・7月26日の自己株式取得)を行っており、上記の納税者側の主張に反する部分はありません。
また、第3期に関しても、会社法の施行により、自由な時期に金銭配当を行い得るようになったことからすると、不自然なところはなく、上記の納税者側の主張は、首肯できるものです。
要するに、第1期の状態がそのまま第3期の前まで続いていたとしたら、上記の納税者側の主張には何の疑義もないわけです。
しかし、実際には、同じ商法による配当規制の下にありながら、第1期と第2期とで株主への利益還元の方法が大きく異なっています。
何故、平成13年3月を境として、株主への利益還元の方法が大きく変わったのでしょうか。
この問に対する答えは、納税者側の主張の中には見当たりません。
しかし、その答えを推測することは可能です。
上記の表は、日本IBMが公表している「日本IBMトピックス」により平成9年から平成14年までの間の日本IBMの各年の「当期利益」の額を確認し、株主への利益還元額と対比したものです。

この表からも直ぐに分かるとおり、第2期の開始の時期である平成13年と平成14年の株主への利益還元の仕方は、明らかに「不自然」です。平成13年と平成14年の当期利益の合計額は2,012億円ですが、この金額は、平成14年12月20日の自己株式取得の金額2,130億円に非常に近い金額となっています。
図1とこの表を見れば、誰もが、平成13年と平成14年には例年のような株主への利益還元を行わないようにしておいて、中間持株会社を設立したところで、自己株式取得(平成14年12月20日)の方法により、貯めた利益の全てを一度に株主に還元している、と判断するでしょう。
このように、納税者側の主張とは反対に、中間持株会社を設けたことと自己株式取得を行ったことには密接不可分の関係がある、と考えられるわけです。
これは、即ち、中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったことには「不自然」さがあるということを意味していると考えています。
――このように精緻な分析に基づく説明をうかがうと、確かに、本件で問題となっている第2期の自己株式取得は「不自然」に見えてきますね。
朝長 IBM事件において「行為又は計算」が「不自然・不合理」であるということに関しては、以上の二点を指摘しておきたいと思います。
平成13年度改正は、より一層、みなし配当制度を重複課税排除に資する仕組みとする趣旨・目的で行われた改正
――次に、「結果」が「不当」であるということに関してはいかがでしょうか。
朝長 その点については、前回のインタビューで、本件は132条の創設の趣旨・目的からすれば株式譲渡損を否認すべき案件であるということを述べさせて頂きましたが、本件は平成13年のみなし配当に関する改正後の制度を適用して株式譲渡損を計上していますので、同年の改正がどのような趣旨・目的で行われたものか、本件のような株式譲渡損を認める趣旨・目的のものであったのか否かということも明らかにしておく必要があります。本件の株式譲渡損を損金の額とすることが平成13年度改正後のみなし配当制度の趣旨・目的からみて適当でないということであれば、本件の「結果」は「不当」である、ということになります。
このため、まず、この平成13年度改正の趣旨・目的についてご説明しましょう。
平成13年度の法人税法24条1項の規定の帳簿価額基準を廃止する改正は、みなし配当制度について、理論的に正しい仕組みとするとともに、法人段階における重複課税(株式発行法人の所得に対する課税と法人株主の株式譲渡益に対する課税という重複課税)を排除するという受取配当益金不算入制度の創設の趣旨・目的により一層沿う仕組みとすることを趣旨・目的として行われたものです。
この平成13年度改正の際には、この改正の趣旨・目的を次のように説明しています。
| 現行制度においては、法人税におけるみなし配当額は、株主が交付を受けた金銭等の額が旧株の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額とすることとされていますが、法人がその活動により稼得した利益を還元したと考えられる部分の金額の有無や多寡は、株主の株式の帳簿価額とは関係がありませんので、改正案においては、この帳簿価額を基準とする取扱いを廃止することとされています。 |
株主における株式の帳簿価額とは関係なく、「法人がその活動により稼得した利益を還元したと考えられる部分の金額」を正しく捉えることは、みなし配当の制度を理論的に正しい仕組みとすることに資するとともに、法人段階における重複課税を排除することに大きく資することとなります。
この平成13年度改正の二つの趣旨・目的のうち、法人段階における重複課税の排除に大きく資するということについて、帳簿価額基準が働く最も単純なケースで具体的に解説を行うこととします。
次の図2をご覧ください。
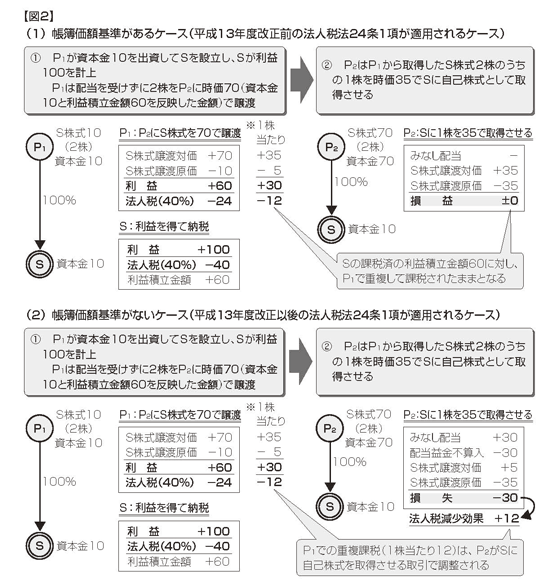
――図2で株式を譲渡するケースを想定しているのは何故ですか?。
朝長 帳簿価額基準は、株式発行法人(図2のS)の資本金等の額を超える金額で株主(図2のP1・P2)が株式の帳簿価額を付している状態でなければ働かないため、帳簿価額基準の検証は、株式発行法人の株式が旧株主から新株主に譲渡されたケースを想定して行う必要があるわけです。
――なるほど。
朝長 図2の二つの図は、法人が子会社を設立して、その子会社において事業を行うケースを示したものであり、図2(1)は帳簿価額基準があるケース、図2(2)は帳簿価額基準がないケースとなっています。
これらのいずれのケースにおいても、P1が保有していたS株式の2株をP2が時価70(資本金10と利益積立金額60を反映した金額)で買い取り、P2は、Sに自己株式1株を時価35で取得させています。
図2(1)のケースを見ると、Sが事業を行って稼得した所得100に対して、法人段階でSに40の課税が行われ、更にP1に24の課税が行われて、合計64の法人税が課される状態となっています。
しかし、全体の所得はSが事業を行って得た100のみですから、本来は、法人段階で課される法人税は、その所得100に対する40のみとなるべきです。
要するに、図2(1)のケースにおいては、P1においてS株式の譲渡利益に対して課される法人税24が過大となっているわけです。
これに対して、図2(2)のケースを見ると、P2においてS株式の1株をSに取得させることによって30の損失が生じているため、法人段階における税負担額は、この損失による12の法人税額の減少効果を加味して、52(Sにおける40+P1における24-P2における12)となっています。
――P1とP2は法人格が異なるため、P1とP2が合併したり連結納税を行ったりしない限り、直ちにP1の利益がP2の損失で相殺されるということにはならないわけですよね。
朝長 そうですね。
しかし、P2の損失をP2の将来の利益から控除することとなった場合には、全体としてみれば、その控除する時点でP1に対して行った課税を取り消した状態と同じ状態になります。
――将来、法人税額が少なくなるわけですね。
朝長 そうなります。
仮に、S株式の分割等が行われて更に自己株式取得が行われるとすれば、P2において生ずる損失は限りなく60に近づくこととなり、法人段階では、P1において計上したS株式の譲渡利益60を実質的に打ち消す損失が計上されて、Sにおいて課された40の法人税のみを負担する状態に近づくこととなります。
この図2(1)のケースと図2(2)のケースとを比べてみて、法人段階の税負担のあり方としていずれが適切かということを考えてみると、図2(2)のケースが適切であるということに異論はないはずです。
これらの二つのケースに違いが生ずるのは、図2(1)のケースにおいては、図2(2)のケースとは異なり、帳簿価額基準があるために、Sが利益積立金額を反映した金額の譲渡対価をP2に支払ったとしても、P2がS株式の帳簿価額を超える譲渡対価の交付を受けない限りみなし配当が発生しないためです。
このように、帳簿価額基準は、結果として、法人段階で重複課税を生じさせるものとなっていたわけです。
このような事情を考慮し、平成13年度改正においては、帳簿価額基準を廃止し、「法人がその活動により稼得した利益を還元したと考えられる部分の金額」を正しく捉えることとして、みなし配当の制度を、より一層、法人段階における重複課税の排除に資する仕組みとすることにしました。
ただし、この平成13年度改正に関しては、図2(1)のケースと図2(2)のケースの例で言えば、P1からP2にS株式が譲渡される際の譲渡益に課税が行われることを前提としていた、ということに留意する必要があります。
要するに、この平成13年度改正は、株主における株式の譲渡益に対する課税によって法人の利益に重複して課税が行われることが有り得ないところにまで、損失の計上を認めて課税所得を減少させることを認めるという趣旨・目的で行ったものではない、ということです。
IBM事件における「結果」はみなし配当制度の趣旨・目的に明らかに反する「不当」なものである
――なるほど。しかし、実際にそのような行為が行われてしまったら、認めざるを得ないということにはならないのでしょうか。
朝長 一般論としては、そのようなケースもあり得ると思います。
しかし、この平成13年度改正と本件のケースに関しては、同改正が本件のようなケースを容認しないという観点に立って行ったものであることは明確ですから、そのようなことにはなりません。
昨年、貴誌のインタビュー(2014.8.25、559号)を受けた際にもご紹介させて頂きましたが、平成12年6月2日の法人課税小委員会においては、みなし配当の制度のあり方に関して、当時の大蔵省主税局が作成した「3 みなし配当に係る現行税制の論点(例)」という資料に基づき、検討が行われています。この資料は、平成13年度改正前の法人税法24条2項の規定に定められていた資産の交付がない場合のみなし配当の規定の問題を指摘したものであり、その問題があったために、同改正において同項を廃止することとなったものですが、この資料に記載されているみなし配当の制度の問題とは、資産の交付がない場合には、みなし配当が益金不算入となって課税対象とならない一方でそのみなし配当相当額だけ株式の帳簿価額が増額されることから、その後、その株式の評価益の過少計上、評価損の計上、譲渡益の過少計上、譲渡損の計上を通じて、課税所得を減少させる結果となる、というものです。
要するに、課税を受けずに株式の帳簿価額を引き上げることによって、実際には生じているはずの利益を計上させないこととなったり、実際には生じていないはずの損失を計上させることとなったりすることで、課税所得を減少させる結果となるものは、課税上の弊害があると言わざるを得ず、認めるわけにはいかない、ということです。
この資料は、24条2項の規定を廃止する改正の資料であり、1項の改正に関する資料ではありませんが、課税を受けずに株式の帳簿価額を引き上げて課税所得を圧縮することを認めないこととするために2項を廃止する改正を行っておきながら、同時に、課税を受けずに帳簿価額を引き上げて課税所得を圧縮することを1項において認めることとする改正を行うなどということは、絶対に有り得ません。
――平成13年度の24条の改正は、全体としてみれば、IBM事件における「結果」を容認しない趣旨・目的で行われたものであることが明らかであり、IBM事件における「結果」は、みなし配当制度の趣旨・目的に明らかに反する「不当」なものである、ということですね。
朝長 そういうことになります。
IBM事件における「結果」は法人税法そのものの趣旨・目的にも反する明らかに「不当」なものである
――昨年の朝長先生へのインタビューの中で、IBM事件においては日本とアメリカのいずれでも課税されない所得を創り出しているというお話がありましたが、この点に関しても、もう少し具体的にお話を聞かせてください。
朝長 分かり易いように、シンプルなケースでご説明しましょう。
次の図3は、通常の自己株式取得を行ったもの(ケース1)、中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったもの(ケース2)、そして、本件と同じようにアメリカの株主と日本の法人との間に中間持株会社を設けて自己株式取得を行ったもの(ケース3)について、それぞれの法人税における取扱いを示したものです。
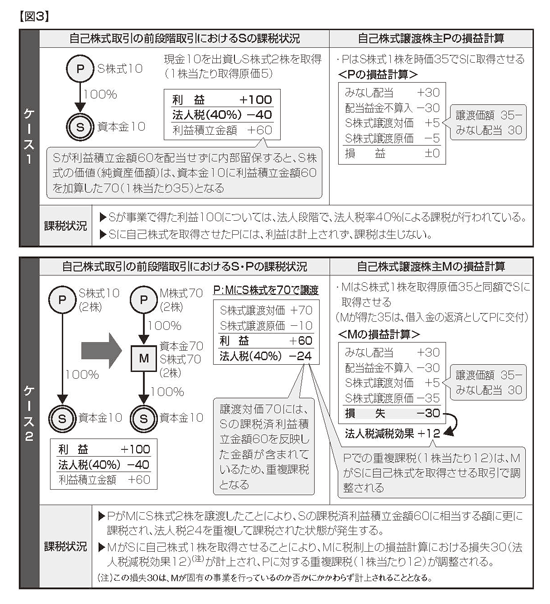
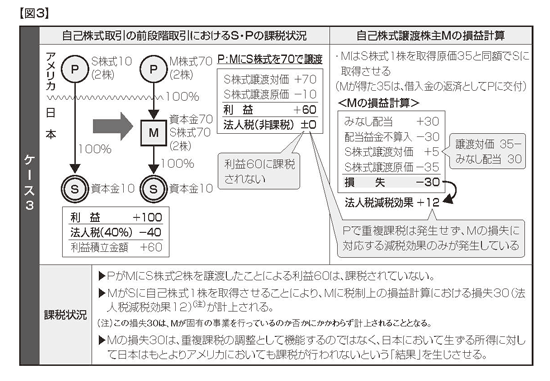
図3の三つのケースにおいては、いずれも事業はSのみが行い、その事業で得られた利益はいずれも100で、法人税率はいずれも40%と仮定しています。
ケース1:通常の自己株式取得 ケース1においては、P・Sのグループは、Sが事業を行って稼得した100の利益について、法人段階で法人税率40%に相当する法人税40を負担することとなっています。
このケースは、何ら疑義のない通常の自己株式取得の取扱いとなっています。
ケース2:親会社が中間持株会社を設けて行う自己株式取得 ケース2は、中間持株会社を設けて自己株式取得を行うこととしたケースです。
このケースにおいては、株式の譲渡益に対して課税が行われ、自己株式取得に伴ってみなし配当と株式の譲渡損失が計上されることとなります。
また、このケースでは、Sの利益100について法人税40を負担しながら、更に、Sの利益積立金額60を反映して値が増加したS株式の譲渡益60についても法人税24を負担することとなり、重複課税が先行することとなりますが、MがS株式を自己株式取得により手放す都度、先に計上した譲渡益を実質的に打ち消す損失を計上する状態となって、次第に法人段階における重複課税が是正されることとなります。
ケース3:米国の親会社が日本に中間持株会社を設けて行う自己株式取得 ケース3は、中間持株会社を設けて自己株式取得を行う点ではケース2と同様ですが、PにおいてS株式の譲渡益に課税が行われないという点で、ケース2とは大きく異なります。このケースにおいては、PにおけるS株式の譲渡益の課税によってSの利益に重複して課税が行われることが有り得ないにもかかわらず、Mで損失を計上されているわけです。
このため、このケースにおいては、Mの損失30は、法人段階における重複課税を排除するのではなく、日本における事業で得る所得30に対する日本の課税を免れるという「結果」を生じさせることになります。
そして、この日本における事業で得る所得30に対しては、日本とアメリカのいずれの国においても課税されることはないわけです。
当然のことながら、法人税法は、「所得」があればそれに過不足なく課税することを予定しており、このケースのように、現に「所得」が存在するにもかかわらず、その「所得」に対して課税を行わないという状態は、所得課税の理論では説明できず、課税上も弊害のある異常な事態と言わなければなりません。
――なるほど。IBM事件の「結果」は、そもそも「所得」に課税をするという法人税法の趣旨・目的にも反しているため、「不当」であるということですね。
朝長 そうです。
IBM事件においては、日本で稼得した「所得」がどの国でも課税されないという「結果」になっているわけですが、この「結果」は、平成13年度改正によるみなし配当の制度の趣旨・目的に反するというに止まらず、法人税法そのものの趣旨・目的にも反する明らかに「不当」なものであると考えています。
昨年のインタビューの最後にお話をさせて頂いたように、IBM事件は、日本IBMに大きな利益があればあるほど大きな損失が計上できるというスキームになっており、被合併法人で実際に発生した損失を合併法人で控除してよいのか否かが争われているヤフー事件よりも、明らかに「租税回避」の性格が強いと思っています。IBM事件のようなスキームで税負担を減少させることは、社会通念上も容認されないものと考えられます。
二つの「租税回避」事件に関する見解が求められる
――今回のインタビューで、132条の解釈やIBM事件の内容に関する理解が相当に深まりました。
朝長 IBM事件は、初めて包括的な租税回避防止規定として創られた132条の解釈と適用が争われているものであり、ヤフー事件以上に重要な事件と言ってもよいものであることは、既に述べたとおりです。
ヤフー事件においては、私だけでなく、国側で今村先生、納税者側で7名の税法学者が132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の解釈・適用に関して鑑定意見書を書かれています。この納税者側で鑑定意見書を書かれた7名のうちの一人は、IBM事件に関して「法律鑑定意見書」を書かれており、見解が分かりましたので、昨年のインタビュー(2014.8.25、559号)で触れさせて頂いたところですが、他の方々も、ヤフー事件とともにIBM事件に関する見解を披歴して頂くと、「租税回避」に関する研究や実務の水準の向上に資するものと思われます。
第1回目のインタビューでもお話をさせて頂いたところですが、時期を同じくして起こったこれらの二つの「租税回避」事件は、従来の「租税回避」に関する理論や条文解釈を抜本的に変えることになる可能性のあるかつてない極めて重要な事件ですから、出来るだけ多くの研究者や実務家が自らの見解を出されるべきであると思っています。
――これらの二つの事件は、いずれも我が国における最も重要な税務訴訟事件の一つに数えられることになるものと思われますので、そうなるように期待したいですね。
第1回から今回まで長時間にわたり、非常に貴重なお話を聞かせて頂き、誠に有り難うございました。本件の判決が確定しましたら、またお話をお聞かせ下さい。
朝長 判決が確定しましたら、裁判では触れられなかったことも含め、少し視野を広げてお話をしたいと思っています。
――宜しくお願いします。
(了)
| 朝長英樹 ともなが ひでき 財務省主税局において、金融取引に係る法人税制の抜本改正(平成12年)・組織再編成税制の創設(平成13年)・連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。 税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。 現在、日本税制研究所 代表理事、朝長英樹税理士事務所 所長 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















