解説記事2015年09月07日 【実務解説】 国外転出時課税制度の概要と問題点(特に国外転出相続時課税において申告期限で未分割の場合)(2015年9月7日号・№609)
実務解説
国外転出時課税制度の概要と問題点(特に国外転出相続時課税において申告期限で未分割の場合)
税理士 竹内陽一
1 国外転出時課税制度の概要 有価証券等1億円以上(価額は所基通59-6による。)を有する居住者(下記図表1の事由前10年以内に5年超住所を有していた場合)に、図表1の各事由(国外転出、贈与、相続)が発生した場合に、転出居住者が保有する有価証券、非居住者受贈者が取得した有価証券、非居住者相続人全員が取得した有価証券について、みなし譲渡課税が課税される。
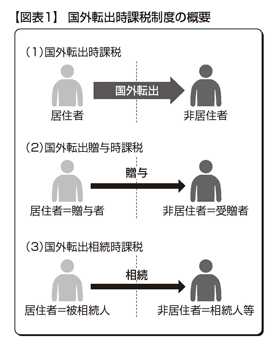
いずれの場合も、居住者本人、非居住者受贈者、非居住者相続人全員(この場合のみ、全員とされているので注意が必要)が各事由の日以後5年以内に帰国した場合に、更正の請求により、取消しとなる。
国外転出時課税と国外転出相続時課税については、一定の期限内に納税管理人届出をした場合にのみ、担保提供等により納税猶予が選択できる。国外転出贈与時課税については、担保提供等により納税猶予が選択できる。
納税猶予の場合、原則5年以内、延長して10年以内に帰国すれば、更正の請求により取消しとなる。一部譲渡があれば、当然一部期限確定となる。5年以内の帰国は納税猶予を選択しなかった場合においても、当然取消しとなる(所法60条の2⑥、60条の3⑥)。
納税猶予の特典として、譲渡による一部期限確定及び期間満了による全部期限確定において、価値が下落していた場合の期限確定した所得税についての減額規定があるが、これは期限確定により納付した所得税についてであって、5年以内等帰国の場合は、そもそも取消しとなり、課税自体が消滅する。
2 国外転出時課税の評価日・申告期限・納税猶予申請期限
(1)国外転出時課税 国外転出時課税の申告期限と納税猶予は次の3類型となる(図表2参照)。
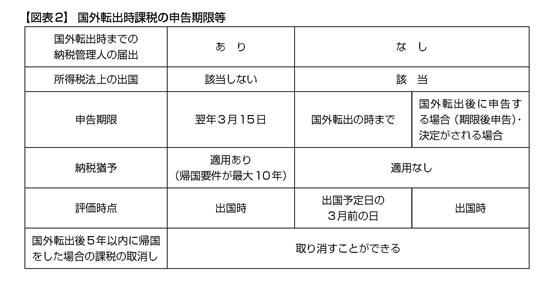
① 国外転出時までに納税管理人の届出がない場合……評価時点は出国予定日の3月前の日となり、出国前に申告と納税が必要となる。唯一、評価日の特例はこの場合のみで、他の全ての場合、評価日は各事由発生日である。この場合納税猶予の選択はない。
② 国外転出時までに納税管理人の届出をした場合……通常の確定申告期限(翌年3/15)となり、納付も確定申告と同様であり、納税猶予の選択ができる。
これは納税管理人の届出を国外転出時までに行った場合のみである。
③ 国外転出時までの納税管理人の届出がなく、出国後に期限後申告を行う場合……期限後申告となる。評価時点は出国時、又は決定される場合(この特例の期間制限は法定申告期限から7年に延長された)、納税猶予選択はできない。
以下、国外転出時課税制度の納税猶予には、期限内申告要件と担保提供要件がある。納税猶予選択の場合、5年以内帰国要件が最大10年に延長できる。なお課税の場合も納税猶予の場合も帰国取消し要件は共通であり、納税猶予の場合のみ10年に延長できる。
以下すべての国外転出時課税制度において、5年以内帰国と更正の請求による取消し規定がある。
(2)国外転出贈与時課税 確定申告期限(翌年3/15)が居住者贈与者のみなし譲渡申告期限となり、非居住者受贈者の贈与税申告期限となる。納税管理人の届出は意味がないので、納税猶予の選択は担保提供等により、常に可能であり、5年以内等の非居住者受贈者の帰国後の更正の請求により取消しとなる。
3 国外転出相続時課税と準確定申告期限において未分割の場合の問題点 準確定の申告期限は死亡の日より4月以内とされており、国外転出相続時みなし譲渡課税についての申告期限は、特に制度上措置されなかった。
しかしながらこの4月以内の期限は、非居住者相続人が株式等を相続するか否かに関わる問題であり、単に被相続人の生前の所得を申告するものではないことから、実務上、大変困難であり、この倍の8月程度の期間がほしいところである。
納税管理人の届出は、この4月以内で、非居住者相続人の全員が届け出た場合のみが納税猶予の対象となる。
準確定の申告期限において、有価証券が未分割か分割かは納税者において大問題であるが、このみなし譲渡課税の所得税の制度においては、準確定申告時に未分割であって、その後に分割が確定した場合の規定が一切規定されていない(相続税法では55条、32条①一に相当する規定)。
準確定申告時に未分割である場合に、相続税法55条に準じて申告するように言われているが、相続税法55条の本書きはいわば確認的規定であり、その但書及び相続税法32条(30条・31条)は創設的規定である。
国外転出相続時課税にこのような条文がない状態において、未分割の場合に、未分割でみなし譲渡課税の申告をすることは、分割確定時に更正の請求ができるかどうかがわからない状態にあるので、実務的には十分な注意が必要である。
特に所得税においては、タックスアンサーNo.1376不動産所得の収入計上時期(未分割遺産から生じる不動産所得)に明らかにされているように、未分割は法定相続分に応じて申告し、「分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。」ということが基本とされているので、なお更である。
即ち、相続税法55条のような明確な規定がなく、国外転出相続時課税について、国税庁等の文書においても、未分割の場合の記載が何もないので、未分割でみなし譲渡の準確定申告をすることは、納税者の納得感を得るうえでも、大変困難な状態となっている。
しかも帰国による取消し規定が、その非居住者相続人ごとではなく、非居住者相続人全員であることが必要な規定のため、仮に非居住者相続人が2名以上の場合、1名でも帰国しない相続人がいれば、帰国による取消しもできず、また分割により居住者相続人がすべてを取得した場合においても、いったん未分割で正しく準確定申告をした場合は、分割による更正の請求はできるかどうかは定かではない(図表3参照)。
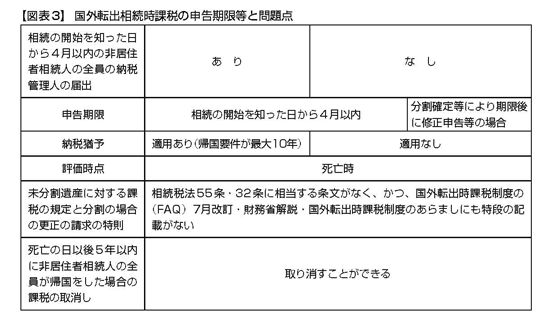
4 国外転出相続時課税において、実際に非居住者相続人がいて、準確定の申告期限において未分割の場合の実務対応 被相続人死亡後4月以内において未分割でみなし譲渡の申告を正しくするためには、財産の価額を未分割で計算するのみでなく、相続税評価額とは異なる限定承認の場合の時価とされている所基通59-6等の時価で計算し、かつ銘柄ごとの取得原価を把握し、財産の価額のみならず、含み益=みなし譲渡所得金額の配分においても未分割=非居住者相続人の法定相続分で計算しなければならない。
(1)相続税申告は相続税評価額で行い、
(2)みなし譲渡申告の価額は、限定承認の価額とされている所基通59-6で行い、
(3)その有価証券の銘柄ごとの取得価額も把握し、
時価ベースでの含み益=みなし譲渡所得において、非居住者相続人の法定相続分割合で未分割の計算をする。
準確定の申告期限で未分割の場合、完璧な含み益の未分割申告を行った場合に、分割の確定に伴う所得税法上の更正の請求の特例はなく、通則法23条の適用において、法律の規定に従い計算の誤りがない場合に該当することから、通則法23条の適用もないと解されている。
そうならば、実務家の立場として、この国外転出相続時課税において、帰国予定のない非居住者相続人がいる場合は、下記図表4ケースBのように、準確定の申告期限において、分割を優先し、申告期限までの申告を見送ることが考えられる。この場合のリスクは未分割が長期に継続した場合に含み益に関して未分割による課税の更正が行われることである。
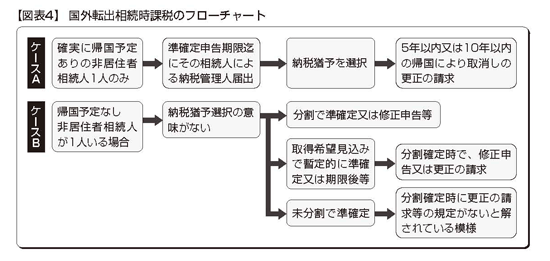
また準確定の申告期限に関わらず、分割確定により修正申告を行う場合に期限後または修正の加算税及び延滞税のリスクがあることになる。
この更正のリスクを回避するためには、通常とられる方法として、暫定的な申告と納税を行うことが充分考えられる。
この場合も、非居住者相続人と居住者相続人の同意が必要であり、そのうえで非居住者相続人が分割取得を希望する銘柄と株数で他の相続人の同意を得て、申告を行い、そのみなし譲渡所得税額を非居住者相続人が納税することが考えられるのではないか。
また、分割した際に最終的な納税額が異なる場合は、暫定的な申告であればその計算に誤りがあることになり、通則法19条又は23条の適用が考えられるのではないかと思われる。
国外転出時課税制度の概要と問題点(特に国外転出相続時課税において申告期限で未分割の場合)
税理士 竹内陽一
1 国外転出時課税制度の概要 有価証券等1億円以上(価額は所基通59-6による。)を有する居住者(下記図表1の事由前10年以内に5年超住所を有していた場合)に、図表1の各事由(国外転出、贈与、相続)が発生した場合に、転出居住者が保有する有価証券、非居住者受贈者が取得した有価証券、非居住者相続人全員が取得した有価証券について、みなし譲渡課税が課税される。
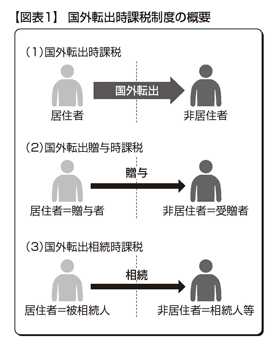
いずれの場合も、居住者本人、非居住者受贈者、非居住者相続人全員(この場合のみ、全員とされているので注意が必要)が各事由の日以後5年以内に帰国した場合に、更正の請求により、取消しとなる。
国外転出時課税と国外転出相続時課税については、一定の期限内に納税管理人届出をした場合にのみ、担保提供等により納税猶予が選択できる。国外転出贈与時課税については、担保提供等により納税猶予が選択できる。
納税猶予の場合、原則5年以内、延長して10年以内に帰国すれば、更正の請求により取消しとなる。一部譲渡があれば、当然一部期限確定となる。5年以内の帰国は納税猶予を選択しなかった場合においても、当然取消しとなる(所法60条の2⑥、60条の3⑥)。
納税猶予の特典として、譲渡による一部期限確定及び期間満了による全部期限確定において、価値が下落していた場合の期限確定した所得税についての減額規定があるが、これは期限確定により納付した所得税についてであって、5年以内等帰国の場合は、そもそも取消しとなり、課税自体が消滅する。
2 国外転出時課税の評価日・申告期限・納税猶予申請期限
(1)国外転出時課税 国外転出時課税の申告期限と納税猶予は次の3類型となる(図表2参照)。
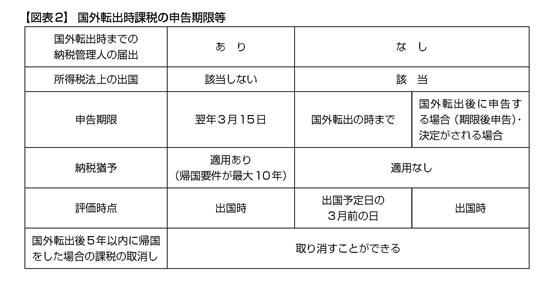
① 国外転出時までに納税管理人の届出がない場合……評価時点は出国予定日の3月前の日となり、出国前に申告と納税が必要となる。唯一、評価日の特例はこの場合のみで、他の全ての場合、評価日は各事由発生日である。この場合納税猶予の選択はない。
② 国外転出時までに納税管理人の届出をした場合……通常の確定申告期限(翌年3/15)となり、納付も確定申告と同様であり、納税猶予の選択ができる。
これは納税管理人の届出を国外転出時までに行った場合のみである。
③ 国外転出時までの納税管理人の届出がなく、出国後に期限後申告を行う場合……期限後申告となる。評価時点は出国時、又は決定される場合(この特例の期間制限は法定申告期限から7年に延長された)、納税猶予選択はできない。
以下、国外転出時課税制度の納税猶予には、期限内申告要件と担保提供要件がある。納税猶予選択の場合、5年以内帰国要件が最大10年に延長できる。なお課税の場合も納税猶予の場合も帰国取消し要件は共通であり、納税猶予の場合のみ10年に延長できる。
以下すべての国外転出時課税制度において、5年以内帰国と更正の請求による取消し規定がある。
(2)国外転出贈与時課税 確定申告期限(翌年3/15)が居住者贈与者のみなし譲渡申告期限となり、非居住者受贈者の贈与税申告期限となる。納税管理人の届出は意味がないので、納税猶予の選択は担保提供等により、常に可能であり、5年以内等の非居住者受贈者の帰国後の更正の請求により取消しとなる。
3 国外転出相続時課税と準確定申告期限において未分割の場合の問題点 準確定の申告期限は死亡の日より4月以内とされており、国外転出相続時みなし譲渡課税についての申告期限は、特に制度上措置されなかった。
しかしながらこの4月以内の期限は、非居住者相続人が株式等を相続するか否かに関わる問題であり、単に被相続人の生前の所得を申告するものではないことから、実務上、大変困難であり、この倍の8月程度の期間がほしいところである。
納税管理人の届出は、この4月以内で、非居住者相続人の全員が届け出た場合のみが納税猶予の対象となる。
準確定の申告期限において、有価証券が未分割か分割かは納税者において大問題であるが、このみなし譲渡課税の所得税の制度においては、準確定申告時に未分割であって、その後に分割が確定した場合の規定が一切規定されていない(相続税法では55条、32条①一に相当する規定)。
準確定申告時に未分割である場合に、相続税法55条に準じて申告するように言われているが、相続税法55条の本書きはいわば確認的規定であり、その但書及び相続税法32条(30条・31条)は創設的規定である。
国外転出相続時課税にこのような条文がない状態において、未分割の場合に、未分割でみなし譲渡課税の申告をすることは、分割確定時に更正の請求ができるかどうかがわからない状態にあるので、実務的には十分な注意が必要である。
特に所得税においては、タックスアンサーNo.1376不動産所得の収入計上時期(未分割遺産から生じる不動産所得)に明らかにされているように、未分割は法定相続分に応じて申告し、「分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。」ということが基本とされているので、なお更である。
即ち、相続税法55条のような明確な規定がなく、国外転出相続時課税について、国税庁等の文書においても、未分割の場合の記載が何もないので、未分割でみなし譲渡の準確定申告をすることは、納税者の納得感を得るうえでも、大変困難な状態となっている。
しかも帰国による取消し規定が、その非居住者相続人ごとではなく、非居住者相続人全員であることが必要な規定のため、仮に非居住者相続人が2名以上の場合、1名でも帰国しない相続人がいれば、帰国による取消しもできず、また分割により居住者相続人がすべてを取得した場合においても、いったん未分割で正しく準確定申告をした場合は、分割による更正の請求はできるかどうかは定かではない(図表3参照)。
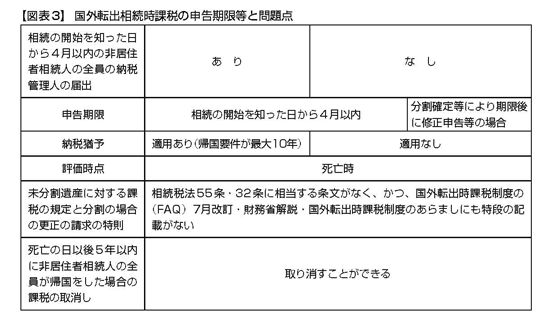
4 国外転出相続時課税において、実際に非居住者相続人がいて、準確定の申告期限において未分割の場合の実務対応 被相続人死亡後4月以内において未分割でみなし譲渡の申告を正しくするためには、財産の価額を未分割で計算するのみでなく、相続税評価額とは異なる限定承認の場合の時価とされている所基通59-6等の時価で計算し、かつ銘柄ごとの取得原価を把握し、財産の価額のみならず、含み益=みなし譲渡所得金額の配分においても未分割=非居住者相続人の法定相続分で計算しなければならない。
(1)相続税申告は相続税評価額で行い、
(2)みなし譲渡申告の価額は、限定承認の価額とされている所基通59-6で行い、
(3)その有価証券の銘柄ごとの取得価額も把握し、
時価ベースでの含み益=みなし譲渡所得において、非居住者相続人の法定相続分割合で未分割の計算をする。
準確定の申告期限で未分割の場合、完璧な含み益の未分割申告を行った場合に、分割の確定に伴う所得税法上の更正の請求の特例はなく、通則法23条の適用において、法律の規定に従い計算の誤りがない場合に該当することから、通則法23条の適用もないと解されている。
そうならば、実務家の立場として、この国外転出相続時課税において、帰国予定のない非居住者相続人がいる場合は、下記図表4ケースBのように、準確定の申告期限において、分割を優先し、申告期限までの申告を見送ることが考えられる。この場合のリスクは未分割が長期に継続した場合に含み益に関して未分割による課税の更正が行われることである。
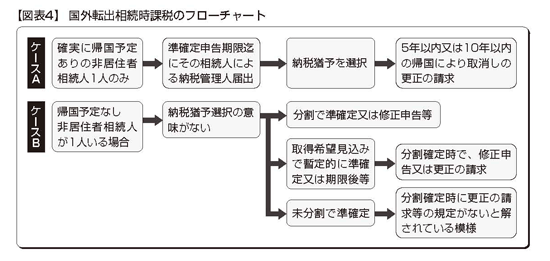
また準確定の申告期限に関わらず、分割確定により修正申告を行う場合に期限後または修正の加算税及び延滞税のリスクがあることになる。
この更正のリスクを回避するためには、通常とられる方法として、暫定的な申告と納税を行うことが充分考えられる。
この場合も、非居住者相続人と居住者相続人の同意が必要であり、そのうえで非居住者相続人が分割取得を希望する銘柄と株数で他の相続人の同意を得て、申告を行い、そのみなし譲渡所得税額を非居住者相続人が納税することが考えられるのではないか。
また、分割した際に最終的な納税額が異なる場合は、暫定的な申告であればその計算に誤りがあることになり、通則法19条又は23条の適用が考えられるのではないかと思われる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















