解説記事2015年10月19日 【ニュース特集】 動き出した消費税の軽減税率(2015年10月19日号・№614)
ニュース特集
財務省の軽減税率制度案は白紙に
動き出した消費税の軽減税率
消費税の軽減税率制度導入に向けた動きが活発化してきた。菅義偉官房長官は10月13日、平成29年4月の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率制度の導入を検討する考えを示した。軽減税率制度については、財務省が示した日本型軽減税率制度案ではないと明言。与党の税制改正大綱に沿って軽減税率導入を与党税制協議会で議論が進められるとした。また、EU型の軽減税率制度導入に消極的であった野田毅自民党税制調査会会長から宮沢洋一参議院議員に会長が交代。年末の税制改正大綱取りまとめに向けて検討を開始する。
公明党が念頭に置く軽減税率制度は区分経理に対応した請求書等保存方式だ。インボイス制度と比べると事業者負担が少ないほか、免税事業者からの仕入税額控除も可能になる点などをメリットとして挙げているが、そもそも事業者サイドは軽減税率制度導入に強く反対している。平成29年4月から軽減税率制度を導入するのであれば一刻も早く制度設計を行う必要があるが、その行方はいまだに不透明なままだ。
消費者への負担増により連立与党の公明党から強い反対
自民党及び公明党の税制調査会は、一時中断していた与党税制協議会を9月10日に開催。財務省は同協議会で日本型軽減税率制度案の説明を行った。同制度は、対象となる「酒類を除く飲食料品」(外食サービスを含む)を購入する際に、レジ等において、「個人番号カード」(マイナンバーカード)を利用することにより消費税2%分相当をポイントとして取得。消費者はパソコン等により還付申請を行うというもの。当初、検討課題として挙がっていたEU型の軽減税率制度とは異なり、税率は10%の単一税率となっている。インボイス制度の導入もない仕組みのため、事業者負担を大幅に軽減することが可能になった点が特徴だ。

公明党が与党税制協議会で財務省案に反対
財務省の日本型軽減税率制度案は、①対象品目の設定が困難、②インボイス方式等の導入による事業者の事務負担の増加、③低所得者だけでなく高所得者にまで恩恵が及ぶという3つの課題に対応するものであっただけに一時はまとまるかに見えたが、消費者側に還付申請などの負担を強いるほか、高齢者などが対応できるかどうかといった問題点により、連立与党である公明党から強い反対意見を受け頓挫。EU型の軽減税率制度導入に消極的な自民党との間に大きな溝を残したまま、与党税制協議会を再び中断。10月中旬から改めて検討を開始するとしていた。
平成29年4月の消費税率10%への引き上げ時までの時間が近づくなか、政府は連立与党である公明党に配慮。平成27年度税制改正大綱において「消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。」ことが明記されたことを重く見て財務省の日本型軽減税率制度案を白紙撤回するとともに、公明党が主張する軽減税率制度を導入すべく舵をとった格好。
具体的な制度設計は平成28年度税制改正大綱に盛り込むべく与党税制協議会で検討が行われることになるが、公明党が念頭に置いているのはEU型の軽減税率制度であり、区分経理に対応した請求書等保存方式に売手の請求書交付義務等を追加した方式である(図1参照)。まずは、この方式をたたき台として議論が進められることになりそうだ。
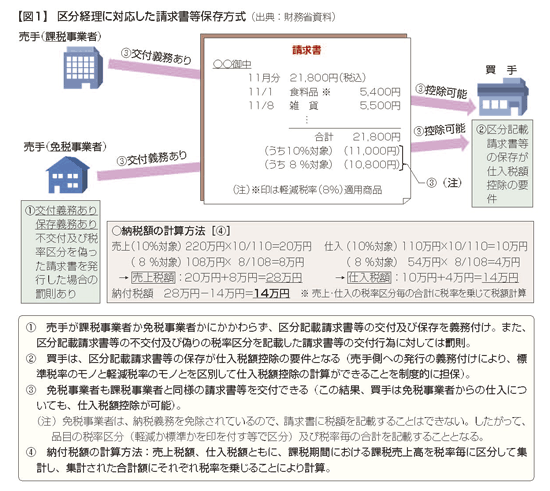
公明党が念頭に置く軽減税率制度とは?
この区分経理に対応した請求書等保存方式に売手の請求書交付義務等を追加した方式の概要は図1のとおりだ。EU型のインボイス方式とは異なり、区分記載請求書等には、商品毎の税額の記載は要さず、仕入税額控除を行う際にも税額の積上げ計算を必要としない仕組みである。インボイス方式と比べると事業者負担が少ないほか、免税事業者からの仕入税額控除も可能になる点などをメリットとして挙げている。ただ、500万を超えるといわれる免税事業者に新たに適用税率を判断させることになるため、多大な事務負担が生じることが懸念されている。
インボイス方式導入までの当面の措置 加えて、同方式は将来的なEU型のインボイス方式導入までの当面の措置との位置づけだ。インボイス方式は登録事業者に対して、インボイスの交付及び保存を義務付ける制度(図2参照)。インボイスとは事業者番号、請求書番号、作成者、交付を受ける者、課税資産の譲渡等の内容及び適用税率、適用税率別対価の額の合計額及び消費税額等が記載された請求書等のこと。買手はインボイスの保存が仕入税額控除の要件となる。
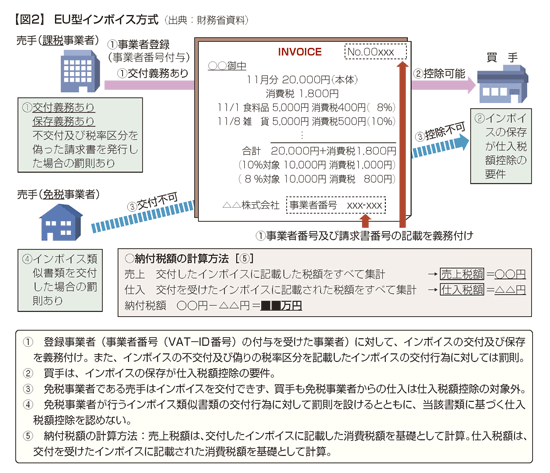
インボイス方式は事業者の事務負担が大幅に増加することになるが、なかでも免税事業者にとっては死活問題となる。免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となるため、取引の相手先から避けられる可能性が高いからだ。免税事業者は、仕入税額控除を行うために課税事業者を選択することによりインボイスを発行することができるが、中小零細企業の免税事業者が対応できるかどうかは未知数。それ相応の周知期間や準備期間が必要になろう。
対象は「酒類及び外食を除く食料品」を想定 現時点で想定される対象品目は「酒類及び外食を除く食料品」だ。ここで問題となってくるのは財源と対象分野の線引きだ。
財務省の日本型軽減税率制度案の場合は対象品目を「酒類を除く飲食料品」(外食サービスを含む)に設定していた。一見すると公明党が主張する「酒類及び外食を除く食料品」よりも対象範囲が大きいが、国民1人当たり4,000円程度と一定額を上限としていたため、財源は約5,000億円の減収とされていたが、「酒類及び外食を除く食料品」の場合は約9,800億円の減収になるとされている。他の財源がなければ消費税率引き上げによる社会保障財源が減少するという事態にもなる。また、高所得者に恩恵を与えるという問題も解決しない。
加えて、対象品目の設定に関して外食が除かれる場合にはテイクアウトや出前のケースはどうなるのかといった調理された食品に関する線引きの問題が浮上することになる。
平成29年4月から導入可能?
与党税制協議は年末に取りまとめる予定の平成28年度税制改正大綱において軽減税率制度の導入を盛り込む方向だ。ただ、公明党が念頭に置く軽減税率制度は消費者には何ら負担は生じないものの、事業者には多大な負担が生じることになる。そもそも事業者からの反対が強い軽減税率制度について与党間でどのような調整が付くかは未知数といえる。
また、仮に平成28年度税制改正大綱に軽減税率制度が盛り込まれたとしても新制度に対する準備期間などを考えると平成29年4月からの導入にも疑問符が付く。年末までの残された僅かな時間のなかでどのような決着になるか注目されるところだ。
なお、政府は、平成29年4月の消費税率10%引き上げに関してはリーマン・ショックのような事態にならない限り再延期はないとの方針を示している。
財務省の軽減税率制度案は白紙に
動き出した消費税の軽減税率
消費税の軽減税率制度導入に向けた動きが活発化してきた。菅義偉官房長官は10月13日、平成29年4月の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率制度の導入を検討する考えを示した。軽減税率制度については、財務省が示した日本型軽減税率制度案ではないと明言。与党の税制改正大綱に沿って軽減税率導入を与党税制協議会で議論が進められるとした。また、EU型の軽減税率制度導入に消極的であった野田毅自民党税制調査会会長から宮沢洋一参議院議員に会長が交代。年末の税制改正大綱取りまとめに向けて検討を開始する。
公明党が念頭に置く軽減税率制度は区分経理に対応した請求書等保存方式だ。インボイス制度と比べると事業者負担が少ないほか、免税事業者からの仕入税額控除も可能になる点などをメリットとして挙げているが、そもそも事業者サイドは軽減税率制度導入に強く反対している。平成29年4月から軽減税率制度を導入するのであれば一刻も早く制度設計を行う必要があるが、その行方はいまだに不透明なままだ。
消費者への負担増により連立与党の公明党から強い反対
自民党及び公明党の税制調査会は、一時中断していた与党税制協議会を9月10日に開催。財務省は同協議会で日本型軽減税率制度案の説明を行った。同制度は、対象となる「酒類を除く飲食料品」(外食サービスを含む)を購入する際に、レジ等において、「個人番号カード」(マイナンバーカード)を利用することにより消費税2%分相当をポイントとして取得。消費者はパソコン等により還付申請を行うというもの。当初、検討課題として挙がっていたEU型の軽減税率制度とは異なり、税率は10%の単一税率となっている。インボイス制度の導入もない仕組みのため、事業者負担を大幅に軽減することが可能になった点が特徴だ。

公明党が与党税制協議会で財務省案に反対
財務省の日本型軽減税率制度案は、①対象品目の設定が困難、②インボイス方式等の導入による事業者の事務負担の増加、③低所得者だけでなく高所得者にまで恩恵が及ぶという3つの課題に対応するものであっただけに一時はまとまるかに見えたが、消費者側に還付申請などの負担を強いるほか、高齢者などが対応できるかどうかといった問題点により、連立与党である公明党から強い反対意見を受け頓挫。EU型の軽減税率制度導入に消極的な自民党との間に大きな溝を残したまま、与党税制協議会を再び中断。10月中旬から改めて検討を開始するとしていた。
平成29年4月の消費税率10%への引き上げ時までの時間が近づくなか、政府は連立与党である公明党に配慮。平成27年度税制改正大綱において「消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。」ことが明記されたことを重く見て財務省の日本型軽減税率制度案を白紙撤回するとともに、公明党が主張する軽減税率制度を導入すべく舵をとった格好。
具体的な制度設計は平成28年度税制改正大綱に盛り込むべく与党税制協議会で検討が行われることになるが、公明党が念頭に置いているのはEU型の軽減税率制度であり、区分経理に対応した請求書等保存方式に売手の請求書交付義務等を追加した方式である(図1参照)。まずは、この方式をたたき台として議論が進められることになりそうだ。
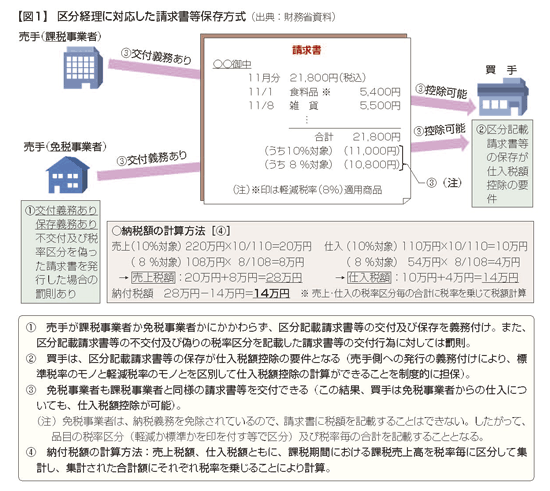
公明党が念頭に置く軽減税率制度とは?
この区分経理に対応した請求書等保存方式に売手の請求書交付義務等を追加した方式の概要は図1のとおりだ。EU型のインボイス方式とは異なり、区分記載請求書等には、商品毎の税額の記載は要さず、仕入税額控除を行う際にも税額の積上げ計算を必要としない仕組みである。インボイス方式と比べると事業者負担が少ないほか、免税事業者からの仕入税額控除も可能になる点などをメリットとして挙げている。ただ、500万を超えるといわれる免税事業者に新たに適用税率を判断させることになるため、多大な事務負担が生じることが懸念されている。
インボイス方式導入までの当面の措置 加えて、同方式は将来的なEU型のインボイス方式導入までの当面の措置との位置づけだ。インボイス方式は登録事業者に対して、インボイスの交付及び保存を義務付ける制度(図2参照)。インボイスとは事業者番号、請求書番号、作成者、交付を受ける者、課税資産の譲渡等の内容及び適用税率、適用税率別対価の額の合計額及び消費税額等が記載された請求書等のこと。買手はインボイスの保存が仕入税額控除の要件となる。
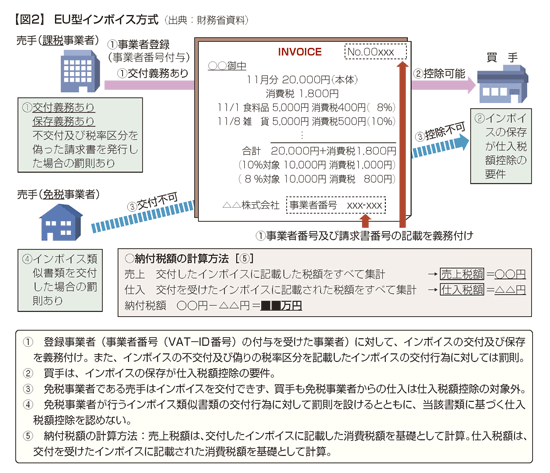
インボイス方式は事業者の事務負担が大幅に増加することになるが、なかでも免税事業者にとっては死活問題となる。免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となるため、取引の相手先から避けられる可能性が高いからだ。免税事業者は、仕入税額控除を行うために課税事業者を選択することによりインボイスを発行することができるが、中小零細企業の免税事業者が対応できるかどうかは未知数。それ相応の周知期間や準備期間が必要になろう。
対象は「酒類及び外食を除く食料品」を想定 現時点で想定される対象品目は「酒類及び外食を除く食料品」だ。ここで問題となってくるのは財源と対象分野の線引きだ。
財務省の日本型軽減税率制度案の場合は対象品目を「酒類を除く飲食料品」(外食サービスを含む)に設定していた。一見すると公明党が主張する「酒類及び外食を除く食料品」よりも対象範囲が大きいが、国民1人当たり4,000円程度と一定額を上限としていたため、財源は約5,000億円の減収とされていたが、「酒類及び外食を除く食料品」の場合は約9,800億円の減収になるとされている。他の財源がなければ消費税率引き上げによる社会保障財源が減少するという事態にもなる。また、高所得者に恩恵を与えるという問題も解決しない。
加えて、対象品目の設定に関して外食が除かれる場合にはテイクアウトや出前のケースはどうなるのかといった調理された食品に関する線引きの問題が浮上することになる。
平成29年4月から導入可能?
与党税制協議は年末に取りまとめる予定の平成28年度税制改正大綱において軽減税率制度の導入を盛り込む方向だ。ただ、公明党が念頭に置く軽減税率制度は消費者には何ら負担は生じないものの、事業者には多大な負担が生じることになる。そもそも事業者からの反対が強い軽減税率制度について与党間でどのような調整が付くかは未知数といえる。
また、仮に平成28年度税制改正大綱に軽減税率制度が盛り込まれたとしても新制度に対する準備期間などを考えると平成29年4月からの導入にも疑問符が付く。年末までの残された僅かな時間のなかでどのような決着になるか注目されるところだ。
なお、政府は、平成29年4月の消費税率10%引き上げに関してはリーマン・ショックのような事態にならない限り再延期はないとの方針を示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















