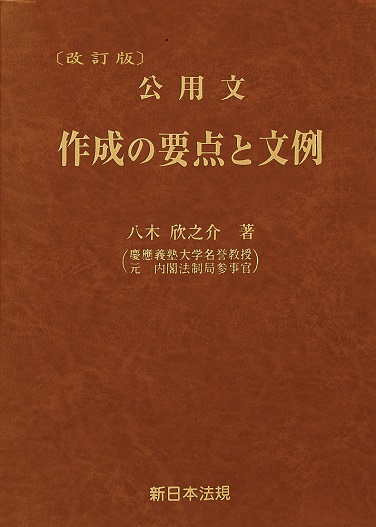解説記事2015年11月09日 【ニュース特集】 検証 日産自動車事件(2015年11月9日号・№617)
特集 インタビュー
時価で計算すべきだったみなし配当
検証 日産自動車事件
本誌612号(8頁)でもお伝えしたとおり、日産自動車グループの再編における日産自動車の子会社の減資に伴って同社に寄附金課税が行われたことの是非が争われた税務訴訟で、本年9月24日に最高裁が同社の上告受理申立てを不受理とすることを決定し、同社の敗訴が確定している。この事件は、ヤフー事件やIBM事件と時を同じくして行われた資本等取引(減資)に関する巨額課税事件であり、企業グループの再編に影響を及ぼす可能性があるとして、実務家の注目を集めていたところだ。
資本等取引の取扱いは、平成13年度税制改正によって大きく改められており、この改正の基本的な考え方に関する捉え方の違いにより、この事件の勝敗が分かれたのではないかと言われている。そこで本誌では、財務省主税局において平成13年度の資本等取引の取扱いの抜本改正を自ら手掛けた朝長英樹税理士に、この事件の判決文を基に判決のポイントなどを聞いた。
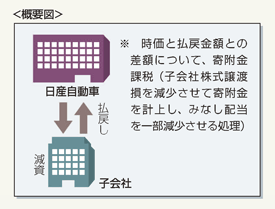
日産自動車事件の概要
――日産自動車事件を一言で言うとすれば、どう表現すれば良いでしょうか。
朝長 本件は、子会社が減資を行い、親会社に時価よりも低い金額を交付したところ、親会社に対し、時価と交付を受けた金額との差額について子会社への寄附として課税が行われた事件ですので、一言で言うとすれば、「減資を低額で行ったことで寄附金課税を受けた事件」ということになります。
――寄附金課税自体はそれほど難解なものではありませんが、資本等取引において寄附金課税ということになると分かり難いですね。
朝長 みなし配当も関係してきますし、分かり難いと感ずるのは仕方がないかも知れませんね。
――本件では、4名の著名な学者の方々が納税者側で意見書を書いています。
朝長 そのようですね。1名の方は、補充意見書も提出されているようです。
――学者の方々の関心も高いということですね。
朝長 本件における問題は、資本等取引や無償譲渡という少し専門的な分野の問題ですから、納税者側も学者の方々の意見に期待するということになるのでしょうし、学者の方々も関心を持たれるでしょうね。
ヤフー事件やIBM事件に関しても同じことを申し上げているのですが、税務訴訟において学者の方々が意見書を書かれた場合には、自ら公表するようにして頂いた方が良いと思っています。それを積み重ねて行けば、日本の税法解釈のレベルが大きく向上することになるはずです。
平成12年・13年改正で資本等取引の取扱いが大きく変化
――本件の最大のポイントは、「資本等取引」における「取引」の価額がどのようなものかという理解でよろしいでしょうか。
朝長 そうですね。本件に適用されている法人税法61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定は、平成12年改正において22条(各事業年度の所得の金額の計算)の別段の定めとして設けさせて頂き、現在は「資本等取引」に取り込まれている「資本積立金額」と「利益積立金額」の規定は、平成13年改正において全面的に見直しをさせて頂いたわけですが、これらの改正は、「損益取引」であろうが「資本等取引」であろうが、「取引」は適正な価額で行ってもらう必要がある、という観点に立って行いました。
これは、これらの改正の前後の「資本等取引」に関する規定を比べて見て頂くと直ぐに分かります。
――確かに、「損益取引」は時価で行わなければならないのに「資本等取引」は当事者がやり取りした金額で行えば良い、というはおかしいですよね。「取引」である限り、どちらも適正な価額で行うべきであるというのが当然のような気がします。
朝長 そうですね。
しかし、平成12年・13年改正の前の法人税法はそのようにはなっていませんでした。平成12年改正により、61条の2第2項において、被合併法人の株主の取扱いに関して旧株を譲渡するものと位置付けさせて頂きましたが、これは、「資本等取引」であったとしても、「取引」である限り、適正な価額で行ってもらう必要がある、という認識に基づくものでした。平成12年・13年改正で、「資本等取引」も全て適正な価額で行ってもらうという前提を整えたことで、法人における適格と非適格、株主における株主適格と株主非適格から成る体系的な組織再編成税制の構築が可能となりました。
納税者側は「払戻限度超過額は収益にも寄附金にもならない」と主張
――納税者側は、主位的主張と予備的主張を行っていたようですね。主位的主張はどのようなものでしょうか。
朝長 納税者側は控訴審で、主位的主張として、「旧商法上、減資には払戻限度額があって、その払戻限度額を超過する部分の払戻しは違法であるため、払戻限度額までしか払い戻さなかったのであり、払戻限度超過額を「収益」(子会社株式の譲渡対価)として計上することは許されず、また、払い戻されることがなかった払戻限度超過額は寄附金に該当しない」と述べています。
原審では、納税者側は主に払戻限度超過額は寄附金に該当しないという観点から主張を展開しており、主張の内容自体は基本的には同様と見てよいと考えます。
寄附金とされた金額は629億円で、払戻限度超過額は406億円とされていますので、税務調査により寄附金とされた金額の大半が払戻限度超過額ということになります。
裁判所は「払戻限度超過額が収益と寄附金になる」と判示
――それに対して高裁はどのような判断をしたのでしょうか。
朝長 高裁も地裁と同様に納税者側の主張を退け、払戻限度超過額を収益とするとともに寄附金と判断しています。その理由は、一部の字句修正を除いて地裁の判決が説示するとおりとした上で、さらに次のように述べています。
――結論は分かりますが、判断の理由がいま一つ分かり難いですね。
朝長 地裁の判決には、次のような部分があり、上記の高裁の判決の記述は、この部分を踏まえたものです。
要するに、営利を目的とする法人は損をする取引を選択しないはずであり、損をする取引を選択したということは、損をした部分の金額を寄附したということである、というわけです。
納税者側は、減資は「事業税の負担に対応するためのものであって、原告の事業上必要かつ合理的なもの」であり、かつ、「払戻しの金額は旧商法上の規制を反映したもの」であったと主張しているわけですが、それでもなお上記のような理由によって課税が妥当であるとされている点に注目しておく必要があります。
――なるほど。実務を考えると、非常に重要なところですね。
寄附金課税は避けられない
――朝長先生は、この主位的主張の部分をどのように見ておられますか。
朝長 私は、このような主張はそもそも争点にならないと考えています。
――それはどういうことでしょうか。
朝長 この主張は、要約すると、法制で制限された価額を法人税法上の時価とするべきであるというものですが、法人税法においては、先ほども触れたとおり、特に平成12年・13年改正以後はそのような考え方は採っていません。現在の法人税法は、「取引」はあくまでも時価によって行うことを求めています。
――法制で「取引」の価額が制限されてどうしようもない場合であっても、寄附金課税が行われるということになるのでしょうか。
朝長 そういうことにはなりません。法制で「取引」の価額が制限されてその価額を超える価額で取引することができないという場合には、その制限された価額が時価となるはずです。法制で制限された価額と時価に差額が生ずるのは、その法制で制限された取引以外の取引が有り得る場合のみとなります。
本件の場合も、減資以外に子会社株式を処分することが可能であるため、時価による取引を行った場合と同様の課税が行われているわけです。
平成12年改正前であれば納税者側の主張のような主張も有り得た
――なるほど。この主位的主張が争点にならないというのは、この主張では納税者は勝てない、というご見解ということでしょうか。
朝長 そのように考えています。払戻限度超過額の部分が寄附金とされることは避けられず、納税者側の立場に立って申し上げると、これを争点とすることは得策ではなかったと思っています。
――勝算があるところを争点とするべきであって、勝算がないところを争点とするのは得策ではないということですか。
朝長 そうですね。
後にお話をすることになりますが、本件に関しては、他の部分でかなりの金額の課税を取り戻すことが可能であったと考えています。
税務訴訟では、勝算があるのか否か、どこにどのくらいの勝算があるのかということについて、専門家としてどのように判断するのかということが非常に重要となります。
――もし本件が平成12年改正前に起きていたとしたら、朝長先生もこの主位的主張のような主張をされたのでしょうか。
朝長 平成12年改正前の法人税法には、「資本等取引」について、商法に則って取引を行ったのであれば法人税法上もその取引をそのまま認めるという内容になっている規定がいくつも存在していましたので、当然、そのような主張をすることになったはずです。
しかし、先ほども触れたとおり、平成12年・13年改正で、そのような規定は全て無くしました。
平成12年・13年改正を境として、法人税法における「資本等取引」に関する捉え方や取扱いは大きく変わっています。
みなし配当の額に関しては勝算がある
――先ほど、他の部分でかなりの課税の取戻しが可能であったというお話がありましたが、それはどの部分でしょうか。
朝長 納税者側が主位的主張が採用されない場合の予備的主張として、みなし配当の額について、実際に払い戻した金額ではなく、時価とされる金額を基礎として計算するべきであると主張していますが、この部分です。納税者側は、準備書面も非常に多く提出し、全体的には相当に力を込めて取り組んでいると感じますが、この予備的主張の部分に関しては、十分に掘り下げた主張がされているとは言えません。判決文でも、納税者の主位的主張を記載した部分が5頁であるのに対し、予備的主張を記載した部分は、1頁半くらいしかありません。
この予備的主張の部分に対し、高裁は、みなし配当の額は実際に払い戻した金額を基礎として計算するべきであるとして、納税者側の主張を退けていますが、私はこの高裁の判断は誤っていると思っています。
――みなし配当の額を時価で計算することがどうして課税金額の減少になるのか、分かり易く説明して頂けないでしょうか。
朝長 文章だけでは分かり難いので、大勢に影響のない細かなものは省略して、納税者が行った確定申告、国税当局が行った更正処分等、そして、納税者の予備的主張について、仕訳の形式にして確認してみたいと思います。
なお、この仕訳は、平成12年の改正で有価証券の譲渡損益の計算に関する規定である61条の2を設ける前に存在していた22条、24条及び37条の解釈を正確に理解することができるように、同年前のこれらの規定の適用関係に合致するように書いています。
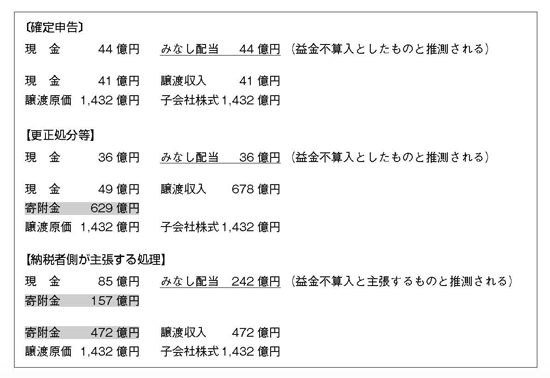
みなし配当に括弧書きを付し、寄附金を二つに分けたところは私の判断であり、【納税者側が主張する処理】の仕訳は、私が判決文の中の納税者側の主張から推測して作ったもので、端数の関係等で1億円単位の数字は貸借の金額が合うように調整をしています。
――実際の払戻額である85億円を交付金額として計算すればみなし配当の額は36億円にしかならないが、子会社株式の時価である714億円(みなし配当と譲渡収入の合計額)を交付金額として計算すれば、みなし配当の額は206億円の増加となり、譲渡収入は206億円の減少となって、所得金額が同額だけ減少するということですね。
朝長 そうです。
――受取配当益金不算入について当初申告要件が廃止されたのは平成23年ですから、同年前の処理が争われている本件においては、受取配当の税務調査による増加額は益金不算入とはならないのではありませんか?
朝長 増額される受取配当を益金不算入とするのか否かということまでは争点に含まれていないわけですが、増額される部分も益金不算入となり得ると思っています。
――増額される受取配当が益金不算入となるということまで主張してそれが認められなければ、意味がないですよね。
朝長 そうですね。増額される受取配当が更正処分等によって減少した8億円だけしか益金不算入とならないということであれば、そもそも受取配当の増額を争点にする意味はほとんどないと言ってよいでしょう。この点に関しては、平成22年3月19日に東京地裁において、結果は納税者側の敗訴となっていますが、説示の中でも、税務調査によるみなし配当の増加額について、益金不算入の適用の意思があったか否かで追加的に益金不算入とするのか否かを判断するという考え方が示されています。
本件は、税務調査によるみなし配当の増加額が益金不算入となるか否かということの前に、みなし配当の額は実際の交付金額に基づいて計算するから増加しない、ということになってしまっていますが、しかし、本来は、納税者側が主張しているように、みなし配当の額は時価で計算するのが正しく、その結果、益金不算入額が増えて、200億円強の課税所得金額が少なくなる可能性が十分にある、と考えています。
22条2項の無償譲渡の定めの「解釈」と「事実関係」の区別に課題
――納税者側の主張が採用されなかったのはその主張に課題があったということでしょうか。
朝長 そうですね。納税者側の主張では、22条2項の無償譲渡の定めの「解釈」と「事実関係」の区別が明確ではなく、これがみなし配当を時価に基づいて計算すべきであるという主張が採用されなかった大きな原因と考えています。
「みなし配当」の規定である24条1項を見てみると、同項においては、「配当」と「みなす」と定めることにより、「配当」が行われた「事実」がないものについて、「配当」が行われた「事実」があるものとして取り扱うこととしています。
諸外国では、「事実認定」によって「配当」と認定するということはあっても、「みなす」という擬制によって「配当」と同様に取り扱うということはないのではないかと思います。
「事実認定」によって「配当」と認定することも、擬制によって「配当」と同様に取り扱うことも、結果は同じであるため、違いを気にする必要はないのではないかと思われがちですが、決してそういうことではなく、立法と解釈の観点からすると、非常に大きな違いがあることを良く理解しておく必要があります。
「みなす」という擬制の制度を創るのか否かということは、大きな立法判断になります。「事実認定」によって認定をすべきものについて「みなす」という擬制の制度を設けることは、許されません。
また、「みなす」という擬制の制度によってみなすこととなる「事実」は、その制度によってみなされることとなる「事実」とは異なると解釈することになります。24条1項各号に掲げられている合併や資本の払戻し等は、「配当」ではないと認識するが故に、「配当」と「みなす」と定めているわけです。
このように、24条では、「配当」ではないものについて、「みなす」ことによって「配当」と擬制するものとされているわけですが、「事実認定」によって「配当」となるものがあった場合にどうなるのかというと、「事実認定」によって「配当」となるものに対しては、「みなす」ことによって「配当」と擬制する24条の規定は適用されません。
これは、立法と解釈の常識と言うべきものですが、この24条の規定と22条2項の無償譲渡の定めの違いを正しく理解する必要があります。
22条2項の無償譲渡の定めは確認規定
――22条2項の無償譲渡の定めは確認規定ということで良いわけですね。
朝長 そうです。
24条1項は「みなす」と規定しているわけですから創設規定ですが、22条2項の無償譲渡の定めは、「みなす」とか「推定する」と規定しているわけではなく、単に無償譲渡に係る収益の額を益金の額とすると規定しているだけですから、無償譲渡で収益が発生するという前提に立った上での確認規定ということになります。当然のことながら、「みなす」と規定しているものと「みなす」と規定していないものとが同じ解釈になるということは、有り得ません。
財務省主税局で租税立法に携わった経験から申し上げると、無償譲渡においては対価の授受が行われませんので、22条2項の無償譲渡の定めを立法化するに際しては、少なくとも、内閣法制局の条文案の審査の場面では、「みなす」必要があるのか否かということが検討の俎上に載せられたはずであると考えています。
立法論としては、創設規定とする必要があるのか確認規定ということでよいのかという点は検討の余地があると考えますが、現に創設された22条2項の無償譲渡の定めが確認規定として作られていることは明白であり、解釈論としては、この定めを創設規定と解釈することは明らかな誤りであると考えています。
――立法論と解釈論は峻別しなければならないわけですね。
朝長 22条2項の無償譲渡の定めに関しても、立法論の議論か解釈論の議論か分からないものが少なくありませんが、これらは明確に分けて議論をする必要があります。
無償譲渡による収益・寄附の有無は「事実」の領域の問題
――22条2項の無償譲渡の定めは、無償譲渡の収益に対応する部分を寄附金とするという37条の無償譲渡における寄附金の定めと一体的に設けられたわけですよね。
朝長 そうですね。
例えば、AからBに資産の無償譲渡が行われた場合には、AがBに時価相当額の資産を寄附した「事実」があり、Aはその寄附をするに当たってその資産の時価相当額の収益を得た「事実」があるという「事実認定」が行われるという前提に立って、22条2項の無償譲渡の定めと37条の無償譲渡における寄附金の定めを適用する、ということになっています。
ただし、税務調査で無償譲渡において益金を計上する申告調整が行われていないものが発見されたというような場合には、常に寄附金とされるわけではなく、後日、対価を収受するということであれば、「未収金」等として処理するということも珍しくありません。
寄附があるのか否かということは、無償譲渡による寄附も含めて、「事実認定」の問題である、ということです。
仮に、資産が無償譲渡された場合に、資産を無償譲渡した者が収益を得たという「事実」がないという前提に立つとすれば、22条2項において、資産を無償譲渡した法人の収益の額と資産を時価譲渡した法人の収益の額とを同列に並べて、「益金の額に算入すべき金額は、……収益の額とする。」というような規定の仕方をすることは有りません。この22条2項の規定の仕方は、無償譲渡に収益の額がないと認識した上で収益の額があるものとするという場合の規定の仕方ではないことが明らかです。このような規定の仕方は、資産の無償譲渡をした法人にも収益の額があるという前提がなければ有り得ない、ということです。法令の解釈は、立法を良く理解して行う必要があります。
――対価が授受されないものも、対価が授受されるものと同じように収益と寄附があると捉えるということは、「事実」の範囲が広いということですかね。
朝長 そうですね。「事実関係」の「事実」を広く捉えていることは間違いありません。
このように「事実関係」の「事実」を広く捉えることの是非は、立法論の場面で検討の余地があると考えますが、しかし、既にご説明をしたとおり、解釈論の場面では、その是非は問題とはならず、無償譲渡による収益と寄附が存在するのか否かということは「事実」の領域の問題として位置付ける必要があります。
――納税者側は、無償譲渡に収益と寄附が存在するということを「事実」と捉えていなかったのでしょうか。
朝長 その辺りが明確ではありません。地裁の判決文にある納税者側の主張と高裁の判決文にある納税者側の主張のいずれの中でも、無償譲渡に関する22条2項の定めと37条の定めに基づく主張においては、「擬制」という用語が多用されています。地裁では10個、高裁では6個の「擬制」という用語が用いられています。
この「擬制」とは、法の世界では、ある事実について、それとは異なる事実と同じものとして取り扱い、その異なる事実に認められた法律効果をある事実にも発生させることをいい、専らみなし規定や推定規定の「解釈」を述べる場面で用いられることとなります。
私は、「法令の解釈」には「擬制」があるが、「事実」に「擬制」はないと考えています。
地裁の判決文における納税者側の主張も、高裁の判決文にある納税者側の主張も、「擬制」という用語を多用してなされる主張が「解釈」と「事実」のいずれを主張するものかということが必ずしも明確ではありません。
収益・寄附の有無が「事実関係」なら、みなし配当も時価による計算が筋
――本件のみなし配当を実際の交付金額に基づいて計算するべきか、あるいは、時価に基づいて計算するべきかという問題と、無償譲渡による収益・寄附の有無が「事実」の領域の問題であるということとは、どのように関係するのでしょうか。
朝長 みなし配当の規定である24条1項も、「事実」に当てはめて適用されることとなるわけですから、無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」があるのであれば、その無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」に同項を当てはめて適用しなければならない、ということになります。
24条1項には、「金銭その他の資産の交付を受けた」という「事実関係」に関する文言があり、これが実際に「交付」を受けたものでなければならないと解釈されたことが主たる納税者側の敗因となっていると考えて良いわけですが、22条2項の上記の整理からすると、この「事実関係」を示す文言は、無償譲渡における収益・寄附があるという「事実認定」を行った後の「事実関係」を指すものでなければなりません。そして、無償譲渡による収益・寄附があったという「事実」があるのであれば、「交付」を受けた「事実」もあると整理せざるを得ません。
高裁判決においては、子会社株式の譲渡損益を計算する場面で、61条の2第1項の「対価の額」について、当事者間で取り決めた対価の額ではなく、22条2項の無償譲渡の定めの解釈を根拠として、時価に置き換えて同項が適用されています。この「対価の額」がどのような金額となるのかということは、「事実」の領域の問題であって、「みなす」ことによって「対価の額」が時価とされるわけではありません。
一つの取引において、みなし配当を計算する場合の「事実」と子会社株式の譲渡損益を計算する場合の「事実」が異なるということは、有り得ないことです。
――もし22条2項の無償譲渡の定めが「みなし」の規定となっており、収益があると「擬制」をするものであったと仮定すればどうなるのでしょうか。
朝長 無償譲渡においては収益が存在しないという「事実」があるということになり、寄附として課税をするためには、寄附金の規定においても無償譲渡を寄附と「みなす」ことが必要となります。
そして、24条1項の「金銭その他の資産の交付を受けた」という部分に関しては、「交付を受けたものとみなす」と規定しない限り、実際に「交付」を受けたものしか指さない、ということになります。
――判決どおりということですね。
朝長 そういうことですね。
法人税法と所得税法では無償譲渡に関する「事実関係」の捉え方が異なる
――ところで、法人の株主には法人も個人も存在するわけですが、法人税法と所得税法の無償譲渡の取扱いには違いがあります。所得税法においても同様に考えて良いのでしょうか。
朝長 所得税法には、法人税法22条2項の無償譲渡の定めと同じような定めは設けられていませんので、同じにはなりません。
所得税法においては、資産を時価の2分の1未満で譲渡した場合に時価で譲渡したものと「みなす」こととされている定めが存在するのみです。ここでは、資産の譲渡に関する取扱いにおいて、時価による譲渡があったものと「みなす」とされていますので、無償譲渡の例で言うと、「事実関係」について時価によって譲渡したという「事実」がないと捉え、その上で、資産の譲渡に関する取扱いにおいては、時価による譲渡があったものと擬制して課税する、ということです。
法人税法61条の2第1項には「有価証券の譲渡をした」という文言があり、この「譲渡」には無償譲渡や低額譲渡が含まれていますが、所得税法における有価証券の「譲渡」には、みなし譲渡とされない低額譲渡は含まれていません。
みなし配当に関しても同様で、所得税法におけるみなし譲渡の規定の「みなし」は、みなし配当の規定には及びませんので、所得税法25条1項のみなし配当の規定の「金銭その他の資産の交付を受けた」という文言は、法人税法24条1項の文言と同様となってはいますが、その法人税法24条1項の文言の解釈とは異なり、実際に「交付」を受けたものだけを指すことになります。
換言すれば、所得税法においては、無償譲渡の場合には所得税法25条1項の「交付」に該当するものはないということになるが、法人税法においては、無償譲渡の場合にも法人税法24条1項の「交付」に該当するものがある、ということになります。
このように、法人税法と所得税法では、みなし配当の規定の適用を想定する「事実関係」の捉え方が違っているわけですから、「譲渡」と同じように、「交付」の捉え方に違いが出てくるのは、当然のことです。24条のみなし配当の規定も、平成13年に抜本的に見直して改正をさせて頂いたわけですが、立法に当たっては、違いがあるのは当然と考えていたものを用語が同じということで同じ解釈になると簡単に言われてしまうと、かなり違和感を感じますね。
「事実関係」を適切に説明すれば、みなし配当は時価で計算されていたはず
――法人税法と所得税法では、そもそも無償譲渡に関する「事実関係」の捉え方が違っているので、「交付」も同じ解釈にはならないということですね。本件だけの問題ではなく、24条1項の解釈の問題ですから、影響も大きいですよね。
朝長 法律の規定を作る場合には、必ずその規定をどのようなものに適用するのかということを想定することになります。22条2項の無償譲渡の定めに関しても、どのようなものに適用することを意図して作られたのかということを考えてみると、自ずと法人税法が無償譲渡における「事実関係」として想定しているものが見えてきます。
本件においては、22条2項の無償譲渡の定めが適用される「事実関係」をその定めの「解釈」と明確に区別して説明することが必要であったと思っています。
そうすれば、24条1項のみなし配当の規定も、無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」に当てはめるべきであるということになり、みなし配当も時価に基づいて計算する必要がある、ということになったのではないかと考えています。
――本日は、お忙しい中、貴重なお話をお聞かせ頂き、誠にありがとうございました。
時価で計算すべきだったみなし配当
検証 日産自動車事件
本誌612号(8頁)でもお伝えしたとおり、日産自動車グループの再編における日産自動車の子会社の減資に伴って同社に寄附金課税が行われたことの是非が争われた税務訴訟で、本年9月24日に最高裁が同社の上告受理申立てを不受理とすることを決定し、同社の敗訴が確定している。この事件は、ヤフー事件やIBM事件と時を同じくして行われた資本等取引(減資)に関する巨額課税事件であり、企業グループの再編に影響を及ぼす可能性があるとして、実務家の注目を集めていたところだ。
資本等取引の取扱いは、平成13年度税制改正によって大きく改められており、この改正の基本的な考え方に関する捉え方の違いにより、この事件の勝敗が分かれたのではないかと言われている。そこで本誌では、財務省主税局において平成13年度の資本等取引の取扱いの抜本改正を自ら手掛けた朝長英樹税理士に、この事件の判決文を基に判決のポイントなどを聞いた。
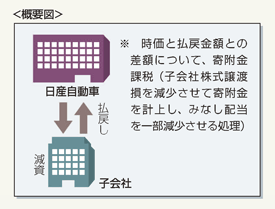
日産自動車事件の概要
――日産自動車事件を一言で言うとすれば、どう表現すれば良いでしょうか。
朝長 本件は、子会社が減資を行い、親会社に時価よりも低い金額を交付したところ、親会社に対し、時価と交付を受けた金額との差額について子会社への寄附として課税が行われた事件ですので、一言で言うとすれば、「減資を低額で行ったことで寄附金課税を受けた事件」ということになります。
――寄附金課税自体はそれほど難解なものではありませんが、資本等取引において寄附金課税ということになると分かり難いですね。
朝長 みなし配当も関係してきますし、分かり難いと感ずるのは仕方がないかも知れませんね。
――本件では、4名の著名な学者の方々が納税者側で意見書を書いています。
朝長 そのようですね。1名の方は、補充意見書も提出されているようです。
――学者の方々の関心も高いということですね。
朝長 本件における問題は、資本等取引や無償譲渡という少し専門的な分野の問題ですから、納税者側も学者の方々の意見に期待するということになるのでしょうし、学者の方々も関心を持たれるでしょうね。
ヤフー事件やIBM事件に関しても同じことを申し上げているのですが、税務訴訟において学者の方々が意見書を書かれた場合には、自ら公表するようにして頂いた方が良いと思っています。それを積み重ねて行けば、日本の税法解釈のレベルが大きく向上することになるはずです。
平成12年・13年改正で資本等取引の取扱いが大きく変化
――本件の最大のポイントは、「資本等取引」における「取引」の価額がどのようなものかという理解でよろしいでしょうか。
朝長 そうですね。本件に適用されている法人税法61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定は、平成12年改正において22条(各事業年度の所得の金額の計算)の別段の定めとして設けさせて頂き、現在は「資本等取引」に取り込まれている「資本積立金額」と「利益積立金額」の規定は、平成13年改正において全面的に見直しをさせて頂いたわけですが、これらの改正は、「損益取引」であろうが「資本等取引」であろうが、「取引」は適正な価額で行ってもらう必要がある、という観点に立って行いました。
これは、これらの改正の前後の「資本等取引」に関する規定を比べて見て頂くと直ぐに分かります。
――確かに、「損益取引」は時価で行わなければならないのに「資本等取引」は当事者がやり取りした金額で行えば良い、というはおかしいですよね。「取引」である限り、どちらも適正な価額で行うべきであるというのが当然のような気がします。
朝長 そうですね。
しかし、平成12年・13年改正の前の法人税法はそのようにはなっていませんでした。平成12年改正により、61条の2第2項において、被合併法人の株主の取扱いに関して旧株を譲渡するものと位置付けさせて頂きましたが、これは、「資本等取引」であったとしても、「取引」である限り、適正な価額で行ってもらう必要がある、という認識に基づくものでした。平成12年・13年改正で、「資本等取引」も全て適正な価額で行ってもらうという前提を整えたことで、法人における適格と非適格、株主における株主適格と株主非適格から成る体系的な組織再編成税制の構築が可能となりました。
納税者側は「払戻限度超過額は収益にも寄附金にもならない」と主張
――納税者側は、主位的主張と予備的主張を行っていたようですね。主位的主張はどのようなものでしょうか。
朝長 納税者側は控訴審で、主位的主張として、「旧商法上、減資には払戻限度額があって、その払戻限度額を超過する部分の払戻しは違法であるため、払戻限度額までしか払い戻さなかったのであり、払戻限度超過額を「収益」(子会社株式の譲渡対価)として計上することは許されず、また、払い戻されることがなかった払戻限度超過額は寄附金に該当しない」と述べています。
原審では、納税者側は主に払戻限度超過額は寄附金に該当しないという観点から主張を展開しており、主張の内容自体は基本的には同様と見てよいと考えます。
寄附金とされた金額は629億円で、払戻限度超過額は406億円とされていますので、税務調査により寄附金とされた金額の大半が払戻限度超過額ということになります。
裁判所は「払戻限度超過額が収益と寄附金になる」と判示
――それに対して高裁はどのような判断をしたのでしょうか。
朝長 高裁も地裁と同様に納税者側の主張を退け、払戻限度超過額を収益とするとともに寄附金と判断しています。その理由は、一部の字句修正を除いて地裁の判決が説示するとおりとした上で、さらに次のように述べています。
| 法人税が企業の経済活動によって稼得された成果(企業利益)を課税物件とするものであることに照らすと、法人税法22条2項にいう「収益」とは、経済的な実態に即して実質的に理解するのが相当であり、また、このように解するのが同項の趣旨でもある租税の公平な負担の観念に合致することになる。 |
| 控訴人が本件払戻限度超過額を収受することが旧商法の規定により許されないとしても、そのことをもって、直ちにその収益性を否定することはできないと解するのが相当である。 |
朝長 地裁の判決には、次のような部分があり、上記の高裁の判決の記述は、この部分を踏まえたものです。
| 原告は、本件事業再編は原告の製造する自動車等の販売体制を構築するためにされたもので、そのうち本件株式消却を伴う減資は本件各子会社における事業税の負担に対応するためのものであって、原告の事業上必要かつ合理的なものであり、払戻しの金額は旧商法上の規制を反映したものであった旨を主張するが、原告が営利を目的とする法人であること、事業の再編の手続として本件において採用されたもの以外のものを選択することが妨げられていたと見るべき格別の証拠ないし事情は見当たらないこと、本件株式消却を伴う減資は直接には本件各子会社の本件合併による消滅までの間のいわゆる税金対策を主たる目的とするものであること等からすれば、原告の主張するような事情のほか、原告と本件各子会社とが法人税法上の連結納税に係る関係にあることをもっても、上記のような経済的な利益の対価のない移転を内容とする手続を執ることが原告にとっての通常の経済取引として是認することができる合理的な理由に当たると直ちに解することは困難というべきであるし、他に本件においてこのような合理的な理由が存在したことをうかがわせる証拠ないし事情は見当たらない。 |
納税者側は、減資は「事業税の負担に対応するためのものであって、原告の事業上必要かつ合理的なもの」であり、かつ、「払戻しの金額は旧商法上の規制を反映したもの」であったと主張しているわけですが、それでもなお上記のような理由によって課税が妥当であるとされている点に注目しておく必要があります。
――なるほど。実務を考えると、非常に重要なところですね。
寄附金課税は避けられない
――朝長先生は、この主位的主張の部分をどのように見ておられますか。
朝長 私は、このような主張はそもそも争点にならないと考えています。
――それはどういうことでしょうか。
朝長 この主張は、要約すると、法制で制限された価額を法人税法上の時価とするべきであるというものですが、法人税法においては、先ほども触れたとおり、特に平成12年・13年改正以後はそのような考え方は採っていません。現在の法人税法は、「取引」はあくまでも時価によって行うことを求めています。
――法制で「取引」の価額が制限されてどうしようもない場合であっても、寄附金課税が行われるということになるのでしょうか。
朝長 そういうことにはなりません。法制で「取引」の価額が制限されてその価額を超える価額で取引することができないという場合には、その制限された価額が時価となるはずです。法制で制限された価額と時価に差額が生ずるのは、その法制で制限された取引以外の取引が有り得る場合のみとなります。
本件の場合も、減資以外に子会社株式を処分することが可能であるため、時価による取引を行った場合と同様の課税が行われているわけです。
平成12年改正前であれば納税者側の主張のような主張も有り得た
――なるほど。この主位的主張が争点にならないというのは、この主張では納税者は勝てない、というご見解ということでしょうか。
朝長 そのように考えています。払戻限度超過額の部分が寄附金とされることは避けられず、納税者側の立場に立って申し上げると、これを争点とすることは得策ではなかったと思っています。
――勝算があるところを争点とするべきであって、勝算がないところを争点とするのは得策ではないということですか。
朝長 そうですね。
後にお話をすることになりますが、本件に関しては、他の部分でかなりの金額の課税を取り戻すことが可能であったと考えています。
税務訴訟では、勝算があるのか否か、どこにどのくらいの勝算があるのかということについて、専門家としてどのように判断するのかということが非常に重要となります。
――もし本件が平成12年改正前に起きていたとしたら、朝長先生もこの主位的主張のような主張をされたのでしょうか。
朝長 平成12年改正前の法人税法には、「資本等取引」について、商法に則って取引を行ったのであれば法人税法上もその取引をそのまま認めるという内容になっている規定がいくつも存在していましたので、当然、そのような主張をすることになったはずです。
しかし、先ほども触れたとおり、平成12年・13年改正で、そのような規定は全て無くしました。
平成12年・13年改正を境として、法人税法における「資本等取引」に関する捉え方や取扱いは大きく変わっています。
みなし配当の額に関しては勝算がある
――先ほど、他の部分でかなりの課税の取戻しが可能であったというお話がありましたが、それはどの部分でしょうか。
朝長 納税者側が主位的主張が採用されない場合の予備的主張として、みなし配当の額について、実際に払い戻した金額ではなく、時価とされる金額を基礎として計算するべきであると主張していますが、この部分です。納税者側は、準備書面も非常に多く提出し、全体的には相当に力を込めて取り組んでいると感じますが、この予備的主張の部分に関しては、十分に掘り下げた主張がされているとは言えません。判決文でも、納税者の主位的主張を記載した部分が5頁であるのに対し、予備的主張を記載した部分は、1頁半くらいしかありません。
この予備的主張の部分に対し、高裁は、みなし配当の額は実際に払い戻した金額を基礎として計算するべきであるとして、納税者側の主張を退けていますが、私はこの高裁の判断は誤っていると思っています。
――みなし配当の額を時価で計算することがどうして課税金額の減少になるのか、分かり易く説明して頂けないでしょうか。
朝長 文章だけでは分かり難いので、大勢に影響のない細かなものは省略して、納税者が行った確定申告、国税当局が行った更正処分等、そして、納税者の予備的主張について、仕訳の形式にして確認してみたいと思います。
なお、この仕訳は、平成12年の改正で有価証券の譲渡損益の計算に関する規定である61条の2を設ける前に存在していた22条、24条及び37条の解釈を正確に理解することができるように、同年前のこれらの規定の適用関係に合致するように書いています。
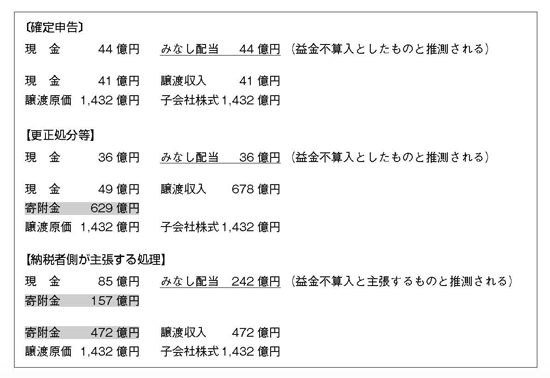
みなし配当に括弧書きを付し、寄附金を二つに分けたところは私の判断であり、【納税者側が主張する処理】の仕訳は、私が判決文の中の納税者側の主張から推測して作ったもので、端数の関係等で1億円単位の数字は貸借の金額が合うように調整をしています。
――実際の払戻額である85億円を交付金額として計算すればみなし配当の額は36億円にしかならないが、子会社株式の時価である714億円(みなし配当と譲渡収入の合計額)を交付金額として計算すれば、みなし配当の額は206億円の増加となり、譲渡収入は206億円の減少となって、所得金額が同額だけ減少するということですね。
朝長 そうです。
――受取配当益金不算入について当初申告要件が廃止されたのは平成23年ですから、同年前の処理が争われている本件においては、受取配当の税務調査による増加額は益金不算入とはならないのではありませんか?
朝長 増額される受取配当を益金不算入とするのか否かということまでは争点に含まれていないわけですが、増額される部分も益金不算入となり得ると思っています。
――増額される受取配当が益金不算入となるということまで主張してそれが認められなければ、意味がないですよね。
朝長 そうですね。増額される受取配当が更正処分等によって減少した8億円だけしか益金不算入とならないということであれば、そもそも受取配当の増額を争点にする意味はほとんどないと言ってよいでしょう。この点に関しては、平成22年3月19日に東京地裁において、結果は納税者側の敗訴となっていますが、説示の中でも、税務調査によるみなし配当の増加額について、益金不算入の適用の意思があったか否かで追加的に益金不算入とするのか否かを判断するという考え方が示されています。
本件は、税務調査によるみなし配当の増加額が益金不算入となるか否かということの前に、みなし配当の額は実際の交付金額に基づいて計算するから増加しない、ということになってしまっていますが、しかし、本来は、納税者側が主張しているように、みなし配当の額は時価で計算するのが正しく、その結果、益金不算入額が増えて、200億円強の課税所得金額が少なくなる可能性が十分にある、と考えています。
22条2項の無償譲渡の定めの「解釈」と「事実関係」の区別に課題
――納税者側の主張が採用されなかったのはその主張に課題があったということでしょうか。
朝長 そうですね。納税者側の主張では、22条2項の無償譲渡の定めの「解釈」と「事実関係」の区別が明確ではなく、これがみなし配当を時価に基づいて計算すべきであるという主張が採用されなかった大きな原因と考えています。
「みなし配当」の規定である24条1項を見てみると、同項においては、「配当」と「みなす」と定めることにより、「配当」が行われた「事実」がないものについて、「配当」が行われた「事実」があるものとして取り扱うこととしています。
諸外国では、「事実認定」によって「配当」と認定するということはあっても、「みなす」という擬制によって「配当」と同様に取り扱うということはないのではないかと思います。
「事実認定」によって「配当」と認定することも、擬制によって「配当」と同様に取り扱うことも、結果は同じであるため、違いを気にする必要はないのではないかと思われがちですが、決してそういうことではなく、立法と解釈の観点からすると、非常に大きな違いがあることを良く理解しておく必要があります。
「みなす」という擬制の制度を創るのか否かということは、大きな立法判断になります。「事実認定」によって認定をすべきものについて「みなす」という擬制の制度を設けることは、許されません。
また、「みなす」という擬制の制度によってみなすこととなる「事実」は、その制度によってみなされることとなる「事実」とは異なると解釈することになります。24条1項各号に掲げられている合併や資本の払戻し等は、「配当」ではないと認識するが故に、「配当」と「みなす」と定めているわけです。
このように、24条では、「配当」ではないものについて、「みなす」ことによって「配当」と擬制するものとされているわけですが、「事実認定」によって「配当」となるものがあった場合にどうなるのかというと、「事実認定」によって「配当」となるものに対しては、「みなす」ことによって「配当」と擬制する24条の規定は適用されません。
これは、立法と解釈の常識と言うべきものですが、この24条の規定と22条2項の無償譲渡の定めの違いを正しく理解する必要があります。
22条2項の無償譲渡の定めは確認規定
――22条2項の無償譲渡の定めは確認規定ということで良いわけですね。
朝長 そうです。
24条1項は「みなす」と規定しているわけですから創設規定ですが、22条2項の無償譲渡の定めは、「みなす」とか「推定する」と規定しているわけではなく、単に無償譲渡に係る収益の額を益金の額とすると規定しているだけですから、無償譲渡で収益が発生するという前提に立った上での確認規定ということになります。当然のことながら、「みなす」と規定しているものと「みなす」と規定していないものとが同じ解釈になるということは、有り得ません。
財務省主税局で租税立法に携わった経験から申し上げると、無償譲渡においては対価の授受が行われませんので、22条2項の無償譲渡の定めを立法化するに際しては、少なくとも、内閣法制局の条文案の審査の場面では、「みなす」必要があるのか否かということが検討の俎上に載せられたはずであると考えています。
立法論としては、創設規定とする必要があるのか確認規定ということでよいのかという点は検討の余地があると考えますが、現に創設された22条2項の無償譲渡の定めが確認規定として作られていることは明白であり、解釈論としては、この定めを創設規定と解釈することは明らかな誤りであると考えています。
――立法論と解釈論は峻別しなければならないわけですね。
朝長 22条2項の無償譲渡の定めに関しても、立法論の議論か解釈論の議論か分からないものが少なくありませんが、これらは明確に分けて議論をする必要があります。
無償譲渡による収益・寄附の有無は「事実」の領域の問題
――22条2項の無償譲渡の定めは、無償譲渡の収益に対応する部分を寄附金とするという37条の無償譲渡における寄附金の定めと一体的に設けられたわけですよね。
朝長 そうですね。
例えば、AからBに資産の無償譲渡が行われた場合には、AがBに時価相当額の資産を寄附した「事実」があり、Aはその寄附をするに当たってその資産の時価相当額の収益を得た「事実」があるという「事実認定」が行われるという前提に立って、22条2項の無償譲渡の定めと37条の無償譲渡における寄附金の定めを適用する、ということになっています。
ただし、税務調査で無償譲渡において益金を計上する申告調整が行われていないものが発見されたというような場合には、常に寄附金とされるわけではなく、後日、対価を収受するということであれば、「未収金」等として処理するということも珍しくありません。
寄附があるのか否かということは、無償譲渡による寄附も含めて、「事実認定」の問題である、ということです。
仮に、資産が無償譲渡された場合に、資産を無償譲渡した者が収益を得たという「事実」がないという前提に立つとすれば、22条2項において、資産を無償譲渡した法人の収益の額と資産を時価譲渡した法人の収益の額とを同列に並べて、「益金の額に算入すべき金額は、……収益の額とする。」というような規定の仕方をすることは有りません。この22条2項の規定の仕方は、無償譲渡に収益の額がないと認識した上で収益の額があるものとするという場合の規定の仕方ではないことが明らかです。このような規定の仕方は、資産の無償譲渡をした法人にも収益の額があるという前提がなければ有り得ない、ということです。法令の解釈は、立法を良く理解して行う必要があります。
――対価が授受されないものも、対価が授受されるものと同じように収益と寄附があると捉えるということは、「事実」の範囲が広いということですかね。
朝長 そうですね。「事実関係」の「事実」を広く捉えていることは間違いありません。
このように「事実関係」の「事実」を広く捉えることの是非は、立法論の場面で検討の余地があると考えますが、しかし、既にご説明をしたとおり、解釈論の場面では、その是非は問題とはならず、無償譲渡による収益と寄附が存在するのか否かということは「事実」の領域の問題として位置付ける必要があります。
――納税者側は、無償譲渡に収益と寄附が存在するということを「事実」と捉えていなかったのでしょうか。
朝長 その辺りが明確ではありません。地裁の判決文にある納税者側の主張と高裁の判決文にある納税者側の主張のいずれの中でも、無償譲渡に関する22条2項の定めと37条の定めに基づく主張においては、「擬制」という用語が多用されています。地裁では10個、高裁では6個の「擬制」という用語が用いられています。
この「擬制」とは、法の世界では、ある事実について、それとは異なる事実と同じものとして取り扱い、その異なる事実に認められた法律効果をある事実にも発生させることをいい、専らみなし規定や推定規定の「解釈」を述べる場面で用いられることとなります。
私は、「法令の解釈」には「擬制」があるが、「事実」に「擬制」はないと考えています。
地裁の判決文における納税者側の主張も、高裁の判決文にある納税者側の主張も、「擬制」という用語を多用してなされる主張が「解釈」と「事実」のいずれを主張するものかということが必ずしも明確ではありません。
収益・寄附の有無が「事実関係」なら、みなし配当も時価による計算が筋
――本件のみなし配当を実際の交付金額に基づいて計算するべきか、あるいは、時価に基づいて計算するべきかという問題と、無償譲渡による収益・寄附の有無が「事実」の領域の問題であるということとは、どのように関係するのでしょうか。
朝長 みなし配当の規定である24条1項も、「事実」に当てはめて適用されることとなるわけですから、無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」があるのであれば、その無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」に同項を当てはめて適用しなければならない、ということになります。
24条1項には、「金銭その他の資産の交付を受けた」という「事実関係」に関する文言があり、これが実際に「交付」を受けたものでなければならないと解釈されたことが主たる納税者側の敗因となっていると考えて良いわけですが、22条2項の上記の整理からすると、この「事実関係」を示す文言は、無償譲渡における収益・寄附があるという「事実認定」を行った後の「事実関係」を指すものでなければなりません。そして、無償譲渡による収益・寄附があったという「事実」があるのであれば、「交付」を受けた「事実」もあると整理せざるを得ません。
高裁判決においては、子会社株式の譲渡損益を計算する場面で、61条の2第1項の「対価の額」について、当事者間で取り決めた対価の額ではなく、22条2項の無償譲渡の定めの解釈を根拠として、時価に置き換えて同項が適用されています。この「対価の額」がどのような金額となるのかということは、「事実」の領域の問題であって、「みなす」ことによって「対価の額」が時価とされるわけではありません。
一つの取引において、みなし配当を計算する場合の「事実」と子会社株式の譲渡損益を計算する場合の「事実」が異なるということは、有り得ないことです。
――もし22条2項の無償譲渡の定めが「みなし」の規定となっており、収益があると「擬制」をするものであったと仮定すればどうなるのでしょうか。
朝長 無償譲渡においては収益が存在しないという「事実」があるということになり、寄附として課税をするためには、寄附金の規定においても無償譲渡を寄附と「みなす」ことが必要となります。
そして、24条1項の「金銭その他の資産の交付を受けた」という部分に関しては、「交付を受けたものとみなす」と規定しない限り、実際に「交付」を受けたものしか指さない、ということになります。
――判決どおりということですね。
朝長 そういうことですね。
法人税法と所得税法では無償譲渡に関する「事実関係」の捉え方が異なる
――ところで、法人の株主には法人も個人も存在するわけですが、法人税法と所得税法の無償譲渡の取扱いには違いがあります。所得税法においても同様に考えて良いのでしょうか。
朝長 所得税法には、法人税法22条2項の無償譲渡の定めと同じような定めは設けられていませんので、同じにはなりません。
所得税法においては、資産を時価の2分の1未満で譲渡した場合に時価で譲渡したものと「みなす」こととされている定めが存在するのみです。ここでは、資産の譲渡に関する取扱いにおいて、時価による譲渡があったものと「みなす」とされていますので、無償譲渡の例で言うと、「事実関係」について時価によって譲渡したという「事実」がないと捉え、その上で、資産の譲渡に関する取扱いにおいては、時価による譲渡があったものと擬制して課税する、ということです。
法人税法61条の2第1項には「有価証券の譲渡をした」という文言があり、この「譲渡」には無償譲渡や低額譲渡が含まれていますが、所得税法における有価証券の「譲渡」には、みなし譲渡とされない低額譲渡は含まれていません。
みなし配当に関しても同様で、所得税法におけるみなし譲渡の規定の「みなし」は、みなし配当の規定には及びませんので、所得税法25条1項のみなし配当の規定の「金銭その他の資産の交付を受けた」という文言は、法人税法24条1項の文言と同様となってはいますが、その法人税法24条1項の文言の解釈とは異なり、実際に「交付」を受けたものだけを指すことになります。
換言すれば、所得税法においては、無償譲渡の場合には所得税法25条1項の「交付」に該当するものはないということになるが、法人税法においては、無償譲渡の場合にも法人税法24条1項の「交付」に該当するものがある、ということになります。
このように、法人税法と所得税法では、みなし配当の規定の適用を想定する「事実関係」の捉え方が違っているわけですから、「譲渡」と同じように、「交付」の捉え方に違いが出てくるのは、当然のことです。24条のみなし配当の規定も、平成13年に抜本的に見直して改正をさせて頂いたわけですが、立法に当たっては、違いがあるのは当然と考えていたものを用語が同じということで同じ解釈になると簡単に言われてしまうと、かなり違和感を感じますね。
「事実関係」を適切に説明すれば、みなし配当は時価で計算されていたはず
――法人税法と所得税法では、そもそも無償譲渡に関する「事実関係」の捉え方が違っているので、「交付」も同じ解釈にはならないということですね。本件だけの問題ではなく、24条1項の解釈の問題ですから、影響も大きいですよね。
朝長 法律の規定を作る場合には、必ずその規定をどのようなものに適用するのかということを想定することになります。22条2項の無償譲渡の定めに関しても、どのようなものに適用することを意図して作られたのかということを考えてみると、自ずと法人税法が無償譲渡における「事実関係」として想定しているものが見えてきます。
本件においては、22条2項の無償譲渡の定めが適用される「事実関係」をその定めの「解釈」と明確に区別して説明することが必要であったと思っています。
そうすれば、24条1項のみなし配当の規定も、無償譲渡による収益・寄附があるという「事実」に当てはめるべきであるということになり、みなし配当も時価に基づいて計算する必要がある、ということになったのではないかと考えています。
――本日は、お忙しい中、貴重なお話をお聞かせ頂き、誠にありがとうございました。
| 朝長英樹 ともなが ひでき 財務省主税局において、金融取引に係る法人税制の抜本改正(平成12年)・組織再編成税制の創設(平成13年)・連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。 税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。 現在、日本税制研究所 代表理事、朝長英樹税理士事務所 所長 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.