解説記事2015年11月16日 【税理士のための相続法講座】 相続分(3)-相続分の放棄と譲渡(2015年11月16日号・№618)
税理士のための相続法講座
第9回
相続分(3)-相続分の放棄と譲渡
弁護士 間瀬まゆ子
今回は、相続分が変動する場面として、相続分の放棄と相続分の譲渡についてお話します。
1 相続分の放棄 相続分の放棄は、共同相続人がその相続分を放棄することをいい、明文の根拠はないものの、実務上、遺産に対する共有持ち分権を放棄する意思表示と捉えられています。相続の放棄と似た言葉ですが、内容は異なります。
相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所に申述することが必要ですが(民法915条1項、938条)、相続分の放棄は相続開始後、遺産分割までの間であればいつでも可能であり、方式についての制限もありません。
効果についても、他の共同相続人の相続分には影響を及ぼすものの、相続放棄をした場合と異なり、相続分を放棄した相続人も相続人としての地位を失うことはないと解されています。すなわち、債権者の同意がない限り法定相続分相当の相続債務を免れることができませんので注意が必要です(本誌606号、第6回「承認と放棄(2)-相続放棄」参照)。
このような相続分の放棄は、相続放棄に比べ、あまり馴染みのない手続きかもしれません。使われることがあるのは、当事者間で紛争が生じて調停に発展した際に、調停手続きから離脱したいという相続人がいるような場合です。先ほど方式に制限がないと説明しましたが、調停実務においては、相続分の放棄をする旨の書面への本人の署名と実印による押印及び印鑑証明書の添付が求められるのが一般的です(調停外においても、各種の相続手続きに必要になりますので、やはり実印による押印と印鑑証明書は必須でしょう。)。
以下、一部の共同相続人が相続分の放棄をした場合に、他の共同相続人の相続分がどうなるか、事例に基づいて説明します。
仮に熟慮期間内であれば、Dは相続放棄をすることが可能です。その場合、Dははじめから相続人でなかったことになり(民法939条)、Bの相続分が1/2、CとEの相続分はそれぞれ1/4(1/2×1/2)となります。
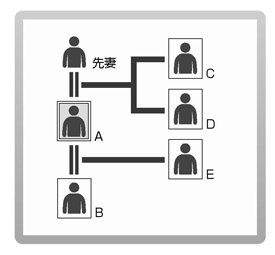
これに対し、熟慮期間を過ぎてしまったため、Dが相続分の放棄をした場合はどうでしょうか。この場合、Dが相続人としての地位を失うことはないものの、相続登記を経ているというような事情がない限り、遺産分割の手続きからは脱退できます。そして、Dの相続分1/6(1/2×1/3)については、以下のとおり、残りの相続人に、各人の相続分率に応じて配分されることになります(ただし、多数当事者事案について、これと異なる処理をすることがあります。)。
まず、B・C・Eの相続分の比率を出します。
1/2:1/6:1/6=3:1:1
そうすると、それぞれの相続分率が以下のとおりに求められます。
Bの相続分率 3/(3+1+1)=3/5
C・Eの各相続分率 1/(3+1+1)=1/5
この相続分率に基づいてDの相続分を再配分し、D以外の相続人の元の相続分に加算します。結果として、Bらの相続分はそれぞれ以下のとおりとなります。
Bの相続分 1/2+(1/6×3/5)
C・Eの各相続分 1/6+(1/6×1/5)
2 相続分の譲渡 相続人は、遺産分割前であれば、相続分を譲渡することができます(民法905条参照)。相続分の譲渡の対象となる「相続分」は、積極財産のみならず消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対して各共同相続人が有する持分あるいは法律上の地位と説明されています。債権者との関係では譲渡人たる相続人が直ちに債務を免れ得ないこと及び法文の定めはないものの実務上厳格な方式が求められることは相続分の放棄の場合と同様です。
相続分の譲渡は、相続人を整理するために使われることがあります。例えば、遺産分割協議をまとめようとしたものの、多数いる相続人全員の納得が得られずやむなく調停を起こすことになった場合に、こちらに協力的な相続人についてのみ先に相続分を譲渡してもらって、調停の相手方を減らしておくというようなケースです。また、先ほどの事案のように、遺産分割の手続きから脱退する目的で行われることもあります。
ただ、例えば、先ほどの事案のDがCに相続分を譲渡した場合に、残りの相続人であるB及びEの相続分に及ぼす影響は、相続分の放棄の場合と異なります。具体的には、Cに対して相続分を譲渡すると、Cの相続分のみが元の1/6にDの相続分1/6を加算した1/3に増加し、B及びEの相続分には影響がないことになります。
相続分の譲渡の相手方は、相続人である必要はなく、第三者への譲渡も可能ですし、一部の譲渡も認められます。実例はそれほど多くないでしょうが、例えば、事実婚の配偶者のように、本来遺産分割協議に加わってしかるべき人を加えるために、他の相続人が協力して一部の相続分を譲渡する場合等が考えられます。
なお、他の共同相続人から見て好ましくない第三者に譲渡されてしまった場合を想定し、民法は、他の共同相続人に、価額弁償をして第三者の相続分を譲り受ける権利(取戻権)を認めています(民法905条1項)。しかし、行使期間が譲渡から1ケ月と非常に短く、実用的な制度とはなっていません(同条2項)。
相続分の譲受人は、譲渡人の地位を承継し、遺産分割手続に関与することが可能になります(似たような場合として、相続分ではなく、個々の遺産に対する共有持分を第三者に譲渡することがありますが、この場合に譲受人が共有状態の解消を求めるためには、遺産分割の手続きによることはできず、共有物分割請求訴訟を提起する必要があります。)。また、相続分の譲受人は、譲り受けた相続分に相当するプラスの財産を承継するのみならず、債務も承継することになります。相続債権者との関係については諸説ありますが、並存的債務引受になる等と解されています。
第9回
相続分(3)-相続分の放棄と譲渡
弁護士 間瀬まゆ子
今回は、相続分が変動する場面として、相続分の放棄と相続分の譲渡についてお話します。
1 相続分の放棄 相続分の放棄は、共同相続人がその相続分を放棄することをいい、明文の根拠はないものの、実務上、遺産に対する共有持ち分権を放棄する意思表示と捉えられています。相続の放棄と似た言葉ですが、内容は異なります。
相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所に申述することが必要ですが(民法915条1項、938条)、相続分の放棄は相続開始後、遺産分割までの間であればいつでも可能であり、方式についての制限もありません。
効果についても、他の共同相続人の相続分には影響を及ぼすものの、相続放棄をした場合と異なり、相続分を放棄した相続人も相続人としての地位を失うことはないと解されています。すなわち、債権者の同意がない限り法定相続分相当の相続債務を免れることができませんので注意が必要です(本誌606号、第6回「承認と放棄(2)-相続放棄」参照)。
このような相続分の放棄は、相続放棄に比べ、あまり馴染みのない手続きかもしれません。使われることがあるのは、当事者間で紛争が生じて調停に発展した際に、調停手続きから離脱したいという相続人がいるような場合です。先ほど方式に制限がないと説明しましたが、調停実務においては、相続分の放棄をする旨の書面への本人の署名と実印による押印及び印鑑証明書の添付が求められるのが一般的です(調停外においても、各種の相続手続きに必要になりますので、やはり実印による押印と印鑑証明書は必須でしょう。)。
以下、一部の共同相続人が相続分の放棄をした場合に、他の共同相続人の相続分がどうなるか、事例に基づいて説明します。
| Aが亡くなった。法定相続人は妻Bと3人の子。そのうちCとEは以前から非常に仲が悪く、Dは「面倒なことに巻き込まれたくない。財産ももらわなくてよい。」と思っている。 |
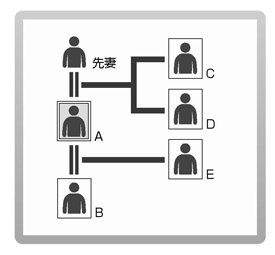
これに対し、熟慮期間を過ぎてしまったため、Dが相続分の放棄をした場合はどうでしょうか。この場合、Dが相続人としての地位を失うことはないものの、相続登記を経ているというような事情がない限り、遺産分割の手続きからは脱退できます。そして、Dの相続分1/6(1/2×1/3)については、以下のとおり、残りの相続人に、各人の相続分率に応じて配分されることになります(ただし、多数当事者事案について、これと異なる処理をすることがあります。)。
まず、B・C・Eの相続分の比率を出します。
1/2:1/6:1/6=3:1:1
そうすると、それぞれの相続分率が以下のとおりに求められます。
Bの相続分率 3/(3+1+1)=3/5
C・Eの各相続分率 1/(3+1+1)=1/5
この相続分率に基づいてDの相続分を再配分し、D以外の相続人の元の相続分に加算します。結果として、Bらの相続分はそれぞれ以下のとおりとなります。
Bの相続分 1/2+(1/6×3/5)
C・Eの各相続分 1/6+(1/6×1/5)
2 相続分の譲渡 相続人は、遺産分割前であれば、相続分を譲渡することができます(民法905条参照)。相続分の譲渡の対象となる「相続分」は、積極財産のみならず消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対して各共同相続人が有する持分あるいは法律上の地位と説明されています。債権者との関係では譲渡人たる相続人が直ちに債務を免れ得ないこと及び法文の定めはないものの実務上厳格な方式が求められることは相続分の放棄の場合と同様です。
相続分の譲渡は、相続人を整理するために使われることがあります。例えば、遺産分割協議をまとめようとしたものの、多数いる相続人全員の納得が得られずやむなく調停を起こすことになった場合に、こちらに協力的な相続人についてのみ先に相続分を譲渡してもらって、調停の相手方を減らしておくというようなケースです。また、先ほどの事案のように、遺産分割の手続きから脱退する目的で行われることもあります。
ただ、例えば、先ほどの事案のDがCに相続分を譲渡した場合に、残りの相続人であるB及びEの相続分に及ぼす影響は、相続分の放棄の場合と異なります。具体的には、Cに対して相続分を譲渡すると、Cの相続分のみが元の1/6にDの相続分1/6を加算した1/3に増加し、B及びEの相続分には影響がないことになります。
相続分の譲渡の相手方は、相続人である必要はなく、第三者への譲渡も可能ですし、一部の譲渡も認められます。実例はそれほど多くないでしょうが、例えば、事実婚の配偶者のように、本来遺産分割協議に加わってしかるべき人を加えるために、他の相続人が協力して一部の相続分を譲渡する場合等が考えられます。
なお、他の共同相続人から見て好ましくない第三者に譲渡されてしまった場合を想定し、民法は、他の共同相続人に、価額弁償をして第三者の相続分を譲り受ける権利(取戻権)を認めています(民法905条1項)。しかし、行使期間が譲渡から1ケ月と非常に短く、実用的な制度とはなっていません(同条2項)。
相続分の譲受人は、譲渡人の地位を承継し、遺産分割手続に関与することが可能になります(似たような場合として、相続分ではなく、個々の遺産に対する共有持分を第三者に譲渡することがありますが、この場合に譲受人が共有状態の解消を求めるためには、遺産分割の手続きによることはできず、共有物分割請求訴訟を提起する必要があります。)。また、相続分の譲受人は、譲り受けた相続分に相当するプラスの財産を承継するのみならず、債務も承継することになります。相続債権者との関係については諸説ありますが、並存的債務引受になる等と解されています。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























