解説記事2015年12月14日 【税理士のための相続法講座】 相続分(4)-特別受益(2015年12月14日号・№622)
税理士のための相続法講座
第10回
相続分(4)-特別受益
弁護士 間瀬まゆ子
相続税の計算においても相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算されますが、民法上も、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合、当該遺贈や生前贈与を相続分の前渡しとみて、計算上これを相続財産に加算して相続分を算定することになっています(民法903条)。「特別受益の持戻し」といわれる制度です。ただ、税務の生前贈与加算と異なり、特別受益の持戻しの対象となる贈与については年数の制限はなく、古い贈与も含まれます(相続人間の対立があるときに贈与を主張する側がそれを立証できるかはまた別の問題です。)。
特別受益がある場合には、相続開始時に被相続人が有していた積極財産に相続人が受けた特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、これに各相続人の相続分を乗じて一応の相続分を算定し、ここから特別受益分を控除して特別受益者が現実に取得すべき相続分を確定します。
一応の相続分が特別受益分を上回っていれば、特別受益者も相続財産から分配を受けられますが、マイナスになった場合には相続分はゼロとなります(マイナス分の財産を返還する必要はありません。)。
特別受益として持ち戻す価格の評価基準時は相続開始時です。特別受益者が贈与された財産を焼失させてしまったり、他に売却したりした場合や、修繕等により価値の増減が生じた場合は、贈与された時の状態のままであるとみなして評価をします(民法904条)。例えば、2000万円の土地を贈与された後これを2500万円で売却できたとしても、相続開始時の評価額が1800万円であれば持戻しの額は1800万円となります。ただし、贈与を受けた建物が地震等の不可抗力で倒壊したような場合には、受贈者は何らの贈与を受けなかったものとみなされます(ただ、補償金等を受けている場合は当該補償金等が持戻しの対象となります。)。
次に、代襲相続人がいる場合の特別受益の考え方ですが、被代襲者に対する生前贈与は、代襲相続人の特別受益になると解されています。また、代襲相続人自身が受けた生前贈与については、代襲原因が発生した後に代襲相続人が受けた受益のみを持戻しの対象とするのが通説です。そのため、この場合、贈与の時期が重要な意味を持つことになります。
特別受益の持戻しは、被相続人が免除しておくことが可能です(民法903条3項)。多額の贈与がある場合には、持戻しの対象とするか否か、遺言で明確にしておくことが肝要です。なお、持戻しの免除をしても、遺留分を害する場合には、その限度で減殺請求の対象となります。
特別受益に関して争いとなり易いのは、特別受益の評価のほか、そもそも特別受益が存するかという点です。どのような贈与が、遺産の前渡しとしての贈与にあたり、持戻しの対象とされるのか、明確な基準はありません。家庭裁判所が関わる場面では、事案ごとに個別の事情に応じた解決が図られるため、共通したルールを見出すことは困難なのですが、以下、2つの事例をもとに、実務の傾向を見ていきたいと思います。
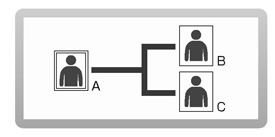
民法903条1項は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ときに、当該贈与が特別受益になると定めています。ここでいう「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが実務上問題となることが多く、これについては、贈与金額や贈与の趣旨等から判断すべきとされています。
まず、大学進学及び海外留学について考えます。高等教育の学資については、被相続人の資力や社会的地位、他の相続人との比較等から判断されることになりますが、相続人全員が大学以上の教育を受けている場合、多少の金額の多寡はあっても、特別受益とはされないのが通常でしょう。ただ、上記のケースでは、Cのみ海外留学をしています。多額の海外留学費用がかかったとなると、その支出については特別受益と評価される可能性もあります。しかし、その場合でも、Aの持戻し免除の意思表示が認定され(持戻し免除の意思表示は黙示でも構いません。)、特別受益として考慮されないことも多いと思われます。教育費については、扶養の一内容と認識され、遺産の先渡しの趣旨を含まないのが一般的と解されるためです。
続いて、Bが受けていた援助についてです。ある程度以上の年齢で自立できる子に対する援助は、特別受益に該当し得るところですが、Bはうつ病で退職したとのことですので、その後も精神的な疾患のために就労が困難であったということであれば、Aによる援助も扶養義務の範囲として、特別受益にはあたらないと判断される可能性が高いでしょう。ただ、毎月の援助額に変動があり、ある程度以上の金額を渡した月があったという場合には、その月の分について特別受益とされる可能性もあります。
更に、BがAの生前に下ろしていた預金はどうなるでしょうか。一般的な感覚としては、「Bが使い込んだのではないか。」と疑いたくなるところですが、Bが「Aの指示で下ろした後Aに手渡した。」と説明しており、Cの方でも具体的な事情を把握していないと思われますので、AとBとの間で贈与の合意があったと認定することは困難と思われます。となると、「生計の資本」の解釈以前に贈与の事実を認定できませんので、特別受益に該当するとの主張は認められ難いと思われます。この辺りは税務の感覚とは異なるところかもしれません。
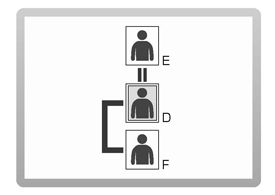
まず、生命保険金については、受取人に指定されたEが自己の固有の権利として保険金請求権を取得すると解されているため、遺産分割の対象とはならず、特別受益にも原則としてあたらないものとされています。ただ、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により、特別受益に準じて死亡保険金も持戻しの対象となるというのが判例です(最二小決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。この判断を受け、例えば、相続財産が約8400万円であるのに対して、特定の相続人が約5200万円の保険金を受け取ったケースで、当該保険金を持戻しの対象とすべきとした下級審の裁判例(名古屋高決平成18年3月27日家月58巻10号66頁)があります。
この点、Eが受け取る保険金は400万円で、相続財産4000万円(不動産3000万円+預貯金1000万円)の10分の1の金額です。この程度であれば、最高裁のいう「特段の事情」があったとまでは言えず、持戻しの対象とはされない可能性が高いと思われます。
なお、特別な事情があるとして持ち戻されることになった場合に、具体的に持ち戻されるべき価額は、保険料の額ではなく受け取った保険金の額となります(ただし、被相続人が負担した保険料に対応する部分に限ります。)。
続いて、勤務先の規程等に基づいて特定の遺族に支給される死亡退職金等の遺族給付ですが、これらについては相続財産には含まれず、かつ、受給権者の生活保障という趣旨に照らし、特別受益にも含めないのが一般的です。したがって、持戻しの対象とはなりません。
一方、持株会から支払われる精算金については、死亡退職金等と異なり、支払う遺族についての定めはないのが通常でしょうから、Dの相続財産に含まれ、そもそもEが単独で取得できるものではないと考えます。したがって、特別受益に該当するかは問題となりません。
第10回
相続分(4)-特別受益
弁護士 間瀬まゆ子
相続税の計算においても相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算されますが、民法上も、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合、当該遺贈や生前贈与を相続分の前渡しとみて、計算上これを相続財産に加算して相続分を算定することになっています(民法903条)。「特別受益の持戻し」といわれる制度です。ただ、税務の生前贈与加算と異なり、特別受益の持戻しの対象となる贈与については年数の制限はなく、古い贈与も含まれます(相続人間の対立があるときに贈与を主張する側がそれを立証できるかはまた別の問題です。)。
特別受益がある場合には、相続開始時に被相続人が有していた積極財産に相続人が受けた特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、これに各相続人の相続分を乗じて一応の相続分を算定し、ここから特別受益分を控除して特別受益者が現実に取得すべき相続分を確定します。
一応の相続分が特別受益分を上回っていれば、特別受益者も相続財産から分配を受けられますが、マイナスになった場合には相続分はゼロとなります(マイナス分の財産を返還する必要はありません。)。
特別受益として持ち戻す価格の評価基準時は相続開始時です。特別受益者が贈与された財産を焼失させてしまったり、他に売却したりした場合や、修繕等により価値の増減が生じた場合は、贈与された時の状態のままであるとみなして評価をします(民法904条)。例えば、2000万円の土地を贈与された後これを2500万円で売却できたとしても、相続開始時の評価額が1800万円であれば持戻しの額は1800万円となります。ただし、贈与を受けた建物が地震等の不可抗力で倒壊したような場合には、受贈者は何らの贈与を受けなかったものとみなされます(ただ、補償金等を受けている場合は当該補償金等が持戻しの対象となります。)。
次に、代襲相続人がいる場合の特別受益の考え方ですが、被代襲者に対する生前贈与は、代襲相続人の特別受益になると解されています。また、代襲相続人自身が受けた生前贈与については、代襲原因が発生した後に代襲相続人が受けた受益のみを持戻しの対象とするのが通説です。そのため、この場合、贈与の時期が重要な意味を持つことになります。
特別受益の持戻しは、被相続人が免除しておくことが可能です(民法903条3項)。多額の贈与がある場合には、持戻しの対象とするか否か、遺言で明確にしておくことが肝要です。なお、持戻しの免除をしても、遺留分を害する場合には、その限度で減殺請求の対象となります。
特別受益に関して争いとなり易いのは、特別受益の評価のほか、そもそも特別受益が存するかという点です。どのような贈与が、遺産の前渡しとしての贈与にあたり、持戻しの対象とされるのか、明確な基準はありません。家庭裁判所が関わる場面では、事案ごとに個別の事情に応じた解決が図られるため、共通したルールを見出すことは困難なのですが、以下、2つの事例をもとに、実務の傾向を見ていきたいと思います。
| 被相続人Aは自宅不動産と預貯金を残して亡くなったが、自宅不動産についてのみ、「長男Bに相続させる」との遺言を残していた。Aの相続に係る相続人はBと次男C。Bは大学を出て働いていたが、うつ病を患って退職し、以後はAと同居して生活費を負担してもらうほか、毎月2万円程度の現金を受け取っていた。一方、Cは、国内の大学を出た後海外に留学し、その学費は全てAに負担してもらっていた。また、Cが通帳を見たところ、Aが亡くなる直前に多額の現金が引き出されていたが、Bは、「Aの指示で下ろした後Aに手渡した。Aが何に使ったのかは分からない。」と説明している。 |
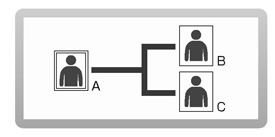
民法903条1項は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ときに、当該贈与が特別受益になると定めています。ここでいう「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが実務上問題となることが多く、これについては、贈与金額や贈与の趣旨等から判断すべきとされています。
まず、大学進学及び海外留学について考えます。高等教育の学資については、被相続人の資力や社会的地位、他の相続人との比較等から判断されることになりますが、相続人全員が大学以上の教育を受けている場合、多少の金額の多寡はあっても、特別受益とはされないのが通常でしょう。ただ、上記のケースでは、Cのみ海外留学をしています。多額の海外留学費用がかかったとなると、その支出については特別受益と評価される可能性もあります。しかし、その場合でも、Aの持戻し免除の意思表示が認定され(持戻し免除の意思表示は黙示でも構いません。)、特別受益として考慮されないことも多いと思われます。教育費については、扶養の一内容と認識され、遺産の先渡しの趣旨を含まないのが一般的と解されるためです。
続いて、Bが受けていた援助についてです。ある程度以上の年齢で自立できる子に対する援助は、特別受益に該当し得るところですが、Bはうつ病で退職したとのことですので、その後も精神的な疾患のために就労が困難であったということであれば、Aによる援助も扶養義務の範囲として、特別受益にはあたらないと判断される可能性が高いでしょう。ただ、毎月の援助額に変動があり、ある程度以上の金額を渡した月があったという場合には、その月の分について特別受益とされる可能性もあります。
更に、BがAの生前に下ろしていた預金はどうなるでしょうか。一般的な感覚としては、「Bが使い込んだのではないか。」と疑いたくなるところですが、Bが「Aの指示で下ろした後Aに手渡した。」と説明しており、Cの方でも具体的な事情を把握していないと思われますので、AとBとの間で贈与の合意があったと認定することは困難と思われます。となると、「生計の資本」の解釈以前に贈与の事実を認定できませんので、特別受益に該当するとの主張は認められ難いと思われます。この辺りは税務の感覚とは異なるところかもしれません。
| 被相続人Dが亡くなった。法定相続人は妻Eと兄Fで、主な相続財産は自宅3000万円と預貯金1000万円。遺言はない。Eが調べたところ、Dは生前保険に入っており、死亡保険金400万円が下りることが分かった(受取人はE)。また、Dの勤務先から、死亡退職金が遺族に支払われるほか、加入していた従業員持株会も退会扱いになり、持分を換価した分の現金が戻って来るとの説明を受けた。 |
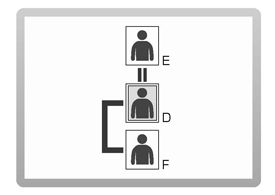
まず、生命保険金については、受取人に指定されたEが自己の固有の権利として保険金請求権を取得すると解されているため、遺産分割の対象とはならず、特別受益にも原則としてあたらないものとされています。ただ、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により、特別受益に準じて死亡保険金も持戻しの対象となるというのが判例です(最二小決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。この判断を受け、例えば、相続財産が約8400万円であるのに対して、特定の相続人が約5200万円の保険金を受け取ったケースで、当該保険金を持戻しの対象とすべきとした下級審の裁判例(名古屋高決平成18年3月27日家月58巻10号66頁)があります。
この点、Eが受け取る保険金は400万円で、相続財産4000万円(不動産3000万円+預貯金1000万円)の10分の1の金額です。この程度であれば、最高裁のいう「特段の事情」があったとまでは言えず、持戻しの対象とはされない可能性が高いと思われます。
なお、特別な事情があるとして持ち戻されることになった場合に、具体的に持ち戻されるべき価額は、保険料の額ではなく受け取った保険金の額となります(ただし、被相続人が負担した保険料に対応する部分に限ります。)。
続いて、勤務先の規程等に基づいて特定の遺族に支給される死亡退職金等の遺族給付ですが、これらについては相続財産には含まれず、かつ、受給権者の生活保障という趣旨に照らし、特別受益にも含めないのが一般的です。したがって、持戻しの対象とはなりません。
一方、持株会から支払われる精算金については、死亡退職金等と異なり、支払う遺族についての定めはないのが通常でしょうから、Dの相続財産に含まれ、そもそもEが単独で取得できるものではないと考えます。したがって、特別受益に該当するかは問題となりません。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















