解説記事2016年02月29日 【ニュース特集】 平成28年度・組織再編税制関係改正のすべて(2016年2月29日号・№632)
ニュース特集
各種「継続要件」の解釈明確化、適格現物出資の範囲見直し…etc.
平成28年度・組織再編税制関係改正のすべて
平成28年度税制改正では、消費税の軽減税率導入に伴う消費税法の改正や移転価格税制に係る文書化制度の見直しといった目玉改正が実施される一方、組織再編税制関係でも複数の改正が実施される。組織再編税制関係の改正項目の多くは政令事項であり、比較的“小粒”だが、その中には従来の実務を改めるものも含まれており、実務家にとっては是非とも押さえておきたい内容となっている。
本特集では、平成28年度税制改正における組織再編税制関係の改正項目を総ざらいする。
株主数50人以上の法人にも継続保有要件課す“安全策”は不要
まずは、共同事業を行うための新設合併等における「株式継続保有要件」に関する解釈の明確化だ。平成28年度税制改正大綱には、「共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件の判定について明確化する」との一文が盛り込まれている(与党の平成28年度税制改正大綱74頁(1)②)。
現行法人税法上、新設合併等に係る共同事業を営むための適格要件の1つである「株式継続保有要件」は、被合併法人、分割法人及び株式移転完全子法人(以下、「被合併法人等」という)の株主の数が50人以上である場合には免除されている(法令4の3④五、⑧六イ、⑳五)。大綱で想定されているのは、共同事業を行うための新設合併、新設分割、株式移転(以下、「新設合併等」という)において、組織再編の当事者となる一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースである。
この場合、株式継続保有要件は、株主数が「50人未満」である場合にかかってくるが、このように新設合併等において一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースでは、実務上、より厳しい要件に合わせる形で、株主数が50人未満の法人のみならず、50人以上の法人に対しても自主的に継続保有要件を課すという“安全策”がとられてきた。
こうした中、平成28年度税制改正では、あくまで「それぞれの法人ごと」に継続保有要件の適用の有無を判定すればよいことが明確化される。すなわち、組織再編の当事者となる一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースでは、後者についてのみ継続保有要件を適用すればよいことになる。
株式交換・移転税制の役員継続要件、合併税制と平仄
平成28年度税制改正は、株式交換・移転税制に関する改正が多いのも特徴となっている。
税制改正大綱では、株式交換・移転税制について下記の改正を実施することが明記されている。それぞれについて解説しよう。
まずイは、株式交換・移転税制における役員継続要件の取扱いを、合併税制に合わせたものだ。
現行法人税法上、共同で事業を営むための株式交換(株式移転)は、株式交換(移転)完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換(移転)に伴って退任(株式交換(移転)完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く)をするものでないことを求める「特定役員継続要件」が設けられている((法令4条の3⑯二、⑳二)。そして、この特定役員継続要件は、特定役員のうち“1人でも”当該株式交換や移転に伴って退任した場合には満たさないこととなる旨の取扱いがある(国税庁の質疑応答事例「株式移転における特定役員継続要件の判定」参照)。
これに対し、合併においては「合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること」とされており(法令4条の3④二)、株式交換・移転税制と合併税制の間で齟齬がある。
そこで平成28年度税制改正では、株式交換・移転税制においても、特定役員の“全て”が退任しない限り、特定役員継続要件を満たすこととする。この改正に伴い、上記質疑応答の内容は変更されることになろう。
簿価純資産価額算定に係る事務負担を軽減
次いでロは、事務負担軽減のために行われる改正である。
現行法上、適格株式交換・移転により親法人が取得する子法人株式の取得価額は、株主が50人以上である子法人の場合には、「株式交換等の“直前”の簿価純資産価額」でなければならないとされている(法令119条①九ロ、十一ロ)。しかし、株式交換等の直前の簿価純資産価額を計算するためには、仮決算をし、場合によっては時価評価が必要になるなど手間がかかることから、平成28年度税制改正では株式交換等の直前の簿価純資産価額ではなく、「子法人の直前の申告における簿価純資産価額」をベースに、資本金等の額、利益積立金額の出入りだけ調整すれば済むようにする。
株式交換完全親法人等の事業に関連しない事業は引継ぎ不要
「ハ その他適格要件について、所要の措置を講ずる。」には2つの改正が含まれている。1つが株式交換・移転後の“二次再編”における事業継続要件の明確化である。
株式交換や移転後に分割や合併などの“二次再編”が行われることがあるが、この場合に問題となるのが「事業継続要件」だ。
株式交換を例にとると、現行法人税法上、二次再編がない場合には「株式交換完全子法人の事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」との事業継続要件が設けられ(法令4条の3⑯四)、二次再編が行われる場合(当該株式交換後に適格合併等により子法人事業を移転することが見込まれている場合)には、「その移転する事業が移転後の法人において引き続き営まれ、かつ移転しない事業が子法人において引き続き営まれることが見込まれている」との要件が設けられている(同カッコ書き)。
この条文を見ると、二次再編のないケースでは「親法人事業と関連する事業」の継続とあるが、二次再編がある場合には「親法人事業と関連する」との限定がなく、「移転しない事業」も子法人において継続する見込みであることが求められていることから、実務では、「二次再編の場合は子法人の“すべての事業”を継続しなければならない」との解釈が存在している。
この点について平成28年度税制改正では、二次再編がある場合であっても、継続が求められるのはあくまで「株式交換完全親法人等に関連する事業」のみであることが明確にされる。
例えば、図1のように、株式交換完全親法人(以下、単に「親法人」)がA事業を営み、株式交換完全子法人(以下、単に「子法人」)が親法人のA事業に関連するa事業と、関連しないB事業を営んでおり、二次再編として、子法人のa事業の一部を分割して分割承継法人に承継させる一方、B事業はやめるものとする。
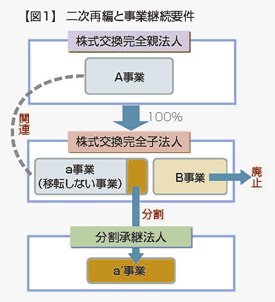
この場合、現在の「二次再編の場合は子法人の“すべての事業”を継続しなければならない」との解釈によると、子法人がB事業を継続しない以上、事業継続要件を満たさないこととなってしまう。
そこで平成28年度税制改正では、二次再編の場合であっても、あくまで株式交換完全親法人等と「関連する事業」のみが引き続き営まれることが見込まれる限り、事業継続要件を満たすことが明確にされる。図1の例では、子法人においてa事業の継続が見込まれている限り、B事業は継続が見込まれていなくても、事業継続要件は満たすことになる。
ただし、a事業が分割ができない事業である場合には、「移転しない事業(=株式交換完全子法人に残ったa事業)が子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」という要件は不要とする。すなわち、a事業を丸ごと承継させていたとしても、事業継続要件には抵触しないこととなる。
また、二次再編が適格合併である場合には、そもそも株式交換完全子法人等が消滅してしまうため、やはり「移転しない事業が子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」との要件は不要とされる。
同様の改正は株式移転(法令4条の3⑳四)についても実施される。
株式移転後の支配関係、順次の適格合併直前までの継続で可
2つ目が、株式移転に係る支配関係継続要件について会社法との齟齬の解消を図るものだ。
現行法人税法上、株式移転後に、株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、株式移転完全親法人を合併法人とする適格合併が行われる場合の支配関係継続要件としては、株式移転完全親法人が、その適格合併の直前まで「株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の株式の“全部”を保有する関係が継続すること」が求められている(法令4条の3⑲一ロ・二ロ)。
一方、会社法上、吸収合併は「存続会社及び消滅会社の2社」により行われるものとされている。すなわち、上記のような3社合併であっても、2つの吸収合併が行われたものと取り扱われることになる(会社法2条二十七)。法人税法施行令4条の3が想定している「3社合併」という概念は会社法上は存在しない。
例えばA社を合併法人とし、B社とC社を被合併法人とする合併があった場合、会社法上はあくまでも「A社・B社の合併+A社・C社の合併」と考えることになる。ただ、そうなると法人税法上はA社・C社の合併の際にはA社はB社株式を保有していないことになり、支配関係継続要件を満たせない。
こうした中、平成28年度税制改正では、「順次行われる適格合併の直前まで」親法人と子法人の関係が継続されれば、支配関係継続要件を満たすことが明確にされる。
帰属主義踏まえ日本PEへの国内資産の現物出資も適格に
最後は適格現物出資の範囲見直しだ。こちらは税制改正大綱上「円滑・適正な納税のための環境整備」の1つとして実施される(与党の平成28年度税制改正大綱67頁(1))。
現物出資税制の改正は、平成26年度税制改正で、外国法人の事業所得に関する課税の基本的な考え方が「総合主義」から「帰属主義」に変更され、平成28年4月から実施されることに対応するもの。
現行制度上、内国法人が外国法人に対し、国内不動産など国内にある事業所に属する資産(25%以上を有する外国法人株式を除く)を移転した場合、当該移転は適格現物出資の対象から除かれている。しかし、帰属主義が導入されたことで、外国法人に対する現物出資であっても、現物出資される国内資産が日本のPEに帰属する限り、日本の課税権は失われない。そこで、日本のPEに対する国内資産の現物出資を適格対象に追加する(図2①)。
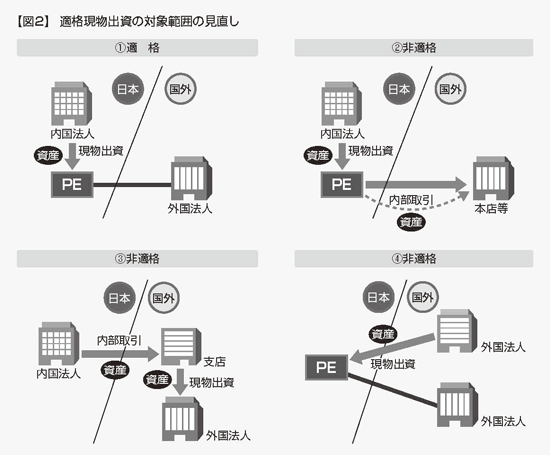
ただし、当該PEへの現物出資後、当該PEと国外の本店等との間で簿価で資産の内部取引が行われ、内部取引後に資産が国外で譲渡された場合、課税が困難となる恐れがある。そこで、「現物出資後に資産を内部取引により移転しないことが見込まれている場合」に限り、適格対象とする(図2②)。
また、内国法人が外国の支店等に国内資産を内部取引し、これがさらに外国法人(PEではない)に現物出資された場合、日本の課税権が失われることになる。そこで、内国法人が外国法人に対し「その現物出資の日前1年以内に内国法人の本店等から内部取引された国外事業所資産」を移転する現物出資を適格対象から除外する。(図2③参照。ただし、現金、預金、棚卸資産、有価証券を除く)。
このほか、現行制度では、外国法人が内国法人に対して国外にある事業所に属する資産(国内不動産を除く)の移転を行うケースは適格現物出資の対象外とされているが、帰属主義の実施を踏まえ、国外資産の含み損が日本に持ち込まれることによる課税上の弊害を防止するため、外国法人が他の外国法人の日本PEに対して国外事業所資産を現物出資する場合も、非適格現物出資とする(図2④参照)。
各種「継続要件」の解釈明確化、適格現物出資の範囲見直し…etc.
平成28年度・組織再編税制関係改正のすべて
平成28年度税制改正では、消費税の軽減税率導入に伴う消費税法の改正や移転価格税制に係る文書化制度の見直しといった目玉改正が実施される一方、組織再編税制関係でも複数の改正が実施される。組織再編税制関係の改正項目の多くは政令事項であり、比較的“小粒”だが、その中には従来の実務を改めるものも含まれており、実務家にとっては是非とも押さえておきたい内容となっている。
本特集では、平成28年度税制改正における組織再編税制関係の改正項目を総ざらいする。
株主数50人以上の法人にも継続保有要件課す“安全策”は不要
まずは、共同事業を行うための新設合併等における「株式継続保有要件」に関する解釈の明確化だ。平成28年度税制改正大綱には、「共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件の判定について明確化する」との一文が盛り込まれている(与党の平成28年度税制改正大綱74頁(1)②)。
現行法人税法上、新設合併等に係る共同事業を営むための適格要件の1つである「株式継続保有要件」は、被合併法人、分割法人及び株式移転完全子法人(以下、「被合併法人等」という)の株主の数が50人以上である場合には免除されている(法令4の3④五、⑧六イ、⑳五)。大綱で想定されているのは、共同事業を行うための新設合併、新設分割、株式移転(以下、「新設合併等」という)において、組織再編の当事者となる一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースである。
この場合、株式継続保有要件は、株主数が「50人未満」である場合にかかってくるが、このように新設合併等において一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースでは、実務上、より厳しい要件に合わせる形で、株主数が50人未満の法人のみならず、50人以上の法人に対しても自主的に継続保有要件を課すという“安全策”がとられてきた。
こうした中、平成28年度税制改正では、あくまで「それぞれの法人ごと」に継続保有要件の適用の有無を判定すればよいことが明確化される。すなわち、組織再編の当事者となる一方の法人の株主数が50人以上、もう一方の法人の株主数が50人未満というケースでは、後者についてのみ継続保有要件を適用すればよいことになる。
株式交換・移転税制の役員継続要件、合併税制と平仄
平成28年度税制改正は、株式交換・移転税制に関する改正が多いのも特徴となっている。
税制改正大綱では、株式交換・移転税制について下記の改正を実施することが明記されている。それぞれについて解説しよう。
まずイは、株式交換・移転税制における役員継続要件の取扱いを、合併税制に合わせたものだ。
現行法人税法上、共同で事業を営むための株式交換(株式移転)は、株式交換(移転)完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換(移転)に伴って退任(株式交換(移転)完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く)をするものでないことを求める「特定役員継続要件」が設けられている((法令4条の3⑯二、⑳二)。そして、この特定役員継続要件は、特定役員のうち“1人でも”当該株式交換や移転に伴って退任した場合には満たさないこととなる旨の取扱いがある(国税庁の質疑応答事例「株式移転における特定役員継続要件の判定」参照)。
これに対し、合併においては「合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること」とされており(法令4条の3④二)、株式交換・移転税制と合併税制の間で齟齬がある。
そこで平成28年度税制改正では、株式交換・移転税制においても、特定役員の“全て”が退任しない限り、特定役員継続要件を満たすこととする。この改正に伴い、上記質疑応答の内容は変更されることになろう。
| >税制改正大綱(74頁(1)①) |
| イ 共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。 ロ 適格株式交換等により親法人が取得する子法人株式の取得価額について、株主が50人以上である子法人の場合には、その子法人の直前の申告における簿価純資産価額にその後の資本金等の額等の増減を調整したものとする。 ハ その他適格要件について、所要の措置を講ずる。 |
簿価純資産価額算定に係る事務負担を軽減
次いでロは、事務負担軽減のために行われる改正である。
現行法上、適格株式交換・移転により親法人が取得する子法人株式の取得価額は、株主が50人以上である子法人の場合には、「株式交換等の“直前”の簿価純資産価額」でなければならないとされている(法令119条①九ロ、十一ロ)。しかし、株式交換等の直前の簿価純資産価額を計算するためには、仮決算をし、場合によっては時価評価が必要になるなど手間がかかることから、平成28年度税制改正では株式交換等の直前の簿価純資産価額ではなく、「子法人の直前の申告における簿価純資産価額」をベースに、資本金等の額、利益積立金額の出入りだけ調整すれば済むようにする。
株式交換完全親法人等の事業に関連しない事業は引継ぎ不要
「ハ その他適格要件について、所要の措置を講ずる。」には2つの改正が含まれている。1つが株式交換・移転後の“二次再編”における事業継続要件の明確化である。
株式交換や移転後に分割や合併などの“二次再編”が行われることがあるが、この場合に問題となるのが「事業継続要件」だ。
株式交換を例にとると、現行法人税法上、二次再編がない場合には「株式交換完全子法人の事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」との事業継続要件が設けられ(法令4条の3⑯四)、二次再編が行われる場合(当該株式交換後に適格合併等により子法人事業を移転することが見込まれている場合)には、「その移転する事業が移転後の法人において引き続き営まれ、かつ移転しない事業が子法人において引き続き営まれることが見込まれている」との要件が設けられている(同カッコ書き)。
この条文を見ると、二次再編のないケースでは「親法人事業と関連する事業」の継続とあるが、二次再編がある場合には「親法人事業と関連する」との限定がなく、「移転しない事業」も子法人において継続する見込みであることが求められていることから、実務では、「二次再編の場合は子法人の“すべての事業”を継続しなければならない」との解釈が存在している。
この点について平成28年度税制改正では、二次再編がある場合であっても、継続が求められるのはあくまで「株式交換完全親法人等に関連する事業」のみであることが明確にされる。
例えば、図1のように、株式交換完全親法人(以下、単に「親法人」)がA事業を営み、株式交換完全子法人(以下、単に「子法人」)が親法人のA事業に関連するa事業と、関連しないB事業を営んでおり、二次再編として、子法人のa事業の一部を分割して分割承継法人に承継させる一方、B事業はやめるものとする。
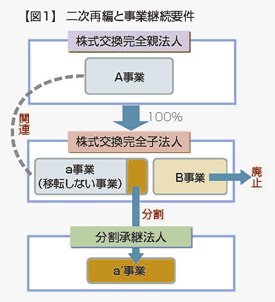
この場合、現在の「二次再編の場合は子法人の“すべての事業”を継続しなければならない」との解釈によると、子法人がB事業を継続しない以上、事業継続要件を満たさないこととなってしまう。
そこで平成28年度税制改正では、二次再編の場合であっても、あくまで株式交換完全親法人等と「関連する事業」のみが引き続き営まれることが見込まれる限り、事業継続要件を満たすことが明確にされる。図1の例では、子法人においてa事業の継続が見込まれている限り、B事業は継続が見込まれていなくても、事業継続要件は満たすことになる。
ただし、a事業が分割ができない事業である場合には、「移転しない事業(=株式交換完全子法人に残ったa事業)が子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」という要件は不要とする。すなわち、a事業を丸ごと承継させていたとしても、事業継続要件には抵触しないこととなる。
また、二次再編が適格合併である場合には、そもそも株式交換完全子法人等が消滅してしまうため、やはり「移転しない事業が子法人において引き続き営まれることが見込まれていること」との要件は不要とされる。
同様の改正は株式移転(法令4条の3⑳四)についても実施される。
株式移転後の支配関係、順次の適格合併直前までの継続で可
2つ目が、株式移転に係る支配関係継続要件について会社法との齟齬の解消を図るものだ。
現行法人税法上、株式移転後に、株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、株式移転完全親法人を合併法人とする適格合併が行われる場合の支配関係継続要件としては、株式移転完全親法人が、その適格合併の直前まで「株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の株式の“全部”を保有する関係が継続すること」が求められている(法令4条の3⑲一ロ・二ロ)。
一方、会社法上、吸収合併は「存続会社及び消滅会社の2社」により行われるものとされている。すなわち、上記のような3社合併であっても、2つの吸収合併が行われたものと取り扱われることになる(会社法2条二十七)。法人税法施行令4条の3が想定している「3社合併」という概念は会社法上は存在しない。
例えばA社を合併法人とし、B社とC社を被合併法人とする合併があった場合、会社法上はあくまでも「A社・B社の合併+A社・C社の合併」と考えることになる。ただ、そうなると法人税法上はA社・C社の合併の際にはA社はB社株式を保有していないことになり、支配関係継続要件を満たせない。
こうした中、平成28年度税制改正では、「順次行われる適格合併の直前まで」親法人と子法人の関係が継続されれば、支配関係継続要件を満たすことが明確にされる。
帰属主義踏まえ日本PEへの国内資産の現物出資も適格に
最後は適格現物出資の範囲見直しだ。こちらは税制改正大綱上「円滑・適正な納税のための環境整備」の1つとして実施される(与党の平成28年度税制改正大綱67頁(1))。
現物出資税制の改正は、平成26年度税制改正で、外国法人の事業所得に関する課税の基本的な考え方が「総合主義」から「帰属主義」に変更され、平成28年4月から実施されることに対応するもの。
現行制度上、内国法人が外国法人に対し、国内不動産など国内にある事業所に属する資産(25%以上を有する外国法人株式を除く)を移転した場合、当該移転は適格現物出資の対象から除かれている。しかし、帰属主義が導入されたことで、外国法人に対する現物出資であっても、現物出資される国内資産が日本のPEに帰属する限り、日本の課税権は失われない。そこで、日本のPEに対する国内資産の現物出資を適格対象に追加する(図2①)。
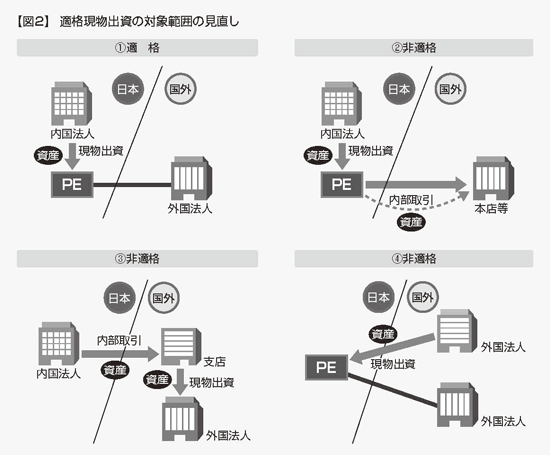
ただし、当該PEへの現物出資後、当該PEと国外の本店等との間で簿価で資産の内部取引が行われ、内部取引後に資産が国外で譲渡された場合、課税が困難となる恐れがある。そこで、「現物出資後に資産を内部取引により移転しないことが見込まれている場合」に限り、適格対象とする(図2②)。
また、内国法人が外国の支店等に国内資産を内部取引し、これがさらに外国法人(PEではない)に現物出資された場合、日本の課税権が失われることになる。そこで、内国法人が外国法人に対し「その現物出資の日前1年以内に内国法人の本店等から内部取引された国外事業所資産」を移転する現物出資を適格対象から除外する。(図2③参照。ただし、現金、預金、棚卸資産、有価証券を除く)。
このほか、現行制度では、外国法人が内国法人に対して国外にある事業所に属する資産(国内不動産を除く)の移転を行うケースは適格現物出資の対象外とされているが、帰属主義の実施を踏まえ、国外資産の含み損が日本に持ち込まれることによる課税上の弊害を防止するため、外国法人が他の外国法人の日本PEに対して国外事業所資産を現物出資する場合も、非適格現物出資とする(図2④参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















