解説記事2016年02月29日 【未公開裁決事例紹介】 役員退職給与の算定方法は平均功績倍率が最も合理的(2016年2月29日号・№632)
未公開裁決事例紹介
役員退職給与の算定方法は平均功績倍率が最も合理的
同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り
○役員退職慰労金規定に基づいて支給されたか否かにかかわらず、役員退職給与の額に不相当に高額な部分の金額がある場合には、法人税法34条(役員給与の損金不算入)2項の適用により、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないとされた事例(平成27年6月23日、棄却)。また、審判所は、役員退職給与の適正額を算定する平均功績倍率法は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法34条2項等の趣旨に最も合致する合理的な方法であると判断した。
基礎事実等
(1)事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、死亡退職した代表取締役に支給した役員退職給与を損金の額に算入したところ、原処分庁が、不相当に高額な部分の金額があり、当該金額については損金の額に算入されないとして法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、当該役員退職給与は相当な金額であるとして、その全部の取消しを求めた事案である。
(2)審査請求に至る経緯(略)
(3)関係法令の要旨(略)
(4)基礎事実 以下の事実は、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人の沿革等について (イ)請求人は、昭和27年9月29日に設立された同族会社である。
(ロ)××(以下「本件代表取締役」という。)は、昭和56年10月20日に請求人の取締役に、平成15年10月20日には請求人の代表取締役にそれぞれ就任したが、××に死亡退職した。
ロ 役員退職給与について (イ)平成21年7月1日に開催された請求人の臨時株主総会において、本件代表取締役に対する退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)として420,000,000円を支給する旨の決議がされた。
なお、請求人の役員退職慰労金規定(以下「本件退職慰労金規定」という。)に基づき、本件代表取締役の最終報酬月額2,400,000円(以下「本件最終報酬月額」という。)に役員在任期間27年(端数を切り上げた年数であり、以下「本件勤続年数」という。)、役員倍数5倍及び功労加算1.3倍をそれぞれ乗じた金額を基に本件役員退職給与の額は算定されている。
(ロ)請求人は、本件役員退職給与の額を損金の額に算入して本件事業年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」といい、本件確定申告に係る申告書を「本件確定申告書」という。)をした(以下、損金の額に算入した本件役員退職給与の額を「本件役員退職給与計上額」という。)。
ハ 原処分について 原処分庁は、本件役員退職給与について、法人税法施行令第70条第2号に規定する退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(以下「役員退職給与相当額」という。)を217,080,000円であると算定(以下、算定した額を「原処分庁算定額」という。)し、本件役員退職給与計上額のうち、原処分庁算定額を超える202,920,000円は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額に当たり、本件事業年度の法人税に係る所得の金額の計算上損金の額に算入できないとして、別表1(略)の「更正処分等」欄記載のとおり、本件更正処分等を行った。
争点および主張 本件の争点は、本件役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分として損金の額に算入されない金額があるか否かなど。当事者の主張は表のとおり。
審判所の判断
イ 法令等解釈 法人税法第34条第2項が、不相当に高額な役員退職給与の損金不算入を定めている趣旨は、法人の役員に対する退職給与が法人の利益処分たる性質を有することが多いことから、同項の規定を受けた法人税法施行令第70条第2号に規定する基準に照らして一般に相当と認められる金額に限り損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、実体に即した適正な課税を行うことにあると解される。
そして、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の規定に照らせば、法人が退職する役員に対して支出した役員退職給与の額が、その相当であると認められる金額を超え、「不相当に高額な部分の金額」を含むか否かを判断するためには、当該退職役員がその法人の業務に従事した期間及びその退職の事情を考慮するとともに、同業類似法人の役員に対する退職給与の支給の状況等と比較して検討するのが相当である。
ロ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係書類及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)請求人は、本件代表取締役に対し、報酬として、平成17年1月から平成18年9月まで月額2,000,000円、平成18年10月から平成19年10月まで月額2,200,000円、平成19年11月から平成20年10月まで月額2,400,000円を計上した。
(ロ)請求人は、本件代表取締役の報酬について、平成19年11月から平成20年10月まで定期同額給与を月額2,400,000円、事前確定届出給与を平成19年12月に7,200,000円(以下「本件賞与」という。)支給する旨の法人税法第34条第1項第2号に規定する届出書を平成19年10月22日に原処分庁に提出した。
なお、本件事業年度においては、役員に対する定期同額給与は支払われたものの、事前確定届出給与の支払はなかった。
(ハ)原処分庁は、イ(ロ)A(A)から(E)までの選定基準に基づき(編注:表1の原処分庁の主張を参照)、請求人の同業類似法人を別表2記載の順号AからEまでの5社を選定し(以下、選定された5社を「本件同業類似法人」という。)、これらの功績倍率の平均値3.35を本件同業類似法人の平均功績倍率とした。
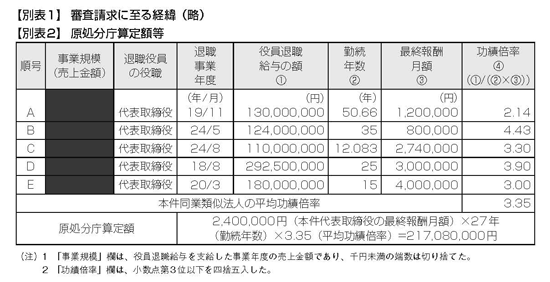
なお、原処分庁が金属製品製造業として選定した法人は、日本標準産業分類の分類項目表による「中分類24-金属製品製造業」に該当する業種を営む法人と同一である。
(ニ)原処分庁は、本件同業類似法人の平均功績倍率3.35に、本件最終報酬月額である2,400,000円及び本件勤続年数である27年を乗じて、原処分庁算定額(217,080,000円)を算定した。
ハ 当てはめ (イ)原処分庁算定額の算定方法等について
A 算定方法について
原処分庁は、上記ロ(ハ)及び(ニ)のとおり、本件役員退職給与相当額を算定するに当たり、平均功績倍率法を用いて算定した。そこで、まず、原処分庁が算定方法として平均功績倍率法を用いたことが合埋的であると認められるか否かを審理する。
役員退職給与相当額の具体的な算定方法としては、一般に、平均功績倍率法及び最高功績倍率法などがあり、平均功績倍率法は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて算定する方法であるところ、①最終報酬月額は、通常、当該退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえること、②勤続年数は、法人税法施行令第70条第2号が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当すること、③功績倍率は、役員退職給与額が当該退職役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じた金額に対し、いかなる倍率になっているかを示す数値であり、当該退職役員の法人に対する功績や法人の退職給与支払能力など、最終報酬月額及び勤続年数以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であるということができるところ、同業類似法人における功績倍率の平均値を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものといえることからすれば、このような最終報酬月額、勤続年数及び平均功績倍率を用いて役員退職給与の適正額を算定する平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法というべきである。
本件においては、上記ロ(イ)のとおり、本件代表取締役の報酬は、平成19年11月以降、月額2,400,000円であり、退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情があるとは認められないことからすれば、本件役員退職給与相当額の算定方法については、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法である平均功績倍率法により算定すべきである。
したがって、原処分庁が本件役員退職給与相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたことは合理的である。
B 同業類似法人の選定基準について
次に、原処分庁が本件同業類似法人を選定した基準が合理的であると認められるか否かを審理する。
(A)業種の類似性について
請求人の事業内容は、木工事用器材、仮設資材、安全金具の製造販売などであるところ、請求人が当審判所に提出するために、商品ごとにその売上金額を記載して順位を付けるなどしてまとめた書面(以下「本件売上明細書」という。)及び当審判所の調査の結果によれば、平成18年8月21日から平成19年8月20日までの事業年度(以下「平成19年8月期」という。)の最も大きな割合を占める活動は、金属製品製造販売であると認めることができ、本件事業年度においてもこれに反する証拠資料は見当たらないから、原処分庁が本件同業類似法人を日本標準産業分類の「中分類24-金属製品製造業」に該当する法人から選定したことは、合理的であるというべきである。
これに対し、請求人は、本件売上明細書によれば、平成19年8月期におけるリース及び販売商品のメンテナンス業の売上金額の総売上金額に占める割合が13.77%であるから、同業類似法人を金属製品製造業で抽出するのは合理的でない旨主張するが、同期において、金属製品製造販売が最も大きな割合を占める活動であったことは上記のとおりであるから、請求人の主張は上記判断を左右するものではない。
(B)事業規模の類似性について
売上金額を事業規模に係る選定基準の柱とし、売上金額が、請求人の本件事業年度の売上金額の2倍から半分、いわゆる倍半基準内にある法人を選定したことは、事業規模の類似性を担保しているから、合理的であるというべきである。
(C)地域の類似性について
同業類似法人の選定地域を××としたことについてみるに、請求人の納税地は××であるところ、経済事情の類似すると認められる同一県内に存する法人を対象としていることから、合理的であるというべきである。
(D)退職役員の役職及び退職事由の類似性について
退職事由が死亡である代表取締役に対する退職給与の支払があることを基準としているところ、基礎事実のとおり、本件代表取締役が、請求人の代表取締役であり、請求人を死亡退職したことからすれば、合理的であるというべきである。
C 小括
以上によれば、原処分庁が本件役員退職給与相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたこと、及び、本件同業類似法人の選定に当たっての選定基準は、いずれも合理的であるというべきである。そして、当審判所の調査の結果によっても、上記Bの選定基準によって選定された同業類似法人は、別表2記載の順号AからEの5社であったことから、原処分庁が請求人の同業類似法人を本件同業類似法人としたことは相当である。
D 請求人の主張について
(A)請求人は、本件役員退職給与は、本件退職慰労金規定に基づいて支給されたものであり、役員退職金を恣意的に大きくして租税回避を行ったものではないから、本件役員退職給与は全額損金の額に算入されるべきである旨主張する。
しかしながら、法人税法第34条第2項は、役員退職給与の額が同業類似法人の役員に対する退職給与の支給状況等に照らし、不相当に高額な部分については損金の額に算入しない旨の規定であり、役員退職給与が役員退職慰労金規定に基づいて支払われたか否かにかかわらず、その額に不相当に高額な部分がある場合には、同項の適用があるのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(B)請求人は、会社法は、役員賞与を役員報酬の一つとして位置付けているのであるから、本件役員退職給与相当額を平均功績倍率法により算定する際の最終報酬月額は、本件賞与を加味して算定するべきである旨主張する。
しかしながら、最終報酬月額は、通常、当該退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに、退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえるものであること、及び、上記ロ(ロ)のとおり、本件事業年度において、役員に対する事前確定届出給与(賞与)の支払はないことから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
(C)請求人は、平均功績倍率法の適用の前提を欠く本件においては、本件役員退職給与相当額を最高功績倍率法により算定するべきである旨主張する。
しかしながら、平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法であって、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分ではない場合、又は、その抽出件数が僅少であり、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人が極めて類似していると認められる場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って最高功績倍率法を適用すべきであるところ、本件において上記の特段の事情があると認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件役員退職給与相当額(審判所認定額)について
A 原処分庁は、原処分庁算定額を平均功績倍率法により算定しているが、本件代表取締役の勤続年数の取扱いについて、別表2の「勤続年数」欄記載のとおり、勤続年数の1年未満の端数処理に統一性が見られない。また、功績倍率の小数点以下の取扱いについては、小数点第3位以下を四捨五入して算定している。
これらに関して、当審判所は、勤続年数については、1年未満の端数は切り上げ、また、功績倍率の小数点以下については、小数点第3位以下を切り上げて算定するのが相当であると認める。
B そうすると、別表3記載のとおり、審判所認定の本件同業類似法人の平均功績倍率は3.26となり、これに本件最終報酬月額及び本件勤続年数を乗じた211,248,000円(以下、当該算定額を「審判所算定額」という。)が、本件役員退職給与相当額と認められる。
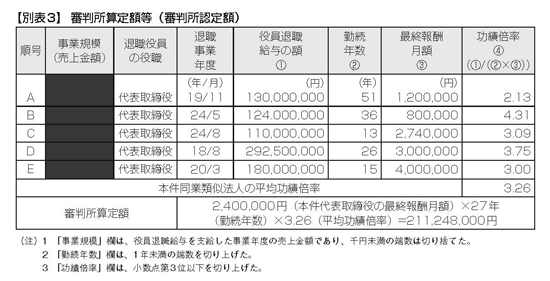
C よって、本件役員退職給与計上額(420,000,000円)のうち、審判所算定額(211,248,000円)を超える208,752,000円は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となる。
したがって、本件役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額がある。
本件更正処分について 本件役員退職給与計上額については、不相当に高額な部分の金額があり、当該不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないところ、当審判所で算定した損金の額に算入されない金額(208,752,000円)は、原処分における当該金額(202,920,000円)を上回るから、本件更正処分は適法である。
役員退職給与の算定方法は平均功績倍率が最も合理的
同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り
○役員退職慰労金規定に基づいて支給されたか否かにかかわらず、役員退職給与の額に不相当に高額な部分の金額がある場合には、法人税法34条(役員給与の損金不算入)2項の適用により、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないとされた事例(平成27年6月23日、棄却)。また、審判所は、役員退職給与の適正額を算定する平均功績倍率法は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法34条2項等の趣旨に最も合致する合理的な方法であると判断した。
基礎事実等
(1)事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、死亡退職した代表取締役に支給した役員退職給与を損金の額に算入したところ、原処分庁が、不相当に高額な部分の金額があり、当該金額については損金の額に算入されないとして法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、当該役員退職給与は相当な金額であるとして、その全部の取消しを求めた事案である。
(2)審査請求に至る経緯(略)
(3)関係法令の要旨(略)
(4)基礎事実 以下の事実は、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人の沿革等について (イ)請求人は、昭和27年9月29日に設立された同族会社である。
(ロ)××(以下「本件代表取締役」という。)は、昭和56年10月20日に請求人の取締役に、平成15年10月20日には請求人の代表取締役にそれぞれ就任したが、××に死亡退職した。
ロ 役員退職給与について (イ)平成21年7月1日に開催された請求人の臨時株主総会において、本件代表取締役に対する退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)として420,000,000円を支給する旨の決議がされた。
なお、請求人の役員退職慰労金規定(以下「本件退職慰労金規定」という。)に基づき、本件代表取締役の最終報酬月額2,400,000円(以下「本件最終報酬月額」という。)に役員在任期間27年(端数を切り上げた年数であり、以下「本件勤続年数」という。)、役員倍数5倍及び功労加算1.3倍をそれぞれ乗じた金額を基に本件役員退職給与の額は算定されている。
(ロ)請求人は、本件役員退職給与の額を損金の額に算入して本件事業年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」といい、本件確定申告に係る申告書を「本件確定申告書」という。)をした(以下、損金の額に算入した本件役員退職給与の額を「本件役員退職給与計上額」という。)。
ハ 原処分について 原処分庁は、本件役員退職給与について、法人税法施行令第70条第2号に規定する退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(以下「役員退職給与相当額」という。)を217,080,000円であると算定(以下、算定した額を「原処分庁算定額」という。)し、本件役員退職給与計上額のうち、原処分庁算定額を超える202,920,000円は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額に当たり、本件事業年度の法人税に係る所得の金額の計算上損金の額に算入できないとして、別表1(略)の「更正処分等」欄記載のとおり、本件更正処分等を行った。
争点および主張 本件の争点は、本件役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分として損金の額に算入されない金額があるか否かなど。当事者の主張は表のとおり。
| 【表1】役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分として損金の額に算入されない金額があるか否か |
| 原処分庁 | 請 求 人 |
| (イ)役員退職給与相当額の算定方法については、退職役員に退職給与を支給した当該法人と同種の事業を営み、その事業規模が類似する法人(以下「同業類似法人」という。)の役員に対する退職給与の支給の状況を平均功績倍率(役員退職給与の額を、最終報酬月額に勤続年数を乗じた金額で除して算出したいわゆる功績倍率の平均値をいう。)として把握し、同業類似法人の平均功績倍率に当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて算定する平均功績倍率法を用いるのが合理的である。 (ロ)平均功績倍率法を用いて算定すると、本件役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分がある。 なお、原処分庁算定額は、次のとおり合理的に算定している。 A 請求人の同業類似法人は、次のとおり合理的な基準により選定している。 (A)金属製品製造業を主として営む法人であること。 (B)役員退職給与を支給した事業年度の売上金額が、請求人の本件事業年度の売上金額の2分の1から2倍の範囲内の法人であること。 (C)××の各税務署の管轄内に納税地を有する法人であること。 (D)代表取締役に対する役員退職給与を支給した法人であること。 (E)死亡を退職事由とする役員退職給与を支給した法人であること。 B 役員の最終報酬月額は、退職間際に当該役員の報酬が大幅に引き下げられたなどの特段の事情がない限り、役員在職中における法人に対する功績を最もよく反映したものであると解されるから、本件最終報酬月額に賞与の額を加味する必要はない。 (ハ)最高功績倍率法を用いる場合とは、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合や、抽出できる法人が僅少、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人とが極めて類似している場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特殊な場合に限られるものであり、本件において、最高功績倍率法を用いる必要があると認めるに足りる事情があるとは認められない。 | (イ)法人税法第34条第2項が、法人の役員報酬のうち不相当に高額な部分についてその法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととしていることの趣旨は、役員報酬が役務の対価として企業会計上は損金の額に算入されるべきものであるところ、法人によっては実際は賞与に当たるものを報酬の名目で役員に給付する傾向があるため、そのような隠れた利益処分に対処し、課税の公平を確保しようとするところにある。 本件役員退職給与は、従前から定められた本件退職慰労金規定に基づいて支給されたものであり、役員退職金の支払を恣意的に大きくして、損金とすることで利益を減少させ実質的な租税回避を行ったものではないことから、本件役員退職給与は、全額損金の額に算入されるべきである。 したがって、本件役員退職給与計上額に不相当に高額な部分はない。 (ロ)本件役員退職給与計上額に不相当に高額な部分があったとしても、原処分庁算定額は、次の理由から適正な額とはいえない。 A 原処分庁は、同業類似法人の選定に当たり、次の事情を適切に反映していない。 (A)請求人は、金属製品製造業のほかに、リースや販売商品のメンテナンス業についても相応の売上げを有しており、事業内容について金属製品製造業を基準とするのは合理的ではない。 (B)役員退職慰労金規定の有無を考慮していない。 (C)請求人は、木工事用器材などの製造販売及び仮設資材のリースなど多様な事業を営んでいることや、卸先も、インターネットで世界的に受注するようになってきていることから、××に納税地を有する法人だけを対象とするのは合理的ではない。 (D)本件代表取締役の功績と同等の功績のある法人を基準としていない。 B 会社法は、役員賞与を役員報酬の一つとして位置付けているのであるから、本件代表取締役に対する退職給与として相当であると認められる金額(以下「本件役員退職給与相当額」という。)を平均功績倍率法により算定する際の最終報酬月額は、賞与を加味して算定するべきである。 (ハ)本件最終報酬月額が本件代表取締役の功績を適正に評価した金額ではなく、同業類似法人の抽出基準が合理的ではない本件においては、平均功績倍率法の適用の前提を欠くので、本件役員退職給与相当額は最高功績倍率法により算定するべきである。 |
審判所の判断
イ 法令等解釈 法人税法第34条第2項が、不相当に高額な役員退職給与の損金不算入を定めている趣旨は、法人の役員に対する退職給与が法人の利益処分たる性質を有することが多いことから、同項の規定を受けた法人税法施行令第70条第2号に規定する基準に照らして一般に相当と認められる金額に限り損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、実体に即した適正な課税を行うことにあると解される。
そして、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の規定に照らせば、法人が退職する役員に対して支出した役員退職給与の額が、その相当であると認められる金額を超え、「不相当に高額な部分の金額」を含むか否かを判断するためには、当該退職役員がその法人の業務に従事した期間及びその退職の事情を考慮するとともに、同業類似法人の役員に対する退職給与の支給の状況等と比較して検討するのが相当である。
ロ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係書類及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)請求人は、本件代表取締役に対し、報酬として、平成17年1月から平成18年9月まで月額2,000,000円、平成18年10月から平成19年10月まで月額2,200,000円、平成19年11月から平成20年10月まで月額2,400,000円を計上した。
(ロ)請求人は、本件代表取締役の報酬について、平成19年11月から平成20年10月まで定期同額給与を月額2,400,000円、事前確定届出給与を平成19年12月に7,200,000円(以下「本件賞与」という。)支給する旨の法人税法第34条第1項第2号に規定する届出書を平成19年10月22日に原処分庁に提出した。
なお、本件事業年度においては、役員に対する定期同額給与は支払われたものの、事前確定届出給与の支払はなかった。
(ハ)原処分庁は、イ(ロ)A(A)から(E)までの選定基準に基づき(編注:表1の原処分庁の主張を参照)、請求人の同業類似法人を別表2記載の順号AからEまでの5社を選定し(以下、選定された5社を「本件同業類似法人」という。)、これらの功績倍率の平均値3.35を本件同業類似法人の平均功績倍率とした。
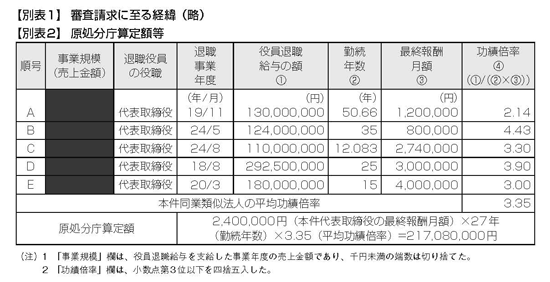
なお、原処分庁が金属製品製造業として選定した法人は、日本標準産業分類の分類項目表による「中分類24-金属製品製造業」に該当する業種を営む法人と同一である。
(ニ)原処分庁は、本件同業類似法人の平均功績倍率3.35に、本件最終報酬月額である2,400,000円及び本件勤続年数である27年を乗じて、原処分庁算定額(217,080,000円)を算定した。
ハ 当てはめ (イ)原処分庁算定額の算定方法等について
A 算定方法について
原処分庁は、上記ロ(ハ)及び(ニ)のとおり、本件役員退職給与相当額を算定するに当たり、平均功績倍率法を用いて算定した。そこで、まず、原処分庁が算定方法として平均功績倍率法を用いたことが合埋的であると認められるか否かを審理する。
役員退職給与相当額の具体的な算定方法としては、一般に、平均功績倍率法及び最高功績倍率法などがあり、平均功績倍率法は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて算定する方法であるところ、①最終報酬月額は、通常、当該退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえること、②勤続年数は、法人税法施行令第70条第2号が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当すること、③功績倍率は、役員退職給与額が当該退職役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じた金額に対し、いかなる倍率になっているかを示す数値であり、当該退職役員の法人に対する功績や法人の退職給与支払能力など、最終報酬月額及び勤続年数以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であるということができるところ、同業類似法人における功績倍率の平均値を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものといえることからすれば、このような最終報酬月額、勤続年数及び平均功績倍率を用いて役員退職給与の適正額を算定する平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法というべきである。
本件においては、上記ロ(イ)のとおり、本件代表取締役の報酬は、平成19年11月以降、月額2,400,000円であり、退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情があるとは認められないことからすれば、本件役員退職給与相当額の算定方法については、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法である平均功績倍率法により算定すべきである。
したがって、原処分庁が本件役員退職給与相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたことは合理的である。
B 同業類似法人の選定基準について
次に、原処分庁が本件同業類似法人を選定した基準が合理的であると認められるか否かを審理する。
(A)業種の類似性について
請求人の事業内容は、木工事用器材、仮設資材、安全金具の製造販売などであるところ、請求人が当審判所に提出するために、商品ごとにその売上金額を記載して順位を付けるなどしてまとめた書面(以下「本件売上明細書」という。)及び当審判所の調査の結果によれば、平成18年8月21日から平成19年8月20日までの事業年度(以下「平成19年8月期」という。)の最も大きな割合を占める活動は、金属製品製造販売であると認めることができ、本件事業年度においてもこれに反する証拠資料は見当たらないから、原処分庁が本件同業類似法人を日本標準産業分類の「中分類24-金属製品製造業」に該当する法人から選定したことは、合理的であるというべきである。
これに対し、請求人は、本件売上明細書によれば、平成19年8月期におけるリース及び販売商品のメンテナンス業の売上金額の総売上金額に占める割合が13.77%であるから、同業類似法人を金属製品製造業で抽出するのは合理的でない旨主張するが、同期において、金属製品製造販売が最も大きな割合を占める活動であったことは上記のとおりであるから、請求人の主張は上記判断を左右するものではない。
(B)事業規模の類似性について
売上金額を事業規模に係る選定基準の柱とし、売上金額が、請求人の本件事業年度の売上金額の2倍から半分、いわゆる倍半基準内にある法人を選定したことは、事業規模の類似性を担保しているから、合理的であるというべきである。
(C)地域の類似性について
同業類似法人の選定地域を××としたことについてみるに、請求人の納税地は××であるところ、経済事情の類似すると認められる同一県内に存する法人を対象としていることから、合理的であるというべきである。
(D)退職役員の役職及び退職事由の類似性について
退職事由が死亡である代表取締役に対する退職給与の支払があることを基準としているところ、基礎事実のとおり、本件代表取締役が、請求人の代表取締役であり、請求人を死亡退職したことからすれば、合理的であるというべきである。
C 小括
以上によれば、原処分庁が本件役員退職給与相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたこと、及び、本件同業類似法人の選定に当たっての選定基準は、いずれも合理的であるというべきである。そして、当審判所の調査の結果によっても、上記Bの選定基準によって選定された同業類似法人は、別表2記載の順号AからEの5社であったことから、原処分庁が請求人の同業類似法人を本件同業類似法人としたことは相当である。
D 請求人の主張について
(A)請求人は、本件役員退職給与は、本件退職慰労金規定に基づいて支給されたものであり、役員退職金を恣意的に大きくして租税回避を行ったものではないから、本件役員退職給与は全額損金の額に算入されるべきである旨主張する。
しかしながら、法人税法第34条第2項は、役員退職給与の額が同業類似法人の役員に対する退職給与の支給状況等に照らし、不相当に高額な部分については損金の額に算入しない旨の規定であり、役員退職給与が役員退職慰労金規定に基づいて支払われたか否かにかかわらず、その額に不相当に高額な部分がある場合には、同項の適用があるのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(B)請求人は、会社法は、役員賞与を役員報酬の一つとして位置付けているのであるから、本件役員退職給与相当額を平均功績倍率法により算定する際の最終報酬月額は、本件賞与を加味して算定するべきである旨主張する。
しかしながら、最終報酬月額は、通常、当該退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに、退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえるものであること、及び、上記ロ(ロ)のとおり、本件事業年度において、役員に対する事前確定届出給与(賞与)の支払はないことから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
(C)請求人は、平均功績倍率法の適用の前提を欠く本件においては、本件役員退職給与相当額を最高功績倍率法により算定するべきである旨主張する。
しかしながら、平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法であって、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分ではない場合、又は、その抽出件数が僅少であり、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人が極めて類似していると認められる場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って最高功績倍率法を適用すべきであるところ、本件において上記の特段の事情があると認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件役員退職給与相当額(審判所認定額)について
A 原処分庁は、原処分庁算定額を平均功績倍率法により算定しているが、本件代表取締役の勤続年数の取扱いについて、別表2の「勤続年数」欄記載のとおり、勤続年数の1年未満の端数処理に統一性が見られない。また、功績倍率の小数点以下の取扱いについては、小数点第3位以下を四捨五入して算定している。
これらに関して、当審判所は、勤続年数については、1年未満の端数は切り上げ、また、功績倍率の小数点以下については、小数点第3位以下を切り上げて算定するのが相当であると認める。
B そうすると、別表3記載のとおり、審判所認定の本件同業類似法人の平均功績倍率は3.26となり、これに本件最終報酬月額及び本件勤続年数を乗じた211,248,000円(以下、当該算定額を「審判所算定額」という。)が、本件役員退職給与相当額と認められる。
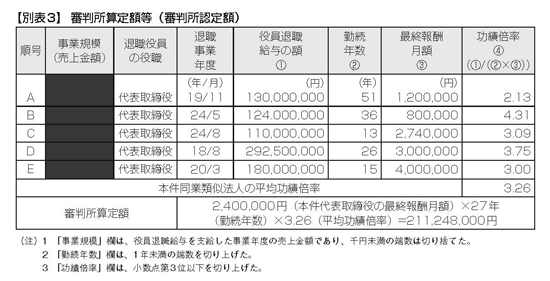
C よって、本件役員退職給与計上額(420,000,000円)のうち、審判所算定額(211,248,000円)を超える208,752,000円は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となる。
したがって、本件役員退職給与計上額には、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額がある。
本件更正処分について 本件役員退職給与計上額については、不相当に高額な部分の金額があり、当該不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないところ、当審判所で算定した損金の額に算入されない金額(208,752,000円)は、原処分における当該金額(202,920,000円)を上回るから、本件更正処分は適法である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















