解説記事2016年03月28日 【新会計基準解説】 「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表(2016年3月28日号・№636)
新会計基準解説
「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表 企業会計基準委員会 専門研究員 島田謡子
企業会計基準委員会 研究員 桑井瑞樹
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成28年2月4日に、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(以下「本意見募集文書」という。)を公表した(脚注1)(コメント期限は平成28年5月31日である。)。本稿では、本意見募集文書の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 公表の経緯
我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていない。このような状況の中、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606(脚注2))を公表している。
これらの状況を踏まえ、当委員会は、平成27年3月20日に開催された第308回企業会計基準委員会において、IFRS第15号を踏まえた我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定した(「Ⅲ.収益認識に関する包括的な会計基準を開発する意義」を参照)。
当委員会では、収益認識に関する包括的な会計基準の開発にあたって、IFRS第15号の内容を出発点として検討を開始しているが(「Ⅳ.開発する会計基準の内容」を参照)、これにより、財務諸表作成者に適用上の課題が生じることも想定される。当委員会ではこうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として連結財務諸表及び個別財務諸表に導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するために、本意見募集文書を公表することとした。
Ⅲ 収益認識に関する包括的な会計基準を開発する意義
当委員会は、IFRS第15号を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行うことには、次のような意義があると考えている。
・我が国の会計基準の体系の整備
我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発は、会計基準の体系の整備につながり、我が国の会計基準の高品質化に寄与すると考えられる。
・企業間の財務諸表の比較可能性の向上
我が国の会計基準の体系において包括的な会計基準を開発することにより、我が国の企業間の財務諸表の比較可能性が向上することが期待される。また、IFRS第15号は、Topic 606と文言レベルで概ね同一の基準であること、業種横断的で多様な取引に統一的に適用されるものであることから、同基準に準拠して財務情報が作成された場合、国際的な比較可能性が改善することも期待される。
・開示情報の充実
新たに開示(注記事項)の定めを設けることにより、我が国の企業の財務諸表における財務情報の質が向上することが期待される。また、IFRS第15号では開示情報が大幅に拡充されており、同基準に準拠して財務情報が作成された場合、財務諸表利用者の情報ニーズにより応えるものとなると期待される。
一方で、IFRS第15号における開示要求は、コストが便益に見合わないとの意見も聞かれており、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発において定める開示(注記事項)の具体的な内容については、個別に慎重な検討が必要になると考えられる。
Ⅳ 開発する会計基準の内容
収益認識に関する包括的な会計基準については、次の観点からIFRS第15号の内容を出発点として検討を始めている。
・IFRS第15号とTopic 606は概ね文言レベルで同一なものとなっており、IFRS第15号の内容を出発点としない場合、国際的な整合性を図ることが困難となること
・IFRS第15号は5つのステップにより収益を認識するという特徴を有しており、出発点としては、その体系を評価する必要があると考えられること
・連結財務諸表の作成にあたって指定国際会計基準や米国会計基準を適用する企業について、個別財務諸表においても同様の内容の基準を用いることのニーズが聞かれること
今後開発する会計基準の内容や文言について、IFRS第15号との間でどの程度整合性を図るべきか等については、本意見募集文書に寄せられた適用上の課題の内容等を踏まえた上で検討を行う予定である(脚注3)。
なお、IFRSでは、重要性について、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」において包括的に記述されており、各会計基準において重要性に関する特段の定めは原則として設けられていない。一方、我が国の会計基準では、個々の基準において、必要に応じて重要性に関する定めが設けられてきた。このため、今後、収益認識に関する包括的な会計基準の開発にあたって、重要性に関する定めを設けるべきか否かについても、検討にあたっての論点になり得るものと考えられる。
Ⅴ 会計基準の開発に関する当面の目標時期
当委員会では、本意見募集文書に寄せられた意見を踏まえ、収益認識に関する包括的な会計基準の案の策定に向けた検討を行う予定である。その開発にあたり、公開草案公表前に、検討状況について何らかの形式(脚注4)で一般に意見を求めることも考えられるが、この点については、本意見募集文書に寄せられた内容等を踏まえた上で検討を行う予定である。
収益認識に関する包括的な会計基準の最終的な基準化の時期について、当委員会におけるこれまでの審議の過程では、我が国における収益認識基準の開発は、広範な業種や企業に重要な影響を与える可能性があるため、慎重に進めるべきとの意見も聞かれている一方で、指定国際会計基準を任意適用する企業や米国会計基準を利用する企業から、IFRS第15号及びTopic 606の強制適用日と整合させるべきとの意見も聞かれている。当委員会では、これらの意見を踏まえて、IFRS第15号及びTopic 606の強制適用日(IFRS第15号においては平成30年1月1日以後開始する事業年度、Topic 606においては平成29年12月15日より後に開始する事業年度)に適用が可能となることを当面の目標としている。
Ⅵ 本意見募集文書の質問事項
本意見募集文書では、次の質問項目を設けている。
質問1 回答者の属性 ・どのような立場(財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人、学識経験者等)で質問にご回答いただいているか。
質問2 検討の進め方に対するご意見 ・「Ⅳ.開発する会計基準の内容」に記載した理由によりIFRS第15号の内容を出発点として検討を行っているが、その進め方に関するご意見を頂きたい。
・質問項目には記載されていないが、開発する会計基準の内容や文言について、IFRS第15号との間でどの程度整合性を図るべきかについてのご意見を記載頂くことも考えられる。
質問3 予備的に識別した論点に対するご意見 ・当委員会では、予備的に17個の論点を識別しているが、「予備的に識別した適用上の課題」、「影響を受けると考えられる取引例」の記載内容は適切か否かについて、ご意見を頂きたい。
質問4 その他の論点の照会 ・17個の論点以外の適用上の課題を識別している場合には、可能な限り詳細に、その内容をお教え頂きたい。
質問5 開示(注記事項)に対するご意見 ・IFRS第15号の開示(注記事項)規定について、どの程度、我が国の会計基準において取り入れるかについては、便益とコストについて十分に分析を行う必要がある。その観点で、以下の意見を頂きたい。
>IFRS第15号の注記事項の中で、特に収益の分析において有用と考えられる注記事項
>IFRS第15号の注記の中で、実務上のコスト負担の観点から、注記事項として取り入れることに懸念があるもの
Ⅶ IFRS第15号の概要
本意見募集文書では、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを、我が国の収益認識に関する包括的な会計基準として連結及び個別財務諸表に導入した場合に重要な影響を受ける可能性があると、当委員会で予備的に識別した論点を記載している。
したがって、まずは、IFRS第15号の概要について説明する。
1 基本原則と5つのステップ IFRS第15号の基本原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で描写するように、企業が収益を認識することである。IFRS第15号では、この原則を達成するために、【図表1】のステップに従って収益を認識する。
以下、【図表1】の5つのステップを簡単な取引例を用いて説明する。
以下の【図表2】は、この取引例に5つのステップを当てはめた場合のフローを示している。
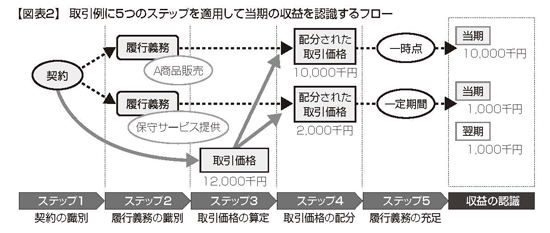
Ⅷ 当委員会が予備的に識別している適用上の論点
本意見募集文書は、公表の経緯及び質問事項等と、それに続く「第1部 IFRS第15号に関して予備的に識別している適用上の課題」(以下「第1部」という。)及び「第2部 IFRS第15号の概要」(以下「第2部」という。)で構成されている。
第1部では、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを、我が国の収益認識に関する包括的な会計基準として連結財務諸表及び個別財務諸表に導入した場合の論点を予備的に識別した上で、適用上の課題の分析を行っている(脚注5)。第2部は、第1部の理解に資するよう、IFRS第15号の規定の概要について記載している。
以下では、本章意見文書の第1部で示した各論点(【図表3】参照)のうち、重要な影響を及ぼすと考えられる(※)を付した論点について、(1)IFRS第15号での取扱い、(2)財務報告数値の相違、(3)予備的に識別した適用上の課題、(4)影響を受けると考えられる取引例の概要を項目ごとに説明する。また、開示についても「Ⅸ.1.IFRS第15号における主な開示項目」及び、「Ⅸ.2.予備的に識別した適用上の課題」について記載している。
1 【論点1】契約の結合(ステップ1)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、同一の顧客(又は顧客の関連当事者)と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約が次のいずれかに該当する場合、契約を結合して「単一の契約」とすることとされている(第17項(脚注6))。
・契約が単一の商業的な目的を有するパッケージとして交渉されている。
・1つの契約で支払われる対価の金額が、他の契約の価格又は履行に左右される。
・複数の契約で約束した財又はサービス(あるいは各契約で約束した財又はサービスの一部)が、【論点3】で検討する履行義務の識別の要件に照らして、単一の履行義務であると判断される。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約会計基準の定めを除き、複数の契約の結合に関する一般的な定めはない。通常は、個々の契約が収益認識の基本的な単位になると考えられるが、契約内容を勘案して別の単位で収益を認識することもあると考えられる。IFRS第15号において複数の契約が「単一の契約」とされた場合、それを基に【論点3】等のプロセスを通じて収益を認識する単位やその単位に配分される金額が決められる。その結果、日本基準の実務において個々の契約を収益認識の単位としている場合、単位の違い又は単位は同じでも各単位への配分金額の違いにより、収益を認識する時期や、1期間に認識する金額が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・複数の契約を「単一の契約」に結合するか否かを判断する際に、結合すべき契約の範囲の決定が困難な場合があり、その判断のための業務プロセスの変更を伴う可能性があると考えられる。
・会計システム上、契約単位で収益認識の処理を行っている場合、複数の契約を「単一の契約」とみなして処理できるようにシステム改修を行う必要が生じる可能性がある。
・IFRS第15号において複数の契約が「単一の契約」とされた場合、日本基準の実務において個々の契約を収益認識の単位としている場合と比べて、収益の金額や利益率が変動する可能性があり、社内の業績管理の方法に変更が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 同一の顧客と同時又はほぼ同時に複数の契約を締結する取引(例:汎用ソフトウェアを顧客仕様にカスタマイズして提供する場合にソフトウェア本体の利用権の提供とカスタマイズの契約を分けている場合や、ソフトウェアの受注制作において開発工程ごとに契約を分けている場合)に影響が生じる可能性があると考えられる。
2 【論点2】契約の変更(ステップ1)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約の変更は、【図表4】のように会計処理することとされている。
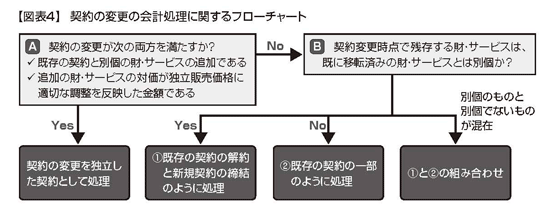
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約や受注制作のソフトウェアを除き、契約の変更に関する一般的な定めはなく、個々の契約の変更の内容を勘案して会計処理が行われていると考えられ、日本基準の実務とIFRS第15号とで、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・契約の変更の内容が様々であることから、【図表4】(B)のように、既存の契約自体の変更と判断されるか否かについては、判断が困難な場合があると考えられる。
・契約の変更が頻繁に行われるような業種では、会計処理の負担が大きくなる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 提供する財又はサービスの内容や価格の変更が生じる取引(例:建設、ソフトウェアの開発や設備等の長期の受注製作、電気通信契約)が影響を受けると考えられる。
3 【論点3】約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約に複数の財又はサービスが含まれており、契約に含まれる財又はサービスが、同じ契約内の別の財又はサービスと別個のものである場合には、独立した履行義務(収益認識の単位)として識別し、区分して会計処理することとされている。「別個のもの」とは、具体的には、当該財又はサービスについて次の要件の両方に該当する場合であるとされている(第27項)。
・個々の財又はサービスのレベルでの区分可能性
顧客がその財又はサービスからの便益を、それ単独で(又は顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて)得ることができる(第27項(a))。
・契約の観点からの区分可能性
財又はサービスを顧客に移転する約束が、同一契約内の他の約束と区分して識別できる(第27項(b))。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約とソフトウェア取引以外では取引を分割することは明示的に求められていない。工事契約等については、認識の単位として、契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づくとされており、実質的な取引の単位を反映するように契約書上の取引を分割することが必要となる場合があるとされている(脚注7)。また、ソフトウェアの複合取引については、収益認識時点が異なる複数の取引が1つの契約とされていても、財又はサービスの内容や各々の金額の内訳が顧客との間で明らかにされている場合には、契約上の対価を適切に分解するとされており、また、内訳金額が明らかでない場合でも、管理上の適切な区分に基づき分解することができるとされている(脚注8)。
ただし、工事契約とソフトウェア取引についてもIFRS第15号で定められている履行義務の識別と同一の方法で分割することが求められているわけではないため、IFRS第15号とで会計処理の単位が異なる場合には、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・履行義務の識別に関する2つの要件の判断が困難である可能性がある。また、判断を要する取引の形態が多様である場合、実務負担が大きくなる可能性がある。
・日本基準の実務よりも収益の認識単位が増加する場合、契約情報(例:オーダー番号)をさらに細分化して登録するなど、システム対応が必要となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 商品等の提供とその後の一定期間にわたる付随的サービスの提供が1つの契約に含まれる取引等の、収益の認識時点が異なる複数の財又はサービスを一体で提供する取引(例:機械の販売と据付サービスや保守サービス、ソフトウェア開発とその後のサポート・サービス)に影響が生じる可能性がある。
4 【論点4】追加的な財又はサービスに対する顧客のオプション(ポイント制度等)(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、商品やサービスの提供に付随して付与されるポイントは、追加的な財又はサービスを無料又は値引価格で取得する顧客のオプションとして取り扱うこととされている。当該オプションには販売インセンティブ、顧客特典クレジット(又はポイント)、契約更新オプションあるいは将来の財又はサービスに係るその他の値引き等が含まれる(B39項)。
このようなオプションについて、当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供する場合(例えば、当該財又はサービスについて、その地域又は市場において同じ客層に通常与えられる範囲を超える値引きを提供する場合)、顧客の支払は実質的に将来の財又はサービスに対するものとして取り扱い(すなわち、別の履行義務とする。)、以下の会計処理を行うこととされている(【図表5】参照)(B40項)。
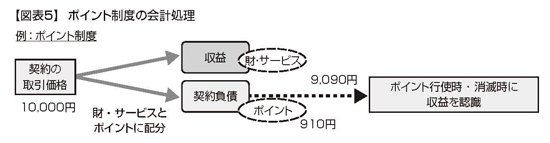
・契約の取引価格全体を、独立販売価格に基づいて、オプション付与時に当初提供した財又はサービスとオプション部分に配分する。
・オプション部分を契約負債として繰り延べる。
・将来の財又はサービスの移転時又は当該オプションの消滅時に収益を認識する。
(2)財務報告数値の相違 IFRS第15号のもとでは、追加的な財又はサービスに対する顧客のオプションについて、オプションに対応する収益を繰り延べる。日本基準の実務では、ポイントについては、一般的に、顧客への商品の販売時又はサービスの提供時にそれらの価格により一括して収益認識し、将来のポイントとの交換に要すると見込まれる金額(販売価格のケースもあれば原価のケースもある)を引当金として費用を計上する実務が多いと考えられるため、収益を認識する時期及び一定期間内に認識される収益の金額が異なる可能性がある。また、日本基準の実務において企業が負担する原価を基礎として引当金を計算している場合、IFRS第15号により繰り延べる収益の金額との相違が大きくなる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 我が国のポイント制度については、複数企業による相互利用や制度間の交換、電子マネーへの交換等複雑化しており、企業が関係するポイント制度に関する取引を詳細に分析した上で、IFRS第15号に従って会計処理するために業務プロセスの再構築(システム改修を伴うことがある。)を行う負担が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業が顧客に財又はサービスを提供する際に、付随して追加的な財又はサービスに対するオプションを提供する取引(例:商品の販売やサービスの提供に伴いポイントを付与する取引)が影響を受ける可能性がある。
5 【論点5】知的財産ライセンスの供与(ステップ2及びステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、ライセンス供与について、顧客が権利を有する知的財産が企業の活動により著しく影響を受けるかどうかにより、ライセンス供与の性質(知的財産にアクセスする権利か、ライセンスを使用する権利か)を判断し、収益の認識時期を決定することとされている(【図表6】参照)(B56項)。
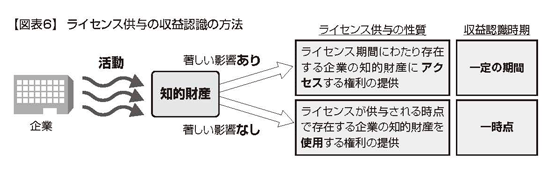
ライセンス供与について「企業の知的財産にアクセスする権利」に該当するのは次のすべての要件を満たす場合である(B58項)。
① 顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行うことが、契約上要求されているか又は顧客により合理的に期待されている。
② ライセンスによって供与される権利に基づき、顧客が①で識別された企業の活動によって直接的に影響を受ける。
③ 上記のように企業が活動しても、当該活動が生じるにつれて顧客に財又はサービスが移転することがない。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、知的財産ライセンスに関する一般的な定めはなく、日本基準の実務とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・ライセンス供与後に企業が行う活動が、顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動であるかどうかの判定が困難である可能性がある。
・単一の履行義務として識別されたライセンス契約に他の付随サービスが含まれる場合、いずれの性質をより重視して収益認識時点を判断すべきかが困難である可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 顧客に知的財産のライセンスを供与する取引(例:特許権の使用許諾、一定地域における独占販売権を与えるライセンス取引、メディア・コンテンツやフランチャイズ権のライセンス、ソフトウェアのライセンス及び医薬品業界の導出取引)が影響を受ける可能性があると考えられる。
6 【論点6】変動対価(売上等に応じて変動するリベート、仮価格等)(ステップ3)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約上の対価に変動性がある場合(変動対価)、期待値(確率で加重平均した金額)又は最頻値(最も可能性の高い金額)のうち、より対価を適切に予測できる方法によりその金額を見積ることとされている(第50項及び第53項)。ただし、取引価格に含められる金額(すなわち、収益金額)は、事後に重大な収益金額の戻入れ(減額)が生じない可能性が非常に高い範囲に制限されている(変動対価の制限)(第56項)。変動対価が含まれる可能性のある取引としては、値引き、リベート、返金、クレジット、インセンティブ、業績ボーナス、ペナルティー等が例示されている(第51項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準の実務では、支払の可能性が高いと判断された時点で売上リベートを認識するケースや、仮価格について、顧客との交渉状況に応じて収益金額の見直しを行うケースがあると考えられる。IFRS第15号において、売上リベートの見積りや仮価格の精算見込みの影響をより早い時点(履行義務の充足時)に反映させると判断される場合、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・売上リベートについて、リベート支払の条件達成の判断が困難となる可能性がある(特に、書面の契約ではなく、商慣習等による場合)。ただし、実務上、困難が生じるのは、期末又は四半期末までに条件を達成したか否かが確定しない場合であると考えられる。
・仮価格について、最終価格をどのように見積るかの判断が困難となる可能性がある。ただし、実務上、困難が生じるのは、期末又は四半期末までに価格が決定されない場合であると考えられる。
・「変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲」を見積ることが求められるが、重大な戻入れが生じない可能性について、判断が困難となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 契約上、又は業界の慣行として商品受渡後の価格調整が行われる取引が影響を受ける可能性がある。また、売上に関連して企業から顧客に何らかの対価を支払う場合、その対価に変動要素がある取引にも影響がある可能性がある。
具体的には、多くの業種において行われている仮価格による取引、販売数量や業績達成に応じたインセンティブを付すリベート等が生じる取引、及び販売店が消費者に対して行う値引きについて、メーカーがその値引きの一部を負担する取引等が影響を受ける可能性がある。
7 【論点7】返品権付き販売(ステップ3)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、返品権付きの商品(及び条件付きで返金が認められるサービス)について、販売した商品等のうち返品が見込まれる部分については収益を認識しないこととされている。受け取った(又は受け取ることのできる)金額のうち、返品が見込まれる部分は返金負債として計上するとともに、当該返金に関して、顧客から商品を回収する権利(すなわち、将来返品を受け入れることが見込まれる商品)については資産として計上する(B21項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準の実務では、販売時に対価の全額が収益として認識した上で、過去の返品実績等に基づき返品調整引当金を計上(引当金の繰入額については、売上総利益の調整として表示)する例が多く見られるため、IFRS第15号を採用した場合に、収益を認識する時期が異なる可能性がある(【図表7】参照)。
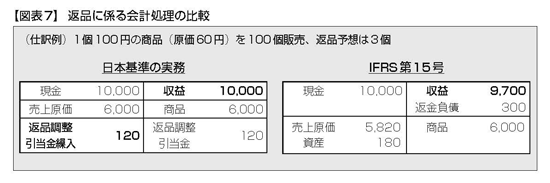
(3)予備的に識別した適用上の課題 IFRS第15号では、返品が見込まれる商品について当初の販売時に収益を認識しないことになるため、収益の数値を経営指標として使用している場合にその取扱いを見直すことが必要になる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業の提供する財又はサービスに関して、返金を伴う返品や別の財又はサービスとの交換を認めている取引(例:出版社や音楽用ソフトの制作販売会社等で行われている返品権付き販売、通信販売を行う場合に一定期間の返品を認める制度を設けている場合の取引)が影響を受ける可能性がある。
8 【論点9①】一定の期間にわたり充足される履行義務(進捗度を合理的に算定できる場合)(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、企業が財又はサービスを顧客に移転することにより、履行義務を充足した時点で収益を認識することが要求されている。財又はサービスが顧客に移転するのは、顧客がその財又はサービスに対する支配を獲得した時点(又は獲得するに従って)である(第33項)。
次の要件のいずれかに該当する場合には、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたって顧客に移転するために、一定の期間にわたり履行義務が充足する(すなわち、一定の期間にわたって収益を認識する)ものとされている(第35項)。
・顧客が、企業の履行により提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費する(主にサービスの提供。例えば、清掃サービス)。
・企業の履行により、財又はサービス(例えば、仕掛品)を創出するか又は増価させ、顧客が当該財又はサービスの創出又は増価につれてそれを支配する。
・企業の履行により企業が他に転用できる財又はサービスを創出せず、かつ、企業が現在までに完了した履行に対する支払(移転した財又はサービスの販売価格に近似した金額)を受ける強制可能な権利を有している。
履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務となる(すなわち一時点で収益を認識する。)(第38項)。また、一定の期間にわたり充足される履行義務についての収益を認識するのは、進捗度を合理的に測定できる場合のみである(進捗度を合理的に算定できない工事契約等については【論点9②】を参照)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、役務の提供に関して、一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合には、時間の経過を基礎として収益を認識するとされている(脚注9)。日本基準の実務では、役務に関する収益は、役務の提供が完了した時点で認識される例や、継続して役務の提供を行う場合には時間の経過を基礎として認識される例が見られる。
工事契約や受注制作のソフトウェアについては、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準が適用され、それ以外の場合は工事完成基準が適用される(脚注10)。なお、工事契約に金額的な重要性がない等の理由により、個別に工事契約に関する実行予算や工事原価等に関する管理が行われていない工事契約については、工事進行基準の適用要件を満たさないとされている(脚注11)。また、工期がごく短いものは、金額的重要性や工事契約としての性格が乏しいと想定されることから、通常、工事完成基準を適用することになると考えられるとされている(脚注12)。
これらの日本基準の定めに従った場合と、IFRS第15号の「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件を検討した場合とで判断が異なるときには、日本基準とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なると判断される場合には、管理プロセスの見直し(システム改修を伴うことがある。)が必要となったり、対象となる取引の予算管理方法に変更が生じたりする可能性がある。
・「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件の検討にあたって、顧客以外への資産の転用可能性、及び現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有しているかどうかの判断が困難となる可能性がある。また、取引量が多い場合、実務負担が大きくなる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 一定期間にわたって継続的にサービスを提供する契約や、一定期間で製品を製造する契約(例:輸送サービス、管理や事務代行等のサービス提供取引、ソフトウェア開発やビル建設等の長期の個別受注取引)等幅広い業務が影響を受ける可能性があると考えられる。
9 【論点9②】一定の期間にわたり充足される履行義務(進捗度を合理的に測定できない場合)(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、一定の期間にわたり収益を認識すると判断した取引について、その進捗度を合理的に測定出来ないが、発生するコストを回収すると見込んでいる場合、当該履行義務の結果を合理的に測定できるようになるまで、発生したコストが回収されると見込まれる範囲でのみ収益を認識(いわゆる工事原価回収基準(脚注13)を適用)することとされている(第45項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、進捗部分について成果の確実性が認められない場合には工事完成基準によることになるため、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・工事原価回収基準に対応するため、また、プロジェクトの契約期間中に進捗度を合理的に測定できるようになった等の理由で、工事原価回収基準から工事進行基準への切替えが生じる可能性があり、契約件数が多い場合には財務報告プロセスの見直し(財務会計システムの改修を含む)が必要となる可能性がある。
・進捗部分について成果の確実性が認められない工事契約等について、IFRS第15号により収益(及び同額の原価)が認識されることになる場合、工事契約等の収益及び利益率に関する予算管理の方法の変更も含め、企業の内部管理に影響が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 収益や原価等の見積りの策定に工事開始後一定期間を要する工事が影響を受ける可能性があると考えられる。
10 【論点10】一時点で充足される履行義務(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではないと判定された場合に、当該履行義務は一時点で充足されるものとして取り扱うこととされている(第32項)(【論点9①】を参照)。この場合、財又はサービスの支配が顧客に移転された時点で収益を認識する。財又はサービスの支配が移転されたか否かを判断するにあたっては、次の指標も考慮する(第38項)。
・企業が支払を受ける現在の権利を有している。
・顧客が法的所有権を有している。
・企業が物理的占有を移転した。
・顧客が所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している。
・顧客が検収した。
(2)財務報告数値の相違 日本基準における実務では、物品の販売について出荷基準、引渡基準及び検収基準等が、取引の性質を考慮の上、使い分けられているが、IFRS第15号における支配の移転の時期と一致しない場合には、収益の認識時期が異なることになる。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準における実務において出荷基準により収益を認識しており、IFRS第15号において日本基準における実務と収益の認識時期が異なると判断される場合には、経理処理に関わるプロセスを変更することが必要となる可能性がある。
・日本基準における実務がIFRS第15号における収益の認識時期と異なると判断される場合に、IFRS第15号の認識時期を反映するように業務を見直す必要が生じ、システム改修や、関連部署との折衝、物流プロセスの見直しの検討が必要となる可能性がある。
なお、財務諸表を作成する観点では、IFRS第15号と日本基準における実務との間で、期を跨ぐ取引(期末日前に出荷し期末日後に顧客が検収する取引等)について収益を認識する会計期間が異なると判断される場合には、その影響を財務諸表に反映させるか否かに関して、当該取引より生じる差異の金額的及び質的重要性や発生事由により判断することもあり得ると考えられる。
(4)影響を受けると考えられる取引例 物品の販売契約や輸出契約等の取引(特に、出荷してから顧客による検収まで一定程度の期間がある取引)が影響を受ける可能性があると考えられる。
11 【論点13】本人か代理人かの検討(総額表示又は純額表示)(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合には、企業は、企業の役割が自ら財又はサービスを提供することなのか(企業が本人であり、総額で収益を認識)、それとも、他者が提供する財又はサービスを手配することなのか(企業が代理人であり、手数料部分について純額で収益を認識)を判断するとされている(B35項及びB36項)。
この判断においては、財又はサービスが顧客に移転される前に企業が当該財又はサービスを支配しているかどうかがその規準となる(B35項)。また、企業が代理人である(すなわち、財又はサービスを顧客に提供する前に財又はサービスを支配していない。)ことを示す指標が次のように定められている(B37項)。
① 他の当事者が契約履行の主たる責任を有している。
② 顧客が財を注文した前後において、出荷中にも返品時にも、企業が在庫リスクを有していない。
③ 当該他の当事者の財又はサービスの価格の設定において企業に裁量権がなく、そのため、企業が当該財又はサービスから受け取ることのできる便益が限定されている。
④ 企業の対価が手数料の形式によるものである。
⑤ 当該他の当事者の財又はサービスと交換に顧客から受け取ることのできる金額について、企業が信用リスクに晒されていない。
なお、IASBは2015年7月に公開草案「IFRS第15号の明確化」を公表し、本人か代理人かの検討に関する明確化の修正提案を行っている。当該提案では、代理人であることを示す指標(B37項)を、本人であることを示す指標として再構成した上で、④の「対価が手数料の形式によるものである」という指標を削除することを提案している。また、コメント受領後の再審議において、⑤の信用リスクに関する指標も削除する方向で暫定決定している。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、ソフトウェア取引(脚注14)を除き、収益に関して売上と仕入を総額で表示するか純額で表示するかに関する一般的な定めはない。特定の取引についてIFRS第15号の定めに基づき代理人と判定された場合、収益を純額で認識することになるため、日本基準における実務において収益を総額で認識している場合、認識される収益の金額が減少することになる。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準の実務とIFRS第15号とで本人か代理人かの判断が異なる場合には、収益の経営指標としての位置付けやその他の収益を基礎とする業績指標(売上高利益率等)の位置付けに影響を与える可能性がある。
・IFRS第15号では、(1)の一定の要件と指標に基づき企業が本人か代理人かを判断することとされるが、約束された財又はサービスが顧客に移転される前に企業が当該財又はサービスを支配しているかどうかについて判定が困難となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業間の取引を仲介するケース等(例:卸売業における取引、小売業におけるいわゆる消化仕入や返品条件付買取仕入、メーカーの製造受託の取引や有償支給取引及び電子商取引サイト運営に係る取引)について、影響が生じる可能性があると考えられる。
Ⅸ 開示(注記事項)
1 IFRS第15号における主な開示項目 IFRS第15号は、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにすることを開示の目的としており、この目的を達成するために、【図表8】のような詳細な定量的情報及び定性的情報の注記が求められている(第110項)。
2 予備的に識別した適用上の課題 IFRS第15号による注記を行う場合、日本基準に比べ、追加的な情報を入手するための体制を整備する負担が増加する可能性がある。特に、次の開示項目については、まず契約残高を集計し、当期に認識した収益に対応する契約や発生原因等を識別したりする必要があると考えられる。
・期首に契約負債だったが当期に収益として認識されたものの金額
・変動対価の影響等により、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務について当期に認識した収益の金額
また、残存履行義務に関して、「報告期間末現在で未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額」及び「未充足の履行義務に配分した取引価格の総額について企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか。」について、多くの子会社を有する連結グループにおける企業ごとの多様な実務の統一や、契約の変更や追加注文への対応を図る必要がある可能性があり、さらに、将来の見込みが必要となる可能性がある。
X おわりに
収益認識は、基本的にすべての企業に関係する事項であり、当委員会が取り組んできた会計基準の中で、最も重要な部類に属するものと考えられる。開発にあたっては、関係者の意見を十分に聴取する必要があると考えており、本意見募集に多くの関係者からコメントを頂くことを期待している。
脚注
1 本意見募集文書の全文については、当委員会のウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/shueki2016/shueki2016_01.pdf)を参照のこと。
2 FASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 606「顧客との契約から生じる収益」
3 IFRS第15号の公表に伴い、同様の考え方により、固定資産の売却損益の認識時期等の改正もなされているが、今回の収益認識に関する包括的な会計基準の検討の範囲には含めていない。
4 当委員会は、これまで公開草案を公表する前に、「論点整理」、「検討状況の整理」、「試案」等の形式で、一般に意見を求めた例がある。
5 各論点の記載内容を読む際には、以下の点に留意されたい。
・各論点の記載内容は、当委員会事務局による調査や当委員会における審議において識別されたものであり、すべてを網羅したものではない。
・IFRS第15号を適用した場合の会計処理に関する記載は、IFRS第15号の解釈を示したものではない。
・適用上の課題の記載は、基本的に金額的・質的重要性を考慮していない。
6 項番号は、特に断りのない限り、IFRS第15号における項番号を指している(以下の論点について同様)。
7 企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」(以下「工事契約会計基準」)第7項
8 実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「ソフトウェア取引実務対応報告」) 3
9 企業会計原則注解(注5)(2)及び(4)
10 工事契約会計基準第5項及び第9項
11 工事契約会計基準第50項
12 工事契約会計基準第53項
13 工事契約会計基準第54項では、「工事原価を発生した期間に費用として認識しつつ、工事原価のうち回収可能性が高い部分についてのみ工事収益を計上する方法」と説明されている。
14 ソフトウェア取引については、一連の営業過程における仕入及び販売に関して通常負担すべき様々なリスク(瑕疵担保、在庫リスクや信用リスク)を負っていない場合には、総額表示は適切ではないとされている(ソフトウェア取引実務対応報告 4)
「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表 企業会計基準委員会 専門研究員 島田謡子
企業会計基準委員会 研究員 桑井瑞樹
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成28年2月4日に、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(以下「本意見募集文書」という。)を公表した(脚注1)(コメント期限は平成28年5月31日である。)。本稿では、本意見募集文書の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 公表の経緯
我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていない。このような状況の中、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606(脚注2))を公表している。
これらの状況を踏まえ、当委員会は、平成27年3月20日に開催された第308回企業会計基準委員会において、IFRS第15号を踏まえた我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定した(「Ⅲ.収益認識に関する包括的な会計基準を開発する意義」を参照)。
当委員会では、収益認識に関する包括的な会計基準の開発にあたって、IFRS第15号の内容を出発点として検討を開始しているが(「Ⅳ.開発する会計基準の内容」を参照)、これにより、財務諸表作成者に適用上の課題が生じることも想定される。当委員会ではこうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として連結財務諸表及び個別財務諸表に導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するために、本意見募集文書を公表することとした。
Ⅲ 収益認識に関する包括的な会計基準を開発する意義
当委員会は、IFRS第15号を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行うことには、次のような意義があると考えている。
・我が国の会計基準の体系の整備
我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発は、会計基準の体系の整備につながり、我が国の会計基準の高品質化に寄与すると考えられる。
・企業間の財務諸表の比較可能性の向上
我が国の会計基準の体系において包括的な会計基準を開発することにより、我が国の企業間の財務諸表の比較可能性が向上することが期待される。また、IFRS第15号は、Topic 606と文言レベルで概ね同一の基準であること、業種横断的で多様な取引に統一的に適用されるものであることから、同基準に準拠して財務情報が作成された場合、国際的な比較可能性が改善することも期待される。
・開示情報の充実
新たに開示(注記事項)の定めを設けることにより、我が国の企業の財務諸表における財務情報の質が向上することが期待される。また、IFRS第15号では開示情報が大幅に拡充されており、同基準に準拠して財務情報が作成された場合、財務諸表利用者の情報ニーズにより応えるものとなると期待される。
一方で、IFRS第15号における開示要求は、コストが便益に見合わないとの意見も聞かれており、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発において定める開示(注記事項)の具体的な内容については、個別に慎重な検討が必要になると考えられる。
Ⅳ 開発する会計基準の内容
収益認識に関する包括的な会計基準については、次の観点からIFRS第15号の内容を出発点として検討を始めている。
・IFRS第15号とTopic 606は概ね文言レベルで同一なものとなっており、IFRS第15号の内容を出発点としない場合、国際的な整合性を図ることが困難となること
・IFRS第15号は5つのステップにより収益を認識するという特徴を有しており、出発点としては、その体系を評価する必要があると考えられること
・連結財務諸表の作成にあたって指定国際会計基準や米国会計基準を適用する企業について、個別財務諸表においても同様の内容の基準を用いることのニーズが聞かれること
今後開発する会計基準の内容や文言について、IFRS第15号との間でどの程度整合性を図るべきか等については、本意見募集文書に寄せられた適用上の課題の内容等を踏まえた上で検討を行う予定である(脚注3)。
なお、IFRSでは、重要性について、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」において包括的に記述されており、各会計基準において重要性に関する特段の定めは原則として設けられていない。一方、我が国の会計基準では、個々の基準において、必要に応じて重要性に関する定めが設けられてきた。このため、今後、収益認識に関する包括的な会計基準の開発にあたって、重要性に関する定めを設けるべきか否かについても、検討にあたっての論点になり得るものと考えられる。
Ⅴ 会計基準の開発に関する当面の目標時期
当委員会では、本意見募集文書に寄せられた意見を踏まえ、収益認識に関する包括的な会計基準の案の策定に向けた検討を行う予定である。その開発にあたり、公開草案公表前に、検討状況について何らかの形式(脚注4)で一般に意見を求めることも考えられるが、この点については、本意見募集文書に寄せられた内容等を踏まえた上で検討を行う予定である。
収益認識に関する包括的な会計基準の最終的な基準化の時期について、当委員会におけるこれまでの審議の過程では、我が国における収益認識基準の開発は、広範な業種や企業に重要な影響を与える可能性があるため、慎重に進めるべきとの意見も聞かれている一方で、指定国際会計基準を任意適用する企業や米国会計基準を利用する企業から、IFRS第15号及びTopic 606の強制適用日と整合させるべきとの意見も聞かれている。当委員会では、これらの意見を踏まえて、IFRS第15号及びTopic 606の強制適用日(IFRS第15号においては平成30年1月1日以後開始する事業年度、Topic 606においては平成29年12月15日より後に開始する事業年度)に適用が可能となることを当面の目標としている。
Ⅵ 本意見募集文書の質問事項
本意見募集文書では、次の質問項目を設けている。
質問1 回答者の属性 ・どのような立場(財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人、学識経験者等)で質問にご回答いただいているか。
質問2 検討の進め方に対するご意見 ・「Ⅳ.開発する会計基準の内容」に記載した理由によりIFRS第15号の内容を出発点として検討を行っているが、その進め方に関するご意見を頂きたい。
・質問項目には記載されていないが、開発する会計基準の内容や文言について、IFRS第15号との間でどの程度整合性を図るべきかについてのご意見を記載頂くことも考えられる。
質問3 予備的に識別した論点に対するご意見 ・当委員会では、予備的に17個の論点を識別しているが、「予備的に識別した適用上の課題」、「影響を受けると考えられる取引例」の記載内容は適切か否かについて、ご意見を頂きたい。
質問4 その他の論点の照会 ・17個の論点以外の適用上の課題を識別している場合には、可能な限り詳細に、その内容をお教え頂きたい。
質問5 開示(注記事項)に対するご意見 ・IFRS第15号の開示(注記事項)規定について、どの程度、我が国の会計基準において取り入れるかについては、便益とコストについて十分に分析を行う必要がある。その観点で、以下の意見を頂きたい。
>IFRS第15号の注記事項の中で、特に収益の分析において有用と考えられる注記事項
>IFRS第15号の注記の中で、実務上のコスト負担の観点から、注記事項として取り入れることに懸念があるもの
Ⅶ IFRS第15号の概要
本意見募集文書では、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを、我が国の収益認識に関する包括的な会計基準として連結及び個別財務諸表に導入した場合に重要な影響を受ける可能性があると、当委員会で予備的に識別した論点を記載している。
したがって、まずは、IFRS第15号の概要について説明する。
1 基本原則と5つのステップ IFRS第15号の基本原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で描写するように、企業が収益を認識することである。IFRS第15号では、この原則を達成するために、【図表1】のステップに従って収益を認識する。
| 【図表1】IFRS第15号を適用するための5つのステップ |
| ステップ1:顧客との契約を識別する |
| ステップ2:契約における履行義務(収益の認識の単位)を識別する |
| ステップ3:取引価格を算定する |
| ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する |
| ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足につれて)収益を認識する |
以下、【図表1】の5つのステップを簡単な取引例を用いて説明する。
【取引例】
企業は、当期首において標準的なA商品の販売と2年間の保守サービスの提供を一体で顧客と契約し、当期にA商品を顧客に引き渡し、当期と翌期に保守サービスを行う。契約書に記載されたA商品と2年間の保守サービスの提供の対価の合計金額は12,000千円である。
以上の結果、企業が当該契約について当期(1年間)に認識する収益金額は次のようになる。 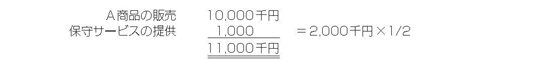 |
以下の【図表2】は、この取引例に5つのステップを当てはめた場合のフローを示している。
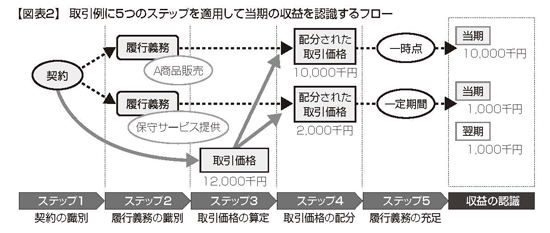
Ⅷ 当委員会が予備的に識別している適用上の論点
本意見募集文書は、公表の経緯及び質問事項等と、それに続く「第1部 IFRS第15号に関して予備的に識別している適用上の課題」(以下「第1部」という。)及び「第2部 IFRS第15号の概要」(以下「第2部」という。)で構成されている。
第1部では、仮にIFRS第15号の基準本文(適用指針を含む。)の内容のすべてを、我が国の収益認識に関する包括的な会計基準として連結財務諸表及び個別財務諸表に導入した場合の論点を予備的に識別した上で、適用上の課題の分析を行っている(脚注5)。第2部は、第1部の理解に資するよう、IFRS第15号の規定の概要について記載している。
以下では、本章意見文書の第1部で示した各論点(【図表3】参照)のうち、重要な影響を及ぼすと考えられる(※)を付した論点について、(1)IFRS第15号での取扱い、(2)財務報告数値の相違、(3)予備的に識別した適用上の課題、(4)影響を受けると考えられる取引例の概要を項目ごとに説明する。また、開示についても「Ⅸ.1.IFRS第15号における主な開示項目」及び、「Ⅸ.2.予備的に識別した適用上の課題」について記載している。
| 【図表3】IFRS第15号に関して予備的に識別している適用上の課題 1.主に収益認識の金額や時期に影響を与える可能性のある論点 |
| ステップ | 論 点 | 各論点の内容 |
| ステップ1 | 論点1(※) | 契約の結合 |
| 論点2(※) | 契約の変更 | |
| ステップ2 | 論点3(※) | 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断 |
| 論点4(※) | 追加的な財又はサービスに対する顧客のオプション(ポイント制度等) | |
| 論点5(※) | 知的財産ライセンスの供与 | |
| ステップ3 | 論点6(※) | 変動対価(売上等に応じて変動するリベート、仮価格等) |
| 論点7(※) | 返品権利付き販売 | |
| ステップ4 | 論点8 | 独立販売価格に基づく配分 |
| ステップ5 | 論点9(※) | 一定の期間にわたり充足される履行義務 |
| 論点10(※) | 一時点で充足される履行義務 | |
| 論点11 | 顧客の未行使の権利(商品券等) | |
| 論点12 | 返金不能の前払報酬 |
2.主に財務諸表における収益の表示に影響を与える可能性のある論点 |
| ステップ | 論 点 | 各論点の内容 |
| ステップ2 | 論点13(※) | 本人か代理人かの検討(総額表示又は純額表示) |
| ステップ3 | 論点14 | 第三者に代わって回収される金額(間接税等) |
| 論点15 | 顧客に支払われる対価の表示 |
3.その他の論点 |
| 論 点 | 各論点の内容 |
| 論点16 | 契約コスト |
| 論点17 | 貸借対照表項目の表示科目 |
4.開示(注記事項)(※)
1 【論点1】契約の結合(ステップ1)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、同一の顧客(又は顧客の関連当事者)と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約が次のいずれかに該当する場合、契約を結合して「単一の契約」とすることとされている(第17項(脚注6))。
・契約が単一の商業的な目的を有するパッケージとして交渉されている。
・1つの契約で支払われる対価の金額が、他の契約の価格又は履行に左右される。
・複数の契約で約束した財又はサービス(あるいは各契約で約束した財又はサービスの一部)が、【論点3】で検討する履行義務の識別の要件に照らして、単一の履行義務であると判断される。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約会計基準の定めを除き、複数の契約の結合に関する一般的な定めはない。通常は、個々の契約が収益認識の基本的な単位になると考えられるが、契約内容を勘案して別の単位で収益を認識することもあると考えられる。IFRS第15号において複数の契約が「単一の契約」とされた場合、それを基に【論点3】等のプロセスを通じて収益を認識する単位やその単位に配分される金額が決められる。その結果、日本基準の実務において個々の契約を収益認識の単位としている場合、単位の違い又は単位は同じでも各単位への配分金額の違いにより、収益を認識する時期や、1期間に認識する金額が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・複数の契約を「単一の契約」に結合するか否かを判断する際に、結合すべき契約の範囲の決定が困難な場合があり、その判断のための業務プロセスの変更を伴う可能性があると考えられる。
・会計システム上、契約単位で収益認識の処理を行っている場合、複数の契約を「単一の契約」とみなして処理できるようにシステム改修を行う必要が生じる可能性がある。
・IFRS第15号において複数の契約が「単一の契約」とされた場合、日本基準の実務において個々の契約を収益認識の単位としている場合と比べて、収益の金額や利益率が変動する可能性があり、社内の業績管理の方法に変更が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 同一の顧客と同時又はほぼ同時に複数の契約を締結する取引(例:汎用ソフトウェアを顧客仕様にカスタマイズして提供する場合にソフトウェア本体の利用権の提供とカスタマイズの契約を分けている場合や、ソフトウェアの受注制作において開発工程ごとに契約を分けている場合)に影響が生じる可能性があると考えられる。
2 【論点2】契約の変更(ステップ1)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約の変更は、【図表4】のように会計処理することとされている。
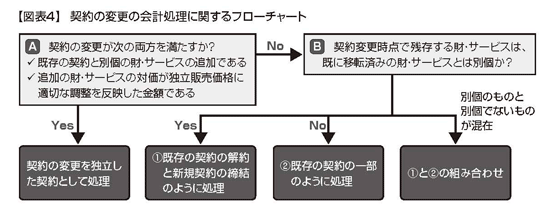
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約や受注制作のソフトウェアを除き、契約の変更に関する一般的な定めはなく、個々の契約の変更の内容を勘案して会計処理が行われていると考えられ、日本基準の実務とIFRS第15号とで、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・契約の変更の内容が様々であることから、【図表4】(B)のように、既存の契約自体の変更と判断されるか否かについては、判断が困難な場合があると考えられる。
・契約の変更が頻繁に行われるような業種では、会計処理の負担が大きくなる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 提供する財又はサービスの内容や価格の変更が生じる取引(例:建設、ソフトウェアの開発や設備等の長期の受注製作、電気通信契約)が影響を受けると考えられる。
3 【論点3】約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約に複数の財又はサービスが含まれており、契約に含まれる財又はサービスが、同じ契約内の別の財又はサービスと別個のものである場合には、独立した履行義務(収益認識の単位)として識別し、区分して会計処理することとされている。「別個のもの」とは、具体的には、当該財又はサービスについて次の要件の両方に該当する場合であるとされている(第27項)。
・個々の財又はサービスのレベルでの区分可能性
顧客がその財又はサービスからの便益を、それ単独で(又は顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて)得ることができる(第27項(a))。
・契約の観点からの区分可能性
財又はサービスを顧客に移転する約束が、同一契約内の他の約束と区分して識別できる(第27項(b))。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、工事契約とソフトウェア取引以外では取引を分割することは明示的に求められていない。工事契約等については、認識の単位として、契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づくとされており、実質的な取引の単位を反映するように契約書上の取引を分割することが必要となる場合があるとされている(脚注7)。また、ソフトウェアの複合取引については、収益認識時点が異なる複数の取引が1つの契約とされていても、財又はサービスの内容や各々の金額の内訳が顧客との間で明らかにされている場合には、契約上の対価を適切に分解するとされており、また、内訳金額が明らかでない場合でも、管理上の適切な区分に基づき分解することができるとされている(脚注8)。
ただし、工事契約とソフトウェア取引についてもIFRS第15号で定められている履行義務の識別と同一の方法で分割することが求められているわけではないため、IFRS第15号とで会計処理の単位が異なる場合には、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・履行義務の識別に関する2つの要件の判断が困難である可能性がある。また、判断を要する取引の形態が多様である場合、実務負担が大きくなる可能性がある。
・日本基準の実務よりも収益の認識単位が増加する場合、契約情報(例:オーダー番号)をさらに細分化して登録するなど、システム対応が必要となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 商品等の提供とその後の一定期間にわたる付随的サービスの提供が1つの契約に含まれる取引等の、収益の認識時点が異なる複数の財又はサービスを一体で提供する取引(例:機械の販売と据付サービスや保守サービス、ソフトウェア開発とその後のサポート・サービス)に影響が生じる可能性がある。
4 【論点4】追加的な財又はサービスに対する顧客のオプション(ポイント制度等)(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、商品やサービスの提供に付随して付与されるポイントは、追加的な財又はサービスを無料又は値引価格で取得する顧客のオプションとして取り扱うこととされている。当該オプションには販売インセンティブ、顧客特典クレジット(又はポイント)、契約更新オプションあるいは将来の財又はサービスに係るその他の値引き等が含まれる(B39項)。
このようなオプションについて、当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供する場合(例えば、当該財又はサービスについて、その地域又は市場において同じ客層に通常与えられる範囲を超える値引きを提供する場合)、顧客の支払は実質的に将来の財又はサービスに対するものとして取り扱い(すなわち、別の履行義務とする。)、以下の会計処理を行うこととされている(【図表5】参照)(B40項)。
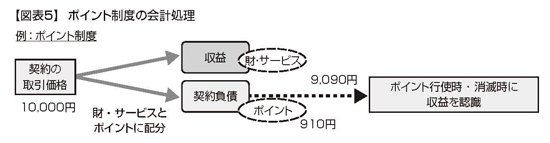
・契約の取引価格全体を、独立販売価格に基づいて、オプション付与時に当初提供した財又はサービスとオプション部分に配分する。
・オプション部分を契約負債として繰り延べる。
・将来の財又はサービスの移転時又は当該オプションの消滅時に収益を認識する。
(2)財務報告数値の相違 IFRS第15号のもとでは、追加的な財又はサービスに対する顧客のオプションについて、オプションに対応する収益を繰り延べる。日本基準の実務では、ポイントについては、一般的に、顧客への商品の販売時又はサービスの提供時にそれらの価格により一括して収益認識し、将来のポイントとの交換に要すると見込まれる金額(販売価格のケースもあれば原価のケースもある)を引当金として費用を計上する実務が多いと考えられるため、収益を認識する時期及び一定期間内に認識される収益の金額が異なる可能性がある。また、日本基準の実務において企業が負担する原価を基礎として引当金を計算している場合、IFRS第15号により繰り延べる収益の金額との相違が大きくなる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 我が国のポイント制度については、複数企業による相互利用や制度間の交換、電子マネーへの交換等複雑化しており、企業が関係するポイント制度に関する取引を詳細に分析した上で、IFRS第15号に従って会計処理するために業務プロセスの再構築(システム改修を伴うことがある。)を行う負担が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業が顧客に財又はサービスを提供する際に、付随して追加的な財又はサービスに対するオプションを提供する取引(例:商品の販売やサービスの提供に伴いポイントを付与する取引)が影響を受ける可能性がある。
5 【論点5】知的財産ライセンスの供与(ステップ2及びステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、ライセンス供与について、顧客が権利を有する知的財産が企業の活動により著しく影響を受けるかどうかにより、ライセンス供与の性質(知的財産にアクセスする権利か、ライセンスを使用する権利か)を判断し、収益の認識時期を決定することとされている(【図表6】参照)(B56項)。
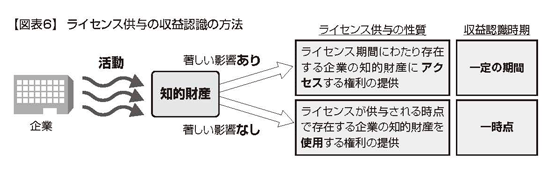
ライセンス供与について「企業の知的財産にアクセスする権利」に該当するのは次のすべての要件を満たす場合である(B58項)。
① 顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行うことが、契約上要求されているか又は顧客により合理的に期待されている。
② ライセンスによって供与される権利に基づき、顧客が①で識別された企業の活動によって直接的に影響を受ける。
③ 上記のように企業が活動しても、当該活動が生じるにつれて顧客に財又はサービスが移転することがない。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、知的財産ライセンスに関する一般的な定めはなく、日本基準の実務とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・ライセンス供与後に企業が行う活動が、顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動であるかどうかの判定が困難である可能性がある。
・単一の履行義務として識別されたライセンス契約に他の付随サービスが含まれる場合、いずれの性質をより重視して収益認識時点を判断すべきかが困難である可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 顧客に知的財産のライセンスを供与する取引(例:特許権の使用許諾、一定地域における独占販売権を与えるライセンス取引、メディア・コンテンツやフランチャイズ権のライセンス、ソフトウェアのライセンス及び医薬品業界の導出取引)が影響を受ける可能性があると考えられる。
6 【論点6】変動対価(売上等に応じて変動するリベート、仮価格等)(ステップ3)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、契約上の対価に変動性がある場合(変動対価)、期待値(確率で加重平均した金額)又は最頻値(最も可能性の高い金額)のうち、より対価を適切に予測できる方法によりその金額を見積ることとされている(第50項及び第53項)。ただし、取引価格に含められる金額(すなわち、収益金額)は、事後に重大な収益金額の戻入れ(減額)が生じない可能性が非常に高い範囲に制限されている(変動対価の制限)(第56項)。変動対価が含まれる可能性のある取引としては、値引き、リベート、返金、クレジット、インセンティブ、業績ボーナス、ペナルティー等が例示されている(第51項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準の実務では、支払の可能性が高いと判断された時点で売上リベートを認識するケースや、仮価格について、顧客との交渉状況に応じて収益金額の見直しを行うケースがあると考えられる。IFRS第15号において、売上リベートの見積りや仮価格の精算見込みの影響をより早い時点(履行義務の充足時)に反映させると判断される場合、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・売上リベートについて、リベート支払の条件達成の判断が困難となる可能性がある(特に、書面の契約ではなく、商慣習等による場合)。ただし、実務上、困難が生じるのは、期末又は四半期末までに条件を達成したか否かが確定しない場合であると考えられる。
・仮価格について、最終価格をどのように見積るかの判断が困難となる可能性がある。ただし、実務上、困難が生じるのは、期末又は四半期末までに価格が決定されない場合であると考えられる。
・「変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲」を見積ることが求められるが、重大な戻入れが生じない可能性について、判断が困難となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 契約上、又は業界の慣行として商品受渡後の価格調整が行われる取引が影響を受ける可能性がある。また、売上に関連して企業から顧客に何らかの対価を支払う場合、その対価に変動要素がある取引にも影響がある可能性がある。
具体的には、多くの業種において行われている仮価格による取引、販売数量や業績達成に応じたインセンティブを付すリベート等が生じる取引、及び販売店が消費者に対して行う値引きについて、メーカーがその値引きの一部を負担する取引等が影響を受ける可能性がある。
7 【論点7】返品権付き販売(ステップ3)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、返品権付きの商品(及び条件付きで返金が認められるサービス)について、販売した商品等のうち返品が見込まれる部分については収益を認識しないこととされている。受け取った(又は受け取ることのできる)金額のうち、返品が見込まれる部分は返金負債として計上するとともに、当該返金に関して、顧客から商品を回収する権利(すなわち、将来返品を受け入れることが見込まれる商品)については資産として計上する(B21項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準の実務では、販売時に対価の全額が収益として認識した上で、過去の返品実績等に基づき返品調整引当金を計上(引当金の繰入額については、売上総利益の調整として表示)する例が多く見られるため、IFRS第15号を採用した場合に、収益を認識する時期が異なる可能性がある(【図表7】参照)。
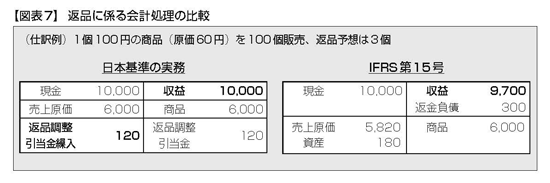
(3)予備的に識別した適用上の課題 IFRS第15号では、返品が見込まれる商品について当初の販売時に収益を認識しないことになるため、収益の数値を経営指標として使用している場合にその取扱いを見直すことが必要になる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業の提供する財又はサービスに関して、返金を伴う返品や別の財又はサービスとの交換を認めている取引(例:出版社や音楽用ソフトの制作販売会社等で行われている返品権付き販売、通信販売を行う場合に一定期間の返品を認める制度を設けている場合の取引)が影響を受ける可能性がある。
8 【論点9①】一定の期間にわたり充足される履行義務(進捗度を合理的に算定できる場合)(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、企業が財又はサービスを顧客に移転することにより、履行義務を充足した時点で収益を認識することが要求されている。財又はサービスが顧客に移転するのは、顧客がその財又はサービスに対する支配を獲得した時点(又は獲得するに従って)である(第33項)。
次の要件のいずれかに該当する場合には、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたって顧客に移転するために、一定の期間にわたり履行義務が充足する(すなわち、一定の期間にわたって収益を認識する)ものとされている(第35項)。
・顧客が、企業の履行により提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費する(主にサービスの提供。例えば、清掃サービス)。
・企業の履行により、財又はサービス(例えば、仕掛品)を創出するか又は増価させ、顧客が当該財又はサービスの創出又は増価につれてそれを支配する。
・企業の履行により企業が他に転用できる財又はサービスを創出せず、かつ、企業が現在までに完了した履行に対する支払(移転した財又はサービスの販売価格に近似した金額)を受ける強制可能な権利を有している。
履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務となる(すなわち一時点で収益を認識する。)(第38項)。また、一定の期間にわたり充足される履行義務についての収益を認識するのは、進捗度を合理的に測定できる場合のみである(進捗度を合理的に算定できない工事契約等については【論点9②】を参照)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、役務の提供に関して、一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合には、時間の経過を基礎として収益を認識するとされている(脚注9)。日本基準の実務では、役務に関する収益は、役務の提供が完了した時点で認識される例や、継続して役務の提供を行う場合には時間の経過を基礎として認識される例が見られる。
工事契約や受注制作のソフトウェアについては、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準が適用され、それ以外の場合は工事完成基準が適用される(脚注10)。なお、工事契約に金額的な重要性がない等の理由により、個別に工事契約に関する実行予算や工事原価等に関する管理が行われていない工事契約については、工事進行基準の適用要件を満たさないとされている(脚注11)。また、工期がごく短いものは、金額的重要性や工事契約としての性格が乏しいと想定されることから、通常、工事完成基準を適用することになると考えられるとされている(脚注12)。
これらの日本基準の定めに従った場合と、IFRS第15号の「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件を検討した場合とで判断が異なるときには、日本基準とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準とIFRS第15号とで収益の認識時期が異なると判断される場合には、管理プロセスの見直し(システム改修を伴うことがある。)が必要となったり、対象となる取引の予算管理方法に変更が生じたりする可能性がある。
・「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件の検討にあたって、顧客以外への資産の転用可能性、及び現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有しているかどうかの判断が困難となる可能性がある。また、取引量が多い場合、実務負担が大きくなる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 一定期間にわたって継続的にサービスを提供する契約や、一定期間で製品を製造する契約(例:輸送サービス、管理や事務代行等のサービス提供取引、ソフトウェア開発やビル建設等の長期の個別受注取引)等幅広い業務が影響を受ける可能性があると考えられる。
9 【論点9②】一定の期間にわたり充足される履行義務(進捗度を合理的に測定できない場合)(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、一定の期間にわたり収益を認識すると判断した取引について、その進捗度を合理的に測定出来ないが、発生するコストを回収すると見込んでいる場合、当該履行義務の結果を合理的に測定できるようになるまで、発生したコストが回収されると見込まれる範囲でのみ収益を認識(いわゆる工事原価回収基準(脚注13)を適用)することとされている(第45項)。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、進捗部分について成果の確実性が認められない場合には工事完成基準によることになるため、収益の認識時期が異なる可能性がある。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・工事原価回収基準に対応するため、また、プロジェクトの契約期間中に進捗度を合理的に測定できるようになった等の理由で、工事原価回収基準から工事進行基準への切替えが生じる可能性があり、契約件数が多い場合には財務報告プロセスの見直し(財務会計システムの改修を含む)が必要となる可能性がある。
・進捗部分について成果の確実性が認められない工事契約等について、IFRS第15号により収益(及び同額の原価)が認識されることになる場合、工事契約等の収益及び利益率に関する予算管理の方法の変更も含め、企業の内部管理に影響が生じる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 収益や原価等の見積りの策定に工事開始後一定期間を要する工事が影響を受ける可能性があると考えられる。
10 【論点10】一時点で充足される履行義務(ステップ5)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではないと判定された場合に、当該履行義務は一時点で充足されるものとして取り扱うこととされている(第32項)(【論点9①】を参照)。この場合、財又はサービスの支配が顧客に移転された時点で収益を認識する。財又はサービスの支配が移転されたか否かを判断するにあたっては、次の指標も考慮する(第38項)。
・企業が支払を受ける現在の権利を有している。
・顧客が法的所有権を有している。
・企業が物理的占有を移転した。
・顧客が所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している。
・顧客が検収した。
(2)財務報告数値の相違 日本基準における実務では、物品の販売について出荷基準、引渡基準及び検収基準等が、取引の性質を考慮の上、使い分けられているが、IFRS第15号における支配の移転の時期と一致しない場合には、収益の認識時期が異なることになる。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準における実務において出荷基準により収益を認識しており、IFRS第15号において日本基準における実務と収益の認識時期が異なると判断される場合には、経理処理に関わるプロセスを変更することが必要となる可能性がある。
・日本基準における実務がIFRS第15号における収益の認識時期と異なると判断される場合に、IFRS第15号の認識時期を反映するように業務を見直す必要が生じ、システム改修や、関連部署との折衝、物流プロセスの見直しの検討が必要となる可能性がある。
なお、財務諸表を作成する観点では、IFRS第15号と日本基準における実務との間で、期を跨ぐ取引(期末日前に出荷し期末日後に顧客が検収する取引等)について収益を認識する会計期間が異なると判断される場合には、その影響を財務諸表に反映させるか否かに関して、当該取引より生じる差異の金額的及び質的重要性や発生事由により判断することもあり得ると考えられる。
(4)影響を受けると考えられる取引例 物品の販売契約や輸出契約等の取引(特に、出荷してから顧客による検収まで一定程度の期間がある取引)が影響を受ける可能性があると考えられる。
11 【論点13】本人か代理人かの検討(総額表示又は純額表示)(ステップ2)
(1)IFRS第15号での取扱い IFRS第15号では、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合には、企業は、企業の役割が自ら財又はサービスを提供することなのか(企業が本人であり、総額で収益を認識)、それとも、他者が提供する財又はサービスを手配することなのか(企業が代理人であり、手数料部分について純額で収益を認識)を判断するとされている(B35項及びB36項)。
この判断においては、財又はサービスが顧客に移転される前に企業が当該財又はサービスを支配しているかどうかがその規準となる(B35項)。また、企業が代理人である(すなわち、財又はサービスを顧客に提供する前に財又はサービスを支配していない。)ことを示す指標が次のように定められている(B37項)。
① 他の当事者が契約履行の主たる責任を有している。
② 顧客が財を注文した前後において、出荷中にも返品時にも、企業が在庫リスクを有していない。
③ 当該他の当事者の財又はサービスの価格の設定において企業に裁量権がなく、そのため、企業が当該財又はサービスから受け取ることのできる便益が限定されている。
④ 企業の対価が手数料の形式によるものである。
⑤ 当該他の当事者の財又はサービスと交換に顧客から受け取ることのできる金額について、企業が信用リスクに晒されていない。
なお、IASBは2015年7月に公開草案「IFRS第15号の明確化」を公表し、本人か代理人かの検討に関する明確化の修正提案を行っている。当該提案では、代理人であることを示す指標(B37項)を、本人であることを示す指標として再構成した上で、④の「対価が手数料の形式によるものである」という指標を削除することを提案している。また、コメント受領後の再審議において、⑤の信用リスクに関する指標も削除する方向で暫定決定している。
(2)財務報告数値の相違 日本基準では、ソフトウェア取引(脚注14)を除き、収益に関して売上と仕入を総額で表示するか純額で表示するかに関する一般的な定めはない。特定の取引についてIFRS第15号の定めに基づき代理人と判定された場合、収益を純額で認識することになるため、日本基準における実務において収益を総額で認識している場合、認識される収益の金額が減少することになる。
(3)予備的に識別した適用上の課題 当委員会で予備的に識別した適用上の課題は次のとおりである。
・日本基準の実務とIFRS第15号とで本人か代理人かの判断が異なる場合には、収益の経営指標としての位置付けやその他の収益を基礎とする業績指標(売上高利益率等)の位置付けに影響を与える可能性がある。
・IFRS第15号では、(1)の一定の要件と指標に基づき企業が本人か代理人かを判断することとされるが、約束された財又はサービスが顧客に移転される前に企業が当該財又はサービスを支配しているかどうかについて判定が困難となる可能性がある。
(4)影響を受けると考えられる取引例 企業間の取引を仲介するケース等(例:卸売業における取引、小売業におけるいわゆる消化仕入や返品条件付買取仕入、メーカーの製造受託の取引や有償支給取引及び電子商取引サイト運営に係る取引)について、影響が生じる可能性があると考えられる。
Ⅸ 開示(注記事項)
1 IFRS第15号における主な開示項目 IFRS第15号は、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにすることを開示の目的としており、この目的を達成するために、【図表8】のような詳細な定量的情報及び定性的情報の注記が求められている(第110項)。
| 【図表8】IFRS第15号における主な開示項目 |
| 項目 | 主な内容 | |
| 顧客との契約 | ||
| 収益の分解 | ▪適切な区分(例:製品ライン、地理的区分、顧客、契約期間)ごとの収益の開示 ▪分解した収益情報と各報告セグメントの収益情報との関係性 | |
| 契約残高 | ▪債権・契約資産・契約負債の期首・期末残高 ▪期首に契約負債だったが当期に収益として認識されたものの金額 ▪過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益金額(例:取引価格の変動) ▪契約資産・契約負債の残高の重大な変動の説明 | |
| 履行義務 | ▪履行義務を充足する時点 ▪重大な支払条件 ▪企業が移転を約束した財・サービスの内容 ▪返品・返金の義務 | |
| 残存履行義務に配分した取引価格 | ▪期末に未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格総額 ▪上記金額が収益として認識される時期 | |
| IFRS第15号の適用における重要な判断 | ||
| 履行義務の充足の時期の決定 | ▪一定の期間にわたり充足する履行義務:収益を認識するための使用した方法及びその理由 ▪一時点で充足される履行義務:顧客が財・サービスを支配する時点に関する判断 | |
| 取引価格・履行義務への配分額の算定 | ▪次の項目に使用した方法・インプット・仮定 >取引価格の算定(変動対価の見積り等) >変動対価の見積りの制限に対する評価 >取引価格の配分(独立販売価格の見積り、値引き・変動対価の配分等) ▪返品・返金の義務の測定 | |
| 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産 | ||
| 契約コストから認識した資産 | ▪金額を算定する際の判断・償却方法 ▪契約獲得のために発生したコスト・契約を履行するために発生したコストの主要区分別期末残高 ▪当期の償却金額・減損損失 | |
2 予備的に識別した適用上の課題 IFRS第15号による注記を行う場合、日本基準に比べ、追加的な情報を入手するための体制を整備する負担が増加する可能性がある。特に、次の開示項目については、まず契約残高を集計し、当期に認識した収益に対応する契約や発生原因等を識別したりする必要があると考えられる。
・期首に契約負債だったが当期に収益として認識されたものの金額
・変動対価の影響等により、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務について当期に認識した収益の金額
また、残存履行義務に関して、「報告期間末現在で未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額」及び「未充足の履行義務に配分した取引価格の総額について企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか。」について、多くの子会社を有する連結グループにおける企業ごとの多様な実務の統一や、契約の変更や追加注文への対応を図る必要がある可能性があり、さらに、将来の見込みが必要となる可能性がある。
X おわりに
収益認識は、基本的にすべての企業に関係する事項であり、当委員会が取り組んできた会計基準の中で、最も重要な部類に属するものと考えられる。開発にあたっては、関係者の意見を十分に聴取する必要があると考えており、本意見募集に多くの関係者からコメントを頂くことを期待している。
脚注
1 本意見募集文書の全文については、当委員会のウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/shueki2016/shueki2016_01.pdf)を参照のこと。
2 FASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 606「顧客との契約から生じる収益」
3 IFRS第15号の公表に伴い、同様の考え方により、固定資産の売却損益の認識時期等の改正もなされているが、今回の収益認識に関する包括的な会計基準の検討の範囲には含めていない。
4 当委員会は、これまで公開草案を公表する前に、「論点整理」、「検討状況の整理」、「試案」等の形式で、一般に意見を求めた例がある。
5 各論点の記載内容を読む際には、以下の点に留意されたい。
・各論点の記載内容は、当委員会事務局による調査や当委員会における審議において識別されたものであり、すべてを網羅したものではない。
・IFRS第15号を適用した場合の会計処理に関する記載は、IFRS第15号の解釈を示したものではない。
・適用上の課題の記載は、基本的に金額的・質的重要性を考慮していない。
6 項番号は、特に断りのない限り、IFRS第15号における項番号を指している(以下の論点について同様)。
7 企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」(以下「工事契約会計基準」)第7項
8 実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「ソフトウェア取引実務対応報告」) 3
9 企業会計原則注解(注5)(2)及び(4)
10 工事契約会計基準第5項及び第9項
11 工事契約会計基準第50項
12 工事契約会計基準第53項
13 工事契約会計基準第54項では、「工事原価を発生した期間に費用として認識しつつ、工事原価のうち回収可能性が高い部分についてのみ工事収益を計上する方法」と説明されている。
14 ソフトウェア取引については、一連の営業過程における仕入及び販売に関して通常負担すべき様々なリスク(瑕疵担保、在庫リスクや信用リスク)を負っていない場合には、総額表示は適切ではないとされている(ソフトウェア取引実務対応報告 4)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















