解説記事2016年05月16日 【SCOPE】 返金伝票綴りは印紙税の対象、過怠税めぐり企業側敗訴(2016年5月16日号・№642)
裁判所、1冊4,000円の「判取帳」に該当
返金伝票綴りは印紙税の対象、過怠税めぐり企業側敗訴
日用雑貨などの販売業を営む原告企業が作成および保管していた「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税の課税対象となる「判取帳」に該当するか否かが問題となった裁判で、原告企業が敗訴する判決が下された(東京地裁平成27年12月18日判決・敗訴した原告企業は控訴)。裁判所は、3枚複写100組綴りのお客様返金伝票のうち、1枚目(売場控)のみが残った伝票綴りは2以上の相手方(複数の顧客)から付込証明(返金額などを記入)を受ける目的をもって作成されたものである点などから「判取帳」に該当すると判断したうえで、印紙税過怠税(324万円)の賦課決定処分は適法であると結論付けた。
複数の顧客から金銭の受領事実の証明を受けるものか否かが問題に
印紙税の課税対象である「判取帳」は、2以上の相手から金銭の受領事実などの付込証明を受ける目的で作成される帳簿のことで、1冊につき4,000円の印紙税が課税される(表参照)。本件で問題となったのは、日用雑貨などを販売する原告企業が保存していた「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税の課税対象となる「判取帳」に該当するか否かという点だ。原告企業が利用していたお客様返金伝票は、3枚1組複写式の伝票が100組綴られている冊子形態のもの(図参照)。原告企業が返品等受付事務に使用した結果、3枚1組複写のうち2枚目(事務所控)および3枚目(商品貼付用)の伝票は事務所控えなどとするために切り離される一方で、1枚目の伝票(売場控)には伝票綴りから分離するための切取り線がなく、冊子形態の伝票綴りに綴られた状態で保管されていた。
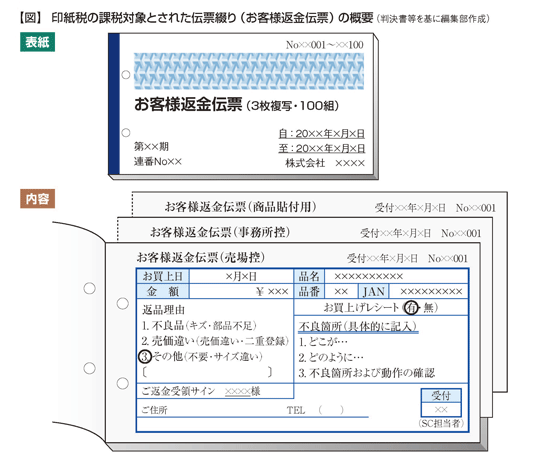
原告企業が保有していた270冊(3年間分)の伝票綴りに対し税務署は、印紙税が課税される「判取帳」に該当すると判断したうえで、印紙税が納付されていないことを理由に過怠税324万円の賦課決定処分を行った。
これを不服とする原告企業は、裁判のなかで、①お客様返金伝票(売場控)が綴られた伝票綴りは印紙税の課税単位となる「一の文書」に該当しないこと、②2以上の相手から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されたものではないこと、③印紙税法上の帳簿に該当しないことなどを指摘したうえで、原告企業が保管していた伝票綴りは「判取帳」には該当しないと主張した。
裁判所は、まず、①伝票綴りの冊子の表紙には綴られた100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載されていること、②お客様返金伝票の1枚目(売場控)は切り離されずに保管・管理されていたこと等を踏まえ、お客様返金伝票(売場控)のみが残された伝票綴りは1冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められることから、その伝票綴り全体をもって「一の文書」に該当すると判断した。
次に、伝票の文書自体の形式・内容のほか、使用方法および使用実態の諸点からみて、伝票綴りは複数の顧客から金銭の受領の事実につき付込証明を受ける目的で作成されたものであると認定したうえで、伝票綴りは「第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成」(課税物件表20号)されたものであると判断した。
そして、伝票綴りは店舗で多数回発生する商取引(販売商品の返金など)に関して金銭の受領事実という課税事項を継続的または連続的に記載証明する目的で作成された「帳簿」であると判断。以上の点を踏まえ裁判所は、原告企業が保管していた伝票綴りは「判取帳」に該当するとしたうえで、印紙税過怠税賦課決定処分は適法であると結論付けた。
返金伝票綴りは印紙税の対象、過怠税めぐり企業側敗訴
日用雑貨などの販売業を営む原告企業が作成および保管していた「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税の課税対象となる「判取帳」に該当するか否かが問題となった裁判で、原告企業が敗訴する判決が下された(東京地裁平成27年12月18日判決・敗訴した原告企業は控訴)。裁判所は、3枚複写100組綴りのお客様返金伝票のうち、1枚目(売場控)のみが残った伝票綴りは2以上の相手方(複数の顧客)から付込証明(返金額などを記入)を受ける目的をもって作成されたものである点などから「判取帳」に該当すると判断したうえで、印紙税過怠税(324万円)の賦課決定処分は適法であると結論付けた。
複数の顧客から金銭の受領事実の証明を受けるものか否かが問題に
印紙税の課税対象である「判取帳」は、2以上の相手から金銭の受領事実などの付込証明を受ける目的で作成される帳簿のことで、1冊につき4,000円の印紙税が課税される(表参照)。本件で問題となったのは、日用雑貨などを販売する原告企業が保存していた「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税の課税対象となる「判取帳」に該当するか否かという点だ。原告企業が利用していたお客様返金伝票は、3枚1組複写式の伝票が100組綴られている冊子形態のもの(図参照)。原告企業が返品等受付事務に使用した結果、3枚1組複写のうち2枚目(事務所控)および3枚目(商品貼付用)の伝票は事務所控えなどとするために切り離される一方で、1枚目の伝票(売場控)には伝票綴りから分離するための切取り線がなく、冊子形態の伝票綴りに綴られた状態で保管されていた。
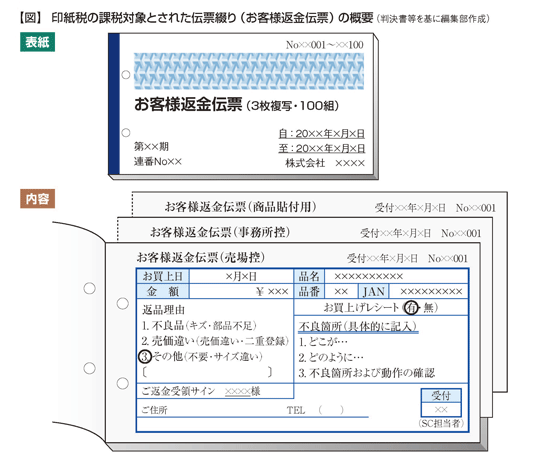
| 【表】印紙税法別表第一 課税物件表(編注・一部簡略化) |
| 番 号 | 課税物件 | 課税標準および税率 | |
| 物件名 | 定 義 | ||
| 二十 | 判取帳 | 1 判取帳とは、第十七号(金銭の受取書など)等に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。 | 一冊につき 四千円 |
原告企業が保有していた270冊(3年間分)の伝票綴りに対し税務署は、印紙税が課税される「判取帳」に該当すると判断したうえで、印紙税が納付されていないことを理由に過怠税324万円の賦課決定処分を行った。
これを不服とする原告企業は、裁判のなかで、①お客様返金伝票(売場控)が綴られた伝票綴りは印紙税の課税単位となる「一の文書」に該当しないこと、②2以上の相手から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されたものではないこと、③印紙税法上の帳簿に該当しないことなどを指摘したうえで、原告企業が保管していた伝票綴りは「判取帳」には該当しないと主張した。
裁判所は、まず、①伝票綴りの冊子の表紙には綴られた100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載されていること、②お客様返金伝票の1枚目(売場控)は切り離されずに保管・管理されていたこと等を踏まえ、お客様返金伝票(売場控)のみが残された伝票綴りは1冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められることから、その伝票綴り全体をもって「一の文書」に該当すると判断した。
次に、伝票の文書自体の形式・内容のほか、使用方法および使用実態の諸点からみて、伝票綴りは複数の顧客から金銭の受領の事実につき付込証明を受ける目的で作成されたものであると認定したうえで、伝票綴りは「第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成」(課税物件表20号)されたものであると判断した。
そして、伝票綴りは店舗で多数回発生する商取引(販売商品の返金など)に関して金銭の受領事実という課税事項を継続的または連続的に記載証明する目的で作成された「帳簿」であると判断。以上の点を踏まえ裁判所は、原告企業が保管していた伝票綴りは「判取帳」に該当するとしたうえで、印紙税過怠税賦課決定処分は適法であると結論付けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















