資料2016年07月04日 【重要資料】 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(2016年7月4日号・№649)
重要資料
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成28年4月6日付課評2-10ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成28年4月6日付課評2-12ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
1 取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)
1 従来の取扱い 取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式により計算することとしている。
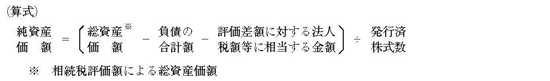
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という。)として「38%」を乗じて計算した金額としていた。
2 通達改正の概要等
(1)法人税の税率の改正の内容 平成28年度税制改正により、法人税率が23.9%から23.4%(注)に引き下げられ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。
(注)所得税法等の一部を改正する法律第2条に基づく改正後の法人税率は23.2%であるが、同法附則第26条により、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度における法人税率は23.4%とされている。
(2)通達改正の概要 上記(1)の改正により、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、「法人税率等の合計割合」を「38%」から「37%」に改正することとした。
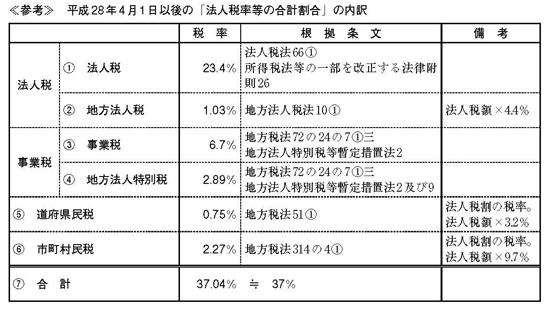
(3)明細書通達の改正 本改正に伴い、次の評価明細書における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄について改正した。
・ 「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
・ 「第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」
(4)適用時期 平成28年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとした。
2 利付公社債の評価等
1 従来の取扱い 利付公社債については、以下の(1)から(3)に分類した上で、各々以下のとおり評価することとしている。
(1)金融商品取引所に上場されているもの
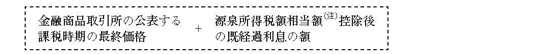
(注)源泉所得税額相当額には、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下(2)及び(3)について同じ。
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたもの((1)に該当するものを除く。)
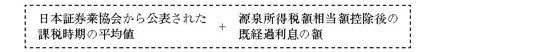
(3)(1)又は(2)に掲げる以外のもの
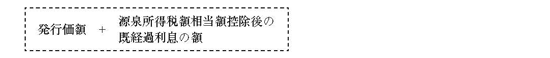
2 通達改正の概要等
(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し) 平成25年度税制改正により、地方税(道府県民税)に関し、平成28年1月1日以後に受ける特定公社債等(注)の利子等に係る所得については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされた(地方税法23①十四・十五、71の31)。
(注)特定公社債等とは、特定公社債(特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などの一定の公社債をいう。)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権のことをいう。
(2)通達改正の概要 利付公社債については、上記(1)の税制改正により、平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る所得に対して課される道府県民税に関し、利子割に加えて配当割が含まれることとされたことから、利付公社債の評価について「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」に含むこととしている「特別徴収されるべき道府県民税」に、配当割も含まれるよう、「特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額」を「特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額」と改正することとした。
また、評価通達において「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」を控除することとしている他の財産についても同様に取り扱うことを明確にした。
(3)適用時期 平成28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとした。
3 割引発行の公社債の評価
1 従来の取扱い 割引発行の公社債の評価については、次に掲げる区分に従い、原則として市場価額を基に評価することとしている。
(1)金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)
(3)(1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債
2 通達改正の概要等
(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し) 従来、割引債の償還差益に係る所得に対する課税については、割引債の発行時に源泉徴収することとされており、個人については他の所得と分離して源泉徴収のみで課税が終了する源泉分離課税とされ、割引債の譲渡所得は非課税とされていたが、平成25年度税制改正により、割引債を含む公社債の譲渡による譲渡所得に対して所得税を課税することとされたことに伴い、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益に係る所得税の源泉徴収については発行時ではなく、利付公社債の利子と同様に償還時に行うこととされた(租税特別措置法41の12の2)。
(2)通達改正の概要 従来、割引発行の公社債の償還差益に係る所得税相当額は発行時に源泉徴収されていたため、評価通達上、当該所得税相当額に係る取扱いは明記されていない。
今般の改正を受けて、割引発行の公社債の償還差益に係る源泉所得税相当額が、発行時ではなく償還時に源泉徴収がなされる場合が生じることとなることから、このような場合の償還差益に係る源泉所得税相当額については、評価上、考慮する必要があるものと考えられる。
そこで、割引発行の公社債の評価について、差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価することとした。
(3)適用時期 平成28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとした。
| 資産評価企画官情報 資産課税課情報 | 第1号 第13号 | 平成28年5月20日 | 国税庁 資産評価企画官 資産課税課 |
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成28年4月6日付課評2-10ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成28年4月6日付課評2-12ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
1 取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)
| 平成28年度税制改正において、法人税率の改正が行われたことに伴い、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」を38%から37%に改正するなど所要の改正を行った。(評価通達186-2、明細書通達=改正) |
1 従来の取扱い 取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式により計算することとしている。
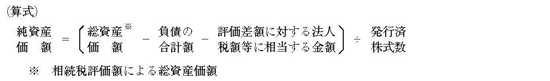
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という。)として「38%」を乗じて計算した金額としていた。
2 通達改正の概要等
(1)法人税の税率の改正の内容 平成28年度税制改正により、法人税率が23.9%から23.4%(注)に引き下げられ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。
(注)所得税法等の一部を改正する法律第2条に基づく改正後の法人税率は23.2%であるが、同法附則第26条により、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度における法人税率は23.4%とされている。
(2)通達改正の概要 上記(1)の改正により、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、「法人税率等の合計割合」を「38%」から「37%」に改正することとした。
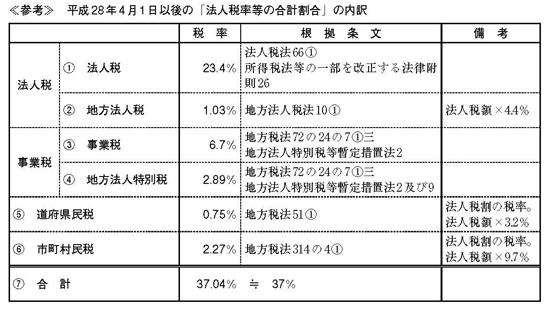
(3)明細書通達の改正 本改正に伴い、次の評価明細書における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄について改正した。
・ 「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
・ 「第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」
(4)適用時期 平成28年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとした。
2 利付公社債の評価等
| 平成25年度税制改正において、公社債等に係る所得に対する道府県民税の課税方式が見直され、平成28年1月1日以後に受ける特定公社債等の利子等に係る所得については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされたことから、利付公社債の評価等について、「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」に含むこととしている「特別徴収されるべき道府県民税」に利子割の額のみならず配当割の額に相当する金額も含まれるよう所要の改正を行った。 (評価通達193、197-2=改正) |
1 従来の取扱い 利付公社債については、以下の(1)から(3)に分類した上で、各々以下のとおり評価することとしている。
(1)金融商品取引所に上場されているもの
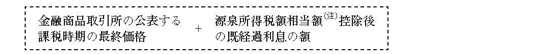
(注)源泉所得税額相当額には、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下(2)及び(3)について同じ。
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたもの((1)に該当するものを除く。)
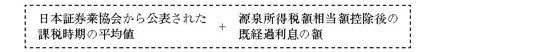
(3)(1)又は(2)に掲げる以外のもの
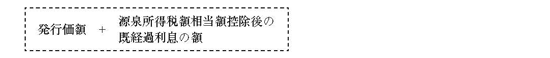
2 通達改正の概要等
(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し) 平成25年度税制改正により、地方税(道府県民税)に関し、平成28年1月1日以後に受ける特定公社債等(注)の利子等に係る所得については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされた(地方税法23①十四・十五、71の31)。
(注)特定公社債等とは、特定公社債(特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などの一定の公社債をいう。)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権のことをいう。
(2)通達改正の概要 利付公社債については、上記(1)の税制改正により、平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る所得に対して課される道府県民税に関し、利子割に加えて配当割が含まれることとされたことから、利付公社債の評価について「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」に含むこととしている「特別徴収されるべき道府県民税」に、配当割も含まれるよう、「特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額」を「特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額」と改正することとした。
また、評価通達において「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」を控除することとしている他の財産についても同様に取り扱うことを明確にした。
(3)適用時期 平成28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとした。
3 割引発行の公社債の評価
| 平成25年度税制改正において、公社債等に係る所得に対する所得税の課税方式が見直され、平成28年1月1日以後に発行される割引発行の公社債の償還差益に係る源泉徴収は、発行時ではなく償還時に行うこととされたことから、割引発行の公社債の評価について、割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を控除した金額によって評価する所要の改正を行った。 (評価通達197-3=改正) |
1 従来の取扱い 割引発行の公社債の評価については、次に掲げる区分に従い、原則として市場価額を基に評価することとしている。
(1)金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)
(3)(1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債
2 通達改正の概要等
(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し) 従来、割引債の償還差益に係る所得に対する課税については、割引債の発行時に源泉徴収することとされており、個人については他の所得と分離して源泉徴収のみで課税が終了する源泉分離課税とされ、割引債の譲渡所得は非課税とされていたが、平成25年度税制改正により、割引債を含む公社債の譲渡による譲渡所得に対して所得税を課税することとされたことに伴い、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益に係る所得税の源泉徴収については発行時ではなく、利付公社債の利子と同様に償還時に行うこととされた(租税特別措置法41の12の2)。
(2)通達改正の概要 従来、割引発行の公社債の償還差益に係る所得税相当額は発行時に源泉徴収されていたため、評価通達上、当該所得税相当額に係る取扱いは明記されていない。
今般の改正を受けて、割引発行の公社債の償還差益に係る源泉所得税相当額が、発行時ではなく償還時に源泉徴収がなされる場合が生じることとなることから、このような場合の償還差益に係る源泉所得税相当額については、評価上、考慮する必要があるものと考えられる。
そこで、割引発行の公社債の評価について、差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価することとした。
(3)適用時期 平成28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















