解説記事2016年09月26日 【税務マエストロ】 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(2)(2016年9月26日号・№660)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(2)
#173 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#174 日本・台湾租税協定と国内法の整備④
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 前月号では、自販機を利用した消費税の還付スキームに対する平成22年度改正法による対応を確認した。今月は、平成22年度改正法の弊害と問題点(抜け穴)について確認する。
1 届出書が無効とされるケース
(1)課税事業者選択不適用届出書 課税選択の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできないこととされている。
そこで、課税選択の強制適用期間中に、翌期から免税事業者となるために「課税事業者選択不適用届出書」を提出した事業者が、その後、同一の課税期間中に調整対象固定資産を取得することとなったような場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされる(消法9⑦)。
【具体例1】課税事業者を選択した個人事業者が、「課税事業者選択不適用届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合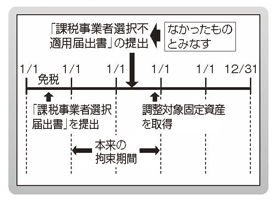
ちなみに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」には次のような欄が設けられている。
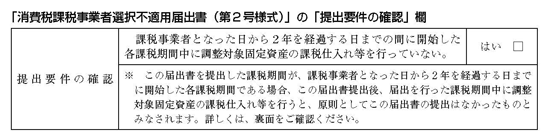
要するに、課税選択の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、「課税事業者選択不適用届出書」の提出に制限があるので、調整対象固定資産の取得状況を確認のうえ、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなさいということである。
しかし、前記【具体例1】のケースでは、「課税事業者選択不適用届出書」を提出した時点では調整対象固定資産を取得していないのであるから、現実問題として考えた場合、税務署側でのチェックは相当に難しいように感じられる。結果、事後のトラブルを防止するためには、納税者が届出書の提出状況と調整対象固定資産の取得状況を確認し、速やかに「取り下げ願い」を提出して提出済の届出書を取り下げるなどの措置が必要となるのである。
法律の辻褄合わせのためだけに、実務が悪戯に煩雑になったことについて、課税庁は何も責任を感じていないのであろうか?
(2)簡易課税制度選択届出書 課税選択をした事業者や資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人が、課税事業者としての強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの間は「簡易課税制度選択届出書」を提出することができない(消法37③)。
【具体例2】新設法人が、3期目から簡易課税制度の適用を受けるため、2期目に「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合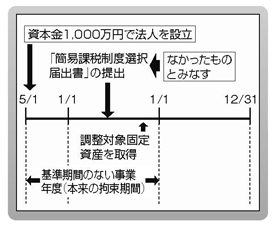
【具体例3】新設法人が、1期目から簡易課税制度の適用を受けるため、1期目に「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合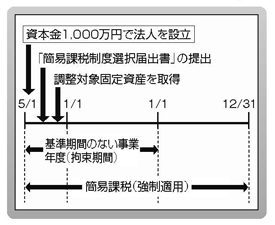
「簡易課税制度選択届出書」の提出後に調整対象固定資産を取得した場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされる(消法37④)。
なお、新設法人などについては、届出書の提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが認められている。このような場合には、「簡易課税制度選択届出書」を提出した後で調整対象固定資産を取得した場合であっても、みなし仕入率により仕入控除税額を計算するため、その届出書の効力は当然に有効となる(消法37②ただし書、消令56②)。
ちなみに、「消費税簡易課税制度選択届出書」には下記のような欄が設けられている。
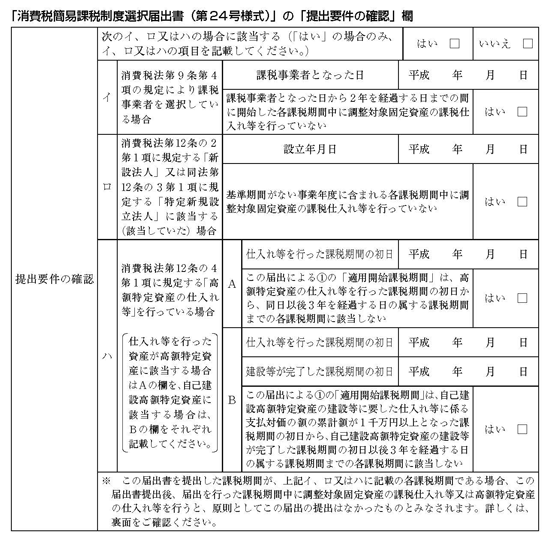
要するに、課税選択をした資本金1,000万円未満の新設法人や、設立事業年度から納税義務者となる資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人が、課税事業者としての強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、「簡易課税制度選択届出書」の提出に制限があるので、調整対象固定資産の取得状況を確認のうえ、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなさいということである。
しかし、前記【具体例2】のケースでは、「簡易課税制度選択届出書」を提出した時点では調整対象固定資産を取得していないのであるから、現実問題として考えた場合、税務署側でのチェックは相当に難しいように感じられる。結果、事後のトラブルを防止するためには、納税者が届出書の提出状況と調整対象固定資産の取得状況を確認し、速やかに「取り下げ願い」を提出して提出済の届出書を取り下げるなどの措置が必要となるのである。
実務の現場において、計算が簡単だからという理由だけで簡易課税を選択する事業者は皆無に等しいはずである。あらかたの中小事業者は、本則計算と簡易課税を天秤にかけ、簡易課税が有利だから簡易課税を選択しているのである。
「簡易課税制度選択届出書」を取り下げないままに簡易課税で申告納付をし、数年経ってから届出書の取り下げを指導されて本則課税により修正申告することになったらどうであろう……騙し討ちを喰らったような印象を受けるのは決して筆者だけではあるまい。
2 22年度改正法の問題点 22年度改正法により、下記①~③の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(第三年度の課税期間)までの間は本則課税が強制適用となる。
22年度改正法は、①の課税選択のケースであれば強制適用期間中、②・③の新設法人のケースであれば基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産を取得した場合でなければ適用することができない。また、取得資産が棚卸資産であれば、どんなに高額な資産であっても22年度改正法は適用されないことになる。
結果、抜け穴だらけの22年度改正法の隙間をつくように、次の①~④のような節税スキームが横行したことが、28年度改正に繋がったものと思われる。
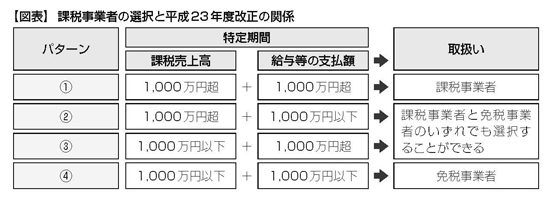
パターン①で課税事業者となる場合とパターン②~③のケースで課税事業者を選択する場合には、第3-(2)号様式(消費税課税事業者届出書 )を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。
)を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。
ただし、「課税事業者選択届出書」のように提出期限が定められたものではない。
「課税事業者選択届出書」は原則として事前提出が義務付けられているにもかかわらず、「課税事業者届出書」には期限がなく、さらには「3年縛り」も適用されないことに違和感を感じているのは筆者だけであろうか……?
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
今週のマエストロ&テーマ
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(2)
#173 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#174 日本・台湾租税協定と国内法の整備④
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 前月号では、自販機を利用した消費税の還付スキームに対する平成22年度改正法による対応を確認した。今月は、平成22年度改正法の弊害と問題点(抜け穴)について確認する。
1 届出書が無効とされるケース
(1)課税事業者選択不適用届出書 課税選択の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできないこととされている。
そこで、課税選択の強制適用期間中に、翌期から免税事業者となるために「課税事業者選択不適用届出書」を提出した事業者が、その後、同一の課税期間中に調整対象固定資産を取得することとなったような場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされる(消法9⑦)。
【具体例1】課税事業者を選択した個人事業者が、「課税事業者選択不適用届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合
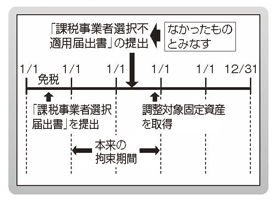
ちなみに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」には次のような欄が設けられている。
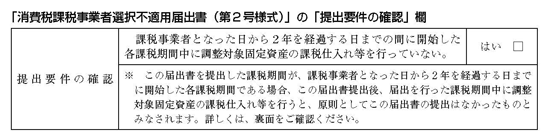
要するに、課税選択の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、「課税事業者選択不適用届出書」の提出に制限があるので、調整対象固定資産の取得状況を確認のうえ、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなさいということである。
しかし、前記【具体例1】のケースでは、「課税事業者選択不適用届出書」を提出した時点では調整対象固定資産を取得していないのであるから、現実問題として考えた場合、税務署側でのチェックは相当に難しいように感じられる。結果、事後のトラブルを防止するためには、納税者が届出書の提出状況と調整対象固定資産の取得状況を確認し、速やかに「取り下げ願い」を提出して提出済の届出書を取り下げるなどの措置が必要となるのである。
法律の辻褄合わせのためだけに、実務が悪戯に煩雑になったことについて、課税庁は何も責任を感じていないのであろうか?
(2)簡易課税制度選択届出書 課税選択をした事業者や資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人が、課税事業者としての強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの間は「簡易課税制度選択届出書」を提出することができない(消法37③)。
【具体例2】新設法人が、3期目から簡易課税制度の適用を受けるため、2期目に「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合
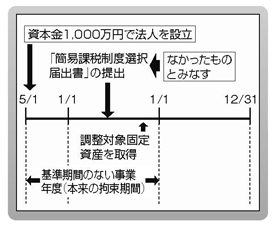
【具体例3】新設法人が、1期目から簡易課税制度の適用を受けるため、1期目に「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得した場合
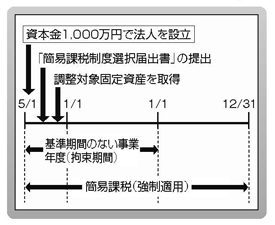
「簡易課税制度選択届出書」の提出後に調整対象固定資産を取得した場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされる(消法37④)。
なお、新設法人などについては、届出書の提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが認められている。このような場合には、「簡易課税制度選択届出書」を提出した後で調整対象固定資産を取得した場合であっても、みなし仕入率により仕入控除税額を計算するため、その届出書の効力は当然に有効となる(消法37②ただし書、消令56②)。
ちなみに、「消費税簡易課税制度選択届出書」には下記のような欄が設けられている。
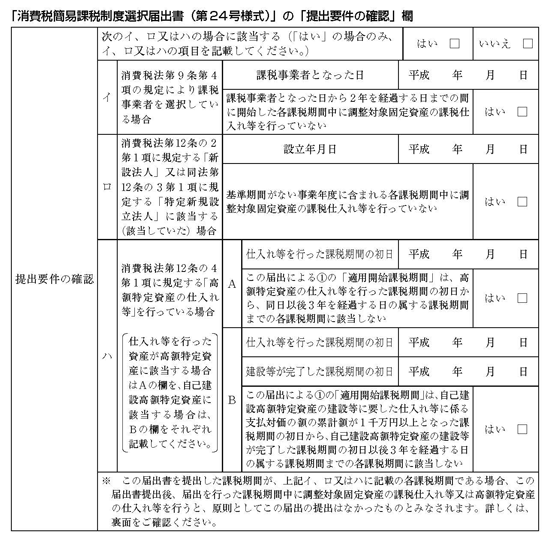
要するに、課税選択をした資本金1,000万円未満の新設法人や、設立事業年度から納税義務者となる資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人が、課税事業者としての強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、「簡易課税制度選択届出書」の提出に制限があるので、調整対象固定資産の取得状況を確認のうえ、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなさいということである。
しかし、前記【具体例2】のケースでは、「簡易課税制度選択届出書」を提出した時点では調整対象固定資産を取得していないのであるから、現実問題として考えた場合、税務署側でのチェックは相当に難しいように感じられる。結果、事後のトラブルを防止するためには、納税者が届出書の提出状況と調整対象固定資産の取得状況を確認し、速やかに「取り下げ願い」を提出して提出済の届出書を取り下げるなどの措置が必要となるのである。
実務の現場において、計算が簡単だからという理由だけで簡易課税を選択する事業者は皆無に等しいはずである。あらかたの中小事業者は、本則計算と簡易課税を天秤にかけ、簡易課税が有利だから簡易課税を選択しているのである。
「簡易課税制度選択届出書」を取り下げないままに簡易課税で申告納付をし、数年経ってから届出書の取り下げを指導されて本則課税により修正申告することになったらどうであろう……騙し討ちを喰らったような印象を受けるのは決して筆者だけではあるまい。
2 22年度改正法の問題点 22年度改正法により、下記①~③の期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(第三年度の課税期間)までの間は本則課税が強制適用となる。
| ① 課税選択をした事業者の強制適用期間 ② 資本金1,000万円以上の新設法人の基準期間がない事業年度(設立事業年度とその翌事業年度) ③ 特定新規設立法人の基準期間がない事業年度(設立事業年度とその翌事業年度) |
結果、抜け穴だらけの22年度改正法の隙間をつくように、次の①~④のような節税スキームが横行したことが、28年度改正に繋がったものと思われる。
| ① 建物などの高額な棚卸資産を取得し、本則課税により消費税の還付を受けた期の翌期に資産を売却し、簡易課税制度の適用を受けるような事例 ② 課税事業者の強制適用期間を経過してから固定資産を取得することにより、その翌期は免税事業者や簡易課税適用事業者となるような事例 ③ 資本金1,000万円以上の法人を設立し、基準期間がない事業年度を経過してから固定資産を取得することにより、その翌期は免税事業者や簡易課税適用事業者となるような事例 ④ 特定期間中の課税売上高と給与等の支払額のいずれかが1,000万円を超える場合には、課税事業者を選択せずとも課税事業者となることができる。 結果、課税事業者届出書(特定期間用)を提出して課税事業者となり、固定資産を取得しても、いわゆる「3年縛り」の規定は適用されないため、その翌期は免税事業者や簡易課税適用事業者となるような事例 |
(事例1)棚卸資産を取得するケース
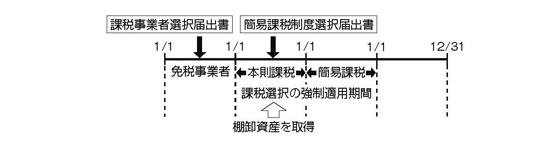
(事例2)新設法人が課税選択をして固定資産を取得するケース
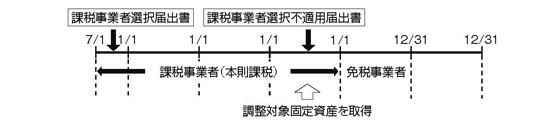
(事例3)新設法人が3期目に固定資産を取得するケース
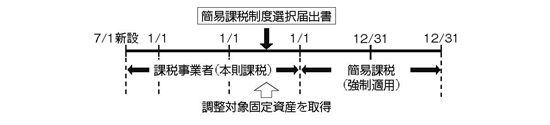
(事例4)簡易課税適用事業者が固定資産を取得するケース
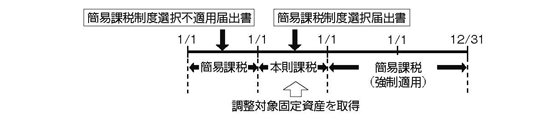 (事例5)課税事業者届出書(特定期間用)を提出して固定資産を取得するケース
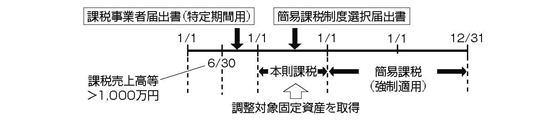 |
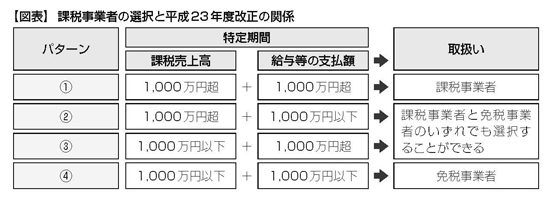
パターン①で課税事業者となる場合とパターン②~③のケースで課税事業者を選択する場合には、第3-(2)号様式(消費税課税事業者届出書
 )を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。
)を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。ただし、「課税事業者選択届出書」のように提出期限が定められたものではない。
「課税事業者選択届出書」は原則として事前提出が義務付けられているにもかかわらず、「課税事業者届出書」には期限がなく、さらには「3年縛り」も適用されないことに違和感を感じているのは筆者だけであろうか……?
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















