解説記事2016年10月10日 【SCOPE】 外国子会社合算税制の見直しの方向性が明らかに(2016年10月10日号・№662)
対象地域を拡大、経済実体なければ合算対象に
外国子会社合算税制の見直しの方向性が明らかに
平成29年度税制改正での実現が確実視されている「外国子会社合算税制」の見直しの方向性が政府税制調査(9月29日開催)で示された。財務省が明らかにした内容は、トリガー税率が20%未満の外国子会社等のすべての所得を親会社の合算対象とする現行制度について、新たに外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象か否かを判断するというもの。これにより、トリガー税率20%以上の外国子会社であっても「一定の金融所得や実質的活動のない事業から生じた所得等」(受動的所得)が日本の親会社の合算対象とされる一方で、実体のある事業から生じた所得(能動的所得)であれば合算の対象外となる。また、対象地域の拡大などによる企業の事務負担増に配慮するため、現行のトリガー税率を代替・補完する「制度適用免除基準」を検討・設定されることも明らかとなった。
トリガー税率に代わる制度適用免除基準を設定し、企業の事務負担増に配慮
日本の「外国子会社合算税制」は、租税負担割合(トリガー税率)が20%未満の外国子会社等のすべての所得について日本の親会社の所得に合算して課税するというもの。
ただし、外国子会社等に経済活動の実体があり、4つの「適用除外基準」(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④所在地国基準又は非関連者基準)を満たす場合は外国子会社合算税制の適用対象外となる。
税率20%以上であっても合算課税の対象に 現行の制度で財務省が問題としているものの1つは、外国子会社のトリガー税率が20%以上であれば、その経済実体を伴わない所得であっても親会社の所得に合算されないという点だ。
この問題に対応するために財務省が政府税制調査会で示した見直しの方向性は、外国子会社等のすべての所得を親会社の合算対象とする現行の事業体アプローチに代えて、外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象を決定するというアプローチを新たに採用するというもの。
具体的には、子会社自らが取り組む商品の製造・販売やサービスの提供による対価の獲得等の経済実体がある事業から得た所得を「能動的所得」として、外国子会社合算税制の適用対象外(子会社所在地国で課税)とする。一方で、一定の金融所得や実質的活動のない事業から得られる所得などは経済実体がない「受動的所得」として、外国子会社合算税制の適用対象(日本で課税)とする。
また、企業に過度の事務負担が生じないように配慮するために、現行のトリガー税率を代替・補完する「制度適用免除基準」を検討・設定する。
財務省の提案に対し会合の出席委員から
は、見直しの方向性に正面から反対する意見は見られなかったものの、「受動的所得」と「能動的所得」の定義や判断が課題となるという意見や制度の複雑化などを懸念する意見が相次いだ。
会合後の記者会見で中里会長は、受動的所得と能動的所得の区分について「区分は難しいが外国では対応しているので、できることだと思います」と話すとともに、「過度に複雑化してしまうと企業を苦しめるだけですから、その点は十分に配慮したいと思います」と話し、次回以降の会合で外国子会社合算税制の見直しに関する議論を継続する方針を示した。
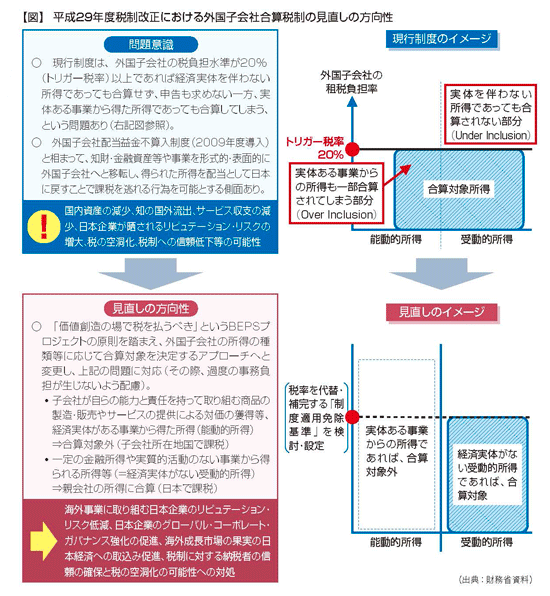
外国子会社合算税制の見直しの方向性が明らかに
平成29年度税制改正での実現が確実視されている「外国子会社合算税制」の見直しの方向性が政府税制調査(9月29日開催)で示された。財務省が明らかにした内容は、トリガー税率が20%未満の外国子会社等のすべての所得を親会社の合算対象とする現行制度について、新たに外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象か否かを判断するというもの。これにより、トリガー税率20%以上の外国子会社であっても「一定の金融所得や実質的活動のない事業から生じた所得等」(受動的所得)が日本の親会社の合算対象とされる一方で、実体のある事業から生じた所得(能動的所得)であれば合算の対象外となる。また、対象地域の拡大などによる企業の事務負担増に配慮するため、現行のトリガー税率を代替・補完する「制度適用免除基準」を検討・設定されることも明らかとなった。
トリガー税率に代わる制度適用免除基準を設定し、企業の事務負担増に配慮
日本の「外国子会社合算税制」は、租税負担割合(トリガー税率)が20%未満の外国子会社等のすべての所得について日本の親会社の所得に合算して課税するというもの。
ただし、外国子会社等に経済活動の実体があり、4つの「適用除外基準」(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④所在地国基準又は非関連者基準)を満たす場合は外国子会社合算税制の適用対象外となる。
税率20%以上であっても合算課税の対象に 現行の制度で財務省が問題としているものの1つは、外国子会社のトリガー税率が20%以上であれば、その経済実体を伴わない所得であっても親会社の所得に合算されないという点だ。
この問題に対応するために財務省が政府税制調査会で示した見直しの方向性は、外国子会社等のすべての所得を親会社の合算対象とする現行の事業体アプローチに代えて、外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象を決定するというアプローチを新たに採用するというもの。
具体的には、子会社自らが取り組む商品の製造・販売やサービスの提供による対価の獲得等の経済実体がある事業から得た所得を「能動的所得」として、外国子会社合算税制の適用対象外(子会社所在地国で課税)とする。一方で、一定の金融所得や実質的活動のない事業から得られる所得などは経済実体がない「受動的所得」として、外国子会社合算税制の適用対象(日本で課税)とする。
また、企業に過度の事務負担が生じないように配慮するために、現行のトリガー税率を代替・補完する「制度適用免除基準」を検討・設定する。
財務省の提案に対し会合の出席委員から
は、見直しの方向性に正面から反対する意見は見られなかったものの、「受動的所得」と「能動的所得」の定義や判断が課題となるという意見や制度の複雑化などを懸念する意見が相次いだ。
会合後の記者会見で中里会長は、受動的所得と能動的所得の区分について「区分は難しいが外国では対応しているので、できることだと思います」と話すとともに、「過度に複雑化してしまうと企業を苦しめるだけですから、その点は十分に配慮したいと思います」と話し、次回以降の会合で外国子会社合算税制の見直しに関する議論を継続する方針を示した。
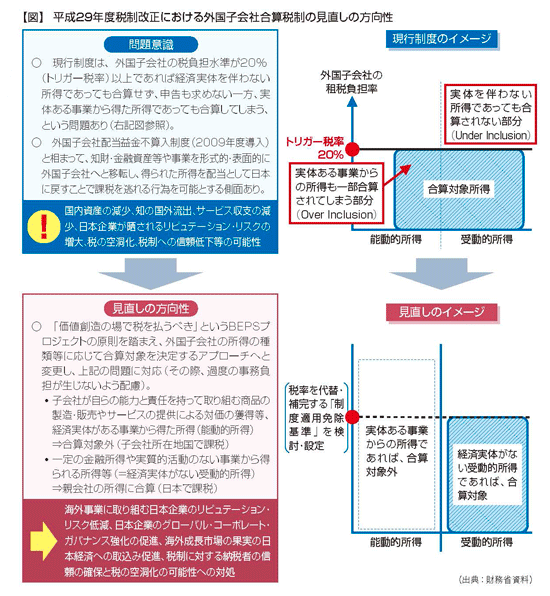
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























