解説記事2016年10月17日 【ニュース特集】 仮装隠ぺいと重加算税をめぐる最近の裁決事例(2016年10月17日号・№663)
ニュース特集
課税仕入の期ずれや相続財産の申告漏れで重加算税取消し
仮装隠ぺいと重加算税をめぐる最近の裁決事例
期ずれなどの経理ミスや申告漏れが税務調査のなかで発覚した場合にしばしば問題となるのは、それが重加算税の対象となる「仮装隠ぺい行為」に該当するか否かという点だ。
本特集では、納税者(請求人)の行為を仮装隠ぺいと認定した税務署の重加算税賦課決定処分が国税不服審判所によって取り消された最近の裁決事例を2つ紹介する。
1つめは、太陽光発電設備の取得費に関する課税仕入の計上時期をめぐる重加算税が取り消されたもの。そしてもう1つの事例は、相続財産である預金口座の一部を「相続についてのお尋ね」の回答書に記載しなかった相続人に対する重加算税が取り消されたものだ。
審判所、請求書作成をもって納税者が引渡日を仮装したとは認められず
最初に紹介する事例は、太陽光発電設備の取得費をその引き渡しがあった課税期間ではなく、その直前の課税期間で課税仕入とした請求人の行為が重加算税の対象となる仮装行為に該当するか否かが問題となったものだ。
法人である請求人(自然エネルギー等による発電・電気の供給及び販売等が主な事業)は、A社に対し太陽光発電設備に関する設置工事を約2億7千万円で発注し(平成26年9月30日)、その取得費を本件課税期間(26年3月期)の課税仕入としていた。
請求人が消費税の確定申告書と共に提出した添付書面には、A社を発行者とする平成26年1月31日付の本件請求書が添付されていたものの、この請求書は請求人が作成したもので、欄外に補足として「工事完了は3月31日までとする。」と記載されていた。そして太陽光発電設備に関する設置工事は平成26年7月15日に完了。請求人は同日、A社から引渡しを受けていた(図参照)。
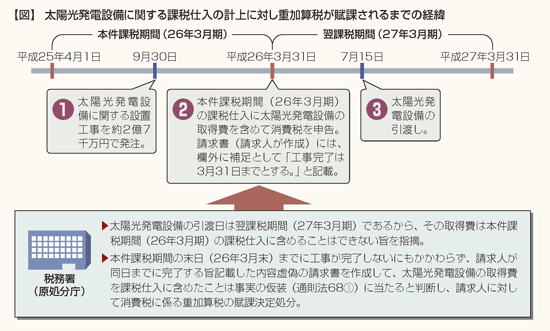
この請求人の行為に対し原処分庁は、請求人は消費税の還付を早く受けたいがために本件課税期間(26年3月期)に太陽光発電設備が完成していないことを十分認識していたにもかかわらず、設置工事が26年3月末までに完了する旨記載した内容虚偽の本件請求書を作成し、太陽光発電設備の取得費を本件課税期間の課税仕入に含めたと指摘。また、内容虚偽の本件請求書を作成した請求人の行為は太陽光発電設備の引き渡しを受けた日を仮装したものというべきであると指摘したうえで、請求人に対する消費税等に係る重加算税の賦課決定処分は適法である旨を主張した。
これに対し国税不服審判所は、本件請求書はあくまで工事代金を請求する書面であって太陽光発電設備の引き渡しに関する書面ではないうえ、本件請求書が平成26年1月31日付で作成されていることからすれば「工事完了は3月31日までとする。」との記載は工事完了の予定日が記載されたものとみるほかないと指摘。また、本件全証拠資料を精査しても、本件請求書が平成26年3月期終了後に日付を遡って作成されたなどの事情は見いだせないなどと指摘した。そのうえで審判所は、請求人が本件請求書を作成したことをもって請求人が太陽光発電設備の引き渡しを受けた日を仮装したとは到底認めることはできないと判断。請求人に対する消費税等に係る重加算税の賦課決定処分を取り消した(平成28年4月19日・関裁(諸)平27第53号)。
預金口座を相続人名義に預け替えただけでは“仮装隠ぺい”と評価できず
次に紹介する事例は、相続財産である預金の一部を「相続についてのお尋ね」の回答書に記載しなかったなどの請求人の行為が重加算税の対象となる隠ぺい行為に該当するか否かが問題となったものである。
生前に被相続人が同人名義としていた預金口座は、「A口座」、「B口座」、「C口座」の3つで、このうちA口座は年金の入金及び公共料金等の支払いなど生活に通常使用する口座として利用されていた。相続発生後、唯一の相続人である請求人(被相続人の長男)は、B口座及びC口座(以下「本件各口座」)について請求人への相続手続き(請求人名義口座への移管)を行ったものの、申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった。
お尋ね回答書の内容を踏まえ税務調査に着手 請求人は、税務署から送付された「相続についてのお尋ね」に対して、自宅(土地建物)及びA口座のみを相続財産とする「お尋ね回答書」を返送。これに対し税務署は、請求人に対する相続税調査を実施した。
請求人は、調査担当者の質問(B口座に係る相続届の写しを示して何か覚えていないかというもの)に対して、解約手続きを行った旨を申述。この申述後、請求人は、調査担当者の次の質問(他に解約手続きをしたものはないかというもの)に対して、他に解約手続きをしたものはないと申述したものの、調査担当者がC口座に係る相続に関する依頼書の写しを示したうえでなにか覚えていないかと質問したのに対して、はっきりと覚えていないが解約に行ったと申述していた。
この請求人の行為に対し原処分庁は、被相続人は生前、相続税の課税を免れる目的であることを請求人に明示した上で生活に通常使用する口座をA口座のみとし、本件各口座が税務署には容易に知り得ない状況を作出するとともに、請求人に対しA口座以外の口座は申告する必要はないと指示していたと指摘。この被相続人の意図を十分理解した上で請求人は本件各口座の預金を記載しないお尋ね回答書を提出し、調査担当者に対してその記載内容に沿った申述を行った後、税務署にその存在を把握されるに至って調査担当者から指摘を受けた口座についてのみ段階的にこれを認める行為を繰り返したと指摘し、重加算税の賦課決定処分は適法であると主張した。
審判所、計画的な無申告であれば重加対象も 国税不服審判所は、被相続人の唯一の相続人である請求人自らが全部相続したことを前提に本件各口座の預金を相続手続きにより自己名義の預金口座に預け替えたりしたというだけでは請求人が本件各口座の預金を隠ぺい・仮装したと評価するとはできないと指摘。また、調査担当者から本件各口座の相続手続きについて指摘されるとその存在を認めており、本件各口座を隠す態度を一貫していたとはいえない点や相続財産に含まれないように装ったりするなどの積極的な措置を行っていない点を踏まえると、本件各口座の記載のないお尋ね回答書を提出したことや調査の当初は本件各口座の存在を隠していたことをもって隠ぺい・仮装行為と評価することは困難であるなどと指摘した。
以上の点などを踏まえ審判所は、請求人は本件各口座の預金を隠ぺい・秘匿しようという確定的な意図・態勢の下に計画的に申告書を提出しなかったとまでは言えないため、重加算税の賦課要件は満たさないと判断。請求人に対する重加算税の賦課決定処分を取り消した(平成28年4月25日・東裁(諸)平27第129号)。
課税仕入の期ずれや相続財産の申告漏れで重加算税取消し
仮装隠ぺいと重加算税をめぐる最近の裁決事例
期ずれなどの経理ミスや申告漏れが税務調査のなかで発覚した場合にしばしば問題となるのは、それが重加算税の対象となる「仮装隠ぺい行為」に該当するか否かという点だ。
本特集では、納税者(請求人)の行為を仮装隠ぺいと認定した税務署の重加算税賦課決定処分が国税不服審判所によって取り消された最近の裁決事例を2つ紹介する。
1つめは、太陽光発電設備の取得費に関する課税仕入の計上時期をめぐる重加算税が取り消されたもの。そしてもう1つの事例は、相続財産である預金口座の一部を「相続についてのお尋ね」の回答書に記載しなかった相続人に対する重加算税が取り消されたものだ。
審判所、請求書作成をもって納税者が引渡日を仮装したとは認められず
最初に紹介する事例は、太陽光発電設備の取得費をその引き渡しがあった課税期間ではなく、その直前の課税期間で課税仕入とした請求人の行為が重加算税の対象となる仮装行為に該当するか否かが問題となったものだ。
法人である請求人(自然エネルギー等による発電・電気の供給及び販売等が主な事業)は、A社に対し太陽光発電設備に関する設置工事を約2億7千万円で発注し(平成26年9月30日)、その取得費を本件課税期間(26年3月期)の課税仕入としていた。
請求人が消費税の確定申告書と共に提出した添付書面には、A社を発行者とする平成26年1月31日付の本件請求書が添付されていたものの、この請求書は請求人が作成したもので、欄外に補足として「工事完了は3月31日までとする。」と記載されていた。そして太陽光発電設備に関する設置工事は平成26年7月15日に完了。請求人は同日、A社から引渡しを受けていた(図参照)。
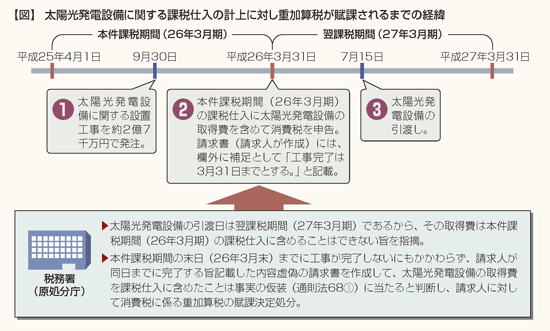
この請求人の行為に対し原処分庁は、請求人は消費税の還付を早く受けたいがために本件課税期間(26年3月期)に太陽光発電設備が完成していないことを十分認識していたにもかかわらず、設置工事が26年3月末までに完了する旨記載した内容虚偽の本件請求書を作成し、太陽光発電設備の取得費を本件課税期間の課税仕入に含めたと指摘。また、内容虚偽の本件請求書を作成した請求人の行為は太陽光発電設備の引き渡しを受けた日を仮装したものというべきであると指摘したうえで、請求人に対する消費税等に係る重加算税の賦課決定処分は適法である旨を主張した。
これに対し国税不服審判所は、本件請求書はあくまで工事代金を請求する書面であって太陽光発電設備の引き渡しに関する書面ではないうえ、本件請求書が平成26年1月31日付で作成されていることからすれば「工事完了は3月31日までとする。」との記載は工事完了の予定日が記載されたものとみるほかないと指摘。また、本件全証拠資料を精査しても、本件請求書が平成26年3月期終了後に日付を遡って作成されたなどの事情は見いだせないなどと指摘した。そのうえで審判所は、請求人が本件請求書を作成したことをもって請求人が太陽光発電設備の引き渡しを受けた日を仮装したとは到底認めることはできないと判断。請求人に対する消費税等に係る重加算税の賦課決定処分を取り消した(平成28年4月19日・関裁(諸)平27第53号)。
預金口座を相続人名義に預け替えただけでは“仮装隠ぺい”と評価できず
次に紹介する事例は、相続財産である預金の一部を「相続についてのお尋ね」の回答書に記載しなかったなどの請求人の行為が重加算税の対象となる隠ぺい行為に該当するか否かが問題となったものである。
生前に被相続人が同人名義としていた預金口座は、「A口座」、「B口座」、「C口座」の3つで、このうちA口座は年金の入金及び公共料金等の支払いなど生活に通常使用する口座として利用されていた。相続発生後、唯一の相続人である請求人(被相続人の長男)は、B口座及びC口座(以下「本件各口座」)について請求人への相続手続き(請求人名義口座への移管)を行ったものの、申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった。
お尋ね回答書の内容を踏まえ税務調査に着手 請求人は、税務署から送付された「相続についてのお尋ね」に対して、自宅(土地建物)及びA口座のみを相続財産とする「お尋ね回答書」を返送。これに対し税務署は、請求人に対する相続税調査を実施した。
請求人は、調査担当者の質問(B口座に係る相続届の写しを示して何か覚えていないかというもの)に対して、解約手続きを行った旨を申述。この申述後、請求人は、調査担当者の次の質問(他に解約手続きをしたものはないかというもの)に対して、他に解約手続きをしたものはないと申述したものの、調査担当者がC口座に係る相続に関する依頼書の写しを示したうえでなにか覚えていないかと質問したのに対して、はっきりと覚えていないが解約に行ったと申述していた。
この請求人の行為に対し原処分庁は、被相続人は生前、相続税の課税を免れる目的であることを請求人に明示した上で生活に通常使用する口座をA口座のみとし、本件各口座が税務署には容易に知り得ない状況を作出するとともに、請求人に対しA口座以外の口座は申告する必要はないと指示していたと指摘。この被相続人の意図を十分理解した上で請求人は本件各口座の預金を記載しないお尋ね回答書を提出し、調査担当者に対してその記載内容に沿った申述を行った後、税務署にその存在を把握されるに至って調査担当者から指摘を受けた口座についてのみ段階的にこれを認める行為を繰り返したと指摘し、重加算税の賦課決定処分は適法であると主張した。
審判所、計画的な無申告であれば重加対象も 国税不服審判所は、被相続人の唯一の相続人である請求人自らが全部相続したことを前提に本件各口座の預金を相続手続きにより自己名義の預金口座に預け替えたりしたというだけでは請求人が本件各口座の預金を隠ぺい・仮装したと評価するとはできないと指摘。また、調査担当者から本件各口座の相続手続きについて指摘されるとその存在を認めており、本件各口座を隠す態度を一貫していたとはいえない点や相続財産に含まれないように装ったりするなどの積極的な措置を行っていない点を踏まえると、本件各口座の記載のないお尋ね回答書を提出したことや調査の当初は本件各口座の存在を隠していたことをもって隠ぺい・仮装行為と評価することは困難であるなどと指摘した。
以上の点などを踏まえ審判所は、請求人は本件各口座の預金を隠ぺい・秘匿しようという確定的な意図・態勢の下に計画的に申告書を提出しなかったとまでは言えないため、重加算税の賦課要件は満たさないと判断。請求人に対する重加算税の賦課決定処分を取り消した(平成28年4月25日・東裁(諸)平27第129号)。
| 審判所、被相続人が本件各口座を隠ぺいしたとは認められず |
| 2番目に紹介した裁決事例で原処分庁は、被相続人が本件各口座を隠ぺいしたという状況を請求人が利用した旨を指摘し、重加算税の賦課決定処分は適法であるという主張を展開していた。 しかし、この主張に対し審判所は、地元の複数の金融機関に自己名義の預金口座を開設し、特定の口座のみを生活に通常使用する口座とすることは何ら不自然なことではないと指摘。また、そのほかに被相続人において本件各口座を解約して他の種類の財産にし、あるいは本件各口座の名義を請求人に変更したといった事情もないことからすれば、被相続人が本件各口座を隠ぺいしたとは認められないとしたうえで、原処分庁の主張を斥ける判断を示している。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















