解説記事2016年10月31日 【税務マエストロ】 日本・台湾租税協定と国内法の整備⑤(2016年10月31日号・№665)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
日本・台湾租税協定と国内法の整備⑤
#176 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#177
租税公課と消費税の関係
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
3 日台租税協定に係る国内法の整備(承前)
(3)配当等に対する源泉徴収の特例
① 軽減税率の適用 外国居住者等(台湾居住者)が支払いを受ける配当等のうち、その外国において当該外国の法令に基づき、当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する源泉徴収税率は、10%に軽減される。これは、一般の租税条約における「軽減税率(又は限度税率)」と同様、台湾居住者に支払われる配当等に対する源泉徴収税率を、所得税法による税率ではなく、すべて10%を適用するものである(15条1項)。
一般の租税条約の適用にあたっては、条約実施特例法第3条の2の規定により、それぞれの条約に定める軽減税率が適用されることとなるが、台湾居住者が支払いを受ける配当等及び日台租税協定については租税条約等実施特例法の適用がないため、今般の日台租税協定実施法で手当てされたものである。
(参考)条約実施特例法第3条の2
なお、日本が締結した租税条約における軽減税率及び所得税法における源泉徴収税率は、おおむね次のようになっている。
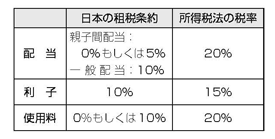
このように、昨今の租税条約では、親子間配当や使用料に対しては免税(0%)としている中で、日台租税協定及び日台租税協定実施法では、これらの源泉徴収税率を一律10%に軽減したところに特徴がある。なお、台湾の所得税法上の源泉徴収税率は、一律20%とされている。
なお、租税特別措置法等が非課税若しくはさらに低い税率を定める場合には、それらの規定が優先され、この軽減税率に関する規定、つまり日台租税協定実施法第15条第1項の規定は、適用されない(15条11項)。
② 対象となる配当等の範囲 軽減税率の対象となる「対象配当等」とは、対象配当、対象利子及び対象使用料で国内源泉所得に該当するものとなる(15条1項)。
(イ)対象配当
「対象配当」とは、内国法人から支払いを受ける次に掲げる所得(信用に係る債権から生じる所得を除く。)をいう(15条29項1項、政令14条9項)。
(i)所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、金銭の分配又は基金利息その他経済的性質がこれらに準ずるもの(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権又は資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に係る剰余金の配当は除く)。いわゆる一般的な配当が該当しよう。
(ii)投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の収益の分配は除く)
なお、日台租税協定において「配当」については、「この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生じる所得及びその分配を行う法人が居住者とされる地域の法令上株式から生じる所得と同様に取り扱われる所得をいう」と定義されている(協定10条3項)。これは、日本が締結した一般的な租税条約における定義と同様のものとなっている。
(ロ)対象利子
「対象利子」とは、次に掲げる所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生じる所得を除く。)をいう(15条29項2項、政令14条10項)。
(i)信用に係る債権から生じる所得。具体的には、公社債、預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生じる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)が該当する。
(ii)合同運用信託、公社債投資信託又は公募公債等運用投資信託の収益の分配
(iii)所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当で、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権又は資産の流動化に関する法律第230条第1項第
2号に規定する社債的受益権に係るもの。
(iv)所得税法第161条第1項第10号に規定する所得税法施行令第283条第3項に定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生じる差益
(v)所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
(vi)租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
なお、日台租税協定において「利子」については、「この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得で当該所得が生じた地域の租税に関する法令上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。」と定義されている(協定11条5項)。これは、日本が締結した一般的な租税条約における定義と同様のものとなっている。
(ハ)対象使用料
「対象使用料」とは、著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう(15条29項3号)。なお、所得税法第161条第1項第11号の使用料の定義では、「その譲渡の対価」という規定により著作権や工業所有権等の権利の譲渡も「使用料」に含まれることとなるが、日台租税協定実施法では、主として、権利の使用の対価又は情報の対価が「使用料」とされており、権利の譲渡の対価は「使用料」に含まれないこととなる。この結果、使用料の基因となる工業所有権や著作権の譲渡対価については、軽減税率の適用がないこととなる。
また、日台租税協定において「使用料」については、「この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びテレビジョン放送用又はラジオ放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作物、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支払金をいう。」と定義されている(協定12条3項)。当然のことながら、ここでも使用料の支払いの基因となる権利の譲渡対価は含まれていない。
③ 軽減又は非課税の対象から除外される対象配当等 (イ)国内事業所等に帰属する対象配当等
対象配当等のうち、国内事業所等を有する外国居住者等の当該国内事業等に帰属するものについては、軽減税率の対象外とされている(15条26項1号)。これは、日台租税協定の「恒久的施設に実質的に関連する配当の取扱」に関する規定(協定10条4項)、「恒久的施設に実質的に関連する利子の取扱」に関する規定(協定11条6項)及び「恒久的施設に実質的に関連する使用料の取扱」に関する規定(協定12条4項)を措置したものである。なお、恒久的施設に帰属する配当等について軽減税率の対象外とするこれらの措置については、一般的な租税条約には定められているところである。
(ロ)独立企業間価格を超える対象利子等
対象利子及び対象使用料(以下「対象利子等」)の支払を受ける者が「外国関連者」である場合において、当該外国関連者がその支払いを受ける対象利子等の額が「独立企業間価格」を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、軽減税率の対象外になる(15条27項)。これは、日台租税協定の「独立企業間価格を超過する利子の取扱」に関する規定(協定11条8項)及び「独立企業間価格を超過する使用料の取扱」に関する規定(協定12条6項)を措置したものであるが、この軽減税率の対象外とされる部分は、所得税法の定めによって課税されることとなる。
なお、この「外国関連者」とは、外国居住者等でその支払いをする者との間に特殊の関係のあるものが該当する(15条27項)。また、「特殊の関係」とは、租税特別措置法第40条の3の3第2項第1号イ(非居住者の内部取引に係る課税の特例)に規定する特殊の関係をいい(政令14条7項)、特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれ取引が行われた時の現況によるものとされている(政令14条8項)。
④ 外国政府等が受ける対象利子の非課税 「外国の権限ある機関等」が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(台湾居住者)が支払を受ける「非課税対象利子」で、日本の国内源泉所得に該当するもののうち、外国(台湾)においてその法令に基づきその外国の権限ある機関等が又は外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税が課されないこととされた(15条2項)。また、これら非課税とされる利子で法人税の申告納税の対象となるものについては、法人税の非課税措置も設けられた(15条20項)。
この「外国の権限ある機関等」とは外国の権限ある機関(一般的には政府が該当し、この場合は台湾政府)、外国の中央銀行又は政府系金融機関(外国の権限ある機関によりその発行済株式又は出資の全部を保有されているものに限る。)が該当する(15条2項、政令14条1項、規則6条10項)。また、「非課税対象利子」とは、対象利子のうち、外国の中央銀行又は輸出入銀行によって保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものが該当する(政令14条2項)。
なお、こうした特定の者が受ける利子の非課税取り扱いは、日本が締結した一般的な租税条約に定められているところである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
日本・台湾租税協定と国内法の整備⑤
#176 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#177
租税公課と消費税の関係
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
3 日台租税協定に係る国内法の整備(承前)
(3)配当等に対する源泉徴収の特例
① 軽減税率の適用 外国居住者等(台湾居住者)が支払いを受ける配当等のうち、その外国において当該外国の法令に基づき、当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する源泉徴収税率は、10%に軽減される。これは、一般の租税条約における「軽減税率(又は限度税率)」と同様、台湾居住者に支払われる配当等に対する源泉徴収税率を、所得税法による税率ではなく、すべて10%を適用するものである(15条1項)。
一般の租税条約の適用にあたっては、条約実施特例法第3条の2の規定により、それぞれの条約に定める軽減税率が適用されることとなるが、台湾居住者が支払いを受ける配当等及び日台租税協定については租税条約等実施特例法の適用がないため、今般の日台租税協定実施法で手当てされたものである。
(参考)条約実施特例法第3条の2
| 相手国居住者等が支払いを受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項……(略)までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。 |
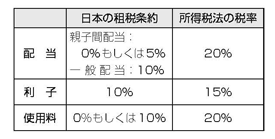
このように、昨今の租税条約では、親子間配当や使用料に対しては免税(0%)としている中で、日台租税協定及び日台租税協定実施法では、これらの源泉徴収税率を一律10%に軽減したところに特徴がある。なお、台湾の所得税法上の源泉徴収税率は、一律20%とされている。
なお、租税特別措置法等が非課税若しくはさらに低い税率を定める場合には、それらの規定が優先され、この軽減税率に関する規定、つまり日台租税協定実施法第15条第1項の規定は、適用されない(15条11項)。
② 対象となる配当等の範囲 軽減税率の対象となる「対象配当等」とは、対象配当、対象利子及び対象使用料で国内源泉所得に該当するものとなる(15条1項)。
(イ)対象配当
「対象配当」とは、内国法人から支払いを受ける次に掲げる所得(信用に係る債権から生じる所得を除く。)をいう(15条29項1項、政令14条9項)。
(i)所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、金銭の分配又は基金利息その他経済的性質がこれらに準ずるもの(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権又は資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に係る剰余金の配当は除く)。いわゆる一般的な配当が該当しよう。
(ii)投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の収益の分配は除く)
なお、日台租税協定において「配当」については、「この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生じる所得及びその分配を行う法人が居住者とされる地域の法令上株式から生じる所得と同様に取り扱われる所得をいう」と定義されている(協定10条3項)。これは、日本が締結した一般的な租税条約における定義と同様のものとなっている。
(ロ)対象利子
「対象利子」とは、次に掲げる所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生じる所得を除く。)をいう(15条29項2項、政令14条10項)。
(i)信用に係る債権から生じる所得。具体的には、公社債、預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生じる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)が該当する。
(ii)合同運用信託、公社債投資信託又は公募公債等運用投資信託の収益の分配
(iii)所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当で、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権又は資産の流動化に関する法律第230条第1項第
2号に規定する社債的受益権に係るもの。
(iv)所得税法第161条第1項第10号に規定する所得税法施行令第283条第3項に定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生じる差益
(v)所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
(vi)租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
なお、日台租税協定において「利子」については、「この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得で当該所得が生じた地域の租税に関する法令上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。」と定義されている(協定11条5項)。これは、日本が締結した一般的な租税条約における定義と同様のものとなっている。
(ハ)対象使用料
「対象使用料」とは、著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう(15条29項3号)。なお、所得税法第161条第1項第11号の使用料の定義では、「その譲渡の対価」という規定により著作権や工業所有権等の権利の譲渡も「使用料」に含まれることとなるが、日台租税協定実施法では、主として、権利の使用の対価又は情報の対価が「使用料」とされており、権利の譲渡の対価は「使用料」に含まれないこととなる。この結果、使用料の基因となる工業所有権や著作権の譲渡対価については、軽減税率の適用がないこととなる。
また、日台租税協定において「使用料」については、「この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びテレビジョン放送用又はラジオ放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作物、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支払金をいう。」と定義されている(協定12条3項)。当然のことながら、ここでも使用料の支払いの基因となる権利の譲渡対価は含まれていない。
③ 軽減又は非課税の対象から除外される対象配当等 (イ)国内事業所等に帰属する対象配当等
対象配当等のうち、国内事業所等を有する外国居住者等の当該国内事業等に帰属するものについては、軽減税率の対象外とされている(15条26項1号)。これは、日台租税協定の「恒久的施設に実質的に関連する配当の取扱」に関する規定(協定10条4項)、「恒久的施設に実質的に関連する利子の取扱」に関する規定(協定11条6項)及び「恒久的施設に実質的に関連する使用料の取扱」に関する規定(協定12条4項)を措置したものである。なお、恒久的施設に帰属する配当等について軽減税率の対象外とするこれらの措置については、一般的な租税条約には定められているところである。
(ロ)独立企業間価格を超える対象利子等
対象利子及び対象使用料(以下「対象利子等」)の支払を受ける者が「外国関連者」である場合において、当該外国関連者がその支払いを受ける対象利子等の額が「独立企業間価格」を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、軽減税率の対象外になる(15条27項)。これは、日台租税協定の「独立企業間価格を超過する利子の取扱」に関する規定(協定11条8項)及び「独立企業間価格を超過する使用料の取扱」に関する規定(協定12条6項)を措置したものであるが、この軽減税率の対象外とされる部分は、所得税法の定めによって課税されることとなる。
なお、この「外国関連者」とは、外国居住者等でその支払いをする者との間に特殊の関係のあるものが該当する(15条27項)。また、「特殊の関係」とは、租税特別措置法第40条の3の3第2項第1号イ(非居住者の内部取引に係る課税の特例)に規定する特殊の関係をいい(政令14条7項)、特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれ取引が行われた時の現況によるものとされている(政令14条8項)。
④ 外国政府等が受ける対象利子の非課税 「外国の権限ある機関等」が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(台湾居住者)が支払を受ける「非課税対象利子」で、日本の国内源泉所得に該当するもののうち、外国(台湾)においてその法令に基づきその外国の権限ある機関等が又は外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税が課されないこととされた(15条2項)。また、これら非課税とされる利子で法人税の申告納税の対象となるものについては、法人税の非課税措置も設けられた(15条20項)。
この「外国の権限ある機関等」とは外国の権限ある機関(一般的には政府が該当し、この場合は台湾政府)、外国の中央銀行又は政府系金融機関(外国の権限ある機関によりその発行済株式又は出資の全部を保有されているものに限る。)が該当する(15条2項、政令14条1項、規則6条10項)。また、「非課税対象利子」とは、対象利子のうち、外国の中央銀行又は輸出入銀行によって保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものが該当する(政令14条2項)。
なお、こうした特定の者が受ける利子の非課税取り扱いは、日本が締結した一般的な租税条約に定められているところである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















