解説記事2017年03月06日 【ニュース特集】 エフオーアイの粉飾決算事件、東京地裁判決を読み解く(2017年3月6日号・№681)
ニュース特集
匿名投書による対応がキーポイントに
エフオーアイの粉飾決算事件、東京地裁判決を読み解く
粉飾決算が発覚しマザーズを上場廃止となったエフオーアイの元株主ら約200人が、当時の役員や主幹事証券会社などに対して損害賠償を求めた事件で、東京地方裁判所(谷口安史裁判長)は平成28年12月20日、元役員及び主幹事証券会社に約1億7,000万円の損害賠償請求を認めた(現在、控訴中)。監査役に対しては、権限を行使して調査を行えば、エフオーアイにおいて粉飾決算が行われていた事実が判明していた可能性があったと指摘。また、主幹事証券会社に対しては、実施した追加審査は不十分であったと認定されている。エフオーアイの粉飾決算事件は、上場から上場廃止までの期間が約7か月と短かったため注目を集めたが、上場前から粉飾決算が行われ、上場審査時に粉飾決算を指摘する匿名の投書が寄せられるなどしており、監査役や主幹事証券会社、自主規制法人などのその時の対応が焦点となっている(なお、会計監査人は裁判途中で和解)。
上場前の平成16年3月期から役員らが粉飾決算
本件は、半導体製造装置の製作販売会社であるエフオーアイが、架空の売上げを計上して粉飾決算を行い、虚偽記載のある有価証券届出書を提出して東京証券取引所の市場であるマザーズへの上場を行ったが、その後粉飾決算の事実が発覚したもの。このため、上場時の募集若しくは売出しに応じ、又は上場後の取引所市場においてエフオーアイ株式を取得した原告らが、エフオーアイの役員、同社株式の募集又は売出しを行った元引受証券会社及び販売を受託した証券会社、当該売出しに係る株式の所有者並びに東京証券取引所等を被告として、金融商品取引法21条1項1号、2号、4号、22条1項及び17条、会社法429条2項又は民法上の不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案である。
エフオーアイにおいては、平成16年3月期において、決算が大幅な赤字となって銀行融資を受けることができなくなることを防ぐため、役員らが相談の上、架空の売上げを計上することにより、決算書類には売上高が23億2,799万9,328円である旨記載する粉飾決算を行った(実際の売上高は7億1,941万328円であった)。平成17年3月期以降も平成21年3月期までの間、売上高を実際よりも水増しして計上する方法による粉飾決算を継続。平成21年3月期の粉飾額は115億3,639万5,000円に及び、決算書類に記載された売上高の97.3%が架空の売上げとなっていた。
なお、事件の主な経緯を示すと表のとおりである。
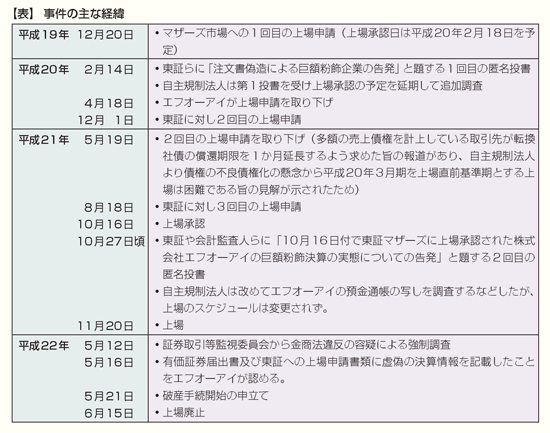
“相当な注意”を用いた監査とは認められず
裁判所は、エフオーアイの有価証券届出書等において、平成17年3月期から平成21年3月期までの売上高について虚偽記載があったことは、金商法21条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)などにいう「重要な事項」についての虚偽記載に当たることは明らかであるとした。
その上で、役員らについては、粉飾決算を主導又は容認してきたことから、有価証券届出書の虚偽記載を知っていたことは明らかであるとし、金商法21条1項1号などの責任を免れないとした。
また、監査役に関しては、エフオーアイによる粉飾を認識していなかったものと認められるため、“相当な注意”を用いたにもかかわらず有価証券届出書の虚偽記載を知ることができなかったと認められるかどうかが検討されている。
この点、監査役らは、定期的に監査役会を開催し、業務監査に関する事項を協議していたほか、期末決算監査に関する会計監査人とのミーティングを行うなど、一応の監査を行っていると認められている。
本来の監査役の業務監査で是正されるべき しかし、取締役らの違法行為は、本来監査役の業務監査によって是正されるべきものであると指摘。監査役は、エフオーアイの売上げが急増したにもかかわらず売掛金の回収が進まない状況において、架空の売上げが計上されている可能性について疑問を抱き、売上げの実在性について独自の調査を行うなどの対応を執ることは十分に可能であったというべきであるが、会計監査人の報告を受ける以外にかかる観点から何らかの調査を行ったことをうかがわせる証拠はなかったなどとしている。
また、監査役会において、上場申請取下げの理由について他の役員ら又は主幹事証券会社に問い合わせをするなどして調査すれば、第1投書の存在を認識することは十分に可能であったというべきであり、その上で監査役の権限を行使して調査を行えば、エフオーアイにおいて粉飾決算が行われていた事実が判明していた可能性がないとはいえないとした。よって、監査役らは、相当な注意を用いて監査を行っていたとは認められないとし、金商法21条1項1号などの責任を免れることはできないと判断されている。
上場申請時の主幹事証券会社にも損害賠償責任
新規上場に際し、発行会社が発行する株式を広く投資者に販売する目的で、その全部又は一部を引き受ける元引受証券会社は、有価証券届出書又は目論見書に虚偽記載があった場合には免責事由を立証しない限り、募集又は売出しにより株式を取得した投資者の損害を賠償すべき責任を課せられている。その趣旨は、株式の募集・売出しを引き受ける元引受証券会社は、発行会社の事業の状況を正確に把握できる立場にあるとともに、有価証券届出書及びこれに基づいて作成される目論見書の内容を審査し得る立場にあることから、これに重い責任を課すことによって、開示書類の正確性を担保し、投資者の利益を保護する点にあるからだ。
裁判所は、元引受証券会社が行う引受審査の手続については、自主規制団体である日本証券業協会が本件規則等を定めているが、引受審査に当たって元引受証券会社が用いるべき相当の注意の基準を定めたものとして、公的規制に準ずる効力を有するものと解するのが相当であるとした。
その上で、財務情報を始めとする企業情報の適正な開示は、投資者による適切な投資判断の前提条件であること、本件規則においても、企業内容等の適正な開示が引受審査項目として掲げられていることからすれば、財務情報が適正に開示されているかどうか、すなわち粉飾が行われていないかどうかという点についても、当然に厳正な引受審査の対象となると考えられる。
もっとも、会計監査を経た財務情報の第三者に対する適正な開示は、第一次的には会計の専門家である公認会計士等の責任によって担保するというのが法の趣旨であると考えられるとし、元引受証券会社は、引受審査において、会計監査を経た財務情報(財務計算部分以外のものを含む)について、公認会計士等が行った会計監査の信頼性を疑わせるような事情あるいは財務情報の内容が正確でないことを疑わせるような事情が存在するか否かについては厳正に審査する必要があるが、そのような審査の結果、かかる事情が存在しないことが確認できた場合には、当該監査結果を信頼することが許され、元引受証券会社において公認会計士等と同様の審査を改めて行わなければならないものではないと解するのが相当であるとした。
会計監査が前提 主幹事証券会社である元引受証券会社に関しては、財務諸表に表示されたエフオーアイの財務情報については、会計監査人による適正かつ合理的な監査を経たものであり、一応これが実態を反映した正確なものであると信頼することが許されるというべきであり、これと矛盾するような情報に接したり、本件粉飾を疑わせる事情に係る審査において当該信頼が揺らぐような事情が判明したりしない限り、当該財務情報が正確であることを前提に引受審査を行うことが許されるとした。
実情をよく知る内部通報が この点、主幹事証券会社については、粉飾を疑わせる事情について十分な審査を行ったとしているが、匿名投書に対する対応については不十分であったと認定されている。
匿名投書の内容は、粉飾の経緯や偽装の手口を具体的に指摘しているほか、エフオーアイの役職者名、決算書上の売上高、取引先、主幹事証券会社の担当者名が実際と合致しているなど、これが単なる部外者によるいたずらなどではなく、エフオーアイの実情をよく知る内部者による通報であることが推認されるものとなっていた。
このように、事情をよく知る内部者が作成したことが推認される文書において、粉飾決算である事実が、その手口を含め具体的に指摘されていたのであるから、主幹事証券会社としては、当該文書が指摘するような手口による粉飾が実際に行われているのではないかという懐疑心をもって、粉飾の疑いを打ち消すだけの十分な引受審査を行うことが要請されていたというべきであると指摘したが、追加審査としては全販売案件に係る帳票類の写しの突合作業にとどまっており、取引先への照会もなく、匿名投書を受領したことを踏まえた審査としては不十分であったと認定。主幹事証券会社としての注意を尽くしていたとは認め難いとし、上場に際して証券会社による募集又は売り出しに応じてエフオーアイ株式を取得した投資家(原告)に対して、金商法21条1項4号及び17条の責任を負うとした(金商法17条の責任は主幹事証券会社が目論見書を使用して本件株式を販売した原告に限る)。
上場後の責任は問わず 一方、上場後に市場でエフオーアイ株式を取得した投資家(原告)に対しては、有価証券届出書に虚偽の記載があることを容易に知り得たにもかかわらず、漫然と放置したものとまでは評価することはできないため、不法行為責任を負うものではないと判断されている。
東証及び自主規制法人の責任は?
自主規制法人に対する注意義務についても問われている。上場審査は上場申請会社が資金調達を行うのにふさわしい会社であるかどうかを審査し、一般の投資者が不測の損害を被ることを防止するための手続であると指摘。自主規制法人も投資者に対し、上場要件を欠く株式会社の上場を防止し、市場の公正さを維持すべく一定の注意義務を負うと解するのが相当であるとした。その上で、自主規制法人については、公認会計士等による適正な監査が行われていない可能性があり、又は当該財務諸表の内容自体について不自然、不合理な部分があるなど、当該財務諸表の正確性に疑いを生じさせるような事情が存在したにもかかわらず、そのような事情を看過し、追加の審査を行うことなく漫然と上場を承認したと認められる場合に投資者に対する不法行為責任を負うと解するのが相当であるとした。
この点、自主規制法人は、会計監査人から売上の実在性についての監査手法について確認したほか、帳票類や預金通帳の確認も行うなどしており、漫然と追加の調査を行うことを怠ったものと評価することはできないとし、投資者に対して負っていた注意義務に違反する行為があったということはできないとして請求を斥けた。
東証は不法行為責任を負わず なお、東京証券取引所については、同取引所から委託を受けた自主規制法人が独立した立場で上場審査の全部を行っていたものと認められ、仮に自主規制法人が行った上場審査の過程において過失があったとしても、不法行為責任を負うことはないとしている。
匿名投書による対応がキーポイントに
エフオーアイの粉飾決算事件、東京地裁判決を読み解く
粉飾決算が発覚しマザーズを上場廃止となったエフオーアイの元株主ら約200人が、当時の役員や主幹事証券会社などに対して損害賠償を求めた事件で、東京地方裁判所(谷口安史裁判長)は平成28年12月20日、元役員及び主幹事証券会社に約1億7,000万円の損害賠償請求を認めた(現在、控訴中)。監査役に対しては、権限を行使して調査を行えば、エフオーアイにおいて粉飾決算が行われていた事実が判明していた可能性があったと指摘。また、主幹事証券会社に対しては、実施した追加審査は不十分であったと認定されている。エフオーアイの粉飾決算事件は、上場から上場廃止までの期間が約7か月と短かったため注目を集めたが、上場前から粉飾決算が行われ、上場審査時に粉飾決算を指摘する匿名の投書が寄せられるなどしており、監査役や主幹事証券会社、自主規制法人などのその時の対応が焦点となっている(なお、会計監査人は裁判途中で和解)。
上場前の平成16年3月期から役員らが粉飾決算
本件は、半導体製造装置の製作販売会社であるエフオーアイが、架空の売上げを計上して粉飾決算を行い、虚偽記載のある有価証券届出書を提出して東京証券取引所の市場であるマザーズへの上場を行ったが、その後粉飾決算の事実が発覚したもの。このため、上場時の募集若しくは売出しに応じ、又は上場後の取引所市場においてエフオーアイ株式を取得した原告らが、エフオーアイの役員、同社株式の募集又は売出しを行った元引受証券会社及び販売を受託した証券会社、当該売出しに係る株式の所有者並びに東京証券取引所等を被告として、金融商品取引法21条1項1号、2号、4号、22条1項及び17条、会社法429条2項又は民法上の不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案である。
エフオーアイにおいては、平成16年3月期において、決算が大幅な赤字となって銀行融資を受けることができなくなることを防ぐため、役員らが相談の上、架空の売上げを計上することにより、決算書類には売上高が23億2,799万9,328円である旨記載する粉飾決算を行った(実際の売上高は7億1,941万328円であった)。平成17年3月期以降も平成21年3月期までの間、売上高を実際よりも水増しして計上する方法による粉飾決算を継続。平成21年3月期の粉飾額は115億3,639万5,000円に及び、決算書類に記載された売上高の97.3%が架空の売上げとなっていた。
なお、事件の主な経緯を示すと表のとおりである。
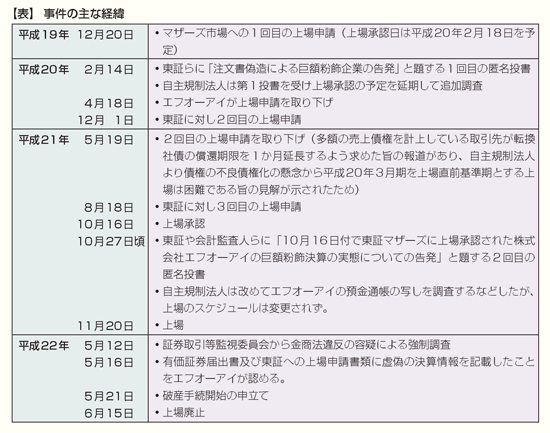
“相当な注意”を用いた監査とは認められず
裁判所は、エフオーアイの有価証券届出書等において、平成17年3月期から平成21年3月期までの売上高について虚偽記載があったことは、金商法21条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)などにいう「重要な事項」についての虚偽記載に当たることは明らかであるとした。
その上で、役員らについては、粉飾決算を主導又は容認してきたことから、有価証券届出書の虚偽記載を知っていたことは明らかであるとし、金商法21条1項1号などの責任を免れないとした。
| >(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) |
| 金融商品取引法第二十一条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。 一 当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。) 二 当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方) 三 当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人 四 当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関 |
また、監査役に関しては、エフオーアイによる粉飾を認識していなかったものと認められるため、“相当な注意”を用いたにもかかわらず有価証券届出書の虚偽記載を知ることができなかったと認められるかどうかが検討されている。
この点、監査役らは、定期的に監査役会を開催し、業務監査に関する事項を協議していたほか、期末決算監査に関する会計監査人とのミーティングを行うなど、一応の監査を行っていると認められている。
本来の監査役の業務監査で是正されるべき しかし、取締役らの違法行為は、本来監査役の業務監査によって是正されるべきものであると指摘。監査役は、エフオーアイの売上げが急増したにもかかわらず売掛金の回収が進まない状況において、架空の売上げが計上されている可能性について疑問を抱き、売上げの実在性について独自の調査を行うなどの対応を執ることは十分に可能であったというべきであるが、会計監査人の報告を受ける以外にかかる観点から何らかの調査を行ったことをうかがわせる証拠はなかったなどとしている。
また、監査役会において、上場申請取下げの理由について他の役員ら又は主幹事証券会社に問い合わせをするなどして調査すれば、第1投書の存在を認識することは十分に可能であったというべきであり、その上で監査役の権限を行使して調査を行えば、エフオーアイにおいて粉飾決算が行われていた事実が判明していた可能性がないとはいえないとした。よって、監査役らは、相当な注意を用いて監査を行っていたとは認められないとし、金商法21条1項1号などの責任を免れることはできないと判断されている。
上場申請時の主幹事証券会社にも損害賠償責任
新規上場に際し、発行会社が発行する株式を広く投資者に販売する目的で、その全部又は一部を引き受ける元引受証券会社は、有価証券届出書又は目論見書に虚偽記載があった場合には免責事由を立証しない限り、募集又は売出しにより株式を取得した投資者の損害を賠償すべき責任を課せられている。その趣旨は、株式の募集・売出しを引き受ける元引受証券会社は、発行会社の事業の状況を正確に把握できる立場にあるとともに、有価証券届出書及びこれに基づいて作成される目論見書の内容を審査し得る立場にあることから、これに重い責任を課すことによって、開示書類の正確性を担保し、投資者の利益を保護する点にあるからだ。
裁判所は、元引受証券会社が行う引受審査の手続については、自主規制団体である日本証券業協会が本件規則等を定めているが、引受審査に当たって元引受証券会社が用いるべき相当の注意の基準を定めたものとして、公的規制に準ずる効力を有するものと解するのが相当であるとした。
その上で、財務情報を始めとする企業情報の適正な開示は、投資者による適切な投資判断の前提条件であること、本件規則においても、企業内容等の適正な開示が引受審査項目として掲げられていることからすれば、財務情報が適正に開示されているかどうか、すなわち粉飾が行われていないかどうかという点についても、当然に厳正な引受審査の対象となると考えられる。
もっとも、会計監査を経た財務情報の第三者に対する適正な開示は、第一次的には会計の専門家である公認会計士等の責任によって担保するというのが法の趣旨であると考えられるとし、元引受証券会社は、引受審査において、会計監査を経た財務情報(財務計算部分以外のものを含む)について、公認会計士等が行った会計監査の信頼性を疑わせるような事情あるいは財務情報の内容が正確でないことを疑わせるような事情が存在するか否かについては厳正に審査する必要があるが、そのような審査の結果、かかる事情が存在しないことが確認できた場合には、当該監査結果を信頼することが許され、元引受証券会社において公認会計士等と同様の審査を改めて行わなければならないものではないと解するのが相当であるとした。
会計監査が前提 主幹事証券会社である元引受証券会社に関しては、財務諸表に表示されたエフオーアイの財務情報については、会計監査人による適正かつ合理的な監査を経たものであり、一応これが実態を反映した正確なものであると信頼することが許されるというべきであり、これと矛盾するような情報に接したり、本件粉飾を疑わせる事情に係る審査において当該信頼が揺らぐような事情が判明したりしない限り、当該財務情報が正確であることを前提に引受審査を行うことが許されるとした。
実情をよく知る内部通報が この点、主幹事証券会社については、粉飾を疑わせる事情について十分な審査を行ったとしているが、匿名投書に対する対応については不十分であったと認定されている。
匿名投書の内容は、粉飾の経緯や偽装の手口を具体的に指摘しているほか、エフオーアイの役職者名、決算書上の売上高、取引先、主幹事証券会社の担当者名が実際と合致しているなど、これが単なる部外者によるいたずらなどではなく、エフオーアイの実情をよく知る内部者による通報であることが推認されるものとなっていた。
このように、事情をよく知る内部者が作成したことが推認される文書において、粉飾決算である事実が、その手口を含め具体的に指摘されていたのであるから、主幹事証券会社としては、当該文書が指摘するような手口による粉飾が実際に行われているのではないかという懐疑心をもって、粉飾の疑いを打ち消すだけの十分な引受審査を行うことが要請されていたというべきであると指摘したが、追加審査としては全販売案件に係る帳票類の写しの突合作業にとどまっており、取引先への照会もなく、匿名投書を受領したことを踏まえた審査としては不十分であったと認定。主幹事証券会社としての注意を尽くしていたとは認め難いとし、上場に際して証券会社による募集又は売り出しに応じてエフオーアイ株式を取得した投資家(原告)に対して、金商法21条1項4号及び17条の責任を負うとした(金商法17条の責任は主幹事証券会社が目論見書を使用して本件株式を販売した原告に限る)。
上場後の責任は問わず 一方、上場後に市場でエフオーアイ株式を取得した投資家(原告)に対しては、有価証券届出書に虚偽の記載があることを容易に知り得たにもかかわらず、漫然と放置したものとまでは評価することはできないため、不法行為責任を負うものではないと判断されている。
東証及び自主規制法人の責任は?
自主規制法人に対する注意義務についても問われている。上場審査は上場申請会社が資金調達を行うのにふさわしい会社であるかどうかを審査し、一般の投資者が不測の損害を被ることを防止するための手続であると指摘。自主規制法人も投資者に対し、上場要件を欠く株式会社の上場を防止し、市場の公正さを維持すべく一定の注意義務を負うと解するのが相当であるとした。その上で、自主規制法人については、公認会計士等による適正な監査が行われていない可能性があり、又は当該財務諸表の内容自体について不自然、不合理な部分があるなど、当該財務諸表の正確性に疑いを生じさせるような事情が存在したにもかかわらず、そのような事情を看過し、追加の審査を行うことなく漫然と上場を承認したと認められる場合に投資者に対する不法行為責任を負うと解するのが相当であるとした。
この点、自主規制法人は、会計監査人から売上の実在性についての監査手法について確認したほか、帳票類や預金通帳の確認も行うなどしており、漫然と追加の調査を行うことを怠ったものと評価することはできないとし、投資者に対して負っていた注意義務に違反する行為があったということはできないとして請求を斥けた。
東証は不法行為責任を負わず なお、東京証券取引所については、同取引所から委託を受けた自主規制法人が独立した立場で上場審査の全部を行っていたものと認められ、仮に自主規制法人が行った上場審査の過程において過失があったとしても、不法行為責任を負うことはないとしている。
| 【参考】虚偽開示書類の提出会社及び役員等の損害賠償責任 |
| 発行市場 | 流通市場 | |
| 提出会社 | 金商法18条 無過失責任 | 金商法21条の2 過失責任(立証責任転換) |
| 提出会社の役員等 | 金商法21条 過失責任(立証責任転換) | 金商法22条、24条の4等 過失責任(立証責任転換) |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























