解説記事2017年04月10日 【税理士のための相続法講座】 相続人の不存在(2017年4月10日号・№686)
税理士のための相続法講座
第26回
相続人の不存在
弁護士 間瀬まゆ子
今回は、相続人が存在しない場合(全ての法定相続人が相続放棄した場合を含みます。)についてのお話です。
税理士が相続人不存在のケースに関わることはあまりないかもしれませんが、万一遭遇した場合に備えて、相続人不存在の場合にどのような手続きが必要になるのか、大まかなところだけでも把握しておくとよいでしょう。
1 相続財産法人と相続財産管理人 相続人が不存在の場合、相続財産は法人となります(民法951条)。しかし、相続財産法人が存在するというだけでは、Aは何らの法的手段をとることができません。Bの残した財産から弁済を受けるためには、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人は、相続財産法人の事務を行う者で、利害関係人の請求により(法律上は検察官にも請求権があります。)家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所から選任された相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行っていきます。Aも、この手続きの中で「請求の申出」をして、弁済を求めることができます(民法957条)。
清算を終えた後、残った財産があれば、これは国庫に帰属することになります。ただし、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)からの財産分与の請求があり、裁判所がこれを認めた場合には、国庫への帰属に先立ち、特別縁故者への支払がなされます。
2 相続財産管理人の選任申立 相続財産管理人の選任の申立ができる利害関係人として一般に想定されるのは、Aのような相続債権者のほか、特定遺贈を受けた受遺者、特別受遺者等です。その他、稀ではありますが、遺産分割協議中に相続人の一人が亡くなり、その相続人に相続人がいないため、分割協議を進めるために相続財産管理人の選任が必要となるというような場合もあります。
相続財産管理人選任の申立に際しては、裁判所に数十万円から100万円の予納金を納める必要があります(相続財産から相続財産管理人の報酬を支払えない場合に、この予納金が充てられることになります。)。それに加えて、申立を専門家に依頼した場合には、当該専門家に支払う報酬も必要になりますので、申立人にとっては相当な負担です。
また、専門家に申立を依頼するなら、その専門家に相続財産管理人になってもらうのが簡便のように思われますが、裁判所によって、申立に際して相続財産管理人の候補者を立てたとしても、当該候補者ではなく、裁判所の管理する名簿に登載された弁護士等から選出する運用がなされているところもあります。
更に、相続財産管理人が選任されて終わりではなく、その後、以下の手続きが履践されることになるのですが、全てが終了するまでには、約1年を要すると言われており、時間もかかります。
このように、厳格に行われる手続きであるため、相続財産管理人を選任してもらって弁済を受けるまでには、相当な費用と時間を要します。結局は、回収可能性との兼ね合いで申立てをするかを判断していかざるを得ないことになりますが、実務上は、断念するケースの方が圧倒的に多いのではないかと思います。
3 特別縁故者と国庫への帰属 前述のとおり、特別縁故者が財産分与の請求をし、裁判所がこれを認めると、清算後に残った財産から一定の支払いを受けることができます(民法958条の3)。
しかし、特別縁故者にあたると裁判所に認めてもらえたとしても、実際に分与を受けられる額は限られています。最近の裁判例としては、被相続人の従兄に、遺産総額約3億7875万円のうちの300万円の分与を認めた東京高裁平成26年5月21日決定(判時2271号44ページ)や、被相続人の身の回りの世話をした近隣の友人及び成年後見人であった親族にそれぞれ500万円の分与を認めた大阪高裁平成28年3月2日決定(判時2310号85ページ)等があります。
一方、最終的に、民法959条に基づき国庫に帰属することとなった正確な金額は不明です。ただ、平成27年度の国の「一般会計歳入明細書」中の「裁判所主管」の項目を見ると、「雑収」として約420億円が計上されており、増減理由として「相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等のため」との記載がなされています。420億円の全額ではないでしょうが、相当な金額の相続財産が国庫に帰属するに至っていることが推測されます。
4 最後に 相続財産管理人の選任の申立件数は年々増加しています。平成17年に10,736件であったのが、平成27年には18,568件となっています。この間、亡くなる方の数も増えていますが(平成17年の約108万人から平成27年には約129万まで増加しています。)、割合で見ると、被相続人数が2割弱の増加に留まるのに対し、相続財産管理人選任等申立件数の方は7割超に及んでいます。相続件数の増加以上に、相続財産管理人選任申立件数の増加のペースが速いことが分かります。
今後も、少子化社会ゆえに、相続人がまったくいない相続は増えていくことでしょう。
前述のとおり、相続財産管理人選任の申立ては気軽に出来るものではありませんので、もし相続開始前に対策を採り得るのならば、遺言を残してもらったり、死因贈与契約を結んでおいてもらったりすることが肝要のように思われます。
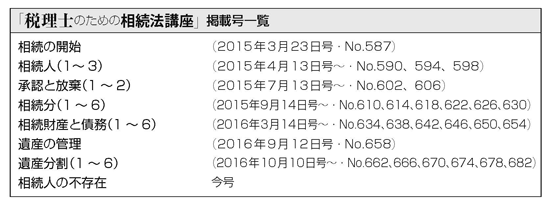
第26回
相続人の不存在
弁護士 間瀬まゆ子
| Aは、Bに対する債権を有していた。Bが亡くなったが、親族が全員相続放棄をしたため、相続人がいない状態になった。Bは債務超過ではあったものの、自宅の土地建物が無担保の状態で残されていることが判明した。 |
税理士が相続人不存在のケースに関わることはあまりないかもしれませんが、万一遭遇した場合に備えて、相続人不存在の場合にどのような手続きが必要になるのか、大まかなところだけでも把握しておくとよいでしょう。
1 相続財産法人と相続財産管理人 相続人が不存在の場合、相続財産は法人となります(民法951条)。しかし、相続財産法人が存在するというだけでは、Aは何らの法的手段をとることができません。Bの残した財産から弁済を受けるためには、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人は、相続財産法人の事務を行う者で、利害関係人の請求により(法律上は検察官にも請求権があります。)家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所から選任された相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行っていきます。Aも、この手続きの中で「請求の申出」をして、弁済を求めることができます(民法957条)。
清算を終えた後、残った財産があれば、これは国庫に帰属することになります。ただし、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)からの財産分与の請求があり、裁判所がこれを認めた場合には、国庫への帰属に先立ち、特別縁故者への支払がなされます。
2 相続財産管理人の選任申立 相続財産管理人の選任の申立ができる利害関係人として一般に想定されるのは、Aのような相続債権者のほか、特定遺贈を受けた受遺者、特別受遺者等です。その他、稀ではありますが、遺産分割協議中に相続人の一人が亡くなり、その相続人に相続人がいないため、分割協議を進めるために相続財産管理人の選任が必要となるというような場合もあります。
相続財産管理人選任の申立に際しては、裁判所に数十万円から100万円の予納金を納める必要があります(相続財産から相続財産管理人の報酬を支払えない場合に、この予納金が充てられることになります。)。それに加えて、申立を専門家に依頼した場合には、当該専門家に支払う報酬も必要になりますので、申立人にとっては相当な負担です。
また、専門家に申立を依頼するなら、その専門家に相続財産管理人になってもらうのが簡便のように思われますが、裁判所によって、申立に際して相続財産管理人の候補者を立てたとしても、当該候補者ではなく、裁判所の管理する名簿に登載された弁護士等から選出する運用がなされているところもあります。
更に、相続財産管理人が選任されて終わりではなく、その後、以下の手続きが履践されることになるのですが、全てが終了するまでには、約1年を要すると言われており、時間もかかります。
| ① 相続財産管理人選任の公告 ② 相続財産管理人による相続財産の調査と管理 ③ 相続債権者と受遺者に対する請求申出の公告 ④ 相続債権者と受遺者への弁済 ⑤ 相続人捜索の公告 ⑥ 特別縁故者への相続財産分与 ⑦ 相続財産管理人に対する報酬付与 ⑧ 残余財産の国庫帰属 ⑨ 管理終了の報告 |
3 特別縁故者と国庫への帰属 前述のとおり、特別縁故者が財産分与の請求をし、裁判所がこれを認めると、清算後に残った財産から一定の支払いを受けることができます(民法958条の3)。
しかし、特別縁故者にあたると裁判所に認めてもらえたとしても、実際に分与を受けられる額は限られています。最近の裁判例としては、被相続人の従兄に、遺産総額約3億7875万円のうちの300万円の分与を認めた東京高裁平成26年5月21日決定(判時2271号44ページ)や、被相続人の身の回りの世話をした近隣の友人及び成年後見人であった親族にそれぞれ500万円の分与を認めた大阪高裁平成28年3月2日決定(判時2310号85ページ)等があります。
一方、最終的に、民法959条に基づき国庫に帰属することとなった正確な金額は不明です。ただ、平成27年度の国の「一般会計歳入明細書」中の「裁判所主管」の項目を見ると、「雑収」として約420億円が計上されており、増減理由として「相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等のため」との記載がなされています。420億円の全額ではないでしょうが、相当な金額の相続財産が国庫に帰属するに至っていることが推測されます。
4 最後に 相続財産管理人の選任の申立件数は年々増加しています。平成17年に10,736件であったのが、平成27年には18,568件となっています。この間、亡くなる方の数も増えていますが(平成17年の約108万人から平成27年には約129万まで増加しています。)、割合で見ると、被相続人数が2割弱の増加に留まるのに対し、相続財産管理人選任等申立件数の方は7割超に及んでいます。相続件数の増加以上に、相続財産管理人選任申立件数の増加のペースが速いことが分かります。
今後も、少子化社会ゆえに、相続人がまったくいない相続は増えていくことでしょう。
前述のとおり、相続財産管理人選任の申立ては気軽に出来るものではありませんので、もし相続開始前に対策を採り得るのならば、遺言を残してもらったり、死因贈与契約を結んでおいてもらったりすることが肝要のように思われます。
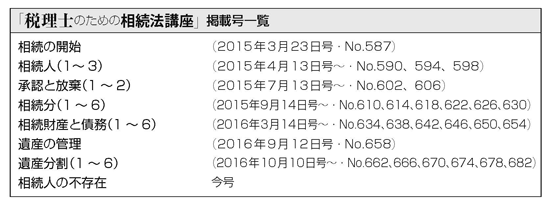
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























