解説記事2017年07月10日 【ニュース特集】 e-Tax「義務化」に向けた実務上の論点(2017年7月10日号・№698)
ニュース特集
平成30年度税制改正で議論へ 実施時期や対象書類は?
e-Tax「義務化」に向けた実務上の論点
政府が検討を進める電子申告制度の義務化に向けた「基本計画」が公表された。
基本計画では、法人税・消費税のe-Tax利用率として大法人は「100%」、中小法人は「85%以上(将来的には100%)」と高い目標値が設定されている。大法人の法人税・消費税の電子申告の義務化の時期については「平成29年度に検討を開始し、早期に結論を得る」とされるにとどまっているが、本誌取材によると、最速のケースでは平成30年度分の確定申告から電子申告が求められる可能性がある。電子申告制度の見直しは税調に議論の場を移し、平成30年度税制改正のテーマとなるだろう。
電子申告義務化の早期実現のカギを握るのが対象書類の範囲だ。現状は紙で提出されることが多い別表の内訳明細書、財務諸表や勘定科目内訳明細書なども含めすべての添付書類をe-Taxで提出することとなった場合、大規模なシステム改修を迫られる企業が出てくることも予想され、電子申告義務化の実施スケジュールに影響が出る可能性がある。
大企業に残る“紙による決裁文化”
「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)で「事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化、IT化を進める新たな規制・制度改革手法の導入」が打ち出されたことを受け、内閣府の規制改革推進会議に設けられた「行政手続部会」では、行政手続コストの削減策を検討してきたが、その中で、営業の許可・認可に係る手続や社会保険に関する手続などとともに「重点分野」に位置付けられているのが、国税と地方税の電子申告だ。行政手続部会は平成29年3月29日に各種の取組みの時期などを示した「行政手続部会取りまとめ」をとりまとめた後、4月17日の会合で「基本計画策定のための作業方針(案)」を示し、各省庁に対し本年6月末までに基本計画を作成し、公表することを求めていた。これを受け、財務省は2017年6月30日付で「行政手続コスト削減のための基本計画」を公表している。
所得税、法人税、消費税の申告や申請・届出等、国税の各種手続きの申告・納税システムである「e-Tax」の利用率は現状では表1のとおりとなっている。
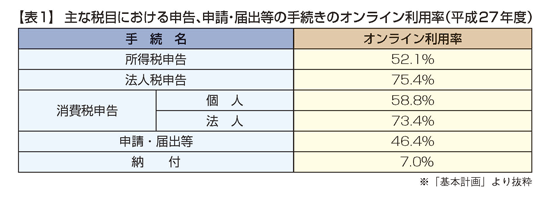
法人税申告のオンライン利用率は75.4%に達しているが、これを国税局の調査課所管法人(原則として資本金1億円以上の法人)に限ると、52.1%にとどまる。これは、大企業においては紙の書類による決裁文化が根強く残っているほか、経理担当者が自ら申告を行うケースが多いことなどが影響しているものとみられる。一方、中小企業では税理士が納税者に代わってオンラインで申告するケースが多いため、必然的にオンライン利用率も高率になるものと考えられる。
最速で平成30年6月申告分から義務化
ただし、今回の基本計画で打ち出された法人税・消費税についてのe-Tax利用率の目標値は大法人が「100%」、中小法人が「85%以上(将来的には100%)」と、大法人の方が高く設定されている。なお、ここでいう「大法人」とは、基本的には法人税法上の大法人である「資本金1億円超」の法人になると考えられるが、大法人の子会社である中小法人や連結納税を行っている場合における中小法人の取扱いも今後の重要論点となる。
企業にとってまず気になるのが実施時期だろう。基本計画では、大法人の法人税・消費税の電子申告の義務化の時期について、「平成29年度に検討を開始し、早期に結論を得る」(2頁2(1)参照)との記述にとどまっている。
そこで、基本計画のベースとなった規制改革推進会議の「行政手続部会取りまとめ」(平成29年3月29日付)を見ると、行政手続コストの削減に向けた「取組期間は、3年とする(平成31年度まで)。ただし事項によっては5年まで許容する(平成33年度まで)」とされている。規制改革推進会議では、電子申告の実施に向けた取組みのPDCAサイクルを回す観点から税務当局に早期対応を求めると考えられる。これから先、規制改革推進会議の枠組みで基本計画に関する各省からのヒアリングが行われることになるが、具体的な制度設計に関する検討の場は、政府税調や与党税調に移ることになるだろう。
税務当局も今のところ平成30年度税制改正で具体的な制度内容を固め、平成30年度分の申告からの義務化を視野に入れている模様。3月決算法人の単体納税の場合、平成30年度分の申告は、申告期限の1ヶ月延長を含めると実質的には平成31年6月、連結納税の場合は実質7月ということになる。これであれば、「行政手続部会取りまとめ」が求める「平成31年度まで」というハードルをクリアできる。
ただし、企業の準備に時間がかかる場合は、「平成31年度分の申告」(実際の申告のタイミングは平成32年6月又は7月)をもって「平成31年度まで」を満たすという考え方も存在している。この点についてはまだ確定しておらず、今後、議論されることになる。
添付書類も「原則」義務化
電子申告義務化の早期実現のカギを握るのが対象書類の範囲だ。
例えば外国税額控除に関する別表六(四)は、大企業になると件数があまりにも多すぎるため、別表上は総額だけを書き、内訳明細書は別途エクセルデータで作成して出力し、紙で提出するという企業も少なくない。減価償却資産に関する別表十六についても同じような問題がある。
また、財務諸表や勘定科目内訳明細書を紙で提出している企業は多い。
仮にこれらをすべてe-Taxで提出するとなると、企業によっては大規模なシステム改修が求められることになり、平成30年度分の申告までには対応が間に合わないとの声がある。そうなれば、段階的な制度の導入や移行措置が必要になる可能性もある。
基本原則には「原則として添付書類も含めて電子申告を義務化する方向で検討」とある。大企業の中でも電子申告をしていないところは少なからずある中で、電子申告を義務化する場合には、どの書類を対象とするのかが最大の論点の一つとなるだろう。
自社で使用する勘定科目名をそのまま使うことが可能に
電子申告を義務化するにあたっては、e-Taxの使い勝手の改善も重要なテーマとなる。基本計画では以下のような改善策を打ち出している(表2参照)。
【表2】e-Taxの使い勝手の大幅改善
まず注目されるのが、「ロ(ハ)法人納税者のe-Taxメッセージボックスの閲覧方法の改善」だ。多くの企業では、申告書等を作成する経理担当者と源泉徴収票を作成する給与担当者が分かれていることが少なくない。これは、源泉徴収票には役職員の個別の給与というセンシティブな個人情報が記載されているためである。ところが、現状のe-Taxでは、「メッセージボックス」がどの部署からも閲覧可能になっている。このため、給与の情報が担当者以外にも閲覧されてしまうことがある。そこで基本計画には、部署単位で情報を管理できるようメッセージボックスの閲覧方法の改善を行う旨が盛り込まれている。
また、「(ロ)e-Taxソフトにおける財務諸表の勘定科目設定機能の実装」は企業の負担軽減につながりそうだ。具体的には、企業が使用している勘定科目と、e-Taxで使われている国税庁指定の約1,600の勘定科目を関連付けることにより、企業は自社で使用している勘定科目をそのままの名称で使用することが可能になる。税務当局は会計ソフト会社にもこの関連付けへの対応を働きかける。
地方税の申告会場で作成したデータがe-Taxに
このほか、「ワンスオンリー原則」として、法人設立届出書等の電子的提出の一元化、電子申告における共通入力事務の重複排除などが実施される(表3参照)。
このうち「(イ)地方団体で作成した所得税確定申告書データの引継ぎの推進」とは、地方税の申告会場で所得税の確定申告書を作成した場合(地方ではよく見られる取り組み)、このデータをe-Taxに引き継ぐというもの。これにより、納税者は改めて税務署に所得税確定申告書を提出する必要がなくなる。
【表3】ワンスオンリー原則として実施される施策
平成30年度税制改正で議論へ 実施時期や対象書類は?
e-Tax「義務化」に向けた実務上の論点
政府が検討を進める電子申告制度の義務化に向けた「基本計画」が公表された。
基本計画では、法人税・消費税のe-Tax利用率として大法人は「100%」、中小法人は「85%以上(将来的には100%)」と高い目標値が設定されている。大法人の法人税・消費税の電子申告の義務化の時期については「平成29年度に検討を開始し、早期に結論を得る」とされるにとどまっているが、本誌取材によると、最速のケースでは平成30年度分の確定申告から電子申告が求められる可能性がある。電子申告制度の見直しは税調に議論の場を移し、平成30年度税制改正のテーマとなるだろう。
電子申告義務化の早期実現のカギを握るのが対象書類の範囲だ。現状は紙で提出されることが多い別表の内訳明細書、財務諸表や勘定科目内訳明細書なども含めすべての添付書類をe-Taxで提出することとなった場合、大規模なシステム改修を迫られる企業が出てくることも予想され、電子申告義務化の実施スケジュールに影響が出る可能性がある。
大企業に残る“紙による決裁文化”
「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)で「事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化、IT化を進める新たな規制・制度改革手法の導入」が打ち出されたことを受け、内閣府の規制改革推進会議に設けられた「行政手続部会」では、行政手続コストの削減策を検討してきたが、その中で、営業の許可・認可に係る手続や社会保険に関する手続などとともに「重点分野」に位置付けられているのが、国税と地方税の電子申告だ。行政手続部会は平成29年3月29日に各種の取組みの時期などを示した「行政手続部会取りまとめ」をとりまとめた後、4月17日の会合で「基本計画策定のための作業方針(案)」を示し、各省庁に対し本年6月末までに基本計画を作成し、公表することを求めていた。これを受け、財務省は2017年6月30日付で「行政手続コスト削減のための基本計画」を公表している。
所得税、法人税、消費税の申告や申請・届出等、国税の各種手続きの申告・納税システムである「e-Tax」の利用率は現状では表1のとおりとなっている。
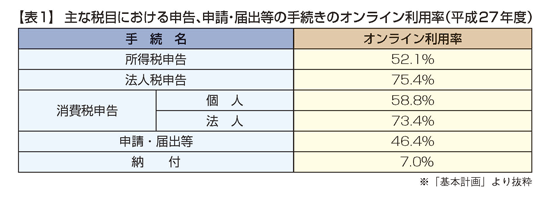
法人税申告のオンライン利用率は75.4%に達しているが、これを国税局の調査課所管法人(原則として資本金1億円以上の法人)に限ると、52.1%にとどまる。これは、大企業においては紙の書類による決裁文化が根強く残っているほか、経理担当者が自ら申告を行うケースが多いことなどが影響しているものとみられる。一方、中小企業では税理士が納税者に代わってオンラインで申告するケースが多いため、必然的にオンライン利用率も高率になるものと考えられる。
最速で平成30年6月申告分から義務化
ただし、今回の基本計画で打ち出された法人税・消費税についてのe-Tax利用率の目標値は大法人が「100%」、中小法人が「85%以上(将来的には100%)」と、大法人の方が高く設定されている。なお、ここでいう「大法人」とは、基本的には法人税法上の大法人である「資本金1億円超」の法人になると考えられるが、大法人の子会社である中小法人や連結納税を行っている場合における中小法人の取扱いも今後の重要論点となる。
企業にとってまず気になるのが実施時期だろう。基本計画では、大法人の法人税・消費税の電子申告の義務化の時期について、「平成29年度に検討を開始し、早期に結論を得る」(2頁2(1)参照)との記述にとどまっている。
そこで、基本計画のベースとなった規制改革推進会議の「行政手続部会取りまとめ」(平成29年3月29日付)を見ると、行政手続コストの削減に向けた「取組期間は、3年とする(平成31年度まで)。ただし事項によっては5年まで許容する(平成33年度まで)」とされている。規制改革推進会議では、電子申告の実施に向けた取組みのPDCAサイクルを回す観点から税務当局に早期対応を求めると考えられる。これから先、規制改革推進会議の枠組みで基本計画に関する各省からのヒアリングが行われることになるが、具体的な制度設計に関する検討の場は、政府税調や与党税調に移ることになるだろう。
税務当局も今のところ平成30年度税制改正で具体的な制度内容を固め、平成30年度分の申告からの義務化を視野に入れている模様。3月決算法人の単体納税の場合、平成30年度分の申告は、申告期限の1ヶ月延長を含めると実質的には平成31年6月、連結納税の場合は実質7月ということになる。これであれば、「行政手続部会取りまとめ」が求める「平成31年度まで」というハードルをクリアできる。
ただし、企業の準備に時間がかかる場合は、「平成31年度分の申告」(実際の申告のタイミングは平成32年6月又は7月)をもって「平成31年度まで」を満たすという考え方も存在している。この点についてはまだ確定しておらず、今後、議論されることになる。
添付書類も「原則」義務化
電子申告義務化の早期実現のカギを握るのが対象書類の範囲だ。
例えば外国税額控除に関する別表六(四)は、大企業になると件数があまりにも多すぎるため、別表上は総額だけを書き、内訳明細書は別途エクセルデータで作成して出力し、紙で提出するという企業も少なくない。減価償却資産に関する別表十六についても同じような問題がある。
また、財務諸表や勘定科目内訳明細書を紙で提出している企業は多い。
仮にこれらをすべてe-Taxで提出するとなると、企業によっては大規模なシステム改修が求められることになり、平成30年度分の申告までには対応が間に合わないとの声がある。そうなれば、段階的な制度の導入や移行措置が必要になる可能性もある。
基本原則には「原則として添付書類も含めて電子申告を義務化する方向で検討」とある。大企業の中でも電子申告をしていないところは少なからずある中で、電子申告を義務化する場合には、どの書類を対象とするのかが最大の論点の一つとなるだろう。
自社で使用する勘定科目名をそのまま使うことが可能に
電子申告を義務化するにあたっては、e-Taxの使い勝手の改善も重要なテーマとなる。基本計画では以下のような改善策を打ち出している(表2参照)。
【表2】e-Taxの使い勝手の大幅改善
| イ マイナポータルの利活用の推進
(イ)マイナポータルからe-Taxへのシームレスな認証連携 【29年1月実施】 (ロ)マイナポータルの「お知らせ」機能の活用 【31年1月以降順次実施に向けて検討】 ロ 認証手続等の簡便化 (イ)マイナポータルからe-Taxへのシームレスな認証連携 【29年1月実施】 (ロ)個人納税者のe-Tax利用の認証手続の簡便化 【31年1月実施予定】 (ハ)法人納税者のe-Taxメッセージボックスの閲覧方法の改善 【30年度実施に向けて検討】 ハ 申告書等の送信手続の利便性向上 (イ)申告書等の送信容量の拡大 【30年度実施に向けて検討】 (ロ)e-Taxソフトにおける財務諸表の勘定科目設定機能の実装 【30年度実施に向けて検討】 ニ e-Tax利用による手続簡素化 【31年度実施に向けて検討】 ホ e-Tax受付時間の更なる拡大 【30年度実施に向けて検討】 |
まず注目されるのが、「ロ(ハ)法人納税者のe-Taxメッセージボックスの閲覧方法の改善」だ。多くの企業では、申告書等を作成する経理担当者と源泉徴収票を作成する給与担当者が分かれていることが少なくない。これは、源泉徴収票には役職員の個別の給与というセンシティブな個人情報が記載されているためである。ところが、現状のe-Taxでは、「メッセージボックス」がどの部署からも閲覧可能になっている。このため、給与の情報が担当者以外にも閲覧されてしまうことがある。そこで基本計画には、部署単位で情報を管理できるようメッセージボックスの閲覧方法の改善を行う旨が盛り込まれている。
また、「(ロ)e-Taxソフトにおける財務諸表の勘定科目設定機能の実装」は企業の負担軽減につながりそうだ。具体的には、企業が使用している勘定科目と、e-Taxで使われている国税庁指定の約1,600の勘定科目を関連付けることにより、企業は自社で使用している勘定科目をそのままの名称で使用することが可能になる。税務当局は会計ソフト会社にもこの関連付けへの対応を働きかける。
地方税の申告会場で作成したデータがe-Taxに
このほか、「ワンスオンリー原則」として、法人設立届出書等の電子的提出の一元化、電子申告における共通入力事務の重複排除などが実施される(表3参照)。
このうち「(イ)地方団体で作成した所得税確定申告書データの引継ぎの推進」とは、地方税の申告会場で所得税の確定申告書を作成した場合(地方ではよく見られる取り組み)、このデータをe-Taxに引き継ぐというもの。これにより、納税者は改めて税務署に所得税確定申告書を提出する必要がなくなる。
【表3】ワンスオンリー原則として実施される施策
| (5)地方税との情報連携の徹底(法人設立届出書等の電子的提出の一元化、電子申告における共通入力事務の重複排除等)
イ 電子的提出の一元化等 (イ)地方団体で作成した所得税確定申告書データの引継ぎの推進 (ロ)給与・公的年金等の源泉徴収票及び支払報告書の電子的提出の一元化の推進 (ハ)法人納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出手続の電子的提出の一元化 【31年度実施に向けて検討】 (ニ)法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除 【総務省と連携して31年度実施に向けて検討】 ロ 国と地方の情報連携等 (イ)e-TaxとeLTAXの仕様の共通化の推進 【29年度以降順次実施】 (ロ)e-TaxソフトとeLTAXソフト(PCdesk)との連携の推進 【31年度実施に向けて検討】 (6)その他 イ 異動届出書等の提出先の一元化 【29年4月実施】 ロ 登記事項証明書(商業)の添付省略 【29年4月一部実施】 ハ 差額課税に係る酒税納税申告書の提出頻度削減 【29年4月実施】 ニ 印紙税一括納付承認申請の提出頻度削減 【制度改正を含め検討】 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























