解説記事2017年09月04日 【税務マエストロ】 租税条約の意義と現状②(2017年9月4日号・№705)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
租税条約の意義と現状②
#196 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#197
非課税(2)~土地の譲渡及び貸付け
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
1 租税条約の意義 租税条約の意義は、大きく「課税関係の明確化」及び「政府間協力の推進」という2つの側面でとらえることができる。これら2つの意義が相互に影響し合い、その結果、租税条約締結国間の投資及び経済の交流が促進されると考えられている。
(1)課税関係の明確化(承前)
(2)政府間協力の推進 租税条約の2つの意義のうち、「課税関係の明確化」は納税者サイドに大きなメリット等を与えることに重点をおいた政策である一方、「政府間協力の推進」は、条約タイトルにあるように「二重課税の回避及び脱税の防止」を主な目的とした税務行政面に着目した政策である。具体的には、脱税・租税回避防止に着目した政策手段と、二重課税の発生及びその排除、調整を実現するための政策手段に分けられる。その両面で、租税条約締結国の政府間が協力体制を構築、推進していくことが、租税条約の意義の一つといえる。
① 脱税・租税回避の防止 イ)濫用防止規定(特典条項)
租税条約の規定を巧みに利用し、結果的に租税負担の大幅な軽減を実現することは、租税回避の一形態と考えられている。租税負担の軽減と租税回避の境界線は必ずしも明確ではないが、本来的に租税条約が適用されるべきでない者に適用され、その結果租税条約の恩典(一般的には軽減税率等による課税の減免)が、その者に与えられてしまうことを租税条約の濫用(Treaty Shopping)としてとらえ、そうした濫用が起きないような手当てが租税条約には設けられている。
最も重要な規定は、「特典条項」といわれるもので、これは、その条約の適用により恩典を享受することができる者を制限するものである。この特典条項が定められていない場合、一般的には、その租税条約は相手国の居住者(相手国法人および相手国居住個人)であれば何の制限もなくその者に適用されることとなるものであるが、特典条項はその条約の適用に当たっての要件を定め、その要件を充足した者をいわゆる「適格者」として、その租税条約の恩典を享受することができる、つまり租税条約が適用される者とし、租税条約が適用されるべきでない者を排除している。
わが国は、2004年発効の米国との間の租税条約(日米租税条約:全面改正)においてはじめてこの特典条項を導入しているが、現在、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダ、スイス、ニュージーランド、スウェーデン、ドイツとの間との租税条約において特典条項を設けているところである。なお、この特典条項により、適格者とされる者は、例えば日米租税条約では、次の者に限定されている。
(i)個人
(ii)国、地方公共団体、中央銀行、特定の公益法人、年金基金
(iii)公開法人(上場企業)及びその関連企業
(iv)日米の居住者が一定割合を保有する法人
(v)適格に事業を行う法人
(vi)税務当局が適格者と認定した法人
また、租税条約によっては、特典条項の対象となる恩典の種類が異なる点にも注意を要する。つまり、租税条約によって源泉地免税とされる場合(たとえば、ロイヤルティの源泉税免税、株式等のキャピタルゲインの免税など)のみ、特典条項に定める要件を満たす必要があるとする租税条約もある。こうした租税条約の場合、その他の規定の適用に当たっては、特典条項の要件による制限はないこととなる。
ロ)情報交換
租税条約に定める政府間協力の典型例として、「情報交換」が挙げられる。これは、適正課税の実現のために有益と認められる種々の情報を、租税条約の相手国に提供する制度であり、その形態として、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び「自動的情報交換」の3つの形態に分類して捉えられている(図表1参照)。
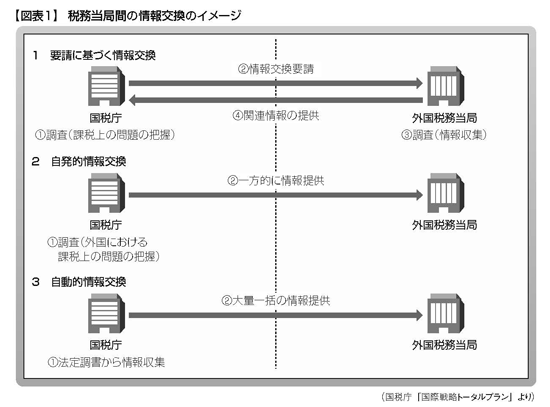
「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局に必要な情報の収集・提供を要請するもので、要請を受けた相手国からその対象となる情報の提供を受けることとなる。当然のことながら、わが国が相手国から情報提供の要請を受けることもあり、その際には、対象となる情報を入手するために税務調査が行われることとなる(脚注1)。「要請に基づく情報交換」は、海外の法人等との取引の内容や、海外金融機関の口座情報など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な情報の入手手段とされている。国税庁は、外国税務当局から海外法人の決算書及び申告書、登記情報、契約書、インボイス、銀行預金口座取引明細書、海外法人における経理処理が分かる資料のほか、外国税務当局の調査担当者が取引担当者に直接ヒアリングした内容などの情報が提供されており、調査に活用されているとしている。
「自発的情報交換」とは、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で相手国の税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供するものであり、まさしく国際協力の観点から重要視されてきている。
「自動的情報交換」とは、一般的には法定調書などから把握した非居住者等への支払等(利子、配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものである。現在、国税庁では、外国税務当局から「自動的情報交換」により提供を受けた利子、配当等に関する情報を申告内容と照合し、海外投資所得や国外財産等について内容を確認する必要があると認められた場合には、税務調査を行うなど、効果的に活用しているとしている。
なお、自動的情報交換の枠組みの一つとして、OECDは、平成26年に、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)及びその実施細則(コメンタリー)を公表し、わが国を含めG20がこれを承認している。この基準によれば、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座の口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報の報告を受け、その情報を租税条約等に基づいて、その非居住者の居住地国の税務当局に提供することになる。平成28年11月現在、101カ国・地域が、平成30年までにこの基準に従って自動的情報交換を開始することを表明しているが、わが国ではこの基準に対応するため、平成27年度税制改正において、国内に所在する金融機関等が口座保有者の氏名、住所、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報を所轄税務署長に報告する制度を導入したところである。この制度は平成29年1月1日から施行され、国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局に提供されることとなる。
ハ)徴収共助
租税条約の相手国の租税の滞納者につき、当該滞納された租税を、わが国において、わが国内にある財産から、相手国に代わって徴収し、それを相手国に送金等する制度が「徴収共助」である。租税を徴収するための権限は、執行管轄権の制約から、原則として、自国の領域外で行使することができないため、滞納者が海外に財産を有している場合でも、わが国の税務当局がその海外財産について滞納処分を執行することはできず、また逆に外国の滞納者がわが国内に財産を有していても、その財産に対して滞納処分を行うことはできないこととなる。これを可能とする制度が「徴収共助」と位置づけられる。具体的には、財産の所在地国が税務行政執行共助条約(いわゆる「マルチ条約」)又は「徴収共助」の規定を含む租税条約の締約国である場合には、締約国の税務当局が協力して互いに相手国の租税を徴収する「徴収共助」の枠組みにより対処することとなる(脚注2)。
なお、わが国においては、マルチ条約が平成25(2013)年10月に発効し、平成28(2016)年10月現在、マルチ条約の締約国はわが国を含め65カ国となっている。このうち、徴収共助を実施することとしているのは48の国・地域であり、また、既存の二国間の租税条約に徴収共助の規定を追加する条約改正が順次行われるなど、現在徴収共助のネットワークが拡充している状況である。
② 相互協議 相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続である。わが国においては、61の租税条約(適用対象国・地域は72か国・地域)において、相互協議に関する規定が置かれている。
相互協議の前提となる「租税条約の規定に適合しない課税」とは、租税条約に定められた課税原則に反する課税であり、直接的には源泉地では免税となる所得に対する課税(たとえば、PEを有しない相手国法人に対する課税や、限度税率以上の課税など)であるが、結果的に二重課税となる課税(たとえば移転価格税制に基づく課税)も含まれる。
現在、相互協議の発生件数は、年間150件から200件程度であるが、おおむねその8割近くが「事前確認」に関するもので、その意味では、租税条約に基づく相互協議(事前確認)によりあらかじめ二重課税の発生を阻止する効果がもたらされているととらえることができる(図表2参照)。
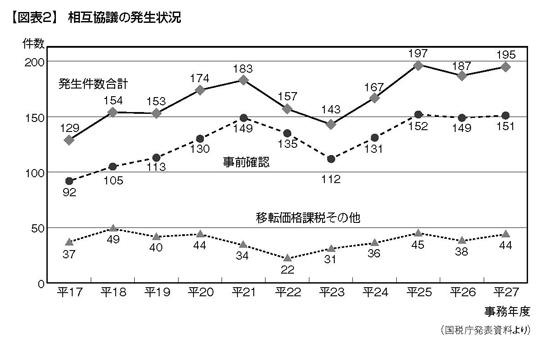
③ 無差別条項 租税条約には、相手国企業又は個人に対する課税上の無差別取扱いが定められている。これは、直接的には、両国間の税務当局が積極的に協力して行動を起こす制度ではないが、相手国企業、個人に内国民待遇を保証することであり、その意味では協力関係ともいえよう。
租税条約に定められている無差別取扱いは、一般的に相手国の国民を自国民と同等に取り扱う「国籍無差別」、相手国の企業(つまりはPE)を自国企業と同等に取り扱う「PE無差別」、相手国企業の子会社を自国企業と同様に扱う「資本無差別」が定められている。これら各無差別条項は、相互協議等で、相手国の行き過ぎた課税に対して反論する際には有効な論拠となると考えられる。
脚注
1 租税条約実施特例法第9条
2 租税条約実施特例法第11条、第11条の2
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
租税条約の意義と現状②
#196 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#197
非課税(2)~土地の譲渡及び貸付け
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
1 租税条約の意義 租税条約の意義は、大きく「課税関係の明確化」及び「政府間協力の推進」という2つの側面でとらえることができる。これら2つの意義が相互に影響し合い、その結果、租税条約締結国間の投資及び経済の交流が促進されると考えられている。
(1)課税関係の明確化(承前)
(2)政府間協力の推進 租税条約の2つの意義のうち、「課税関係の明確化」は納税者サイドに大きなメリット等を与えることに重点をおいた政策である一方、「政府間協力の推進」は、条約タイトルにあるように「二重課税の回避及び脱税の防止」を主な目的とした税務行政面に着目した政策である。具体的には、脱税・租税回避防止に着目した政策手段と、二重課税の発生及びその排除、調整を実現するための政策手段に分けられる。その両面で、租税条約締結国の政府間が協力体制を構築、推進していくことが、租税条約の意義の一つといえる。
① 脱税・租税回避の防止 イ)濫用防止規定(特典条項)
租税条約の規定を巧みに利用し、結果的に租税負担の大幅な軽減を実現することは、租税回避の一形態と考えられている。租税負担の軽減と租税回避の境界線は必ずしも明確ではないが、本来的に租税条約が適用されるべきでない者に適用され、その結果租税条約の恩典(一般的には軽減税率等による課税の減免)が、その者に与えられてしまうことを租税条約の濫用(Treaty Shopping)としてとらえ、そうした濫用が起きないような手当てが租税条約には設けられている。
最も重要な規定は、「特典条項」といわれるもので、これは、その条約の適用により恩典を享受することができる者を制限するものである。この特典条項が定められていない場合、一般的には、その租税条約は相手国の居住者(相手国法人および相手国居住個人)であれば何の制限もなくその者に適用されることとなるものであるが、特典条項はその条約の適用に当たっての要件を定め、その要件を充足した者をいわゆる「適格者」として、その租税条約の恩典を享受することができる、つまり租税条約が適用される者とし、租税条約が適用されるべきでない者を排除している。
わが国は、2004年発効の米国との間の租税条約(日米租税条約:全面改正)においてはじめてこの特典条項を導入しているが、現在、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダ、スイス、ニュージーランド、スウェーデン、ドイツとの間との租税条約において特典条項を設けているところである。なお、この特典条項により、適格者とされる者は、例えば日米租税条約では、次の者に限定されている。
(i)個人
(ii)国、地方公共団体、中央銀行、特定の公益法人、年金基金
(iii)公開法人(上場企業)及びその関連企業
(iv)日米の居住者が一定割合を保有する法人
(v)適格に事業を行う法人
(vi)税務当局が適格者と認定した法人
また、租税条約によっては、特典条項の対象となる恩典の種類が異なる点にも注意を要する。つまり、租税条約によって源泉地免税とされる場合(たとえば、ロイヤルティの源泉税免税、株式等のキャピタルゲインの免税など)のみ、特典条項に定める要件を満たす必要があるとする租税条約もある。こうした租税条約の場合、その他の規定の適用に当たっては、特典条項の要件による制限はないこととなる。
ロ)情報交換
租税条約に定める政府間協力の典型例として、「情報交換」が挙げられる。これは、適正課税の実現のために有益と認められる種々の情報を、租税条約の相手国に提供する制度であり、その形態として、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び「自動的情報交換」の3つの形態に分類して捉えられている(図表1参照)。
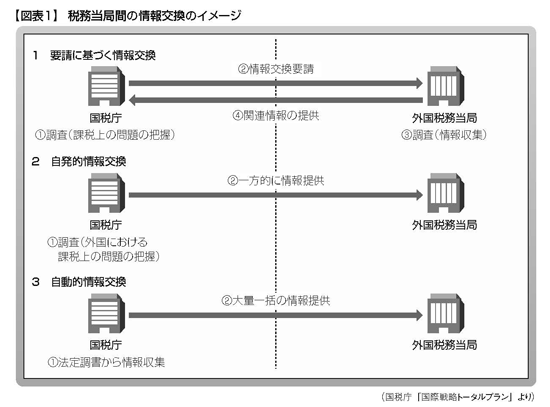
「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局に必要な情報の収集・提供を要請するもので、要請を受けた相手国からその対象となる情報の提供を受けることとなる。当然のことながら、わが国が相手国から情報提供の要請を受けることもあり、その際には、対象となる情報を入手するために税務調査が行われることとなる(脚注1)。「要請に基づく情報交換」は、海外の法人等との取引の内容や、海外金融機関の口座情報など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な情報の入手手段とされている。国税庁は、外国税務当局から海外法人の決算書及び申告書、登記情報、契約書、インボイス、銀行預金口座取引明細書、海外法人における経理処理が分かる資料のほか、外国税務当局の調査担当者が取引担当者に直接ヒアリングした内容などの情報が提供されており、調査に活用されているとしている。
「自発的情報交換」とは、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で相手国の税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供するものであり、まさしく国際協力の観点から重要視されてきている。
「自動的情報交換」とは、一般的には法定調書などから把握した非居住者等への支払等(利子、配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものである。現在、国税庁では、外国税務当局から「自動的情報交換」により提供を受けた利子、配当等に関する情報を申告内容と照合し、海外投資所得や国外財産等について内容を確認する必要があると認められた場合には、税務調査を行うなど、効果的に活用しているとしている。
なお、自動的情報交換の枠組みの一つとして、OECDは、平成26年に、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)及びその実施細則(コメンタリー)を公表し、わが国を含めG20がこれを承認している。この基準によれば、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座の口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報の報告を受け、その情報を租税条約等に基づいて、その非居住者の居住地国の税務当局に提供することになる。平成28年11月現在、101カ国・地域が、平成30年までにこの基準に従って自動的情報交換を開始することを表明しているが、わが国ではこの基準に対応するため、平成27年度税制改正において、国内に所在する金融機関等が口座保有者の氏名、住所、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報を所轄税務署長に報告する制度を導入したところである。この制度は平成29年1月1日から施行され、国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局に提供されることとなる。
ハ)徴収共助
租税条約の相手国の租税の滞納者につき、当該滞納された租税を、わが国において、わが国内にある財産から、相手国に代わって徴収し、それを相手国に送金等する制度が「徴収共助」である。租税を徴収するための権限は、執行管轄権の制約から、原則として、自国の領域外で行使することができないため、滞納者が海外に財産を有している場合でも、わが国の税務当局がその海外財産について滞納処分を執行することはできず、また逆に外国の滞納者がわが国内に財産を有していても、その財産に対して滞納処分を行うことはできないこととなる。これを可能とする制度が「徴収共助」と位置づけられる。具体的には、財産の所在地国が税務行政執行共助条約(いわゆる「マルチ条約」)又は「徴収共助」の規定を含む租税条約の締約国である場合には、締約国の税務当局が協力して互いに相手国の租税を徴収する「徴収共助」の枠組みにより対処することとなる(脚注2)。
なお、わが国においては、マルチ条約が平成25(2013)年10月に発効し、平成28(2016)年10月現在、マルチ条約の締約国はわが国を含め65カ国となっている。このうち、徴収共助を実施することとしているのは48の国・地域であり、また、既存の二国間の租税条約に徴収共助の規定を追加する条約改正が順次行われるなど、現在徴収共助のネットワークが拡充している状況である。
② 相互協議 相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続である。わが国においては、61の租税条約(適用対象国・地域は72か国・地域)において、相互協議に関する規定が置かれている。
相互協議の前提となる「租税条約の規定に適合しない課税」とは、租税条約に定められた課税原則に反する課税であり、直接的には源泉地では免税となる所得に対する課税(たとえば、PEを有しない相手国法人に対する課税や、限度税率以上の課税など)であるが、結果的に二重課税となる課税(たとえば移転価格税制に基づく課税)も含まれる。
現在、相互協議の発生件数は、年間150件から200件程度であるが、おおむねその8割近くが「事前確認」に関するもので、その意味では、租税条約に基づく相互協議(事前確認)によりあらかじめ二重課税の発生を阻止する効果がもたらされているととらえることができる(図表2参照)。
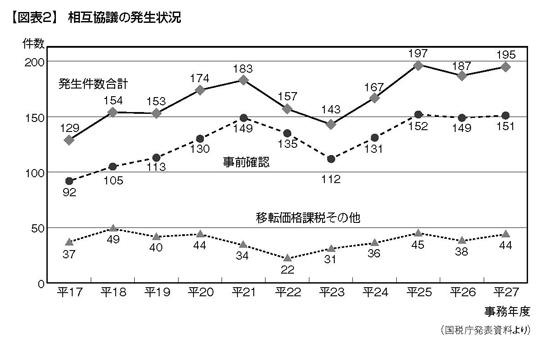
③ 無差別条項 租税条約には、相手国企業又は個人に対する課税上の無差別取扱いが定められている。これは、直接的には、両国間の税務当局が積極的に協力して行動を起こす制度ではないが、相手国企業、個人に内国民待遇を保証することであり、その意味では協力関係ともいえよう。
租税条約に定められている無差別取扱いは、一般的に相手国の国民を自国民と同等に取り扱う「国籍無差別」、相手国の企業(つまりはPE)を自国企業と同等に取り扱う「PE無差別」、相手国企業の子会社を自国企業と同様に扱う「資本無差別」が定められている。これら各無差別条項は、相互協議等で、相手国の行き過ぎた課税に対して反論する際には有効な論拠となると考えられる。
脚注
1 租税条約実施特例法第9条
2 租税条約実施特例法第11条、第11条の2
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















