解説記事2017年10月02日 【税務マエストロ】 租税条約の意義と現状③(2017年10月2日号・№709)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
租税条約の意義と現状③
#198 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#199
非課税(3)~有価証券・支払手段の譲渡
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
2 租税条約における重要な前提
(1)租税条約と国内法の関係
① 租税条約の優先 租税条約を含む「条約」は、関連国内法制に優先してその効力を有するというのが、現状における一般的な理解である。この原則は、それぞれ各条約に明文として規定されているものではないが、憲法第98条第2項の「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という規定が根拠とされる。したがって、一般的には、租税条約の定めに抵触するような国内法を制定したとしても、租税条約の定めが優先し、その範囲において国内法の規定が適用されないこととなる。例えば、租税条約における限度税率(源泉徴収税率)を適用せず、それを超える税率で源泉徴収することを求める規定を法制化したとしても、その規定は適用されず、租税条約の限度税率を超える税率での源泉徴収はできないこととなる。
② 米国における「後法優先」 日本をはじめ、諸外国では、上記のごとく「条約」が国内法に優先することと理解されているが、米国はこうした国際的な理解と相反する考え方を採っている。米国においては、国内法も国際法も等位であり、したがって後に定められた内容が既存の規定の内容に抵触する場合には、前の内容を否定する後の内容が優先するという考え方を採っている。結果的に先に定められた租税条約をオーバーライドする国内法(後法)が優先することがありえることとなる。たとえば1980年にはFIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax of 1980)により、米国非居住者による一定の米国所在不動産を保有する米国法人の株式の譲渡について、株式譲渡でなく不動産譲渡と捉えて課税するとし、事実課税されてきている。こうした場合には、当然のことながら、米国は国際約束である租税条約を履行しないという立場に置かれることになるが、現実的には、相手国はこれを阻止できていない状況である。かつて、米国サーベンス上院議員の、各国は米国によるオーバーライドの可能性を認識した上で条約を締結しているのであるから条約をオーバーライドする国内法は条約違反とはいえない旨の発言に対し、ドイツの関係者から猛烈な抗議が寄せられ、物議をかもしたことがある。
なお、現行の日米租税条約では、こうした紛争を防ぐ観点から、条約違反となる国内法改正がある場合には、日米両国間で協議をすることが定められている(29条)。この協議は、その協議の要請があってから3ヶ月以内に行われることとなるが、その協議において、具体的にどのような措置が検討されるのか、また、そもそも特別な措置を講じることが可能かどうか明らかではない。
(2)プリザベーション・クローズ プリザベーション・クローズとは、租税条約及びその解釈における一般原則である。具体的には、租税条約によって国内法に基づく租税負担以上の課税ができないことである。たとえば、国内法では非課税所得とされているにも関わらず、租税条約を根拠に当該所得に課税したり、また、国内法による税率以上の課税を租税条約に定めたとしても、その税率による課税はできないという原則である。つまり、結果的に、租税条約は課税を減免する方向にしか働かないこととなる。租税条約は国内法に優先するのであるが、それは納税者にとって有利な場合のみ優先するということとなる。
なお、この原則は、明文の規定がなくとも租税条約の一般原則として考えられているところであるが、現行の日米租税条約には次のように明示されている(脚注1)。
(3)セイビング・クローズ
セイビング・クローズとは、租税条約は相手国の居住者に適用されるもので、自国の居住者には適用されないという原則である。つまり、租税条約は相手国の居住者(自国にとっては非居住者)に対する租税の減免等の課税関係を定めるものであって、自国の居住者の課税関係には影響を及ぼさない、つまり居住者の租税は租税条約によって減免されないというものである(脚注2)。自国の居住者には租税条約を適用しないという意味で、自国民留保とも呼ばれる。
また、セイビング・クローズは、一般的には明文として規定されることは少ないが、例外的に規定されることもある。例えば、現行日米租税条約では次のように規定されている。
なお、米国との間では、上記のように、自国居住者に対しては国内法による課税(つまり条約は適用されない)を行うことを定めつつ、米国市民課税も居住者課税と扱われるため、結果的に米国市民課税の容認という意味合いもある(脚注3)。また、租税回避を意図して、米国居住者又は米国市民の地位を失った場合には、米国におけるセイビング・クローズの適用は、10年間留保されている。つまり、米国が、租税回避のために米国市民でなくなったと認定した場合には、その後10年間は市民課税を行うことができることとなる。たとえば5年前に米国を出国して日本居住者となった個人が日米条約の適用に当たり、米国税務当局から当該出国は租税回避の意図ありと認定された場合には、条約を適用せず、国内法に基づく市民課税を行うことがありえるのである。こうした場合、租税回避の意図があるかどうかの判断は、一義的には米国当局に委ねられることとなり、納税者サイドの主張や日本当局の主張と相容れないケースも生じよう。そうした場合には、結果的に相互協議により解決されることになろう。
3 我が国の租税条約ネットワーク 現在、わが国が締結している租税に関する条約は、2国間条約及び多国間条約の2種類あり、内容的には、課税の減免を定める条約と政府間協力を定める条約に分類できる。これらは重複して適用されることもある。次の財務省資料から、地理的なイメージとあわせて、わが国の租税条約ネットワークを把握することができよう(次頁図参照)。
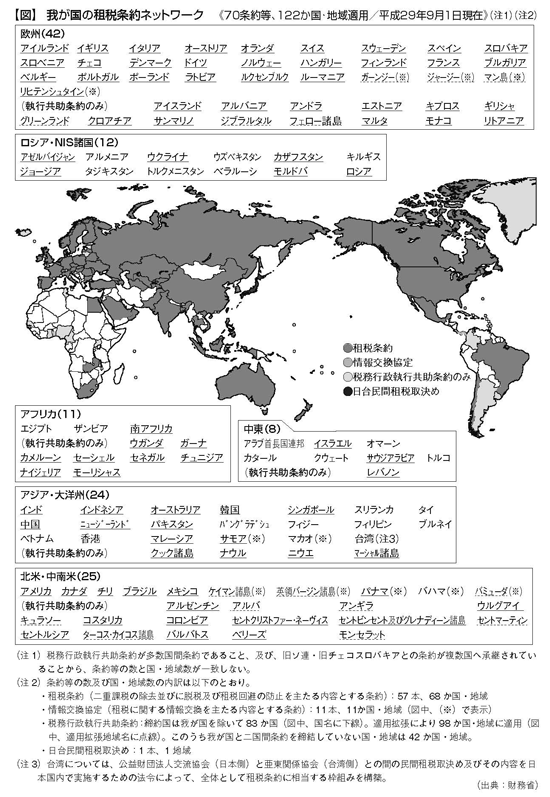
① 一般的な租税条約 現在わが国が締結している租税条約は、OECDモデル条約に準拠したものとなっている。これは、日本がOECD加盟国の主要なメンバーとして、モデル条約やその解釈等OECDにおける国際課税分野の議論を主導してきたことに一因があろう。OECDモデル条約は、その前身であるOEEC(欧州経済協力機構)の時代から検討を始め、OECD(経済協力開発機構)となってから、1963年に「所得及び資本に対する二重課税回避のための条約草案」として公表された条約草案がベースとなっている。その後一部が改正されて1977年にOECDの閣僚理事会で正式に採択されたものが、一般に認識されていた「OECDモデル条約」である。なお、昨今OECDモデル条約及びコメンタリーは頻繁に改正され、現在に至っている。
一方、OECDモデル条約に相対するものとして、国連モデル条約がある。現在の国連モデル条約は、先進国と発展途上国との間のモデル条約といわれている。いわゆる先進国クラブといわれるOECDが制定したOECDモデル条約と比して、より発展途上国側の視点に立った課税原則が盛り込まれている。つまり、より発展途上国側により大きな課税権を認める傾向があり、具体的には、源泉地国での源泉税率がOECDモデルに比して高く、また事業所得の課税権の根拠となるPEの範囲が広くとらえられている。課税権の配分という視点では、発展途上国の課税権に重きを置くことは合理的であるが、発展途上国が外国資本による対内投資の促進を図るという視点では、課税権の確保というポリシーは逆効果となる可能性もあろう。
② 情報交換条約 OECDは情報交換に特化した規定のみで構成される情報交換条約のモデルを公表している。これは、タックスヘイブン等から、租税に関する情報を収集することを目的としているものであるが、一方OECDメンバー国(具体的にはスイス、ベルギー、ルクセンブルグ、オーストリアなど)が採る過剰な銀行秘密政策の打破ということも目的であったようである。こうした観点では、情報交換条約の意義は、課税に結びつく情報の収集というより資産(資金)の秘匿性やマネーロンダリング等の問題への対抗策としての意味合いが強いものといえる。
なお、わが国は、一般的にタックスヘイブンと呼ばれる諸国との間(11か国・地域)で情報交換条約を締結しているが、これらの国・地域には、「パナマ文書」問題で話題となったパナマや英領バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダなどが含まれている。また、香港との租税条約は、形式上は一般的な租税条約の形態であるが、その意味合いとしては、情報交換条約と位置付けることができよう。
③ 税務行政執行共助条約 我が国が2011年11月に署名した「租税に関する相互行政支援に関する条約」がいわゆる「税務行政執行共助条約」といわれる多国間条約である。この条約は、署名した締結国間で税金に関する行政支援、具体的には「情報交換」、「徴収共助」、「送達共助」を相互に行うことを定めるもので、国税庁等の税務当局間で協力して国際的な脱税および租税回避行為に対処していくことを目的とした条約である。この条約は、留保(脚注4)を付しての署名が認められているが、2017年8月現在、112か国・地域が署名済みであり、2013年10月に発効している。
④ BEPS多国間条約 BEPS多国間条約は、BEPSプロジェクト行動15の勧告に基づき、我が国を含むおよそ100か国・地域が参加した交渉によって策定され、2016年12月31日に署名のために解放され、2017年6月7日にわが国も含め67か国・地域が署名し、現在70か国・地域が署名に至っている。
この条約は、2国間の租税条約の改正プロセスは多大な時間と労力を要することから、こうした通常の改正プロセスを踏まずに、改正の効果を実現するために考え出されたものと位置付けることができる。既存の条約の特定の部分のみを修正するものであり、当該BEPS多国間条約に署名した特定国の間では、既存の租税条約の規定を修正した内容のBEPS多国間条約の規定が適用されることとなる。しかしながら、プリザベーション・クローズとの関係では、当該BEPS多国間条約により修正される内容は、慎重に選択される必要があろう。
脚注
1 現行日米租税条約における当該規定は、旧日米条約(1971年3月署名、2004年3月現行条約発効により、失効)にも、同様に定められていた(第4条2項)。
2 一般的な租税条約には、外国税額控除に関する規定(特にタックススペアリングなど)、所得税法上居住者に該当する「学生」、「教授」等に対する減免措置等、セイビング・クローズの例外となる規定もある。
3 日本の居住者と競合する場合(二重居住者となる場合)には、市民課税との競合においては日本の居住性が優先し(4条2項(a))、通常の二重居住者である場合には4条3項の規定に基づき振り分けられることとなる。
4 留保とは、条約の特定の規定については合意しない、したがって義務的適用を保証しないことをいう。例えば、税務行政執行条約でいえば、情報交換は実行するが、徴収共助は実行しないことが可能となる。
この記事に関するご意見・お問合せはta@lotus21.co.jpにお寄せください。
今週のマエストロ&テーマ
租税条約の意義と現状③
#198 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#199
非課税(3)~有価証券・支払手段の譲渡
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
2 租税条約における重要な前提
(1)租税条約と国内法の関係
① 租税条約の優先 租税条約を含む「条約」は、関連国内法制に優先してその効力を有するというのが、現状における一般的な理解である。この原則は、それぞれ各条約に明文として規定されているものではないが、憲法第98条第2項の「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という規定が根拠とされる。したがって、一般的には、租税条約の定めに抵触するような国内法を制定したとしても、租税条約の定めが優先し、その範囲において国内法の規定が適用されないこととなる。例えば、租税条約における限度税率(源泉徴収税率)を適用せず、それを超える税率で源泉徴収することを求める規定を法制化したとしても、その規定は適用されず、租税条約の限度税率を超える税率での源泉徴収はできないこととなる。
② 米国における「後法優先」 日本をはじめ、諸外国では、上記のごとく「条約」が国内法に優先することと理解されているが、米国はこうした国際的な理解と相反する考え方を採っている。米国においては、国内法も国際法も等位であり、したがって後に定められた内容が既存の規定の内容に抵触する場合には、前の内容を否定する後の内容が優先するという考え方を採っている。結果的に先に定められた租税条約をオーバーライドする国内法(後法)が優先することがありえることとなる。たとえば1980年にはFIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax of 1980)により、米国非居住者による一定の米国所在不動産を保有する米国法人の株式の譲渡について、株式譲渡でなく不動産譲渡と捉えて課税するとし、事実課税されてきている。こうした場合には、当然のことながら、米国は国際約束である租税条約を履行しないという立場に置かれることになるが、現実的には、相手国はこれを阻止できていない状況である。かつて、米国サーベンス上院議員の、各国は米国によるオーバーライドの可能性を認識した上で条約を締結しているのであるから条約をオーバーライドする国内法は条約違反とはいえない旨の発言に対し、ドイツの関係者から猛烈な抗議が寄せられ、物議をかもしたことがある。
なお、現行の日米租税条約では、こうした紛争を防ぐ観点から、条約違反となる国内法改正がある場合には、日米両国間で協議をすることが定められている(29条)。この協議は、その協議の要請があってから3ヶ月以内に行われることとなるが、その協議において、具体的にどのような措置が検討されるのか、また、そもそも特別な措置を講じることが可能かどうか明らかではない。
(2)プリザベーション・クローズ プリザベーション・クローズとは、租税条約及びその解釈における一般原則である。具体的には、租税条約によって国内法に基づく租税負担以上の課税ができないことである。たとえば、国内法では非課税所得とされているにも関わらず、租税条約を根拠に当該所得に課税したり、また、国内法による税率以上の課税を租税条約に定めたとしても、その税率による課税はできないという原則である。つまり、結果的に、租税条約は課税を減免する方向にしか働かないこととなる。租税条約は国内法に優先するのであるが、それは納税者にとって有利な場合のみ優先するということとなる。
なお、この原則は、明文の規定がなくとも租税条約の一般原則として考えられているところであるが、現行の日米租税条約には次のように明示されている(脚注1)。
| 第1条第2項
この条約の規定は、次のものによって現在又は将来認められる非課税、免税、所得控除、税額控除その他の租税の減免をいかなる態様においても制限するものと解してはならない。 (a)一方の締約国が課する租税の額を決定するに当たって適用される当該一方の締約国の法令 (b)両締約国間の他の二国間協定又は両締約国が当事国となっている多国間協定 |
また、セイビング・クローズは、一般的には明文として規定されることは少ないが、例外的に規定されることもある。例えば、現行日米租税条約では次のように規定されている。
| 第1条4項 (a)この条約は、5の場合を除くほか、第4条の規定に基づき一方の締約国の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税及び合衆国の市民に対する合衆国の課税に影響を及ぼすものではない。 |
3 我が国の租税条約ネットワーク 現在、わが国が締結している租税に関する条約は、2国間条約及び多国間条約の2種類あり、内容的には、課税の減免を定める条約と政府間協力を定める条約に分類できる。これらは重複して適用されることもある。次の財務省資料から、地理的なイメージとあわせて、わが国の租税条約ネットワークを把握することができよう(次頁図参照)。
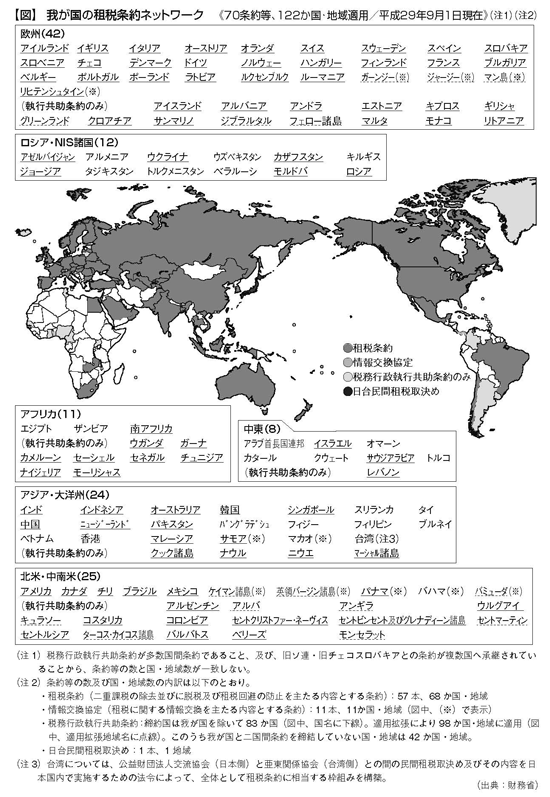
① 一般的な租税条約 現在わが国が締結している租税条約は、OECDモデル条約に準拠したものとなっている。これは、日本がOECD加盟国の主要なメンバーとして、モデル条約やその解釈等OECDにおける国際課税分野の議論を主導してきたことに一因があろう。OECDモデル条約は、その前身であるOEEC(欧州経済協力機構)の時代から検討を始め、OECD(経済協力開発機構)となってから、1963年に「所得及び資本に対する二重課税回避のための条約草案」として公表された条約草案がベースとなっている。その後一部が改正されて1977年にOECDの閣僚理事会で正式に採択されたものが、一般に認識されていた「OECDモデル条約」である。なお、昨今OECDモデル条約及びコメンタリーは頻繁に改正され、現在に至っている。
一方、OECDモデル条約に相対するものとして、国連モデル条約がある。現在の国連モデル条約は、先進国と発展途上国との間のモデル条約といわれている。いわゆる先進国クラブといわれるOECDが制定したOECDモデル条約と比して、より発展途上国側の視点に立った課税原則が盛り込まれている。つまり、より発展途上国側により大きな課税権を認める傾向があり、具体的には、源泉地国での源泉税率がOECDモデルに比して高く、また事業所得の課税権の根拠となるPEの範囲が広くとらえられている。課税権の配分という視点では、発展途上国の課税権に重きを置くことは合理的であるが、発展途上国が外国資本による対内投資の促進を図るという視点では、課税権の確保というポリシーは逆効果となる可能性もあろう。
② 情報交換条約 OECDは情報交換に特化した規定のみで構成される情報交換条約のモデルを公表している。これは、タックスヘイブン等から、租税に関する情報を収集することを目的としているものであるが、一方OECDメンバー国(具体的にはスイス、ベルギー、ルクセンブルグ、オーストリアなど)が採る過剰な銀行秘密政策の打破ということも目的であったようである。こうした観点では、情報交換条約の意義は、課税に結びつく情報の収集というより資産(資金)の秘匿性やマネーロンダリング等の問題への対抗策としての意味合いが強いものといえる。
なお、わが国は、一般的にタックスヘイブンと呼ばれる諸国との間(11か国・地域)で情報交換条約を締結しているが、これらの国・地域には、「パナマ文書」問題で話題となったパナマや英領バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダなどが含まれている。また、香港との租税条約は、形式上は一般的な租税条約の形態であるが、その意味合いとしては、情報交換条約と位置付けることができよう。
③ 税務行政執行共助条約 我が国が2011年11月に署名した「租税に関する相互行政支援に関する条約」がいわゆる「税務行政執行共助条約」といわれる多国間条約である。この条約は、署名した締結国間で税金に関する行政支援、具体的には「情報交換」、「徴収共助」、「送達共助」を相互に行うことを定めるもので、国税庁等の税務当局間で協力して国際的な脱税および租税回避行為に対処していくことを目的とした条約である。この条約は、留保(脚注4)を付しての署名が認められているが、2017年8月現在、112か国・地域が署名済みであり、2013年10月に発効している。
④ BEPS多国間条約 BEPS多国間条約は、BEPSプロジェクト行動15の勧告に基づき、我が国を含むおよそ100か国・地域が参加した交渉によって策定され、2016年12月31日に署名のために解放され、2017年6月7日にわが国も含め67か国・地域が署名し、現在70か国・地域が署名に至っている。
この条約は、2国間の租税条約の改正プロセスは多大な時間と労力を要することから、こうした通常の改正プロセスを踏まずに、改正の効果を実現するために考え出されたものと位置付けることができる。既存の条約の特定の部分のみを修正するものであり、当該BEPS多国間条約に署名した特定国の間では、既存の租税条約の規定を修正した内容のBEPS多国間条約の規定が適用されることとなる。しかしながら、プリザベーション・クローズとの関係では、当該BEPS多国間条約により修正される内容は、慎重に選択される必要があろう。
脚注
1 現行日米租税条約における当該規定は、旧日米条約(1971年3月署名、2004年3月現行条約発効により、失効)にも、同様に定められていた(第4条2項)。
2 一般的な租税条約には、外国税額控除に関する規定(特にタックススペアリングなど)、所得税法上居住者に該当する「学生」、「教授」等に対する減免措置等、セイビング・クローズの例外となる規定もある。
3 日本の居住者と競合する場合(二重居住者となる場合)には、市民課税との競合においては日本の居住性が優先し(4条2項(a))、通常の二重居住者である場合には4条3項の規定に基づき振り分けられることとなる。
4 留保とは、条約の特定の規定については合意しない、したがって義務的適用を保証しないことをいう。例えば、税務行政執行条約でいえば、情報交換は実行するが、徴収共助は実行しないことが可能となる。
この記事に関するご意見・お問合せはta@lotus21.co.jpにお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















