解説記事2018年01月15日 【ニュース特集】 役員退職金の過大判定で東京地裁が注目判決(2018年1月15日号・№722)
ニュース特集
平均功績倍率の“1.5倍”まで損金算入可も、国側は控訴を提起
役員退職金の過大判定で東京地裁が注目判決
原告法人が死亡退職した代表取締役に支給した役員退職給与のなかに損金不算入となる「不相当に高額」な部分の金額があるか否かが争われた税務訴訟で東京地裁は平成29年10月13日、法人税更正処分等の一部を取り消す判決を下した。今回の判決で注目されるのは、役員退職給与の過大判定をめぐり、東京地裁が「特段の事情がない限り、同業類似法人の平均功績倍率の“1.5倍”を用いて役員退職給与の相当額を算定すべき」という判断基準を示した点である。東京地裁が示した判断基準が確定すれば、類似事案に影響を及ぼす可能性もあるなか、国側は国側(控訴人)敗訴部分については全て不服であるとして控訴を提起している。注目される東京高裁(控訴審)判決は、年内(早ければ夏頃)にも下される見込みだ。
納税者側は最高功績倍率を、国側は平均功績倍率を採用すべきと主張
損金算入の対象となる役員退職給与であっても、その役員退職給与の額に「不相当に高額」(法法34②、法令70二)な部分の金額があれば、その不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされている(下囲み参照)。今回紹介する税務訴訟で問題となったのは、原告法人が死亡退職した代表取締役に対して支給した役員退職給与の額に不相当に高額な部分の金額として損金に算入されない金額があるか否かという点である。
(編注・条文一部簡略化)
事実関係をみると、建材金物の製造販売等を目的とする原告法人(同族会社)は、平成20年10月に死亡退職した代表取締役に対して、功績倍率法に基づく役員退職給与4億2,000万円を次の算式により計算したうえで平成21年8月期中に支給していた。この支給額は、原告法人の役員退職慰労金規定および臨時株主総会の決議に基づくものである。
これに対し税務署は、独自に抽出した同業類似法人5社の平均功績倍率が「3.35」であったことから、役員退職給与の適正額を約2億1,700万円と算定したうえで、同額を超える約2億300万円が不相当に高額であるとして損金算入を否認する法人税更正処分等を行った。これを不服とした原告法人は審査請求を行ったものの、国税不服審判所が棄却の裁決(なお裁決のなかで審判所は、端数処理などに誤りがあることから平均功績倍率を「3.26」と認定している)を下したことから、東京地裁に対して法人税更正処分等の取り消しを求める訴訟を提起していた。
国側、3方法のうち平均功績倍率法が合理的 納税者の訴えに対し被告である国側は、役員退職給与相当額の算定方法として、「平均功績倍率法」、「1年当たり平均額法」、「最高功績倍率法」の3つ(表1参照)を挙げたうえで、このうち「平均功績倍率法」が法令(法法34②、法令70二)の趣旨に最も合致する合理的な算定方法であると指摘。本件における役員退職給与相当額の算定に当たっても平均功績倍率法を用いることが相当であるとしたうえで、平均功績倍率「3.26」により算定した役員退職給与約2億1,124万円を超える約2億875万円は不相当に高額な金額(法法34②)として損金に算入されないと主張した。これに対し納税者側は、最高功績倍率法等の納税者により有利な算定方法を採用すべきであると反論していた。
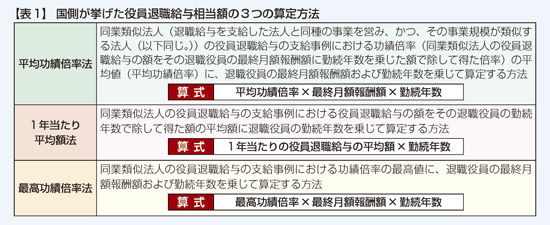
地裁、特段の事情がない限り平均功績倍率の“1.5倍”で適正額を算定すべき
東京地裁は、納税者が主張した最高功績倍率法について、①功績倍率の最高値は最高値に係る法人の特殊性等に影響されるもので指標として客観性が劣ること、②合理的な抽出基準により同業類似法人が5法人という相当数の法人が抽出されているうえ、これらの法人の功績倍率に極端なバラつきがなく、その僅差も平均の30%程度の範囲内に収まっていることを指摘し、最高功績倍率法がより適切であるとみるべき事情は見当たらないとした。一方で、国側が主張した平均功績倍率法について地裁は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われ、かつ、その平均功績倍率を適用することが相当と認められる限り、法令(法法34②、法令70二)の趣旨に合致する合理的な方法であると判断した。
そして地裁は、国側が原告法人の同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準が合理的であると認められるか否かを検討。ここで地裁は、国側が用いた5つの抽出基準(①同一県内に納税地を有すること、②金属製品製造業を基幹事業としていること、③売上金額が原告法人の半額以上倍額以下であること、④死亡を理由とした代表取締役に対する役員退職給与の支払いがあること、⑤訴訟等が係属していないこと)を合理的であると認めたうえで、その類似法人5法人の平均功績倍率を「3.26」と認定した(同業類似法人の内容は表2参照)。
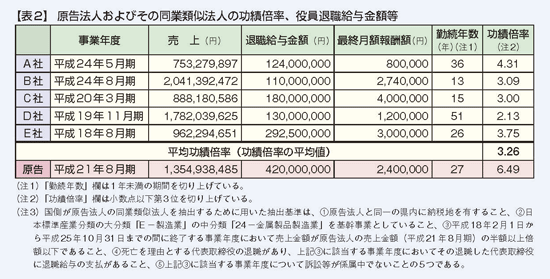
平均功績倍率から相当程度乖離を許容すべき 次に地裁は、平均功績倍率「3.26」を原告法人に適用し、これに基づき算定された金額をもって死亡退職した代表取締役に対する役員退職給与として相当な金額と認めることができるか否かを検討。ここで地裁は、本来役員退職給与が退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、①平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額であると解することはあまりにも硬直的な考え方であること、②平均功績倍率法を採用すると、原告法人の同業類似法人のなかにその平均値(平均功績倍率)を超える事例(同業類似法人)があることになる点が不合理であること、③納税者側の一般的な認識可能性を考慮すると、事後的な課税庁側の調査による同業類似法人の平均功績倍率から相当程度の乖離を許容すべきであることを指摘。この点を踏まえ地裁は、役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数(1.5倍)を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は適正な役員退職給与の額であるという判断基準を示した。
そして本件について地裁は、死亡退職した代表取締役は原告法人の取締役及び代表者として借金の完済(平成9年頃にあった8億円以上の借金を平成20年頃までに完済)や売上金額の増加(昭和56年の約7億円から平成15年頃には約15億円に増加)、経営者の世代交代の橋渡し(昭和56年に取締役に就任した後、平成15年には三男が代表取締役社長に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任したこと)などに相応の功績を有していたことがうかがわれることからすると、功績倍率を「4.89(平均功績倍率3.26×1.5)」として算定される役員退職給与の額について特段の事情があるとは認められないと認定した。
そのうえで地裁は、役員退職給与4億2,000万円のうち約3億1,687万円(最終報酬月額240万円×在籍期間27年×功績倍率4.89)までの部分は役員退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではないことから、この金額を超える約1億313万円は不相当に高額な部分の金額に当たるとしたうえで(なお、税務署が認定した過大役員退職給与は約2億300万円である)、法人税更正処分等のうち納付すべき法人税約3,100万円を取り消した(表3参照)。
平均功績倍率の“1.5倍”まで損金算入可も、国側は控訴を提起
役員退職金の過大判定で東京地裁が注目判決
原告法人が死亡退職した代表取締役に支給した役員退職給与のなかに損金不算入となる「不相当に高額」な部分の金額があるか否かが争われた税務訴訟で東京地裁は平成29年10月13日、法人税更正処分等の一部を取り消す判決を下した。今回の判決で注目されるのは、役員退職給与の過大判定をめぐり、東京地裁が「特段の事情がない限り、同業類似法人の平均功績倍率の“1.5倍”を用いて役員退職給与の相当額を算定すべき」という判断基準を示した点である。東京地裁が示した判断基準が確定すれば、類似事案に影響を及ぼす可能性もあるなか、国側は国側(控訴人)敗訴部分については全て不服であるとして控訴を提起している。注目される東京高裁(控訴審)判決は、年内(早ければ夏頃)にも下される見込みだ。
納税者側は最高功績倍率を、国側は平均功績倍率を採用すべきと主張
損金算入の対象となる役員退職給与であっても、その役員退職給与の額に「不相当に高額」(法法34②、法令70二)な部分の金額があれば、その不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされている(下囲み参照)。今回紹介する税務訴訟で問題となったのは、原告法人が死亡退職した代表取締役に対して支給した役員退職給与の額に不相当に高額な部分の金額として損金に算入されない金額があるか否かという点である。
| 法人税法34条2項(役員給与の損金不算入) |
| 内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 |
| 法人税法施行令第70条二号(過大な役員給与の額) |
| 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(……略……)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額 |
事実関係をみると、建材金物の製造販売等を目的とする原告法人(同族会社)は、平成20年10月に死亡退職した代表取締役に対して、功績倍率法に基づく役員退職給与4億2,000万円を次の算式により計算したうえで平成21年8月期中に支給していた。この支給額は、原告法人の役員退職慰労金規定および臨時株主総会の決議に基づくものである。
| 「最終月額給料240万円」×「勤続年数27年」×「役員倍数5倍×功労加算1.3倍」(功績倍率「6.5」) |
国側、3方法のうち平均功績倍率法が合理的 納税者の訴えに対し被告である国側は、役員退職給与相当額の算定方法として、「平均功績倍率法」、「1年当たり平均額法」、「最高功績倍率法」の3つ(表1参照)を挙げたうえで、このうち「平均功績倍率法」が法令(法法34②、法令70二)の趣旨に最も合致する合理的な算定方法であると指摘。本件における役員退職給与相当額の算定に当たっても平均功績倍率法を用いることが相当であるとしたうえで、平均功績倍率「3.26」により算定した役員退職給与約2億1,124万円を超える約2億875万円は不相当に高額な金額(法法34②)として損金に算入されないと主張した。これに対し納税者側は、最高功績倍率法等の納税者により有利な算定方法を採用すべきであると反論していた。
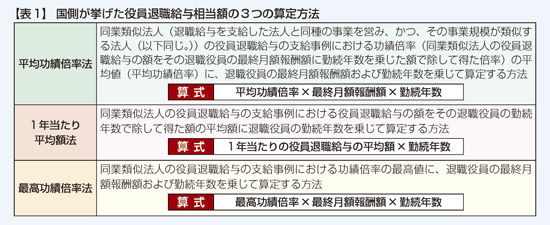
地裁、特段の事情がない限り平均功績倍率の“1.5倍”で適正額を算定すべき
東京地裁は、納税者が主張した最高功績倍率法について、①功績倍率の最高値は最高値に係る法人の特殊性等に影響されるもので指標として客観性が劣ること、②合理的な抽出基準により同業類似法人が5法人という相当数の法人が抽出されているうえ、これらの法人の功績倍率に極端なバラつきがなく、その僅差も平均の30%程度の範囲内に収まっていることを指摘し、最高功績倍率法がより適切であるとみるべき事情は見当たらないとした。一方で、国側が主張した平均功績倍率法について地裁は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われ、かつ、その平均功績倍率を適用することが相当と認められる限り、法令(法法34②、法令70二)の趣旨に合致する合理的な方法であると判断した。
そして地裁は、国側が原告法人の同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準が合理的であると認められるか否かを検討。ここで地裁は、国側が用いた5つの抽出基準(①同一県内に納税地を有すること、②金属製品製造業を基幹事業としていること、③売上金額が原告法人の半額以上倍額以下であること、④死亡を理由とした代表取締役に対する役員退職給与の支払いがあること、⑤訴訟等が係属していないこと)を合理的であると認めたうえで、その類似法人5法人の平均功績倍率を「3.26」と認定した(同業類似法人の内容は表2参照)。
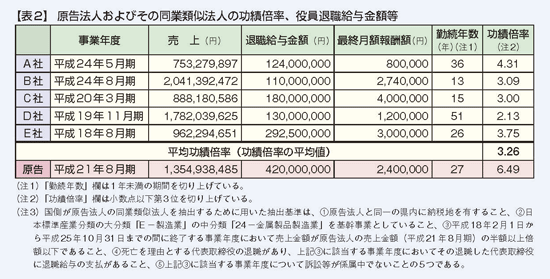
平均功績倍率から相当程度乖離を許容すべき 次に地裁は、平均功績倍率「3.26」を原告法人に適用し、これに基づき算定された金額をもって死亡退職した代表取締役に対する役員退職給与として相当な金額と認めることができるか否かを検討。ここで地裁は、本来役員退職給与が退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、①平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額であると解することはあまりにも硬直的な考え方であること、②平均功績倍率法を採用すると、原告法人の同業類似法人のなかにその平均値(平均功績倍率)を超える事例(同業類似法人)があることになる点が不合理であること、③納税者側の一般的な認識可能性を考慮すると、事後的な課税庁側の調査による同業類似法人の平均功績倍率から相当程度の乖離を許容すべきであることを指摘。この点を踏まえ地裁は、役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数(1.5倍)を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は適正な役員退職給与の額であるという判断基準を示した。
そして本件について地裁は、死亡退職した代表取締役は原告法人の取締役及び代表者として借金の完済(平成9年頃にあった8億円以上の借金を平成20年頃までに完済)や売上金額の増加(昭和56年の約7億円から平成15年頃には約15億円に増加)、経営者の世代交代の橋渡し(昭和56年に取締役に就任した後、平成15年には三男が代表取締役社長に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任したこと)などに相応の功績を有していたことがうかがわれることからすると、功績倍率を「4.89(平均功績倍率3.26×1.5)」として算定される役員退職給与の額について特段の事情があるとは認められないと認定した。
そのうえで地裁は、役員退職給与4億2,000万円のうち約3億1,687万円(最終報酬月額240万円×在籍期間27年×功績倍率4.89)までの部分は役員退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではないことから、この金額を超える約1億313万円は不相当に高額な部分の金額に当たるとしたうえで(なお、税務署が認定した過大役員退職給与は約2億300万円である)、法人税更正処分等のうち納付すべき法人税約3,100万円を取り消した(表3参照)。
| 【表3】東京地裁が認定した本件代表取締役に対する役員退職給与相当額及び法人税額 |
| 最終月額報酬 | 勤続年数 | 功績倍率 | 退職給与金額 | 納付すべき法人税額 |
| 2,400,000円 | 27年 | 4.89 | 316,872,000円 | 48,206,600円 |
【参考】国側が主張した本件代表取締役に対する役員退職給与相当額及び法人税額 |
| 最終月額報酬 | 勤続年数 | 功績倍率 | 退職給与金額 | 納付すべき法人税額 |
| 2,400,000円 | 27年 | 3.26 | 211,248,000円 | 79,893,800円 |
| 敗訴した国側、「1.5倍」は根拠のない数値と言わざるを得ないと控訴審で主張 |
| 今回紹介した東京地裁判決を不服として控訴した国側は、控訴理由書(平成29年12月15日付)を東京高裁に提出している。そのなかで国側は、「1.5倍」という数値は当事者が原審で一切主張しておらず、算定根拠やそれを用いる合理的な理由を何ら示していないので、根拠のない数値と言わざるを得ないと主張している。また、控訴理由書のなかで国側は、東京地裁が「法法34条2項及び法令70条各号の規定は、課税庁が課税処分を行う際の準則であるのみならず、法人税の納税者が法人税の申告をする際に従うべき準則でもある」と判示している点を踏まえると、1.5倍という値が一人歩きするおそれも否定できないと指摘。国側は、今後納税者が公刊物等を通じて把握した同業類似法人の平均功績倍率に1.5倍を乗じて役員退職給与を支給することになりかねず、1.5倍を乗じた事例が蓄積していくことになると、従前の平均功績倍率に1.5倍を乗じた値が後続の同業類似法人に定着し、その結果としてその数値のさらに1.5倍(当初の2.25倍)に基づき納税者が役員退職給与の額を算定することにもなりかねないと指摘している。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















