解説記事2018年03月05日 【特別解説】 IFRS第9号「金融商品」を早期適用しているIFRS任意適用日本企業の開示(減損)(2018年3月5日号・№729)
特別解説
IFRS第9号「金融商品」を早期適用しているIFRS任意適用日本企業の開示(減損)
はじめに
2018年1月1日以後開始する事業年度から、IFRS第9号「金融商品」が強制適用される。これにより、これまで長年にわたって金融商品の認識及び測定を規定してきたIAS第39号が廃止され、IFRS第9号に全面的に置き換えられることになる。今後は、主に金融機関を中心に、金融商品の分類や貸付金の減損、ヘッジ会計など幅広い分野の会計処理方法が変わり、様々な情報の開示が新たに求められることになるが、本稿では、IFRS第9号を既に早期適用しているIFRS任意適用日本企業(IFRSにより連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を公表している企業)が行った、金融商品の信用リスクや減損処理の開示を取り上げてみたい。
金融商品の信用リスクや減損に関する開示規定
信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額(すべてのキャッシュ・フロー不足)を当初の実効金利で割り引いたものであり、予想信用損失とは、信用損失をそれぞれの債務不履行発生リスクでウェイト付けした加重平均をいう(IFRS第9号付録A)。
企業は毎期末、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失(金融商品の予想存続期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失)に等しい金額で測定しなければならず、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12ヶ月の予想信用損失(全期間の予想信用損失のうち、ある金融商品について報告日後12ヶ月以内で生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失を表す部分)に等しい金額で測定しなければならないとされている(IFRS第9号 5.5.3項及び5.5.5項。一般的なアプローチ)。しかしながら、営業債権、契約資産及びリース債権については、常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない(単純化したアプローチ)。
金融商品の減損処理(売掛金や貸付金等に対する貸倒引当金の計上方法等)についてはIFRS第9号が規定しているが、開示についてはIFRS第7号「金融商品:開示」の第35A項から第35N項において、主として下記の項目を開示することが求められている。
・予想信用損失の測定に用いた方法、仮定及び情報
・予想信用損失の金額の変動及び当該変動の理由
・重大な信用リスクの集中に関する情報
・金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したのかどうかをどのように判定したのか
・債務不履行の定義(その定義を選択した理由を含む)
・予想信用損失を集合的ベースで測定した場合には、金融商品のグループ分けの方法
・信用減損の判定の方法や直接償却の方針
・著しい信用リスクの増加や信用が毀損している証拠を判定するために用いた方法
・将来予測的な情報を予想信用損失の算定に織り込んだ方法
・期中に行った見積り技法又は重要な仮定の変更及び当該変更の理由
・損失評価引当金の期首残高から期末残高への調整表
・損失評価引当金の変動に寄与した金融商品の総額での帳簿価額の変動
・契約上のキャッシュ・フローの条件変更の内容及び影響と、そうした条件変更が予想信用損失の測定に与える影響
・担保及びその他の信用補完に関する情報
・信用リスク格付けごとの金融資産の総額での帳簿価額
豊田自動織機による開示(2017年3月期)
豊田自動織機は、信用リスクの管理方法について定性的な開示を行った後、単純化したアプローチを適用している売上債権及びその他の債権と一般的なアプローチを適用している金融資産(主に販売金融に係る貸付金)とに分けて、定量的な開示を行っている。
「ⅰ)信用リスク
当社グループの主な債権である売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金には、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)があります。当社グループは、トレジャリーポリシーなどの社内規程に基づき、主要な取引先の状況を格付けや決算書に基づいて定期的にモニタリングするとともに、期日管理および残高管理を行うことで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。なお、リース投資資産は、リース対象資産の所有権は移転せず、また期日管理および残高管理を行っているため、回収リスクは僅少です。なお、取引先について重大な信用リスクの集中はありません。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンター・パーティ・リスクを軽減するため、主に格付機関が信用力が高いと判定している金融機関とのみ取引を行っております。
なお、売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金について、これら債権の全部または一部について回収ができず、または回収が極めて困難であると判断された場合には債務不履行とみなしております。金融資産の帳簿価額の合計額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。
・売上債権およびリース投資資産に係る予想信用損失の測定
売上債権には重大な金融要素が含まれていないため、売上債権の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。リース投資資産については、リース投資資産の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する売上債権およびリース投資資産については、過去の貸倒実績等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しています。
・販売金融に係る貸付金に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、販売金融に係る貸付金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、過去の貸倒実績率等をもとに将来12ヵ月の予想信用損失を集合的に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在および将来の経済状況の予測を反映させる方針です。一方、期末日時点で期日経過や財務状況の悪化等により信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額などをもとに、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を個別に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。また、債務不履行とみなされた場合は、信用減損金融資産としております。
報告期間の末日現在で期日が経過している、単純化したアプローチを適用している売上債権及びその他の債権の予想信用損失は、次のとおりであります(編注:表1参照)。

一般的なアプローチを適用している金融資産は、主に販売金融に係る貸付金です。販売金融に係る貸付金の信用リスクごとの金額は、以下の通りです(編注:表2参照)。」

味の素による開示(2017年3月期)
味の素は、IFRS第9号の規定を踏まえて、いわゆる予想損失モデルについて詳細に説明をした後、一般的なアプローチが適用される金融資産と単純化されたアプローチが適用される金融資産とに分けて、損失評価引当金及び対象となる金融資産に関する定量的情報と定性的情報を開示している。また、「信用リスクの著しい増大」や「債務不履行」に関する具体的な判断基準が示されている点も特徴的である。
「(4)損失評価引当金
① 信用リスク管理実務
当社グループは、償却原価で測定する金融資産の予想信用損失及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融商品)の予想信用損失に対して損失評価引当金を計上しております。
損失評価引当金の認識・測定に当たっては、金融資産に関する信用リスクの著しい増大の有無及び信用減損の有無によって金融資産をステージに分類しております。
ステージ1:信用リスクの著しい増大が見受けられない。
ステージ2:信用リスクの著しい増大が見受けられるが、信用減損は見受けられない。
ステージ3:信用リスクの著しい増大、信用減損がともに顕在化している。
なお、信用リスクの著しい増大とは、当初認識時と比較して、期末日に債務不履行発生のリスクが著しく増大していることをいいます。当社グループにおいては、利息又は元本の支払いについて、原則として30日超の延滞の事実に、債務者の属する業界の景気動向等を加味し、債務者の弁済能力が将来において変化する可能性を踏まえて、信用リスクの著しい増大の有無を判断しております。
また、当社グループにおいては、発行者又は債務者の重大な財政的困難、利息又は元本の支払いについて原則として90日超の延滞などが生じた場合に債務不履行が生じていると判断しております。
債務不履行に該当した場合は信用減損の客観的な証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分類しております。
上記のステージに関わらず、法的に債権が消滅する場合など、金融資産の全部又は一部について回収できないと合理的に判断される場合は、当該金融資産の帳簿価額を直接償却しております。
損失評価引当金の見積りに当たっては、一部の金融資産の予想信用損失を集合的ベースで測定しており、グループ会社ごとに独自にグループ又はサブグループを設定しております。
予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値です。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、当該金融資産に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、著しく増大していない場合は、12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております(一般的なアプローチ)。
なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権は、損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております(単純化されたアプローチ)。
12か月及び全期間の予想信用損失の測定に当たっては、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、期末日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を用いております。なお、予想信用損失を集合的ベースで測定する際、過去における債務不履行の実績率を用いることがあります。
② 損失評価引当金及び対象となる金融資産に関する定量的及び定性的情報
一般的なアプローチが適用される金融資産 償却原価で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の主な期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表3参照。なお、移行日(2015年4月1日)現在の注記は省略した)。
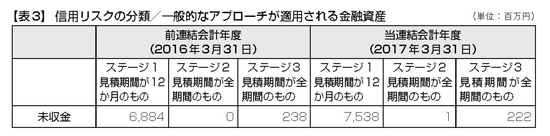 表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しており、連結財政状態計算書上、売上債権及びその他の債権に含まれております。
表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しており、連結財政状態計算書上、売上債権及びその他の債権に含まれております。
上記に対応する損失評価引当金のクラス別増減は以下のとおりです(編注:表4参照)。
 単純化されたアプローチが適用される金融資産
償却原価で測定する金融資産の期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表5参照)。
単純化されたアプローチが適用される金融資産
償却原価で測定する金融資産の期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表5参照)。
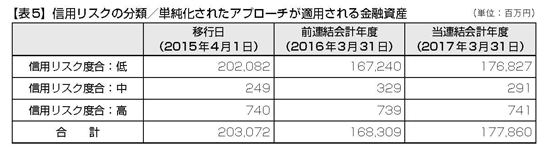
表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しております。信用リスク度合(低、中、高)は、ステージの分類(ステージ1、2、3)を参考に判断しております。
上記に対応する損失評価引当金の増減は以下のとおりです(編注:表6参照)。」
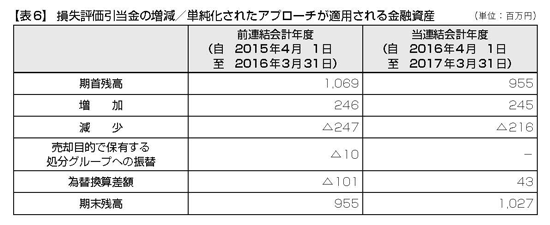
兼松による開示(2017年3月期)
兼松は、営業債権、その他の債権(貸付金)及びその他の投資(負債性金融商品である有価証券)に分けて、予想信用損失の測定方法を次のように開示している。
「② 企業の有するリスクへの対応状況について(リスク管理の目的、方針及び手続並びにリスクを測定するために用いている方法)
(i)営業債権に係る予想信用損失の測定
営業債権には重大な金融要素が含まれていないため、営業債権の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。非延滞債権については、多数の取引先より構成されているため一括してグルーピングしたうえで、過去の貸倒実績等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しています。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。
なお、支払遅延及び支払延期要請があった場合でも、その原因が一時的な資金需要によるものであり、債務不履行のリスクが低く、近い将来に契約上のキャッシュ・フローの義務を履行するための強い能力を有しているものと判断された場合には延滞債権として取り扱っておりません。
(ii)その他の債権に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、貸付金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、過去の貸倒実績率等をもとに将来12ヶ月の予想信用損失を集合的に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。
一方、期末日時点で、信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額などをもとに、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を個別に見積って当該金融商品に係る損失引当金の額を算定しております。
(ⅲ)その他の投資(負債性金融商品である有価証券)に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、負債性金融商品である有価証券に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、将来12ヶ月の予想信用損失を見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。一方、期末日時点で、信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。これらの予想信用損失の見積りに際しては、大手格付機関が公表しているデフォルト率を考慮して算定しております。
信用減損した金融資産について、信用調査の結果、その全部又は一部が回収不能であることが判明し、直接償却することが適切と判断された場合には、直接償却を行っております。」
おわりに
2018年1月1日以後開始する事業年度は、本稿で取り上げたIFRS第9号に加え、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用初年度でもあり、IFRSを適用する企業にとっては大きな節目の年になることが予想される。我が国の会計基準も、収益認識に関する会計基準の最終基準化が近づいており、金融商品会計基準も、IFRS第9号の規定を踏まえて今後見直しが始まる可能性もある。これまでわが国では、金融機関はともかく、事業会社では、重要な会計方針や引当金明細表を除いては、引当金や貸倒損失に関する詳細な開示はほとんど行われてこなかったため、我が国でIFRS第9号を踏まえた会計基準が策定された場合には、IFRS任意適用企業や金融機関のみならず、事業会社の金融商品や貸倒引当金に関する開示も一変する可能性があるであろう。
IFRS第9号「金融商品」を早期適用しているIFRS任意適用日本企業の開示(減損)
はじめに
2018年1月1日以後開始する事業年度から、IFRS第9号「金融商品」が強制適用される。これにより、これまで長年にわたって金融商品の認識及び測定を規定してきたIAS第39号が廃止され、IFRS第9号に全面的に置き換えられることになる。今後は、主に金融機関を中心に、金融商品の分類や貸付金の減損、ヘッジ会計など幅広い分野の会計処理方法が変わり、様々な情報の開示が新たに求められることになるが、本稿では、IFRS第9号を既に早期適用しているIFRS任意適用日本企業(IFRSにより連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を公表している企業)が行った、金融商品の信用リスクや減損処理の開示を取り上げてみたい。
金融商品の信用リスクや減損に関する開示規定
信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額(すべてのキャッシュ・フロー不足)を当初の実効金利で割り引いたものであり、予想信用損失とは、信用損失をそれぞれの債務不履行発生リスクでウェイト付けした加重平均をいう(IFRS第9号付録A)。
企業は毎期末、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失(金融商品の予想存続期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失)に等しい金額で測定しなければならず、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12ヶ月の予想信用損失(全期間の予想信用損失のうち、ある金融商品について報告日後12ヶ月以内で生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失を表す部分)に等しい金額で測定しなければならないとされている(IFRS第9号 5.5.3項及び5.5.5項。一般的なアプローチ)。しかしながら、営業債権、契約資産及びリース債権については、常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない(単純化したアプローチ)。
金融商品の減損処理(売掛金や貸付金等に対する貸倒引当金の計上方法等)についてはIFRS第9号が規定しているが、開示についてはIFRS第7号「金融商品:開示」の第35A項から第35N項において、主として下記の項目を開示することが求められている。
・予想信用損失の測定に用いた方法、仮定及び情報
・予想信用損失の金額の変動及び当該変動の理由
・重大な信用リスクの集中に関する情報
・金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したのかどうかをどのように判定したのか
・債務不履行の定義(その定義を選択した理由を含む)
・予想信用損失を集合的ベースで測定した場合には、金融商品のグループ分けの方法
・信用減損の判定の方法や直接償却の方針
・著しい信用リスクの増加や信用が毀損している証拠を判定するために用いた方法
・将来予測的な情報を予想信用損失の算定に織り込んだ方法
・期中に行った見積り技法又は重要な仮定の変更及び当該変更の理由
・損失評価引当金の期首残高から期末残高への調整表
・損失評価引当金の変動に寄与した金融商品の総額での帳簿価額の変動
・契約上のキャッシュ・フローの条件変更の内容及び影響と、そうした条件変更が予想信用損失の測定に与える影響
・担保及びその他の信用補完に関する情報
・信用リスク格付けごとの金融資産の総額での帳簿価額
豊田自動織機による開示(2017年3月期)
豊田自動織機は、信用リスクの管理方法について定性的な開示を行った後、単純化したアプローチを適用している売上債権及びその他の債権と一般的なアプローチを適用している金融資産(主に販売金融に係る貸付金)とに分けて、定量的な開示を行っている。
「ⅰ)信用リスク
当社グループの主な債権である売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金には、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)があります。当社グループは、トレジャリーポリシーなどの社内規程に基づき、主要な取引先の状況を格付けや決算書に基づいて定期的にモニタリングするとともに、期日管理および残高管理を行うことで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。なお、リース投資資産は、リース対象資産の所有権は移転せず、また期日管理および残高管理を行っているため、回収リスクは僅少です。なお、取引先について重大な信用リスクの集中はありません。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンター・パーティ・リスクを軽減するため、主に格付機関が信用力が高いと判定している金融機関とのみ取引を行っております。
なお、売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金について、これら債権の全部または一部について回収ができず、または回収が極めて困難であると判断された場合には債務不履行とみなしております。金融資産の帳簿価額の合計額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。
・売上債権およびリース投資資産に係る予想信用損失の測定
売上債権には重大な金融要素が含まれていないため、売上債権の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。リース投資資産については、リース投資資産の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する売上債権およびリース投資資産については、過去の貸倒実績等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しています。
・販売金融に係る貸付金に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、販売金融に係る貸付金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、過去の貸倒実績率等をもとに将来12ヵ月の予想信用損失を集合的に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在および将来の経済状況の予測を反映させる方針です。一方、期末日時点で期日経過や財務状況の悪化等により信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額などをもとに、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を個別に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。また、債務不履行とみなされた場合は、信用減損金融資産としております。
報告期間の末日現在で期日が経過している、単純化したアプローチを適用している売上債権及びその他の債権の予想信用損失は、次のとおりであります(編注:表1参照)。

一般的なアプローチを適用している金融資産は、主に販売金融に係る貸付金です。販売金融に係る貸付金の信用リスクごとの金額は、以下の通りです(編注:表2参照)。」

味の素による開示(2017年3月期)
味の素は、IFRS第9号の規定を踏まえて、いわゆる予想損失モデルについて詳細に説明をした後、一般的なアプローチが適用される金融資産と単純化されたアプローチが適用される金融資産とに分けて、損失評価引当金及び対象となる金融資産に関する定量的情報と定性的情報を開示している。また、「信用リスクの著しい増大」や「債務不履行」に関する具体的な判断基準が示されている点も特徴的である。
「(4)損失評価引当金
① 信用リスク管理実務
当社グループは、償却原価で測定する金融資産の予想信用損失及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融商品)の予想信用損失に対して損失評価引当金を計上しております。
損失評価引当金の認識・測定に当たっては、金融資産に関する信用リスクの著しい増大の有無及び信用減損の有無によって金融資産をステージに分類しております。
ステージ1:信用リスクの著しい増大が見受けられない。
ステージ2:信用リスクの著しい増大が見受けられるが、信用減損は見受けられない。
ステージ3:信用リスクの著しい増大、信用減損がともに顕在化している。
なお、信用リスクの著しい増大とは、当初認識時と比較して、期末日に債務不履行発生のリスクが著しく増大していることをいいます。当社グループにおいては、利息又は元本の支払いについて、原則として30日超の延滞の事実に、債務者の属する業界の景気動向等を加味し、債務者の弁済能力が将来において変化する可能性を踏まえて、信用リスクの著しい増大の有無を判断しております。
また、当社グループにおいては、発行者又は債務者の重大な財政的困難、利息又は元本の支払いについて原則として90日超の延滞などが生じた場合に債務不履行が生じていると判断しております。
債務不履行に該当した場合は信用減損の客観的な証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分類しております。
上記のステージに関わらず、法的に債権が消滅する場合など、金融資産の全部又は一部について回収できないと合理的に判断される場合は、当該金融資産の帳簿価額を直接償却しております。
損失評価引当金の見積りに当たっては、一部の金融資産の予想信用損失を集合的ベースで測定しており、グループ会社ごとに独自にグループ又はサブグループを設定しております。
予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値です。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、当該金融資産に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、著しく増大していない場合は、12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております(一般的なアプローチ)。
なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権は、損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております(単純化されたアプローチ)。
12か月及び全期間の予想信用損失の測定に当たっては、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、期末日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を用いております。なお、予想信用損失を集合的ベースで測定する際、過去における債務不履行の実績率を用いることがあります。
② 損失評価引当金及び対象となる金融資産に関する定量的及び定性的情報
一般的なアプローチが適用される金融資産 償却原価で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の主な期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表3参照。なお、移行日(2015年4月1日)現在の注記は省略した)。
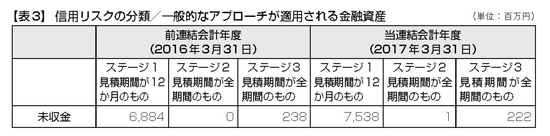 表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しており、連結財政状態計算書上、売上債権及びその他の債権に含まれております。
表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しており、連結財政状態計算書上、売上債権及びその他の債権に含まれております。上記に対応する損失評価引当金のクラス別増減は以下のとおりです(編注:表4参照)。
 単純化されたアプローチが適用される金融資産
償却原価で測定する金融資産の期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表5参照)。
単純化されたアプローチが適用される金融資産
償却原価で測定する金融資産の期末残高について、当社グループの内部規程に基づいた信用リスクの分類は以下のとおりです(編注:表5参照)。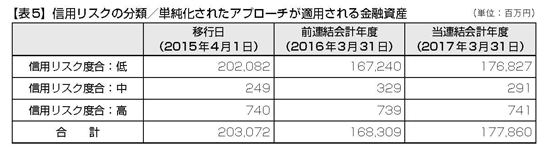
表中の金額は信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しております。信用リスク度合(低、中、高)は、ステージの分類(ステージ1、2、3)を参考に判断しております。
上記に対応する損失評価引当金の増減は以下のとおりです(編注:表6参照)。」
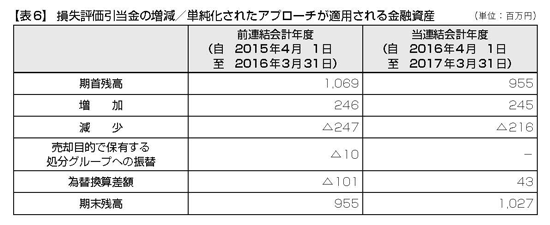
兼松による開示(2017年3月期)
兼松は、営業債権、その他の債権(貸付金)及びその他の投資(負債性金融商品である有価証券)に分けて、予想信用損失の測定方法を次のように開示している。
「② 企業の有するリスクへの対応状況について(リスク管理の目的、方針及び手続並びにリスクを測定するために用いている方法)
(i)営業債権に係る予想信用損失の測定
営業債権には重大な金融要素が含まれていないため、営業債権の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。非延滞債権については、多数の取引先より構成されているため一括してグルーピングしたうえで、過去の貸倒実績等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しています。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。
なお、支払遅延及び支払延期要請があった場合でも、その原因が一時的な資金需要によるものであり、債務不履行のリスクが低く、近い将来に契約上のキャッシュ・フローの義務を履行するための強い能力を有しているものと判断された場合には延滞債権として取り扱っておりません。
(ii)その他の債権に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、貸付金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、過去の貸倒実績率等をもとに将来12ヶ月の予想信用損失を集合的に見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。
一方、期末日時点で、信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額などをもとに、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を個別に見積って当該金融商品に係る損失引当金の額を算定しております。
(ⅲ)その他の投資(負債性金融商品である有価証券)に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、負債性金融商品である有価証券に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、将来12ヶ月の予想信用損失を見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。一方、期末日時点で、信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を見積って当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。これらの予想信用損失の見積りに際しては、大手格付機関が公表しているデフォルト率を考慮して算定しております。
信用減損した金融資産について、信用調査の結果、その全部又は一部が回収不能であることが判明し、直接償却することが適切と判断された場合には、直接償却を行っております。」
おわりに
2018年1月1日以後開始する事業年度は、本稿で取り上げたIFRS第9号に加え、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用初年度でもあり、IFRSを適用する企業にとっては大きな節目の年になることが予想される。我が国の会計基準も、収益認識に関する会計基準の最終基準化が近づいており、金融商品会計基準も、IFRS第9号の規定を踏まえて今後見直しが始まる可能性もある。これまでわが国では、金融機関はともかく、事業会社では、重要な会計方針や引当金明細表を除いては、引当金や貸倒損失に関する詳細な開示はほとんど行われてこなかったため、我が国でIFRS第9号を踏まえた会計基準が策定された場合には、IFRS任意適用企業や金融機関のみならず、事業会社の金融商品や貸倒引当金に関する開示も一変する可能性があるであろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















