解説記事2018年03月12日 【ニュース特集】 所得税・消費税の審理事例Q&A(2018年3月12日号・№730)
ニュース特集
所得控除、申告・加算税etc.
所得税・消費税の審理事例Q&A
税務当局の所得税・消費税に係る審理事例が明らかになった。医療費控除の事例では、産後ケアセンターへの入所費用は医療費控除の対象とならないとしている。また、申告・加算税関係では、出国後に納税管理人の届出を行い、確定申告書を出国後に提出したときには無申告加算税が賦課されること、消費税関係では、土地建物を一括譲渡した場合、譲渡対価の総額から土地の対価の額を控除した残額を建物の譲渡対価の額とする区分方法は、合理的とは認められないことなどが示されている。
Ⅰ 課税・非課税等
生命保険会社の誤りによって増加した税負担等を補填するために、生保年金受給者に支払われる補填金の課税関係
Q1 適格退職年金は、所得税法上の公的年金等として取り扱われる年金であったが、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度は廃止され、適格退職年金として支払われていた年金を引き続き公的年金等と取り扱うためには、同日までに他の一定の年金制度へ移行する必要があった。
しかしながら、X生命保険株式会社(以下「X生命」という)は、一部の適格退職年金(以下「移行事務疎漏年金」という)について、当該移行手続を失念していたことから、平成24年4月以降、X生命から支払われていた移行事務疎漏年金については、公的年金等には該当せず、いわゆる個人年金に該当するものであったことが判明した。
その結果、X生命が移行事務疎漏年金について、公的年金等として行っていた源泉徴収は誤っていたこととなり、当該年金の受給者(以下「年金受給者」という)の税負担等が増加することとなることから、X生命は、年金受給者に対して税負担等の増加分を補填金として支払うこととした。
この場合に、年金受給者がX生命から支払を受ける補填金の課税関係はどうなるか。
A
年金受給者がX生命から支払を受ける補填金は非課税となる。 損害保険契約に基づく保険金および損害保険契約に準ずる共済契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金は、非課税とされている(所法9①十七、所令30二)。
設問の補填金は、X生命が旧適格退職年金の移行事務を怠ったことによって、年金受給者が被ることとなった損害を賠償するために、X生命が年金受給者に対して支払うものであり、不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金に該当する。
したがって、年金受給者がX生命から支払を受ける補填金は非課税となる。
国際連合大学から支払われる給与に係る課税関係
Q2 居住者Xは、国際連合大学から給与を得ている。
当該給与の支払明細には、支払日および支払金額(円)などが表記されている。
国際連合大学は、当該給与の支払の際に所得税の源泉徴収を行っていないところ、当該給与の課税関係はどうなるか。
A
Xが、「国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定」(以下「協定」という)第12条《大学本部の職員》に定める国際連合の職員である大学本部の職員に該当する場合には、当該給与に対する課税は免除される。 協定第12条第16項1は、国際連合の職員である大学本部の職員が享有する特権および免除について規定している。
そして、同項1(b)では「大学が支払った給料及び手当に対する課税の免除」として、課税の免除に係る規定が置かれている。
したがって、Xが協定第12条の適用を受けることができる国際連合の職員である大学本部の職員に該当する場合には、国際連合大学から支払を受けた給与に対する課税は免除されることとなる。
なお、協定第12条第18項3において、「政府は、この条の規定の範囲内に属する者にその写真を添付した身分証明書を交付する。この証明書は、すべての日本国の当局との関係において身分を証明するために使用される。」と規定されており、協定第12条の適用がある者に該当するか否かは、当該証明書によって確認することができる。
Ⅱ 所得区分等
司法修習生に対する経済的支援(修習給付金)の課税関係
Q3 平成29年度以降に採用される予定の司法修習生に対する経済的支援として、以下の給付制度が新設され、最高裁判所から司法修習生に対する修習給付金が給付される予定であるが、当該修習給付金の課税関係はどうなるか。
(修習給付金の概要)
① 基本給付 司法修習生に一律月額13.5万円
② 住居給付 月額3.5万円(修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象)
③ 移転給付 旅費法の移転料基準に準拠して支払
A
①から③の全てが雑所得となる。
①および②は必要経費として計上できるものがなく、また、③は実費相当額が支払われていることから課税関係が生じない。 修習給付金の支払元である最高裁判所と司法修習生とは雇用関係等になく、修習給付金は司法修習生に対する給与として支払われるものではないため、上記①から③のいずれも給与所得(所法28)には該当しない。
そして、これらの修習給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、①から③の全てが雑所得(所法35)に区分される。
なお、上記①基本給付および②住居給付は、生活維持のために支払われるものとされているため、必要経費として計上できるものはない。
③移転給付については、研修のための移転費用に充てられるものであり、その実費相当額が支払われることとされているものであるから、結果として、課税の対象とはならない。
Ⅲ 所得控除
産後ケアセンターへの入所費用の医療費控除該当性
Q4 X産後ケアセンターは、出産後の産じょく期において、身体回復のため、母子が入所することができる施設である。
当該施設は、医療法に基づかない施設として設置され、当該施設では専門職により、母乳授乳ケア、育児指導、ボディケアおよび美容等を行い、心身のケアを行っているが、医療行為に該当する行為は行われていない。
なお、当該施設の利用料金は、宿泊する部屋の広さ等によって設定金額に差異がある。
当該入所費用は、医療費控除の対象となるか。
A
X産後ケアセンターへの入所費用は、医療費控除の対象とならない。 産後ケアセンターとは、一般的には、出産後の育児支援を目的として、母子が一緒に過ごすことができる医療機関が運営する宿泊施設である。
産後ケアには、①十分なケアによる産後の回復のため、家事や育児の援助、休養・栄養管理など産後の回復に必要な日常生活のケアを受けるもの、②精神的に不安になりがちな女性の心身のケア、子育ての指導を支える産後ケアを提供するもの、③初めての育児に戸惑うことから、分からない事や不安があってもすぐに質問でき、疑問を解消すれば、スムーズに育児をスタートできることを目的とするもの等がある。
ところで、医療費控除の対象となる医療費とは、所得税法第73条《医療費控除》において、医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価として通常認められるものをいい、①医師または助産師等の施術者による診療、施術または分べんの介助の費用に相当するもの、②医師等による診療等を受けるための入院若しくは入所等の対価として支払う部屋代、食事代等の費用で通常必要なもの等が含まれるとされている。
しかしながら、本件のX産後ケアセンターに係る入所費用は、上記のことからすれば、医師等による診療等を受けるための入所等の対価として支払う部屋代、食事代等の費用に当たらない。
したがって、当該入所費用は医療費控除の対象とならない。
市区町村長等が交付した「障害者控除対象者認定書」に遡及して認定する旨の記載があった場合の障害者控除の適用等について
Q5 介護保険法により「要介護認定」を受けていたXが、Z市に対し「障害者控除対象者認定書」の交付を要求した。これを受け、Z市長は、認定日を7年前とする「障害者控除対象者認定書」をXに交付した。
このとき、Xは7年前から遡及して障害者控除の適用を受けることができるか。
A
Xがこれまで確定申告において障害者控除の適用をしていなかった場合、過去5年間は更正の請求の有無にかかわらず減額更正をすることができるが、6年前以前について更正の請求をすることはできない。 所得税法上、障害者控除の適用を受けるためには、納税者本人またはその控除対象配偶者および扶養親族のうちに、障害者がいることが要件とされている(所法79)。
ここでいう障害者とは、「障害者手帳」等の交付を受けている者のほか、所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第2項第6号に定める「市町村長等の認定を受けている者」も含まれるため、市区町村長等より障害者として認定され、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている者は、所得税法に規定する障害者として取り扱われることとなる。
そして、設例のXのように、7年前に遡って障害者控除対象者の認定を受けた場合は、7年前の認定日から障害者であったことになるため、Xは、認定日である7年前から所得税法に規定する「障害者」に該当することになる。
以上のことから、Xがこれまで確定申告において障害者控除の適用をしていなかった場合、過去5年間については、更正の請求の有無にかかわらず税額を減算すべきものであることから、納税者の申出等によりそのような事実が確認されたときには、減額更正をすることができる(通法70)。
しかしながら、過去に遡って障害者控除対象者の認定を受けたとしても、それは国税通則法第23条《更正の請求》第2項の後発的事由に当たるものではないことから、6年前以前について更正の請求をすることはできない。
国外にある外国銀行の納税者名義の口座から国外居住親族に送金した場合の送金書類
Q6 納税者Xが、国外にある外国銀行の本人口座からインターネット取引で親族の口座に送金した場合、当該送金に係る書類は、国外居住親族の生活費等に充てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにする書類(以下「送金等関係書類」という)に該当するか。
A
外国銀行が銀行法第4条《営業の免許》第1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当する。 居住者が国外居住親族を扶養親族とするには、当該国外居住親族が生計を一にすることを明らかにする書類を添付することとされており(所法120③二)、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項第1号において、送金等関係書類として、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という)第2条《定義》第3号に規定する金融機関の書類またはその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするものを添付することとされている。
国送法第2条第3号は、金融機関の定義について国送法施行令第2条《金融機関の範囲》に委任しており、同条は金融機関の範囲を「銀行法第2条第1項に規定する銀行」等と規定し、銀行法第2条《定義等》第1項では、「『銀行』とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者」と規定している。
そして、銀行法第47条《外国銀行の免許等》第1項は、「外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。」と規定していることから、外国銀行が同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行は銀行法第2条第1項に規定する「銀行」に該当し、外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当するものと認められる。
したがって、外国銀行が銀行法4条1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当する。
Ⅳ 申告・加算税等
出国する場合の準確定申告と納税管理人の届出
Q7 確定申告義務を有する居住者Xが、国内に住所および居所を有しなくなった後に、納税管理人を通じて税務署長に「納税管理人の届出書」を提出した。
この場合、Xの確定申告書の提出期限はいつとなるのか。
A
Xの確定申告書の提出期限は出国の時となる。 所得税法にいう「出国」とは、居住者である場合、国税通則法第117条《納税管理人》第2項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいう(所法2①四十二)。
設問の場合、Xが納税管理人の届出をしたのは国内に住所および居所を有しないこととなった後であることから、Xが納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなったときが「出国」の時となる。
そして、確定申告義務を有する居住者が、その年の翌年3月15日までに出国をする場合には、その出国の時までに、その時の現況により確定申告書を提出しなければならないこととされており(所法120①、126①、127①)、「出国」に該当する場合の確定申告書の提出期限はその出国の時となることから、設問の場合、Xは、出国の時までに確定申告書を提出しなければならない。
なお、納税管理人の届出をして国内に住所および居所を有しないこととなる場合は、申告および納付ともその年の翌年2月16日から3月15日までの間にすればよいこととされているが、出国後に納税管理人の届出をした場合の申告期限に関する特別な取扱いはないことから、設問の場合、Xは出国後、出国の時までの申告について無申告の状況にあり、確定申告書を出国後に提出したときには、出国後の納税管理人の届出の有無にかかわらず期限後申告(通法18①、②)として取り扱われ、無申告加算税が賦課されることとなる。
期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用
Q8 XおよびYは兄弟で、ともに給与所得者であるほか、不動産所得の基因となる貸付物件(事業的規模、共有持分2分の1ずつ)を保有している。XおよびYは、いずれも平成29年分の所得税の確定申告をする義務を有していたが、確定申告書の提出を失念しており、両者ともに法定申告期限である3月15日から4週間を経過する4月12日に自主的に期限後申告書を提出した。
XおよびYは、期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用制度(通法66⑦、以下「本制度」という)の適用を受けていない。
なお、Xは、当該期限後申告書に係る第三期分の税額を、現金で法定申告期限内に納付している。
Yは、振替納税を利用しているため、振替日に引き落とされると考え、期限後申告書の提出日である4月12日までに当該期限後申告書に係る第三期分の税額を納付しなかった。
また、XおよびYは、いずれも青色申告特別控除額を65万円と記載して期限後申告書を提出していたが、その後、10万円へ減額する修正申告書を自主的に提出した。
この場合において、
① XおよびYは、本制度の適用を受けることができるか。
② XおよびYが提出した修正申告書に対して加算税は賦課されるか。また、賦課される加算税は何か。
A
① Xの期限後申告については、本制度が適用され、無申告加算税が不適用となる。
Yの期限後申告については、本制度は適用されず、無申告加算税の対象となるが、期限後申告書の提出が決定を予知したものでないため、当該期限後申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
② Xの修正申告は、更正を予知したものでないため、過少申告加算税は賦課されない。
Yの修正申告は、更正を予知したものでないため、当該修正申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することとされており(所法120①、123①)、①法定申告期限後に確定申告書を提出(期限後申告)した場合または決定を受けた場合、②法定申告期限後の確定申告書の提出または決定があった後に修正申告書を提出した場合または更正を受けた場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、申告等によって納付することとなる税額のほかに無申告加算税が賦課される(通法66①)。
なお、これらの申告書の提出が、税務署の調査により更正または決定を受けることを予知してされたものでない場合において、税務署の調査に係る事前通知がある前に提出されたものであるときは、無申告加算税は5%を乗じて計算した金額に軽減される(通法66⑥)。
おって、期限後申告書の提出が、税務署の調査により決定を受けることを予知してされたものでない場合において、その提出が法定申告期限から1月以内であって、その申告により納付すべき税額の全額が法定納期限(振替納税を利用している場合は、期限後申告書を提出した日)までに納付されており、かつ、その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、本制度の適用も受けていない場合には、無申告加算税は賦課されないこととされている(通法66⑦、通令27の2①、②)。
設問の①の場合、Xの期限後申告は、本制度の適用要件を満たしているため、Xに無申告加算税は賦課されない。
Yは、振替納税を利用しているが、期限後申告書の提出日までに、当該期限後申告により納付すべき税額を納付していないため、本制度は適用されず、Yには無申告加算税が賦課される。
なお、Yの期限後申告書の提出は決定を予知したものでないことから、その期限後申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
設問の②の場合、Xの期限後申告は、本制度の要件を満たしているため、その後に修正申告をした場合には、無申告加算税ではなく過少申告加算税の対象となるが、その修正申告書の提出が更正を予知したものでないことから、過少申告加算税は賦課されない。
また、Yの期限後申告は、本制度の要件を満たしていないため、その後に修正申告をした場合には、無申告加算税が賦課されることとなるが、修正申告書の提出が更正を予知したものでないことから、修正申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の記載例(所得控除額の増加を伴う場合)
Q9 国外財産調書未提出者に更正処分をするに当たり、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の加重分の適用がある場合において、所得控除の追加認容(医療費控除の追加等)を加味すると、付表の8の5の計算上、「 」欄の「D」欄および「
」欄の「D」欄および「 」欄の「G」欄の金額がマイナスになり、付表の指示どおり算定すると「
」欄の「G」欄の金額がマイナスになり、付表の指示どおり算定すると「 」欄の「F」欄の「加算税の基礎となる税額」の「加重分」欄が過少申告加算税の対象となる税額を上回ってしまうが、どのように記載すればよいか。
」欄の「F」欄の「加算税の基礎となる税額」の「加重分」欄が過少申告加算税の対象となる税額を上回ってしまうが、どのように記載すればよいか。
A
「 」欄の「D」欄と「
」欄の「D」欄と「 」欄の「G」欄の金額がマイナスになる場合は、当該金額を零円として記載する(13頁付表の8の5・記載例参照)。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の「
」欄の「G」欄の金額がマイナスになる場合は、当該金額を零円として記載する(13頁付表の8の5・記載例参照)。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の「 」欄の「D」欄には、正当な事由があると認められる事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
」欄の「D」欄には、正当な事由があると認められる事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
また、同計算書の「 」欄の「G」欄には、国外財産または財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
」欄の「G」欄には、国外財産または財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
Ⅴ 消費税
土地および建物を一括譲渡した場合の対価の額の区分
Q10 個人事業者Xは、事業の用に供していた土地(以下「本件土地」という)および建物(以下「本件建物」といい、本件土地と本件建物を合わせて「本件土地建物」という)を給与所得者Yに対して一括譲渡しているところ、売買契約書では、譲渡の対価の総額のみを記載しており、その内訳を明らかにしていない。
Xは、確定申告に当たり、本件土地の固定資産税評価額を本件土地に係る譲渡の対価の額(以下「本件土地の対価の額」という)とした上で、本件建物に係る譲渡の対価の額(以下「本件建物の対価の額」という)については、本件土地建物の譲渡の対価の総額から本件土地の対価の額を控除した残額としているが、この譲渡の対価の額の区分の方法は、合理的なものと認められるか。
なお、本件建物の対価の額は、本件建物の固定資産税評価額に比し、著しく低額となっている。
A
Xの採用した本件土地建物の譲渡の対価の額の区分の方法は、合理的なものとは認められない。 事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、これらの資産の譲渡の時における課税資産の価額(時価)と非課税資産の価額(時価)の比により区分することとされている(消令45③)。
なお、例えば、譲渡の対価の額が次の方法により区分されている場合には、合理的に区分されているものと認められる。
① 相続税評価額または固定資産税評価額の比により区分する方法
② 通常の取引価額または取得価額の比により区分する方法
③ 不動産鑑定業者の鑑定評価額(その鑑定評価額が合理的であると認められる場合に限る)の比により区分する方法
Xの採用した本件土地建物の譲渡の対価の額の区分の方法は、本件建物の価額(時価)と本件土地の価額(時価)の比により区分する方法ではないことから、合理的なものとは認められない。
消費税の還付請求申告書に係る更正等の期間制限
Q11 個人事業者Xは、国内の事業者から商品を仕入れ、国外の事業者に輸出販売する事業を営んでおり、各年分の課税期間においては、課税標準額がなく、仕入控除税額のみが生ずることから、毎年、還付申告書を提出している。
なお、平成24年分の申告書は、平成25年2月20日に提出されている。
調査において仕入控除税額の計算に誤りが認められたことから、平成24年分以降の各年分について、平成30年3月9日に更正処分を行ったが、この処分は相当と認められるか。
A
Xが提出する申告書は、消費税法第46条第1項および国税通則法施行令第26条に規定する還付請求申告書に該当するものであり、更正処分を行うことができる期間は、申告書が提出された日の翌日から5年を経過する日までとなることから(通法70①一かっこ書)、平成30年2月20日までに更正処分を行う必要がある。
そのため、平成24年分に係る更正処分については、更正の期間制限を徒過した処分となることから、違法な処分となる。 (注)還付請求申告書の更正の期間制限の起算日は、「法定申告期限の翌日」ではなく、「申告書を提出した日の翌日」となることに留意する。
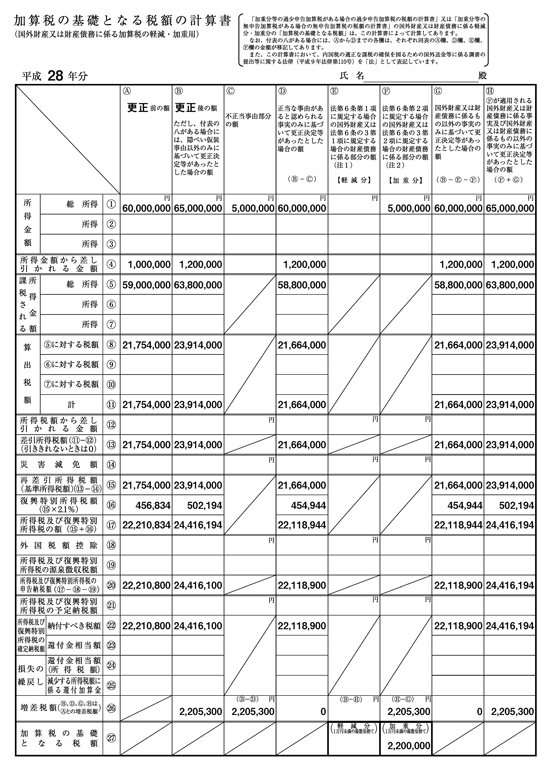
PDFファイルを表示(730_13.pdf)
所得控除、申告・加算税etc.
所得税・消費税の審理事例Q&A
税務当局の所得税・消費税に係る審理事例が明らかになった。医療費控除の事例では、産後ケアセンターへの入所費用は医療費控除の対象とならないとしている。また、申告・加算税関係では、出国後に納税管理人の届出を行い、確定申告書を出国後に提出したときには無申告加算税が賦課されること、消費税関係では、土地建物を一括譲渡した場合、譲渡対価の総額から土地の対価の額を控除した残額を建物の譲渡対価の額とする区分方法は、合理的とは認められないことなどが示されている。
Ⅰ 課税・非課税等
生命保険会社の誤りによって増加した税負担等を補填するために、生保年金受給者に支払われる補填金の課税関係
Q1 適格退職年金は、所得税法上の公的年金等として取り扱われる年金であったが、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度は廃止され、適格退職年金として支払われていた年金を引き続き公的年金等と取り扱うためには、同日までに他の一定の年金制度へ移行する必要があった。
しかしながら、X生命保険株式会社(以下「X生命」という)は、一部の適格退職年金(以下「移行事務疎漏年金」という)について、当該移行手続を失念していたことから、平成24年4月以降、X生命から支払われていた移行事務疎漏年金については、公的年金等には該当せず、いわゆる個人年金に該当するものであったことが判明した。
その結果、X生命が移行事務疎漏年金について、公的年金等として行っていた源泉徴収は誤っていたこととなり、当該年金の受給者(以下「年金受給者」という)の税負担等が増加することとなることから、X生命は、年金受給者に対して税負担等の増加分を補填金として支払うこととした。
この場合に、年金受給者がX生命から支払を受ける補填金の課税関係はどうなるか。
A
年金受給者がX生命から支払を受ける補填金は非課税となる。 損害保険契約に基づく保険金および損害保険契約に準ずる共済契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金は、非課税とされている(所法9①十七、所令30二)。
設問の補填金は、X生命が旧適格退職年金の移行事務を怠ったことによって、年金受給者が被ることとなった損害を賠償するために、X生命が年金受給者に対して支払うものであり、不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金に該当する。
したがって、年金受給者がX生命から支払を受ける補填金は非課税となる。
国際連合大学から支払われる給与に係る課税関係
Q2 居住者Xは、国際連合大学から給与を得ている。
当該給与の支払明細には、支払日および支払金額(円)などが表記されている。
国際連合大学は、当該給与の支払の際に所得税の源泉徴収を行っていないところ、当該給与の課税関係はどうなるか。
A
Xが、「国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定」(以下「協定」という)第12条《大学本部の職員》に定める国際連合の職員である大学本部の職員に該当する場合には、当該給与に対する課税は免除される。 協定第12条第16項1は、国際連合の職員である大学本部の職員が享有する特権および免除について規定している。
そして、同項1(b)では「大学が支払った給料及び手当に対する課税の免除」として、課税の免除に係る規定が置かれている。
したがって、Xが協定第12条の適用を受けることができる国際連合の職員である大学本部の職員に該当する場合には、国際連合大学から支払を受けた給与に対する課税は免除されることとなる。
なお、協定第12条第18項3において、「政府は、この条の規定の範囲内に属する者にその写真を添付した身分証明書を交付する。この証明書は、すべての日本国の当局との関係において身分を証明するために使用される。」と規定されており、協定第12条の適用がある者に該当するか否かは、当該証明書によって確認することができる。
Ⅱ 所得区分等
司法修習生に対する経済的支援(修習給付金)の課税関係
Q3 平成29年度以降に採用される予定の司法修習生に対する経済的支援として、以下の給付制度が新設され、最高裁判所から司法修習生に対する修習給付金が給付される予定であるが、当該修習給付金の課税関係はどうなるか。
(修習給付金の概要)
① 基本給付 司法修習生に一律月額13.5万円
② 住居給付 月額3.5万円(修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象)
③ 移転給付 旅費法の移転料基準に準拠して支払
A
①から③の全てが雑所得となる。
①および②は必要経費として計上できるものがなく、また、③は実費相当額が支払われていることから課税関係が生じない。 修習給付金の支払元である最高裁判所と司法修習生とは雇用関係等になく、修習給付金は司法修習生に対する給与として支払われるものではないため、上記①から③のいずれも給与所得(所法28)には該当しない。
そして、これらの修習給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、①から③の全てが雑所得(所法35)に区分される。
なお、上記①基本給付および②住居給付は、生活維持のために支払われるものとされているため、必要経費として計上できるものはない。
③移転給付については、研修のための移転費用に充てられるものであり、その実費相当額が支払われることとされているものであるから、結果として、課税の対象とはならない。
Ⅲ 所得控除
産後ケアセンターへの入所費用の医療費控除該当性
Q4 X産後ケアセンターは、出産後の産じょく期において、身体回復のため、母子が入所することができる施設である。
当該施設は、医療法に基づかない施設として設置され、当該施設では専門職により、母乳授乳ケア、育児指導、ボディケアおよび美容等を行い、心身のケアを行っているが、医療行為に該当する行為は行われていない。
なお、当該施設の利用料金は、宿泊する部屋の広さ等によって設定金額に差異がある。
当該入所費用は、医療費控除の対象となるか。
A
X産後ケアセンターへの入所費用は、医療費控除の対象とならない。 産後ケアセンターとは、一般的には、出産後の育児支援を目的として、母子が一緒に過ごすことができる医療機関が運営する宿泊施設である。
産後ケアには、①十分なケアによる産後の回復のため、家事や育児の援助、休養・栄養管理など産後の回復に必要な日常生活のケアを受けるもの、②精神的に不安になりがちな女性の心身のケア、子育ての指導を支える産後ケアを提供するもの、③初めての育児に戸惑うことから、分からない事や不安があってもすぐに質問でき、疑問を解消すれば、スムーズに育児をスタートできることを目的とするもの等がある。
ところで、医療費控除の対象となる医療費とは、所得税法第73条《医療費控除》において、医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価として通常認められるものをいい、①医師または助産師等の施術者による診療、施術または分べんの介助の費用に相当するもの、②医師等による診療等を受けるための入院若しくは入所等の対価として支払う部屋代、食事代等の費用で通常必要なもの等が含まれるとされている。
しかしながら、本件のX産後ケアセンターに係る入所費用は、上記のことからすれば、医師等による診療等を受けるための入所等の対価として支払う部屋代、食事代等の費用に当たらない。
したがって、当該入所費用は医療費控除の対象とならない。
市区町村長等が交付した「障害者控除対象者認定書」に遡及して認定する旨の記載があった場合の障害者控除の適用等について
Q5 介護保険法により「要介護認定」を受けていたXが、Z市に対し「障害者控除対象者認定書」の交付を要求した。これを受け、Z市長は、認定日を7年前とする「障害者控除対象者認定書」をXに交付した。
このとき、Xは7年前から遡及して障害者控除の適用を受けることができるか。
A
Xがこれまで確定申告において障害者控除の適用をしていなかった場合、過去5年間は更正の請求の有無にかかわらず減額更正をすることができるが、6年前以前について更正の請求をすることはできない。 所得税法上、障害者控除の適用を受けるためには、納税者本人またはその控除対象配偶者および扶養親族のうちに、障害者がいることが要件とされている(所法79)。
ここでいう障害者とは、「障害者手帳」等の交付を受けている者のほか、所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第2項第6号に定める「市町村長等の認定を受けている者」も含まれるため、市区町村長等より障害者として認定され、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている者は、所得税法に規定する障害者として取り扱われることとなる。
そして、設例のXのように、7年前に遡って障害者控除対象者の認定を受けた場合は、7年前の認定日から障害者であったことになるため、Xは、認定日である7年前から所得税法に規定する「障害者」に該当することになる。
以上のことから、Xがこれまで確定申告において障害者控除の適用をしていなかった場合、過去5年間については、更正の請求の有無にかかわらず税額を減算すべきものであることから、納税者の申出等によりそのような事実が確認されたときには、減額更正をすることができる(通法70)。
しかしながら、過去に遡って障害者控除対象者の認定を受けたとしても、それは国税通則法第23条《更正の請求》第2項の後発的事由に当たるものではないことから、6年前以前について更正の請求をすることはできない。
国外にある外国銀行の納税者名義の口座から国外居住親族に送金した場合の送金書類
Q6 納税者Xが、国外にある外国銀行の本人口座からインターネット取引で親族の口座に送金した場合、当該送金に係る書類は、国外居住親族の生活費等に充てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにする書類(以下「送金等関係書類」という)に該当するか。
A
外国銀行が銀行法第4条《営業の免許》第1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当する。 居住者が国外居住親族を扶養親族とするには、当該国外居住親族が生計を一にすることを明らかにする書類を添付することとされており(所法120③二)、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項第1号において、送金等関係書類として、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という)第2条《定義》第3号に規定する金融機関の書類またはその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするものを添付することとされている。
国送法第2条第3号は、金融機関の定義について国送法施行令第2条《金融機関の範囲》に委任しており、同条は金融機関の範囲を「銀行法第2条第1項に規定する銀行」等と規定し、銀行法第2条《定義等》第1項では、「『銀行』とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者」と規定している。
そして、銀行法第47条《外国銀行の免許等》第1項は、「外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。」と規定していることから、外国銀行が同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行は銀行法第2条第1項に規定する「銀行」に該当し、外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当するものと認められる。
したがって、外国銀行が銀行法4条1項の内閣総理大臣の免許を受けていれば、当該外国銀行の外国口座に係る送金書類についても送金等関係書類に該当する。
Ⅳ 申告・加算税等
出国する場合の準確定申告と納税管理人の届出
Q7 確定申告義務を有する居住者Xが、国内に住所および居所を有しなくなった後に、納税管理人を通じて税務署長に「納税管理人の届出書」を提出した。
この場合、Xの確定申告書の提出期限はいつとなるのか。
A
Xの確定申告書の提出期限は出国の時となる。 所得税法にいう「出国」とは、居住者である場合、国税通則法第117条《納税管理人》第2項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいう(所法2①四十二)。
設問の場合、Xが納税管理人の届出をしたのは国内に住所および居所を有しないこととなった後であることから、Xが納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなったときが「出国」の時となる。
そして、確定申告義務を有する居住者が、その年の翌年3月15日までに出国をする場合には、その出国の時までに、その時の現況により確定申告書を提出しなければならないこととされており(所法120①、126①、127①)、「出国」に該当する場合の確定申告書の提出期限はその出国の時となることから、設問の場合、Xは、出国の時までに確定申告書を提出しなければならない。
なお、納税管理人の届出をして国内に住所および居所を有しないこととなる場合は、申告および納付ともその年の翌年2月16日から3月15日までの間にすればよいこととされているが、出国後に納税管理人の届出をした場合の申告期限に関する特別な取扱いはないことから、設問の場合、Xは出国後、出国の時までの申告について無申告の状況にあり、確定申告書を出国後に提出したときには、出国後の納税管理人の届出の有無にかかわらず期限後申告(通法18①、②)として取り扱われ、無申告加算税が賦課されることとなる。
期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用
Q8 XおよびYは兄弟で、ともに給与所得者であるほか、不動産所得の基因となる貸付物件(事業的規模、共有持分2分の1ずつ)を保有している。XおよびYは、いずれも平成29年分の所得税の確定申告をする義務を有していたが、確定申告書の提出を失念しており、両者ともに法定申告期限である3月15日から4週間を経過する4月12日に自主的に期限後申告書を提出した。
XおよびYは、期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用制度(通法66⑦、以下「本制度」という)の適用を受けていない。
なお、Xは、当該期限後申告書に係る第三期分の税額を、現金で法定申告期限内に納付している。
Yは、振替納税を利用しているため、振替日に引き落とされると考え、期限後申告書の提出日である4月12日までに当該期限後申告書に係る第三期分の税額を納付しなかった。
また、XおよびYは、いずれも青色申告特別控除額を65万円と記載して期限後申告書を提出していたが、その後、10万円へ減額する修正申告書を自主的に提出した。
この場合において、
① XおよびYは、本制度の適用を受けることができるか。
② XおよびYが提出した修正申告書に対して加算税は賦課されるか。また、賦課される加算税は何か。
A
① Xの期限後申告については、本制度が適用され、無申告加算税が不適用となる。
Yの期限後申告については、本制度は適用されず、無申告加算税の対象となるが、期限後申告書の提出が決定を予知したものでないため、当該期限後申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
② Xの修正申告は、更正を予知したものでないため、過少申告加算税は賦課されない。
Yの修正申告は、更正を予知したものでないため、当該修正申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することとされており(所法120①、123①)、①法定申告期限後に確定申告書を提出(期限後申告)した場合または決定を受けた場合、②法定申告期限後の確定申告書の提出または決定があった後に修正申告書を提出した場合または更正を受けた場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、申告等によって納付することとなる税額のほかに無申告加算税が賦課される(通法66①)。
なお、これらの申告書の提出が、税務署の調査により更正または決定を受けることを予知してされたものでない場合において、税務署の調査に係る事前通知がある前に提出されたものであるときは、無申告加算税は5%を乗じて計算した金額に軽減される(通法66⑥)。
おって、期限後申告書の提出が、税務署の調査により決定を受けることを予知してされたものでない場合において、その提出が法定申告期限から1月以内であって、その申告により納付すべき税額の全額が法定納期限(振替納税を利用している場合は、期限後申告書を提出した日)までに納付されており、かつ、その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、本制度の適用も受けていない場合には、無申告加算税は賦課されないこととされている(通法66⑦、通令27の2①、②)。
設問の①の場合、Xの期限後申告は、本制度の適用要件を満たしているため、Xに無申告加算税は賦課されない。
Yは、振替納税を利用しているが、期限後申告書の提出日までに、当該期限後申告により納付すべき税額を納付していないため、本制度は適用されず、Yには無申告加算税が賦課される。
なお、Yの期限後申告書の提出は決定を予知したものでないことから、その期限後申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
設問の②の場合、Xの期限後申告は、本制度の要件を満たしているため、その後に修正申告をした場合には、無申告加算税ではなく過少申告加算税の対象となるが、その修正申告書の提出が更正を予知したものでないことから、過少申告加算税は賦課されない。
また、Yの期限後申告は、本制度の要件を満たしていないため、その後に修正申告をした場合には、無申告加算税が賦課されることとなるが、修正申告書の提出が更正を予知したものでないことから、修正申告により納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課される。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の記載例(所得控除額の増加を伴う場合)
Q9 国外財産調書未提出者に更正処分をするに当たり、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の加重分の適用がある場合において、所得控除の追加認容(医療費控除の追加等)を加味すると、付表の8の5の計算上、「
 」欄の「D」欄および「
」欄の「D」欄および「 」欄の「G」欄の金額がマイナスになり、付表の指示どおり算定すると「
」欄の「G」欄の金額がマイナスになり、付表の指示どおり算定すると「 」欄の「F」欄の「加算税の基礎となる税額」の「加重分」欄が過少申告加算税の対象となる税額を上回ってしまうが、どのように記載すればよいか。
」欄の「F」欄の「加算税の基礎となる税額」の「加重分」欄が過少申告加算税の対象となる税額を上回ってしまうが、どのように記載すればよいか。| (更正前の額)
総所得 6,000万円 所得控除額 100万円 (更正後の額) 総所得 6,500万円 (増差所得の内訳 国送法6条2項の国外財産に係る部分 500万円) 所得控除額 120万円 |
「
 」欄の「D」欄と「
」欄の「D」欄と「 」欄の「G」欄の金額がマイナスになる場合は、当該金額を零円として記載する(13頁付表の8の5・記載例参照)。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の「
」欄の「G」欄の金額がマイナスになる場合は、当該金額を零円として記載する(13頁付表の8の5・記載例参照)。
「加算税の基礎となる税額の計算書(国外財産又は財産債務に係る加算税の軽減・加重用)」の「 」欄の「D」欄には、正当な事由があると認められる事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
」欄の「D」欄には、正当な事由があると認められる事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。また、同計算書の「
 」欄の「G」欄には、国外財産または財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。
」欄の「G」欄には、国外財産または財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて更正決定等があったとした場合の増差税額を記載することとされているが、計算上マイナスの金額となる場合には、増差税額がないものとして「0」と記載する。Ⅴ 消費税
土地および建物を一括譲渡した場合の対価の額の区分
Q10 個人事業者Xは、事業の用に供していた土地(以下「本件土地」という)および建物(以下「本件建物」といい、本件土地と本件建物を合わせて「本件土地建物」という)を給与所得者Yに対して一括譲渡しているところ、売買契約書では、譲渡の対価の総額のみを記載しており、その内訳を明らかにしていない。
Xは、確定申告に当たり、本件土地の固定資産税評価額を本件土地に係る譲渡の対価の額(以下「本件土地の対価の額」という)とした上で、本件建物に係る譲渡の対価の額(以下「本件建物の対価の額」という)については、本件土地建物の譲渡の対価の総額から本件土地の対価の額を控除した残額としているが、この譲渡の対価の額の区分の方法は、合理的なものと認められるか。
なお、本件建物の対価の額は、本件建物の固定資産税評価額に比し、著しく低額となっている。
A
Xの採用した本件土地建物の譲渡の対価の額の区分の方法は、合理的なものとは認められない。 事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、これらの資産の譲渡の時における課税資産の価額(時価)と非課税資産の価額(時価)の比により区分することとされている(消令45③)。
なお、例えば、譲渡の対価の額が次の方法により区分されている場合には、合理的に区分されているものと認められる。
① 相続税評価額または固定資産税評価額の比により区分する方法
② 通常の取引価額または取得価額の比により区分する方法
③ 不動産鑑定業者の鑑定評価額(その鑑定評価額が合理的であると認められる場合に限る)の比により区分する方法
Xの採用した本件土地建物の譲渡の対価の額の区分の方法は、本件建物の価額(時価)と本件土地の価額(時価)の比により区分する方法ではないことから、合理的なものとは認められない。
消費税の還付請求申告書に係る更正等の期間制限
Q11 個人事業者Xは、国内の事業者から商品を仕入れ、国外の事業者に輸出販売する事業を営んでおり、各年分の課税期間においては、課税標準額がなく、仕入控除税額のみが生ずることから、毎年、還付申告書を提出している。
なお、平成24年分の申告書は、平成25年2月20日に提出されている。
調査において仕入控除税額の計算に誤りが認められたことから、平成24年分以降の各年分について、平成30年3月9日に更正処分を行ったが、この処分は相当と認められるか。
A
Xが提出する申告書は、消費税法第46条第1項および国税通則法施行令第26条に規定する還付請求申告書に該当するものであり、更正処分を行うことができる期間は、申告書が提出された日の翌日から5年を経過する日までとなることから(通法70①一かっこ書)、平成30年2月20日までに更正処分を行う必要がある。
そのため、平成24年分に係る更正処分については、更正の期間制限を徒過した処分となることから、違法な処分となる。 (注)還付請求申告書の更正の期間制限の起算日は、「法定申告期限の翌日」ではなく、「申告書を提出した日の翌日」となることに留意する。
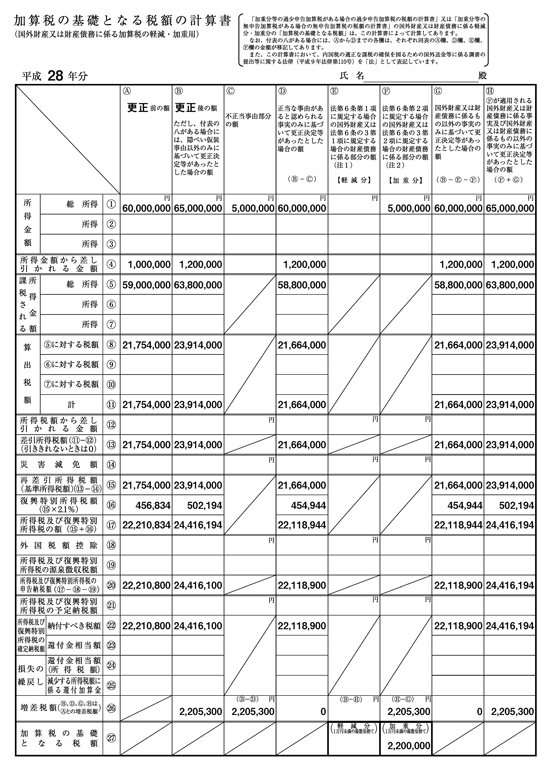
PDFファイルを表示(730_13.pdf)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















