解説記事2018年03月26日 【ニュース特集】 Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置(2018年3月26日号・№732)
ニュース特集
税理士等の経営革新等支援機関の関与が必須
Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置
平成30年度税制改正では、中小企業を対象とした新たな設備投資に係る固定資産税の特例措置が講じられる。これは、平成32年度までの3年間に限り投資した機械装置等に係る固定資産税を2分の1から最大でゼロまで軽減するというもの。現行の固定資産税の軽減措置と基本的に同様の仕組みとなっているが、市町村の条例が前提となっているほか、税理士や公認会計士等の経営革新等支援機関の関与が必須となっているなど、多少制度的に異なる部分もある。また、中小企業にとって気になる「ものづくり・サービス補助金」などの4つの補助金については、市町村が特例率をゼロとすることが優先採択の条件になっている。中小企業庁では各市町村に今後の方針などについてアンケートを行っており、3月末頃を目途に結果を公表する予定だ。こちらの状況も注目される。
本特集では新しい固定資産税の特例措置について取材に基づいた最新情報をQ&A形式で解説する。
平成31年3月末までは両制度が併存
Q
平成30年度税制改正で手当てされる予定の固定資産税の特例措置は、現行の固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例)の期限延長とは違うのでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置と平成30年度税制改正で導入される予定の固定資産税の特例措置とは基本的な仕組みで同様の部分はあるものの、異なる制度となっている(図表1参照)。現行制度は中小企業等経営強化法に基づくものだが、新しい固定資産税の特例措置は、今通常国会に提出された「生産性向上特別措置法案」の制定を前提とするものとなっている。
具体的には、同法により市町村が策定した導入促進基本計画に基づき、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるものが対象となる(単純な更新投資は対象外)。このうち、同法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得されたものに係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間に限り、市町村の条例により最大でゼロから2分の1以下の範囲で軽減される。
なお、現行の固定資産税の軽減措置は平成31年3月31日まで適用することが可能。平成31年3月末までは両制度が併存して存続する形となる(本誌721号40頁参照)。
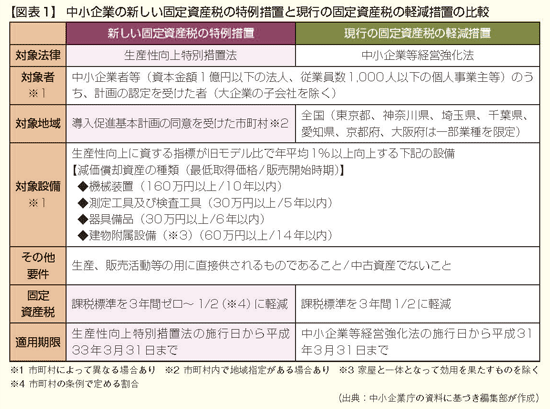
市町村が条例を定めることが必要
Q
固定資産税の特例措置を受けるためのスキームを教えてください。
A 今回の固定資産税の特例措置は事業者側だけでなく、市町村にも大きな役割が与えられている。そもそも今回の特例措置を受けるには、市町村が生産性向上特別措置法に基づき導入促進基本計画を策定し、これを国に同意してもらった上で、市町村の条例を定める必要があるからだ。市町村は条例により、3年間固定資産税の特例率をゼロ以上2分の1以下とすることができる。ただ、あくまでも条例を定めるかどうかは市町村次第となる。多くの市町村で条例を定めることが想定されているが、事業者が税制の適用を受けるには、まずは市町村の条例が定められているか確認する必要がある。
一方、事業者側は市町村の導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、その導入する先端設備等の所在地を管轄する市町村から認定を受けることになる。設備導入により、労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資のほか、生産、販売活動等のために直接供される新たな設備投資であることが必要になる。
なお、先端設備等導入計画には、①先端設備等の種類及び導入時期、②先端設備等導入の内容、③先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法を記載する。
先端設備等の証明はメーカーを通じて工業会に
Q
先端設備等は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備とされています。対象設備であるかどうかは、メーカー等に確認すればよいのですか。
A 対象となる先端設備等の要件は、現行の固定資産税の軽減措置と同様となっており、今回の特例措置も現行制度と同様の仕組みが考えられている。具体的には、中小企業者は、先端設備等導入計画作成時に取得する設備等を決定し、メーカーを通じて担当する工業会等による証明書を入手することになる。入手した証明書は「先端設備等導入計画」に添付して計画申請することになる方向だ。
計画段階で税理士や会計士の関与が必要
Q
現行の固定資産税の軽減措置については、税理士などの経営革新等支援機関の助言は任意となっていますが、新しい固定資産税の特例措置も同様と考えてよいでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置においては、中小企業者が経営力向上計画を容易に提出することができるよう、税理士や公認会計士等の経営革新等支援機関の助言を受けることができるとされている。ただし、これは強制ではなく任意である。
今回の特例措置では、先端設備等導入計画の策定段階で税理士等の関与を必須とする制度が想定されている。
先端設備等の設置場所で適用
Q
固定資産税の特例措置は、機械装置等を設置した場所あるいは本店所在地のどちらで適用されるのでしょうか。
A 固定資産税の特例措置は、本店所在地ではなく、機械装置等の先端設備等を設置した所在地(納税地)で適用されることになる。例えば、市町村の条例が制定されていないところに本店所在地があったとしても、機械装置等を設置した場所の市町村で条例が定められていれば適用対象となる。
認定のハードルは低く、計画の提出先は市町村のみ
Q
先端設備等導入計画の認定を受けることは難しいのでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置の適用を受けるための経営力向上計画の申請書は実質2ページであり、法令の要件さえ整っていれば基本的に認定を受けることができる仕組み
となっている。今回の先端設備等導入計画もほぼ同様の仕組みとなっているので、認定を受けるハードルはそれほど高くないことが想定される。
現行の軽減措置では、事業分野が複数の省庁の所管にまたがっているケースでは認定までの期間が45日程度かかるとされていたほか、どこの省庁で認定を受けるのか分かりにくいといった声が事業者から寄せられていたが、今回の特例措置は計画の提出先は先端設備等のある市町村と明確であり、仕組み自体も単純化されている。
市町村によって対象設備が異なるケースも
Q
市町村の条例次第ということですが、市町村によって対象設備が異なったり、市町村内で地域が指定されたりするといったことがあるのでしょうか。
A 各市町村の財政上の事情などもあるため、対象設備が異なったり、同じ市町村の中で地域指定が講じられたりすることもありうる。
レアケースではあるものの、例えば、製造業に限る、あるいは工業地区に限るといったことが条例で定められる市町村も出てきそうだ。いずれにせよ最終的には各市町村の条例の公布を待つ必要がある。
ファイナンスリースも対象
Q
リース取引も対象となりますか。
A 所有権移転外ファイナンスリースだけでなく、ファイナンスリースも含め、固定資産税の特例措置の対象となっている(ただし、オペレーティングリースは対象外)。
生産性向上特別措置法の施行日前に取得した設備は対象外
Q
生産性向上特別措置法の施行日前に取得した機械装置は対象になりますか。
A 固定資産税の特例措置は、生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得されたものに係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間に限り、市町村の条例により最大でゼロから2分の1以下の範囲で軽減されるため、同法の施行日前に取得したものは対象外となる。
なお、現行の固定資産税の軽減措置では、原則は経営力向上計画の認定後に取得した機械装置等が対象となるが、実務上、認定前に取得したものであっても、取得日から60日以内に同計画の申請が受理されれば軽減措置の適用を受けることができる。今回の特例措置については、現時点(平成30年3月16日時点)では関係省庁と協議中となっている。今後の動向には注目しておきたい点である。
中小企業庁が3月末頃を目途にホームページで公表へ
Q
どのような市町村が条例を制定するのでしょうか。基本的に大きな市町村に限られるのでしょうか。
A 最終的には市町村の判断となるため現時点では全てが明らかになっているわけではないが、例えば、川崎市や千葉市、北九州市といった大きな市から滋賀県の湖南市といった人口が10万人にも満たない市もすでに条例によって固定資産税をゼロにする方針を明らかにしている。特例率がゼロであるかどうかがものづくり補助金等の優先採択となっているため、多くの市町村で特例率をゼロとすることが想定されている。
なお、中小企業庁は全国の市町村に対して条例を制定するか(特例率をゼロにするか)どうかなどのアンケート調査を実施しており、3月末頃を目途にホームページ上に公表する予定としている。
“ゼロ”の市町村には4つの補助金が優先採択
Q
固定資産税の特例率をゼロとした市町村でなければ補助金を受けることはできませんか。
A 今回の固定資産税の特例措置については、条例を制定し、特例率をゼロにすることは市町村次第になっているが、特例率をゼロにした市町村においては、ものづくり補助金等の優先採択を行うことになっている。具体的には下記の4つの補助金が対象となっている。
遅くとも夏頃までの施行を目指す
Q
生産性向上特別措置法はいつから施行される予定ですか。
A 同法案によれば、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされている。国会の審議状況によるが、政府としては春頃の成立・公布、遅くとも夏頃までには施行したいとの意向のようだ。
税理士等の経営革新等支援機関の関与が必須
Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置
平成30年度税制改正では、中小企業を対象とした新たな設備投資に係る固定資産税の特例措置が講じられる。これは、平成32年度までの3年間に限り投資した機械装置等に係る固定資産税を2分の1から最大でゼロまで軽減するというもの。現行の固定資産税の軽減措置と基本的に同様の仕組みとなっているが、市町村の条例が前提となっているほか、税理士や公認会計士等の経営革新等支援機関の関与が必須となっているなど、多少制度的に異なる部分もある。また、中小企業にとって気になる「ものづくり・サービス補助金」などの4つの補助金については、市町村が特例率をゼロとすることが優先採択の条件になっている。中小企業庁では各市町村に今後の方針などについてアンケートを行っており、3月末頃を目途に結果を公表する予定だ。こちらの状況も注目される。
本特集では新しい固定資産税の特例措置について取材に基づいた最新情報をQ&A形式で解説する。
平成31年3月末までは両制度が併存
Q
平成30年度税制改正で手当てされる予定の固定資産税の特例措置は、現行の固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例)の期限延長とは違うのでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置と平成30年度税制改正で導入される予定の固定資産税の特例措置とは基本的な仕組みで同様の部分はあるものの、異なる制度となっている(図表1参照)。現行制度は中小企業等経営強化法に基づくものだが、新しい固定資産税の特例措置は、今通常国会に提出された「生産性向上特別措置法案」の制定を前提とするものとなっている。
具体的には、同法により市町村が策定した導入促進基本計画に基づき、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるものが対象となる(単純な更新投資は対象外)。このうち、同法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得されたものに係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間に限り、市町村の条例により最大でゼロから2分の1以下の範囲で軽減される。
なお、現行の固定資産税の軽減措置は平成31年3月31日まで適用することが可能。平成31年3月末までは両制度が併存して存続する形となる(本誌721号40頁参照)。
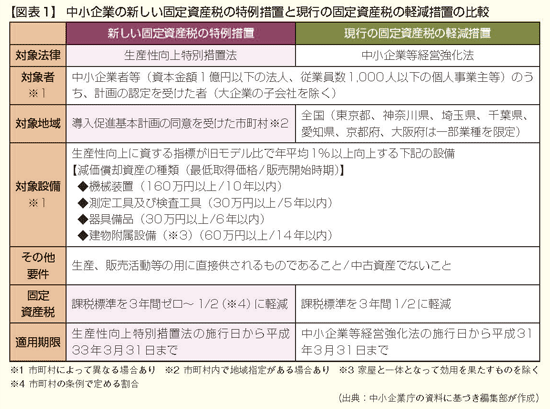
市町村が条例を定めることが必要
Q
固定資産税の特例措置を受けるためのスキームを教えてください。
A 今回の固定資産税の特例措置は事業者側だけでなく、市町村にも大きな役割が与えられている。そもそも今回の特例措置を受けるには、市町村が生産性向上特別措置法に基づき導入促進基本計画を策定し、これを国に同意してもらった上で、市町村の条例を定める必要があるからだ。市町村は条例により、3年間固定資産税の特例率をゼロ以上2分の1以下とすることができる。ただ、あくまでも条例を定めるかどうかは市町村次第となる。多くの市町村で条例を定めることが想定されているが、事業者が税制の適用を受けるには、まずは市町村の条例が定められているか確認する必要がある。
一方、事業者側は市町村の導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、その導入する先端設備等の所在地を管轄する市町村から認定を受けることになる。設備導入により、労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資のほか、生産、販売活動等のために直接供される新たな設備投資であることが必要になる。
なお、先端設備等導入計画には、①先端設備等の種類及び導入時期、②先端設備等導入の内容、③先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法を記載する。
先端設備等の証明はメーカーを通じて工業会に
Q
先端設備等は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備とされています。対象設備であるかどうかは、メーカー等に確認すればよいのですか。
A 対象となる先端設備等の要件は、現行の固定資産税の軽減措置と同様となっており、今回の特例措置も現行制度と同様の仕組みが考えられている。具体的には、中小企業者は、先端設備等導入計画作成時に取得する設備等を決定し、メーカーを通じて担当する工業会等による証明書を入手することになる。入手した証明書は「先端設備等導入計画」に添付して計画申請することになる方向だ。
計画段階で税理士や会計士の関与が必要
Q
現行の固定資産税の軽減措置については、税理士などの経営革新等支援機関の助言は任意となっていますが、新しい固定資産税の特例措置も同様と考えてよいでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置においては、中小企業者が経営力向上計画を容易に提出することができるよう、税理士や公認会計士等の経営革新等支援機関の助言を受けることができるとされている。ただし、これは強制ではなく任意である。
今回の特例措置では、先端設備等導入計画の策定段階で税理士等の関与を必須とする制度が想定されている。
先端設備等の設置場所で適用
Q
固定資産税の特例措置は、機械装置等を設置した場所あるいは本店所在地のどちらで適用されるのでしょうか。
A 固定資産税の特例措置は、本店所在地ではなく、機械装置等の先端設備等を設置した所在地(納税地)で適用されることになる。例えば、市町村の条例が制定されていないところに本店所在地があったとしても、機械装置等を設置した場所の市町村で条例が定められていれば適用対象となる。
認定のハードルは低く、計画の提出先は市町村のみ
Q
先端設備等導入計画の認定を受けることは難しいのでしょうか。
A 現行の固定資産税の軽減措置の適用を受けるための経営力向上計画の申請書は実質2ページであり、法令の要件さえ整っていれば基本的に認定を受けることができる仕組み
となっている。今回の先端設備等導入計画もほぼ同様の仕組みとなっているので、認定を受けるハードルはそれほど高くないことが想定される。
現行の軽減措置では、事業分野が複数の省庁の所管にまたがっているケースでは認定までの期間が45日程度かかるとされていたほか、どこの省庁で認定を受けるのか分かりにくいといった声が事業者から寄せられていたが、今回の特例措置は計画の提出先は先端設備等のある市町村と明確であり、仕組み自体も単純化されている。
市町村によって対象設備が異なるケースも
Q
市町村の条例次第ということですが、市町村によって対象設備が異なったり、市町村内で地域が指定されたりするといったことがあるのでしょうか。
A 各市町村の財政上の事情などもあるため、対象設備が異なったり、同じ市町村の中で地域指定が講じられたりすることもありうる。
レアケースではあるものの、例えば、製造業に限る、あるいは工業地区に限るといったことが条例で定められる市町村も出てきそうだ。いずれにせよ最終的には各市町村の条例の公布を待つ必要がある。
ファイナンスリースも対象
Q
リース取引も対象となりますか。
A 所有権移転外ファイナンスリースだけでなく、ファイナンスリースも含め、固定資産税の特例措置の対象となっている(ただし、オペレーティングリースは対象外)。
生産性向上特別措置法の施行日前に取得した設備は対象外
Q
生産性向上特別措置法の施行日前に取得した機械装置は対象になりますか。
A 固定資産税の特例措置は、生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得されたものに係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間に限り、市町村の条例により最大でゼロから2分の1以下の範囲で軽減されるため、同法の施行日前に取得したものは対象外となる。
なお、現行の固定資産税の軽減措置では、原則は経営力向上計画の認定後に取得した機械装置等が対象となるが、実務上、認定前に取得したものであっても、取得日から60日以内に同計画の申請が受理されれば軽減措置の適用を受けることができる。今回の特例措置については、現時点(平成30年3月16日時点)では関係省庁と協議中となっている。今後の動向には注目しておきたい点である。
中小企業庁が3月末頃を目途にホームページで公表へ
Q
どのような市町村が条例を制定するのでしょうか。基本的に大きな市町村に限られるのでしょうか。
A 最終的には市町村の判断となるため現時点では全てが明らかになっているわけではないが、例えば、川崎市や千葉市、北九州市といった大きな市から滋賀県の湖南市といった人口が10万人にも満たない市もすでに条例によって固定資産税をゼロにする方針を明らかにしている。特例率がゼロであるかどうかがものづくり補助金等の優先採択となっているため、多くの市町村で特例率をゼロとすることが想定されている。
なお、中小企業庁は全国の市町村に対して条例を制定するか(特例率をゼロにするか)どうかなどのアンケート調査を実施しており、3月末頃を目途にホームページ上に公表する予定としている。
“ゼロ”の市町村には4つの補助金が優先採択
Q
固定資産税の特例率をゼロとした市町村でなければ補助金を受けることはできませんか。
A 今回の固定資産税の特例措置については、条例を制定し、特例率をゼロにすることは市町村次第になっているが、特例率をゼロにした市町村においては、ものづくり補助金等の優先採択を行うことになっている。具体的には下記の4つの補助金が対象となっている。
| 補助事業名 | 概 要 |
| ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金) | 中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
| 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) | 小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金) | 中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援 |
| サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金) | 中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援 |
| (出典:中小企業庁) |
遅くとも夏頃までの施行を目指す
Q
生産性向上特別措置法はいつから施行される予定ですか。
A 同法案によれば、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされている。国会の審議状況によるが、政府としては春頃の成立・公布、遅くとも夏頃までには施行したいとの意向のようだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























