解説記事2018年09月03日 【ニュース特集】 31年改正における組織再編税制、役員給与税制の見直し(2018年9月3日号・№753)
ニュース特集
三角合併、業績連動給与を緩和する案が浮上
31年改正における組織再編税制、役員給与税制の見直し
各省庁の平成31年度税制改正要望が出揃い、これから年末に向け税制改正議論が本格化することになるが、同年度改正では組織再編税制と役員給与税制の緩和がテーマとなることが本誌取材により判明した。
組織再編税制では、三角合併の際に“間接100%親会社”の株式を対価とするケースも税制適格再編の対象にすることが検討される。この改正が実現すれば、上場会社の孫会社の組織再編が容易となる。役員給与税制では、平成30年度税制改正で算定基礎となる指標に株価等が追加されるなど見直しが行われたにもかかわらず利用者数が伸びていない業績連動給与の「適正手続要件」の緩和が検討される。具体的には、指名委員会等設置会社の報酬委員会のメンバーに業務執行役員がいたとしても損金算入を認めることなどが議論される模様だ。また、ストックオプションの税制適格要件の緩和も検討される方向となっている(本号7頁参照)。
組織再編税制の見直し
現行組織再編税制で適格再編と認められている三角合併(図1参照)では、合併親法人株式(直接の100%親会社の株式)のみを合併対価として利用することができる(法法2十二の八)。
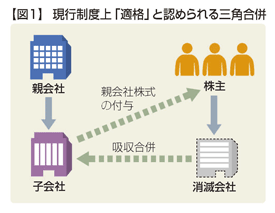
ただ、このように対価が100%親会社株式に限定されていることにより、三角合併を行うことが困難となるケースがある。
例えば上場会社である持株会社A社(親会社)の下に事業会社B社(子会社)がぶら下がっており、さらにその下に事業会社C社(孫会社)がぶら下がっているとする。この場合、孫会社であるC社が自社を存続会社とする税制適格の三角合併を行おうとすれば、C社は消滅会社の株主に対し、親会社であるB社の株式を付与するしかない。しかし、B社は上場会社ではないためその株式には流動性がないことから、消滅会社の株主は合併の対価がB社株式であることに納得しないだろう。そこで平成31年度税制改正では、上場会社である親会社A社(C社にとっての“間接100%親会社”)の株式を三角合併の対価として認める案(図2参照)が検討される。
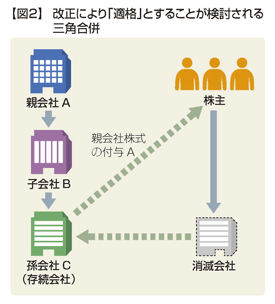
現行制度の下で孫会社が親会社の株式を対価とする三角合併を行うためには、子会社B社が孫会社C社の株式を親会社A社に現物分配し、A社の直下にC社をぶら下げるという手法をとることが考えられる(図3参照)。これにより、C社は三角合併においてA社株式を合併の対価として使えるようになるとはいえ、はじめから孫会社が親会社の株式を対価とする三角合併を認めてしまえば、このような手続き(現物分配)を省略することができるようになるというメリットもある。
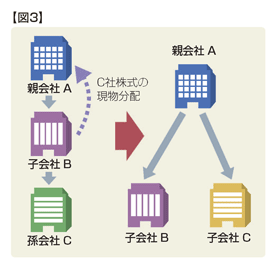
平成18年の会社法の創設時に“合併対価の柔軟化”として、吸収合併等の際には、存続会社の株式を交付せずに「金銭その他の財産」を交付することが認められ、これにより三角合併が解禁されたが、企業側からは三角合併が海外企業による日本企業買収に利用されることを懸念する声が相次ぎ、その実施が会社法施行日の1年後に延期されたという経緯がある。この延期期間を利用し、買収防衛策を導入する会社が相次いだ。しかしそれから10年余りを経て、現在は買収防衛策の廃止に踏み切る企業が相次ぐなどコーポレートガバナンスに関する考え方は一変している。また、好景気による株高ということもあり、株式を利用した組織再編の柔軟化に反対する声は産業界からは聞こえてこない。また、近年はスピンオフ税制や自社株対価TOBの導入など組織再編絡みの大胆な税制措置が相次いで実現していることからすると、“間接100%親会社”株式を対価とする合併を適格再編とする本改正が実現する可能性も決して低くはないだろう。
なお、三角合併と同じ税制は、分割、株式交換にも設けられている(法法2条十二の十一、十二の十七)ため、合併のみならず、分割や株式交換についても同様の議論が行われることになるものとみられる。
役員給与税制の見直し
平成29年度税制改正では、従来の利益連動給与が「業績連動給与」へと名称変更された上で、支給額の算定方法の基礎とすることができる指標に株価等が追加されたところだが、業績連動給与の普及はそれほど進んでいない(本誌704号5頁③参照)。その原因の1つと考えられるのが、詳細な開示要件と適正手続要件だ。
特に適正手続要件については、企業側から「厳しすぎる」との指摘が多い。例えば、指名委員会等設置会社に対しては、「報酬委員会(……業務執行役員が……委員になっているものを除く。)が決定」との要件(法法34条①三イ(2))が課されている。すなわち、たとえ報酬委員会のメンバーの過半数が社外取締役であったり、報酬委員会の委員長が社外取締役であったりしても、一人でも業務執行役員(業務執行を行う取締役や執行役など)(法法34①三)が報酬委員会のメンバーに入っていれば適正手続要件を満たせず、業績連動給与は損金算入できない。
同様の問題は、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社においても起こり得る。平成27年6月1日に導入されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①が、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社に対し、取締役会の独立性・客観性、説明責任を強化する手法の一つとして任意の報酬委員会(報酬諮問委員会)の導入を例示して以来、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社でも報酬諮問委員会を導入するところが増えているが(2018年7月31日現在、東証一部上場会社の34.9%(前年31.7%)が導入)、上記法法34条①三イ(2)同様、この報酬諮問委員会についても、一人でも業務執行役員がメンバーに入っていれば、適正手続要件を満たせないこととなるからだ(法令69条⑮三)。今年6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンスコードの補充原則4-10①では、報酬諮問委員会の設置が従来より強く求められていることから、今後報酬諮問委員会を設置する監査等委員会設置会社や監査役会設置会社が益々増えることが予想される。そうなれば、この要件を問題視する声が強まることになるだろう。
そもそもこの「……業務執行役員が……委員になっているものを除く」との要件は、役員給与税制が大幅に見直された平成18年度税制改正から変わっていない。しかし、見直しから12年が経過し、業績連動給与の重要性は当時とは比べ物にならないほど高まっている。これは、改訂コーポレートガバナンスコードで「中長期的な業績と連動する報酬の割合……を適切に設定すべきである」(補充原則4-2①)とされたほか、最近公表された金融庁のディスクロージャーワーキング報告でも、企業価値の向上に向けた経営陣のインセンティブとして業績連動報酬の重要性が再認識されていることからも分かる。
平成29年度税制改正で「非同族法人の100%子法人」に係る要件が緩和されたことを除き特段の見直しは行われていない適正手続き要件は、そろそろ見直しのタイミングに来ていると言えそうだ。
また、業績連動給与と同じくインセンティブ報酬の一種であるストックオプションの税制適格要件の見直しも検討される方向。
具体的には、権利行使価額を現行の年間1,200万円から2倍以上に拡大することを目指すほか、権利行使期間(付与決議後2年~10年)の見直しも検討される可能性がある。ただし、本改正は「ベンチャー企業」のみが対象となる(詳細は本号7頁参照)。
三角合併、業績連動給与を緩和する案が浮上
31年改正における組織再編税制、役員給与税制の見直し
各省庁の平成31年度税制改正要望が出揃い、これから年末に向け税制改正議論が本格化することになるが、同年度改正では組織再編税制と役員給与税制の緩和がテーマとなることが本誌取材により判明した。
組織再編税制では、三角合併の際に“間接100%親会社”の株式を対価とするケースも税制適格再編の対象にすることが検討される。この改正が実現すれば、上場会社の孫会社の組織再編が容易となる。役員給与税制では、平成30年度税制改正で算定基礎となる指標に株価等が追加されるなど見直しが行われたにもかかわらず利用者数が伸びていない業績連動給与の「適正手続要件」の緩和が検討される。具体的には、指名委員会等設置会社の報酬委員会のメンバーに業務執行役員がいたとしても損金算入を認めることなどが議論される模様だ。また、ストックオプションの税制適格要件の緩和も検討される方向となっている(本号7頁参照)。
組織再編税制の見直し
現行組織再編税制で適格再編と認められている三角合併(図1参照)では、合併親法人株式(直接の100%親会社の株式)のみを合併対価として利用することができる(法法2十二の八)。
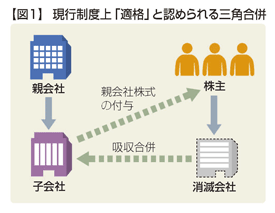
ただ、このように対価が100%親会社株式に限定されていることにより、三角合併を行うことが困難となるケースがある。
例えば上場会社である持株会社A社(親会社)の下に事業会社B社(子会社)がぶら下がっており、さらにその下に事業会社C社(孫会社)がぶら下がっているとする。この場合、孫会社であるC社が自社を存続会社とする税制適格の三角合併を行おうとすれば、C社は消滅会社の株主に対し、親会社であるB社の株式を付与するしかない。しかし、B社は上場会社ではないためその株式には流動性がないことから、消滅会社の株主は合併の対価がB社株式であることに納得しないだろう。そこで平成31年度税制改正では、上場会社である親会社A社(C社にとっての“間接100%親会社”)の株式を三角合併の対価として認める案(図2参照)が検討される。
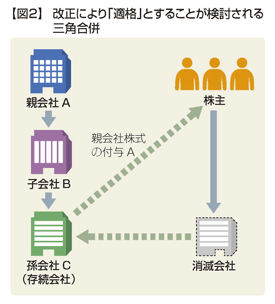
現行制度の下で孫会社が親会社の株式を対価とする三角合併を行うためには、子会社B社が孫会社C社の株式を親会社A社に現物分配し、A社の直下にC社をぶら下げるという手法をとることが考えられる(図3参照)。これにより、C社は三角合併においてA社株式を合併の対価として使えるようになるとはいえ、はじめから孫会社が親会社の株式を対価とする三角合併を認めてしまえば、このような手続き(現物分配)を省略することができるようになるというメリットもある。
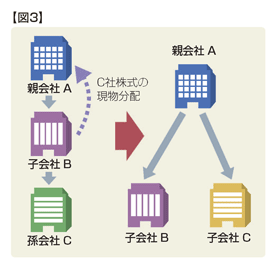
平成18年の会社法の創設時に“合併対価の柔軟化”として、吸収合併等の際には、存続会社の株式を交付せずに「金銭その他の財産」を交付することが認められ、これにより三角合併が解禁されたが、企業側からは三角合併が海外企業による日本企業買収に利用されることを懸念する声が相次ぎ、その実施が会社法施行日の1年後に延期されたという経緯がある。この延期期間を利用し、買収防衛策を導入する会社が相次いだ。しかしそれから10年余りを経て、現在は買収防衛策の廃止に踏み切る企業が相次ぐなどコーポレートガバナンスに関する考え方は一変している。また、好景気による株高ということもあり、株式を利用した組織再編の柔軟化に反対する声は産業界からは聞こえてこない。また、近年はスピンオフ税制や自社株対価TOBの導入など組織再編絡みの大胆な税制措置が相次いで実現していることからすると、“間接100%親会社”株式を対価とする合併を適格再編とする本改正が実現する可能性も決して低くはないだろう。
なお、三角合併と同じ税制は、分割、株式交換にも設けられている(法法2条十二の十一、十二の十七)ため、合併のみならず、分割や株式交換についても同様の議論が行われることになるものとみられる。
役員給与税制の見直し
平成29年度税制改正では、従来の利益連動給与が「業績連動給与」へと名称変更された上で、支給額の算定方法の基礎とすることができる指標に株価等が追加されたところだが、業績連動給与の普及はそれほど進んでいない(本誌704号5頁③参照)。その原因の1つと考えられるのが、詳細な開示要件と適正手続要件だ。
特に適正手続要件については、企業側から「厳しすぎる」との指摘が多い。例えば、指名委員会等設置会社に対しては、「報酬委員会(……業務執行役員が……委員になっているものを除く。)が決定」との要件(法法34条①三イ(2))が課されている。すなわち、たとえ報酬委員会のメンバーの過半数が社外取締役であったり、報酬委員会の委員長が社外取締役であったりしても、一人でも業務執行役員(業務執行を行う取締役や執行役など)(法法34①三)が報酬委員会のメンバーに入っていれば適正手続要件を満たせず、業績連動給与は損金算入できない。
同様の問題は、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社においても起こり得る。平成27年6月1日に導入されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①が、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社に対し、取締役会の独立性・客観性、説明責任を強化する手法の一つとして任意の報酬委員会(報酬諮問委員会)の導入を例示して以来、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社でも報酬諮問委員会を導入するところが増えているが(2018年7月31日現在、東証一部上場会社の34.9%(前年31.7%)が導入)、上記法法34条①三イ(2)同様、この報酬諮問委員会についても、一人でも業務執行役員がメンバーに入っていれば、適正手続要件を満たせないこととなるからだ(法令69条⑮三)。今年6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンスコードの補充原則4-10①では、報酬諮問委員会の設置が従来より強く求められていることから、今後報酬諮問委員会を設置する監査等委員会設置会社や監査役会設置会社が益々増えることが予想される。そうなれば、この要件を問題視する声が強まることになるだろう。
そもそもこの「……業務執行役員が……委員になっているものを除く」との要件は、役員給与税制が大幅に見直された平成18年度税制改正から変わっていない。しかし、見直しから12年が経過し、業績連動給与の重要性は当時とは比べ物にならないほど高まっている。これは、改訂コーポレートガバナンスコードで「中長期的な業績と連動する報酬の割合……を適切に設定すべきである」(補充原則4-2①)とされたほか、最近公表された金融庁のディスクロージャーワーキング報告でも、企業価値の向上に向けた経営陣のインセンティブとして業績連動報酬の重要性が再認識されていることからも分かる。
平成29年度税制改正で「非同族法人の100%子法人」に係る要件が緩和されたことを除き特段の見直しは行われていない適正手続き要件は、そろそろ見直しのタイミングに来ていると言えそうだ。
また、業績連動給与と同じくインセンティブ報酬の一種であるストックオプションの税制適格要件の見直しも検討される方向。
具体的には、権利行使価額を現行の年間1,200万円から2倍以上に拡大することを目指すほか、権利行使期間(付与決議後2年~10年)の見直しも検討される可能性がある。ただし、本改正は「ベンチャー企業」のみが対象となる(詳細は本号7頁参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















