解説記事2018年09月24日 【最新判決研究】 貸家・貸家建付地の「一時的空室」が評価に及ぼす影響(2018年9月24日号・№756)
最新判決研究
貸家・貸家建付地の「一時的空室」が評価に及ぼす影響
大阪高裁平成29年5月11日判決(平成28年(行コ)第329号)
大阪地裁平成28年10月26日判決(平成27年(行ウ)第238号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告、控訴人)は、甲の死亡により、甲を単独で相続し(以下「本件相続」という。)、平成22年9月24日、本件相続に係る相続税の申告書を法定申告期限内に提出した(以下「本件申告」という。)。本件相続に係る相続財産には、8棟の家屋(以下「本件各家屋」という。)及び本件各家屋の敷地を含む土地(以下「本件各土地」という。)が含まれていた。本件各家屋は、いずれも賃貸用の建物であり、本件各土地は、大部分が本件各家屋の敷地である。
本件各家屋の各室は、建物の構成部分である隔壁、扉層(天井及び床)等によって他と完全に遮断され、独立して賃貸の用に供することができるものであり、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)が定める各独立部分に該当する(以下「本件各独立部分」という。)。本件各独立部分の本件各家屋ごとの部屋数等は、1棟9室ないし43室であり、8棟全部で193室になる。また、本件各独立部分の本件相続前後における賃貸状況は、193室のうち73室が空室となっており(以下「本件各空室部分」という。)、本件各空室部分の空室期間は、最短が5月、最長が59月となっている。
(2)Xは、本件申告後、平成23年8月19日、所轄税務署長に対し、貸家につき貸家評価になっていなかったこと等を理由にして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。所轄税務署長は、平成25年3月22日、本件の相続税を増額する更正等(以下「当初更正等」という。)をするとともに、本件更正請求について、更正をすべき理由がない旨の通知(以下「当初通知」という。)をした。その後、Xは、当初更正等及び当初通知に対し異議申立てをしたが、所轄税務署長は、平成25年3月22日から同年11月27日にかけて、増額・減額更正等を行い、当初通知については、記載内容に誤りがあったということで取り消したが、本件更正請求に対して改めて理由がない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。Xは、審査請求を経て、平成27年7月22日、国(被告、被控訴人)に対し、本件通知の取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の争点は、本件各家屋及び本件各土地の価額、具体的には、本件各家屋に係る賃貸割合が、当該各価額にどのように影響するかである。
2 国の主張 (1)評価通達93及び26において、貸家及び貸家建付地の評価に当たり、借家権割合を乗じた計算により減額するものとされているのは、土地上の建物が借家権の目的となっている場合、当該建物賃貸借契約の更新拒絶等が制限されること、借家人が、建物の引渡しを受けたときは、対抗要件を具備すること等の借家権に基づく制約により、貸家及び貸家建付地の経済的価値が低下することを考慮したものである。よって、評価通達26本文(2)にいう「課税時期において賃貸されている」とは、相続税の課税時期である相続開始時において現に借家権の目的となっていることを指す。評価通達26(注)2は、課税時期にたまたま一時的に空室が生じている場合に、評価通達26の例外的な取扱いを定めるものにすぎない。
(2)課税時期において現に賃貸されていない独立部分が一時的空室部分に該当するかについては、当該独立部分が、①課税時期前に継続的に賃貸されてきたものか否か、②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたか否か、③空室の期間中、他の用途に供されていないか、④空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったか否か、⑤課税時期後の賃貸が一時的なものでないかなどの事実関係から判断すべきであり、課税通達26(注)2の「一時的」という文言に照らせば、上記④の賃貸されていない期間の長短が、特に重要な考慮要素となるものといえる。本件各空室部分は、いずれも、賃貸されていない期間が長期に及んでいるから、一時的空室部分に該当しない。
3 Xの主張 (1)評価通達26(注)2は、評価通達26の内容を同法22条に適合させるために、新たに規定されたものであり、貸家が、課税時期の前後を通じて継続的に賃貸業務の目的に供され、収益資産としての実態を失わず維持されている場合には、当該貸家に係る各独立部分のうち、課税時期において空室となっている部分も、課税時期において賃貸されている各独立部分に含めるべき旨を定めたものと解すべきである。
(2)そうすると、貸家に係る各独立部分が一時的空室に該当するかは、当該貸家に、自用の建物ではなく収益資産としての用途に供され、貸家として評価すべき実態があるかという観点から判断すべきであり、具体的には、①建物が建築された目的、②空室となった事情とそれまでの間の利用状況、③前賃借人の退去後、新たな賃借人の募集に着手した時期やその方法などの、賃貸業務の用に供するための努力の有無及び程度、④空室となった以降における当該空室部分の利用状況等を、総合的に考慮して判断すべきである。当該独立部分が賃貸されていない期間の長短は、一時的空室部分該当性を判断するための、重要な考慮要素であるとはいえない。
本件において、①本件各家屋は、賃貸用マンションとして建設され、②本件各空室部分は、いずれも借家人側の事情によって空室となったが、賃貸以外の目的に供されたことはなく、③甲及びXは、本件各家屋の建築以降、課税時期の前後を通じて、本件各係争家屋(本件各独立部分)の賃借人を継続的に募集するなどしており、④本件相続後も、本件各係争家屋を賃貸業務の用に供していることなどからすると、課税時期において、本件各係争家屋には、自用の建物ではなく、貸家として評価すべき実態がある。
三、一審判決要旨
請求棄却。 (1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているが、財産の価額を客観的かつ適正に把握することは必ずしも容易なことではなく、また、納税者ごとに財産の評価の方法が異なることは公平の観点から好ましくないことから、課税実務上、国税庁長官が発した通達である評価通達に基づいて、相続により取得した財産の価額の評価がされているところである。このような課税実務は、評価通達に定められた評価方式が当該財産の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであると認められる場合においては、租税法律関係の確定に際して求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の適正な履行の確保に資するものとして、同法22条の規定の許容するところであると解される。
(2)ア 評価通達93及び26本文が貸家及び貸家建付地について、所要の減額を認めた趣旨は、借家権の目的となっている建物の借家人は当該建物に対する権利を有するとともにその敷地についても借家権に基づいて建物の利用の範囲内である程度の支配権を有しているところ、賃貸人は、自己使用の必要性等の正当の事由がある場合を除き、賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約の申入れをしたりすることができないから、借家権を消滅させるためには立退料の支払を要することになること、借家人は、建物の引渡しを受けたときは、その後その建物について物権を取得した者に対し借家権の効力を対抗することができるから、建物に借家権を付着させたままで建物及びその敷地を譲渡する場合には、その譲受人は、建物及びその敷地の利用について制約を受けること等から、上記の建物及びその敷地の経済的価値が、借家権の目的となっていない建物やその敷地に比べて低くなることを考慮したことにあると解される。
イ もっとも、継続的に賃貸の用に供されている独立部分が課税時期にたまたま賃貸されていなかったような場合にまで当該独立部分を賃貸されていないものとして賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らして必ずしも実情に即したものとはいえない。
そこで、評価通達26(注)2は、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が継続的に賃貸されていたにもかかわらず課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる場合には、例外的に当該独立部分を賃貸されている独立部分と同様に取り扱うこととしたものと解される。
このような評価通達の趣旨に照らせば、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において、当該独立部分が評価通達26(注)2の一時的空室部分といえるためには、当該独立部分の賃貸借契約が課税時期前に終了したものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し、現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど、課税時期前後の賃貸状況等に照らし実質的にみて課税時期に賃貸されていたと同視し得ることを要するというべきである。
ウ 以上のとおり、評価通達93並びに26本文及びその(注)2が、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋について、当該独立部分が課税時期において現に賃貸されていること又は実質的にみて賃貸されていたと同視し得る独立部分の割合(賃貸割合)に応じた減額を認めていることは、家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約があると評価できるか否かに着目するものであり、貸家及び貸家建付地の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであるということができる。
エ これに対し、Xは、貸家に空室が生じた場合に、賃貸割合が減少し、貸家及び貸家建付地の価額が上昇することは、相続税法22条に反する旨主張する。しかしながら、評価通達26本文は、上記アのとおり、家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約が現にあるかを基準としているものといえるところ、評価通達26(注)2はその注記の形式で規定されており、評価通達26本文で定められた取扱いとの関係で、あくまでも例外的な措置として位置付けられていると解されること及びその規定内容をみても、家屋の各独立部分につき、当該部分が継続的に賃貸されていたことを前提としつつ、課税時期において賃貸されていなかったことが「一時的」なものであることを要件としていることに照らせば、Xが主張するように、評価通達26(注)2が、評価通達26本文と異なり、家屋全体の用途から、当該家屋の各独立部分の減価の要否を問題とする趣旨であると解することは、評価通達26の解釈として一貫性に欠けるものであり、文言に照らしても無理があるといわざるを得ない。したがって、評価通達26(注)2は、家屋の独立部分ごとに、賃貸されていなかった期間が一時的であり、実質的にみて借家権の目的となっていると同視し得るかを基準として、一時的空室部分該当性を判断する旨予定しているものと解すべきである。
(3)本件各空室部分についてみると、本件各空室部分が賃貸されていない期間は最も短い場合でも5か月であり、本件各空室部分について、本件相続開始前に賃貸借契約が終了した後も引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在したにもかかわらず上記の期間新たな賃貸借契約が締結されなかったことについて合理的な理由が存在したなどの事情は認められず、むしろ、本件各家屋の賃借人を継続的に募集していたというXの主張を前提とすれば、そのような募集状況にあったにもかかわらず5か月も賃貸されていないことから、上記のような事情はなかったものと推認される。したがって、本件各空室部分は、本件相続税の課税時期に賃貸されていたと同視することはできず、一時的空室部分に該当しない。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却(請求棄却)。
1. 当裁判所も、Xの請求は理由がないと判断する。その理由は、後記のとおり補足するほかは、原判決のとおりであるから、これを引用する。
2. Xは、①原判決は、評価通達26(注)2の趣旨を誤解していること、②原判決の立論は、貸家に係る空室部分の実態を考慮せずに、実質的には単に、賃貸されていない期間の長短のみをもって、一時的空室部分該当性を判断しているにすぎないこと、③一時的空室部分該当性は、当該貸家に係る空室部分が空室となった以降も「収益資産としての実態を失っていないと認めるに足りる客観的事実の有無」により判断すべきであることを指摘し、本件各空室部分は、課税時期において収益資産としての実態を失っていないから、いずれも一時的空室部分に該当すると主張するが、以下のとおり理由がない。
(1)上記①(評価通達の趣旨)について Xは、評価通達26の改正に関する説明文書(以下「企画官情報」という。)の記載を基に、原判決の判断は、相続税法22条に反する違法なものであると主張する。
この点、Xがその主張の根拠とする企画官情報には、「アパート等に現に借家人が存在している場合には、その借家人の有する権利は敷地全体に及ぶと考えられることから、このような一部に空室のあるアパート等については、入居者のいないアパートや一戸建ての貸家と異なり、借家人の存在がその敷地全体の価格形成において相当の減価要素となり得る場合もある」と記載されている。しかし、この部分は、その後の記載も併せて理解すれば、貸家建付地上の貸家に一時的空室部分が生じている場合に、空室部分を賃貸割合の算定において考慮できる場合があること(課税時期においても賃貸されていたものと取り扱うことができること)の理由を説明したにすぎない。Xは、上記記載を捉えて、アパート等の一部に空室が生じた場合でも、他の独立部分に現に借家人が存在する以上、当該空室部分及びこれに係る敷地の評価額に影響はないから、貸家及び貸家建付地としての減額を行うべきであると主張するが、上記記載は、Xの主張を裏付けるものではない。むしろ企画官情報には、評価通達26(注)2の趣旨につき、「建物の全部又は一部が、貸し付けられているかどうかについては、課税時期における現況に基づいて行うのが原則である」が、「継続的に賃貸の用に供されているような場合について、原則どおり賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らし、必ずしも実情に即したものとはいえない」、「そこで、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で…アパート等の各独立部分の一部が課税時期において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして取り扱って差し支えないこととした」と記載されており、これによれば、アパート等の各独立部分につき、当該部分が継続的に賃貸されていたことを前提としつつ、課税時期において賃貸されていなかったことが一時的なものであることを要件として、例外的に貸家建付地としての減額を行うことが説明されているのであるから、このような説明は、もはやXの上記主張と相容れないものである。
(2)上記②(原判決の判断基準)について Xは、単に空室期間の長短のみをもって一時的空室部分該当性を判断した原判決は明らかに誤っていると主張する。
しかし、相続財産につき、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行うか否かは、課税時期において当該財産が現実に賃貸されているか否かを基準に判断すべきであって、現実に賃貸されていない場合には、借家権が存在することに伴う種々の制約による経済的価値の低下がない以上、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行わないのが原則であり、課税時期に現実に賃貸されていないにもかかわらず、一時的空室部分として評価して賃貸されているものに含めることとして差し支えないとする評価通達26(注)2の定めは例外的な取扱いを定めたものにすぎない。そして、評価通達26(注)2が「「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない」と定めるとおり、課税時期において賃貸されていなかったことが「一時的」なものであることを要件としていることからすると、上記例外的な取扱いが認められるか否かを判断するに当たっては、賃貸されていない期間(空室期間)が重要な要素となることは明らかである。
そうすると、一時的空室部分該当性の判断に当たっては、現実の賃貸状況、取り分け、空室期間の長短を重要な要素として考慮しなければならないのであって、これを考慮せずに、本件各空室部分が「継続的に賃貸の用に供されている」状態にあるという理由のみで上記例外的な取扱いを認めることはできない。また、本件各空室部分の空室期間は、最も短い場合でも5か月であり、「例えば1か月程度」にとどまらずに、むしろ長期間に及んでいるといえるから、「一時的」なものであったとはいえない。
(3)上記③(X主張の判断基準)について Xは、不動産の取引実態、すなわち、アパート等の売買取引においては、空室率が高い収益物件は、賃料収入も相対的に少ないから売買価格は低下すること等から、一時的空室部分該当性は、「収益資産としての実態を失っていないと認める客観的な事実の有無」により判断すべきであると主張する。
この点、Xは、「収益資産としての実態」の内容につき、具体的には、賃貸借契約が終了した後も、引き続き賃借人の募集を行い、何時にても新たな賃借人が入居することができるように当該空室部分の保守・管理を行い、不動産所得を生ずべき業務の用に供している事実が認められる場合であると主張する。しかし、評価通達上、課税時期において現実に賃貸されていない場合には、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行わないのが原則であり、課税時期に現実に賃貸されていないにもかかわらず、一時的空室部分と評価して、賃貸されているものに含めることに差し支えはないとする評価通達26(注)2は例外的な取扱いを定めたものにすぎない。そして、一時的空室部分該当性の判断に当たっては、単に賃貸用建物として建築されたか否かという事情のみならず、現実の賃貸状況をも考慮すべきであるところ、評価通達26(注)2の文言や趣旨を考慮すると、本件各空室部分につき、賃貸借契約が終了した後も引き続き賃借人の募集を行い、何時にても新しい賃借人が入居できるように保守・管理が行われていたとしても、それだけで直ちに一時的空室部分に該当するといえないことは明らかである。
五、解説
はじめに 本件は、相続財産である貸家及び貸家建付地の相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。当該「時価」が講学上「客観的交換価値」であると解されているにしても、当該「客観的交換価値」が一義的に明確でないため、実務上、評価通達の定めに依存することになり、当該定めに基づく課税処分が法廷で争われる場合には、本件各判決を含め、多くの裁判例においては、当該定めの合理性を安易に(?)容認し、当該課税処分の適法性を容認することになる。
ところで、平成27年以降の相続税の増税もあって、相続税対策として、自己が所有する土地(宅地)に銀行から借金してアパートを建てることがもてはやされている。それが度が過ぎると(現実にそうなっているのであるが)、そのアパートは空室が多くなって、採算が合わなくなり、相続税対策としても逆効果にもなる。その場合には、本来の「客観的価値」の意義からすると、そのアパートの価値(客観的交換価値)は下落することになるはずである。
しかしながら、前述の評価通達の定めに従うと、空室が多くなればなるほど(採算が合わなくなればなるほど)、そのアパートと敷地(貸家建付地)の評価額が高くなるのである。このようなことは、「客観的交換価値」の本質論に照らすと納得し難いのであるが、法廷を含めた「時価」の解釈論に従えば、納得できない方が間違っていることになる。
ともあれ、近年、相続税対策の結果、アパートの空室急増が社会問題化している折、評価通達が定める評価方法の是非を検討する題材として、本件を取り上げることとした。
1 相続税法上の「時価」と評価通達との関係 (1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。そして、本来、国税庁部内の行政命令である(注1)評価通達は、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(同通達1(2))と定めている。
この前段の「……通常成立すると認められる価額」は、客観的交換価値又は客観的交換価額と称せられ、既に、学説、判例においても、「時価」の意義として容認されている。しかし、「客観的交換価値」であると称しても、それが一義的に明確でないことは、「時価」と同じである。それでは、評価通達が行政命令として各財産の価額を統一しようとする機能を果たせないことになる。
そこで、評価通達は、上記客観的交換価値の具体的な取扱いとして、前述のように、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定め、課税上の評価の統一(ひいては課税の公平)を図るため、各財産の価額を画一的に定めている。例えば、本件で問題となっている貸家建付地の評価の基となる市街化の宅地の価額は、路線価方式(評基通11、14)によって評価されるが、その路線価は、一連の宅地が面している路線ごとに、当該路線に面している標準地の価額を概ね公示価格水準の8割によって評価されている。この場合の評価基準日は、公示価格と同様、その年の1月1日である。
(2)このような路線価方式による宅地の価額は、当該路線に面している標準的な宅地についての1月1日現在で評価されているものであるから、標準価額としての性格を有するものである(注2)。そのため、実際に相続等(例えば、その年の12月末の相続等)によって取得した宅地の価額(客観的交換価値)は、路線価方式によって算定される標準価額と乖離することはあり得ることである(注3)。そして、このような乖離が著しくなり当該標準価額をもって評価することが不適当になることに備え、評価通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている(注4)。
この評価通達6項に関しては、判例においても、評価通達の定めに一般的合理性が認められる場合であっても、当該事案において当該定めを適用し難いと認められる「特別の事情」が認められるときには、当該財産について個別に評価できることを認めている(注5)。
本件においては、主として、本件各家屋の敷地となっている本件各土地の価額について評価通達26項を適用して評価することの適否が争われたものである。この場合、同通達の規定の適否よりも、同通達に定める「一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の解釈(範囲)が中心に争われることになった。もっとも、評価通達26項の規定の是非であれ、当該規定の特定の文言の解釈(適用)であれ、それらの規定によって評価した本件各土地の評価額が、本件各土地の「客観的交換価値」と著しく乖離するようであれば、当該評価額が標準価額であるが故に、本件各土地の価額を個別に評価しなければならないという結論(道理)を導くことになる。よって、次に評価通達26項とそれに関連する93及び94項の内容等について確認する必要がある。
2 貸家・貸家建付地の評価 (1)まず、評価通達93項は、「貸家の価額は、次の算式により評価した価額によって評価する。」と定め、次の算式を示している。
(算式)
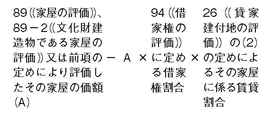
この場合、評価通達89項は、「家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(〈略〉)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。」と定め、別表1は、当該倍率を1.0と定めている。また、評価通達94項は、「借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。」と定めている。また、上記の算式の骨子は、次のとおりである。

上式の借家権割合は、国税局長の定める割合によることになるが、現在、全国一律30%とされている。また、賃借割合は、次の算式による。
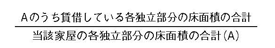
以上のように、貸家の評価には、家屋の価額、借家権割合及び賃借割合が重要な要素となっているが、賃借割合が後述する貸家建付地の評価において関連することになる。
(2)次に、評価通達26項は、貸家建付地の評価について、次のように定めている。
「貸家(94((借家権の評価))に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
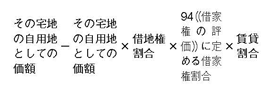
この算式における「借地権割合」及び「賃貸割合」は、それぞれ次による。
(1)「借地権割合」は、27((借地権の評価))の定めによるその宅地に係る借地権割合(同項のただし書に定める地域にある宅地については100分の20とする。次項において同じ。)による。
(2)「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下同じ。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による。
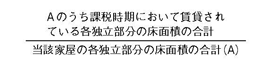
(注)1 上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいう。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。
2 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。」
(3)このような取扱いは、平成11年の評価通達の改正によって従前の取扱いが改められたものであるが、従前の取扱いでは、貸家建付地の価額を次の算式により評価することとしていた(平成11年改正前評基通26)。

上記取扱いを改正した趣旨について、国税庁の担当者は、次のように説明している(注6)。なお、控訴審判決では、企画官情報が引用されているが、国税当局の説明としては同旨のものである。
「貸家の中には、課税時期において、複数の者に対して住宅や店舗等として貸し付けている一棟のアパートやビルなど(以下「アパート等」という。)の一部に賃貸の用に供されていない部分があるものがある。このような貸家の敷地である貸家建付地の評価方法は、上記の考え方に基づき、これまで実務上、賃貸されている部分の床面積の割合により、借家人の有する敷地に対する支配権に相当する金額を算定して、これを自用地としての価額から控除して評価していた。そこで、従来からの実務上の取扱いを明らかにするとともに、①「借家権の目的となっている家屋」とは、現実に貸し付けられている家屋をいうと解すべきであるから、たとえ、その家屋がもっぱら賃貸用として建築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がなく、したがって、貸家建付地としての減価を考慮する必要がないこと、また、②この家屋がアパート等であって、その一部について、課税時期において現実に貸し付けられていない部分がある場合には、当該現実に貸し付けられていない部分に対応する敷地部分については、減額を行わないこととの原則を明らかにし、課税時期におけるその建物のうち現実に貸し付けられている部分の割合を賃貸割合として定め、次の算式により、貸家建付地の価額を求めることとしているのである。」
(4)また、現行の取扱い(注の2)では、本件でも問題とされているのであるが、「賃貸されている各独立部分」には、「課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」を含むこととしているところ、その趣旨について、国税庁担当者は、次のように説明している(注7)。
「ところで、その建物の全体又は一部が、貸し付けられているかどうかについては、課税時期における現況に基づいて行うのが原則であるが、アパート等においては、課税時期にたまたま一時的に空室が生じていることもある。このような空室が一時的に生じているような場合についても、原則どおり賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らし、必ずしも実情に即したものとはいえないと考えられる。そこで、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期において一時的に空室となっていたにすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして取り扱って差し支えないこととしている。
イ 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
ロ 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
ハ 賃貸されていない時期が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であること。
ニ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。」
3 最高裁平成10年2月26日判決の影響 (1)前記2で述べたように、現行の評価通達26項の取扱いの趣旨(正当性)について、国税庁の担当者は、従前の規定においても実務において課税してきた実務上の取扱いを明文化したものである旨説明している。しかし、平成11年に前述のような評価通達26項の改正が行われた契機としては、最高裁平成10年2月26日第一小法廷判決(税資230号851頁)(注8)があったことが挙げられる。同判決の事案では、相続財産である賃貸用新築マンション1棟の家屋と敷地(貸家建付地)の価額の評価(方法)が争われたものであるが、当該マンションが完成して募集に応じて入居が始まったところ、21室中4室入居したところで相続が開始した(当該相続税の法定申告期限頃には満室に近い状況にあった。)。
当該訴訟においては、当該マンション及び当該敷地の全部を貸家及び貸家建付地として評価すべきか、又は空室の17室とそれに対応する敷地部分は自用のものとして評価すべきかが争われた。原告は、当該マンション及び敷地の全体が貸家目的として建築・管理され、賃借人の募集が継続していて応募者に対して賃貸する義務を負っており、当該各物件を売買目的に変更するわけではないから、当該マンション及び敷地の全部を貸家・貸家建付地として評価すべき旨主張した。
(2)これに対し、一審の横浜地裁平成7年7月19日判決(税資213号134頁)は、当時の評価通達26項等の規定について、「これは、建物が借家権の目的となっている場合には、賃借人は一定の正当な理由がない限り、建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申し出ができないため、立退料等の支払いをしなければ、右借地権を幻滅させられず、また借家権が付いたままで貸家及びその敷地を譲渡する場合にも、譲受人は建物及び敷地利用が制約されることなどから、貸家建付地及び貸家の経済的価値がそうでない土地及び建物に比較して低下することを考慮したものと解され、合理的なものと認められる。」と判示し、相続税法上の「時価」の意義との関連について、「いまだ賃貸されていない部屋が存在する場合は、当該部屋の客観的交換価値はそれが借家権の目的となっていないものとして評価すべきである。」と判示し、上記の原告の主張に対しては、「たとえ右のような事情があっても、相続開始時点において、本件建物のうち4室以外は借家権の目的となっていない以上、残りの17室の相続開始時点における客観的交換価値は借家権のないものと認めざるを得ない」と判示し、原告の主張を排斥した。
この横浜地裁判決については、上訴審の東京高裁平成8年4月18日判決(税資216号144頁)及び前述の最高裁判決も、全面的に一審判決の理由を引用して、控訴棄却及び上告棄却をしている(注9)。そして、これらの判決の判旨が、平成11年の評価通達26項の改正の論拠となり、本件各判決の論拠にもなっている。
(3)ところで、財産の客観的な価値である客観的交換価値とは、当該財産の最有効利用の状態においてもたらされる価値にほかならない。本件で問題となっている賃貸用建物とその敷地の価値は、収益物件であるが故にそれらが最高の収益をもたらす場合に最も価値が高まることになるから、当該収益物件の最有効利用の状態すなわち満室の状態において最高の価値たる客観的交換価値が形成されるといえる。昨今のように、賃貸用建物が飽和状態となり、空室が増加しそれが恒常化することは、当該賃貸用建物と敷地の価値を低下させることになり、現にそれが不動産取引の常識となっている。
ところが、前掲各判決とそれを論拠とした現行の評価通達26項とその取扱いを是として本件各判決は、上記の実態とは真逆の論理を構築している。もっとも、本件各判決が判示するように、空室の場合には立退料等の支払義務は免れるであろうが、当該立退料等は、敷金を含む賃料全体の収益項目からの控除項目であるべきであって、当該賃貸建物等の価値の増加項目として位置付けるべきではないと考えられる。もちろん、賃貸用と称して長期間自用に使用する場合もあろうから、それは賃貸か自用かの事実認定の問題でもある。いずれにせよ、現行の評価通達26項の注書にいう「一時的」空室の期間を国税庁担当者がいう「1か月程度」ではなく、当該物件が賃貸用の実態があるか否かによって同通達を運用すべきであろう。
4 本件各係争土地等の評価 (1)本件においては、Xが本件相続によって、8棟の貸家とその敷地を取得した場合に、それらの相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。本件各家屋については、本件相続開始時に、延べ193室のうち73室(約37.8%)が空室となっており、それも最短で5月、最長が59月にわたって入居者がいなかったというものであるから、賃貸物件という点では相当収益力が低下していると言える。そうであれば、当該賃貸物件の価額を収益還元法によって評価すると、当然のことながら当該価額は相当に低下することになるはずである。
しかしながら、本件で問題になっている評価通達26、93及び94項の各取扱いを適用すると、空室が多いほど、評価額が高くなることになる。そのため、本件のような訴訟が提起されることになるが、この問題は、賃貸物件の価額の評価につき、空室による収益力の低下と立退料等の支払を免れるという将来債務の減少のいずれが影響力を有するかではある。また、評価通達26項注2が定める「一時的空室」とは、どの程度の期間を意味するかが問題となる。
(2)これらの問題につき、一審判決は、「家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約があると評価できるか否かに着目するものであり、貸家及び貸家建付地の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであるということができる。」と判示し、本件各家屋については、空室部分が5か月以上になることから「一時的空室」にも該当しない旨判示している。また、控訴審判決も、原判決を支持しつつ、国側が主張する「一時的」とは「1か月程度」という基準について、「本件各空室部分の空室期間は、最も短い場合でも5月であり、「例えば1か月程度」にとどまらず、むしろ長期間に及んでいるといえるから、「一時的」なものであったとはいえない。」と判示している。
このように、本件各判決は、貸家の空室が当該貸家等の価額に対する影響につき、国側が主張する立退料等という将来債務がないことのみを理由にそれを当該価額の増加要因としてとらえ、収益力の低下という賃貸物件の価値減少について一顧だにしないことに問題がある。もっとも、この問題は、前掲の最高裁平成10年2月26日判決の考え方に基づくものであるから、その考え方が否定されない限り、解決されることはないのかも知れない。
5 本件各判決の意義と問題点 以上のように、本件は、相続税対策等として賃貸アパート等の建設がもてはやされる一方、それが過熱して賃貸アパート等の空室問題と当該賃貸アパートの価値下落が深刻化している折、空室を多く抱える賃貸建物と当該敷地との相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。経済学的にいえば、賃貸建物という収益物件は、空室等によって賃料が減少すれば、収益価値(客観的交換価値)は下落することになるが、評価通達における評価では、貸家及び貸家建付地の価額(時価)は増加することになる。このことは、前掲最高裁平成10年2月26日判決によって論拠付けられていることであるが、本件各判決は、そのことを改めて確認したということで、意義を有する。
しかしながら、評価通達26項等の取扱いを是とし、賃貸物件につき、空室が増加し収益価値が下落するほど当該物件の「客観的交換価値」が増加するという本件各判決の論拠については、前述したように、納得できない点が多々あるところである。よって、本件で提起した諸問題が、今後、どのように議論されていくかを注目しておきたい。
(注1)国家行政組織法14条2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。
(注2)評価通達が定める各財産の価額の性格については、品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)120頁、同「財産(資産)評価の実務研究 第3回」季刊・資産承継2018年春号(No.3)192頁等参照。
(注3)前出(注2)各書参照。
(注4)評価通達6項の性格、運用のあり方等については、(注2)各書参照。
(注5)東京高裁昭和56年1月28日判決(税資116号51頁)、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、大津地裁平成9年6月23日判決(税資223号1046頁)、東京地裁平成16年3月2日判決(同254号順号9583)等参照。
(注6)北村厚編「平成30年版 財産評価基本通達逐条解説」(大蔵財務協会 平成30年)212頁。
(注7)前出(注6)213頁。
(注8)詳細については、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)785頁参照。
(注9)類似の裁判例として、東京地裁平成6年7月22日判決(行裁例集45巻7号1634頁)等参照。
貸家・貸家建付地の「一時的空室」が評価に及ぼす影響
大阪高裁平成29年5月11日判決(平成28年(行コ)第329号)
大阪地裁平成28年10月26日判決(平成27年(行ウ)第238号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告、控訴人)は、甲の死亡により、甲を単独で相続し(以下「本件相続」という。)、平成22年9月24日、本件相続に係る相続税の申告書を法定申告期限内に提出した(以下「本件申告」という。)。本件相続に係る相続財産には、8棟の家屋(以下「本件各家屋」という。)及び本件各家屋の敷地を含む土地(以下「本件各土地」という。)が含まれていた。本件各家屋は、いずれも賃貸用の建物であり、本件各土地は、大部分が本件各家屋の敷地である。
本件各家屋の各室は、建物の構成部分である隔壁、扉層(天井及び床)等によって他と完全に遮断され、独立して賃貸の用に供することができるものであり、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)が定める各独立部分に該当する(以下「本件各独立部分」という。)。本件各独立部分の本件各家屋ごとの部屋数等は、1棟9室ないし43室であり、8棟全部で193室になる。また、本件各独立部分の本件相続前後における賃貸状況は、193室のうち73室が空室となっており(以下「本件各空室部分」という。)、本件各空室部分の空室期間は、最短が5月、最長が59月となっている。
(2)Xは、本件申告後、平成23年8月19日、所轄税務署長に対し、貸家につき貸家評価になっていなかったこと等を理由にして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。所轄税務署長は、平成25年3月22日、本件の相続税を増額する更正等(以下「当初更正等」という。)をするとともに、本件更正請求について、更正をすべき理由がない旨の通知(以下「当初通知」という。)をした。その後、Xは、当初更正等及び当初通知に対し異議申立てをしたが、所轄税務署長は、平成25年3月22日から同年11月27日にかけて、増額・減額更正等を行い、当初通知については、記載内容に誤りがあったということで取り消したが、本件更正請求に対して改めて理由がない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。Xは、審査請求を経て、平成27年7月22日、国(被告、被控訴人)に対し、本件通知の取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の争点は、本件各家屋及び本件各土地の価額、具体的には、本件各家屋に係る賃貸割合が、当該各価額にどのように影響するかである。
2 国の主張 (1)評価通達93及び26において、貸家及び貸家建付地の評価に当たり、借家権割合を乗じた計算により減額するものとされているのは、土地上の建物が借家権の目的となっている場合、当該建物賃貸借契約の更新拒絶等が制限されること、借家人が、建物の引渡しを受けたときは、対抗要件を具備すること等の借家権に基づく制約により、貸家及び貸家建付地の経済的価値が低下することを考慮したものである。よって、評価通達26本文(2)にいう「課税時期において賃貸されている」とは、相続税の課税時期である相続開始時において現に借家権の目的となっていることを指す。評価通達26(注)2は、課税時期にたまたま一時的に空室が生じている場合に、評価通達26の例外的な取扱いを定めるものにすぎない。
(2)課税時期において現に賃貸されていない独立部分が一時的空室部分に該当するかについては、当該独立部分が、①課税時期前に継続的に賃貸されてきたものか否か、②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたか否か、③空室の期間中、他の用途に供されていないか、④空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったか否か、⑤課税時期後の賃貸が一時的なものでないかなどの事実関係から判断すべきであり、課税通達26(注)2の「一時的」という文言に照らせば、上記④の賃貸されていない期間の長短が、特に重要な考慮要素となるものといえる。本件各空室部分は、いずれも、賃貸されていない期間が長期に及んでいるから、一時的空室部分に該当しない。
3 Xの主張 (1)評価通達26(注)2は、評価通達26の内容を同法22条に適合させるために、新たに規定されたものであり、貸家が、課税時期の前後を通じて継続的に賃貸業務の目的に供され、収益資産としての実態を失わず維持されている場合には、当該貸家に係る各独立部分のうち、課税時期において空室となっている部分も、課税時期において賃貸されている各独立部分に含めるべき旨を定めたものと解すべきである。
(2)そうすると、貸家に係る各独立部分が一時的空室に該当するかは、当該貸家に、自用の建物ではなく収益資産としての用途に供され、貸家として評価すべき実態があるかという観点から判断すべきであり、具体的には、①建物が建築された目的、②空室となった事情とそれまでの間の利用状況、③前賃借人の退去後、新たな賃借人の募集に着手した時期やその方法などの、賃貸業務の用に供するための努力の有無及び程度、④空室となった以降における当該空室部分の利用状況等を、総合的に考慮して判断すべきである。当該独立部分が賃貸されていない期間の長短は、一時的空室部分該当性を判断するための、重要な考慮要素であるとはいえない。
本件において、①本件各家屋は、賃貸用マンションとして建設され、②本件各空室部分は、いずれも借家人側の事情によって空室となったが、賃貸以外の目的に供されたことはなく、③甲及びXは、本件各家屋の建築以降、課税時期の前後を通じて、本件各係争家屋(本件各独立部分)の賃借人を継続的に募集するなどしており、④本件相続後も、本件各係争家屋を賃貸業務の用に供していることなどからすると、課税時期において、本件各係争家屋には、自用の建物ではなく、貸家として評価すべき実態がある。
三、一審判決要旨
請求棄却。 (1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているが、財産の価額を客観的かつ適正に把握することは必ずしも容易なことではなく、また、納税者ごとに財産の評価の方法が異なることは公平の観点から好ましくないことから、課税実務上、国税庁長官が発した通達である評価通達に基づいて、相続により取得した財産の価額の評価がされているところである。このような課税実務は、評価通達に定められた評価方式が当該財産の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであると認められる場合においては、租税法律関係の確定に際して求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の適正な履行の確保に資するものとして、同法22条の規定の許容するところであると解される。
(2)ア 評価通達93及び26本文が貸家及び貸家建付地について、所要の減額を認めた趣旨は、借家権の目的となっている建物の借家人は当該建物に対する権利を有するとともにその敷地についても借家権に基づいて建物の利用の範囲内である程度の支配権を有しているところ、賃貸人は、自己使用の必要性等の正当の事由がある場合を除き、賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約の申入れをしたりすることができないから、借家権を消滅させるためには立退料の支払を要することになること、借家人は、建物の引渡しを受けたときは、その後その建物について物権を取得した者に対し借家権の効力を対抗することができるから、建物に借家権を付着させたままで建物及びその敷地を譲渡する場合には、その譲受人は、建物及びその敷地の利用について制約を受けること等から、上記の建物及びその敷地の経済的価値が、借家権の目的となっていない建物やその敷地に比べて低くなることを考慮したことにあると解される。
イ もっとも、継続的に賃貸の用に供されている独立部分が課税時期にたまたま賃貸されていなかったような場合にまで当該独立部分を賃貸されていないものとして賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らして必ずしも実情に即したものとはいえない。
そこで、評価通達26(注)2は、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が継続的に賃貸されていたにもかかわらず課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる場合には、例外的に当該独立部分を賃貸されている独立部分と同様に取り扱うこととしたものと解される。
このような評価通達の趣旨に照らせば、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において、当該独立部分が評価通達26(注)2の一時的空室部分といえるためには、当該独立部分の賃貸借契約が課税時期前に終了したものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し、現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど、課税時期前後の賃貸状況等に照らし実質的にみて課税時期に賃貸されていたと同視し得ることを要するというべきである。
ウ 以上のとおり、評価通達93並びに26本文及びその(注)2が、構造上区分された複数の独立部分からなる家屋について、当該独立部分が課税時期において現に賃貸されていること又は実質的にみて賃貸されていたと同視し得る独立部分の割合(賃貸割合)に応じた減額を認めていることは、家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約があると評価できるか否かに着目するものであり、貸家及び貸家建付地の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであるということができる。
エ これに対し、Xは、貸家に空室が生じた場合に、賃貸割合が減少し、貸家及び貸家建付地の価額が上昇することは、相続税法22条に反する旨主張する。しかしながら、評価通達26本文は、上記アのとおり、家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約が現にあるかを基準としているものといえるところ、評価通達26(注)2はその注記の形式で規定されており、評価通達26本文で定められた取扱いとの関係で、あくまでも例外的な措置として位置付けられていると解されること及びその規定内容をみても、家屋の各独立部分につき、当該部分が継続的に賃貸されていたことを前提としつつ、課税時期において賃貸されていなかったことが「一時的」なものであることを要件としていることに照らせば、Xが主張するように、評価通達26(注)2が、評価通達26本文と異なり、家屋全体の用途から、当該家屋の各独立部分の減価の要否を問題とする趣旨であると解することは、評価通達26の解釈として一貫性に欠けるものであり、文言に照らしても無理があるといわざるを得ない。したがって、評価通達26(注)2は、家屋の独立部分ごとに、賃貸されていなかった期間が一時的であり、実質的にみて借家権の目的となっていると同視し得るかを基準として、一時的空室部分該当性を判断する旨予定しているものと解すべきである。
(3)本件各空室部分についてみると、本件各空室部分が賃貸されていない期間は最も短い場合でも5か月であり、本件各空室部分について、本件相続開始前に賃貸借契約が終了した後も引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在したにもかかわらず上記の期間新たな賃貸借契約が締結されなかったことについて合理的な理由が存在したなどの事情は認められず、むしろ、本件各家屋の賃借人を継続的に募集していたというXの主張を前提とすれば、そのような募集状況にあったにもかかわらず5か月も賃貸されていないことから、上記のような事情はなかったものと推認される。したがって、本件各空室部分は、本件相続税の課税時期に賃貸されていたと同視することはできず、一時的空室部分に該当しない。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却(請求棄却)。
1. 当裁判所も、Xの請求は理由がないと判断する。その理由は、後記のとおり補足するほかは、原判決のとおりであるから、これを引用する。
2. Xは、①原判決は、評価通達26(注)2の趣旨を誤解していること、②原判決の立論は、貸家に係る空室部分の実態を考慮せずに、実質的には単に、賃貸されていない期間の長短のみをもって、一時的空室部分該当性を判断しているにすぎないこと、③一時的空室部分該当性は、当該貸家に係る空室部分が空室となった以降も「収益資産としての実態を失っていないと認めるに足りる客観的事実の有無」により判断すべきであることを指摘し、本件各空室部分は、課税時期において収益資産としての実態を失っていないから、いずれも一時的空室部分に該当すると主張するが、以下のとおり理由がない。
(1)上記①(評価通達の趣旨)について Xは、評価通達26の改正に関する説明文書(以下「企画官情報」という。)の記載を基に、原判決の判断は、相続税法22条に反する違法なものであると主張する。
この点、Xがその主張の根拠とする企画官情報には、「アパート等に現に借家人が存在している場合には、その借家人の有する権利は敷地全体に及ぶと考えられることから、このような一部に空室のあるアパート等については、入居者のいないアパートや一戸建ての貸家と異なり、借家人の存在がその敷地全体の価格形成において相当の減価要素となり得る場合もある」と記載されている。しかし、この部分は、その後の記載も併せて理解すれば、貸家建付地上の貸家に一時的空室部分が生じている場合に、空室部分を賃貸割合の算定において考慮できる場合があること(課税時期においても賃貸されていたものと取り扱うことができること)の理由を説明したにすぎない。Xは、上記記載を捉えて、アパート等の一部に空室が生じた場合でも、他の独立部分に現に借家人が存在する以上、当該空室部分及びこれに係る敷地の評価額に影響はないから、貸家及び貸家建付地としての減額を行うべきであると主張するが、上記記載は、Xの主張を裏付けるものではない。むしろ企画官情報には、評価通達26(注)2の趣旨につき、「建物の全部又は一部が、貸し付けられているかどうかについては、課税時期における現況に基づいて行うのが原則である」が、「継続的に賃貸の用に供されているような場合について、原則どおり賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らし、必ずしも実情に即したものとはいえない」、「そこで、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で…アパート等の各独立部分の一部が課税時期において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして取り扱って差し支えないこととした」と記載されており、これによれば、アパート等の各独立部分につき、当該部分が継続的に賃貸されていたことを前提としつつ、課税時期において賃貸されていなかったことが一時的なものであることを要件として、例外的に貸家建付地としての減額を行うことが説明されているのであるから、このような説明は、もはやXの上記主張と相容れないものである。
(2)上記②(原判決の判断基準)について Xは、単に空室期間の長短のみをもって一時的空室部分該当性を判断した原判決は明らかに誤っていると主張する。
しかし、相続財産につき、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行うか否かは、課税時期において当該財産が現実に賃貸されているか否かを基準に判断すべきであって、現実に賃貸されていない場合には、借家権が存在することに伴う種々の制約による経済的価値の低下がない以上、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行わないのが原則であり、課税時期に現実に賃貸されていないにもかかわらず、一時的空室部分として評価して賃貸されているものに含めることとして差し支えないとする評価通達26(注)2の定めは例外的な取扱いを定めたものにすぎない。そして、評価通達26(注)2が「「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない」と定めるとおり、課税時期において賃貸されていなかったことが「一時的」なものであることを要件としていることからすると、上記例外的な取扱いが認められるか否かを判断するに当たっては、賃貸されていない期間(空室期間)が重要な要素となることは明らかである。
そうすると、一時的空室部分該当性の判断に当たっては、現実の賃貸状況、取り分け、空室期間の長短を重要な要素として考慮しなければならないのであって、これを考慮せずに、本件各空室部分が「継続的に賃貸の用に供されている」状態にあるという理由のみで上記例外的な取扱いを認めることはできない。また、本件各空室部分の空室期間は、最も短い場合でも5か月であり、「例えば1か月程度」にとどまらずに、むしろ長期間に及んでいるといえるから、「一時的」なものであったとはいえない。
(3)上記③(X主張の判断基準)について Xは、不動産の取引実態、すなわち、アパート等の売買取引においては、空室率が高い収益物件は、賃料収入も相対的に少ないから売買価格は低下すること等から、一時的空室部分該当性は、「収益資産としての実態を失っていないと認める客観的な事実の有無」により判断すべきであると主張する。
この点、Xは、「収益資産としての実態」の内容につき、具体的には、賃貸借契約が終了した後も、引き続き賃借人の募集を行い、何時にても新たな賃借人が入居することができるように当該空室部分の保守・管理を行い、不動産所得を生ずべき業務の用に供している事実が認められる場合であると主張する。しかし、評価通達上、課税時期において現実に賃貸されていない場合には、貸家及び貸家建付地として所要の減額を行わないのが原則であり、課税時期に現実に賃貸されていないにもかかわらず、一時的空室部分と評価して、賃貸されているものに含めることに差し支えはないとする評価通達26(注)2は例外的な取扱いを定めたものにすぎない。そして、一時的空室部分該当性の判断に当たっては、単に賃貸用建物として建築されたか否かという事情のみならず、現実の賃貸状況をも考慮すべきであるところ、評価通達26(注)2の文言や趣旨を考慮すると、本件各空室部分につき、賃貸借契約が終了した後も引き続き賃借人の募集を行い、何時にても新しい賃借人が入居できるように保守・管理が行われていたとしても、それだけで直ちに一時的空室部分に該当するといえないことは明らかである。
五、解説
はじめに 本件は、相続財産である貸家及び貸家建付地の相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。当該「時価」が講学上「客観的交換価値」であると解されているにしても、当該「客観的交換価値」が一義的に明確でないため、実務上、評価通達の定めに依存することになり、当該定めに基づく課税処分が法廷で争われる場合には、本件各判決を含め、多くの裁判例においては、当該定めの合理性を安易に(?)容認し、当該課税処分の適法性を容認することになる。
ところで、平成27年以降の相続税の増税もあって、相続税対策として、自己が所有する土地(宅地)に銀行から借金してアパートを建てることがもてはやされている。それが度が過ぎると(現実にそうなっているのであるが)、そのアパートは空室が多くなって、採算が合わなくなり、相続税対策としても逆効果にもなる。その場合には、本来の「客観的価値」の意義からすると、そのアパートの価値(客観的交換価値)は下落することになるはずである。
しかしながら、前述の評価通達の定めに従うと、空室が多くなればなるほど(採算が合わなくなればなるほど)、そのアパートと敷地(貸家建付地)の評価額が高くなるのである。このようなことは、「客観的交換価値」の本質論に照らすと納得し難いのであるが、法廷を含めた「時価」の解釈論に従えば、納得できない方が間違っていることになる。
ともあれ、近年、相続税対策の結果、アパートの空室急増が社会問題化している折、評価通達が定める評価方法の是非を検討する題材として、本件を取り上げることとした。
1 相続税法上の「時価」と評価通達との関係 (1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。そして、本来、国税庁部内の行政命令である(注1)評価通達は、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(同通達1(2))と定めている。
この前段の「……通常成立すると認められる価額」は、客観的交換価値又は客観的交換価額と称せられ、既に、学説、判例においても、「時価」の意義として容認されている。しかし、「客観的交換価値」であると称しても、それが一義的に明確でないことは、「時価」と同じである。それでは、評価通達が行政命令として各財産の価額を統一しようとする機能を果たせないことになる。
そこで、評価通達は、上記客観的交換価値の具体的な取扱いとして、前述のように、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定め、課税上の評価の統一(ひいては課税の公平)を図るため、各財産の価額を画一的に定めている。例えば、本件で問題となっている貸家建付地の評価の基となる市街化の宅地の価額は、路線価方式(評基通11、14)によって評価されるが、その路線価は、一連の宅地が面している路線ごとに、当該路線に面している標準地の価額を概ね公示価格水準の8割によって評価されている。この場合の評価基準日は、公示価格と同様、その年の1月1日である。
(2)このような路線価方式による宅地の価額は、当該路線に面している標準的な宅地についての1月1日現在で評価されているものであるから、標準価額としての性格を有するものである(注2)。そのため、実際に相続等(例えば、その年の12月末の相続等)によって取得した宅地の価額(客観的交換価値)は、路線価方式によって算定される標準価額と乖離することはあり得ることである(注3)。そして、このような乖離が著しくなり当該標準価額をもって評価することが不適当になることに備え、評価通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている(注4)。
この評価通達6項に関しては、判例においても、評価通達の定めに一般的合理性が認められる場合であっても、当該事案において当該定めを適用し難いと認められる「特別の事情」が認められるときには、当該財産について個別に評価できることを認めている(注5)。
本件においては、主として、本件各家屋の敷地となっている本件各土地の価額について評価通達26項を適用して評価することの適否が争われたものである。この場合、同通達の規定の適否よりも、同通達に定める「一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の解釈(範囲)が中心に争われることになった。もっとも、評価通達26項の規定の是非であれ、当該規定の特定の文言の解釈(適用)であれ、それらの規定によって評価した本件各土地の評価額が、本件各土地の「客観的交換価値」と著しく乖離するようであれば、当該評価額が標準価額であるが故に、本件各土地の価額を個別に評価しなければならないという結論(道理)を導くことになる。よって、次に評価通達26項とそれに関連する93及び94項の内容等について確認する必要がある。
2 貸家・貸家建付地の評価 (1)まず、評価通達93項は、「貸家の価額は、次の算式により評価した価額によって評価する。」と定め、次の算式を示している。
(算式)
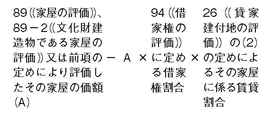
この場合、評価通達89項は、「家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(〈略〉)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。」と定め、別表1は、当該倍率を1.0と定めている。また、評価通達94項は、「借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。」と定めている。また、上記の算式の骨子は、次のとおりである。

上式の借家権割合は、国税局長の定める割合によることになるが、現在、全国一律30%とされている。また、賃借割合は、次の算式による。
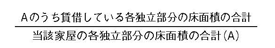
以上のように、貸家の評価には、家屋の価額、借家権割合及び賃借割合が重要な要素となっているが、賃借割合が後述する貸家建付地の評価において関連することになる。
(2)次に、評価通達26項は、貸家建付地の評価について、次のように定めている。
「貸家(94((借家権の評価))に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
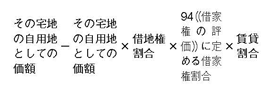
この算式における「借地権割合」及び「賃貸割合」は、それぞれ次による。
(1)「借地権割合」は、27((借地権の評価))の定めによるその宅地に係る借地権割合(同項のただし書に定める地域にある宅地については100分の20とする。次項において同じ。)による。
(2)「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下同じ。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による。
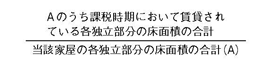
(注)1 上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいう。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。
2 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。」
(3)このような取扱いは、平成11年の評価通達の改正によって従前の取扱いが改められたものであるが、従前の取扱いでは、貸家建付地の価額を次の算式により評価することとしていた(平成11年改正前評基通26)。

上記取扱いを改正した趣旨について、国税庁の担当者は、次のように説明している(注6)。なお、控訴審判決では、企画官情報が引用されているが、国税当局の説明としては同旨のものである。
「貸家の中には、課税時期において、複数の者に対して住宅や店舗等として貸し付けている一棟のアパートやビルなど(以下「アパート等」という。)の一部に賃貸の用に供されていない部分があるものがある。このような貸家の敷地である貸家建付地の評価方法は、上記の考え方に基づき、これまで実務上、賃貸されている部分の床面積の割合により、借家人の有する敷地に対する支配権に相当する金額を算定して、これを自用地としての価額から控除して評価していた。そこで、従来からの実務上の取扱いを明らかにするとともに、①「借家権の目的となっている家屋」とは、現実に貸し付けられている家屋をいうと解すべきであるから、たとえ、その家屋がもっぱら賃貸用として建築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がなく、したがって、貸家建付地としての減価を考慮する必要がないこと、また、②この家屋がアパート等であって、その一部について、課税時期において現実に貸し付けられていない部分がある場合には、当該現実に貸し付けられていない部分に対応する敷地部分については、減額を行わないこととの原則を明らかにし、課税時期におけるその建物のうち現実に貸し付けられている部分の割合を賃貸割合として定め、次の算式により、貸家建付地の価額を求めることとしているのである。」
(4)また、現行の取扱い(注の2)では、本件でも問題とされているのであるが、「賃貸されている各独立部分」には、「課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」を含むこととしているところ、その趣旨について、国税庁担当者は、次のように説明している(注7)。
「ところで、その建物の全体又は一部が、貸し付けられているかどうかについては、課税時期における現況に基づいて行うのが原則であるが、アパート等においては、課税時期にたまたま一時的に空室が生じていることもある。このような空室が一時的に生じているような場合についても、原則どおり賃貸割合を算出することは、不動産の取引実態等に照らし、必ずしも実情に即したものとはいえないと考えられる。そこで、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期において一時的に空室となっていたにすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして取り扱って差し支えないこととしている。
イ 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
ロ 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
ハ 賃貸されていない時期が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であること。
ニ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。」
3 最高裁平成10年2月26日判決の影響 (1)前記2で述べたように、現行の評価通達26項の取扱いの趣旨(正当性)について、国税庁の担当者は、従前の規定においても実務において課税してきた実務上の取扱いを明文化したものである旨説明している。しかし、平成11年に前述のような評価通達26項の改正が行われた契機としては、最高裁平成10年2月26日第一小法廷判決(税資230号851頁)(注8)があったことが挙げられる。同判決の事案では、相続財産である賃貸用新築マンション1棟の家屋と敷地(貸家建付地)の価額の評価(方法)が争われたものであるが、当該マンションが完成して募集に応じて入居が始まったところ、21室中4室入居したところで相続が開始した(当該相続税の法定申告期限頃には満室に近い状況にあった。)。
当該訴訟においては、当該マンション及び当該敷地の全部を貸家及び貸家建付地として評価すべきか、又は空室の17室とそれに対応する敷地部分は自用のものとして評価すべきかが争われた。原告は、当該マンション及び敷地の全体が貸家目的として建築・管理され、賃借人の募集が継続していて応募者に対して賃貸する義務を負っており、当該各物件を売買目的に変更するわけではないから、当該マンション及び敷地の全部を貸家・貸家建付地として評価すべき旨主張した。
(2)これに対し、一審の横浜地裁平成7年7月19日判決(税資213号134頁)は、当時の評価通達26項等の規定について、「これは、建物が借家権の目的となっている場合には、賃借人は一定の正当な理由がない限り、建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申し出ができないため、立退料等の支払いをしなければ、右借地権を幻滅させられず、また借家権が付いたままで貸家及びその敷地を譲渡する場合にも、譲受人は建物及び敷地利用が制約されることなどから、貸家建付地及び貸家の経済的価値がそうでない土地及び建物に比較して低下することを考慮したものと解され、合理的なものと認められる。」と判示し、相続税法上の「時価」の意義との関連について、「いまだ賃貸されていない部屋が存在する場合は、当該部屋の客観的交換価値はそれが借家権の目的となっていないものとして評価すべきである。」と判示し、上記の原告の主張に対しては、「たとえ右のような事情があっても、相続開始時点において、本件建物のうち4室以外は借家権の目的となっていない以上、残りの17室の相続開始時点における客観的交換価値は借家権のないものと認めざるを得ない」と判示し、原告の主張を排斥した。
この横浜地裁判決については、上訴審の東京高裁平成8年4月18日判決(税資216号144頁)及び前述の最高裁判決も、全面的に一審判決の理由を引用して、控訴棄却及び上告棄却をしている(注9)。そして、これらの判決の判旨が、平成11年の評価通達26項の改正の論拠となり、本件各判決の論拠にもなっている。
(3)ところで、財産の客観的な価値である客観的交換価値とは、当該財産の最有効利用の状態においてもたらされる価値にほかならない。本件で問題となっている賃貸用建物とその敷地の価値は、収益物件であるが故にそれらが最高の収益をもたらす場合に最も価値が高まることになるから、当該収益物件の最有効利用の状態すなわち満室の状態において最高の価値たる客観的交換価値が形成されるといえる。昨今のように、賃貸用建物が飽和状態となり、空室が増加しそれが恒常化することは、当該賃貸用建物と敷地の価値を低下させることになり、現にそれが不動産取引の常識となっている。
ところが、前掲各判決とそれを論拠とした現行の評価通達26項とその取扱いを是として本件各判決は、上記の実態とは真逆の論理を構築している。もっとも、本件各判決が判示するように、空室の場合には立退料等の支払義務は免れるであろうが、当該立退料等は、敷金を含む賃料全体の収益項目からの控除項目であるべきであって、当該賃貸建物等の価値の増加項目として位置付けるべきではないと考えられる。もちろん、賃貸用と称して長期間自用に使用する場合もあろうから、それは賃貸か自用かの事実認定の問題でもある。いずれにせよ、現行の評価通達26項の注書にいう「一時的」空室の期間を国税庁担当者がいう「1か月程度」ではなく、当該物件が賃貸用の実態があるか否かによって同通達を運用すべきであろう。
4 本件各係争土地等の評価 (1)本件においては、Xが本件相続によって、8棟の貸家とその敷地を取得した場合に、それらの相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。本件各家屋については、本件相続開始時に、延べ193室のうち73室(約37.8%)が空室となっており、それも最短で5月、最長が59月にわたって入居者がいなかったというものであるから、賃貸物件という点では相当収益力が低下していると言える。そうであれば、当該賃貸物件の価額を収益還元法によって評価すると、当然のことながら当該価額は相当に低下することになるはずである。
しかしながら、本件で問題になっている評価通達26、93及び94項の各取扱いを適用すると、空室が多いほど、評価額が高くなることになる。そのため、本件のような訴訟が提起されることになるが、この問題は、賃貸物件の価額の評価につき、空室による収益力の低下と立退料等の支払を免れるという将来債務の減少のいずれが影響力を有するかではある。また、評価通達26項注2が定める「一時的空室」とは、どの程度の期間を意味するかが問題となる。
(2)これらの問題につき、一審判決は、「家屋の独立部分ごとに、借家権の目的となっていることに基づく制約があると評価できるか否かに着目するものであり、貸家及び貸家建付地の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであるということができる。」と判示し、本件各家屋については、空室部分が5か月以上になることから「一時的空室」にも該当しない旨判示している。また、控訴審判決も、原判決を支持しつつ、国側が主張する「一時的」とは「1か月程度」という基準について、「本件各空室部分の空室期間は、最も短い場合でも5月であり、「例えば1か月程度」にとどまらず、むしろ長期間に及んでいるといえるから、「一時的」なものであったとはいえない。」と判示している。
このように、本件各判決は、貸家の空室が当該貸家等の価額に対する影響につき、国側が主張する立退料等という将来債務がないことのみを理由にそれを当該価額の増加要因としてとらえ、収益力の低下という賃貸物件の価値減少について一顧だにしないことに問題がある。もっとも、この問題は、前掲の最高裁平成10年2月26日判決の考え方に基づくものであるから、その考え方が否定されない限り、解決されることはないのかも知れない。
5 本件各判決の意義と問題点 以上のように、本件は、相続税対策等として賃貸アパート等の建設がもてはやされる一方、それが過熱して賃貸アパート等の空室問題と当該賃貸アパートの価値下落が深刻化している折、空室を多く抱える賃貸建物と当該敷地との相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものである。経済学的にいえば、賃貸建物という収益物件は、空室等によって賃料が減少すれば、収益価値(客観的交換価値)は下落することになるが、評価通達における評価では、貸家及び貸家建付地の価額(時価)は増加することになる。このことは、前掲最高裁平成10年2月26日判決によって論拠付けられていることであるが、本件各判決は、そのことを改めて確認したということで、意義を有する。
しかしながら、評価通達26項等の取扱いを是とし、賃貸物件につき、空室が増加し収益価値が下落するほど当該物件の「客観的交換価値」が増加するという本件各判決の論拠については、前述したように、納得できない点が多々あるところである。よって、本件で提起した諸問題が、今後、どのように議論されていくかを注目しておきたい。
(注1)国家行政組織法14条2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。
(注2)評価通達が定める各財産の価額の性格については、品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)120頁、同「財産(資産)評価の実務研究 第3回」季刊・資産承継2018年春号(No.3)192頁等参照。
(注3)前出(注2)各書参照。
(注4)評価通達6項の性格、運用のあり方等については、(注2)各書参照。
(注5)東京高裁昭和56年1月28日判決(税資116号51頁)、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、大津地裁平成9年6月23日判決(税資223号1046頁)、東京地裁平成16年3月2日判決(同254号順号9583)等参照。
(注6)北村厚編「平成30年版 財産評価基本通達逐条解説」(大蔵財務協会 平成30年)212頁。
(注7)前出(注6)213頁。
(注8)詳細については、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)785頁参照。
(注9)類似の裁判例として、東京地裁平成6年7月22日判決(行裁例集45巻7号1634頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















