解説記事2018年12月03日 【税務マエストロ】 新たな「支払利子の損金算入制限規定」の導入について―平成31年度税制改正の展望―(2018年12月3日号・№765)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
新たな「支払利子の損金算入制限規定」の導入について
―平成31年度税制改正の展望―
#222 栗原宏幸(弁護士・税理士)
略歴 森・濱田松本法律事務所 弁護士・税理士。国際税務、税務紛争、タックス・プランニングに精通。広島県呉市出身。広島学院高校、東京大学法学部、東京大学法科大学院卒業。留学先の米国スタンフォード大学、ニューヨーク大学で国際税務を学ぶ。ニューヨーク大学の国際税務プログラムでは最優秀で表彰を受ける。M&A、ファイナンス等の知識・ノウハウを生かし、法務・税務ワンストップの総合的なアドバイスを得意とする。
1 はじめに 次の平成31年度税制改正では、全ての日本企業を適用対象とする新たな支払利子の損金算入制限規定の導入(現行の過大支払利子税制の改正)が見込まれている。本稿の執筆時点(2018年11月22日)では、まだ平成31年度税制改正大綱が公表されていないため、その全容は明らかでないが、本誌で解説する機会を得たので、導入の背景と想定される改正内容についてここで紹介する(脚注1)。
2 導入の背景 そもそもの発端は、OECDのBEPSプロジェクトである。BEPSプロジェクトでは、国際的租税回避行為への様々な対抗措置が提案されたが、その一つである行動計画4は、各国が利子の控除制限規定を設けることを提言している。
従前問題とされてきた利子控除の租税回避行為とは、グループ内の所得移転、例えば、インターカンパニー・ローンに基づく利子の支払いにより税率の高い国から低い国に所得を移転する、というプランニングであった(脚注2)。
このように従来の議論はグループ内の所得移転にフォーカスがあてられてきたが、BEPSプロジェクトの行動計画4は、第三者からの借入をも対象として利子の控除制限を規定することを提言している。すなわち、行動計画4は、多国籍企業を念頭に置いて、①第三者借入を高課税国で行うこと、②インターカンパニー・ローンによりグループ全体の第三者への支払利子の金額を超える支払利子の控除を行うこと、③第三者借入またはインターカンパニー・ローンを原資として非課税所得を得ること、といったケースを想定し、これらのスキームを利用した、行き過ぎた節税策を抑制することを提言している。
3 BEPSプロジェクト行動計画4の提言内容 以上を踏まえ、BEPSプロジェクト行動計画4は、各法人の純支払利子(支払利子-受取利子)は、原則として、EBITDA(脚注3)の10%~30%(具体的な割合は各国が決定する)を超える部分は所得から控除できない、という控除制限規定を導入することを提言している。
ただし、負債比率の大きい企業がその事業を妨げられないように、グループ全体の純支払利子/EBITDAの割合(グループ比率)が上述の原則的な割合よりも高い場合は、グループ比率を用いて控除限度額を算定することもできるとされている(脚注4)。
基準となるEBITDAは、これに代えてEBIT(Earnings Before Interest and Taxes)を用いることも可能とされているが、いずれの金額の計算上も、非課税所得(資本参加免税の適用を受ける配当所得等)はEBITDA又はEBITに含めるべきでないとされている。
4 損金算入制限規定の日本企業への影響 日本はこれまでもBEPSプロジェクトの提言内容に沿った税制改正を行ってきている(外国子会社からの損金算入配当に対する益金不算入措置の否定、タックスヘイブン対策税制の強化等)。この行動計画4についても、来年度の税制改正(平成31年度税制改正)に支払利子の損金算入制限規定の導入(現行の過大支払利子税制の改正)が盛り込まれることが見込まれている。
支払利子の損金算入制限規定がBEPSプロジェクト行動計画4の提言通りの内容で導入された場合、これまでは海外のグループ会社からの借入だけが対象であった損金算入制限が、国内金融機関を含む第三者借入をも対象とすることになる。現行の過大支払利子税制とBEPSプロジェクトの提言内容の比較については表1を参照頂きたい。
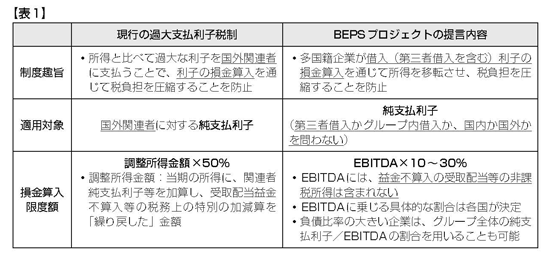
BEPSプロジェクト行動計画4の提言通りに法改正が行われた場合、当該改正が日本企業に対して与える影響としては、例えば以下のようなものが考えられる(脚注5)。
・負債比率の大きい企業、持株会社における税負担の増加 他国での導入状況を踏まえると、損金算入限度額はEBITDAの「30」%になる可能性が高い。昨今の低金利を踏まえると、一般には、日本企業の純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は低いように思われる。
もっとも、負債比率の大きい企業(設備投資が活発なインフラ系の企業や高いレバレッジをかけてM&Aを積極的に行っている企業等)においては、純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は否定できない。
また、グループの持株会社が第三者借入による資金調達を行っている場合、持株会社が子会社から受け取る配当は益金不算入であるから、当該配当の額は、損金算入制限の算定の基礎となるEBITDAに含まれず、その結果、純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性がある。
以上のようにして損金算入が制限されると、法人税の負担が増加し、利益を減少させることとなる。
この点、EBITDAの30%に代えてグループ比率(グループ全体の純支払利子/EBITDAの割合)を用いることが可能であれば、これらの企業も損金算入制限の適用を免れられる可能性があるが、グループ企業が多い場合にはグループ比率の算定の事務負担が問題になり得る。
・証券化取引への影響 実体のある日本企業については、上述の通り純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は一般に低いと考えられるが、いわゆる証券化取引(脚注6)においてはその影響を受ける可能性が高いと考えられる。
証券化取引においては、SPCの収益(原資産からの収益)と費用(その大半が支払利子)がほぼ同額となりSPCに余剰キャッシュフローが残らないように経済条件が設定されているケースが多いと考えられる。現行法では、そのようなケースではSPCに所得はないことから税負担は均等割等を除けば基本的に生じないが、純支払利子の損金算入がEBITDAの30%に制限された場合、SPCに課税所得が発生しこれによりSPCに法人税の税負担が生じる可能性があり、その結果、既存の経済条件を前提にするとSPCが資金ショートし、借入がデフォルトする可能性があると考えられる(次頁の表2参照)。

ただし、原資産からの収益が利子とみなされるものであれば(例えば原資産が住宅ローンや社債である場合)、純支払利子が0となり、損金算入制限規定の適用を受けず、改正による影響を受けない可能性がある。また、不動産の証券化の場合は、原資産に建物が含まれ、その減価償却費をEBITDAの計算上加算することができるため、EBITDAがキャッシュフローよりも大きくなり、減価償却しない原資産のケースと比べるとEBITDAの30%の制限にかかりにくいといえる。このように、一口に証券化取引といっても、損金算入制限規定の適用の見込みは原資産の内容によるといえよう。
5 想定される改正内容 (1)平成31年度税制改正で支払利子の損金算入制限規定を導入することは、既定路線となっている可能性が高い。一方で、上記4で説明したとおり、BEPSプロジェクト行動計画4の提言内容がそのまま導入された場合には、銀行取引その他の負債による資金調達を阻害する可能性が否定できない。そこで、提言内容をそのまま導入するのではなく、従前の実務を阻害しないよう必要な修正を加えて導入することが望ましいといえる。
なお、筆者の把握している限り、関係各省において、そのように適用場面を限定する方向で改正案が練られているようである。
(2)考えられる方向性の1つとして、「利子の受益者が利子について一定税率以上での課税を受けていないケースのみを、損金算入制限規定の適用とすること」が考えられる。このように、所得が外国で相応の課税権に服していること(又は服していないこと)を課税の要件としている例は比較法的に珍しいものではないと思われる。例えば、文脈や内容はやや異なるが、オランダの資本参加免税制度では、外国子会社株式からの配当、株式譲渡益について免税を得るためには、当該外国子会社が居住地国で10%以上の課税を受けていることが要件とされている(subject-to-taxtest)。
もっとも、このように利子の受益者側の事情を利子の支払者側の要件として設定することについては、支払者が要件を判定するために相応の困難・負担が生じることが見込まれる。銀行取引のような相対取引であれば過度な負担は生じないと考えられるが、社債のように不特定多数の債権者が想定される取引においては、受益者側の情報(しかも税負担に関する情報)を支払者が把握することには困難が伴うと考えられる。
また、導管取引等、規定の適用を免れる租税回避行為への対処も必要となろう。
(3)考えられる方向性としては、ほかに、利子の受益者が日本の課税を受けているかどうかを問題にし、「受益者が利子について日本の課税を受けていないケースだけを損金算入制限規定の適用とすること」も考えられる。この場合、ごく少数の例外を除き、日本企業の借入は国内金融機関(外国銀行の在日支店を含む。)からの貸付によるものであるから、銀行取引は基本的に損金算入制限規定には服さないこととなり、非居住者・外国法人が保有する社債が、損金算入制限規定の適用を受ける主な第三者からの資金調達ということになる。
もっとも、このような要件設定は、日本の課税権を保護するという考え方によるものと思われ、国際的な租税回避行為を防止するというBEPSプロジェクトの趣旨になじまないようにも思われる。
また、例は少ないとはいえ、外国銀行による貸付を(損金算入制限規定を通じて借主の選好に影響を与えることにより)国内銀行による貸付よりも不利に取り扱うことになる(脚注7)。
また、日本企業が発行する社債を非居住者・外国法人が保有することは珍しいことではない。特に、租税特別措置法上の民間国外債(同法6条)は、基本的に非居住者・外国法人が保有することを前提とする金融商品である。すなわち、民間国外債は、日本企業の資金調達の多様化を目的として、非居住者・外国法人への発行等の要件を満たすことにより、社債利子に対する日本の所得税等の源泉徴収を特例的に免除するという制度である。民間国外債の利子を損金算入制限の対象とすることは、この制度の政策目的と整合せず、日本企業の国際競争力を低下させる要因となる可能性があるともいえよう。
更に、受益者が日本の課税を受けているかどうかを支払者に判定させることの負担や導管取引等の租税回避行為への対処も問題となりうる。
6 終わりに 本稿では、BEPSプロジェクトにおける利子の控除制限の内容と、これを踏まえた日本への影響及び想定される改正内容について解説した。上述したとおり、支払利子の損金算入制限規定は次の平成31年度税制改正で導入される可能性が高い。今年12月に公表される税制改正大綱の内容を注視する必要がある。
脚注
1 本稿の内容は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する法律事務所の見解ではない。
2 日本においても、これらのプランニングへの対抗措置として、既に、過少資本税制、過大支払利子税制、移転価格税制が設けられている。
3 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizationの略語である。
4 グループ比率を用いる場合、グループ内の特定の法人に負債を集中させるプランニング(上記2の②)が否認されることになる。
5 ここでは議論をシンプルにするため、グループとして連結納税を実施しておらず単体ベースで納税をしている日本企業を前提にしている。
6 証券化取引とは、収益を生む資産(原資産。不動産、リース料債権等、様々)をSPCや信託に保有させて、その収益(不動産なら賃料、リース料債権ならリース料)を投資家への分配に充てる取引をいう。
7 外国銀行の借入人からの受取利子が日本の源泉徴収に服している場合には、日本の課税を受けているから適用対象外とする、という対応も考えられるが、そうすると租税条約で免税を受けられる外国銀行を、源泉徴収に服する外国銀行(租税条約で完全な免税を受けられない外国銀行)よりも不利に取り扱うことになる。
この記事に関するご意見・お問合せはta@lotus21.co.jpにお寄せください。
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
新たな「支払利子の損金算入制限規定」の導入について
―平成31年度税制改正の展望―
#222 栗原宏幸(弁護士・税理士)
略歴 森・濱田松本法律事務所 弁護士・税理士。国際税務、税務紛争、タックス・プランニングに精通。広島県呉市出身。広島学院高校、東京大学法学部、東京大学法科大学院卒業。留学先の米国スタンフォード大学、ニューヨーク大学で国際税務を学ぶ。ニューヨーク大学の国際税務プログラムでは最優秀で表彰を受ける。M&A、ファイナンス等の知識・ノウハウを生かし、法務・税務ワンストップの総合的なアドバイスを得意とする。
1 はじめに 次の平成31年度税制改正では、全ての日本企業を適用対象とする新たな支払利子の損金算入制限規定の導入(現行の過大支払利子税制の改正)が見込まれている。本稿の執筆時点(2018年11月22日)では、まだ平成31年度税制改正大綱が公表されていないため、その全容は明らかでないが、本誌で解説する機会を得たので、導入の背景と想定される改正内容についてここで紹介する(脚注1)。
2 導入の背景 そもそもの発端は、OECDのBEPSプロジェクトである。BEPSプロジェクトでは、国際的租税回避行為への様々な対抗措置が提案されたが、その一つである行動計画4は、各国が利子の控除制限規定を設けることを提言している。
従前問題とされてきた利子控除の租税回避行為とは、グループ内の所得移転、例えば、インターカンパニー・ローンに基づく利子の支払いにより税率の高い国から低い国に所得を移転する、というプランニングであった(脚注2)。
このように従来の議論はグループ内の所得移転にフォーカスがあてられてきたが、BEPSプロジェクトの行動計画4は、第三者からの借入をも対象として利子の控除制限を規定することを提言している。すなわち、行動計画4は、多国籍企業を念頭に置いて、①第三者借入を高課税国で行うこと、②インターカンパニー・ローンによりグループ全体の第三者への支払利子の金額を超える支払利子の控除を行うこと、③第三者借入またはインターカンパニー・ローンを原資として非課税所得を得ること、といったケースを想定し、これらのスキームを利用した、行き過ぎた節税策を抑制することを提言している。
3 BEPSプロジェクト行動計画4の提言内容 以上を踏まえ、BEPSプロジェクト行動計画4は、各法人の純支払利子(支払利子-受取利子)は、原則として、EBITDA(脚注3)の10%~30%(具体的な割合は各国が決定する)を超える部分は所得から控除できない、という控除制限規定を導入することを提言している。
ただし、負債比率の大きい企業がその事業を妨げられないように、グループ全体の純支払利子/EBITDAの割合(グループ比率)が上述の原則的な割合よりも高い場合は、グループ比率を用いて控除限度額を算定することもできるとされている(脚注4)。
基準となるEBITDAは、これに代えてEBIT(Earnings Before Interest and Taxes)を用いることも可能とされているが、いずれの金額の計算上も、非課税所得(資本参加免税の適用を受ける配当所得等)はEBITDA又はEBITに含めるべきでないとされている。
4 損金算入制限規定の日本企業への影響 日本はこれまでもBEPSプロジェクトの提言内容に沿った税制改正を行ってきている(外国子会社からの損金算入配当に対する益金不算入措置の否定、タックスヘイブン対策税制の強化等)。この行動計画4についても、来年度の税制改正(平成31年度税制改正)に支払利子の損金算入制限規定の導入(現行の過大支払利子税制の改正)が盛り込まれることが見込まれている。
支払利子の損金算入制限規定がBEPSプロジェクト行動計画4の提言通りの内容で導入された場合、これまでは海外のグループ会社からの借入だけが対象であった損金算入制限が、国内金融機関を含む第三者借入をも対象とすることになる。現行の過大支払利子税制とBEPSプロジェクトの提言内容の比較については表1を参照頂きたい。
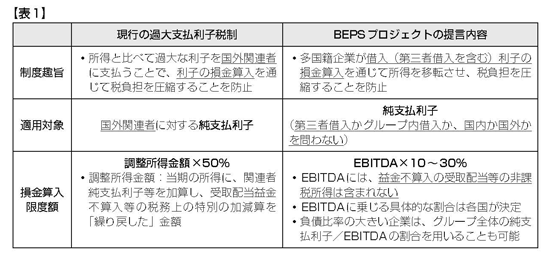
BEPSプロジェクト行動計画4の提言通りに法改正が行われた場合、当該改正が日本企業に対して与える影響としては、例えば以下のようなものが考えられる(脚注5)。
・負債比率の大きい企業、持株会社における税負担の増加 他国での導入状況を踏まえると、損金算入限度額はEBITDAの「30」%になる可能性が高い。昨今の低金利を踏まえると、一般には、日本企業の純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は低いように思われる。
もっとも、負債比率の大きい企業(設備投資が活発なインフラ系の企業や高いレバレッジをかけてM&Aを積極的に行っている企業等)においては、純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は否定できない。
また、グループの持株会社が第三者借入による資金調達を行っている場合、持株会社が子会社から受け取る配当は益金不算入であるから、当該配当の額は、損金算入制限の算定の基礎となるEBITDAに含まれず、その結果、純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性がある。
以上のようにして損金算入が制限されると、法人税の負担が増加し、利益を減少させることとなる。
この点、EBITDAの30%に代えてグループ比率(グループ全体の純支払利子/EBITDAの割合)を用いることが可能であれば、これらの企業も損金算入制限の適用を免れられる可能性があるが、グループ企業が多い場合にはグループ比率の算定の事務負担が問題になり得る。
・証券化取引への影響 実体のある日本企業については、上述の通り純支払利子がEBITDAの30%を上回る可能性は一般に低いと考えられるが、いわゆる証券化取引(脚注6)においてはその影響を受ける可能性が高いと考えられる。
証券化取引においては、SPCの収益(原資産からの収益)と費用(その大半が支払利子)がほぼ同額となりSPCに余剰キャッシュフローが残らないように経済条件が設定されているケースが多いと考えられる。現行法では、そのようなケースではSPCに所得はないことから税負担は均等割等を除けば基本的に生じないが、純支払利子の損金算入がEBITDAの30%に制限された場合、SPCに課税所得が発生しこれによりSPCに法人税の税負担が生じる可能性があり、その結果、既存の経済条件を前提にするとSPCが資金ショートし、借入がデフォルトする可能性があると考えられる(次頁の表2参照)。

ただし、原資産からの収益が利子とみなされるものであれば(例えば原資産が住宅ローンや社債である場合)、純支払利子が0となり、損金算入制限規定の適用を受けず、改正による影響を受けない可能性がある。また、不動産の証券化の場合は、原資産に建物が含まれ、その減価償却費をEBITDAの計算上加算することができるため、EBITDAがキャッシュフローよりも大きくなり、減価償却しない原資産のケースと比べるとEBITDAの30%の制限にかかりにくいといえる。このように、一口に証券化取引といっても、損金算入制限規定の適用の見込みは原資産の内容によるといえよう。
5 想定される改正内容 (1)平成31年度税制改正で支払利子の損金算入制限規定を導入することは、既定路線となっている可能性が高い。一方で、上記4で説明したとおり、BEPSプロジェクト行動計画4の提言内容がそのまま導入された場合には、銀行取引その他の負債による資金調達を阻害する可能性が否定できない。そこで、提言内容をそのまま導入するのではなく、従前の実務を阻害しないよう必要な修正を加えて導入することが望ましいといえる。
なお、筆者の把握している限り、関係各省において、そのように適用場面を限定する方向で改正案が練られているようである。
(2)考えられる方向性の1つとして、「利子の受益者が利子について一定税率以上での課税を受けていないケースのみを、損金算入制限規定の適用とすること」が考えられる。このように、所得が外国で相応の課税権に服していること(又は服していないこと)を課税の要件としている例は比較法的に珍しいものではないと思われる。例えば、文脈や内容はやや異なるが、オランダの資本参加免税制度では、外国子会社株式からの配当、株式譲渡益について免税を得るためには、当該外国子会社が居住地国で10%以上の課税を受けていることが要件とされている(subject-to-taxtest)。
もっとも、このように利子の受益者側の事情を利子の支払者側の要件として設定することについては、支払者が要件を判定するために相応の困難・負担が生じることが見込まれる。銀行取引のような相対取引であれば過度な負担は生じないと考えられるが、社債のように不特定多数の債権者が想定される取引においては、受益者側の情報(しかも税負担に関する情報)を支払者が把握することには困難が伴うと考えられる。
また、導管取引等、規定の適用を免れる租税回避行為への対処も必要となろう。
(3)考えられる方向性としては、ほかに、利子の受益者が日本の課税を受けているかどうかを問題にし、「受益者が利子について日本の課税を受けていないケースだけを損金算入制限規定の適用とすること」も考えられる。この場合、ごく少数の例外を除き、日本企業の借入は国内金融機関(外国銀行の在日支店を含む。)からの貸付によるものであるから、銀行取引は基本的に損金算入制限規定には服さないこととなり、非居住者・外国法人が保有する社債が、損金算入制限規定の適用を受ける主な第三者からの資金調達ということになる。
もっとも、このような要件設定は、日本の課税権を保護するという考え方によるものと思われ、国際的な租税回避行為を防止するというBEPSプロジェクトの趣旨になじまないようにも思われる。
また、例は少ないとはいえ、外国銀行による貸付を(損金算入制限規定を通じて借主の選好に影響を与えることにより)国内銀行による貸付よりも不利に取り扱うことになる(脚注7)。
また、日本企業が発行する社債を非居住者・外国法人が保有することは珍しいことではない。特に、租税特別措置法上の民間国外債(同法6条)は、基本的に非居住者・外国法人が保有することを前提とする金融商品である。すなわち、民間国外債は、日本企業の資金調達の多様化を目的として、非居住者・外国法人への発行等の要件を満たすことにより、社債利子に対する日本の所得税等の源泉徴収を特例的に免除するという制度である。民間国外債の利子を損金算入制限の対象とすることは、この制度の政策目的と整合せず、日本企業の国際競争力を低下させる要因となる可能性があるともいえよう。
更に、受益者が日本の課税を受けているかどうかを支払者に判定させることの負担や導管取引等の租税回避行為への対処も問題となりうる。
6 終わりに 本稿では、BEPSプロジェクトにおける利子の控除制限の内容と、これを踏まえた日本への影響及び想定される改正内容について解説した。上述したとおり、支払利子の損金算入制限規定は次の平成31年度税制改正で導入される可能性が高い。今年12月に公表される税制改正大綱の内容を注視する必要がある。
脚注
1 本稿の内容は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する法律事務所の見解ではない。
2 日本においても、これらのプランニングへの対抗措置として、既に、過少資本税制、過大支払利子税制、移転価格税制が設けられている。
3 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizationの略語である。
4 グループ比率を用いる場合、グループ内の特定の法人に負債を集中させるプランニング(上記2の②)が否認されることになる。
5 ここでは議論をシンプルにするため、グループとして連結納税を実施しておらず単体ベースで納税をしている日本企業を前提にしている。
6 証券化取引とは、収益を生む資産(原資産。不動産、リース料債権等、様々)をSPCや信託に保有させて、その収益(不動産なら賃料、リース料債権ならリース料)を投資家への分配に充てる取引をいう。
7 外国銀行の借入人からの受取利子が日本の源泉徴収に服している場合には、日本の課税を受けているから適用対象外とする、という対応も考えられるが、そうすると租税条約で免税を受けられる外国銀行を、源泉徴収に服する外国銀行(租税条約で完全な免税を受けられない外国銀行)よりも不利に取り扱うことになる。
この記事に関するご意見・お問合せはta@lotus21.co.jpにお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















