解説記事2019年01月07日 【ニュース特集】 過大支払利子税制の見直し、所得相応性基準の全容(2019年1月7日号・№769)
ニュース特集
BEPS勧告による国内法制化項目の目玉が31年改正で実現
過大支払利子税制の見直し、所得相応性基準の全容
与党の平成29年度・30年度税制改正大綱で「今後の検討課題」とされてきたBEPS勧告の国内法制化項目のうち過大支払利子税制(利子控除制限)の見直し及び所得相応性基準の導入がついに平成31年度税制改正で実現することになった。企業側の準備期間に配慮し、適用開始は平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。
平成31年度税制改正大綱を見ると、いずれも過度に企業の負担とならないよう配慮された内容となっていることがうかがえる。過大支払利子税制の見直しでは、国内利子を制限対象外とする一方、調整所得には受取配当益金不算入額を含めないこととなった。固定比率は「20%」と低く設定されたものの、“実害”を受ける企業はかなり限定されることになりそうだ。所得相応性基準については、ライセンス契約に基づくランニング・ロイヤルティに取引単位営業利益法を適用するという実務を無視して課税庁が強引にDCF法が最適手法と判断し、所得相応性基準を発動するのではないかとの懸念の声が企業側から上がっていたが、本誌取材によると、このような形で所得相応性基準が発動されることはない見込み。
本特集では、国際課税分野における平成31年度税制改正の目玉となる過大支払利子税制の見直しと所得相応性基準の内容について、本誌の独自取材で判明した事項も含めお伝えする。
過大支払利子税制
国内利子が制限対象外で、企業の懸念は大きく後退 企業の関心が高かったのが、制限対象の利子に国内への支払利子(以下、国内利子)が含まれるのかどうかという点だ。BEPS勧告をそのまま導入すると、国内・国外/関連・非関連を問わず、全利子が制限対象となる。実際、米国の税制改革でもEU指令でも、全ての利子を制限対象としている。
仮に日本でも国内利子が制限対象とされた場合、BEPSとは無縁の国内系企業、例えば不動産会社や鉄道会社等が、国内における借入が多いというだけで、新たな利子控除制限に抵触する可能性があった。また、国内金融機関から多額の借入れを行った上で積極的に海外展開する企業(商社等)やEBITDAが低い(すなわち、業績がそれほど良くない)企業も軒並み抵触する恐れがあった。さらに銀行からは、顧客企業で損金算入が否認されたことで金融マーケットにマイナスの影響が生じることを懸念する声が上がっていた。
しかし、平成31年度税制改正では、国内利子は現行の過大支払利子税制同様、引続き純支払利子には含まれないこととされた。これにより、上記のような企業側の懸念は大きく後退したと言えよう。
配当益金不算入額を調整所得に含める案消滅 国内利子を制限対象とするか否かということと併せて論点となっていたのが、「受取配当益金不算入額」を調整所得に含めるのか否かということだ。
国内利子を制限対象から除外するという案は当初から浮上していたが、議論の過程では、国内利子を制限対象とする一方、調整所得の定義を見直さない、すなわち「配当益金不算入額を調整所得に含める」とする案も出ていた。調整所得に配当益金不算入額が含まれたままとすれば、仮に国内利子が制限対象とされたとしても、配当依存度の高い企業の一部は救済されることになるからだ。
ただ、税務当局から見ると、子会社からの配当を受領するタイミングは、親会社(納税者)において選択の余地があり、調整所得の“操作可能性”が高いという問題がある。結論として、受取配当益金不算入額を調整所得金額に含めるという案は不採用となった。
固定比率は欧米より厳しい「20%」に設定も、“実害”を受ける企業は限定的 上述のとおり、①制限対象利子から国内利子を除外する、②受取配当益金不算入額は調整所得に含めない、という新たな過大支払利子税制の骨格が固まったところで、残る課題となるのが固定比率の水準だ。
BEPS行動4の勧告では固定比率の水準は固定比率の10%~30%の水準とされているが、米国の税制改革でもEU指令でも全ての利子を制限対象としている中(固定比率は30%)、日本では国内利子を制限対象利子から除外する代わりに固定比率を「20%」という厳しい水準に設定することとなった。その背景には、G20大阪サミットを控え、日本だけ「米欧よりも緩い制度を入れた」との批判は避けたいという税務当局の思惑もありそうだ。
もっとも、国内利子を制限対象から除外した効果は極めて高いことから、固定比率が20%となっても、“実害”を受ける企業はかなり限定されることになりそうだ。
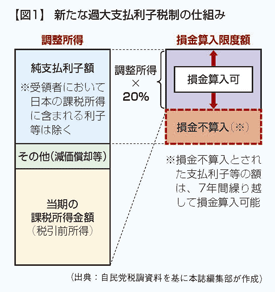
配当を主な収益源とする単体納税の持株会社に救済措置 ただし、実害を受ける企業が全くないというわけではない。
そこで平成31年度税制改正では、デミニマス基準を現行の1,000万円から2,000万円に拡充するほか、「国内企業グループ(持株割合50%超)の合算純支払利子等の額が合算調整所得の20%以下」という新たな適用除外基準が導入される。後者の適用除外基準は、「合算」純支払利子、「合算」調整所得という言葉をわざわざ使っていることからも分かるように、連結納税を採用していない法人に対しても適用されることになる。上述のとおり、配当益金不算入額が調整所得に含まれないこととされた中で、当該適用除外基準は、配当を主な収益源とする単体納税の持株会社に恩恵をもたらすことになるだろう。
施行日前の借入れでも、施行日後に支払った利子は制限対象に このほか、損金不算入額の繰越規定について、繰越期間を7年間から延長することが検討されたが見送られた。
改正過大支払利子税制の施行は、企業の準備期間を考慮して1年後ろ倒しされ、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。ただし、施行日前の借入れに係る利子であっても、施行日後に支払った場合には制限対象となる見込みである点、要注意だ。
所得相応性基準
一定の要件を満たす評価困難な無形資産取引については当初の価格を再評価 所得相応性基準については、2016年中に予定されていたOECDの最終ガイダンス(評価困難な無形資産(HTVI=Hard-to-Value Intangibles)に関するガイダンス)の公表が遅れていたことから、一時は平成31年度税制改正での導入は困難ではないかとの観測もあったが、昨年6月21日に最終ガイダンスが公表されて以降、過大支払利子税制とともに、平成31年度税制改正での導入が規定路線となっていた。
平成31年度税制改正大綱に盛り込まれた所得相応性基準の仕組みは、OECD移転価格ガイドライン第6章を踏まえたものとなっている。所得相応性基準は、取引時の評価が恣意的・不確かなものになりやすいDCF法が使用される場合の“バックストップ”と位置付けられる。具体的には、まず移転価格税制上の無形資産の定義を明確化した上で、比較対象取引が特定できない場合の移転価格算定方法としてDCF法が加えられることになる。ただ、上述のとおりDCF法は各種の前提条件を置く際に恣意的な判断が入り易く、また、結果が大きく乖離する可能性があることから、予測キャッシュ・フロー等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす評価困難な無形資産取引については、当初の価格を再評価できることとされた。
なお、評価困難な無形資産(特定無形資産)の定義は、無形資産の定義とは別に置かれることになる。
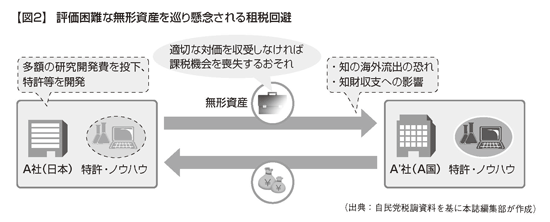
強引な所得相応性基準の発動はなし もっとも、日本企業が無形資産を海外に譲渡することは稀であり、海外子会社との無形資産取引はライセンス契約に基づくことが多い。
こうした中、企業側からは、当該ライセンス契約に基づくランニング・ロイヤルティにTNMM(Transactional Net Margin Method=取引単位営業利益法)を適用するという実務が安定しているにもかかわらず、課税庁が強引にDCF法が最適手法と判断し、所得相応性基準を発動することを懸念する声が上がっていたが、本誌取材により、このような形で所得相応性基準が発動されることはない見込みであることが確認されている。
ただし、既存の移転価格算定方法とDCF法の併用が最適手法となる場合は、なお発動の可能性がある模様。限界事例における適用関係の明確化が今後の課題となるだろう。
発動免除要件としては、取引時点での予測の困難性等を納税者が証明した場合や、乖離幅が20%以内に納まった場合等が挙げられているが、これらはOECD移転価格ガイドラインに沿ったものとなっている。他にも、同ガイドラインのパラ6.193を参考に、APA(事前確認制度)を締結している場合も免除されることになる。
移転価格税制に係る更正期間を6年から7年に延長する一方、四分位法を容認 また、現行制度上「6年間」とされている移転価格税制の更正期間(及び更正の請求期間)が「7年間」に延長される。これは、評価困難な無形資産の商業化には時間がかかることを踏まえ、長期スパンで検証を行う必要があるとの理由による。
一方で、比較対象取引に係る差異調整方法として統計的手法に基づく四分位法(42頁参照)を認める。DCF法を利用した取引を行っていない企業にとっては所得相応性基準の導入に伴う更正期間の延長などはとばっちり以外の何物でもないが、こうした企業の不満を緩和するための措置という見方もできそうだ。
施行日前に行われた無形資産取引は所得相応性基準の適用対象外 所得相応性基準の適用は平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。改正過大支払利子税制同様、1年の猶予期間が置かれている。また、施行日前に行われた無形資産取引については所得相応性基準は適用されない(施行日後の取引について適用する)方向。
所得相応性基準の概要は以上のとおりだが、同基準には法令事項が少なく、多くは通達やQ&Aマターとなりそうだ。
BEPS勧告による国内法制化項目の目玉が31年改正で実現
過大支払利子税制の見直し、所得相応性基準の全容
与党の平成29年度・30年度税制改正大綱で「今後の検討課題」とされてきたBEPS勧告の国内法制化項目のうち過大支払利子税制(利子控除制限)の見直し及び所得相応性基準の導入がついに平成31年度税制改正で実現することになった。企業側の準備期間に配慮し、適用開始は平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。
平成31年度税制改正大綱を見ると、いずれも過度に企業の負担とならないよう配慮された内容となっていることがうかがえる。過大支払利子税制の見直しでは、国内利子を制限対象外とする一方、調整所得には受取配当益金不算入額を含めないこととなった。固定比率は「20%」と低く設定されたものの、“実害”を受ける企業はかなり限定されることになりそうだ。所得相応性基準については、ライセンス契約に基づくランニング・ロイヤルティに取引単位営業利益法を適用するという実務を無視して課税庁が強引にDCF法が最適手法と判断し、所得相応性基準を発動するのではないかとの懸念の声が企業側から上がっていたが、本誌取材によると、このような形で所得相応性基準が発動されることはない見込み。
本特集では、国際課税分野における平成31年度税制改正の目玉となる過大支払利子税制の見直しと所得相応性基準の内容について、本誌の独自取材で判明した事項も含めお伝えする。
過大支払利子税制
国内利子が制限対象外で、企業の懸念は大きく後退 企業の関心が高かったのが、制限対象の利子に国内への支払利子(以下、国内利子)が含まれるのかどうかという点だ。BEPS勧告をそのまま導入すると、国内・国外/関連・非関連を問わず、全利子が制限対象となる。実際、米国の税制改革でもEU指令でも、全ての利子を制限対象としている。
仮に日本でも国内利子が制限対象とされた場合、BEPSとは無縁の国内系企業、例えば不動産会社や鉄道会社等が、国内における借入が多いというだけで、新たな利子控除制限に抵触する可能性があった。また、国内金融機関から多額の借入れを行った上で積極的に海外展開する企業(商社等)やEBITDAが低い(すなわち、業績がそれほど良くない)企業も軒並み抵触する恐れがあった。さらに銀行からは、顧客企業で損金算入が否認されたことで金融マーケットにマイナスの影響が生じることを懸念する声が上がっていた。
| EBITDA |
| Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortizationの略で、「イービットディーエー」「エビーダ」「イービッダー」「イービッドダー」などと呼ばれることが多い。「課税所得+純支払利子+減価償却費」によって計算される。BEPS最終報告書では、「EBITDA×10~30%」を上回る純支払利子を「過大支払利子」として損金算入を認めないことを利子控除制限の基本ルールとして推奨している。 |
しかし、平成31年度税制改正では、国内利子は現行の過大支払利子税制同様、引続き純支払利子には含まれないこととされた。これにより、上記のような企業側の懸念は大きく後退したと言えよう。
配当益金不算入額を調整所得に含める案消滅 国内利子を制限対象とするか否かということと併せて論点となっていたのが、「受取配当益金不算入額」を調整所得に含めるのか否かということだ。
国内利子を制限対象から除外するという案は当初から浮上していたが、議論の過程では、国内利子を制限対象とする一方、調整所得の定義を見直さない、すなわち「配当益金不算入額を調整所得に含める」とする案も出ていた。調整所得に配当益金不算入額が含まれたままとすれば、仮に国内利子が制限対象とされたとしても、配当依存度の高い企業の一部は救済されることになるからだ。
ただ、税務当局から見ると、子会社からの配当を受領するタイミングは、親会社(納税者)において選択の余地があり、調整所得の“操作可能性”が高いという問題がある。結論として、受取配当益金不算入額を調整所得金額に含めるという案は不採用となった。
固定比率は欧米より厳しい「20%」に設定も、“実害”を受ける企業は限定的 上述のとおり、①制限対象利子から国内利子を除外する、②受取配当益金不算入額は調整所得に含めない、という新たな過大支払利子税制の骨格が固まったところで、残る課題となるのが固定比率の水準だ。
BEPS行動4の勧告では固定比率の水準は固定比率の10%~30%の水準とされているが、米国の税制改革でもEU指令でも全ての利子を制限対象としている中(固定比率は30%)、日本では国内利子を制限対象利子から除外する代わりに固定比率を「20%」という厳しい水準に設定することとなった。その背景には、G20大阪サミットを控え、日本だけ「米欧よりも緩い制度を入れた」との批判は避けたいという税務当局の思惑もありそうだ。
もっとも、国内利子を制限対象から除外した効果は極めて高いことから、固定比率が20%となっても、“実害”を受ける企業はかなり限定されることになりそうだ。
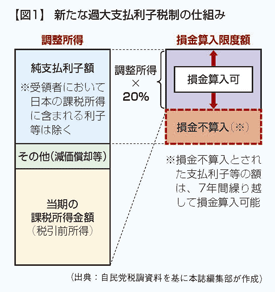
配当を主な収益源とする単体納税の持株会社に救済措置 ただし、実害を受ける企業が全くないというわけではない。
そこで平成31年度税制改正では、デミニマス基準を現行の1,000万円から2,000万円に拡充するほか、「国内企業グループ(持株割合50%超)の合算純支払利子等の額が合算調整所得の20%以下」という新たな適用除外基準が導入される。後者の適用除外基準は、「合算」純支払利子、「合算」調整所得という言葉をわざわざ使っていることからも分かるように、連結納税を採用していない法人に対しても適用されることになる。上述のとおり、配当益金不算入額が調整所得に含まれないこととされた中で、当該適用除外基準は、配当を主な収益源とする単体納税の持株会社に恩恵をもたらすことになるだろう。
施行日前の借入れでも、施行日後に支払った利子は制限対象に このほか、損金不算入額の繰越規定について、繰越期間を7年間から延長することが検討されたが見送られた。
改正過大支払利子税制の施行は、企業の準備期間を考慮して1年後ろ倒しされ、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。ただし、施行日前の借入れに係る利子であっても、施行日後に支払った場合には制限対象となる見込みである点、要注意だ。
所得相応性基準
一定の要件を満たす評価困難な無形資産取引については当初の価格を再評価 所得相応性基準については、2016年中に予定されていたOECDの最終ガイダンス(評価困難な無形資産(HTVI=Hard-to-Value Intangibles)に関するガイダンス)の公表が遅れていたことから、一時は平成31年度税制改正での導入は困難ではないかとの観測もあったが、昨年6月21日に最終ガイダンスが公表されて以降、過大支払利子税制とともに、平成31年度税制改正での導入が規定路線となっていた。
平成31年度税制改正大綱に盛り込まれた所得相応性基準の仕組みは、OECD移転価格ガイドライン第6章を踏まえたものとなっている。所得相応性基準は、取引時の評価が恣意的・不確かなものになりやすいDCF法が使用される場合の“バックストップ”と位置付けられる。具体的には、まず移転価格税制上の無形資産の定義を明確化した上で、比較対象取引が特定できない場合の移転価格算定方法としてDCF法が加えられることになる。ただ、上述のとおりDCF法は各種の前提条件を置く際に恣意的な判断が入り易く、また、結果が大きく乖離する可能性があることから、予測キャッシュ・フロー等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす評価困難な無形資産取引については、当初の価格を再評価できることとされた。
なお、評価困難な無形資産(特定無形資産)の定義は、無形資産の定義とは別に置かれることになる。
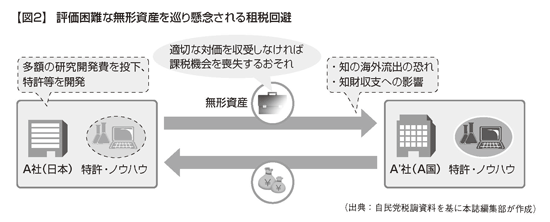
強引な所得相応性基準の発動はなし もっとも、日本企業が無形資産を海外に譲渡することは稀であり、海外子会社との無形資産取引はライセンス契約に基づくことが多い。
こうした中、企業側からは、当該ライセンス契約に基づくランニング・ロイヤルティにTNMM(Transactional Net Margin Method=取引単位営業利益法)を適用するという実務が安定しているにもかかわらず、課税庁が強引にDCF法が最適手法と判断し、所得相応性基準を発動することを懸念する声が上がっていたが、本誌取材により、このような形で所得相応性基準が発動されることはない見込みであることが確認されている。
ただし、既存の移転価格算定方法とDCF法の併用が最適手法となる場合は、なお発動の可能性がある模様。限界事例における適用関係の明確化が今後の課題となるだろう。
発動免除要件としては、取引時点での予測の困難性等を納税者が証明した場合や、乖離幅が20%以内に納まった場合等が挙げられているが、これらはOECD移転価格ガイドラインに沿ったものとなっている。他にも、同ガイドラインのパラ6.193を参考に、APA(事前確認制度)を締結している場合も免除されることになる。
移転価格税制に係る更正期間を6年から7年に延長する一方、四分位法を容認 また、現行制度上「6年間」とされている移転価格税制の更正期間(及び更正の請求期間)が「7年間」に延長される。これは、評価困難な無形資産の商業化には時間がかかることを踏まえ、長期スパンで検証を行う必要があるとの理由による。
一方で、比較対象取引に係る差異調整方法として統計的手法に基づく四分位法(42頁参照)を認める。DCF法を利用した取引を行っていない企業にとっては所得相応性基準の導入に伴う更正期間の延長などはとばっちり以外の何物でもないが、こうした企業の不満を緩和するための措置という見方もできそうだ。
施行日前に行われた無形資産取引は所得相応性基準の適用対象外 所得相応性基準の適用は平成32年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。改正過大支払利子税制同様、1年の猶予期間が置かれている。また、施行日前に行われた無形資産取引については所得相応性基準は適用されない(施行日後の取引について適用する)方向。
所得相応性基準の概要は以上のとおりだが、同基準には法令事項が少なく、多くは通達やQ&Aマターとなりそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















