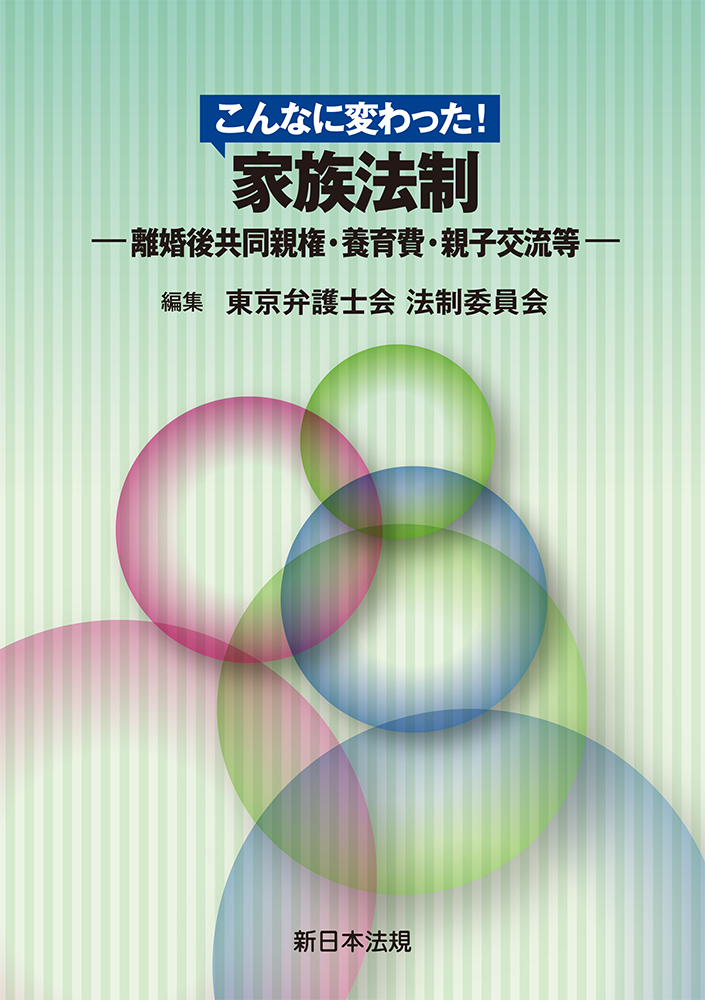解説記事2019年01月14日 【ニュース特集】 全文掲載 エー・ディー・ワークス社訴訟の準備書面(2019年1月14日号・№770)
ニュース特集
更正処分等の取消訴訟における主張内容が判明
全文掲載 エー・ディー・ワークス社訴訟の準備書面
本誌761号(2018年10月29日)掲載の「マンションの仕入税額控除で示されていた当局の見解」(日本税制研究所代表理事・税理士 朝長英樹氏)では、マンション取引を行った事業者がマンションを取得した際に課される消費税について、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係るものとしてその全額を控除することが認められるのか否かが問題となった平成7年と9年の事案において、国税当局がその全額の控除が認められるという法解釈と取扱いを行っていた、ということが当時の検討記録文書から明らかにされたが、今回本誌は、更正処分等の取消訴訟を提起したエー・ディー・ワークス社が昨年12月28日に東京地裁に提出した「原告準備書面(1)」の写しを入手した。
本誌では、その重要性に鑑み、関係者の了解を得て当該書面をそのまま掲載することとした(但し、一部固有名詞をマスキングしている)。
事業者によって是認と否認が混在することは憲法上の平等取扱原則から許されず
エー・ディー・ワークス社の開示資料によれば、同社は、マンション取引における仕入税額控除を否認する同社に対する更正処分等に関し、森・濱田松本法律事務所を代理人として2018年12月14日付で東京地方裁判所に更正処分等の取消訴訟を提起しており、「原告準備書面(1)」は同社が同訴訟において同年12月28日付で裁判所に提出したものである(なお、第1回口頭弁論期日はまだ開催されていない模様)。
この「原告準備書面(1)」は、同訴訟におけるエー・ディー・ワークス社の主張を記載した書面であり、同時に裁判所に提出された朝長英樹税理士の「陳述書」及び「意見書」に基づいたものとなっている。
「原告準備書面(1)」において、エー・ディー・ワークス社は、本件と同種の事例及びその他の事例における過去の課税当局の各種取扱いを踏まえ、個別対応方式による用途区分の判定は「事業者の仕入れの最終的な目的」に基づいて判断するとの解釈が消費税法創設以来の解釈となっていることを明らかにした上で、本件における同社の建物購入(仕入れ)の最終的な目的は建物の販売であるから、当該仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると主張している。そして、同社は、建物の購入から販売までの期間に建物について生じる住宅貸付けの賃料(非課税売上)は「副次的な対価」に過ぎないから用途区分の判定において考慮されるものではないと主張し、客観的に賃料が生じることをもって建物の購入は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとする課税当局の見解は誤りであると主張している。
また、同社は、憲法14条1項に基づく法の執行における「平等取扱原則」の観点から、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者等が存在するにもかかわらず、同社に対して「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理は認められないとして課税処分を行うことは、同社を他の納税者よりも不利益に取り扱うものであるから、平等取扱原則の観点から許されないとも主張している。
以下、エー・ディー・ワークス社が同社に対する更正処分等の取消訴訟において裁判所に提出した「原告準備書面(1)」の写しの全文を掲載する。
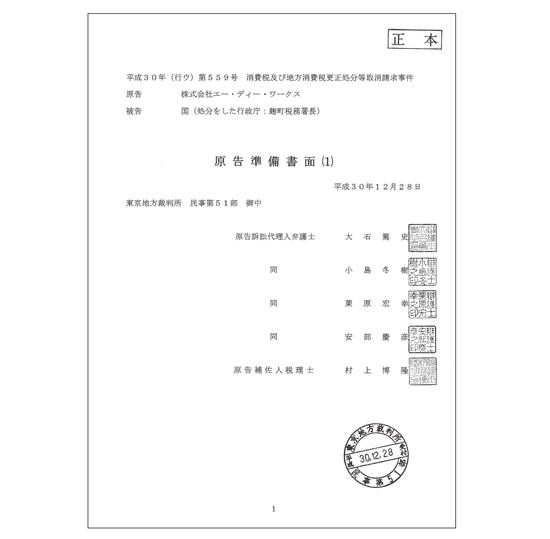
重要資料
平成30年(行ウ)第559号 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
原告 株式会社エー・ディー・ワークス
被告 国(処分をした行政庁:麹町税務署長)
原告準備書面(1)
平成30年12月28日
東京地方裁判所 民事第51部 御中
原告訴訟代理人弁護士 大石篤史
同 小島冬樹
同 栗原宏幸
同 安部慶彦
原告補佐人税理士 村上博隆
目 次(編注:略)
第1 はじめに 本準備書面(1)において、原告は本件の事実関係及び法令の解釈適用を示すことにより、本件更正処分等が違法であることを明らかにする。なお、略語等については、本準備書面(1)で定義したもののほか、訴状の例による。
第2 本件の事案の概要及び争点 原告は、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社である。
原告は、「収益不動産販売事業」を主力事業の一つとしている。「収益不動産販売事業」とは、①マンション等の不動産を所有者から購入し、②建物の管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを行って当該不動産の価値を向上させた上で③顧客に販売する、というものである(甲4 原告のホームページ)。
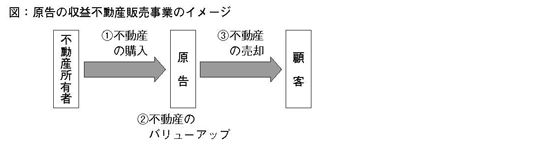
本件の事案は、この原告の収益不動産販売事業に関して、東京国税局が違法な消費税等の更正処分を原告に対して行ったというものである。
すなわち、原告は、この収益不動産販売事業における①の建物の購入(以下「本件課税仕入れ」という。)は、③の顧客への販売を目的とした課税仕入れであり、③の顧客への販売は消費税法上「課税資産の譲渡等」(課税売上)に該当するから、消費税の個別対応方式による仕入税額控除の適用における用途区分の判定上、本件課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものとして、本件課税仕入れに係る消費税額の全額を控除して納付する消費税額を計算していた。
これに対し、東京国税局は、原告が建物を購入してから販売するまでの間に、当該建物について消費税法上「その他の資産の譲渡等」(非課税売上)に該当する住宅貸付けの賃料(消費税法第6条、別表第一第13号)が発生することを奇貨として、用途区分の判定上、本件課税仕入れは販売のみを目的として取得したものとはいえず、本件課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するから、本件課税仕入れに係る消費税額に課税売上割合を乗じて得た額しか控除税額とすることができないとして、本件更正処分等を行った(甲2の1、2の2及び2の3の各「更正の理由」)。
しかし、用途区分の判定は事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて判断すべきものとされているところ、原告は建物販売(課税資産の譲渡等)を最終的な目的として建物を取得しているのであり、住宅貸付けの賃料は用途区分の判定において考慮されない副次的な対価であるに過ぎないから、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものであり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するものではない。よって、本件更正処分等は消費税法第30条第2項第1号の解釈を誤った違法な行政処分である。以上のとおり、本件の第一の争点は、消費税法の個別対応方式による仕入税額控除における用途区分の判定の解釈及び同解釈の本件課税仕入れに対する適用である。この争点に対する当事者の主張の概要は次頁の表のとおりであり、原告の主張及びその論拠の詳細については第3の3(8頁~32頁)で明らかにする。
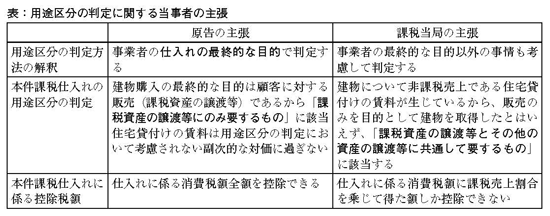
また、他の多くの納税者に関して本件課税仕入れと同種の取引が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとの取扱いが課税当局によって是認されているにもかかわらず、原告に対して本件更正処分等を行い「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」としての取扱いを強要することは、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱うことになるから、本件更正処分等は法の執行における平等取扱原則(憲法第14条第1項)に違反する違法な行政処分である。以上のとおり、本件の第二の争点は、本件更正処分等に対する平等取扱原則の適用である。この争点に関する原告の主張の詳細については第3の4(32頁~33頁)で明らかにする。
以上より、本件更正処分等は違法なものであるから、原告は、本件更正処分等の取消しを求める。
第3 原告の主張
1 はじめに 原告は、消費税法第30条第2項第1号に定める個別対応方式による仕入税額控除の用途区分の判定は事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて判断すべきであり、本件課税仕入れはその最終的な目的が課税資産の譲渡等である建物の販売であるから「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張するものである。
かかる主張が正当であることについて、原告は、東京国税局や税法の立案を担当する財務省(大蔵省)主税局に過去に在籍し、後述する本件と同様の論点が問題となった事例に課税当局側で関与する等、本件の論点及びこれに対する過去の課税当局における取扱いについて知見を有する朝長英樹税理士の意見書(甲5)(以下「朝長税理士意見書」という。)及び陳述書(甲6)(以下「朝長税理士陳述書」という。)を得ている。このうち、朝長税理士意見書(甲5)は、下記3において詳しく述べる原告の法解釈が消費税法第30条第2項第1号の正当な解釈であることを全面的に裏付けている。また、朝長税理士陳述書(甲6)は、本件と同様の論点が問題となった事例について過去に課税当局側でどのように判断がなされたのかや、近時の課税庁の本件の論点の取扱いが一貫しておらず課税の公平が害されていること等について詳細に述べている。
以下では、本件の論点に関連する消費税法の仕組みを簡潔に説明した上で(下記2)、それぞれの争点に関する原告の主張を述べる(下記3及び4)。
2 関連法令等の説明
(1)消費税の仕入税額控除の概要 消費税法上、事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税の納税義務を負っているが(消費税法第5条第1項)、納付すべき消費税の額を算出する際、次頁の図のとおり、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税の額を控除するものとされている(消費税法第30条)。これを「仕入税額控除」という。
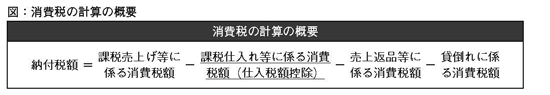
仕入税額控除により控除する消費税の額については、(A)その課税期間における課税売上割合が95パーセント以上であり、かつ、課税売上高が5億円以下である場合には、課税仕入れ等に係る消費税の額を全額控除するものとされているが(消費税法第30条第1項)、(B)これらの要件を満たさない場合(すなわち、当該課税期間における課税売上割合が95パーセント未満であるか、又は、課税売上高が5億円を超える場合)には、課税仕入れ等に係る消費税の額全額を控除することはできず、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のいずれかの方法に基づいて計算される額が控除税額となる(消費税法第30条第2項)(脚注1)。
各本件課税期間に係る仕入税額控除に関して、原告は(B)に基づき「個別対応方式」に基づいて控除税額を計算しているので(甲1の1、1の2及び1の3の各1枚目の「参考事項」)、次に「個別対応方式」について説明する。
(2)個別対応方式の概要 個別対応方式による仕入税額控除の控除税額は、課税仕入れ等が課税資産の譲渡等(課税売上)とその他の資産の譲渡等(非課税売上)のいずれに対応する課税仕入れであるのかを判定して算定するものとされている。
すなわち、個別対応方式において、課税仕入れ等は、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの、③その他の資産の譲渡等にのみ要するもののいずれかに区分される。この区分の判定を「用途区分の判定」という。そして、控除される消費税額は、①の「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する課税仕入れ等に係る消費税額の全額と、②の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する課税仕入れに係る消費税額に事業者の課税売上割合を乗じて得た金額のみとされている(消費税法第30条第2項第1号)。以上につき、以下の表を参照されたい。
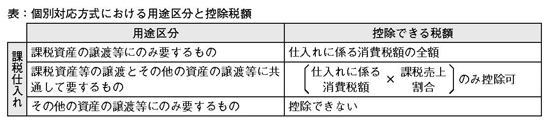
以上のとおり、課税仕入れ等が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する場合にはその仕入れに係る消費税額の全額が控除されるのに対し、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する場合には消費税額の一部しか控除されない。そのため、用途区分の判定は個別対応方式による仕入税額控除の適用において極めて重要である。
第2で述べたとおり、本件の第一の争点は、この用途区分の判定の解釈及び同解釈の本件課税仕入れに対する適用である。そこで、次の3においてこれらの点に関する原告の主張を明らかにする。
3 個別対応方式における用途区分の判定方法
(1)原告の主張の骨子 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうと解釈されている。
そして、個別対応方式における用途区分の判定は、事業者の最終的な目的に基づいて判断すべきものとされており、副次的に得る対価があるとしても、その副次的に得る対価があることをもって当該判定を変えるものとはされていない。
以上より、事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」と判断される場合には、当該課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると解すべきである。 以下詳述する。
(2)「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいう 国税庁が昭和63年12月30日付けで発遣した消費税取扱通達11-1-21によれば、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等」をいうものとされている(甲7 消費税取扱基本通達(抜粋))(脚注2)。当該通達は実質的な内容は変更されずに現在も消費税基本通達11-2-12として存続しているから、「にのみ要する」との文言は「を行うためにのみ必要な」と解釈するのが国税庁の消費税法創設以来の一貫した公権的解釈となっている。
さらに、「課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等」という国税庁の公権的解釈については、国税庁が平成元年2月に発行した『消費税法一問一答集』において、以下のとおり更に詳しい説明がなされている(甲8 『消費税法一問一答集』)。
以上より、国税庁は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」を「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうと解釈している。
かかる解釈は、消費税法の制定経緯を踏まえると、国税庁独自の解釈に留まらず、消費税法を立案した大蔵省主税局(現在の財務省主税局)の解釈でもあると考えられる。すなわち、消費税法は、昭和63年7月29日に政府から法案が国会に提出され、同年12月24日に国会で可決成立し、同年12月30日に公布されており(甲9 日本法令索引)、消費税法施行令と消費税法施行規則も同日に公布されている(甲5 朝長税理士意見書8頁本文16行目~同頁18行目)。そして、上記消費税取扱通達11-1-21を含む消費税取扱通達は、通常の通達が法令の制定等に後れて公表されるのと異なり、消費税法等の公布日である昭和63年12月30日に発遣されている。また、『消費税法一問一答集』(甲8)についても、消費税法等の公布からわずか2ヵ月後の平成元年2月に発行されている。以上の経緯からすると、消費税取扱通達及び『消費税法一問一答集』の内容は、消費税法、消費税法施行令及び消費税法施行規則と同時並行的に、国税庁と大蔵省主税局が詳細な内容のすり合わせ等を行いながら創られたと考えられる(以上の詳細につき、甲5 朝長税理士意見書8頁本文1行目~10頁本文7行目)。とりわけ、個別対応方式における用途区分の判定の根幹である「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の意義について、国税庁と大蔵省主税局がすり合わせをしなかったとは考えがたい。以上より、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうとの解釈は、国税庁のみならず、立法者の公権的解釈でもあるといえる。かかる解釈は、さいたま地裁平成25年6月26日判決(税務訴訟資料263号順号12241)(甲10)でも採用されている。
以上より、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」を意味すると解釈するのが相当である。
(3)用途区分の判定は事業者の最終的な目的に基づいて判断すべきものとされている 以上のとおり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうと解すべきであるところ、その判断をどのように行うべきかが問題となる。
この点については、用途区分の判定は事業者の最終的な目的に基づいて行うべきものとされており、副次的に得る対価があるとしても、その副次的に得る対価があることをもって、当該判断に基づく用途区分の判定を変えるものとはされていない。従って、事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」と判断される場合には、当該課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると解すべきである。 このように一定の割切りをもって事業者の目的を捉えたうえで用途区分の判定を行うことは、消費税法第30条第2項第1号の用途区分の判定が他の消費税法の規定における詳細な定めと比べて非常に簡素な規定しか置いていないことに加え、課税期間終了時の現況等を考慮せずに仕入れ時の状況に基づいて用途区分の判定を行うものとされていること(消費税法基本通達11-2-20)から伺うことができる(甲5 朝長税理士意見書Ⅰ1.(3)(10頁~19頁))。また、上述の「課税資産の譲渡等のみ要するもの」の解釈において「最終的に」課税資産の譲渡等のコストに入るかどうかが問われていることからも、事業者の最終的な目的が何であるかにのみ基づいて用途区分の判定を行うことが妥当といえる。
かかる解釈が消費税法創設以来の確立した解釈であることは、以下に詳述するとおり、過去の課税当局(国税庁・東京国税局)の取扱いにおいて、当該解釈に従った用途区分の判定が現に行われていることから明らかである。
ア 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費に関する事例 この事例が掲載されている書籍(甲11 『回答実例 消費税質疑応答集』)は、平成元年9月に発行されたものであるが、著者の所属は「前国税庁消費税課(現東京国税局消費税課課長)」と記載されており(甲11の奥付)、平成元年9月という当該書籍の発行時期に照らして、国税庁の消費税法創設時の見解を踏まえたものといってよいものである。
以下がその事例の内容及び回答である。
さらに、平成2年4月に発行された『消費税法取扱通達逐条解説』(甲12)には、この事例を取り上げたものと考えられる以下の解説がある。
前者の書籍(甲11)によれば、用途区分の判定は、「課税仕入れ等を行った時に合理的に判定する」とされている。そして、土地の造成工事の費用は、「販売の目的で取得した土地に行った造成費用ですから、一時的に自社の資材置場として使用しているとしても、『非課税資産の譲渡等にのみ要するもの』となります」と説明されている。また、後者の書籍(甲12)によれば、「販売の目的で取得し、一時的に自社資材置場として使用しているときは、最終的な使用目的が販売用であるので非課税用となる」とされている。
以上から、本事例においては、用途区分の判定は「合理的に」行う必要があるところ、その合理的な判定は、所有期間中の一時的な使用の用途に基づいて行うのではなく、事業者の最終的な目的に基づいて行うものとされている。 敷衍すると、取得時において既に転売の約定が成立しているような例外的な場合を除き、不動産を直ちに販売できるという保証はなく、また、不動産は保有しているだけで相当のコスト(固定資産税等)を要することから、通常の事業者であれば、取得時において「直ちに販売できない場合は一時的に別の用途に使用する」という意思を有しているはずである。従って、この事例も取得時にその使用により販売売上以外の売上が想定される事案であったといえるが、この事例では、最終的な目的が販売であることに基づいて用途区分が判定されており、所有期間中にその他の売上が生じる可能性については用途区分の判定において一切考慮されていない。このことから、事業者の最終的な目的だけが用途区分の判定上意味があることは明らかである。
イ マンション建設のための土地取得に要した仲介手数料に関する事例 この事例は、国税庁のウェブサイト(甲13)に掲載されており、次のようなものである。なお、この事例は国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)においても取り上げられているから、国税庁は遅くとも平成10年以降は一貫して以下に示された取扱いをしていることになる。
この事例は、表題からも明らかであるとおり、販売目的で取得した土地について、土地の賃料が副次的な対価として発生する場合に、土地取得時の仲介手数料の用途区分の判定をどのようにして行うかを取り扱ったものである(脚注3)。
なお、この事案では土地の賃料を用途区分の判定において考慮するか否かによって結論の違いは生じない。何故なら、考慮しない場合には(回答のとおり)「土地の売上(非課税)」と「建物の売上(課税)」に基づいて判定を行うため「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるのに対し、考慮する場合には「土地の賃料収入(非課税)」、「土地の売上(非課税)」と「建物の売上(課税)」に基づいて判定を行うため、この場合もまた「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるためである。
しかし、この事例の回答をよく読むと、「その全体の土地の取得は、区分所有となる建物と土地を同時に販売することとなる分譲用のマンションの建設計画に基づいて土地の所有権を取得しているのですから」仲介手数料は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となる、とされていることが分かる。すなわち、この事例では、建物と土地の販売という事業者の最終的な目的のみが用途区分の判定において考慮されており、副次的な対価である土地の賃料は考慮されていない。
以上のとおり、本事例においては、事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて用途区分が判定され、副次的な対価は用途区分の判定上考慮されていない。
ウ 財テクとして行われる株式売買に関する事例 この事例は、国税庁のウェブサイト(甲16)に掲載されており、次のようなものである。なお、この事例は前述した国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)においても取り上げられているから、国税庁は遅くとも平成10年以降は一貫して以下に示された取扱いをしていることになる。
この事例では、財テクとして株式売買を行う場合の株式購入の際に支払う委託売買手数料が、仕入税額控除の対象となるかどうかが問題とされている。
この事例では、購入した株式について配当金を得ることが想定されるにもかかわらず、売買を目的として取得した株式については、配当を得るための仕入れとして取り扱われず、専ら株式の売却にのみ要する仕入れとして取り扱われている。 株式配当は消費税法上の不課税取引であり、不課税取引のための仕入れは「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」にあたるとされているから(消費税法基本通達11-2-16)、仮に委託売買手数料に係る仕入れが配当を得るための仕入れでもあるとすると、当該仕入れは、株式の売却(非課税売上)と配当(不課税取引)に要するものということになり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとされるはずである。しかし、本事例では、株式は売買を目的として購入したものであり、配当という副次的な対価のために要した仕入れではない、ということが明らかにされている。
エ ガス管の移設工事に関する事例 この事例は、前述した国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)において取り上げられている。この事例については国税庁のウェブサイトで確認することができないが、事例が特殊であるため継続して広く公表しておく必要がないとされたためではないかと推測される。
この事例では、他の事業者からの求めに応じてガス管を移設することとし、その場合に他の事業者から他受工事補償金を受け取るという事実関係を前提として、「ガス管移設のための課税仕入れは、他受工事補償金を得るために必要な課税仕入れというよりも、ガスを供給するために必要な課税仕入れと考えられることから、課税売上げにのみ要するものとして取り扱って差し支えない。」と説明されている。
都市ガス業者が収受する他受工事補償金は不課税とされており(甲17 『消費税一問一答(改訂版)』「90他受工事補償金の取扱い」)、上記イのとおり不課税取引のための仕入れは「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」にあたるとされているから、事業者がガス管を移設することにより他受工事補償金を収受することが用途区分の判定上考慮されるのであれば、ガス管移設のための仕入れは、ガスの供給(課税売上)と他受工事補償金の収受(不課税売上)に要するものということになり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるはずである。しかし、本事例では、ガス事業者のガス管移設のための仕入れの最終的な目的がガスの供給であることから、当該仕入れは課税売上げにのみ要するものとされ、副次的な対価である他受工事補償金は用途区分の判定上考慮されていない。
オ 本件と同様の事例における課税当局の判断 上記アからエの各事例にとどまらず、課税当局は、以下のとおり、本件と同様に建物買取り後に住宅貸付けの賃料が発生する建物の仕入れの事案において、上記(1)で示した原告の解釈に従った判断を少なくとも2度行っている(詳細については、甲5 朝長税理士意見書Ⅰ2.(3)~(8)(35頁~44頁)、甲6 朝長税理士陳述書2.及び3.(1頁~4頁))。
(ア)平成7年の事案 この事案(以下「平成7年事案」という。)は、平成6年に国税庁課税部消費税課に質問が寄せられたものである。この事案に関しては、他の多くの事案とは異なり、注意を要する事案として、国税庁が平成6年11月7日から8日にかけて開催した「全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議」において質問の内容と取扱い案の説明を行った上で意見聴取が行われた。
その内容は以下のとおりである(甲18 全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議資料「消費税審理事務当面の問題について」5~6頁)。
以上のとおり、「全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議」において準備された取扱い案においては、分譲用マンションの購入は分譲を目的としているから、仮に一時的に賃貸用に供されるとしても「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとの判断が示された。
その後、平成7年2月16日に、「譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除」と題する取扱い事例が、国税庁から全国の国税局と税務署に対し、FAX通信により送信された。その内容は、上記の取扱い案と同様であり、具体的には以下のとおりである(甲19 消費税FAX通信(抜粋)2~3枚目)。
以上のとおり、平成7年事案においては、分譲を目的として取得したことから、マンションの購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとされており、販売までの間に当該マンションを賃貸に供するとしても、その賃料収入は用途区分の判定において考慮しないとされている。
以上の取扱いは、国税庁のデータベースにも保存されており、その解釈と取扱いは現在まで全く変えずに引き継がれている(甲20 朝長英樹税理士による情報公開請求に係る国税庁の回答)。
(イ)平成9年の事案 この事案(以下「平成9年事案」という。)は、東京国税局で検討を行った事案であり、平成7年事案と同様にマンションの購入が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するかどうかが問題とされた。
東京国税局は平成9年事案を処理するにあたり、国税庁だけでなく、朝長英樹税理士が当時在籍していた大蔵省主税局にも確認をするなどして、慎重に検討を行った。
以上のとおり慎重に検討を行った結果、東京国税局は、マンションを転売目的で取得したことが明らかであることを理由に、マンションの購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとした。事案の内容及び東京国税局の判断は以下のとおりである(甲21 質疑事項回答整理表)。
以上のとおり、平成9年事案では、「法人の処理及び販売活動等から、マンションを転売目的で取得したことは明らかであることから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、仕入税額控除が認められる。」と判断されている。そして、平成9年事案のこの判断にあたり、国税庁課税部消費税課は、「『課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ』かどうかの判定は、課税仕入れを行った日等の状況で行うが、これは、課税仕入れが結果として何の売上げに貢献したかではなく、何の売上げに貢献される目的で行ったかを課税仕入れの時点で判断すべきであることを意味している。」とされている。
以上の説明を踏まえると、課税当局は、平成9年事案において、用途区分の判定を、課税仕入れがどのような売上に貢献したかという客観的な対応関係に基づいて判断するのではなく、課税仕入れを行った事業者の最終的な目的によって判断しているといえる。 また、平成9年事案において、住宅貸付けの賃料は「あくまで居抜きで購入したために副次的に得た対価である」とされ、用途区分の判定上一切考慮されていない。
カ 小括 以上の各事例における課税当局の解釈及び判断によれば、原告が上記(1)で示した解釈が用途区分の判定及び「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の正当な解釈であることは明らかである。
とりわけ、平成7年事案と平成9年事案は、本件の先例として取り扱われるべきものであり、特に平成9年事案は納税者が建物を購入した時点で建物が住宅貸付けに供されていたという点で本件の事案と全く同じである。それらの事案において、課税当局は、原告が主張する最終的な目的に基づいて用途区分を判定し、副次的な対価は考慮しないとの解釈を一貫してとっており、当該解釈に基づき、不動産の購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると判断しているから、本件においても同様の解釈及び適用がなされるべきである。
(4)事業者が建物を棚卸資産として税務処理している事実は建物購入の最終的な目的が販売であることの重要な間接事実と捉えるべきである 事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」かどうかを判断するにあたり、事業者の法人税又は所得税の税務処理上、当該仕入れに係るコストがいかなる収益に対応するものとして取り扱われているかは、事業者の目的を推認させる重要な間接事実となると考えられる。
コストと収益との対応関係を消費税ではなく法人税又は所得税の税務処理により判断する理由は、消費税法には原則として費用と収益の対応関係という考え方は存在しないのに対し、法人税及び所得税においては、会計原則を踏まえた費用・収益対応の考え方がとられているからである。上記ウの事例(財テクとして行われる株式売買に関する事例)において、株式購入の際の手数料が配当金を得るための支払対価ではないと判断されていることに関し、「(当該手数料は)所得税、法人税においても配当金収入のための必要経費又は損金としては取り扱われてはいません。」と所得税及び法人税の観点からの説明が加えられていること(甲16)は、このことを端的に示している。
本件のような建物の購入については、事業者の購入時の税務処理上、当該建物が「固定資産」として処理されている場合、販売までの保有期間中の減価償却により取得費の一部が賃料収入に対応するコストとなる。これに対し、当該建物が当初から「棚卸資産」として継続して処理されている場合には、減価償却資産に棚卸資産は含まれないことから当該建物は減価償却資産に該当せず(法人税法施行令13条柱書)、よって減価償却は行われず、購入代金等は全額が当該建物を譲渡したときの原価となる。換言すれば、事業者の税務処理上、建物が当初から継続して「棚卸資産」として処理されている場合には、当該建物は販売を最終的な目的として取得されたものであると考えることが合理的である。この点は、平成7年事案において「継続して棚卸資産として処理」されていることが判断の決め手となっていること(甲18、19)、平成9年事案においても「経理処理において『販売用不動産』として計上し減価償却も行っていないことから、当該マンションを販売目的の棚卸資産として認識していることから明らかであること」が判断のための重要な事実として摘示されていること(甲21)からも裏付けられる。
なお、販売売上と賃料収入の金額、利益率等は、事後的に生じた客観的な事実に過ぎず、事業者の最終的な目的に基づいて行うべき用途区分の判定において何ら関係のない事実である(上記(3)の各事例においても、これらの点は一切考慮されず、既に説明したとおり事業者の最終的な目的に基づいて判定が行われている)。
(5)本件へのあてはめ-本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する 第2において説明したとおり、原告による本件課税仕入れは、マンション等を原告の顧客に販売することを目的とするものであり、この点について原告と原処分庁(ひいては被告)との間に争いはない。原告が販売を目的として本件課税仕入れを行っていることは、原告が本件更正処分等の対象とされたマンションを購入時から継続して「棚卸資産」として計上しており、税務上も当該マンションを「棚卸資産」として取り扱っていることからも明らかである(甲22 ■■■■■■■■■■に関する原告の仕訳入力チェックリスト(購入時))。
以上より、本件課税仕入れは課税資産の譲渡等に該当する建物販売を最終的な目的とする課税仕入れであり、「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコスト(すなわち建物販売の原価)に入る」課税仕入れであるから、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するというべきである。 原告は、マンションの所有権を取得することによりその他の資産の譲渡等に該当する当該マンションの賃料を受領することになるが、上記のとおり、本件課税仕入れの原告の最終的な目的は建物の販売であり、建物の賃貸ではないから、当該賃料は副次的に得る対価に過ぎず、用途判定において考慮されるものではない。
以上より、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する。
(6)原処分庁の主張に対する原告の反論
ア 原処分庁の主張の骨子 本件に係る審査請求の答弁書において、原処分庁は用途区分の判定につき以下のとおり主張している(甲23 本件更正処分等に係る審査請求の答弁書9枚目(同書別紙の「(22)枚のうち(8)枚目」とされている頁)3行目~13行目)。
以上の一般論のもと、原処分庁は、以下のとおり述べて、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当すると主張している(甲23 本件更正処分等に係る審査請求の答弁書12枚目(同書別紙の「(22)枚のうち(11)枚目」とされている頁)13行目~25行目)。
原処分庁の主張は、要するに、客観的に住宅貸付けの賃料が発生する以上、建物の販売のみを目的として建物を取得したということはできず、住宅貸付けをも目的として取得したとみるべきである、というものと理解される。
しかし、原処分庁の主張は以下の点において誤っている。
イ 原処分庁の主張には論理の飛躍がありその合理的な論拠は一切提示されていない まず、上記で引用した原処分庁の主張には明らかな論理の飛躍がある。1つ目の引用部分を以下に再掲する。
上記の引用部分の2段落目において、原処分庁は、「このような制度趣旨」から、原処分庁が主張する判断手法が導かれると主張する。
しかし、「このような制度趣旨」として引用部分の1段落目で説明されているのは、仕入税額控除においては仕入れと売上げの対応関係が切断されていることと、その結果、仕入税額控除の用途区分の判定は仕入れた時点において行うことのみであり、これらの説明から、「状況等」に基づいて判定を行うべきことや、「当該課税仕入れをした事業者が有する目的、意図等諸般の事情を勘案」すること、「客観的に判断すべき」ことといった結論を導くことはできない。
原処分庁の主張は、事業者の最終的な目的以外の事情をも勘案して用途区分の判定を行うことを正当化しようとするものであるが、以上のとおり、そのように解すべき合理的な根拠は原処分庁からは一切提示されていない。
ウ 原処分庁の解釈は過去の国税庁の取扱いと整合しない 上記(3)で詳述したとおり、事業者の最終的な目的ではない副次的対価については用途区分の判定において考慮しないというのが、消費税法創設時以来の確立した解釈となっている。これに対し、原処分庁の主張は、客観的に発生するあらゆる対価を考慮して用途区分の判定を行うことを強要するものであり、かかる原処分庁の解釈は上記の確立した解釈と整合しないというべきである。消費税法創設当時において用途区分の判定は「課税仕入れ等を行った時に合理的に判定する」(甲11)とされ、「合理的」な判定とは事業者の仕入れの最終的な目的に基づく判断をいうとされていたのであるから、これを「客観的に判断すべき」と言い換えることにより仕入れの最終的な目的以外の事情を考慮して用途区分の判定を行うことは許されないというべきである。
とりわけ、平成9年事案では、納税者が建物を購入した時点で建物が住宅貸付けに供されていたという点で本件の事案と全く同じ事案において、販売目的で取得した不動産について生じる賃料は副次的な対価に過ぎないから用途区分の判定において考慮されないと明確に判断されており、原処分庁の解釈はこの平成9年事案の判断と真正面から抵触する不当な解釈である。
エ 原処分庁が依拠する裁判例はいずれも本件の先例とはならない 原処分庁は、自説の根拠となる裁判例として、①さいたま地裁平成25年6月26日判決(税務訴訟資料263号順号12241)(甲10)、②東京地裁平成24年9月7日判決(税務訴訟資料262号順号12032)(甲24)、③名古屋地裁平成26年10月23日判決(税務訴訟資料264号順号12553)(甲25)を引用している(甲23 本件更正処分等に係る審査請求の答弁書11枚目(同書別紙の「(22)枚のうち(10)枚目」とされている頁)4行目~7行目)。
しかしながら、いずれの裁判例も、本件とは事案が異なるため、本件の判断にあたり先例として取り扱うべきものではない。
まず、①のさいたま地裁判決は、事業者によるマンションの取得がマンションの販売に加えてその賃貸をも目的としていたとして、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とされた事案である。しかし、上記(3)で原告が言及した課税当局の過去の判断は、同判決に一切引用されておらず、従って裁判所の判断の基礎となっていないことが伺えるから、その判旨の正当性には疑問がある。加えて、同事案において、納税者は問題となったマンションを法人税の確定申告書の提出時には「固定資産」に計上しており、その後、税務署担当官の指摘を受けて、修正申告書を提出して「棚卸資産」に変更している。従って、さいたま地裁判決の事案は、当初から「棚卸資産」として税務処理されており販売目的が明確である本件とは異なり、マンションの取得時においては販売だけでなく賃貸をも最終的な目的としていたということができる事案であるから、本件とは事案を異にする。
また、②の東京地裁判決は、いわゆるPFI(公共施設の維持、管理等を民間の事業者が地方公共団体から委託を受けて行うこと)の事案であり、事業者である納税者が地方自治体から受領する施設の整備に関する対価が課税売上である元本部分と非課税売上である金利部分から構成されていたという事案において、納税者が当該対価を得るために行った課税仕入れが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとされた事案である。この事案は、地方自治体との間で合意した対価の額を課税売上と非課税売上に契約上配分したという事実が認定されており、そのため課税売上と非課税売上が事業者の最終的な目的であるということができる事案であるから、課税売上である建物の販売と非課税売上である住宅貸付けの賃料が明確に分かれており、前者が最終的な目的であり後者は副次的な対価である本件とは事案を異にする。
最後に、③の名古屋地裁判決は、建物の一部を事業用賃貸(課税資産の譲渡等)に供し、その余の一部を住宅貸付け(その他の資産の譲渡等)に供する目的で建物を建築したという事案において、当該建物の建築費等が「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であると判断された事案である。しかし、同判決は、用途区分をどのように判定するかが争点となった事案ではなく、用途区分の判定時期が争点となった事案である。すなわち、同事案では、納税者(原告)が、仕入れが行われた課税期間の末日までに事業用賃貸のみが開始され住宅貸付けが開始されなかったことを踏まえて、用途区分の判定は課税期間の末日の時点で判断するべきであり、従って当該仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると主張したが、裁判所は課税仕入れが行われた日の状況によって判断すべきであるとして納税者の主張を否定した。以上のとおり、名古屋地裁判決は本件の争点である用途区分の判定の方法について判断を下したものではないから、本件の先例とはならない。なお、同事案の納税者は建物の販売を目的として建物を建築したものではなく、建物を継続保有して事業用賃貸の賃料(課税売上)と住宅貸付けの賃料(非課税売上)の双方を得ることを目的として建物の建築を行ったものといえるから、原告の主張する解釈によれば、納税者の最終的な目的は課税売上と非課税売上の双方を得ることにあり、裁判所の結論と同じく「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となる。
以上のとおり、原処分庁がその判断の正当性の根拠として引用する裁判例は、いずれも本件の先例とはならないというべきである。
(7)小括 以上より、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものであり、本件課税仕入れが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当することを前提として行われた本件更正処分等は違法な行政処分であるから、速やかに取り消されるべきである。
4 本件更正処分等は法の執行における平等取扱原則に反する違法な行政処分である 本件更正処分等は、他の多くの納税者においては「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が課税当局によって是認されている中で、原告についてかかる税務処理を認めず、ことさらに原告を不利益に取り扱うものであるから、我が国の憲法が要請する平等取扱原則にも違反する違法なものであるというべきである。
すなわち、憲法第14条第1項に由来する「平等取扱原則」は、法の執行の段階においても妥当するとされており、同一の状況にある納税者のうち、一方に対しては課税処分を行いながら、他方に対して課税処分を行わないことは、この平等取扱原則に違反するというべきである(甲26 金子宏『租税法(第22版)』、甲27 大阪高裁昭和44年9月30日判決(高裁民集22巻5号682頁)(スコッチライト事件))。
朝長英樹税理士によると、本件の論点についての課税当局の対応は一貫しておらず、原告のように非課税売上の多寡にかかわらず一律否認された納税者がいる一方で、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者、マンションの取得から販売までの期間が短いものを除いた上で否認を受けた納税者、賃貸収入の否認だけで済んだ納税者が存在する(甲6 朝長税理士陳述書6.(7頁~8頁))。さらに、朝長英樹税理士によると、原告に対する税務調査における担当者の発言等を踏まえると、原告のように一律否認を受けたものがいる一方で、課税当局の方針として、ある程度の非課税売上がある物件だけを否認するというものや、課税期間の末日に所有している物件だけを否認するというものが存在することが伺われる(甲6 朝長税理士陳述書6.(7頁~8頁))。
以上のとおり、本件の論点に対する課税当局の判断は区々として一貫性がなく、憲法第14条第1項が要請する法の執行における平等取扱原則に著しく反する事態が生じている。そのような状況の中で、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者等が存在するにもかかわらず、原告に対して「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理は認められないとして課税処分を行うことは、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱うものであるから、平等取扱原則の観点から許されないというべきである。
以上より、本件更正処分等は憲法第14条第1項に反する違法な行政処分であるというべきである。
第4 被告は本件更正処分等の違法性を判断するために必要な内部資料等を提出すべきである 本件に関する原告の主張は現時点において以上のとおりであるが、朝長税理士意見書(甲5)Ⅰ3.(11)(57頁~58頁)が指摘するとおり、本件更正処分等の前に課税当局が本件及び本件に類似する事例において用途区分の判定をどのように判断していたかに関し、被告は、本件の課税の適否に適切な判断が下されるように協力するという立場に立ち、朝長税理士意見書が列挙する以下の資料を本法廷に提出すべきである。
① 国税庁及び東京国税局にデータとして保存されている仕入税額控除に関する全ての取扱いの目次
② 本件に類似する全ての事案の取扱いのデータ情報(「事例要旨」を収録したものの中の「仕入税額控除」の部分の目次と全ての事例要旨を含む。)
③ 平成9年事案に関する「質疑事項回答整理表」
④ 平成9年事案に関する「質疑事項整理表」の次葉の「〔部門一次担当意見〕の中の「参考」という部分に記載されている「参考3」及び「別添「消費税課意見」」
⑤ その「参考3」の前に存在するはずの「参考1」及び「参考2」
⑥ 「転売目的のマンションを居抜きで買い取った場合の仕入税額控除」という標題のデータ情報
第5 結語 以上のとおり、本件更正処分等は違法な処分であるから、速やかに取り消されるべきである。
以 上
脚注
1 以上とは別に、実際の仕入税額ではなく、課税売上高の一定割合を控除する簡易課税制度もあるが、本件には適用されないので説明を割愛する。
2 また、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と対になる「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」の意義についても同様の解釈がとられている(消費税取扱通達11-1-23)。
3 なお、照会内容は「課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することとなりますか。」とされ、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」となるかどうかが問われているのに対して、回答内容は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。」とされている。本件では照会にあるように「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という結論はおよそ採り難いものであり、また、問いと答えが整合していないが、これは、当初この事例が掲載された平成元年5月発行の『消費税一問一答』(甲15)では誤って答えが「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であるとされたところを、その後国税庁がその誤りに気付き、『消費税一問一答(改訂版)』で答えを修正したときに問いが修正されなかったためであると考えられる。
更正処分等の取消訴訟における主張内容が判明
全文掲載 エー・ディー・ワークス社訴訟の準備書面
本誌761号(2018年10月29日)掲載の「マンションの仕入税額控除で示されていた当局の見解」(日本税制研究所代表理事・税理士 朝長英樹氏)では、マンション取引を行った事業者がマンションを取得した際に課される消費税について、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係るものとしてその全額を控除することが認められるのか否かが問題となった平成7年と9年の事案において、国税当局がその全額の控除が認められるという法解釈と取扱いを行っていた、ということが当時の検討記録文書から明らかにされたが、今回本誌は、更正処分等の取消訴訟を提起したエー・ディー・ワークス社が昨年12月28日に東京地裁に提出した「原告準備書面(1)」の写しを入手した。
本誌では、その重要性に鑑み、関係者の了解を得て当該書面をそのまま掲載することとした(但し、一部固有名詞をマスキングしている)。
事業者によって是認と否認が混在することは憲法上の平等取扱原則から許されず
エー・ディー・ワークス社の開示資料によれば、同社は、マンション取引における仕入税額控除を否認する同社に対する更正処分等に関し、森・濱田松本法律事務所を代理人として2018年12月14日付で東京地方裁判所に更正処分等の取消訴訟を提起しており、「原告準備書面(1)」は同社が同訴訟において同年12月28日付で裁判所に提出したものである(なお、第1回口頭弁論期日はまだ開催されていない模様)。
この「原告準備書面(1)」は、同訴訟におけるエー・ディー・ワークス社の主張を記載した書面であり、同時に裁判所に提出された朝長英樹税理士の「陳述書」及び「意見書」に基づいたものとなっている。
「原告準備書面(1)」において、エー・ディー・ワークス社は、本件と同種の事例及びその他の事例における過去の課税当局の各種取扱いを踏まえ、個別対応方式による用途区分の判定は「事業者の仕入れの最終的な目的」に基づいて判断するとの解釈が消費税法創設以来の解釈となっていることを明らかにした上で、本件における同社の建物購入(仕入れ)の最終的な目的は建物の販売であるから、当該仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると主張している。そして、同社は、建物の購入から販売までの期間に建物について生じる住宅貸付けの賃料(非課税売上)は「副次的な対価」に過ぎないから用途区分の判定において考慮されるものではないと主張し、客観的に賃料が生じることをもって建物の購入は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとする課税当局の見解は誤りであると主張している。
また、同社は、憲法14条1項に基づく法の執行における「平等取扱原則」の観点から、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者等が存在するにもかかわらず、同社に対して「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理は認められないとして課税処分を行うことは、同社を他の納税者よりも不利益に取り扱うものであるから、平等取扱原則の観点から許されないとも主張している。
以下、エー・ディー・ワークス社が同社に対する更正処分等の取消訴訟において裁判所に提出した「原告準備書面(1)」の写しの全文を掲載する。
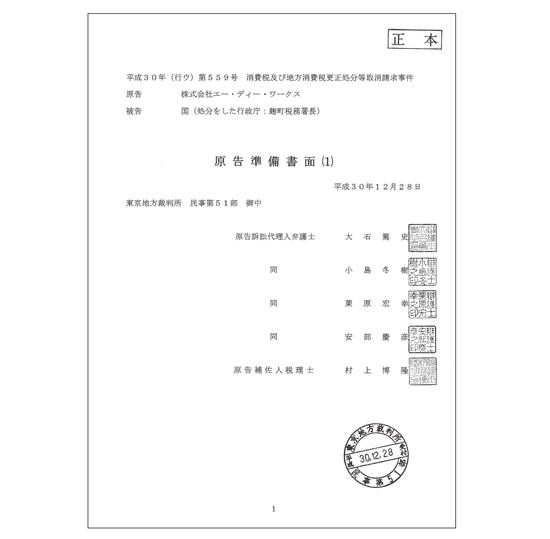
重要資料
平成30年(行ウ)第559号 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
原告 株式会社エー・ディー・ワークス
被告 国(処分をした行政庁:麹町税務署長)
原告準備書面(1)
平成30年12月28日
東京地方裁判所 民事第51部 御中
原告訴訟代理人弁護士 大石篤史
同 小島冬樹
同 栗原宏幸
同 安部慶彦
原告補佐人税理士 村上博隆
目 次(編注:略)
第1 はじめに 本準備書面(1)において、原告は本件の事実関係及び法令の解釈適用を示すことにより、本件更正処分等が違法であることを明らかにする。なお、略語等については、本準備書面(1)で定義したもののほか、訴状の例による。
第2 本件の事案の概要及び争点 原告は、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社である。
原告は、「収益不動産販売事業」を主力事業の一つとしている。「収益不動産販売事業」とは、①マンション等の不動産を所有者から購入し、②建物の管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを行って当該不動産の価値を向上させた上で③顧客に販売する、というものである(甲4 原告のホームページ)。
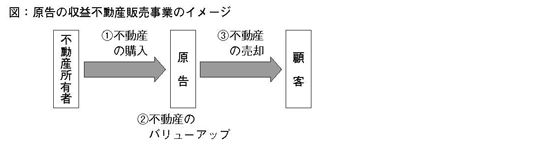
本件の事案は、この原告の収益不動産販売事業に関して、東京国税局が違法な消費税等の更正処分を原告に対して行ったというものである。
すなわち、原告は、この収益不動産販売事業における①の建物の購入(以下「本件課税仕入れ」という。)は、③の顧客への販売を目的とした課税仕入れであり、③の顧客への販売は消費税法上「課税資産の譲渡等」(課税売上)に該当するから、消費税の個別対応方式による仕入税額控除の適用における用途区分の判定上、本件課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものとして、本件課税仕入れに係る消費税額の全額を控除して納付する消費税額を計算していた。
これに対し、東京国税局は、原告が建物を購入してから販売するまでの間に、当該建物について消費税法上「その他の資産の譲渡等」(非課税売上)に該当する住宅貸付けの賃料(消費税法第6条、別表第一第13号)が発生することを奇貨として、用途区分の判定上、本件課税仕入れは販売のみを目的として取得したものとはいえず、本件課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するから、本件課税仕入れに係る消費税額に課税売上割合を乗じて得た額しか控除税額とすることができないとして、本件更正処分等を行った(甲2の1、2の2及び2の3の各「更正の理由」)。
しかし、用途区分の判定は事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて判断すべきものとされているところ、原告は建物販売(課税資産の譲渡等)を最終的な目的として建物を取得しているのであり、住宅貸付けの賃料は用途区分の判定において考慮されない副次的な対価であるに過ぎないから、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものであり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するものではない。よって、本件更正処分等は消費税法第30条第2項第1号の解釈を誤った違法な行政処分である。以上のとおり、本件の第一の争点は、消費税法の個別対応方式による仕入税額控除における用途区分の判定の解釈及び同解釈の本件課税仕入れに対する適用である。この争点に対する当事者の主張の概要は次頁の表のとおりであり、原告の主張及びその論拠の詳細については第3の3(8頁~32頁)で明らかにする。
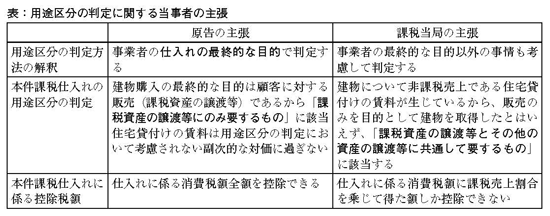
また、他の多くの納税者に関して本件課税仕入れと同種の取引が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとの取扱いが課税当局によって是認されているにもかかわらず、原告に対して本件更正処分等を行い「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」としての取扱いを強要することは、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱うことになるから、本件更正処分等は法の執行における平等取扱原則(憲法第14条第1項)に違反する違法な行政処分である。以上のとおり、本件の第二の争点は、本件更正処分等に対する平等取扱原則の適用である。この争点に関する原告の主張の詳細については第3の4(32頁~33頁)で明らかにする。
以上より、本件更正処分等は違法なものであるから、原告は、本件更正処分等の取消しを求める。
第3 原告の主張
1 はじめに 原告は、消費税法第30条第2項第1号に定める個別対応方式による仕入税額控除の用途区分の判定は事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて判断すべきであり、本件課税仕入れはその最終的な目的が課税資産の譲渡等である建物の販売であるから「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張するものである。
かかる主張が正当であることについて、原告は、東京国税局や税法の立案を担当する財務省(大蔵省)主税局に過去に在籍し、後述する本件と同様の論点が問題となった事例に課税当局側で関与する等、本件の論点及びこれに対する過去の課税当局における取扱いについて知見を有する朝長英樹税理士の意見書(甲5)(以下「朝長税理士意見書」という。)及び陳述書(甲6)(以下「朝長税理士陳述書」という。)を得ている。このうち、朝長税理士意見書(甲5)は、下記3において詳しく述べる原告の法解釈が消費税法第30条第2項第1号の正当な解釈であることを全面的に裏付けている。また、朝長税理士陳述書(甲6)は、本件と同様の論点が問題となった事例について過去に課税当局側でどのように判断がなされたのかや、近時の課税庁の本件の論点の取扱いが一貫しておらず課税の公平が害されていること等について詳細に述べている。
以下では、本件の論点に関連する消費税法の仕組みを簡潔に説明した上で(下記2)、それぞれの争点に関する原告の主張を述べる(下記3及び4)。
2 関連法令等の説明
(1)消費税の仕入税額控除の概要 消費税法上、事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税の納税義務を負っているが(消費税法第5条第1項)、納付すべき消費税の額を算出する際、次頁の図のとおり、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税の額を控除するものとされている(消費税法第30条)。これを「仕入税額控除」という。
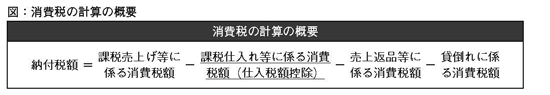
仕入税額控除により控除する消費税の額については、(A)その課税期間における課税売上割合が95パーセント以上であり、かつ、課税売上高が5億円以下である場合には、課税仕入れ等に係る消費税の額を全額控除するものとされているが(消費税法第30条第1項)、(B)これらの要件を満たさない場合(すなわち、当該課税期間における課税売上割合が95パーセント未満であるか、又は、課税売上高が5億円を超える場合)には、課税仕入れ等に係る消費税の額全額を控除することはできず、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のいずれかの方法に基づいて計算される額が控除税額となる(消費税法第30条第2項)(脚注1)。
各本件課税期間に係る仕入税額控除に関して、原告は(B)に基づき「個別対応方式」に基づいて控除税額を計算しているので(甲1の1、1の2及び1の3の各1枚目の「参考事項」)、次に「個別対応方式」について説明する。
(2)個別対応方式の概要 個別対応方式による仕入税額控除の控除税額は、課税仕入れ等が課税資産の譲渡等(課税売上)とその他の資産の譲渡等(非課税売上)のいずれに対応する課税仕入れであるのかを判定して算定するものとされている。
すなわち、個別対応方式において、課税仕入れ等は、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの、③その他の資産の譲渡等にのみ要するもののいずれかに区分される。この区分の判定を「用途区分の判定」という。そして、控除される消費税額は、①の「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する課税仕入れ等に係る消費税額の全額と、②の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する課税仕入れに係る消費税額に事業者の課税売上割合を乗じて得た金額のみとされている(消費税法第30条第2項第1号)。以上につき、以下の表を参照されたい。
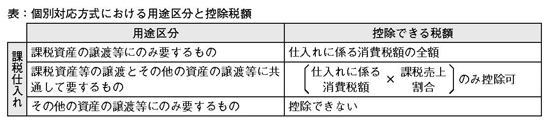
以上のとおり、課税仕入れ等が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する場合にはその仕入れに係る消費税額の全額が控除されるのに対し、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する場合には消費税額の一部しか控除されない。そのため、用途区分の判定は個別対応方式による仕入税額控除の適用において極めて重要である。
第2で述べたとおり、本件の第一の争点は、この用途区分の判定の解釈及び同解釈の本件課税仕入れに対する適用である。そこで、次の3においてこれらの点に関する原告の主張を明らかにする。
3 個別対応方式における用途区分の判定方法
(1)原告の主張の骨子 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうと解釈されている。
そして、個別対応方式における用途区分の判定は、事業者の最終的な目的に基づいて判断すべきものとされており、副次的に得る対価があるとしても、その副次的に得る対価があることをもって当該判定を変えるものとはされていない。
以上より、事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」と判断される場合には、当該課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると解すべきである。 以下詳述する。
(2)「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいう 国税庁が昭和63年12月30日付けで発遣した消費税取扱通達11-1-21によれば、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等」をいうものとされている(甲7 消費税取扱基本通達(抜粋))(脚注2)。当該通達は実質的な内容は変更されずに現在も消費税基本通達11-2-12として存続しているから、「にのみ要する」との文言は「を行うためにのみ必要な」と解釈するのが国税庁の消費税法創設以来の一貫した公権的解釈となっている。
さらに、「課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等」という国税庁の公権的解釈については、国税庁が平成元年2月に発行した『消費税法一問一答集』において、以下のとおり更に詳しい説明がなされている(甲8 『消費税法一問一答集』)。
| (「課税資産の譲渡等にのみ要する」ことの意味) (問434) 光熱費、事務用品などに課されている税額も課税資産の譲渡等にのみ要するものはすべて控除できるというが、課税資産の譲渡等にのみ要するとはどのような意味か。 (答) 課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいう。すなわち、直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等である。 例えば、課税の対象となる商品の製造に直接必要な原材料、製造機械のほか、事務用品、販売費のような間接経費の課税仕入もこれに含まれる(取通11-1-21)。 |
かかる解釈は、消費税法の制定経緯を踏まえると、国税庁独自の解釈に留まらず、消費税法を立案した大蔵省主税局(現在の財務省主税局)の解釈でもあると考えられる。すなわち、消費税法は、昭和63年7月29日に政府から法案が国会に提出され、同年12月24日に国会で可決成立し、同年12月30日に公布されており(甲9 日本法令索引)、消費税法施行令と消費税法施行規則も同日に公布されている(甲5 朝長税理士意見書8頁本文16行目~同頁18行目)。そして、上記消費税取扱通達11-1-21を含む消費税取扱通達は、通常の通達が法令の制定等に後れて公表されるのと異なり、消費税法等の公布日である昭和63年12月30日に発遣されている。また、『消費税法一問一答集』(甲8)についても、消費税法等の公布からわずか2ヵ月後の平成元年2月に発行されている。以上の経緯からすると、消費税取扱通達及び『消費税法一問一答集』の内容は、消費税法、消費税法施行令及び消費税法施行規則と同時並行的に、国税庁と大蔵省主税局が詳細な内容のすり合わせ等を行いながら創られたと考えられる(以上の詳細につき、甲5 朝長税理士意見書8頁本文1行目~10頁本文7行目)。とりわけ、個別対応方式における用途区分の判定の根幹である「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の意義について、国税庁と大蔵省主税局がすり合わせをしなかったとは考えがたい。以上より、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうとの解釈は、国税庁のみならず、立法者の公権的解釈でもあるといえる。かかる解釈は、さいたま地裁平成25年6月26日判決(税務訴訟資料263号順号12241)(甲10)でも採用されている。
以上より、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」を意味すると解釈するのが相当である。
(3)用途区分の判定は事業者の最終的な目的に基づいて判断すべきものとされている 以上のとおり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは「最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」をいうと解すべきであるところ、その判断をどのように行うべきかが問題となる。
この点については、用途区分の判定は事業者の最終的な目的に基づいて行うべきものとされており、副次的に得る対価があるとしても、その副次的に得る対価があることをもって、当該判断に基づく用途区分の判定を変えるものとはされていない。従って、事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」と判断される場合には、当該課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると解すべきである。 このように一定の割切りをもって事業者の目的を捉えたうえで用途区分の判定を行うことは、消費税法第30条第2項第1号の用途区分の判定が他の消費税法の規定における詳細な定めと比べて非常に簡素な規定しか置いていないことに加え、課税期間終了時の現況等を考慮せずに仕入れ時の状況に基づいて用途区分の判定を行うものとされていること(消費税法基本通達11-2-20)から伺うことができる(甲5 朝長税理士意見書Ⅰ1.(3)(10頁~19頁))。また、上述の「課税資産の譲渡等のみ要するもの」の解釈において「最終的に」課税資産の譲渡等のコストに入るかどうかが問われていることからも、事業者の最終的な目的が何であるかにのみ基づいて用途区分の判定を行うことが妥当といえる。
かかる解釈が消費税法創設以来の確立した解釈であることは、以下に詳述するとおり、過去の課税当局(国税庁・東京国税局)の取扱いにおいて、当該解釈に従った用途区分の判定が現に行われていることから明らかである。
ア 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費に関する事例 この事例が掲載されている書籍(甲11 『回答実例 消費税質疑応答集』)は、平成元年9月に発行されたものであるが、著者の所属は「前国税庁消費税課(現東京国税局消費税課課長)」と記載されており(甲11の奥付)、平成元年9月という当該書籍の発行時期に照らして、国税庁の消費税法創設時の見解を踏まえたものといってよいものである。
以下がその事例の内容及び回答である。
| 242 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
問 当社は土木工事、建設工事及び宅地開発事業を行っている中堅の建設業者です。この度、S市M地区の宅地開発を行うこととして、用地を取得し、一部造成工事を行いましたが、宅地の販売開始が翌々事業年度となるので、一時的に当社の資材置場として使用しています。この場合、当期に行った造成工事の費用は、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって、①課税売上げにのみ要するもの、②非課税売上げにのみ要するもの、③課税・非課税売上げに共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。 答 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等について、①課税売上げにのみ要するもの、②非課税売上げにのみ要するもの、③課税・非課税売上げに共通して要するものとに区分することとされていますが、この場合の「非課税売上げにのみ要するもの」とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいうこととされていて、販売用の土地の造成費用はこれに該当するものとされています(取通11-1-23)。また、その課税仕入れ等が非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当するか否かの判定は、課税仕入れ等を行った時に合理的に判定することとされています。 したがって、質問の造成工事の費用については、販売の目的で取得した土地に行った造成費用ですから、一時的に自社の資材置場として使用しているとしても、「非課税資産の譲渡等にのみ要するもの」となります。」 |
| 個別対応方式における土地造成費等の取扱い
〔中略〕 (注)販売用の目的で取得し、一時的に自社の資材置場として使用しているときは、最終的な使用目的が販売用であるので非課税用となる |
以上から、本事例においては、用途区分の判定は「合理的に」行う必要があるところ、その合理的な判定は、所有期間中の一時的な使用の用途に基づいて行うのではなく、事業者の最終的な目的に基づいて行うものとされている。 敷衍すると、取得時において既に転売の約定が成立しているような例外的な場合を除き、不動産を直ちに販売できるという保証はなく、また、不動産は保有しているだけで相当のコスト(固定資産税等)を要することから、通常の事業者であれば、取得時において「直ちに販売できない場合は一時的に別の用途に使用する」という意思を有しているはずである。従って、この事例も取得時にその使用により販売売上以外の売上が想定される事案であったといえるが、この事例では、最終的な目的が販売であることに基づいて用途区分が判定されており、所有期間中にその他の売上が生じる可能性については用途区分の判定において一切考慮されていない。このことから、事業者の最終的な目的だけが用途区分の判定上意味があることは明らかである。
イ マンション建設のための土地取得に要した仲介手数料に関する事例 この事例は、国税庁のウェブサイト(甲13)に掲載されており、次のようなものである。なお、この事例は国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)においても取り上げられているから、国税庁は遅くとも平成10年以降は一貫して以下に示された取扱いをしていることになる。
| 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
【照会要旨】 マンションの分譲を行っている事業者が、分譲用マンションを建設するための土地の所有権を取得する際に仲介業者に支払った仲介手数料に係る税額は、個別対応方式で仕入控除税額を計算する場合、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することとなりますか。 なお、所有権を取得することとなる土地の一部分には取得前から賃借人が存在していることから、当該賃借人から借地権を取得するまでの間は、所有権取得後引き続き当該土地の賃貸人となって賃貸料を徴することとなります。 【回答要旨】 一部に土地の賃貸収入があるということですが、質問の場合のように、その全体の土地の取得は、区分所有となる建物と土地を同時に販売することとなる分譲用のマンションの建設計画に基づいて土地の所有権を取得しているのですから、その取得に際して支払った仲介手数料は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。 |
なお、この事案では土地の賃料を用途区分の判定において考慮するか否かによって結論の違いは生じない。何故なら、考慮しない場合には(回答のとおり)「土地の売上(非課税)」と「建物の売上(課税)」に基づいて判定を行うため「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるのに対し、考慮する場合には「土地の賃料収入(非課税)」、「土地の売上(非課税)」と「建物の売上(課税)」に基づいて判定を行うため、この場合もまた「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるためである。
しかし、この事例の回答をよく読むと、「その全体の土地の取得は、区分所有となる建物と土地を同時に販売することとなる分譲用のマンションの建設計画に基づいて土地の所有権を取得しているのですから」仲介手数料は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となる、とされていることが分かる。すなわち、この事例では、建物と土地の販売という事業者の最終的な目的のみが用途区分の判定において考慮されており、副次的な対価である土地の賃料は考慮されていない。
以上のとおり、本事例においては、事業者の仕入れの最終的な目的に基づいて用途区分が判定され、副次的な対価は用途区分の判定上考慮されていない。
ウ 財テクとして行われる株式売買に関する事例 この事例は、国税庁のウェブサイト(甲16)に掲載されており、次のようなものである。なお、この事例は前述した国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)においても取り上げられているから、国税庁は遅くとも平成10年以降は一貫して以下に示された取扱いをしていることになる。
| 株式の売買に伴う課税仕入れ
【照会要旨】 財テクとして株式の売買を行い、これについて委託売買手数料等を支払っていますが、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、これらの支出は非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価として仕入税額控除の対象とならないことになるのでしょうか。 【回答要旨】 株式の売買に伴う課税仕入れに係る支払対価としては、委託売買手数料、投資顧問料、保護預り料があり、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合におけるこれらの支払対価は次のように、いずれも、非課税売上げにのみ要する課税仕入れとして取り扱います。 1 株式を売却する際の委託売買手数料は、株式の譲渡のための費用ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価に該当し、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合は仕入税額控除の対象にはなりません。 一方、購入した株式については、それを売却するまでの間に配当金を収受することもありますが、株式を購入する際の委託売買手数料は、配当金を得るための支払対価というよりも後日における売却のための取得に要する支払対価と認められますから(所得税、法人税においても配当金収入のための必要経費又は損金としては取り扱われてはいません。)、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る支払対価に該当することとなります。 2 株式の売買に当たって、投資顧問業者から売買に関して、専門的な助言を得る場合があり、このような助言に対して投資顧問業者に支払う投資顧問料も、委託売買手数料と同様に非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。 3 株式の保護預り料は、後日の売却のための支出ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。 |
この事例では、購入した株式について配当金を得ることが想定されるにもかかわらず、売買を目的として取得した株式については、配当を得るための仕入れとして取り扱われず、専ら株式の売却にのみ要する仕入れとして取り扱われている。 株式配当は消費税法上の不課税取引であり、不課税取引のための仕入れは「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」にあたるとされているから(消費税法基本通達11-2-16)、仮に委託売買手数料に係る仕入れが配当を得るための仕入れでもあるとすると、当該仕入れは、株式の売却(非課税売上)と配当(不課税取引)に要するものということになり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとされるはずである。しかし、本事例では、株式は売買を目的として購入したものであり、配当という副次的な対価のために要した仕入れではない、ということが明らかにされている。
エ ガス管の移設工事に関する事例 この事例は、前述した国税庁が平成10年に発行した職員向けの書籍である『消費税一問一答(改訂版)』(甲14)において取り上げられている。この事例については国税庁のウェブサイトで確認することができないが、事例が特殊であるため継続して広く公表しておく必要がないとされたためではないかと推測される。
| 999 ガス管の移設工事に要する費用の仕入税額控除
(問) 都市ガス供給業者が、下水道事業者又は地下鉄事業者等の求めに応じてガス管を移設する場合に受け取る他受工事補償金は課税の対象外であるが、このガス管を移設するために必要な費用のうち課税仕入れに該当するものについては、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって、ガス供給のために必要な課税仕入れ、すなわち課税売上げにのみ要する課税仕入れとして取り扱ってよいか。 (答) ガス管移設のための課税仕入れは、他受工事補償金を得るために必要な課税仕入れというよりも、ガスを供給するために必要な課税仕入れと考えられることから、課税売上げにのみ要するものとして取り扱って差し支えない。 |
都市ガス業者が収受する他受工事補償金は不課税とされており(甲17 『消費税一問一答(改訂版)』「90他受工事補償金の取扱い」)、上記イのとおり不課税取引のための仕入れは「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」にあたるとされているから、事業者がガス管を移設することにより他受工事補償金を収受することが用途区分の判定上考慮されるのであれば、ガス管移設のための仕入れは、ガスの供給(課税売上)と他受工事補償金の収受(不課税売上)に要するものということになり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となるはずである。しかし、本事例では、ガス事業者のガス管移設のための仕入れの最終的な目的がガスの供給であることから、当該仕入れは課税売上げにのみ要するものとされ、副次的な対価である他受工事補償金は用途区分の判定上考慮されていない。
オ 本件と同様の事例における課税当局の判断 上記アからエの各事例にとどまらず、課税当局は、以下のとおり、本件と同様に建物買取り後に住宅貸付けの賃料が発生する建物の仕入れの事案において、上記(1)で示した原告の解釈に従った判断を少なくとも2度行っている(詳細については、甲5 朝長税理士意見書Ⅰ2.(3)~(8)(35頁~44頁)、甲6 朝長税理士陳述書2.及び3.(1頁~4頁))。
(ア)平成7年の事案 この事案(以下「平成7年事案」という。)は、平成6年に国税庁課税部消費税課に質問が寄せられたものである。この事案に関しては、他の多くの事案とは異なり、注意を要する事案として、国税庁が平成6年11月7日から8日にかけて開催した「全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議」において質問の内容と取扱い案の説明を行った上で意見聴取が行われた。
その内容は以下のとおりである(甲18 全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議資料「消費税審理事務当面の問題について」5~6頁)。
| 第三 消費税審理上の諸問題 1 最近における消費税の審理事案で注意を要するものは、次のとおりである。 (1)譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除 A社は、買い取った分譲用マンション(住宅用)を分譲することとしているが、マンション市況の状況等からその分譲の完了までには数年(最長7年程度)を見込んでおり、それまでの間はこの分譲用マンションの一部を一時期賃貸することとした。この場合、仕入税額控除の計算を個別対応方式で行うときにおいて、購入する際に課される消費税額のうち、分譲用マンションの譲渡対価に係るものについては、課税資産の譲渡等(家屋の譲渡)にのみ要するものとして計算をすることができるか。 《取扱い》 本件については、次のとおり取り扱う方向で検討中である。 購入物件は分譲することを目的として取得したマンションであり、課税仕入れの時点では課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することは明らかであることから、仮に一時的に賃貸用に供されるとしても、継続して棚卸資産として処理し、将来的には全て分譲することとしているものについては、法第30条第2項第1号イ《個別対応方式による仕入控除税額の計算》の課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するものとして取り扱って差し支えない。 |
以上のとおり、「全国国税局消費税課長・統括国税調査官会議」において準備された取扱い案においては、分譲用マンションの購入は分譲を目的としているから、仮に一時的に賃貸用に供されるとしても「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとの判断が示された。
その後、平成7年2月16日に、「譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除」と題する取扱い事例が、国税庁から全国の国税局と税務署に対し、FAX通信により送信された。その内容は、上記の取扱い案と同様であり、具体的には以下のとおりである(甲19 消費税FAX通信(抜粋)2~3枚目)。
| 【照会要旨】(抜粋) C社は、買い取った分譲用マンションを分譲することとしているが、マンション市況の状況等からその分譲の完了までには数年を見込んでおり、それまでの間はこの分譲用マンションの一部を一時期賃貸することとしている。 この場合、仕入控除税額の計算を個別対応方式で行うときにおいて、C社がB社から購入する際に課される分譲用マンションに係る消費税額については、課税資産の譲渡等(家屋の譲渡)にのみ要するものとして計算をすることができるか。 【回答要旨】 購入物件は分譲することを目的として取得したマンションであり、課税仕入れの時点では課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することは明らかであることから、仮に一時的に賃貸用に供されるとしても、継続して棚卸資産として処理し(宅地建物取引業者の免許を取得するまでの間は固定資産として処理する場合を含む。)、将来的には全て分譲することとしているものについては、法第30条第2項第1号イの課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するものとして取り扱って差し支えない。 また、これにより課税資産の譲渡等にのみ要するものとして全額控除したものを取得後3年以内に賃貸用住宅に供する場合であっても、棚卸資産であり固定資産ではないことから、法第34条第1項に規定する課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整をする必要はない。 |
(イ)平成9年の事案 この事案(以下「平成9年事案」という。)は、東京国税局で検討を行った事案であり、平成7年事案と同様にマンションの購入が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するかどうかが問題とされた。
東京国税局は平成9年事案を処理するにあたり、国税庁だけでなく、朝長英樹税理士が当時在籍していた大蔵省主税局にも確認をするなどして、慎重に検討を行った。
以上のとおり慎重に検討を行った結果、東京国税局は、マンションを転売目的で取得したことが明らかであることを理由に、マンションの購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するとした。事案の内容及び東京国税局の判断は以下のとおりである(甲21 質疑事項回答整理表)。
| 【質疑内容欄】(抜粋) 調査法人は、平成8年2月15日に親会社の所有するマンション16物件を、賃借人が居住している状態のまま(以下「居抜き」という。)時価で購入し、販売用不動産として計上した。 調査法人は、課税売上割合が95%未満であり、個別対応方式により消費税を申告しているが、販売用不動産の購入に係る仮払消費税は、親会社を通じて収受する居住用賃貸収入に係る課税仕入れに該当するものとして、仕入税額控除を適用せず全額資産計上とした。その後、実地調査において、当該処理は下記の理由により誤りであったので仕入税額控除(約4億8千万円)を認めて欲しいと主張し、さらに更正の請求(別添1のとおり)を行ったものである。 1 16物件のマンションは、当初から販売目的(1棟ごとに居抜きで転売するか、賃貸契約解除後に1戸ごとに販売する)で購入したものであり、購入に係る仮払消費税は「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当し仕入税額控除の適用ができる。 2 16物件のマンションは、販売用不動産として計上し減価償却を行っていないこと、平成8年3月末では転売等は未済であるが、平成8年12月末では、16物件474戸のうち121戸が販売済でありその他159戸が販売予定等であることから、販売目的の取得であることが明らかである。 【回答内容欄】(抜粋) 本件の場合は、法人の処理及び販売活動等から、マンションを転売目的で取得したことが明らかであることから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、仕入税額控除が認められる。 (なお、本件については、消費税課【原告注:国税庁課税部消費税課】から上記と同様の内容の質疑回答を得ている。)」 【参考欄】 (消費税課意見・要約) 当該マンションの購入は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当することから、更正の請求は認められる。 「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」かどうかの判定は、課税仕入れを行った日等の状況で行うが、これは、課税仕入れが結果として何の売上げに貢献したかではなく、何の売上げに貢献される目的で行ったかを課税仕入れの時点で判断すべきであることを意味している。 親会社からのマンションを購入した際に賃貸収入(非課税売上げ)が生じているが、これはあくまで居抜きで購入したために副次的に得た対価である(参考3のとおり)。 (以上、別添「消費税課意見」のとおり)」 |
以上の説明を踏まえると、課税当局は、平成9年事案において、用途区分の判定を、課税仕入れがどのような売上に貢献したかという客観的な対応関係に基づいて判断するのではなく、課税仕入れを行った事業者の最終的な目的によって判断しているといえる。 また、平成9年事案において、住宅貸付けの賃料は「あくまで居抜きで購入したために副次的に得た対価である」とされ、用途区分の判定上一切考慮されていない。
カ 小括 以上の各事例における課税当局の解釈及び判断によれば、原告が上記(1)で示した解釈が用途区分の判定及び「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の正当な解釈であることは明らかである。
とりわけ、平成7年事案と平成9年事案は、本件の先例として取り扱われるべきものであり、特に平成9年事案は納税者が建物を購入した時点で建物が住宅貸付けに供されていたという点で本件の事案と全く同じである。それらの事案において、課税当局は、原告が主張する最終的な目的に基づいて用途区分を判定し、副次的な対価は考慮しないとの解釈を一貫してとっており、当該解釈に基づき、不動産の購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると判断しているから、本件においても同様の解釈及び適用がなされるべきである。
(4)事業者が建物を棚卸資産として税務処理している事実は建物購入の最終的な目的が販売であることの重要な間接事実と捉えるべきである 事業者の最終的な目的に基づいて「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入る」かどうかを判断するにあたり、事業者の法人税又は所得税の税務処理上、当該仕入れに係るコストがいかなる収益に対応するものとして取り扱われているかは、事業者の目的を推認させる重要な間接事実となると考えられる。
コストと収益との対応関係を消費税ではなく法人税又は所得税の税務処理により判断する理由は、消費税法には原則として費用と収益の対応関係という考え方は存在しないのに対し、法人税及び所得税においては、会計原則を踏まえた費用・収益対応の考え方がとられているからである。上記ウの事例(財テクとして行われる株式売買に関する事例)において、株式購入の際の手数料が配当金を得るための支払対価ではないと判断されていることに関し、「(当該手数料は)所得税、法人税においても配当金収入のための必要経費又は損金としては取り扱われてはいません。」と所得税及び法人税の観点からの説明が加えられていること(甲16)は、このことを端的に示している。
本件のような建物の購入については、事業者の購入時の税務処理上、当該建物が「固定資産」として処理されている場合、販売までの保有期間中の減価償却により取得費の一部が賃料収入に対応するコストとなる。これに対し、当該建物が当初から「棚卸資産」として継続して処理されている場合には、減価償却資産に棚卸資産は含まれないことから当該建物は減価償却資産に該当せず(法人税法施行令13条柱書)、よって減価償却は行われず、購入代金等は全額が当該建物を譲渡したときの原価となる。換言すれば、事業者の税務処理上、建物が当初から継続して「棚卸資産」として処理されている場合には、当該建物は販売を最終的な目的として取得されたものであると考えることが合理的である。この点は、平成7年事案において「継続して棚卸資産として処理」されていることが判断の決め手となっていること(甲18、19)、平成9年事案においても「経理処理において『販売用不動産』として計上し減価償却も行っていないことから、当該マンションを販売目的の棚卸資産として認識していることから明らかであること」が判断のための重要な事実として摘示されていること(甲21)からも裏付けられる。
なお、販売売上と賃料収入の金額、利益率等は、事後的に生じた客観的な事実に過ぎず、事業者の最終的な目的に基づいて行うべき用途区分の判定において何ら関係のない事実である(上記(3)の各事例においても、これらの点は一切考慮されず、既に説明したとおり事業者の最終的な目的に基づいて判定が行われている)。
(5)本件へのあてはめ-本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する 第2において説明したとおり、原告による本件課税仕入れは、マンション等を原告の顧客に販売することを目的とするものであり、この点について原告と原処分庁(ひいては被告)との間に争いはない。原告が販売を目的として本件課税仕入れを行っていることは、原告が本件更正処分等の対象とされたマンションを購入時から継続して「棚卸資産」として計上しており、税務上も当該マンションを「棚卸資産」として取り扱っていることからも明らかである(甲22 ■■■■■■■■■■に関する原告の仕訳入力チェックリスト(購入時))。
以上より、本件課税仕入れは課税資産の譲渡等に該当する建物販売を最終的な目的とする課税仕入れであり、「その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコスト(すなわち建物販売の原価)に入る」課税仕入れであるから、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するというべきである。 原告は、マンションの所有権を取得することによりその他の資産の譲渡等に該当する当該マンションの賃料を受領することになるが、上記のとおり、本件課税仕入れの原告の最終的な目的は建物の販売であり、建物の賃貸ではないから、当該賃料は副次的に得る対価に過ぎず、用途判定において考慮されるものではない。
以上より、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する。
(6)原処分庁の主張に対する原告の反論
ア 原処分庁の主張の骨子 本件に係る審査請求の答弁書において、原処分庁は用途区分の判定につき以下のとおり主張している(甲23 本件更正処分等に係る審査請求の答弁書9枚目(同書別紙の「(22)枚のうち(8)枚目」とされている頁)3行目~13行目)。
| 仕入税額控除は、流通過程における税負担の累積を防止するため、一定の要件の下に、資産の譲渡等に係る税額から仕入れに係る税額を控除する制度であるが、消費税法第30条の規定に照らすと、仕入れた資産が、仕入日の属する課税期間中に譲渡されるとは限らないため、控除額の算定においては、仕入れと売上げの対応関係を切断し、当該資産の譲渡が実際に課税資産の譲渡に該当したか否かを考慮することなく、仕入れた時点において、課税仕入れに当たるか否かを判断するものとしたと解される。 このような制度趣旨に鑑みると、上記用途区分は、課税仕入れを行った日の状況等に基づき、当該課税仕入れをした事業者が有する目的、意図等諸般の事情を勘案し、事業者において行う将来の多様な取引のうち、どのような取引に要するものであるのかを客観的に判断すべきものと解するのが相当である。 |
| (ハ) 小括 上記(イ)のとおり、課税仕入れが行われた日は、本件各物件の引渡しを受けた日(物件取得日)であることが認められ、課税仕入れにおける用途区分は、当該引渡しを受けた日の状況に基づいて客観的に判断すべきこととなるところ、上記(ロ)のとおり、請求人【原告注:原告のことを指す。】は、販売目的で引渡しを受けた日以降、不動産賃貸収入を得ることとなり、また、請求人の事業スキームによりあらかじめ当該不動産賃貸収入を得ることを計画していたことが伺えることからすれば、本件各物件は、いずれも、「課税資産の譲渡等」のみを目的として取得されたものということはできない。 したがって、請求人における本件各物件の取得は、「課税資産の譲渡等」(課税売上げ)である建物の再販売のみを目的として取得したものであるということも、また、「その他の資産の譲渡等」(非課税売上げ)に当たる住宅の貸付けのみを目的として取得したものであるということもできないから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。 |
しかし、原処分庁の主張は以下の点において誤っている。
イ 原処分庁の主張には論理の飛躍がありその合理的な論拠は一切提示されていない まず、上記で引用した原処分庁の主張には明らかな論理の飛躍がある。1つ目の引用部分を以下に再掲する。
| 仕入税額控除は、流通過程における税負担の累積を防止するため、一定の要件の下に、資産の譲渡等に係る税額から仕入れに係る税額を控除する制度であるが、消費税法第30条の規定に照らすと、仕入れた資産が、仕入日の属する課税期間中に譲渡されるとは限らないため、控除額の算定においては、仕入れと売上げの対応関係を切断し、当該資産の譲渡が実際に課税資産の譲渡に該当したか否かを考慮することなく、仕入れた時点において、課税仕入れに当たるか否かを判断するものとしたと解される。 このような制度趣旨に鑑みると、上記用途区分は、課税仕入れを行った日の状況等に基づき、当該課税仕入れをした事業者が有する目的、意図等諸般の事情を勘案し、事業者において行う将来の多様な取引のうち、どのような取引に要するものであるのかを客観的に判断すべきものと解するのが相当である。 |
しかし、「このような制度趣旨」として引用部分の1段落目で説明されているのは、仕入税額控除においては仕入れと売上げの対応関係が切断されていることと、その結果、仕入税額控除の用途区分の判定は仕入れた時点において行うことのみであり、これらの説明から、「状況等」に基づいて判定を行うべきことや、「当該課税仕入れをした事業者が有する目的、意図等諸般の事情を勘案」すること、「客観的に判断すべき」ことといった結論を導くことはできない。
原処分庁の主張は、事業者の最終的な目的以外の事情をも勘案して用途区分の判定を行うことを正当化しようとするものであるが、以上のとおり、そのように解すべき合理的な根拠は原処分庁からは一切提示されていない。
ウ 原処分庁の解釈は過去の国税庁の取扱いと整合しない 上記(3)で詳述したとおり、事業者の最終的な目的ではない副次的対価については用途区分の判定において考慮しないというのが、消費税法創設時以来の確立した解釈となっている。これに対し、原処分庁の主張は、客観的に発生するあらゆる対価を考慮して用途区分の判定を行うことを強要するものであり、かかる原処分庁の解釈は上記の確立した解釈と整合しないというべきである。消費税法創設当時において用途区分の判定は「課税仕入れ等を行った時に合理的に判定する」(甲11)とされ、「合理的」な判定とは事業者の仕入れの最終的な目的に基づく判断をいうとされていたのであるから、これを「客観的に判断すべき」と言い換えることにより仕入れの最終的な目的以外の事情を考慮して用途区分の判定を行うことは許されないというべきである。
とりわけ、平成9年事案では、納税者が建物を購入した時点で建物が住宅貸付けに供されていたという点で本件の事案と全く同じ事案において、販売目的で取得した不動産について生じる賃料は副次的な対価に過ぎないから用途区分の判定において考慮されないと明確に判断されており、原処分庁の解釈はこの平成9年事案の判断と真正面から抵触する不当な解釈である。
エ 原処分庁が依拠する裁判例はいずれも本件の先例とはならない 原処分庁は、自説の根拠となる裁判例として、①さいたま地裁平成25年6月26日判決(税務訴訟資料263号順号12241)(甲10)、②東京地裁平成24年9月7日判決(税務訴訟資料262号順号12032)(甲24)、③名古屋地裁平成26年10月23日判決(税務訴訟資料264号順号12553)(甲25)を引用している(甲23 本件更正処分等に係る審査請求の答弁書11枚目(同書別紙の「(22)枚のうち(10)枚目」とされている頁)4行目~7行目)。
しかしながら、いずれの裁判例も、本件とは事案が異なるため、本件の判断にあたり先例として取り扱うべきものではない。
まず、①のさいたま地裁判決は、事業者によるマンションの取得がマンションの販売に加えてその賃貸をも目的としていたとして、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とされた事案である。しかし、上記(3)で原告が言及した課税当局の過去の判断は、同判決に一切引用されておらず、従って裁判所の判断の基礎となっていないことが伺えるから、その判旨の正当性には疑問がある。加えて、同事案において、納税者は問題となったマンションを法人税の確定申告書の提出時には「固定資産」に計上しており、その後、税務署担当官の指摘を受けて、修正申告書を提出して「棚卸資産」に変更している。従って、さいたま地裁判決の事案は、当初から「棚卸資産」として税務処理されており販売目的が明確である本件とは異なり、マンションの取得時においては販売だけでなく賃貸をも最終的な目的としていたということができる事案であるから、本件とは事案を異にする。
また、②の東京地裁判決は、いわゆるPFI(公共施設の維持、管理等を民間の事業者が地方公共団体から委託を受けて行うこと)の事案であり、事業者である納税者が地方自治体から受領する施設の整備に関する対価が課税売上である元本部分と非課税売上である金利部分から構成されていたという事案において、納税者が当該対価を得るために行った課税仕入れが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるとされた事案である。この事案は、地方自治体との間で合意した対価の額を課税売上と非課税売上に契約上配分したという事実が認定されており、そのため課税売上と非課税売上が事業者の最終的な目的であるということができる事案であるから、課税売上である建物の販売と非課税売上である住宅貸付けの賃料が明確に分かれており、前者が最終的な目的であり後者は副次的な対価である本件とは事案を異にする。
最後に、③の名古屋地裁判決は、建物の一部を事業用賃貸(課税資産の譲渡等)に供し、その余の一部を住宅貸付け(その他の資産の譲渡等)に供する目的で建物を建築したという事案において、当該建物の建築費等が「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であると判断された事案である。しかし、同判決は、用途区分をどのように判定するかが争点となった事案ではなく、用途区分の判定時期が争点となった事案である。すなわち、同事案では、納税者(原告)が、仕入れが行われた課税期間の末日までに事業用賃貸のみが開始され住宅貸付けが開始されなかったことを踏まえて、用途区分の判定は課税期間の末日の時点で判断するべきであり、従って当該仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であると主張したが、裁判所は課税仕入れが行われた日の状況によって判断すべきであるとして納税者の主張を否定した。以上のとおり、名古屋地裁判決は本件の争点である用途区分の判定の方法について判断を下したものではないから、本件の先例とはならない。なお、同事案の納税者は建物の販売を目的として建物を建築したものではなく、建物を継続保有して事業用賃貸の賃料(課税売上)と住宅貸付けの賃料(非課税売上)の双方を得ることを目的として建物の建築を行ったものといえるから、原告の主張する解釈によれば、納税者の最終的な目的は課税売上と非課税売上の双方を得ることにあり、裁判所の結論と同じく「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」となる。
以上のとおり、原処分庁がその判断の正当性の根拠として引用する裁判例は、いずれも本件の先例とはならないというべきである。
(7)小括 以上より、本件課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するものであり、本件課税仕入れが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当することを前提として行われた本件更正処分等は違法な行政処分であるから、速やかに取り消されるべきである。
4 本件更正処分等は法の執行における平等取扱原則に反する違法な行政処分である 本件更正処分等は、他の多くの納税者においては「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が課税当局によって是認されている中で、原告についてかかる税務処理を認めず、ことさらに原告を不利益に取り扱うものであるから、我が国の憲法が要請する平等取扱原則にも違反する違法なものであるというべきである。
すなわち、憲法第14条第1項に由来する「平等取扱原則」は、法の執行の段階においても妥当するとされており、同一の状況にある納税者のうち、一方に対しては課税処分を行いながら、他方に対して課税処分を行わないことは、この平等取扱原則に違反するというべきである(甲26 金子宏『租税法(第22版)』、甲27 大阪高裁昭和44年9月30日判決(高裁民集22巻5号682頁)(スコッチライト事件))。
朝長英樹税理士によると、本件の論点についての課税当局の対応は一貫しておらず、原告のように非課税売上の多寡にかかわらず一律否認された納税者がいる一方で、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者、マンションの取得から販売までの期間が短いものを除いた上で否認を受けた納税者、賃貸収入の否認だけで済んだ納税者が存在する(甲6 朝長税理士陳述書6.(7頁~8頁))。さらに、朝長英樹税理士によると、原告に対する税務調査における担当者の発言等を踏まえると、原告のように一律否認を受けたものがいる一方で、課税当局の方針として、ある程度の非課税売上がある物件だけを否認するというものや、課税期間の末日に所有している物件だけを否認するというものが存在することが伺われる(甲6 朝長税理士陳述書6.(7頁~8頁))。
以上のとおり、本件の論点に対する課税当局の判断は区々として一貫性がなく、憲法第14条第1項が要請する法の執行における平等取扱原則に著しく反する事態が生じている。そのような状況の中で、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理が税務調査で是認された納税者等が存在するにもかかわらず、原告に対して「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」としての税務処理は認められないとして課税処分を行うことは、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱うものであるから、平等取扱原則の観点から許されないというべきである。
以上より、本件更正処分等は憲法第14条第1項に反する違法な行政処分であるというべきである。
第4 被告は本件更正処分等の違法性を判断するために必要な内部資料等を提出すべきである 本件に関する原告の主張は現時点において以上のとおりであるが、朝長税理士意見書(甲5)Ⅰ3.(11)(57頁~58頁)が指摘するとおり、本件更正処分等の前に課税当局が本件及び本件に類似する事例において用途区分の判定をどのように判断していたかに関し、被告は、本件の課税の適否に適切な判断が下されるように協力するという立場に立ち、朝長税理士意見書が列挙する以下の資料を本法廷に提出すべきである。
① 国税庁及び東京国税局にデータとして保存されている仕入税額控除に関する全ての取扱いの目次
② 本件に類似する全ての事案の取扱いのデータ情報(「事例要旨」を収録したものの中の「仕入税額控除」の部分の目次と全ての事例要旨を含む。)
③ 平成9年事案に関する「質疑事項回答整理表」
④ 平成9年事案に関する「質疑事項整理表」の次葉の「〔部門一次担当意見〕の中の「参考」という部分に記載されている「参考3」及び「別添「消費税課意見」」
⑤ その「参考3」の前に存在するはずの「参考1」及び「参考2」
⑥ 「転売目的のマンションを居抜きで買い取った場合の仕入税額控除」という標題のデータ情報
第5 結語 以上のとおり、本件更正処分等は違法な処分であるから、速やかに取り消されるべきである。
以 上
脚注
1 以上とは別に、実際の仕入税額ではなく、課税売上高の一定割合を控除する簡易課税制度もあるが、本件には適用されないので説明を割愛する。
2 また、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と対になる「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」の意義についても同様の解釈がとられている(消費税取扱通達11-1-23)。
3 なお、照会内容は「課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することとなりますか。」とされ、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」となるかどうかが問われているのに対して、回答内容は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。」とされている。本件では照会にあるように「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という結論はおよそ採り難いものであり、また、問いと答えが整合していないが、これは、当初この事例が掲載された平成元年5月発行の『消費税一問一答』(甲15)では誤って答えが「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」であるとされたところを、その後国税庁がその誤りに気付き、『消費税一問一答(改訂版)』で答えを修正したときに問いが修正されなかったためであると考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.