解説記事2019年01月21日 【ニュース特集】 相続開始直前の現金引出し、当局は「故意の隠蔽」に照準(2019年1月21日号・№771)
ニュース特集
質問応答記録書で行為時の「認識」を証拠化
相続開始直前の現金引出し、当局は「故意の隠蔽」に照準
国税当局が、相続開始前の直前出金を「隠蔽行為」と判断した東京高裁平成30年7月11日判決に注目しているようだ。本判決は、裁判所が、納税者の出金時の認識を「過少申告の意図」(ことさら過少理論における重加賦課要件)ではなく、「隠蔽行為」(国税通則法68条1項)と評価するための根拠として認定した事例。国税当局は、本判決の内容を調査担当者等に情報提供する中で、相続開始前の直前出金による申告除外に対して重加算税の賦課を検討する場合、まずは積極的な(故意の)仮装隠蔽行為の事実が認められないかどうかを検討することが有効であると指摘。外形的行為のみで隠蔽行為の故意(認識)が明白でない場合には、行為時における行為者の認識を「質問応答記録書」で証拠化することが重要であるとしている。
重加算税の賦課要件(国税通則法、最高裁昭和62年判決)
国税当局が、調査担当者等に周知している平成30年7月11日判決を確認する前に、国税通則法68条1項、最高裁昭和62年5月8日判決から重加算税の賦課要件をみておきたい。
国税通則法68条1項は、「第65条1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を 隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」には、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨、規定している。
過少申告の認識は必要なし
上記の国税通則法68条1項に係る解釈を示したのが最高裁昭和62年5月8日判決だ。
同判決は、国税通則法68条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、納税者が申告に際して、過少申告を行うことの認識を有している必要はない旨、判示している(前頁・下掲参照)。
過少申告行為とは別に、故意の隠蔽行為が必要
国税通則法68条1項の規定及び最高裁昭和62年判決を踏まえ、国税当局は、重加算税の賦課要件について、以下のようにまとめている。
(1)過少申告をすることは「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」たことに該当すると解する余地もあるが(所得金額を殊更に過少に申告した内容虚偽の所得税確定申告書を提出する過少申告行為は「偽りその他不正の行為」に含まれる(最高裁昭和48年3月20日判決))、上記の重加算税の賦課要件は、あくまでも「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」であることから、過少申告の申告書の提出そのものとは別個の何らかの「隠蔽、仮装」行為があり、申告書の提出がこれに「基づく」(最高裁昭和62年判決では、「原因として」と表現)ものであるといえることが必要である。
(2)つまり、納税者に、過少申告行為とは別に、故意(客観的に隠蔽、仮装となる行為の認識)に課税要件事実の隠蔽又は仮装の行為があり、その隠蔽、仮装行為に基づき(原因として)過少申告の結果が発生したものであれば足り、申告に際して、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない(図表1参照)。
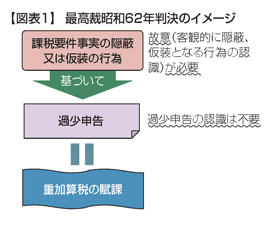
「ことさら過少理論」を示した最高裁平成7年判決
重加算税の賦課要件の原則は、上記の最高裁昭和62年判決の判断となるが、国税当局は、同判決の場合以外(証拠書類の廃棄、架空契約書の作成などの積極的な隠蔽、仮装行為がない場合)で最高裁が重加算税を賦課できるケースを示したものとして、最高裁平成7年4月28日判決を挙げている。
この最高裁平成7年判決の判例理論が、いわゆる「ことさら過少理論」とされるものである。
過少申告の意図+特段の行動 重加算税の賦課要件について、最高裁平成7年判決は、次の解釈を示した。
税理士に対して所得を秘匿
上記の解釈を示したうえで、最高裁は、本事案について、「上告人は、①昭和60年から62年までの3箇年にわたって、税務署長に所得税の確定申告をするに当たり、株式等の売買による前記多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、あえて申告書にこれを全く記載しなかったのみならず、②右各年分の確定申告書の作成を顧問税理士に依頼した際に、同税理士から、その都度、同売買による所得の有無について質問を受け、資料の提出も求められたにもかかわらず、確定的な脱税の意思に基づいて、右所得のあることを同税理士に対して秘匿し、何らの資料も提供することなく、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させ、③これを税務署長に提出したものである」と認定。「右によれば、上告人は、当初から所得を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものであるから、その意図に基づいて上告人のした本件の過少申告行為は、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たすものというべきである」と結論づけている。
なお、国税当局が、納税者の「特段の行動」として、税理士に対する所得の秘匿(最高裁平成7年4月28日判決)、税務調査における虚偽資料の提出等(最高裁平成6年11月22日判決)を重視している点については、本誌725号4頁を参照。
2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するか検討
最高裁平成7年判決について、国税当局は、最高裁昭和62年判決の重加算税の賦課要件を前提とした上で、過少申告行為とは別に積極的な隠蔽・仮装行為が存在しない場合においても、上記①~③のような場合には、重加算税の賦課要件を満たすとする判例理論(ことさら過少理論)を示したものと指摘(図表2参照)。
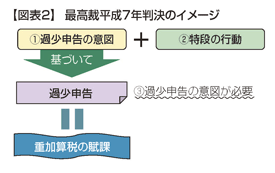 最高裁昭和62年判決とことさら過少理論の最高裁平成7年判決は場面が異なるものであり、矛盾するものではないことから、重加算税の賦課を検討する場合には、調査により把握した事実関係から、上記2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するのかを検討する必要があるとしている。
最高裁昭和62年判決とことさら過少理論の最高裁平成7年判決は場面が異なるものであり、矛盾するものではないことから、重加算税の賦課を検討する場合には、調査により把握した事実関係から、上記2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するのかを検討する必要があるとしている。
調査担当者等に周知された東京高裁平成30年判決
最高裁昭和62年判決、最高裁平成7年判決を念頭に、国税当局が調査担当者等に情報提供した東京高裁平成30年7月11日判決をみていきたい。
相続開始前に100回以上出金 事件の概要は、以下のようなものだ。
X(納税者)は、平成24年に死亡した被相続人の相続に係る相続税の申告書を提出した。
Y(課税庁)は、被相続人名義の預貯金及び有価証券(本件預貯金等)のほか、本件相続開始の約半年前から相続開始までの間に100回以上にわたり、Xが被相続人名義の本件預貯金口座から出金した5,180万円のうち、X名義の預金口座へ入金した1,070万円(被相続人からXへの返還請求権が発生したもの)及び自宅に保管していた現金3,810万円(本件現金)を被相続人の相続財産であるなどとして、相続税の更正処分をした。また、本件現金及び本件返還請求権を申告していなかったことは、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為に該当するとして、重加算税の賦課決定処分等をした。
「隠蔽」には当たらないと主張 Xは、本件預貯金等、本件現金及び本件返還請求権は、被相続人に帰属する相続財産ではなく、被相続人の亡夫(平成19年亡)の未分割財産であり、また、本件預貯金等は被相続人の固有財産と誤解して出金したものであり、「隠蔽」には当たらないなどと主張して、提訴した。
「ことさら過少理論」ではなく、本来の「隠蔽」行為を主張
本件では、被相続人名義の本件各預貯金口座から相続開始前に現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内で保管した行為が、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当するか否かが争点の1つとされた。
税理士の関与も虚偽答弁もなし 上記争点に係る国側の主張方針は、いわゆる「ことさら過少理論」による主張ではなく、本来の国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為について主張立証するというもの(図表3参照)。「ことさら過少理論」を採用しなかった理由は、本件ではXの相続税の申告に当たり税理士は関与しておらず、また、Xは調査担当者に対し、直前出金の事実を隠匿することなくその現金の所在や使途を説明しており、虚偽答弁等が認められなかったからだ。なお、国側が、「隠蔽」行為に該当するものとして主張した各事実及びそれを立証するために裁判所へ提出した主な証拠については、図表4を参照。
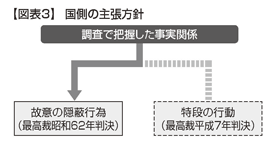
被相続人の帰属財産と判明しにくい状態を作出
本件について、裁判所は、Ⅰ Xは、本件預貯金等を被相続人の相続財産として申告をする必要があることを認識していた、Ⅱ Xは、相続税課税の対象となるのは相続開始時の被相続人の預貯金であり、それ以前に被相続人名義の預貯金から引き出してしまえば相続税を軽減できるという単純な考えを有していた、Ⅲ 本件相続開始前に本件各預貯金口座から預貯金残高の大半を占め、かつ、被相続人の医療費等の支払に要する額を大幅に上回る現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内に保管していたことを事実として認定。
Xは、外形的に本件現金及び本件返還請求権が被相続人に帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出しており、これら一連の行為は、故意に課税標準又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠す行為であり、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると判断している(図表5参照)。
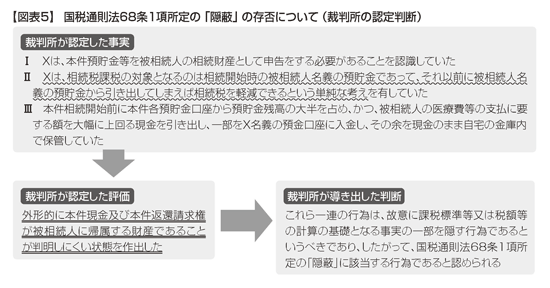
単純な考えに基づく申告でも、重加算税を免れず
また、裁判所は、最高裁昭和62年判決の判示内容(国税通則法68条1項に規定する重加算税は故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではなく、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない)からすれば、Xが相続開始前に被相続人名義の預貯金から現金を引き出しておけば相続税を軽減できるという単純な考えを有し、そのような認識に基づいて本件相続に係る相続税の申告をしたとしても、重加算税を免れることはできないと指摘。
Xは、隠蔽の状態を利用して、本件現金及び本件返還請求権を被相続人の相続財産として記載せずに本件申告書を提出したのであるから、「隠蔽」をしたところに基づき本件申告書を提出したと認められるとしている。
「まずは積極的な仮装隠蔽行為の検討をしてみるべし」
東京高裁平成30年判決を受けて、国税当局は、相続税の調査で被相続人の相続財産である預貯金口座等からの直前出金による申告除外が判明し、重加算税の賦課を検討する場合、まずは積極的な(故意の)仮装隠蔽行為の事実が認められないかどうかを検討することが有効であるとしている。この指摘の背景には、調査担当者が直前出金に対して重加算税の賦課を検討する場合、「ことさら過少理論」に当てはめ、質問応答記録書の証拠収集をするケースが多い状況があるようだ。
的確に質問応答記録書に録取 なお、国税当局は、「ことさら過少理論」による「特段の行動」としての証拠収集が困難であった本件において、Xが本件預貯金等を相続財産として申告する必要があることを認識し、相続開始時以前の預貯金からの引出しで相続税を軽減できると考えていたことについて、的確に質問応答記録書に録取し、証拠化することで、積極的な仮装隠蔽行為を主張したことは、今後の調査の参考になるとしている。
積極的な隠蔽行為の判断過程で納税者の認識を認定
故意(認識)を明らかにするため また、国税当局は、最高裁昭和62年判決が「申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない」としている点と、本件で裁判所が認定した事実、Ⅰ及びⅡの納税者の認識との関係について、以下のように説明している。
(1)申告に際して過少申告の認識は不要であるが、隠蔽行為自体には故意(客観的に隠蔽、仮装となる行為の認識)が必要であり、また、隠蔽行為、つまり「課税要件に該当する事実の全部又は一部をかくすこと」の「かくす」とは、「人に知られないようにする、(人に知られないように事実を)いつわる。」〔広辞苑〕ことを意味する。
(2)本件で裁判所が認定した事実である、Ⅲ「相続開始前に本件各預貯金口座から現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内で保管していた」は、それが故意又は認識しているものであるかは明白ではなかった。
(3)そこで、XのⅠ及びⅡの単純ではあるが、「かくす」ための動機といえる事実により故意(認識)を明らかにし、Ⅲの事実と併せて主張することにより、外形的に本件現金及び本件返還請求権が被相続人に帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出したものであり、これら一連の行為は、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると評価されたものである。
可能な限り多くの聴き取り等の証拠を収集
さらに、国税当局は、例えば、「現金を自宅床下に保管していた」など、行為そのものが客観的に「隠蔽」行為と評価できる場合はよいが、本件のように、行為のみではそれが故意又は認識しているものであるか明白でない場合は、行為時における行為者の故意(客観的に隠蔽となる行為の認識)に係る証拠(質問応答記録書)を収集することで納税者の「隠蔽」行為を認定することが可能になると強調。本件では、Ⅰ及びⅡの事実認定に係る証拠(図表4・国側の主張立証の(4)(5))は、「隠蔽」行為自体の故意(認識)の事実を支える証拠として有用であったと考えられることから、調査においては、課税要件事実を支える事実について可能な限り多くの聴き取り等の証拠を収集することが重要であると指摘している。
他の相続人から相続財産を「かくす」という理由でも
なお、国税当局は、本件では隠蔽行為の理由が相続税を軽減するためというものであったが、例えば、他の相続人から相続財産を「かくす」ためという理由であっても、その隠蔽行為に基づいて過少申告をした場合には重加算税の賦課要件を満たすとしている。
質問応答記録書で行為時の「認識」を証拠化
相続開始直前の現金引出し、当局は「故意の隠蔽」に照準
国税当局が、相続開始前の直前出金を「隠蔽行為」と判断した東京高裁平成30年7月11日判決に注目しているようだ。本判決は、裁判所が、納税者の出金時の認識を「過少申告の意図」(ことさら過少理論における重加賦課要件)ではなく、「隠蔽行為」(国税通則法68条1項)と評価するための根拠として認定した事例。国税当局は、本判決の内容を調査担当者等に情報提供する中で、相続開始前の直前出金による申告除外に対して重加算税の賦課を検討する場合、まずは積極的な(故意の)仮装隠蔽行為の事実が認められないかどうかを検討することが有効であると指摘。外形的行為のみで隠蔽行為の故意(認識)が明白でない場合には、行為時における行為者の認識を「質問応答記録書」で証拠化することが重要であるとしている。
重加算税の賦課要件(国税通則法、最高裁昭和62年判決)
国税当局が、調査担当者等に周知している平成30年7月11日判決を確認する前に、国税通則法68条1項、最高裁昭和62年5月8日判決から重加算税の賦課要件をみておきたい。
国税通則法68条1項は、「第65条1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を 隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」には、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨、規定している。
過少申告の認識は必要なし
上記の国税通則法68条1項に係る解釈を示したのが最高裁昭和62年5月8日判決だ。
同判決は、国税通則法68条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、納税者が申告に際して、過少申告を行うことの認識を有している必要はない旨、判示している(前頁・下掲参照)。
| 最高裁昭和62年5月8日判決 |
| 国税通則法68条に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠蔽又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政上の措置であって、故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではないから(最高裁昭和43年、45年判決)、同法68条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解するのが相当である。 |
過少申告行為とは別に、故意の隠蔽行為が必要
国税通則法68条1項の規定及び最高裁昭和62年判決を踏まえ、国税当局は、重加算税の賦課要件について、以下のようにまとめている。
(1)過少申告をすることは「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」たことに該当すると解する余地もあるが(所得金額を殊更に過少に申告した内容虚偽の所得税確定申告書を提出する過少申告行為は「偽りその他不正の行為」に含まれる(最高裁昭和48年3月20日判決))、上記の重加算税の賦課要件は、あくまでも「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」であることから、過少申告の申告書の提出そのものとは別個の何らかの「隠蔽、仮装」行為があり、申告書の提出がこれに「基づく」(最高裁昭和62年判決では、「原因として」と表現)ものであるといえることが必要である。
(2)つまり、納税者に、過少申告行為とは別に、故意(客観的に隠蔽、仮装となる行為の認識)に課税要件事実の隠蔽又は仮装の行為があり、その隠蔽、仮装行為に基づき(原因として)過少申告の結果が発生したものであれば足り、申告に際して、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない(図表1参照)。
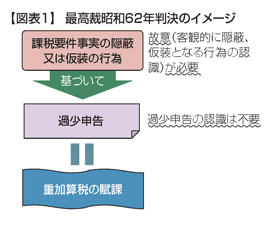
「ことさら過少理論」を示した最高裁平成7年判決
重加算税の賦課要件の原則は、上記の最高裁昭和62年判決の判断となるが、国税当局は、同判決の場合以外(証拠書類の廃棄、架空契約書の作成などの積極的な隠蔽、仮装行為がない場合)で最高裁が重加算税を賦課できるケースを示したものとして、最高裁平成7年4月28日判決を挙げている。
この最高裁平成7年判決の判例理論が、いわゆる「ことさら過少理論」とされるものである。
過少申告の意図+特段の行動 重加算税の賦課要件について、最高裁平成7年判決は、次の解釈を示した。
| 重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものである。しかし、右の重加算税制度の趣旨に鑑みれば架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、①当初から所得を過少に申告することを意図し、②その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、③その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされるものと解すべきである。 |
なお、国税当局が、納税者の「特段の行動」として、税理士に対する所得の秘匿(最高裁平成7年4月28日判決)、税務調査における虚偽資料の提出等(最高裁平成6年11月22日判決)を重視している点については、本誌725号4頁を参照。
2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するか検討
最高裁平成7年判決について、国税当局は、最高裁昭和62年判決の重加算税の賦課要件を前提とした上で、過少申告行為とは別に積極的な隠蔽・仮装行為が存在しない場合においても、上記①~③のような場合には、重加算税の賦課要件を満たすとする判例理論(ことさら過少理論)を示したものと指摘(図表2参照)。
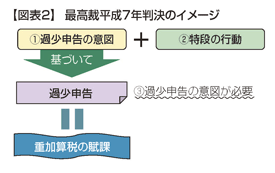 最高裁昭和62年判決とことさら過少理論の最高裁平成7年判決は場面が異なるものであり、矛盾するものではないことから、重加算税の賦課を検討する場合には、調査により把握した事実関係から、上記2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するのかを検討する必要があるとしている。
最高裁昭和62年判決とことさら過少理論の最高裁平成7年判決は場面が異なるものであり、矛盾するものではないことから、重加算税の賦課を検討する場合には、調査により把握した事実関係から、上記2つの最高裁判例のいずれの場合に該当するのかを検討する必要があるとしている。調査担当者等に周知された東京高裁平成30年判決
最高裁昭和62年判決、最高裁平成7年判決を念頭に、国税当局が調査担当者等に情報提供した東京高裁平成30年7月11日判決をみていきたい。
相続開始前に100回以上出金 事件の概要は、以下のようなものだ。
X(納税者)は、平成24年に死亡した被相続人の相続に係る相続税の申告書を提出した。
Y(課税庁)は、被相続人名義の預貯金及び有価証券(本件預貯金等)のほか、本件相続開始の約半年前から相続開始までの間に100回以上にわたり、Xが被相続人名義の本件預貯金口座から出金した5,180万円のうち、X名義の預金口座へ入金した1,070万円(被相続人からXへの返還請求権が発生したもの)及び自宅に保管していた現金3,810万円(本件現金)を被相続人の相続財産であるなどとして、相続税の更正処分をした。また、本件現金及び本件返還請求権を申告していなかったことは、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為に該当するとして、重加算税の賦課決定処分等をした。
「隠蔽」には当たらないと主張 Xは、本件預貯金等、本件現金及び本件返還請求権は、被相続人に帰属する相続財産ではなく、被相続人の亡夫(平成19年亡)の未分割財産であり、また、本件預貯金等は被相続人の固有財産と誤解して出金したものであり、「隠蔽」には当たらないなどと主張して、提訴した。
「ことさら過少理論」ではなく、本来の「隠蔽」行為を主張
本件では、被相続人名義の本件各預貯金口座から相続開始前に現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内で保管した行為が、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当するか否かが争点の1つとされた。
税理士の関与も虚偽答弁もなし 上記争点に係る国側の主張方針は、いわゆる「ことさら過少理論」による主張ではなく、本来の国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為について主張立証するというもの(図表3参照)。「ことさら過少理論」を採用しなかった理由は、本件ではXの相続税の申告に当たり税理士は関与しておらず、また、Xは調査担当者に対し、直前出金の事実を隠匿することなくその現金の所在や使途を説明しており、虚偽答弁等が認められなかったからだ。なお、国側が、「隠蔽」行為に該当するものとして主張した各事実及びそれを立証するために裁判所へ提出した主な証拠については、図表4を参照。
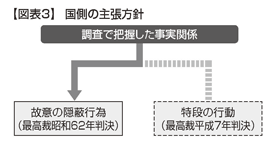
| 【図表4】国側が主張した事実及び立証 |
| 主張した事実 | 主な証拠 |
| (1)相続開始日以前に、Xが本件各預貯金口座から現金5,180 万円を引き出したこと | 預金照会回答 |
| (2)X が、上記(1)の現金のうち、1,070 万円を、相続開始日以前に、X 名義の預金口座へ入金したこと | 預金照会回答 |
| (3)X は、本件現金及びX 名義の預金口座に入金した現金を、本件申告において被相続人の相続財産として計上せず、本件相続開始日の箇所のみの各口座の通帳の写しを申告書に添付し、本件各預貯金口座について、出金後である本件相続開始日時点の残高にて申告していること | 相続税申告書、添付書類(本件各預貯金口座の通帳の写し(本件相続開始日の箇所のみ)) |
| (4)Xは、本件各預貯金口座から、相続開始前数か月の間に、出金した現金について、相続財産として申告しなかった理由につき、相続税の申告書に計上する金額は、相続開始日現在の残高で計算することを知っていたので、被相続人名義の預金から出金し、残高が減ることによって、相続税対策として現金を出金した旨を供述したこと | 質問応答記録書 |
| (5)X は、本件相続開始時点において自宅の金庫に保管していた本件現金及び被相続人の相続開始前にXの預金口座に入金された本件返還請求権に相当する金額を申告しなかったことについて、これらの財産を申告する必要があることは知っていたが、預金から現金にすることで預金の残高が減れば、その預金残高の金額で申告することで相続税を少なくできると考え出金を行い、これらの財産以外の預金残高で申告をした旨供述したこと | 質問応答記録書 |
被相続人の帰属財産と判明しにくい状態を作出
本件について、裁判所は、Ⅰ Xは、本件預貯金等を被相続人の相続財産として申告をする必要があることを認識していた、Ⅱ Xは、相続税課税の対象となるのは相続開始時の被相続人の預貯金であり、それ以前に被相続人名義の預貯金から引き出してしまえば相続税を軽減できるという単純な考えを有していた、Ⅲ 本件相続開始前に本件各預貯金口座から預貯金残高の大半を占め、かつ、被相続人の医療費等の支払に要する額を大幅に上回る現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内に保管していたことを事実として認定。
Xは、外形的に本件現金及び本件返還請求権が被相続人に帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出しており、これら一連の行為は、故意に課税標準又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠す行為であり、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると判断している(図表5参照)。
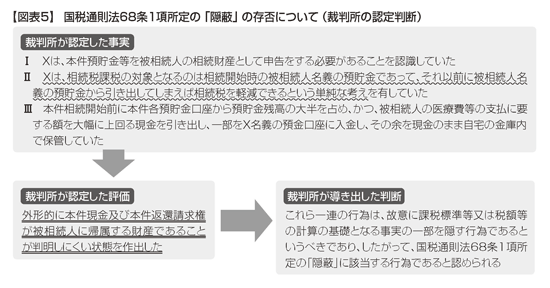
単純な考えに基づく申告でも、重加算税を免れず
また、裁判所は、最高裁昭和62年判決の判示内容(国税通則法68条1項に規定する重加算税は故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではなく、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない)からすれば、Xが相続開始前に被相続人名義の預貯金から現金を引き出しておけば相続税を軽減できるという単純な考えを有し、そのような認識に基づいて本件相続に係る相続税の申告をしたとしても、重加算税を免れることはできないと指摘。
Xは、隠蔽の状態を利用して、本件現金及び本件返還請求権を被相続人の相続財産として記載せずに本件申告書を提出したのであるから、「隠蔽」をしたところに基づき本件申告書を提出したと認められるとしている。
「まずは積極的な仮装隠蔽行為の検討をしてみるべし」
東京高裁平成30年判決を受けて、国税当局は、相続税の調査で被相続人の相続財産である預貯金口座等からの直前出金による申告除外が判明し、重加算税の賦課を検討する場合、まずは積極的な(故意の)仮装隠蔽行為の事実が認められないかどうかを検討することが有効であるとしている。この指摘の背景には、調査担当者が直前出金に対して重加算税の賦課を検討する場合、「ことさら過少理論」に当てはめ、質問応答記録書の証拠収集をするケースが多い状況があるようだ。
的確に質問応答記録書に録取 なお、国税当局は、「ことさら過少理論」による「特段の行動」としての証拠収集が困難であった本件において、Xが本件預貯金等を相続財産として申告する必要があることを認識し、相続開始時以前の預貯金からの引出しで相続税を軽減できると考えていたことについて、的確に質問応答記録書に録取し、証拠化することで、積極的な仮装隠蔽行為を主張したことは、今後の調査の参考になるとしている。
積極的な隠蔽行為の判断過程で納税者の認識を認定
故意(認識)を明らかにするため また、国税当局は、最高裁昭和62年判決が「申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない」としている点と、本件で裁判所が認定した事実、Ⅰ及びⅡの納税者の認識との関係について、以下のように説明している。
(1)申告に際して過少申告の認識は不要であるが、隠蔽行為自体には故意(客観的に隠蔽、仮装となる行為の認識)が必要であり、また、隠蔽行為、つまり「課税要件に該当する事実の全部又は一部をかくすこと」の「かくす」とは、「人に知られないようにする、(人に知られないように事実を)いつわる。」〔広辞苑〕ことを意味する。
(2)本件で裁判所が認定した事実である、Ⅲ「相続開始前に本件各預貯金口座から現金を引き出し、一部をX名義の預金口座に入金し、その余を現金のまま自宅の金庫内で保管していた」は、それが故意又は認識しているものであるかは明白ではなかった。
(3)そこで、XのⅠ及びⅡの単純ではあるが、「かくす」ための動機といえる事実により故意(認識)を明らかにし、Ⅲの事実と併せて主張することにより、外形的に本件現金及び本件返還請求権が被相続人に帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出したものであり、これら一連の行為は、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると評価されたものである。
可能な限り多くの聴き取り等の証拠を収集
さらに、国税当局は、例えば、「現金を自宅床下に保管していた」など、行為そのものが客観的に「隠蔽」行為と評価できる場合はよいが、本件のように、行為のみではそれが故意又は認識しているものであるか明白でない場合は、行為時における行為者の故意(客観的に隠蔽となる行為の認識)に係る証拠(質問応答記録書)を収集することで納税者の「隠蔽」行為を認定することが可能になると強調。本件では、Ⅰ及びⅡの事実認定に係る証拠(図表4・国側の主張立証の(4)(5))は、「隠蔽」行為自体の故意(認識)の事実を支える証拠として有用であったと考えられることから、調査においては、課税要件事実を支える事実について可能な限り多くの聴き取り等の証拠を収集することが重要であると指摘している。
他の相続人から相続財産を「かくす」という理由でも
なお、国税当局は、本件では隠蔽行為の理由が相続税を軽減するためというものであったが、例えば、他の相続人から相続財産を「かくす」ためという理由であっても、その隠蔽行為に基づいて過少申告をした場合には重加算税の賦課要件を満たすとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















