税務ニュース2013年04月15日 同族法人貸付、物納と評価単位の関係は(2013年4月15日号・№495) 相続人の事情(物納申請)で評価単位判定は左右されず
同族法人貸付、物納と評価単位の関係は
相続人の事情(物納申請)で評価単位判定は左右されず
課税当局では、被相続人が同族関係者である同族法人に貸し付けられている土地の評価単位について確認を行っている。具体的には、被相続人Aが図1のようなX土地を所有していた場合で、被相続人AおよびBは、XY土地をC社に賃貸借契約により貸し付けており、C社と連名で「土地の無償返還に関する届出書」を提出。X土地は、相続人Dが相続により取得し、AはC社の同族関係者であるというケースだ。
この場合の宅地の評価単位について、当局は、XY土地は、C社に貸し付けられており一体として利用されているが、貸主側の貸宅地の評価では、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価するとしている。
なお、X土地は貸宅地として評価するが、無償返還届出書の提出により自用地価額の80%に相当する金額となり、C社の株式評価上、X土地の借地権相当額(自用地価額の20%相当額)が資産の部に計上される。
また、当局では、自宅敷地として一体利用していた宅地を相続により取得した後、X、Yの2画地に分筆して、X画地について物納申請を行った場合の評価単位も検討(図2参照)。このケースでは、XY土地全体を1画地の宅地として評価するとしている。その理由は、相法22条の規定、評基通1(2)の定めから、評価単位の判定は課税時期の現況に基づいて行わなければならず、相続開始後の相続人の事情(物納申請)によって左右されものではないというものだ。また、物納申請を行ったとしても物納が許可されない場合や物納申請を取り下げる場合などがあることからも評価単位の判定に物納申請の有無を影響させることはできないとしている。
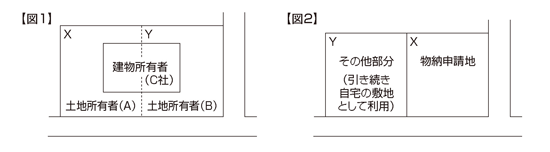
相続人の事情(物納申請)で評価単位判定は左右されず
|
この場合の宅地の評価単位について、当局は、XY土地は、C社に貸し付けられており一体として利用されているが、貸主側の貸宅地の評価では、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価するとしている。
なお、X土地は貸宅地として評価するが、無償返還届出書の提出により自用地価額の80%に相当する金額となり、C社の株式評価上、X土地の借地権相当額(自用地価額の20%相当額)が資産の部に計上される。
また、当局では、自宅敷地として一体利用していた宅地を相続により取得した後、X、Yの2画地に分筆して、X画地について物納申請を行った場合の評価単位も検討(図2参照)。このケースでは、XY土地全体を1画地の宅地として評価するとしている。その理由は、相法22条の規定、評基通1(2)の定めから、評価単位の判定は課税時期の現況に基づいて行わなければならず、相続開始後の相続人の事情(物納申請)によって左右されものではないというものだ。また、物納申請を行ったとしても物納が許可されない場合や物納申請を取り下げる場合などがあることからも評価単位の判定に物納申請の有無を影響させることはできないとしている。
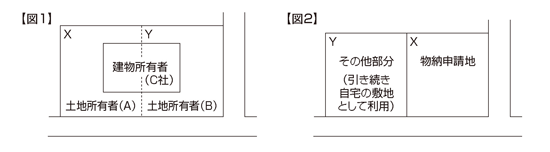
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























