資料1996年03月01日 【裁決事例】 譲渡土地に係る賃貸契約は実態を伴わないものであるから、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例(平成2年分所得税/更正処分は棄却、賦課決定処分は一部取消)
(平8.3.1裁決、裁決事例集No.51 236頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
審査請求人(以下「請求人」という。)は会社員であるが、平成2年分の所得税について、確定申告書に次表の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
次いで、請求人は、次表の「修正申告1」欄のとおりとする修正申告書を平成3年4月10日に提出した。
さらに、請求人は、次表の「修正申告2」欄のとおりとする修正申告書を平成3年5月20日に提出した。
J税務署長は、これに対し、平成3年12月24日付で次表の「更正処分等」欄のとおりの更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
(図一)
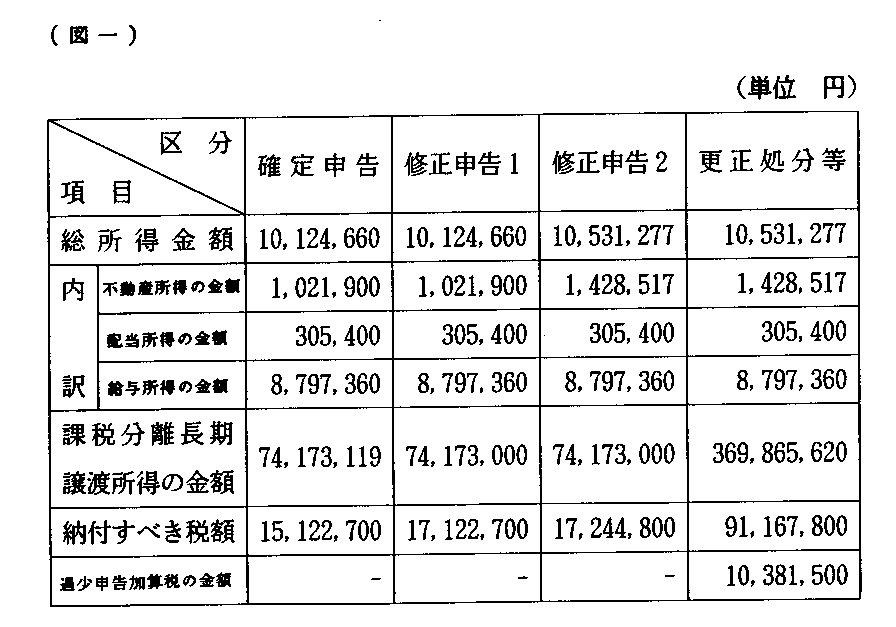
請求人は、これらの処分を不服として、平成4年2月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成4年5月12日付でいずれも棄却の異議決定をした。
請求人は、異議決定を経た後のこれらの処分に不服があるとして、平成4年6月12日に審査請求をした。
なお、請求人は、平成4年2月14日に住所をP市R町1丁目11番6―1301号からQ市S町一丁目6番20号に移動したので、これに伴い、原処分庁はJ税務署長からK税務署長となった。
その後、請求人は、平成5年3月19日にe国へ出国し、国内に住所及び居所を有していないこととなったが、L(請求人の母)が上記の住所地に引き続き居住しているので納税地に変動はない。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 更正処分について
請求人は、平成元年11月6日に株式会社M(以下「M社」という。)との間で次表の土地(以下「本件土地」という。)を404,114,547円で譲渡する旨の不動産売買契約を締結し、平成2年12月12日にM社に引き渡した。
(単位 平方メートル)
番号 所在 地番 地目 地積
1 Q市S町一丁目 2307番 宅 地 139.47
2 Q市S町一丁目 2308番 宅 地 133.85
合 計 273.32
次いで、請求人は、平成2年3月26日にN株式会社との間でT市W町三丁目169番2の宅地1,355.4平方メートル(以下「本件買換土地」という。)を410,000,000円で譲り受ける旨の不動産売買契約を締結し、同土地を取得した。
ところで、請求人は、本件土地の譲渡について、租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(以下「買換特例」という。)を適用して平成2年分の所得税の確定申告をした。
これに対して、原処分庁は、請求人がLとの間の本件土地の使用貸借が継続中であるにもかかわらず、昭和63年9月1日付で有限会社Sとの間で有限会社Sに本件土地を賃貸する旨の契約(以下「本件土地賃貸借契約」という。)をしたものであるから、本件土地賃貸借契約は実態の伴わない契約であり、請求人が有限会社Sに対し本件土地を賃貸していたものとは認められないとして、本件土地が、買換特例が適用される個人が事業の用に供していた資産(以下「事業用資産」という。)には該当しないと認定した上、本件土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額を更正した。
しかしながら、本件土地は、次のとおり事業用資産に該当するので、更正処分は違法である。
(イ)請求人が本件土地を取得し、本件土地賃貸借契約を締結するまでの経緯は、次のとおりである。
A Y(請求人の父)は、昭和45年に本件土地の上に次表の賃貸用倉庫(以下「本件建物」という。)を新築し、これをZ株式会社(以下「Z社」という。)との間で賃貸借契約(以下「Y賃貸借契約」という。)を結び賃貸していたが、昭和57年12月16日に死亡したことから、本件土地を請求人が相続し、本件建物をLが相続した。
所 在 Q市S町一丁目2308番地、2307番地
家屋番号 2308番
構造種類 鉄骨造スレート葺2階建 倉庫
床面積 1階 132.75平方メートル 2階 33.12平方メートル
B Lは、相続開始の日である昭和57年12月16日(以下「本件相続開始の日」という。)から昭和59年8月31日まで、上記のY賃貸借契約をそのまま継続して本件建物をZ社に賃貸していた。
なお、Lは、Y賃貸借契約を継続して本件建物をZ社に賃貸するに際し、本来は敷地である本件土地の所有者である請求人と本件土地の使用について協議をすべきであったが、Lは、従来の使用関係に変化がないものと判断し、請求人と協議をしなかったものである。
C Lは、不動産管理会社である有限会社Sが昭和59年9月1日に設立されたことに伴い、Yから引き継いだY賃貸借契約を合意解除した上で、同日付で有限会社Sとの間で、L所有の不動産を有限会社Sに賃貸する旨の不動産賃貸借契約(以下「本件建物等賃貸借契約」という。)を締結した。
本件建物等賃貸借契約を締結する際、貸主であるLも借主である有限会社Sの代表取締役A(請求人の兄Bの妻)も本件土地の使用関係については念頭になかったことから、本件土地は有限会社Sへの賃貸の対象にされていなかった。
D 請求人は、昭和60年7月からa国に単身赴任していたが、昭和63年8月にb本社勤務を命ぜられ同年9月14日に帰国した。
E 請求人は、有限会社Sが昭和59年9月1日に設立され、本件建物等賃貸借契約に基づきLから本件建物を賃借し、その管理・運用を営んでいること及び本件土地が本件建物等賃貸借契約に含まれていないことを、帰国して初めて知った。
F 請求人は、本件相続開始の日までさかのぼって、Lとの間で本件土地に係る賃貸契約をして、その間の地代を請求することも可能であったが、母と子の間柄であり、昭和63年8月までは地代を請求せず、Lとの使用貸借を本件相続開始の日までさかのぼって追認することとした。
G 請求人は、昭和63年9月1日にLとの間の本件土地に係る使用貸借契約を合意解除し、同日付で有限会社Sとの間で、本件土地賃貸借契約を締結した。
(ロ)建物の所有者とその敷地の所有者が相違し、その建物が第三者に賃貸されるという場合、建物所有者が受け取る家賃の中に敷地利用の対価が含まれているから、建物所有者はその家賃の一部を地代として敷地所有者に支払うというのが通常の契約の方法である。
しかし、本件の場合は、本件建物の所有者がその敷地の所有者である請求人の母親であり、本件建物の賃借人(有限会社S)及び本件建物の転借人(Z社)が請求人の親族によって設立された同族会社であることから、本件建物の賃貸関係と本件土地の賃貸関係とに混乱が生じ、本件土地の所有者である請求人の立場を不安定にするというような危険の発生は考えられない。
そこで、(1)請求人は本件土地を有限会社Sに賃貸し、(2)Lは本件建物を有限会社Sに賃貸し、(3)有限会社Sは本件土地及び本件建物を一括してZ社に転貸し、(4)有限会社Sが転貸収入から請求人及びLに対して賃借料を支払うという契約にしたものである。
本件建物及び本件土地の所有関係や賃借料の額を請求人、L及び有限会社Sの三者の間で明確にしておくという点で、上記のような契約の結び方にも合理性があるというべきである。
(ハ)請求人は、昭和63年9月から本件土地がM社に引き渡された平成2年12月の前月まで、本件土地賃貸借契約に基づく賃貸料を有限会社Sから受領し、平成元年分及び平成2年分については、所得税の確定申告書を提出して不動産所得の申告をしてきた。
ただし、昭和63年分についてはこの不動産所得の申告を失念したものである。
(ニ)以上のとおり、請求人は、本件土地を本件相続開始の日から昭和63年8月31日まではLに無償で貸し付けていたが、同年9月1日以後は有限会社Sに有償で賃貸していたものである。
したがって、本件土地は、買換特例が適用される事業用資産に該当する。
ロ 賦課決定処分について
上記イのとおり更正処分は違法であるから、その全部の取消しに伴い、過少申告加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり、いずれも適法である。
イ 更正処分について
(イ)本件土地及び本件建物について調査したところ、次の事実が認められる。
A 請求人、L及びBは、昭和58年6月10日付でYの遺産に係る分割協議書(以下「本件遺産分割協議書」という。)を作成した。
本件遺産分割協議書には、本件土地を請求人が相続し、本件建物をLが相続する旨の記載がある。
B 本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は昭和55年7月10日に昭和45年4月5日付新築を原因としてY名義で所有権保存の登記がされ、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYからLに所有権移転の登記がされている。
C 本件土地に係る登記簿謄本によれば、本件土地は昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYから請求人に所有権移転の登記がされている。
D Yは、Y賃貸借契約により本件建物をZ社へ賃貸していた。
また、Lは、本件相続開始の日から昭和59年9月1日に有限会社Sへ本件建物を貸し付けるまでの間、Y賃貸借契約をそのまま継続していた。
E Lは、昭和59年9月1日からM社へ引き渡す平成2年12月までの間、本件建物等賃貸借契約に基づき本件建物を有限会社Sへ貸し付けていた。なお、有限会社Sは、本件建物をZ社へ転貸していた。
F 請求人は、本件相続開始の日からM社へ引き渡す平成2年12月末日までの間、本件土地に係る地代又は権利金等をLから一度も受領してはいない。
G 請求人は、昭和63年9月1日付で有限会社Sとの間で本件土地賃貸借契約を締結した。
H 本件相続開始の日からM社へ引き渡されるまでの間、本件土地の上には本件建物以外の建物・構築物は建築されていない。
(ロ)上記(イ)の事実から判断すると、Lが本件土地の上に存在していた本件建物を本件相続開始の日から昭和59年8月までZ社に賃貸し、さらに、同年9月からM社へ引き渡すまで有限会社Sに賃貸していたのであるから、本件建物の所有者であるLと敷地の所有者である請求人との間には、本件相続開始の日からM社へ引き渡すまでの間、本件土地に係る賃借関係が継続して存在していたものと認められる。
そして、Lは、請求人に対して、本件土地に係る地代又は権利金等を一度も支払ったことがないから、本件土地の使用に係る請求人とLとの間の関係は、民法第593条に規定する「使用貸借」の関係であったと認められる。
本件土地賃貸借契約は、請求人が昭和63年9月1日付で本件建物の借家人である有限会社Sとの間で締結したものであるが、本件土地については、上記のとおり、請求人とLとの間で使用貸借関係が継続して存在していたのであるから重複して契約されたこととなり、本件土地賃貸借契約は実態を伴わない契約であると認められる。
よって、請求人の有限会社Sへの本件土地の賃貸は、措置法施行令第25条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第2項において事業に準ずるものとして規定されている、「事業と称するにいたらない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行なうもの」には当たらないから、本件土地は買換特例が適用される事業用資産には該当しないこととなる。
したがって、本件土地の譲渡には買換特例の適用がないとしてした原処分は適法である。
ロ 賦課決定処分について
上記イのとおり、更正処分は適法であり、かつ、請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、過少申告加算税の賦課決定処分も適法である。
3 判断
(1)更正処分について
本件土地が買換特例の対象となる事業用資産に該当するか否かについて争いがあるので、調査・審理したところ次のとおりである。
イ 次のことについては、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによってもその事実が認められる。
(イ)本件建物は、昭和45年4月5日にY所有の本件土地の上に新築され、Y賃貸借契約に基づいてZ社の高圧ガス取扱所として使用されていた。
Y賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和52年10月1日
賃 貸 人 Y 賃 借 人 Z株式会社
賃貸借物件 Q市S町一丁目2307・2308番地 倉庫(本件建物)
賃貸借期間 昭和52年10月1日から5年間
賃 貸 料 1か月350,000円
支払期日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人が自社の店舗及び倉庫の用途に使用する。
(ロ)Yは、昭和57年12月16日に死亡し、昭和58年6月10日付で作成された本件遺産分割協議書により、請求人が本件土地、Lが本件建物をそれぞれ相続した。
(ハ)Lは、Y賃貸借契約に基づく本件建物に係る賃貸借関係を、本件相続開始の日から昭和59年8月31日までの間そのまま継続させていた。
(ニ)Lは、昭和59年9月1日に不動産の賃貸及び管理を主な事業目的とする有限会社Sを設立して、同日付で同社との間で本件建物を含む同人所有の不動産について本件建物等賃貸借契約を締結し、以後、当該不動産の管理を有限会社Sに任せた。
本件建物等賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和59年9月1日
賃 貸 人 L 賃 借 人 有限会社S
賃貸借物件 1 Q市S町一丁目618番 宅地133.15平方メートル
2 〃 〃 617番地―4 居宅・事務所・倉庫
3 〃 〃 2307・2308番地 車庫(本件建物)
4 C市D町19番地 店舗・共同住宅
賃貸借期間 定めなし。
賃 貸 料 1か月1,000,000円
支払月日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人は他の者に転貸ができる。
(ホ)有限会社Sは、Z社との間でLからの賃貸借物件のうちの一つである本件建物を昭和59年9月1日からZ社に賃貸する旨の賃貸借契約(以下「有限会社S賃貸借契約」という。)を締結してこれを賃貸した。
有限会社S賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和59年9月1日
賃 貸 人 有限会社S 賃 借 人 Z株式会社
賃貸借物件 Q市S町一丁目2307・2308番地 車庫(本件土地)
賃貸借期間 昭和59年9月1日から昭和64年8月31日までの5年間
賃 貸 料 1か月410,000円
支払期日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人は自社の倉庫以外の用途に使用してはならない。
(ヘ)請求人は、有限会社Sとの間で昭和63年9月1日付の土地賃貸借契約書(以下「本件土地賃貸借契約書」という。)を作成し、本件土地賃貸借契約を締結して本件土地を賃貸した。
本件土地賃貸借契約書の主な内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和63年9月1日
賃 貸 人 請 求 人 賃 借 人 有限会社S
賃貸借物件 1 Q市S町一丁目2307・2308番 宅地 273.32平方メートル(本件土地)
賃貸借期間 昭和63年9月1日から昭和68年8月31までの5年間
賃 貸 料 1か月120,000円の割で年額1,440,000円
支払期日 定めなし。
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参又は振り込む。
特約事項 賃借人はZ社へ転貸する。
(ト)請求人及びLは、平成元年11月6日にM社との間で本件土地及び本件建物を総額406,000,000円(請求人が本件土地を404,114,547円、Lが本件建物を1,885,453円)でM社へ売却する旨の不動産売買契約を締結した。
(チ)請求人は、平成2年3月26日に本件買換土地をN株式会社から410,000,000円で購入した。
(リ)本件土地は、措置法第37条第1項の表の1号の上欄の「イ」に掲げる首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地に該当し、本件買換土地が措置法第37条第1項の表の1号の下欄の「イ」に掲げる土地等に該当する。
ロ 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。
(イ)本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は、昭和55年7月10日に昭和45年4月5日付新築を原因としてY名義で所有権保存の登記がされ、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYからLに所有権移転の登記がされ、平成2年12月10日付取壊しを原因としてその登記用紙が閉鎖されている。
(ロ)本件土地に係る登記簿謄本によれば、本件土地は、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYから請求人に所有権移転の登記がされ、平成2年12月12日付売買を原因として、M社に所有権移転登記がされている。
(ハ)本件土地の上には、本件相続開始の日から平成2年12月12日までの間、本件建物以外の建物・構築物は建築されていない。
(ニ)本件建物等賃貸借契約及び有限会社S賃貸借契約は、本件建物が取り壊される直前まで継続していた。
(ホ)請求人は、昭和58年3月に大学を卒業した後、就職した会社の都合によりLとは同居していない。
(ヘ)請求人及びLは、平成元年10月に本件土地及び本件建物の売却について、不動産業者であるE社の代表者F(以下「F」という。)と専任媒介契約を締結した。
(ト)有限会社Sの総勘定元帳には、請求人に対する本件土地の賃借料(以下「本件土地賃貸料」という。)が昭和63年9月から平成2年11月まで毎月末日に120,000円ずつ未払金として記載されている。
有限会社Sの未払金残高及びその支払状況は次表のとおりである。
(図二)
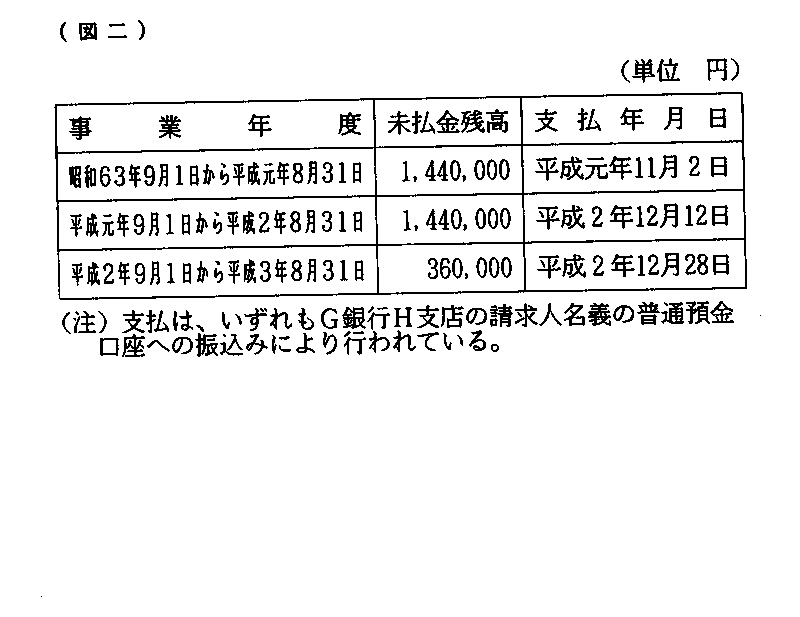
(チ)本件土地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「本件固定資産税等」という。)は、次表のとおりG銀行H支店のL名義の普通預金口座からQ市へ納付されている。
(単位 円)
昭和63年度分 平成元年度分 平成2年度分
振 替 金 額 振 替 金 額 振 替 金 額
年 月 日 年 月 日 年 月 日
昭和63年 71,600 平成元年 76,100 平成 2年 76,100
5月31日 5月 1日 5月 1日
昭和63年 68,000 平成 元年 74,000 平成 2年 74,000
8月 1日 7月31日 7月31日
昭和63年 68,000 平成 元年 74,000 平成 2年 74,000
12月26日 12月25日 12月25日
平成 元年 68,000 平成 2年 74,000 平成 3年 74,000
2月28日 2月28日 2月28日
合 計 275,600 合 計 298,100 合 計 298,100
(リ)Lが支払った本件固定資産税等を請求人が返済したかどうかが、G銀行H支店の請求人名義の預金口座からは確認ができない。
(ヌ)請求人の所得税の確定申告の状況は次のとおりである。
A 昭和63年分の確定申告書は提出していない。
B 平成元年分の確定申告において、昭和64年1月から平成元年12月までの、本件土地賃貸料1,440,000円を不動産所得に係る収入金額欄に、本件固定資産税等の合計額298,100円を必要経費欄に記載した確定申告書をJ税務署長に提出している。
C 平成2年分の確定申告において、平成2年1月から同年11月までの本件土地賃貸料1,320,000円を不動産所得に係る収入金額欄に、本件固定資産税等の合計額298,100円を必要経費欄に記載した確定申告書をJ税務署長に提出している。
(ル)Lは、昭和63年分の確定申告書の不動産所得の計算において、本件固定資産税等の合計額275,600円を必要経費に含めて記載した確定申告書をK税務署長に提出している。
ハ Lは、平成6年4月6日に当審判所に対して、次のとおり答述している。
(イ)請求人は昭和58年に大学を卒業してc株式会社に入社、d支店勤務となり、昭和59年4月から昭和60年7月までb本社勤務、同年7月から昭和63年8月までa国へ単身赴任し、昭和63年9月14日に帰国後b本社勤務、平成5年3月にe国f勤務となって現在に至っており、請求人が大学を卒業して以降は現在まで請求人とは同居したことがない。
(ロ)本件建物を相続で取得後、本件建物の敷地である本件土地に係る賃貸借契約を請求人との間で締結したことはなく、また、請求人に対して本件土地の賃借料の支払をしたこともない。
(ハ)a国から帰国した請求人から、土地を貸していれば地代をもらうのは当然のことだからと言われ、会計事務所に相談して請求人と有限会社Sとの間で本件土地賃貸借契約を締結した。
(ニ)平成元年8月に本件建物に対するg県の計量保安課の担当官の立入調査があり、多くの改善命令を受けたが、その全部をクリアすることは難しく、担当官に移転を指導されたので事業所の移転を決意した。
(ホ)本件建物は、平成2年12月7日までZ社の事業所として使用していたが、平成2年12月10日に取り壊した。
(ヘ)本件土地は、平成2年12月12日にM社へ引き渡した。
ニ Lは、平成6年7月18日に当審判所に対して、次のとおり記載した文書を提出している。
(イ)請求人が昭和60年7月にa国へ転勤してどれくらい過ぎた頃か分からないが、請求人から、Q市のことが気になり土地のことなど、どんな方法で経理等をしているかと電話があったが、遠いところで電話がうまくつながらず、そのときは話ができなかった。
(ロ)昭和63年になって請求人が帰国する少し前に請求人と一度か二度電話をしたが、帰ってからということで、同年9月14日に請求人が帰国したときに地代について話をした結果、金額等は関与税理士に任せることで合意した。
ホ 請求人の関与税理士であるh(以下、同人の事務所を「h経理事務所」という。)の事務員k(以下「k」という。)は、平成6年6月27日に当審判所に対し、次のとおり述べている。
(イ)有限会社Sは、現金主義により、銀行帳、金銭出納帳、振替伝票及び入出金伝票を同社で作成し、決算月に未払金等の決算調整をh経理事務所で行った上で、総勘定元帳、試算表及び決算書類を作成している。
(ロ)本件土地賃貸料は、有限会社Sの決算月に一括して計上したと思う。
(ハ)本件土地賃貸借契約書の用紙は、h経理事務所にある定形の書式に氏名や金額等を記入した原稿を基にh経理事務所の職員の妻にタイプを依頼して作成した。
(ニ)本件土地賃貸借契約書は、有限会社Sの事務所でL、同社の代表者A、自分及びh経理事務所の事務員が同席の上で作成した。押印されている請求人の印章は、Lが出したものを自分が押したかもしれない。
(ホ)本件土地賃貸借契約書は昭和63年9月1日付であるが同日には作成していない。しかし、少なくとも同年9月中には作成したと思う。
(ヘ)本件土地の譲渡に係る税金関係については、T市の土地を購入した際に、事業用の資産の買換えに該当するかどうか相談された。
なお、本件土地を売る時点では、その相談はなかったと記憶している。
(ト)Lの昭和63年分の所得税の確定申告は、前年のものを基本にして作成したために本件固定資産税等を必要経費に含めたものとなった。
(チ)請求人の昭和63年分所得税の確定申告は自分が失念した。
ヘ 請求人の代理人である税理士のmは、平成6年7月1日に当審判所に対し、本件土地賃貸借契約書のタイプ打ちはサービスでしたようであり、その代金の請求書がなく提示要求に応えることができない旨、昭和63年9月中に作成したことについては、自分の説明を信じてもらうほかない旨答述している。
ト Fは、平成6年5月13日に当審判所に対し、次のとおり述べている。
(イ)平成元年10月に本件土地の売却についての専任媒介契約をしたが、Lさんから具体的な話を受けたのはその契約をした1~2か月前であると思う。
(ロ)本件土地の売却依頼を受けたころ、土地譲渡の税金のことについて相談をうけ、登記簿謄本を取り寄せたら本件建物と本件土地の所有者が相続により異なっていた。そこで、事業用資産で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合に買換特例の適用が認められるかということを、顧問の税理士さんとよく相談するように話をしたと思う。
チ 措置法第37条第1項は、事業に準ずるものとして政令で定めるものの用に供していた資産も事業用資産に含まれる旨規定しており、これを受けた同法施行令第25条第2項は、事業用資産には事業に準ずるものとして、事業と称するにいたらない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行なうものの用に供していた資産も含まれる旨規定している。
この場合、「相当の対価を得て継続的に貸付け等の行為を行なう」とは、一般に、相当の所得を得る目的で継続的に対価を得て貸付け等の行為を行なうことをいい、継続的に貸付け等の行為を行っているかどうかについては、原則として、その貸付け等に係る契約の効力の発生したときの現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうかによるものとされている。
また、買換特例は、その適用要件の一つとして、個人が所有している資産のうち、「所有者自らが事業の用に供している資産」を譲渡した場合に限って適用されるものである。
したがって、譲渡資産が事業の用に供されているとしても、その資産の所有者以外の者の事業の用に供している場合には、買換特例の適用はないことになる。
ただし、資産の所有者と生計を一にする親族がその資産を事業の用に供している場合には、資産の所有者自らが事業の用に供しているものとして、買換特例の適用があると解するのが相当である。
リ 上記イないしチの事実及び答述等に基づき、本件土地が買換特例の対象となる事業用資産に該当するか否かについて検討する。
(イ)請求人は、本件土地賃貸借契約について、本件土地賃貸借契約書のとおり適正に締結されたものであると主張する。
しかしながら、本件土地賃貸借契約の一方の当事者である請求人は、上記ハの(イ)のLの答述によれば、本件土地賃貸借契約書に記載されている契約日である昭和63年9月1日にはa国に依然として在住しており帰国していないはずであるから、契約書の契約日の記載は真正でないと認められる。
また、請求人に本件土地賃貸借契約書の作成費用に係る請求書の提示を求めたが、請求人がこれに応じないことから本件土地賃貸借契約書の作成時期をその作成費用の支払の事実から特定をすることもできない。
(ロ)本件固定資産税等は、昭和63年の第3期分以後も上記ロの(チ)及び(リ)のとおり、Lの普通預金口座から引き続き出金されているのに対し、請求人が出金額に相当する金員をLへ返済した事実は確認できない。
そして、上記ロの(ル)のとおり、Lは不動産所得の計算において本件固定資産税等を必要経費に含めて昭和63年分の所得税の確定申告をし、また、上記ロの(ヌ)のAのとおり、請求人は昭和63年分の確定申告書を提出していない。
この点について、kは、上記ホの(ホ)、(ト)及び(チ)のとおり、本件土地賃貸借契約書が作成されたのは、昭和63年9月中であり、本件固定資産税等をLの必要経費に含めて申告したのは前年のものを基にしたためであり、請求人の昭和63年分の確定申告は自分が失念したと述べている。
しかしながら、上記ホの(ニ)のkの述べたところによれば、(1)kは本件土地賃貸借契約書の作成に同席していること及び(2)Lの昭和63年分の必要経費に計上されている固定資産税等は物件ごとの自家消費割合が詳細に計算され、同計算はkが計算したことが認められることから、kは、昭和63年分のLの確定申告書を作成した当時、本件土地賃貸借契約が存在するのであれば、これを十分認識しうる立場にあり、かつ、Lの固定資産税等のあん分計算をする際には、課税物件及び所有名義を確認する必要があったと認められるから、上記のkの述べたことには信ぴょう性がない。
したがって、上記事実からすれば、Lの昭和63年分の所得税の確定申告書が作成された当時、本件土地賃貸借契約が締結されていたと認めることはできない。
(ハ)有限会社Sは、上記ロの(ト)のとおり、本件土地賃貸料を昭和63年9月1日から平成元年8月31日までの事業年度の未払金に計上し、平成元年11月2日に支払っているが、上記ホの(ロ)のkが述べたところによれば、同事業年度の本件土地賃貸料の記帳が行われたのは、有限会社Sの同事業年度の決算整理の時期である平成元年10月ころであることが認められる。
(ニ)上記イの(イ)、(ニ)ないし(へ)のとおり、本件土地又は本件建物について作成された各賃貸借契約書の中で本件土地賃貸借契約書のみが賃貸料の支払期日の定めがなく、この点について上記ホの(ハ)のとおり、本件土地賃貸借契約書はh経理事務所の定形の書式を利用して原稿を作成したものであるとkは述べているところ、一般的に不動産賃貸借契約は、賃料の支払期日を賃料の計算期間の直前又は直後とすることが通例であり、本件土地賃貸借契約書の作成に使用したh経理事務所の定形の書式にこれらの内容が記載されていなかったとは考えにくいことから、本件土地賃貸借契約書に賃料の支払期日の定めがないことは極めて不自然であると認められる。
(ホ)上記ハの(ニ)のLの答述及び上記トの(イ)のFが述べたところによれば、Lは、平成元年8月に本件土地及び本件建物の譲渡を決意したこと、また、平成元年10月に請求人及びLがFと本件土地及び本件建物について専任媒介契約を締結したことが認められる。
(ヘ)Fは、上記トの(ロ)の平成元年8月ないし9月ころ、本件土地が買換特例の対象になる事業用資産に該当するか否かについて税理士とよく相談するようにLに話した旨述べていることからすると、平成元年8月ないし9月ころは、Fが把握した事実関係の下では当然に本件土地に買換特例の適用があるとは考えられる状況ではなかったことが推認できる。
上記(イ)ないし(へ)の事実からすると、本件土地賃貸借契約は、本件土地賃貸借契約書の日付である昭和63年9月1日に締結されたものではなく、平成元年10月ころに買換特例の適用を受けんがために昭和63年9月1日までさかのぼって締結されたものであると認められる。
このことから、本件土地賃貸借契約に基づく貸付けは、賃貸借の実態を伴っていないと認められ、かつ、本件土地及び本件建物の売却を予定しながら、本件土地賃貸借契約が締結されていることから、本件土地賃貸借契約書に記載された契約期間が5年間になっているとしても、事業に準ずるものに該当するための要件である継続性を欠くと認められる。
ヌ 請求人は、(1)本件土地賃貸借契約はLとの間の本件土地の使用貸借契約を合意解除した上で適正に締結したものであること、(2)請求人とLは親子であり、有限会社SとZ社は請求人の同族関係会社であるから、本件土地賃貸借契約が請求人の立場を不安定にするような危険の発生は考えられず、所有関係や賃貸料の額を請求人、L及び有限会社Sの三者間で明確にしておくという点で、本件土地賃貸借契約には合理性があること及び(3)有限会社Sから受領した賃貸料については平成元年分及び平成2年分の所得税の確定申告において不動産所得として申告していることから、本件土地は事業用資産に該当すると主張する。
しかしながら、本件土地賃貸借契約書が買換特例の適用を受けんがために平成元年10月ころに作成されたものであって、本件土地は事業用資産に該当する条件を具備していないことは上記リのとおりである。
請求人がLとの本件土地の使用貸借契約を合意解除したと主張する昭和63年9月1日以後も、本件建物が取り壊される直前の平成2年12月7日まで、Lは、本件土地上の本件建物を所有して有限会社Sに賃貸することにより本件土地を無償で使用収益していたのであるから、請求人が、Lとの間の本件土地の使用貸借契約を合意解除したものとは認められない。
また、有限会社Sは、本件土地の利用権限を有するLから本件建物を賃借していたのであって、上記関係によって本件建物を十分に利用でき、本件土地賃貸借契約によって所有関係や賃貸料の額が明確になるなどの事情もうかがえないから、本件土地賃貸借契約を締結することについて特段の合理性があるとは認められない。
本件土地賃貸料を不動産所得として申告したからといって、直ちに本件土地賃貸借契約に基づく本件土地の貸付けが事業に準ずるものに当たることにはならない。
なお、請求人とLは、上記ロの(ホ)の事実及び上記ハの(イ)のLの答述によれば、生計を一にしていないと認められることから、本件土地は、上記チのとおり、「請求人が自ら事業の用に供していた資産」には該当しない。
したがって、本件土地は、買換特例の適用対象となる事業用資産であるとする請求人の主張は認めることができない。
以上のとおり、請求人の主張はいずれも理由がなく、原処分庁が、本件土地の譲渡所得の計算に当たり、買換特例を適用することができないとして行った更正処分は適法である。
(2)賦課決定処分について
上記(1)のとおり、更正処分は適法であり、また、請求人には、更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、過少申告加算税を賦課することは相当である。
ところで、更正処分により納付すべき税額に国税通則法第65条第1項及び第2項の規定を適用すると、過少申告加算税の額は10,275,500円となり、当該金額は賦課決定処分の金額に満たないから、過少申告加算税の賦課決定処分はその一部を取り消すべきである。
(3)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所において調査・審理したところによっても、これを不相当とする理由は認められない。
《裁決書(抄)》
1 事実
審査請求人(以下「請求人」という。)は会社員であるが、平成2年分の所得税について、確定申告書に次表の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
次いで、請求人は、次表の「修正申告1」欄のとおりとする修正申告書を平成3年4月10日に提出した。
さらに、請求人は、次表の「修正申告2」欄のとおりとする修正申告書を平成3年5月20日に提出した。
J税務署長は、これに対し、平成3年12月24日付で次表の「更正処分等」欄のとおりの更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
(図一)
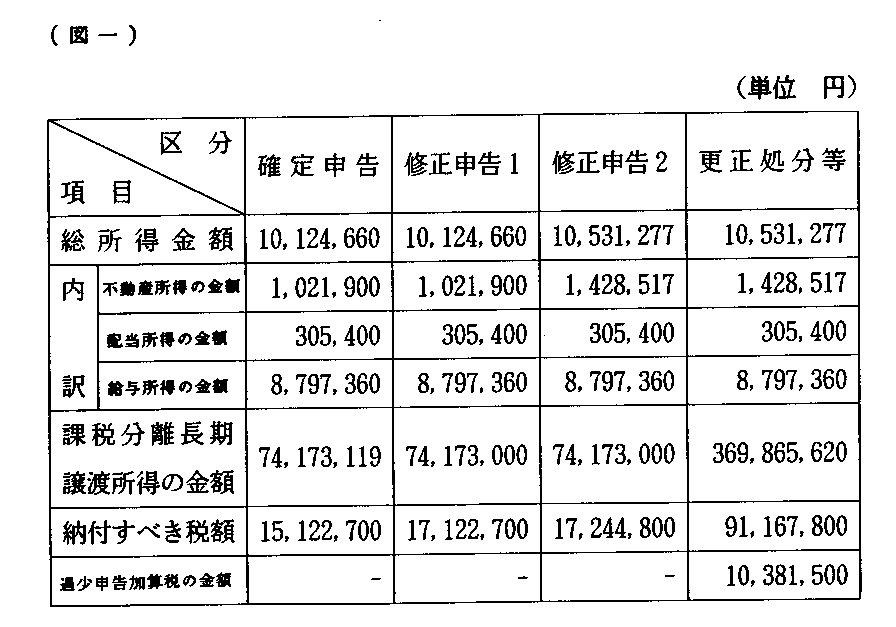
請求人は、これらの処分を不服として、平成4年2月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成4年5月12日付でいずれも棄却の異議決定をした。
請求人は、異議決定を経た後のこれらの処分に不服があるとして、平成4年6月12日に審査請求をした。
なお、請求人は、平成4年2月14日に住所をP市R町1丁目11番6―1301号からQ市S町一丁目6番20号に移動したので、これに伴い、原処分庁はJ税務署長からK税務署長となった。
その後、請求人は、平成5年3月19日にe国へ出国し、国内に住所及び居所を有していないこととなったが、L(請求人の母)が上記の住所地に引き続き居住しているので納税地に変動はない。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 更正処分について
請求人は、平成元年11月6日に株式会社M(以下「M社」という。)との間で次表の土地(以下「本件土地」という。)を404,114,547円で譲渡する旨の不動産売買契約を締結し、平成2年12月12日にM社に引き渡した。
(単位 平方メートル)
番号 所在 地番 地目 地積
1 Q市S町一丁目 2307番 宅 地 139.47
2 Q市S町一丁目 2308番 宅 地 133.85
合 計 273.32
次いで、請求人は、平成2年3月26日にN株式会社との間でT市W町三丁目169番2の宅地1,355.4平方メートル(以下「本件買換土地」という。)を410,000,000円で譲り受ける旨の不動産売買契約を締結し、同土地を取得した。
ところで、請求人は、本件土地の譲渡について、租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(以下「買換特例」という。)を適用して平成2年分の所得税の確定申告をした。
これに対して、原処分庁は、請求人がLとの間の本件土地の使用貸借が継続中であるにもかかわらず、昭和63年9月1日付で有限会社Sとの間で有限会社Sに本件土地を賃貸する旨の契約(以下「本件土地賃貸借契約」という。)をしたものであるから、本件土地賃貸借契約は実態の伴わない契約であり、請求人が有限会社Sに対し本件土地を賃貸していたものとは認められないとして、本件土地が、買換特例が適用される個人が事業の用に供していた資産(以下「事業用資産」という。)には該当しないと認定した上、本件土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額を更正した。
しかしながら、本件土地は、次のとおり事業用資産に該当するので、更正処分は違法である。
(イ)請求人が本件土地を取得し、本件土地賃貸借契約を締結するまでの経緯は、次のとおりである。
A Y(請求人の父)は、昭和45年に本件土地の上に次表の賃貸用倉庫(以下「本件建物」という。)を新築し、これをZ株式会社(以下「Z社」という。)との間で賃貸借契約(以下「Y賃貸借契約」という。)を結び賃貸していたが、昭和57年12月16日に死亡したことから、本件土地を請求人が相続し、本件建物をLが相続した。
所 在 Q市S町一丁目2308番地、2307番地
家屋番号 2308番
構造種類 鉄骨造スレート葺2階建 倉庫
床面積 1階 132.75平方メートル 2階 33.12平方メートル
B Lは、相続開始の日である昭和57年12月16日(以下「本件相続開始の日」という。)から昭和59年8月31日まで、上記のY賃貸借契約をそのまま継続して本件建物をZ社に賃貸していた。
なお、Lは、Y賃貸借契約を継続して本件建物をZ社に賃貸するに際し、本来は敷地である本件土地の所有者である請求人と本件土地の使用について協議をすべきであったが、Lは、従来の使用関係に変化がないものと判断し、請求人と協議をしなかったものである。
C Lは、不動産管理会社である有限会社Sが昭和59年9月1日に設立されたことに伴い、Yから引き継いだY賃貸借契約を合意解除した上で、同日付で有限会社Sとの間で、L所有の不動産を有限会社Sに賃貸する旨の不動産賃貸借契約(以下「本件建物等賃貸借契約」という。)を締結した。
本件建物等賃貸借契約を締結する際、貸主であるLも借主である有限会社Sの代表取締役A(請求人の兄Bの妻)も本件土地の使用関係については念頭になかったことから、本件土地は有限会社Sへの賃貸の対象にされていなかった。
D 請求人は、昭和60年7月からa国に単身赴任していたが、昭和63年8月にb本社勤務を命ぜられ同年9月14日に帰国した。
E 請求人は、有限会社Sが昭和59年9月1日に設立され、本件建物等賃貸借契約に基づきLから本件建物を賃借し、その管理・運用を営んでいること及び本件土地が本件建物等賃貸借契約に含まれていないことを、帰国して初めて知った。
F 請求人は、本件相続開始の日までさかのぼって、Lとの間で本件土地に係る賃貸契約をして、その間の地代を請求することも可能であったが、母と子の間柄であり、昭和63年8月までは地代を請求せず、Lとの使用貸借を本件相続開始の日までさかのぼって追認することとした。
G 請求人は、昭和63年9月1日にLとの間の本件土地に係る使用貸借契約を合意解除し、同日付で有限会社Sとの間で、本件土地賃貸借契約を締結した。
(ロ)建物の所有者とその敷地の所有者が相違し、その建物が第三者に賃貸されるという場合、建物所有者が受け取る家賃の中に敷地利用の対価が含まれているから、建物所有者はその家賃の一部を地代として敷地所有者に支払うというのが通常の契約の方法である。
しかし、本件の場合は、本件建物の所有者がその敷地の所有者である請求人の母親であり、本件建物の賃借人(有限会社S)及び本件建物の転借人(Z社)が請求人の親族によって設立された同族会社であることから、本件建物の賃貸関係と本件土地の賃貸関係とに混乱が生じ、本件土地の所有者である請求人の立場を不安定にするというような危険の発生は考えられない。
そこで、(1)請求人は本件土地を有限会社Sに賃貸し、(2)Lは本件建物を有限会社Sに賃貸し、(3)有限会社Sは本件土地及び本件建物を一括してZ社に転貸し、(4)有限会社Sが転貸収入から請求人及びLに対して賃借料を支払うという契約にしたものである。
本件建物及び本件土地の所有関係や賃借料の額を請求人、L及び有限会社Sの三者の間で明確にしておくという点で、上記のような契約の結び方にも合理性があるというべきである。
(ハ)請求人は、昭和63年9月から本件土地がM社に引き渡された平成2年12月の前月まで、本件土地賃貸借契約に基づく賃貸料を有限会社Sから受領し、平成元年分及び平成2年分については、所得税の確定申告書を提出して不動産所得の申告をしてきた。
ただし、昭和63年分についてはこの不動産所得の申告を失念したものである。
(ニ)以上のとおり、請求人は、本件土地を本件相続開始の日から昭和63年8月31日まではLに無償で貸し付けていたが、同年9月1日以後は有限会社Sに有償で賃貸していたものである。
したがって、本件土地は、買換特例が適用される事業用資産に該当する。
ロ 賦課決定処分について
上記イのとおり更正処分は違法であるから、その全部の取消しに伴い、過少申告加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり、いずれも適法である。
イ 更正処分について
(イ)本件土地及び本件建物について調査したところ、次の事実が認められる。
A 請求人、L及びBは、昭和58年6月10日付でYの遺産に係る分割協議書(以下「本件遺産分割協議書」という。)を作成した。
本件遺産分割協議書には、本件土地を請求人が相続し、本件建物をLが相続する旨の記載がある。
B 本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は昭和55年7月10日に昭和45年4月5日付新築を原因としてY名義で所有権保存の登記がされ、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYからLに所有権移転の登記がされている。
C 本件土地に係る登記簿謄本によれば、本件土地は昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYから請求人に所有権移転の登記がされている。
D Yは、Y賃貸借契約により本件建物をZ社へ賃貸していた。
また、Lは、本件相続開始の日から昭和59年9月1日に有限会社Sへ本件建物を貸し付けるまでの間、Y賃貸借契約をそのまま継続していた。
E Lは、昭和59年9月1日からM社へ引き渡す平成2年12月までの間、本件建物等賃貸借契約に基づき本件建物を有限会社Sへ貸し付けていた。なお、有限会社Sは、本件建物をZ社へ転貸していた。
F 請求人は、本件相続開始の日からM社へ引き渡す平成2年12月末日までの間、本件土地に係る地代又は権利金等をLから一度も受領してはいない。
G 請求人は、昭和63年9月1日付で有限会社Sとの間で本件土地賃貸借契約を締結した。
H 本件相続開始の日からM社へ引き渡されるまでの間、本件土地の上には本件建物以外の建物・構築物は建築されていない。
(ロ)上記(イ)の事実から判断すると、Lが本件土地の上に存在していた本件建物を本件相続開始の日から昭和59年8月までZ社に賃貸し、さらに、同年9月からM社へ引き渡すまで有限会社Sに賃貸していたのであるから、本件建物の所有者であるLと敷地の所有者である請求人との間には、本件相続開始の日からM社へ引き渡すまでの間、本件土地に係る賃借関係が継続して存在していたものと認められる。
そして、Lは、請求人に対して、本件土地に係る地代又は権利金等を一度も支払ったことがないから、本件土地の使用に係る請求人とLとの間の関係は、民法第593条に規定する「使用貸借」の関係であったと認められる。
本件土地賃貸借契約は、請求人が昭和63年9月1日付で本件建物の借家人である有限会社Sとの間で締結したものであるが、本件土地については、上記のとおり、請求人とLとの間で使用貸借関係が継続して存在していたのであるから重複して契約されたこととなり、本件土地賃貸借契約は実態を伴わない契約であると認められる。
よって、請求人の有限会社Sへの本件土地の賃貸は、措置法施行令第25条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第2項において事業に準ずるものとして規定されている、「事業と称するにいたらない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行なうもの」には当たらないから、本件土地は買換特例が適用される事業用資産には該当しないこととなる。
したがって、本件土地の譲渡には買換特例の適用がないとしてした原処分は適法である。
ロ 賦課決定処分について
上記イのとおり、更正処分は適法であり、かつ、請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、過少申告加算税の賦課決定処分も適法である。
3 判断
(1)更正処分について
本件土地が買換特例の対象となる事業用資産に該当するか否かについて争いがあるので、調査・審理したところ次のとおりである。
イ 次のことについては、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによってもその事実が認められる。
(イ)本件建物は、昭和45年4月5日にY所有の本件土地の上に新築され、Y賃貸借契約に基づいてZ社の高圧ガス取扱所として使用されていた。
Y賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和52年10月1日
賃 貸 人 Y 賃 借 人 Z株式会社
賃貸借物件 Q市S町一丁目2307・2308番地 倉庫(本件建物)
賃貸借期間 昭和52年10月1日から5年間
賃 貸 料 1か月350,000円
支払期日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人が自社の店舗及び倉庫の用途に使用する。
(ロ)Yは、昭和57年12月16日に死亡し、昭和58年6月10日付で作成された本件遺産分割協議書により、請求人が本件土地、Lが本件建物をそれぞれ相続した。
(ハ)Lは、Y賃貸借契約に基づく本件建物に係る賃貸借関係を、本件相続開始の日から昭和59年8月31日までの間そのまま継続させていた。
(ニ)Lは、昭和59年9月1日に不動産の賃貸及び管理を主な事業目的とする有限会社Sを設立して、同日付で同社との間で本件建物を含む同人所有の不動産について本件建物等賃貸借契約を締結し、以後、当該不動産の管理を有限会社Sに任せた。
本件建物等賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和59年9月1日
賃 貸 人 L 賃 借 人 有限会社S
賃貸借物件 1 Q市S町一丁目618番 宅地133.15平方メートル
2 〃 〃 617番地―4 居宅・事務所・倉庫
3 〃 〃 2307・2308番地 車庫(本件建物)
4 C市D町19番地 店舗・共同住宅
賃貸借期間 定めなし。
賃 貸 料 1か月1,000,000円
支払月日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人は他の者に転貸ができる。
(ホ)有限会社Sは、Z社との間でLからの賃貸借物件のうちの一つである本件建物を昭和59年9月1日からZ社に賃貸する旨の賃貸借契約(以下「有限会社S賃貸借契約」という。)を締結してこれを賃貸した。
有限会社S賃貸借契約の主な契約内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和59年9月1日
賃 貸 人 有限会社S 賃 借 人 Z株式会社
賃貸借物件 Q市S町一丁目2307・2308番地 車庫(本件土地)
賃貸借期間 昭和59年9月1日から昭和64年8月31日までの5年間
賃 貸 料 1か月410,000円
支払期日 毎月末日
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参する。
特約事項 賃借人は自社の倉庫以外の用途に使用してはならない。
(ヘ)請求人は、有限会社Sとの間で昭和63年9月1日付の土地賃貸借契約書(以下「本件土地賃貸借契約書」という。)を作成し、本件土地賃貸借契約を締結して本件土地を賃貸した。
本件土地賃貸借契約書の主な内容は次表のとおりである。
契約年月日 昭和63年9月1日
賃 貸 人 請 求 人 賃 借 人 有限会社S
賃貸借物件 1 Q市S町一丁目2307・2308番 宅地 273.32平方メートル(本件土地)
賃貸借期間 昭和63年9月1日から昭和68年8月31までの5年間
賃 貸 料 1か月120,000円の割で年額1,440,000円
支払期日 定めなし。
支払方法 賃借人が賃貸人の住所に持参又は振り込む。
特約事項 賃借人はZ社へ転貸する。
(ト)請求人及びLは、平成元年11月6日にM社との間で本件土地及び本件建物を総額406,000,000円(請求人が本件土地を404,114,547円、Lが本件建物を1,885,453円)でM社へ売却する旨の不動産売買契約を締結した。
(チ)請求人は、平成2年3月26日に本件買換土地をN株式会社から410,000,000円で購入した。
(リ)本件土地は、措置法第37条第1項の表の1号の上欄の「イ」に掲げる首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地に該当し、本件買換土地が措置法第37条第1項の表の1号の下欄の「イ」に掲げる土地等に該当する。
ロ 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。
(イ)本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は、昭和55年7月10日に昭和45年4月5日付新築を原因としてY名義で所有権保存の登記がされ、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYからLに所有権移転の登記がされ、平成2年12月10日付取壊しを原因としてその登記用紙が閉鎖されている。
(ロ)本件土地に係る登記簿謄本によれば、本件土地は、昭和58年11月18日に昭和57年12月16日付相続を原因としてYから請求人に所有権移転の登記がされ、平成2年12月12日付売買を原因として、M社に所有権移転登記がされている。
(ハ)本件土地の上には、本件相続開始の日から平成2年12月12日までの間、本件建物以外の建物・構築物は建築されていない。
(ニ)本件建物等賃貸借契約及び有限会社S賃貸借契約は、本件建物が取り壊される直前まで継続していた。
(ホ)請求人は、昭和58年3月に大学を卒業した後、就職した会社の都合によりLとは同居していない。
(ヘ)請求人及びLは、平成元年10月に本件土地及び本件建物の売却について、不動産業者であるE社の代表者F(以下「F」という。)と専任媒介契約を締結した。
(ト)有限会社Sの総勘定元帳には、請求人に対する本件土地の賃借料(以下「本件土地賃貸料」という。)が昭和63年9月から平成2年11月まで毎月末日に120,000円ずつ未払金として記載されている。
有限会社Sの未払金残高及びその支払状況は次表のとおりである。
(図二)
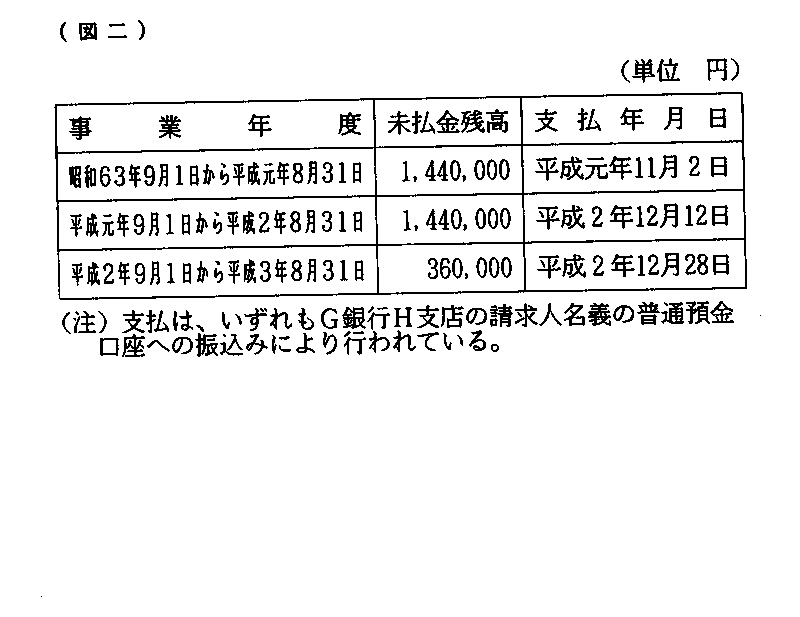
(チ)本件土地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「本件固定資産税等」という。)は、次表のとおりG銀行H支店のL名義の普通預金口座からQ市へ納付されている。
(単位 円)
昭和63年度分 平成元年度分 平成2年度分
振 替 金 額 振 替 金 額 振 替 金 額
年 月 日 年 月 日 年 月 日
昭和63年 71,600 平成元年 76,100 平成 2年 76,100
5月31日 5月 1日 5月 1日
昭和63年 68,000 平成 元年 74,000 平成 2年 74,000
8月 1日 7月31日 7月31日
昭和63年 68,000 平成 元年 74,000 平成 2年 74,000
12月26日 12月25日 12月25日
平成 元年 68,000 平成 2年 74,000 平成 3年 74,000
2月28日 2月28日 2月28日
合 計 275,600 合 計 298,100 合 計 298,100
(リ)Lが支払った本件固定資産税等を請求人が返済したかどうかが、G銀行H支店の請求人名義の預金口座からは確認ができない。
(ヌ)請求人の所得税の確定申告の状況は次のとおりである。
A 昭和63年分の確定申告書は提出していない。
B 平成元年分の確定申告において、昭和64年1月から平成元年12月までの、本件土地賃貸料1,440,000円を不動産所得に係る収入金額欄に、本件固定資産税等の合計額298,100円を必要経費欄に記載した確定申告書をJ税務署長に提出している。
C 平成2年分の確定申告において、平成2年1月から同年11月までの本件土地賃貸料1,320,000円を不動産所得に係る収入金額欄に、本件固定資産税等の合計額298,100円を必要経費欄に記載した確定申告書をJ税務署長に提出している。
(ル)Lは、昭和63年分の確定申告書の不動産所得の計算において、本件固定資産税等の合計額275,600円を必要経費に含めて記載した確定申告書をK税務署長に提出している。
ハ Lは、平成6年4月6日に当審判所に対して、次のとおり答述している。
(イ)請求人は昭和58年に大学を卒業してc株式会社に入社、d支店勤務となり、昭和59年4月から昭和60年7月までb本社勤務、同年7月から昭和63年8月までa国へ単身赴任し、昭和63年9月14日に帰国後b本社勤務、平成5年3月にe国f勤務となって現在に至っており、請求人が大学を卒業して以降は現在まで請求人とは同居したことがない。
(ロ)本件建物を相続で取得後、本件建物の敷地である本件土地に係る賃貸借契約を請求人との間で締結したことはなく、また、請求人に対して本件土地の賃借料の支払をしたこともない。
(ハ)a国から帰国した請求人から、土地を貸していれば地代をもらうのは当然のことだからと言われ、会計事務所に相談して請求人と有限会社Sとの間で本件土地賃貸借契約を締結した。
(ニ)平成元年8月に本件建物に対するg県の計量保安課の担当官の立入調査があり、多くの改善命令を受けたが、その全部をクリアすることは難しく、担当官に移転を指導されたので事業所の移転を決意した。
(ホ)本件建物は、平成2年12月7日までZ社の事業所として使用していたが、平成2年12月10日に取り壊した。
(ヘ)本件土地は、平成2年12月12日にM社へ引き渡した。
ニ Lは、平成6年7月18日に当審判所に対して、次のとおり記載した文書を提出している。
(イ)請求人が昭和60年7月にa国へ転勤してどれくらい過ぎた頃か分からないが、請求人から、Q市のことが気になり土地のことなど、どんな方法で経理等をしているかと電話があったが、遠いところで電話がうまくつながらず、そのときは話ができなかった。
(ロ)昭和63年になって請求人が帰国する少し前に請求人と一度か二度電話をしたが、帰ってからということで、同年9月14日に請求人が帰国したときに地代について話をした結果、金額等は関与税理士に任せることで合意した。
ホ 請求人の関与税理士であるh(以下、同人の事務所を「h経理事務所」という。)の事務員k(以下「k」という。)は、平成6年6月27日に当審判所に対し、次のとおり述べている。
(イ)有限会社Sは、現金主義により、銀行帳、金銭出納帳、振替伝票及び入出金伝票を同社で作成し、決算月に未払金等の決算調整をh経理事務所で行った上で、総勘定元帳、試算表及び決算書類を作成している。
(ロ)本件土地賃貸料は、有限会社Sの決算月に一括して計上したと思う。
(ハ)本件土地賃貸借契約書の用紙は、h経理事務所にある定形の書式に氏名や金額等を記入した原稿を基にh経理事務所の職員の妻にタイプを依頼して作成した。
(ニ)本件土地賃貸借契約書は、有限会社Sの事務所でL、同社の代表者A、自分及びh経理事務所の事務員が同席の上で作成した。押印されている請求人の印章は、Lが出したものを自分が押したかもしれない。
(ホ)本件土地賃貸借契約書は昭和63年9月1日付であるが同日には作成していない。しかし、少なくとも同年9月中には作成したと思う。
(ヘ)本件土地の譲渡に係る税金関係については、T市の土地を購入した際に、事業用の資産の買換えに該当するかどうか相談された。
なお、本件土地を売る時点では、その相談はなかったと記憶している。
(ト)Lの昭和63年分の所得税の確定申告は、前年のものを基本にして作成したために本件固定資産税等を必要経費に含めたものとなった。
(チ)請求人の昭和63年分所得税の確定申告は自分が失念した。
ヘ 請求人の代理人である税理士のmは、平成6年7月1日に当審判所に対し、本件土地賃貸借契約書のタイプ打ちはサービスでしたようであり、その代金の請求書がなく提示要求に応えることができない旨、昭和63年9月中に作成したことについては、自分の説明を信じてもらうほかない旨答述している。
ト Fは、平成6年5月13日に当審判所に対し、次のとおり述べている。
(イ)平成元年10月に本件土地の売却についての専任媒介契約をしたが、Lさんから具体的な話を受けたのはその契約をした1~2か月前であると思う。
(ロ)本件土地の売却依頼を受けたころ、土地譲渡の税金のことについて相談をうけ、登記簿謄本を取り寄せたら本件建物と本件土地の所有者が相続により異なっていた。そこで、事業用資産で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合に買換特例の適用が認められるかということを、顧問の税理士さんとよく相談するように話をしたと思う。
チ 措置法第37条第1項は、事業に準ずるものとして政令で定めるものの用に供していた資産も事業用資産に含まれる旨規定しており、これを受けた同法施行令第25条第2項は、事業用資産には事業に準ずるものとして、事業と称するにいたらない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行なうものの用に供していた資産も含まれる旨規定している。
この場合、「相当の対価を得て継続的に貸付け等の行為を行なう」とは、一般に、相当の所得を得る目的で継続的に対価を得て貸付け等の行為を行なうことをいい、継続的に貸付け等の行為を行っているかどうかについては、原則として、その貸付け等に係る契約の効力の発生したときの現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうかによるものとされている。
また、買換特例は、その適用要件の一つとして、個人が所有している資産のうち、「所有者自らが事業の用に供している資産」を譲渡した場合に限って適用されるものである。
したがって、譲渡資産が事業の用に供されているとしても、その資産の所有者以外の者の事業の用に供している場合には、買換特例の適用はないことになる。
ただし、資産の所有者と生計を一にする親族がその資産を事業の用に供している場合には、資産の所有者自らが事業の用に供しているものとして、買換特例の適用があると解するのが相当である。
リ 上記イないしチの事実及び答述等に基づき、本件土地が買換特例の対象となる事業用資産に該当するか否かについて検討する。
(イ)請求人は、本件土地賃貸借契約について、本件土地賃貸借契約書のとおり適正に締結されたものであると主張する。
しかしながら、本件土地賃貸借契約の一方の当事者である請求人は、上記ハの(イ)のLの答述によれば、本件土地賃貸借契約書に記載されている契約日である昭和63年9月1日にはa国に依然として在住しており帰国していないはずであるから、契約書の契約日の記載は真正でないと認められる。
また、請求人に本件土地賃貸借契約書の作成費用に係る請求書の提示を求めたが、請求人がこれに応じないことから本件土地賃貸借契約書の作成時期をその作成費用の支払の事実から特定をすることもできない。
(ロ)本件固定資産税等は、昭和63年の第3期分以後も上記ロの(チ)及び(リ)のとおり、Lの普通預金口座から引き続き出金されているのに対し、請求人が出金額に相当する金員をLへ返済した事実は確認できない。
そして、上記ロの(ル)のとおり、Lは不動産所得の計算において本件固定資産税等を必要経費に含めて昭和63年分の所得税の確定申告をし、また、上記ロの(ヌ)のAのとおり、請求人は昭和63年分の確定申告書を提出していない。
この点について、kは、上記ホの(ホ)、(ト)及び(チ)のとおり、本件土地賃貸借契約書が作成されたのは、昭和63年9月中であり、本件固定資産税等をLの必要経費に含めて申告したのは前年のものを基にしたためであり、請求人の昭和63年分の確定申告は自分が失念したと述べている。
しかしながら、上記ホの(ニ)のkの述べたところによれば、(1)kは本件土地賃貸借契約書の作成に同席していること及び(2)Lの昭和63年分の必要経費に計上されている固定資産税等は物件ごとの自家消費割合が詳細に計算され、同計算はkが計算したことが認められることから、kは、昭和63年分のLの確定申告書を作成した当時、本件土地賃貸借契約が存在するのであれば、これを十分認識しうる立場にあり、かつ、Lの固定資産税等のあん分計算をする際には、課税物件及び所有名義を確認する必要があったと認められるから、上記のkの述べたことには信ぴょう性がない。
したがって、上記事実からすれば、Lの昭和63年分の所得税の確定申告書が作成された当時、本件土地賃貸借契約が締結されていたと認めることはできない。
(ハ)有限会社Sは、上記ロの(ト)のとおり、本件土地賃貸料を昭和63年9月1日から平成元年8月31日までの事業年度の未払金に計上し、平成元年11月2日に支払っているが、上記ホの(ロ)のkが述べたところによれば、同事業年度の本件土地賃貸料の記帳が行われたのは、有限会社Sの同事業年度の決算整理の時期である平成元年10月ころであることが認められる。
(ニ)上記イの(イ)、(ニ)ないし(へ)のとおり、本件土地又は本件建物について作成された各賃貸借契約書の中で本件土地賃貸借契約書のみが賃貸料の支払期日の定めがなく、この点について上記ホの(ハ)のとおり、本件土地賃貸借契約書はh経理事務所の定形の書式を利用して原稿を作成したものであるとkは述べているところ、一般的に不動産賃貸借契約は、賃料の支払期日を賃料の計算期間の直前又は直後とすることが通例であり、本件土地賃貸借契約書の作成に使用したh経理事務所の定形の書式にこれらの内容が記載されていなかったとは考えにくいことから、本件土地賃貸借契約書に賃料の支払期日の定めがないことは極めて不自然であると認められる。
(ホ)上記ハの(ニ)のLの答述及び上記トの(イ)のFが述べたところによれば、Lは、平成元年8月に本件土地及び本件建物の譲渡を決意したこと、また、平成元年10月に請求人及びLがFと本件土地及び本件建物について専任媒介契約を締結したことが認められる。
(ヘ)Fは、上記トの(ロ)の平成元年8月ないし9月ころ、本件土地が買換特例の対象になる事業用資産に該当するか否かについて税理士とよく相談するようにLに話した旨述べていることからすると、平成元年8月ないし9月ころは、Fが把握した事実関係の下では当然に本件土地に買換特例の適用があるとは考えられる状況ではなかったことが推認できる。
上記(イ)ないし(へ)の事実からすると、本件土地賃貸借契約は、本件土地賃貸借契約書の日付である昭和63年9月1日に締結されたものではなく、平成元年10月ころに買換特例の適用を受けんがために昭和63年9月1日までさかのぼって締結されたものであると認められる。
このことから、本件土地賃貸借契約に基づく貸付けは、賃貸借の実態を伴っていないと認められ、かつ、本件土地及び本件建物の売却を予定しながら、本件土地賃貸借契約が締結されていることから、本件土地賃貸借契約書に記載された契約期間が5年間になっているとしても、事業に準ずるものに該当するための要件である継続性を欠くと認められる。
ヌ 請求人は、(1)本件土地賃貸借契約はLとの間の本件土地の使用貸借契約を合意解除した上で適正に締結したものであること、(2)請求人とLは親子であり、有限会社SとZ社は請求人の同族関係会社であるから、本件土地賃貸借契約が請求人の立場を不安定にするような危険の発生は考えられず、所有関係や賃貸料の額を請求人、L及び有限会社Sの三者間で明確にしておくという点で、本件土地賃貸借契約には合理性があること及び(3)有限会社Sから受領した賃貸料については平成元年分及び平成2年分の所得税の確定申告において不動産所得として申告していることから、本件土地は事業用資産に該当すると主張する。
しかしながら、本件土地賃貸借契約書が買換特例の適用を受けんがために平成元年10月ころに作成されたものであって、本件土地は事業用資産に該当する条件を具備していないことは上記リのとおりである。
請求人がLとの本件土地の使用貸借契約を合意解除したと主張する昭和63年9月1日以後も、本件建物が取り壊される直前の平成2年12月7日まで、Lは、本件土地上の本件建物を所有して有限会社Sに賃貸することにより本件土地を無償で使用収益していたのであるから、請求人が、Lとの間の本件土地の使用貸借契約を合意解除したものとは認められない。
また、有限会社Sは、本件土地の利用権限を有するLから本件建物を賃借していたのであって、上記関係によって本件建物を十分に利用でき、本件土地賃貸借契約によって所有関係や賃貸料の額が明確になるなどの事情もうかがえないから、本件土地賃貸借契約を締結することについて特段の合理性があるとは認められない。
本件土地賃貸料を不動産所得として申告したからといって、直ちに本件土地賃貸借契約に基づく本件土地の貸付けが事業に準ずるものに当たることにはならない。
なお、請求人とLは、上記ロの(ホ)の事実及び上記ハの(イ)のLの答述によれば、生計を一にしていないと認められることから、本件土地は、上記チのとおり、「請求人が自ら事業の用に供していた資産」には該当しない。
したがって、本件土地は、買換特例の適用対象となる事業用資産であるとする請求人の主張は認めることができない。
以上のとおり、請求人の主張はいずれも理由がなく、原処分庁が、本件土地の譲渡所得の計算に当たり、買換特例を適用することができないとして行った更正処分は適法である。
(2)賦課決定処分について
上記(1)のとおり、更正処分は適法であり、また、請求人には、更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、過少申告加算税を賦課することは相当である。
ところで、更正処分により納付すべき税額に国税通則法第65条第1項及び第2項の規定を適用すると、過少申告加算税の額は10,275,500円となり、当該金額は賦課決定処分の金額に満たないから、過少申告加算税の賦課決定処分はその一部を取り消すべきである。
(3)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所において調査・審理したところによっても、これを不相当とする理由は認められない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















