解説記事2020年10月26日 ニュース特集 第一弾 国・地域別ブレンディング&繰越制度の計算例(2020年10月26日号・№855)
ニュース特集
デジタル課税・青写真を読み解く
第一弾
国・地域別ブレンディング&繰越制度の計算例
OECDは10月12日、デジタル課税の青写真(Blueprint)を公表した。青写真は第1の柱(所得配分ルール及びネクサスルールの見直し)、第2の柱(ミニマムタックス)とも200頁を超える膨大な分量となっている。第1の柱ではスコープや残余利益の配分割合、第2の柱ではミニマム税率の水準など、政治判断を要する未解決の分野があり、また、青写真をもとに技術的な分野について市中協議が行われる(締め切りは12月14日)。これらを踏まえ、2021年半ばまでの合意を目指す。
青写真では、比較的高税率国である日本にとって無視できない存在となっている第2の柱における重要論点の一つである所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)において、租税負担割合をどの範囲で算出するかという「ブレンディング」の方法として、日本企業が望んでいた全世界ブレンディングではなく「国・地域別ブレンディング」が採用されることが明確になったほか、一過性の一時差異等によりIIRに捕捉されることを回避し、租税負担割合のボラティリティを平準化、あるいはより広く年度間の負担の平準化を図る観点から、①損失の繰越し、②現地租税繰越、③IIR税額控除、という3つの繰越制度が設けられることも判明している。
本特集では、この国・地域別ブレンディングと繰越制度について、適宜計算例を交えながら緊急レポートする。
国・地域別ブレンディング
トップアップ税額は3段階のプロセスを経て算出
デジタル課税・第2の柱(ミニマムタックス)の所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)においては、租税負担割合をどの範囲で算出するかという「ブレンディング」が大きな論点となっていたが、実はこの点については早い段階で、日本企業が望んでいた全世界ブレンディングではなく「国・地域別ブレンディング」とする方向が固まっていた。国・地域別ブレンディングが採用されることは、OECDが10月12日に公表したデジタル課税の「青写真(Blueprint)」でも確認できる。
以下、国・地域別ブレンディングにおけるトップアップ税額はどのように計算されるのか、青写真を読み解いた上で解説する。計算例を示すにあたり以下の前提を置く。
【前提】
図表1の通り、日本の親会社がA国に子会社3社を有しており、親会社による持株割合はそれぞれ100%とする。日本は所得合算ルールを導入済みであり、最低税率は10%とする。
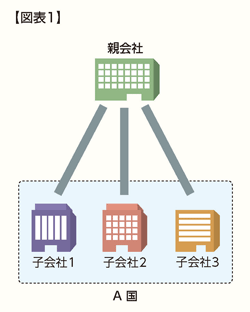
説明を簡便にするため、子会社1〜3の間のグループ内取引はなかったものとする。また、過年度の損失、現地租税繰越額(Local tax carry-forward)、IIR税額控除額(IIR tax credit)もないものとする。
子会社1〜3社の所得等の状況は図表2の通りとし、最下段のトップアップ税額が導き出されるまでのプロセスを解説しよう。
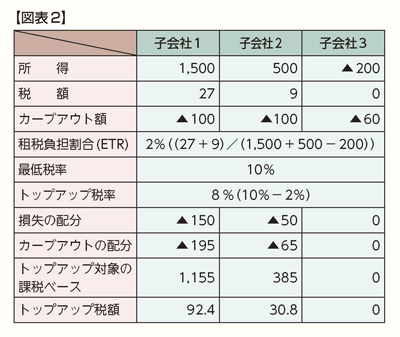
トップアップ税額の計算は3段階からなる。
第1段階は法域ごとの租税負担割合(ETR:Effective Tax Rate)の計算、第2段階はトップアップ税率の計算、第3段階は子会社ごとのトップアップ税額の決定である。
【第1段階:法域ごとのETRの計算】
ETRの分母、分子ともにA国内の子会社の数値を合算する。この結果、ETRは「2%(=(27+9)/(1,500+500−200))」となる。
なお、ETRの計算とは関係がないが、給与の一定割合及び有形資産に係る償却費(土地に係るみなし償却費を含む)の一定割合によって計算されるカーブアウト(適用除外)額は、子会社1〜3でそれぞれ100、100、60だったとする。
【第2段階:トップアップ税率の計算】
最低税率が10%とされているところ、本事例ではA国のETRが2%のため、差分の8%がトップアップ税率となる。
【第3段階:子会社ごとのトップアップ税額の決定】
トップアップ税額は子会社ごとに決定する。所得がプラスの子会社のみについて計算し、所得がマイナスの子会社についてはトップアップ税額がない。トップアップ税額は「課税ベース×トップアップ税率」により計算する。ある子会社の課税ベースの計算上、他の子会社の損失及び法域内のカーブアウトの総額は、所得を有する子会社の所得の比でプロラタ配分し、所得から控除する。
本事例では、まず「子会社3の損失200」を「子会社1と子会社2の所得の比」で按分する。その結果、子会社1は「200×1,500/(1,500+500)=150」、子会社2は「200×500/(1,500+500)=50」の損失の配分を受ける。
カーブアウト額については、A国内の総額が260であるところ、こちらも「子会社1と子会社2の所得の比」で按分する。その結果、子会社1については「260×1,500/2,000=195」、子会社2については「260×500/2,000=65」のカーブアウト額の配分を受ける。
以上により、子会社1の課税ベースは「1,500−150−195」により1,155となり、トップアップ税額は「1,155×トップアップ税率8%×持分割合100%=92.4」となる。また、子会社2の課税ベースは「500−50−65=385」となり、トップアップ税額は385×8%×100%により30.8となる。
コラム IIRと米国GILTIは「共存」
IIRとのダブル適用が懸念されてきた米国のGILTI(グローバル軽課税無形資産所得)については、青写真では「IIR等との共存(co-existence)」との表現が用いられている(「案」の段階で使われていた「適用免除(grandfathering)」との文言は消滅)。
ただ、青写真にはIIRとGILTIとの関係に関する記述量が少なく、依然としてその意味するところは明らかではない。中間親会社の取扱い(すなわち、日本・米国・軽課税国という三層構造における日本のIIRと米国のGILTIのダブル適用の有無等)については継続課題とされた。
繰越制度
一過性の一時差異等によりIIRに捕捉されることを回避も、制度は複雑化
国・地域別ブレンディングの採用は早い段階から既定路線となっていたのに対し、今回の青写真で注目されるのが、IIRにおける繰越制度の導入だ。
IIRでは、多国籍企業の親会社が連結財務諸表の作成目的で使用する会計基準をベースに租税負担割合を計算する。すなわち、分母である国ごとの所得は税務申告上の数値ではなく会計上の数値に一定の調整(グループ内配当や持分法投資損益の除外)を施したものを使用する。この結果、一時差異による租税負担割合の変動の問題が生じる。
例えば税務上、特別償却が行われたとしても、分母の所得は会計上の償却費を前提としたものとなる(すなわち、税務上の特別償却を加味しないためそれほど減少しない)一方、分子の税額は特別償却の結果低くなり、これに伴い租税負担割合が減少し、最低税率に満たなくなる恐れが生じる。特別償却は一時差異であるため、後年度は逆に税務上の償却費が減少し、租税負担割合が上昇することになるわけだが、特別償却を行った年度に限って“運悪く”IIRに捕捉される可能性がある。このような一時差異による租税負担割合のボラティリティを平準化する観点から、あるいはより広く年度間の負担の平準化を図る観点から、3つの繰越ルールが設けられることが青写真で明らかにされている(なお、一時差異に起因する税会差異を解消する全般的な方法として、当初は税効果会計の活用案もあったが、事業者による見積もり・予測に依存することから正確性が保てないのではないかとの指摘があり、青写真では採用されていない。一方、特別償却・即時償却についてはそもそも税務上の償却費を用いる案も議論されている)。
IIRにおける繰越制度は3種類ある。以下、それぞれについて、適宜計算例も交えながら解説する。
【損失の繰越し】
税務と異なり、会計には損失の繰越しという概念はないが、IIRの計算上は考慮する。すなわち、租税負担割合を判定する時点では繰越控除を行わないが、ミニマム税率以下となり、実際にトップアップ(上積み)課税を行う局面では、課税ベースから繰越損失を控除する。繰越期間は無制限とされる予定。
なお、一定の制度適用前の損失の繰越しも認められる方向となっている。
【現地租税繰越(local tax carry-forward)】
現地租税繰越とは、ミニマム税額を超える税額をある年度に支払っていた場合、翌年度以降の租税負担割合の計算上、分子の税額に加算できるというもの。計算例を示せば図表3の通りとなる。
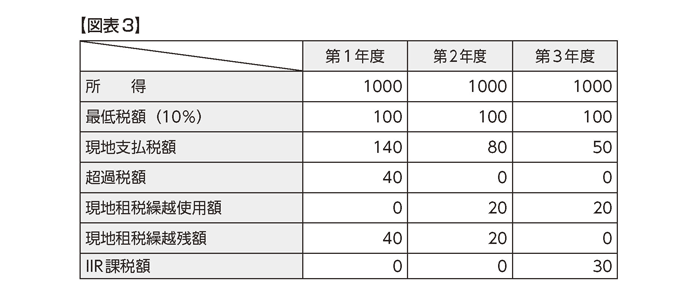
この事例では、軽課税国所在の子会社は1社のみ、ミニマム税率は10%と仮定する。第1年度は所得1,000に対し140の租税を払っているため租税負担割合は14%となり、IIRに抵触しない。むしろ、最低税額100(1,000×10%)に比べ40の税額を余分に支払っている(超過税額)。この超過税額が現地租税繰越額として、第2年度以降に利用可能となる。
すなわち、第2年度については租税負担割合が当初8%(80/1,000)であるところ、分子に現地租税繰越額を加算し、ミニマム税率に抵触しないようにすることができる(租税負担割合=(80+20)/1,000=10%)。第3年度も同様で、租税負担割合が本来5%であるところ(50/1,000)、現地租税繰越の残額20(第1年度発生40−第2年度使用20)を分子に加算できる((50+20)/100)。ただし、それでも租税負担割合は7%にしかならないため、差分の3%分についてトップアップ課税30を行うことになる(1,000×3%)。
【IIR税額控除】
IIR税額控除とは、過去にIIRによるトップアップ課税が行われていた前提で、当年度に超過税額が生じた場合には、過去のトップアップ課税額の範囲内でIIR税額控除の枠を創出し、当年度又は翌年度以降のトップアップ課税額と相殺できるというもの。計算例を示せば図表4の通りとなる。
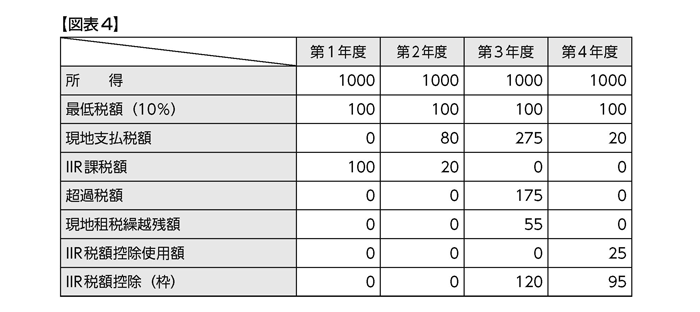
この事例でも、軽課税国所在の子会社は1社のみとし、ミニマム税率は10%と仮定する。第1年度と第2年度においては、ミニマム税率を下回り、それぞれ100、20のIIR課税額が発生している。こうした中、第3年度は275の現地支払税額があり、175の超過税額が発生することとなった。この場合、過年度のIIR税額の範囲内で、IIR税額控除枠120(100+20)が発生し、残余の55(175−120)が上記の現地租税繰越額となる。
これを踏まえ第4年度を見ると、まず、現地支払税額が20しかないため、租税負担割合は本来2%であるところ、分子に現地租税繰越額を加えることにより、7.5%となる((20+55)/1,000)。それでもミニマム税率に満たないということで、一見すると差分の2.5%について25のIIR課税額が発生するようにも見えるが、ここでIIR税額控除を行うことができるため、実際のIIR課税額は0となる(25−25)。なお、IIR税額控除の枠を25使用した結果、残余の枠は95となる(120−25)。
このIIR税額控除(枠)は、当年度又は翌年度以降の「他の法域」におけるIIR税額と相殺することができるという特徴がある。このような仕組みを見ると、「国別ブレンディング」と言っておきながら結局は国境をまたいだ調整を行っていることから、「全世界ブレンディング」と何が異なるのかとの疑問が生じるところだが、青写真は問題ないとの立場を示しており、このようなやり方を認めることで、逆に企業によるプランニングの余地がなくなる旨の説明を行っている。
なお、上記の現地租税繰越の「繰越期間」、及びIIR税額控除における過年度のIIR課税といった場合の「過年度」の意義については、ともに7年とする案が提示されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















