解説記事2020年11月16日 ニュース特集 重加算税取消裁決に係る当局の原因分析・教訓(2020年11月16日号・№858)
ニュース特集
調査で明らかにされる事項とは
重加算税取消裁決に係る当局の原因分析・教訓
国税不服審判所による原処分の取消事案について、課税当局は、事案の概要、取消裁決に至った主な原因、今後の調査に向けた教訓等を調査担当者に周知している。本特集では、質問応答記録書の記載内容等から重加算税が取り消された事例に係る課税当局の原因分析・調査の教訓を紹介する。課税当局が調査で重加算税賦課を見込む場合の証拠収集姿勢をうかがうこともできそうだ。
申述内容から相続人の意図まで読み取ることは到底できない
最初の事案は、相続税における重加算税の賦課決定処分が、隠蔽又は仮装の事実はなかったとして取り消された事例(令和元年11月19日裁決・裁決事例集No.117)。
本事案は、請求人の母(本件相続人)が、相続財産の一部である本件預金を関与税理士に伝えず申告漏れとなったことに対し、原処分庁が、本件相続人が本件預金を隠蔽したとして、重加算税賦課決定処分を行ったもの。調査担当者が作成した調査報告書には、隠蔽行為に係る関与税理士の申述が記載されている(図1参照)。
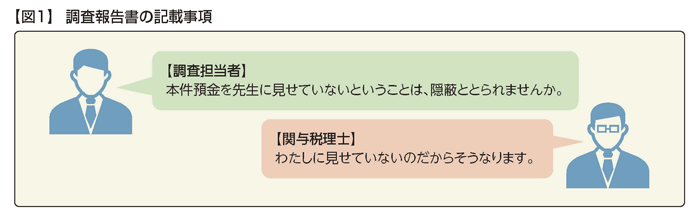
審判所は、関与税理士の申述内容からは、本件相続人が関与税理士に対し、本件預金の存在を過失により伝えなかったのか、意図的に伝えなかったのかということまでは判別できず、あえて本件預金の存在を伝えなかったという意図まで読み取ることは到底できないなどと指摘。本件相続人が相続財産を過少に申告する意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないと判断した。
隠蔽があったという心証を抱かせる事項の記載がなかった
課税当局は、取消裁決に至った主な原因として、以下の点を挙げている。
(1)原処分調査において保全した調査報告書には、事実の隠蔽又は仮装に関する本件相続人の申述はなく、関与税理士の申述しか記載されていなかった。さらに、本件相続人が関与税理士に対して本件預金の存在を意図的に伝えなかったことをうかがわせる事項も記載されていなかった。(⇒審判官に対して納税者に事実の隠蔽又は仮装の行為があったという心証を抱かせる事項が記載されていなかった)。
(2)審判官は、申述内容を明確にするために関与税理士へ質問調査を実施し、その結果、本件相続人に事実の隠蔽又は仮装の行為があったと認めることはできないと判断している(⇒審判官は関与税理士の申述事項を自ら再確認し検証している)。
その上で、今後の調査に向けた教訓として、審判所の事実認定(使用済通帳として破棄できる状況にありながら調査が行われるまで保管し、調査の際には調査担当職員に使用済通帳を素直に提示したこと、預金の申告漏れを指摘されると特段の弁明をすることなく修正申告したことなど)と反対の事実を示すような間接証拠を保全し、過少申告の意図等を推認することができるか検討するのも一つの方法としている(下掲参照)。
【今後の調査に向けた教訓】
| 〇 相続税の申告書の作成を依頼した税理士へ被相続人の財産を提示しなかった事実を相続人が「意図的に伝えなかった」と評価するためには、相続人へ質問調査を実施して当該不提示の理由を確認する必要があります。そして、重加算税を賦課決定する場合には、証拠保全した質問応答記録書に「意図的に伝えなかった」ことをうかがわせる事項が記載されていなければなりません。 〇 裁決では、原処分庁の調査における「①過少申告の意図」の立証が不足していると判断し、本件相続人は本件預金の通帳が使用済通帳として破棄できる状況にありながら本件調査が行われるまで保管し、本件調査の際には本件調査担当職員の求めに応じて本件預金の使用済通帳を素直に提示したことや、本件預金の申告漏れを指摘されると特段の弁明をすることなく修正申告したことなどの状況を事実認定した上で、これらの状況を総合的に判断し「①過少申告の意図、②特段の行動、③その意図に基づく過少申告」が認められないとしています。 そうすると、過少申告の意図等について直接証拠の保全が困難な場合には、これらの事実認定と反対の事実を示すような間接証拠を保全し、過少申告の意図等を推認することができるか検討するのも一つの方法といえそうです。 |
公園の指定管理者が駐車場料金の一部を仮受金経理
次の事案は、駐車場料金の仮受金経理に対する重加算税賦課決定処分が、隠蔽又は仮装の事実はないとして取り消された事例(令和元年12月16日裁決)。
請求人は、公園の指定管理者として請求人の収入とすべき公園の駐車場料金の一部(本件駐車場料金)を仮受金として経理。これに対し、原処分庁が、当該経理は請求人の代表者による経理担当者への指示によるものであり、隠蔽又は仮装の事実に該当するとして、重加算税賦課決定処分を行った。原処分庁は、経理処理及び経理処理に係る経緯をまとめた代表者の申述(質問応答記録書)を証拠としている(図2参照)。
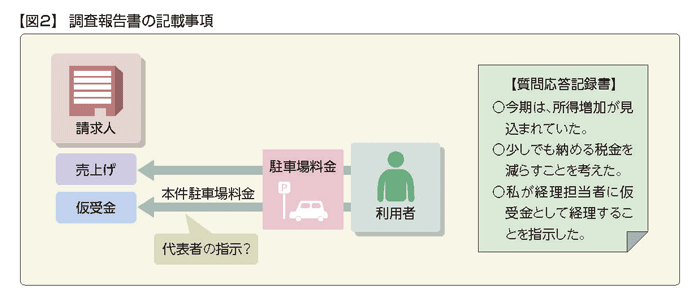
代表者の申述は具体性に欠け、指示の存在も疑わしい
争点は、隠蔽又は仮装に該当する事実があったか否か。
原処分庁は、請求人は本件駐車場料金が請求人の収入であることを前提とする内容の収支計算書を作成し、本件駐車場料金が請求人の収入であることを認識していた。また、請求人の代表者は、同人が経理担当者に対し、本件駐車場料金を仮受金として経理処理するよう指示した旨申述(本件申述)していることから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと主張。
これに対し審判所は、①収支計算書は公園の設置者が定めた書式であり、請求人は当該様式を使用するほかなかったことから、これをもって直ちに、請求人が本件駐車場料金を収入と認識していたとはいえない。②代表者の申述には、経理担当者への指示に関して具体性に欠ける点が多く、指示の存在も疑わしい。③税金を減らすためという当該指示の動機についても、請求人が減価償却費を計上していないという客観的な経理状況と整合せず、疑問があると言わざるを得ないと指摘。本件申述は、その信用性を直ちに認めることはできず、請求人に隠蔽又は仮装と評価すべき行為があったということはできないとした。
時間が限られた調査で、せっかく得られた申述なのだから
課税当局は、取消裁決に至った主な原因として、本件申述が①指示がいつ、どこで、どのようになされたかといった点が不明でありその内容に具体性がないこと、②行為の動機と客観的な経理状況が整合していない内容が含まれていることから、信用性に欠けると評価された点を挙げている。
その上で、今後の調査に向けた教訓として、時間が限られた調査において、せっかく得られた申述を質問応答記録書として証拠化するのだから、事実の要素の具体性があり、他の客観的な証拠が示す事実と整合する、信用性のあるものを作成するよう促している(下掲参照)。
【今後の調査に向けた教訓】
| 本裁決においては、申述内容の具体性がないこと及び行為の動機と客観的な事実が整合していないことから、質問応答記録書の信用性が認められませんでした。すなわち、質問応答記録書に事実の要素(①誰が、②いつ、③どこで、④誰と、⑤何を、⑥なぜ、⑦どのように、⑧どうしたか)の具体性があり、他の客観的な証拠が示す事実と整合するものであれば、信用性のある証拠として評価されたことでしょう。時間が限られた調査において、せっかく得られた申述を、質問応答記録書として証拠化するのですから、後の争訟にも耐えられるものにするよう、これらのポイントを意識して質問応答記録書を作成しましょう。 |
申告書提出後に隠蔽又は仮装の発現があったとは認められない
最後の事案は、調査時の虚偽答弁や主張の変遷が重加算税の賦課要件を充足するか否かが問われた事例(平成30年9月27日裁決・裁決事例集No.112)。
原処分庁は、請求人の調査の際の虚偽答弁等が調査を困難ならしめており、たとえ隠蔽又は仮装の発現とみられる行動が申告書提出後にしかなかったとしても、その発現行為自体から申告書提出時における過少申告の意図が推認されるときは、特段の事情が認められない限り、重加算税の賦課要件を充足すると主張。
これに対し審判所は、請求人の申告書提出後の言動及び提出文書の記載は、記憶の曖昧さや質問に関する認識の相違として説明できる程度であり、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動と評価すべき事実があったとは認められないと指摘。申告書提出後に隠蔽又は仮装の発現があったとは認められないと判断した。
他の証拠に基づく客観的事実等と併せて推認が可能か検討
本事案で課税当局は、重加算税を賦課するに当たっては、隠蔽又は仮装したところに基づいて申告書が提出されたかどうかが重要(その行為は過少申告の前であることが必要)であり、申告後に行われた虚偽答弁等のみでは、「過少申告の意図」があったとは認められないことを確認。
隠蔽又は仮装行為に該当するか否かを「特段の行動」理論に基づき判断する場合は、調査時の虚偽答弁や主張の変遷などの事実のみをもって判断するのではなく、その他の証拠に基づく客観的事実等を総合判断して、隠蔽又は仮装行為を推認できるか検討する必要があるとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























