解説記事2020年11月30日 判例評釈 ユニバーサルミュージック事件・東京高裁判決の検証(2020年11月30日号・№860)
判例評釈
ユニバーサルミュージック事件・東京高裁判決の検証
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・税理士 栗原宏幸
森・濱田松本法律事務所 アソシエイト弁護士 原田 昂
森・濱田松本法律事務所 顧問税理士 山田彰宏
Ⅰ はじめに
1 概 要
本稿では、同族会社等の行為計算否認規定(法人税法132条)を根拠とする課税処分を違法と判断したユニバーサルミュージック事件の東京高裁判決(脚注1)(以下「本判決」という。)を検証する。同事件の第一審である東京地裁判決では納税者が勝訴し、本判決でも納税者が勝訴したが、国が最高裁に上告受理申立てをしたため、現在、事件は最高裁に係属している(脚注2)。
本判決は、企業グループのグループ内再編の一環として行われた取引行為を法人税法132条に基づき否認する場合について、第一審判決やIBM事件東京高裁判決(脚注3)と異なる判断枠組みで判示をしたものであり、本件の帰趨は今後のグループ内再編の実務に大きな影響を与えるため、ここでご紹介する。
2 同族会社等の行為計算否認規定について
(1)行為計算否認規定とは
税法の適用については、法的安定性を確保するため、課税は私法上の法律関係に即して行われ(脚注4)、税負担の有無や多寡を考慮して法形式を選択したとしても、原則として、そのことをもって直ちに税務上否認されることはない(脚注5)。
もっとも、税負担を回避する目的で不当に私法上の法形式を利用する、いわゆる租税回避行為を防止するため、例外的に、当該私法上の法形式を税務上否認する権限が課税当局に与えられている。当該権限を定めた規定は一般に「行為計算否認規定」と呼ばれており、現行法上、同族会社等に関して適用されるもの(法人税法132条、所得税法157条1項等)、組織再編成等に関して適用されるもの(法人税法132条の2、所得税法157条4項)等が存在する。
(2)同族会社等の行為計算否認規定とは
これらの行為計算否認規定のうち、本判決で適用が争われたのは、「同族会社等の行為計算否認規定」である法人税法132条である。
同条は、同族会社(3つ以下の株主グループで50%超の株式を保有される会社)及びこれに準ずる一定の法人につき、「税務署長は……法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる」と規定している(同条1項)。
同条の適用の可否は、基本的に上記下線部の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」という要件(いわゆる「不当性要件」)が満たされるかどうかで決まる。
この点、不当性要件の判断基準としては、従来から、「もっぱら経済的、実質的見地において当該行為計算が純粋経済人の行為として不合理、不自然なものと認められるか否かを基準として判定すべき」とされていた(脚注6)。
(3)本件の第一審判決の判断
ところが、本件の第一審判決では、上述の従来の判断基準を前提としつつも、「同族会社にあっては、自らが同族会社であることの特性を活かして経済活動を行うことは、ごく自然な事柄であって、それ自体が不合理であるとはいえないから、同族会社が、自らが同族会社でなければなし得ないような行為や計算を行ったとしても、そのことをもって直ちに、同族会社と非同族会社との間の税負担の公平が害されることとはならない」とした上で、不当性要件は「法人税の負担が減少するという利益を除けば当該行為又は計算によって得られる経済的利益がおよそないといえるか、あるいは、当該行為又は計算を行う必要性を全く欠いているといえるかなどの観点から検討すべきものである」と判示した。
この判示は、①同族会社であることを経済的合理性の判断において納税者に有利に考慮して良いとする点、及び、②税負担減少以外の経済的合理性がわずかでも認められれば法人税法132条による否認は認められないとする点において、従来の考え方とは異なる納税者に有利な判断枠組みを示したともいえるものであった。そこで、この判断枠組みが本判決においても維持されるのかが注目されていた。
Ⅱ 事案の概要
音楽事業を目的とする日本法人である被控訴人(ユニバーサルミュージック合同会社(UMGK))は、平成20年12月期から平成24年12月期までの法人税の確定申告において、同族会社であるフランス法人(ユニバーサルミュージックインターナショナルファイナンスS.A.S(UMIF))からの借入(以下「本件借入」という。)に係る支払利息の額を損金の額に算入して申告した。
これに対し、税務署長は、当該支払利息の損金算入を認めず、各事業年度に関する法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした(以下「本件更正処分等」という。)。
被控訴人は、本件訴訟を提起し、本件借入は被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた、正当な事業目的(図表1記載の目的①から目的⑧。以下「本件目的」という。)を有する経済的合理性がある取引であり、本件更正処分等は法人税法132条の要件を欠く違法な処分であると主張した。
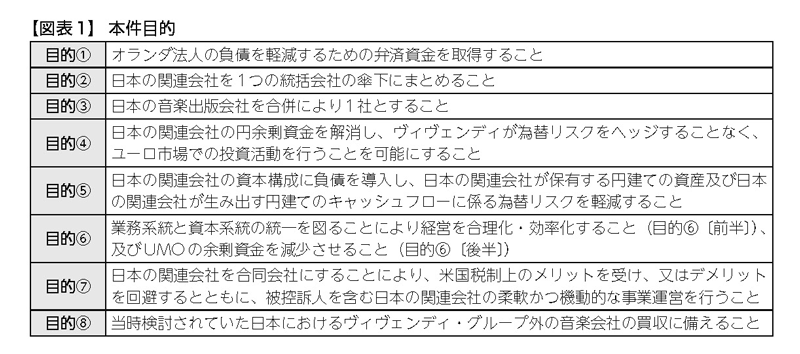
被控訴人の主張に対し、控訴人(国)は、法人税法132条の不当性要件は、同族会社の行為又は計算が、同族会社でなければ通常なし得ない行為又は計算で、かつ、経済的合理性を欠くものである場合に満たされる、との解釈を前提に、本件における一連の行為(本件設立、本件増資、本件借入、本件買収及び本件合併)はこれに該当し不当性要件を満たすとして本件更正処分等の適法性を主張した。
なお、本件借入に関連する事実関係は、図表2のとおりである。
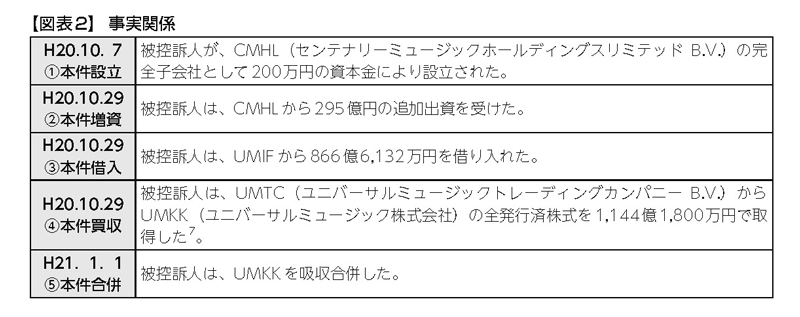
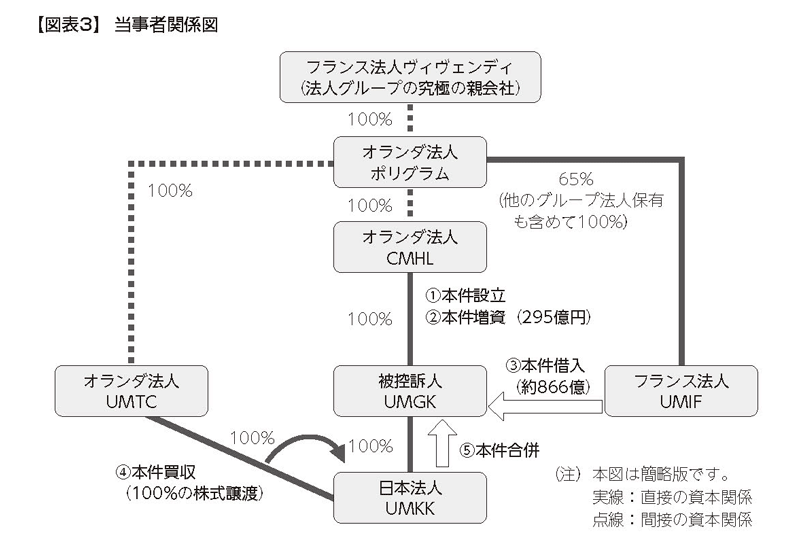
Ⅲ 本判決の内容
1 不当性要件の判断枠組み
本判決は、法人税法132条の不当性要件の判断枠組みについて、従来の考え方に従い、「専ら経済的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不自然、不合理なものと認められるか否か、すなわち経済的合理性を欠くか否かという客観的、合理的基準に従って判断すべきものと解される」と判示した。
そして、経済的合理性の判断に関し、「同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入れが不当性要件に該当するか否かについては、当該借入れの目的、金額、期間等の融資条件、無担保としたことの理由等を踏まえた個別、具体的な事案に即した検討を要するものというべきである」とした上で、「特に、上記のような借入れが当該同族会社の属する企業集団の再編等(以下「企業再編等」という。)の一環として行われた場合においては、組織再編成を含む企業再編等は、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあること等に照らすと、〈1〉当該借入れを伴う企業再編等が、通常は想定されない企業再編等の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、〈2〉税負担の減少以外にそのような借入れを伴う企業再編等を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情も考慮した上で、当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断すべきである」と判示した。
さらに、本判決は、上記Ⅰ.2.(3)の第一審判決の判断枠組みに基づく被控訴人の主張(税負担減少以外の経済的合理性がわずかでも認められれば法人税法132条による否認は認められない旨の主張)について、「企業再編等の一環として行われた同族会社の行為又は計算の不当性要件該当性を上記のような観点から判断することになれば、当該行為又は計算を行う必要性のほとんどが租税回避目的であって、税負担の減少以外の経済的利益がごく僅かである場合でも、経済的合理性があるとされかねない。このようなことは、不当性要件の的確な判別を困難にするものとして、法人税法132条の趣旨及び目的に反し、相当でもない」として、これを排斥した。
2 不当性要件の本件へのあてはめ
本判決は、上記判断枠組みに基づき、本件のスキームに基づく再編取引は、本件目的を①日本の関連会社の経営の合理化、②ユニバーサル・ミュージック・グループ部門のオランダ法人の負債軽減及び③日本の関連会社の財務の合理化という観点から検討してみても、不自然なものではなく、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するといえ、被控訴人に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものといえると判示した。
その上で、本件借入に関する事情を個別に検討し、目的、金額、期間等の融資条件、無担保としたことの理由等に照らしてみても、本件借入が専ら経済的、実質的見地において純粋経済人として不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであるというべき事情は見当たらないとして、本件借入は同族会社であるためにされた不自然、不合理な租税負担の不当回避行為とはいえないと判示し、不当性要件の充足を否定して控訴人の控訴を棄却した。
Ⅳ 本判決の分析
1 本判決の特徴-法人税法132条と同法132条の2の整合的解釈
本判決の特徴は、「同族会社等に係る行為計算否認規定」である法人税法132条の不当性要件を本件借入に対して適用できるか否かを判断するに当たり、その考慮要素として、本件借入が企業再編等の一環として行われたことを理由に、「組織再編成等に係る行為計算否認規定」である(すなわち同条とは別の行為計算否認規定である)法人税法132条の2の不当性要件の考慮要素である、「行為計算の不自然性」(上記Ⅲ.1.〈1〉の下線部)と「合理的な理由となる事業目的等の不存在」(上記Ⅲ.1.〈2〉の下線部)を取り入れた点にある。
この点、本件借入が本件合併を含む企業再編等の一環として行われたこと、特に、本件では、本件合併を行っていなければ本件借入に係る支払利息の損金算入の税効果を活用できなかった(すなわち、本件合併により借入人であるUMGKがUMKKを吸収したことにより初めて利息の損金算入と相殺できる事業収益がUMGKに生じた)(脚注8)ことからすれば、本件では(法人税法132条ではなく)法人税法132条の2を根拠として課税処分を行うことも考えられたのではないかと思われる(脚注9)。
また、訴訟段階でいわゆる「理由の差替え」が認められるとすれば(脚注10)、国としては、法人税法132条の2への理由の差替えや、同法132条に基づく否認を主位的主張とし、同法132条の2に基づく否認を予備的主張とするといった対応も考えられたところである(脚注11)。このように考えた場合、本判決の判示は、本件で仮に同法132条の2が否認の根拠とされた場合であっても同一の結論となるように、同法132条の不当性要件を同法132条の2の不当性要件と整合的に解釈しようとしたものと見る余地がある。
もっとも、法人税法132条の不当性要件は上述のとおり「経済的合理性の有無」の観点から判断するのに対し、法人税法132条の2の不当性要件は「組織再編税制の規定の濫用の有無」の観点から判断する(脚注12)。このように、両規定は異なる観点から租税回避行為を否認する規定であり、後者の濫用判断の考慮要素をそのまま前者の経済的合理性判断に用いるのはやや無理があるように思われる。
例えば、適格合併による子会社の繰越欠損金の引継ぎが法人税法132条の2により否認された事案において、東京高裁は、「行為計算の不自然性」を、合併が「適格合併において通常想定されない組織再編成の手順や方法に基づいているか」という税法の観点を加味して判断しているように思われる(脚注13)。以上に対し、本判決は、同じ「行為計算の不自然性」を、一般に想定される企業再編等の手順や方法に基づいているかという観点、あるいは、被控訴人が再編の目的として掲げた本件目的の観点から判断しており、同じ「行為計算の不自然性」という考慮要素であるにもかかわらず、上述の法人税法132条の2の裁判例の判断とは異なる観点から判断しているように思われる。このように、仮に法人税法132条の2の不当性要件の考慮要素を同法132条の不当性要件に取り込んだとしても、両規定の否認の観点が異なる以上、その実質的内容は異なるものとならざるを得ない面があるように思われる。このような本判決の判断について本件の最高裁がどのような判断を下すのかが注目される。
2 経済的合理性の判断内容について
(1)IBM事件東京高裁判決との関係
ア.IBM事件の概要
本件と同じく多国籍企業のグループ内再編に対する法人税法132条の適用が問題になった事案としてIBM事件がある。
IBM事件は、同族会社である納税者(有限会社アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス)が、米国法人である完全親会社から日本IBM株式会社の株式を購入し、その後、当該株式の一部を同社に自己株式取得させた、という事案である。当該自己株式取得によりみなし配当が生じた結果、取得された株式について納税者に譲渡損失が生じ、納税者が後続事業年度に開始した連結納税において当該譲渡損失を連結欠損金額としたところ、処分行政庁が当該譲渡損失の損金算入を法人税法132条に基づき否認した。
東京高裁は、上記Ⅰ.2.(2)で述べた経済的合理性に基づく不当性要件の判断基準を採用した上で、「経済的合理性を欠く場合には、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引(独立当事者間の通常の取引)と異なっている場合を含むものと解する」と判示した。
イ.IBM事件東京高裁判決と本判決の比較
本判決は、「借入れが企業再編等の一環として行われた場合には、企業再編等自体が、その形態や方法が複雑かつ多様であり、基本的には、いかなる必要性に基づいてどのような形態、方法で行うかにつき当該企業集団の自律的判断に委ねられるものであることからすると、独立当事者間の通常の取引に相当する企業再編等の形態、方法を想定することは極めて困難である」と判示し、上述のIBM事件東京高裁判決の判断枠組みを本件に適用することを明確に否定した。
このように、本判決は、否認対象行為(本件では本件借入)が複数の取引から成る企業再編等の一環として行われたことを理由にIBM事件の判断枠組みの適用を否定している。もっとも、IBM事件で納税者が行った取引も広い意味では企業再編等の一環としての取引行為といえるように思われ、上記の本判決の判示がIBM事件との事案の違いとして十分な説明であるかについては議論の余地があり得るように思われる。
また、たしかに、企業再編等そのものについて独立当事者間取引を想定することが困難な場合があることは否定できないように思われるが、後述のとおり、本件の否認対象である本件借入の条件の合理性を検討するに当たっては、独立当事者間取引との比較という視点はなお有効であったようにも思われる。
(2)同族会社でなければなし得ない行為計算の位置付け
上記Ⅰ.2.(3)のとおり、第一審判決は、同族会社であることを経済的合理性の判断において納税者に有利に考慮して良い旨判示した。この判示に対しては法人税法132条の趣旨及び目的と整合しないとの批判があった(脚注14)。
この点について、本判決は、第一審判決の該当する判示を引用せず、「経済的合理性を欠く同族会社等の行為又は計算が、同族会社であるためにされた不自然、不合理な租税負担の不当回避行為として、不当性要件に該当することになる」と判示しているため、この点に関する第一審判決の判断は採用しなかったと見るのが自然であろう。
このように、本判決は、少なくとも表面上は、同族会社であることを経済的合理性を基礎付ける事情と位置付けてはいないと考えられる。
(3)多国籍企業のグループ法人であることの位置付け
もっとも、本判決は、経済的合理性の判断のあてはめにおいて、被控訴人が多国籍企業のグループ法人であることを不当性要件の充足を否定する方向の要素として考慮していると見ることも可能であり、本判決のあてはめが法人税法132条の趣旨目的である同族会社と非同族会社の税負担の公平の観点から合理的なものであるかについては、議論の余地があり得るように思われる。
すなわち、第一審及び控訴審において、控訴人(国)は、被控訴人が本件借入に伴い財務上約545億円の債務超過となること(脚注15)や本件借入に伴う利息の発生により年間数十億円の利益が減少すること等をもって、本件借入は被控訴人にとって経済的不利益をもたらすものである、と主張していた。
しかし、本判決は、第一審判決と同様に、本件借入により貸借対照表上の純資産がマイナスで債務超過となっているとしても、被控訴人の資金調達は、専らCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に基づきヴィヴェンディの信用力によって行われるから、本件借入により被控訴人の資金調達への影響が生ずるおそれはなく、上記の財務状態であることから直ちに外部の金融機関に対する信用力の低下や倒産リスクを生じることはないことや、UMKK、被控訴人に吸収合併される前の3事業年度において、営業利益を約74〜111億円計上していたところ、本件借入により生ずる支払利息(年約40億円)は、本件合併によりUMKKの事業を承継する被控訴人がその営業利益によって賄うことができる範囲内のものとされたこと等を理由に、控訴人(国)の主張を排斥した。
このように、本判決は、被控訴人が債務超過となることをヴィヴェンディ・グループの信用力によって正当化しているが、この判示は企業グループのグループ法人であること(すなわち同族会社であること)を前提にしなければなし得ない判示であるように思われる。また、営業利益と支払利息の関係についても、過去の実績に基づく営業利益と支払利息との大小を判断するだけで良かったのか(将来の業績見通しや事業の下振れリスクについても考慮する必要はなかったのか)といった疑問が残り、20年という長期の返済期間にもかかわらず無担保の貸付であったことをも加味すると、結局のところ、本判決は被控訴人単独で見た場合の支払不能、倒産等のリスクを十分に考慮していないと見る余地もあるように思われる。別の言い方をすれば、CMS等の企業グループの一員でなければ得られない経済的メリットが、原則として法人ごとに課税所得を算定することを前提とする法人税法の解釈適用において積極評価を受けるべきものかどうかについて慎重な検討が必要であったように思われる。
本判決の考え方を突き詰めていけば、例えば、創業者が全株式を保有するオーナー企業(同族会社に該当する。)であっても、株主である創業者に相当の信用力があり、これにより当該オーナー企業の資金調達が可能な場合には、不当性要件の判定上、債務超過等の通常の法人であれば経済的に不合理とされ得る取引を当該オーナー企業が行っても差し支えない、ということにもなり兼ねないが、本判決がそのような解釈の可能性をも意図したものであったのかは慎重な検討が必要であるように思われる。反対に、オーナー企業について創業者の信用力に基づくファイナンスの正当性が認められないのであれば、何故本件のような巨大な企業グループの一員である場合には親会社の信用力による正当化が認められるのかについて、両者の取扱いの差異に関する説得的な説明が必要となろう。
このように考えると、本件では再編全体の経済的合理性についてグループ全体の事情を考慮するとしても、少なくとも本件借入の個別の条件の経済的合理性については、被控訴人単独で見た場合の経済的合理性にフォーカスし、IBM事件東京高裁判決が判示した独立当事者間取引との比較に基づく判断を適用する余地もあったように思われる。
(4)課税ベースの国外流出と行為計算否認規定の関係
本判決は、第一審判決と同様、デット・プッシュ・ダウン(脚注16)について、「資金効率の最大化を可能とするものとして、財務上の観点からみて、不自然とはいえず、その必要性、合理性を認めることができる。」と判示しているが、この判示が、本件借入の貸主が外国法人であることにより課税ベースの日本からの流出が生じていることについて、どの程度配慮をしているかは判決文からは明らかではない。これまでの裁判例上、法人税法132条は国際的な節税行為への対抗規定と位置付けられてはいないが(脚注17)、税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対して日本を含む各国が国際的協調路線をとる中で、同条の適用の在り方が改めて問われているように思われる(脚注18)。
Ⅴ 上告受理申立理由書について
上告受理申立理由書で、国は、大要、①本件借入以外に採り得る被控訴人にとって経済的負担のより少ない他の手段があったこと、②不当性要件の判断はあくまで更正・決定を受ける同族会社自身の経済的利害との関係で判断すべきこと、③本判決の判断は独立当事者間取引の観点から経済的合理性を判断するIBM事件高裁判決の判断と相反することを指摘し、本件借入について不当性要件は満たされると主張しているようである(脚注19)。
国の①から③の主張のうち②と③は上記IV.2.(1)及び(3)で述べた点と軌を一にするものと考えられる。これらの国の主張に対して最高裁がどのような判断を下すのか、注目される。
脚注
1 東京高裁令和2年6月24日判決・判例集未登載。
2 「ユニバーサル事件で国が上告受理申立て」本誌843号7頁。
3 東京高裁平成27年3月25日判決・判時2267号24頁(確定)。
4 金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019)129頁。
5 いわゆる航空機リース事件控訴審判決(名古屋高裁平成17年10月27日判決・税資255号(順号10180))。
6 最高裁昭和53年4月21日第二小法廷判決・訟月24巻8号1694頁、最高裁昭和59年10月25日第一小法廷判決・集民143号75頁。
7 そのほか、被控訴人は、ポリグラムの間接的な完全子会社である日本法人MGBKK及びV2Jの全発行済株式をそれぞれ14億6,900万円及び32万円で取得している。
8 本件合併の代わりに、UMGKを連結親法人とする連結納税を開始することでUMGKの支払利子の損金算入と傘下の日本法人の所得を通算することも考えられたと思われるが、その場合には傘下の日本法人について連結納税開始時の時価評価課税が生じ得ることから、連結納税によるのではなく本件合併が選択されたものと考えられる。
9 法人税法132条の2は合併等の組織再編成行為を利用した不当な税負担の減少を否認する規定であるため、同条に基づき、合併そのものから生じる税負担の減少ではなく、本件借入に係る支払利子の損金算入まで否認できるのかは議論の余地がある。これは、同条の立法趣旨等との関係で、同条において税負担減少行為として掲げられている「その他の事由」をどの程度広く解釈するかの解釈問題に帰着するように思われる。この点、同条の立法担当者は、組織再編成を利用した租税回避の例として「相手先法人の税額控除枠や各種実積率を利用する目的で、組織再編成を行う」ことや「株式の譲渡損を計上したり、株式の評価を下げるために、分割等を行う」ことを掲げており、これらの例示からすると「その他の事由」には一定の広がりがあると捉えているようにも思われる(中尾陸ほか『改正税法のすべて(平成13年度版)』(大蔵財務協会・2001)243-244頁参照)。
10 「理由の差替え」とは、審査請求や訴訟の審理の過程において、課税処分の理由とされていた課税要件事実(否認の理由)と異なる別の課税要件事実(否認の理由)を処分行政庁側が新たに主張することをいう。これまでの裁判例では、一般に、基本的課税要件事実の同一性の認められる範囲内であれば理由の差替えが認められている(金子・前掲注4)1076-1078頁参照)。行為計算否認規定に関しては、過大な役員報酬としての否認から法人税法132条に基づく否認への理由の差替えを認めた裁判例がある(東京地裁平成8年11月29日判決・判時1602号56頁、その控訴審である東京高裁平成10年4月28日判決・税資231号866頁)。
11 本件ではそのような対応はなされていないようである。
12 最高裁平成28年2月29日第一小法廷判決・民集70巻2号242頁(ヤフー事件最高裁高裁判決)。
13 東京高裁令和元年12月11日判決・金商1595号8頁。但し、本件は納税者が上告・上告受理申立てをしており、最高裁の判断はまだ示されていない。
14 吉村政穂「最近の裁判例に見る租税回避否認規定の課題」租研846号180頁参照。
15 本件合併により抱合せ株式損失が生じ、債務超過となったようである。
16 デット・プッシュ・ダウン(debt push down)とは、一般に、親会社が、借入金の返済に係る経済的負担を、企業グループの資本関係の下流にある子会社に負担させることをいう。
17 このような裁判例上の位置付けにより、IBM事件東京高裁判決において日本IBM株式会社の利益が日米でほぼ非課税となったことについて、「国際的二重非課税(ハイブリッドミスマッチによるBEPS)の論点が完全に欠落」しているとの批判もある(岡村忠生「法人税法132条1項の適用基準と「一連の行為」−IBM事件」税研208号37-40頁参照)。
18 なお、本件では、日本の過少資本税制上のデット・エクイティ・レシオ(3対1)に適合させるため、本件合併後、被控訴人の株主が被控訴人に対して出資を行い、当該出資金により被控訴人が本件借入の一部を返済する予定であったことが本判決において認定されている。当然のことながら、過少資本税制や過大支払利子税制への抵触を回避するための納税者の行動は、それ自体、法人税法132条の不当性要件の判断上、消極評価を受けるべきではない(本判決をこの点から評価するものとして太田洋・増田貴都「ユニバーサルミュージック事件東京高裁判決の分析と検討〔下〕」月刊国際税務Vol.40 No.11 67-68頁)。
19 「国、『純粋経済人の行為として、不合理、不自然な行為』と指摘」本誌849号40-41頁。
栗原宏幸 (くりはら ひろゆき)
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・税理士。
東京大学法学部、東京大学法科大学院、米国スタンフォード大学(LLM)、米国ニューヨーク大学(国際租税LLM)卒業。
M&A、ファイナンス等の知識・ノウハウを生かし、法務・税務ワンストップの総合的なアドバイスを得意とする。
原田 昂 (はらだ たかし)
森・濱田松本法律事務所 アソシエイト弁護士。
東京大学法学部卒業。
税務・事業承継に関する主な著作として、「医療法人における事業承継(上)・(下)」(税経通信Vol.75 No.10,11、2020年、共著)、「観光業界における事業承継−温泉旅館を中心に−」(税経通信Vol.75 No.12、2020年、共著)がある。
山田彰宏 (やまだ あきひろ)
森・濱田松本法律事務所 顧問税理士。
財務省主税局、大阪国税局、KPMG税理士法人で執務。
国際課税・法人税の企画立案、税務調査、タックス・プランニングの実務などの経験を活かし、多面的な税務アドバイスを行っている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















